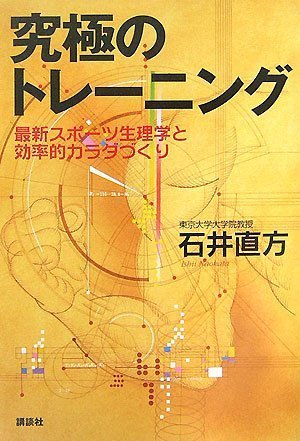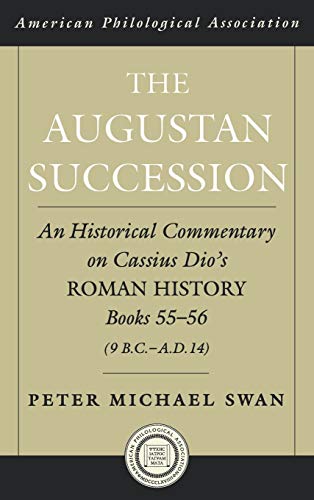1 0 0 0 OA X線の半価層,実効エネルギーの測定精度
- 著者
- 佐藤 孝司
- 出版者
- 医用画像情報学会
- 雑誌
- 放射線像研究 (ISSN:21870233)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.152-157, 1980 (Released:2012-08-27)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 図書館運営費の安定確保に向けて(<特集>図書館経営)
- 著者
- 中林 雅士
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.8, pp.317-323, 2011
- 参考文献数
- 5
大学財政規模が縮小する中,図書館運営予算も削減を余儀なくされている。加えて,大学間の競争は激しさを増しており,図書館はこのような環境変化の中で,自らのミッションを堅持しつつも,新たな環境に適応する必要に迫られている。直近の課題の1つは,図書館運営費の安定確保である。図書館を取り巻く多くのステークホルダーに対する社会的責務を果たすためには,財政問題を避けては通れない。本稿では,図書館運営費の安定確保について,図書館と国庫助成,図書費,業務委託費を取り上げつつ考察する。
1 0 0 0 OA 戦後青年団運動の思想 : 共同主体性をもとめて
- 著者
- 五十嵐 暁郎 イガラシ アキオ Akio Igarashi
- 雑誌
- 立教法学
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.39-54, 1995-07-20
- 著者
- 第1調査研究グループ 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 巻号頁・発行日
- 2015-09 (Released:2015-09-15)
Since the high economic growth period in Japan private motorcars have proliferated in the local cities, where they have become necessities of life for most dwellers today. This paper considers the present state of proliferation by applying some statistical methods to a set of cross-sectional data, an array of transportation and socio-economic variables in 1990 for each of eighty-four medium-sized cities located outside major metropolitan areas (Table 1). In order to solve the problem, the author studies the systematic relationship among the variables or the transportation system. The results may be summarized as follows:First, the eighteen variables on attributes of household, proliferation rate of private vehicle, modal choice in commuting, urban form, road environment and public transit shown in Table 2 were defined as indicators of the transportation system. Using exploratory factor analysis, they were grouped and simplified into five common factors which can be used as sorts of latent variables. The results of the factor analysis are given in Table 3. Of five factors extracted, Factor 5 was not identified even after a promax oblique rotation. Factor 1 was identified as household car ownership, Factor 2 as private traffic generation and traffic restraint, Factor 3 as public traffic generation, Factor 4 as compact car (Kei-jidosha) ownership in suburbs. These four factors correspond to essential elements of the above-mentioned transportation system.Second, for the respective group of key variables comprising each factor, the causal sequence in their internal correlations was examined by means of path analysis to clarify a property of the element. The following became clear after the investigation of the four arrow diagrams in Figure 1 to Figure 4 that show the results of the analysis: (1) The level of household car ownership is influenced by the number of commuters in the household and the family income. In particular the income level has an effect on the proliferation rate of passenger cars. (2) The incidence of traffic accidents is influenced by the model choice of motorcycles in commuting and the level of traffic congestion. This causal relationship is consistent with empirical facts. (3) The level of proliferation of both bus and taxis is influenced by the D.I.D.'s population density. It was proved that the urban form affects the level of public transit service. (4) The level of household compact car ownership is influenced by the proportion of the D.I.D.'s area to the city area. That is, the larger the proportion is, the higher becomes the level.Third, the relationship among elements of the transportation system was illustrated by hypothesizing a causal model for latent variables derived from the factors and then testing it through the multiple indicator method. The results in Table 4 and Figure 5 were obtained empirically, and indicate that three latent variables derived from the first three factors have significant relationships causally. The model represents a link in the chain of the causal cycle in which proliferation of private motorcars causes loss of public transit passengers.Finally, the first latent variable scores for the eighty-four cities were estimated and examined. This latent variable, household car ownership, is a key exogenous one which precedes causally. Figure 6 shows the highest scores to be located in the northern Kanto, the Hokuriku, and the Tokai Districts, the lower ones generally in Northeastern and Western Japan. Furthermore, cities with higher scores are those in which the secondary activities in the economy are of great importance and the increase in population is remarkable (Table 5).
- 著者
- 豊田 秀樹 池原 一哉 吉田 健一
- 出版者
- 日本分類学会
- 雑誌
- データ分析の理論と応用 (ISSN:21864195)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.57-77, 2015
<p> 本研究の目的は,3 次までの積率を明示的にかつ独立に特定できる確率分布を構成することである.非対称正規分布の母数に変換を施して,平均・分散・歪度を直接パラメタライズできるように新たな確率密度関数を構成する.3 次までの積率を独立に特定することで,(1) 統計モデルの一部として組み込んだ際に,直接歪度を推定すること,(2) 潜在変数(因子)の歪度を直接推定すること,(3) 群間で歪度を比較することが可能となる.非対称正規分布と<i><font face="roman">χ</font></i><sup>2</sup> 分布に関するシミュレーション研究により,母数の推定における妥当性が確認された.また,歪度が観察されやすいブランド価値データに提案手法を適用した結果,集団間での3 次までの積率の違いを細かく比較できることが示された.母数推定には,マルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズ推定を用い,サンプリング手法にはハミルトニアンモンテカルロ法を利用した.</p>
1 0 0 0 遺伝子・文化の共進化に関する理論集団遺伝学的研究
遺伝子と文化の共進化の事例研究を3つ行った。1.成人乳糖分解者が多い人類集団で家畜の乳を飲む習慣が普及していることを説明するため、3つの仮説が提唱されている。乳糖分解者と飲乳者の共進化を集団遺伝学のモデルに基づいて理論的に研究し、それぞれの仮説の妥当性を検討した。まず、文化歴史的仮説あるいはカルシウム吸収仮説が成り立つためには、従来言われているよりはるかに強い自然淘汰が要求されることを示した。また、乳に対する好みの効果を検討し、逆原因仮説が成り立つためには乳糖分解者と分解不良者の間で好みに違いがあることが必要で、しかも文化伝達係数がある不等式を満足しなければならないことを示した。逆に、好みの違いが大きすぎると、前者2仮説が成り立ちにくいことも分かった。2.手話とは聾者の自然言語であり、文化伝達によって維持されている。一方、重度の幼児期失聴の約1/2が遺伝性であり、その約2/3が複数の単純劣性遺伝子によって引き起こされている。劣性遺伝の特徴として聾者が世代を隔てて出現する傾向にあるため、親から子への手話の伝達が阻害される。遺伝子と文化の相互作用の観点からこの問題を解析し、劣性遺伝子が2つ存在する場合、手話が失われないためには聾者同士の同類結婚が重要であることを示した。実際、日本や欧米で約90%の同類結婚率が報告されており、手話という特殊な文化現象の存続が聾に関する同類結婚によって可能になっていることが暗示された。さらに、聾学校などで家族以外の者から手話を学習する機会がある場合について検討を加えた。3.文化伝達能力と父親による子育てが共進化する可能性を理論的に検討した。有性一倍体モデルを完全に記述し、平衡点の同定と安定性解析を行った。その結果、母親からの文化伝達の効率がよく、父親からの文化伝達に補助的な意義しかない場合、文化伝達能力と父親による子育てがほぼ独立に進化することが分かった。一方、父親からの文化伝達が特に重要である場合には強い相互作用が見られ、文化伝達能力と父親による子育ての共進化が促進される。また、より現実的な二倍体モデルを部分的に解析したが、本質的な結果において一倍体モデルと一致した。さらに、父性信頼度の低下による効果も検討した。
1 0 0 0 IR 故宮博物院における「フォルモサ展」 : 台湾における歴史認識の変化と文化遺産
- 著者
- 野林 厚志
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 民博通信 (ISSN:03862836)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.12-13, 2004-03
1 0 0 0 故宮博物院をめぐる戦後の両岸対立(1949-1966年)
- 著者
- 家永 真幸
- 出版者
- 日本台湾学会
- 雑誌
- 日本台湾学会報 (ISSN:13449834)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.93-114, 2007-05
- 出版者
- 千里文化財団
- 雑誌
- 季刊民族学 (ISSN:03890333)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.18-21, 2011
1 0 0 0 台湾の博物館における教育事情の調査
- 著者
- 白柳 弘幸
- 出版者
- 玉川大学教育博物館
- 雑誌
- 玉川大学教育博物館紀要
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.23-30, 2011-03-31
- 著者
- Chiu Chunni
- 出版者
- 常磐大学大学院人間科学研究科
- 雑誌
- 常磐大学大学院常磐研究紀要 (ISSN:18816487)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.35-43, 2011-03
1 0 0 0 究極のトレーニング : 最新スポーツ生理学と効率的カラダづくり
1 0 0 0 OA 第58回日本甲状腺学会学術集会
- 出版者
- 一般社団法人 日本内分泌学会
- 雑誌
- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.2, pp.699-705, 2015-09-20 (Released:2015-10-03)
1 0 0 0 OA 多角的視座からの「感情」現象の哲学的解明を通じた価値倫理学の新たな基礎づけの試み
「感情」現象をあらためて哲学的に吟味することを通して、倫理的価値の発生する根源的な場所を明らかにし、ひいては新たな価値倫理学の基礎づけを試みること、それが本研究の目標であった。われわれは、現象学、中世哲学、心の哲学、分析哲学、現象学的精神病理学、精神分析という、各研究分担者の専門的視座から持ち寄られたたさまざまな「感情」研究の成果を相互に批判的に比較検討することを通じて、人間存在にとっての感情現象の根本的意義(謎にみちたこの世界において行為し受苦するわれわれにとっての感情現象の根本的意義)を明らかにする多様な成果を上げることができた。これにより上記目標の核心部分は達成されたと言いうるだろう。
1 0 0 0 OA 企業と学生の価値共創活動について
- 著者
- 河合 勝彦 後藤 良次 杉浦 豪軌 青井 一郎 長屋 隆之
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2014年秋季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.225-228, 2014 (Released:2015-01-30)
右肩上がりの日本経済が終焉を迎え、より性能の高いものをより安くつくることによって製品の売上げを伸ばすという、日本企業成長のシナリオに限界が見えてきた。その一方、製品やサービスにまつわるコストパフォーマンス以外の価値創造が顧客満足度を高め、企業の成長を支えるという事例が増えている。この後者の視点に基づいて、我々は企業と(非技術系)大学生が共同して新しい価値(新しいモビリティ文化)を創造するという実践活動(共創活動)を行っている。本稿は、この共創活動の概要をまとめ、こうした活動に参加することによって得られる企業と学生のメリットについて検討する。さらに、この実践活動で得られたノウハウや遭遇した困難について考察を加える。
- 著者
- Peter Michael Swan
- 出版者
- Oxford University Press
- 巻号頁・発行日
- 2004
- 著者
- 渡辺 裕
- 出版者
- 東京大学文学部美学藝術学研究室
- 雑誌
- 研究 (ISSN:09163379)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.95-120, 1985-03-25 (Released:2007-06-08)