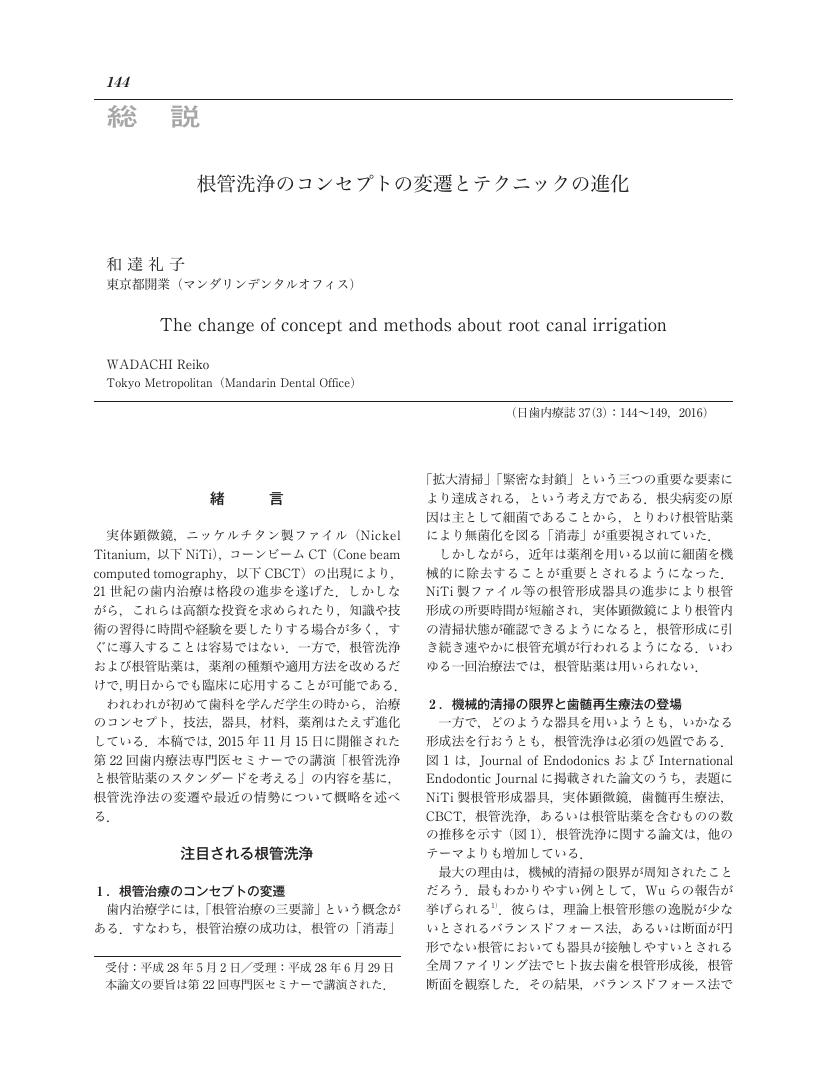2 0 0 0 OA 主翼の応力計算法に就て
- 著者
- 内藤 子生 高田 守正
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空學會誌 (ISSN:18835422)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.44, pp.1205-1224, 1938-12-05 (Released:2009-07-09)
The stress analysis of the wing is now in general calculated by the idea of so called "elastic axis". But the idea is based on the assumption that the metal covered wing is so rigid to torsion that any torque offers to the wing no torsional deflection, and that the torque offers no stress to flangess. Therefore it may be easily supposed that the former idea may fail in the case of large torque. The present paper discribes a rational and rigorous method of stress analysis for wings which was developed and successfully applied by the authors in desigh of an aeroplane. The principle of the present method is based on the well known fact that the total deflection of a beam is the sum of the bending deflection and the shear deflection, considering the whole structure as statically indeterminate. Applying the principle of minimum strain energy, the authors calculated both the energy of bending and the energy of shear as shown in the eqn. (13) of illustrative problem. So the paper notes to the idea of "Shear Lag", and treats it analytically. Fig.3 is the illustrative problem. Flanges are considered to take fiber stress only. Webs, skins and ribs are considered to take shear stress only, recieving no fiber stress in X direction. Shear stresses in webs and skins between ribs are considered constant, changing only at ribs. Balance of the forces are expressed in six components, eqns (1)→(6). The idea of Fig.4 leads to eqs (7)→(10). They may be reduced to the relation (11). Statics gives no farther relation, q is indeterminate and must be solved by the principle of mininum strain energy. Total strain energy may be expresseed by (13), equation for q by (14), required solution for q by (15), and the other unknown by (11) & (15). Thus the inter-action of ribs and skins to both spars are easily calculated, which should be compared with the theory of Paul Kuhn, treating the rib action in the wing of wooden spar (N.A.C.A. Tech. Rep. No 508, 1935). Chapter 5 and 6 are the formula which were practically applied by the authors in the design of a seaplane. In the appendix (the last chapter), phisical meaning of expression (15) are developed. When L=∞ or G=∞, exp. (15) is reduced to the idea of "elastic axis, " in which the first term is for bending and the recond term is for torsion. When tv=tL=0, exp. (5) is reduced to the formnla for fabric covered wing. Thus it is concluded that the idea of "elastic axis" can be correctly applied only for the region far away from wing root and not for the region near the wing root, where the present method is varlid and beneficient.
2 0 0 0 OA 新飛行機
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空學會誌 (ISSN:18835422)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.80, pp.1319-1326, 1941-12-05 (Released:2009-07-09)
2 0 0 0 OA 東洋医学の広場
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.1101-1116, 2001-03-20 (Released:2010-03-12)
- 被引用文献数
- 2 2
2 0 0 0 OA サンゴの光合成と二酸化炭素の固定に関する研究
- 著者
- 仲座 栄三 津嘉山 正光 清家 邦宏
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.1026-1030, 1994-10-30 (Released:2010-03-17)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 病める者と医する者-大塚敬節先生に学びしこと
- 著者
- 藤井 美樹
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.185-194, 1996-09-20 (Released:2010-03-12)
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 間質性肺炎の診断と治療
- 著者
- 杉野 圭史
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.190-195, 2019-11-30 (Released:2020-01-28)
- 参考文献数
- 16
間質性肺炎が疑われた場合は,予後の面および治療内容を決定する上でも特発性肺線維症(idiopathic pulmonary fibrosis; IPF)とそれ以外の間質性肺炎を鑑別することが重要なポイントである.現在,IPFに対しては抗線維化薬であるニンテダニブおよびピルフェニドンが推奨されている.一方,非特異的間質性肺炎,膠原病肺,薬剤性肺炎,過敏性肺炎などでは,ステロイド単独投与や免疫抑制薬との併用療法が一定の効果を示すことが知られている.加えて,急性増悪時のステロイド治療に加えてトロンボモジュリンや抗線維化薬の併用,肺高血圧合併例に対するホスホジエステラーゼ5型阻害薬,エンドセリン受容体拮抗薬などの導入,閉塞性換気障害を有する気腫合併肺線維症患者に対する吸入長時間作動型抗コリン薬・β刺激薬の導入,慢性安定期の患者においては,リハビリテーション導入を考慮する.間質性肺炎患者では,労作時の呼吸困難による身体機能低下がdeconditioningをもたらし,運動耐容能の減少,QOLの低下,不安やうつ状態に繋がると考えられる.これら運動耐容能の減少,QOLの低下,不安やうつ状態に対して,呼吸リハビリテーション(特に運動療法)は改善効果が期待できる.本稿では,間質性肺炎の診断と治療について,自験例を交えながら概説する.
2 0 0 0 OA ヘキサンジオールは細胞内のクロマチンを凝縮させる
- 著者
- 伊藤 優志 井手 聖 前島 一博
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.385-388, 2021 (Released:2021-11-25)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 鉄道廃線敷を活用した観光施設の現状~日独の事例から~
- 著者
- 渡邉 亮 遠藤 俊太郎 曽我 治夫
- 出版者
- 日本交通学会
- 雑誌
- 交通学研究 (ISSN:03873137)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.39-46, 2017 (Released:2019-05-27)
- 参考文献数
- 6
鉄道の廃線敷は、土地利用の転換・活用が難しく、特に地方部で有効に活用されている事例は少ない。しかし、一部では観光施設として有効活用されている事例もある。本研究では、国内3事例、海外1事例について、誕生の背景や施設の保有・運営形態、採算性等をヒアリング調査した。その結果、鉄道時代を上回る集客力を有し、一定の収支を確保している事例が確認でき、廃線敷を活用した施設が新たな観光資源として都市と地域の交流を生む可能性を秘めていることが明らかとなった。
2 0 0 0 OA 進行がん患者の悪夢に柴胡加竜骨牡蛎湯が有効だった1例
- 著者
- 柳原 恵梨 杉本 達哉 佐藤 哲観
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-5, 2022 (Released:2022-01-13)
- 参考文献数
- 18
【緒言】悪夢は緩和ケアの臨床において珍しくない症状の一つだが,がん患者における研究は乏しい.今回われわれは,一般的な不眠治療で緩和されない悪夢による苦痛に対し柴胡加竜骨牡蛎湯が有効だった症例を経験した.【症例】82歳,男性.悪性リンパ腫による疼痛,倦怠感と悪夢を伴う不眠を認めた.身体症状はステロイドで改善したが,悪夢と不眠は持続し,一般的な不眠治療には不応であった.柴胡加竜骨牡蛎湯を投与したところ速やかに悪夢と不眠が改善した.【考察】柴胡加竜骨牡蛎湯は,他の睡眠剤や抗不安薬などに比べて有害事象の懸念が少なく,がん患者の悪夢の治療に安全かつ有効に使用できる可能性がある.【結語】柴胡加竜骨牡蛎湯が進行がん患者の悪夢を改善した.
2 0 0 0 OA 京都府立植物園における樹木の管理・育成
- 著者
- 松谷 茂
- 出版者
- 樹木医学会
- 雑誌
- 樹木医学研究 (ISSN:13440268)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.94-97, 2013-07-31 (Released:2021-03-29)
2 0 0 0 OA ダイエーにおける牛肉事業の展開プロセスとその意義 垂直統合が競争優位をもたらす要因
- 著者
- 森山 一郎
- 出版者
- 日本商業学会
- 雑誌
- 流通研究 (ISSN:13459015)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.101-118, 2016 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 21
小売業者主導の垂直的流通システムについては、これまで資本統合を伴わない管理型を中心に検討が進められてきた。しかし、実際には、小売業者が生産段階の垂直統合に乗り出す例は少なくない。このような企業型と呼ぶべき生産段階への関与は、小売業者主導の垂直的流通システムに関して看過されてきた嫌いがある。そこで本稿では、その最も初期的な事例であり、かつ長期にわたる取り組みを経て品質面での競争優位を獲得したダイエーの牛肉事業を取り上げ、その展開プロセスとそれが成果を生むに至った要因を検討した。本稿における検討の結果、ダイエーの牛肉事業が垂直統合を通じて競争優位を獲得することができたのは、それが牛肉という漸進的な技術・品質改善が有効な商品分野であったこと、垂直統合の継続性が担保されたこと、過度に物量を追求しなかったことによるものであることが示唆された。このような検討結果は、小売業者主導の垂直的流通システムに関して、垂直統合の観点も含め、さらに詳しく検討する余地があることを示している。
- 著者
- Ganesh C. Jagetia
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.74-81, 2007 (Released:2007-03-14)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 139 181
Ionizing radiations produce deleterious effects in the living organisms and the rapid technological advancement has increased human exposure to ionizing radiations enormously. There is a need to protect humans against such effects of ionizing radiation. Attempts to protect against the deleterious effects of ionizing radiations by pharmacological intervention were made as early as 1949 and efforts are continued to search radioprotectors, which may be of great help for human application. This review mainly dwells on the radioprotective potential of plant and herbal extracts. The results obtained from in vitro and in vivo studies indicate that several botanicals such as Gingko biloba, Centella asiatica, Hippophae rhamnoides, Ocimum sanctum, Panax ginseng, Podophyllum hexandrum, Amaranthus paniculatus, Emblica officinalis, Phyllanthus amarus, Piper longum, Tinospora cordifoila, Mentha arvensis, Mentha piperita, Syzygium cumini, Zingiber officinale, Ageratum conyzoides, Aegle marmelos and Aphanamixis polystachya protect against radiation-induced lethality, lipid peroxidation and DNA damage. The fractionation-guided evaluation may help to develop new radioprotectors of desired activities.
2 0 0 0 OA 根管洗浄のコンセプトの変遷とテクニックの進化
- 著者
- 和達 礼子
- 出版者
- 一般社団法人 日本歯内療法学会
- 雑誌
- 日本歯内療法学会雑誌 (ISSN:13478672)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.144-149, 2016 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 周術期の蕁麻疹・アナフィラキシー
- 著者
- 益田 浩司
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.682-685, 2014-05-01 (Released:2017-02-10)
2 0 0 0 OA 改良Frankel分類による頸髄損傷の予後予測
- 著者
- 福田 文雄 植田 尊善
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.29-33, 2001-01-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 11 6
頸髄損傷の評価法として,我々は当センターで考案した独自の評価法を用いている.横位評価として改良Frankel分類を,高位評価として頸髄損傷高位判定評価法を用い,受傷後7日以内に入院し6ヵ月以上経過観察できた294例を対象に,その神経回復を解析し麻痺の予後予測を試みた.改良Frankel B1,B2,B3からD以上への回復は,それぞれ20,32,80%となり,B3はB1,B2に比して有意な差を認めた.同様に改良Frankel C1,C2からD以上への回復は61%と97%であり有意な差がみられた.Frankel分類を細分化することにより,四肢麻痺の機能障害を一層明瞭に評価できるだけでなく,急性期頸髄損傷の神経学的回復において予後予測として有用である.
- 著者
- 糸川 嘉則
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.11, pp.587-592, 1982-11-25 (Released:2018-03-10)
- 著者
- 岡 真由美 星原 徳子 河原 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.13-20, 2020 (Released:2021-02-06)
- 参考文献数
- 15
超高齢社会において、加齢性斜視であるsagging eye syndrome(以下SES)が注目されている。本研究では、SESの鑑別疾患としてあげられる眼球運動神経麻痺との相違を検討し、画像診断の前に視能訓練士が行うべき病態分析と視能評価について述べた。1.年齢区分別の斜視の種類 年齢区分が高くなるほど共同性斜視が減少し、非共同性斜視(眼球運動障害を伴う斜視とする)が増加した。非共同性斜視のうち、年齢区分が高くなるにつれて増加傾向にあったのは滑車神経麻痺、SES、Parkinson 病関連疾患であった。2.SESと眼球運動神経麻痺における複視の発症様式 SESは滑車神経麻痺および外転神経麻痺よりも発症から初診までの期間が長く、複視の発症日が不明確であった。3.SESと眼球運動神経麻痺の眼位・眼球運動 内斜視を伴うSES は外転神経麻痺よりも斜視角が小さく、わずかな上斜視および回旋偏位を伴っていた。上斜視を伴うSESは下転眼に外回旋がみられた。滑車神経麻痺では健眼固視のとき外回旋が上転眼にみられたが、麻痺眼固視のとき一定の傾向がなく、両者を回旋眼で評価することは困難であることがわった。 高齢者の斜視ではSESおよびその合併例が多い。SESと眼球運動神経麻痺との区別は困難であることから、病歴聴取と患者の観察、回旋偏位の検出が有用であり、むき運動検査と合わせて総合的に評価することが重要である。
2 0 0 0 OA 高度情報化社会[第8回] 高度情報化とテクノストレス
- 著者
- 下田 博次
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.8, pp.715-723, 1988 (Released:2012-03-23)
コンピュータ, OA機器から産業用ロボットの普及に伴ってテクノストレスと呼ばれる心身の疲労, 健康障害が問題視されるようになった。このテクノストレスは, マスコミがつくり出した心理不安であるとか, コンピュータが直接のストレス発生原因ではないという人もいる。だが一方では多くの症例報告とプログラミング作業から発生するストレス調査もすすんでいる。テクノストレスはコンピュータ関連労働の種類によってその表れと原因が違い, きめ細かい対応が必要である。しかし最終的には, 個人のライフスタイルと企業風土の問題に帰するところが大である。
2 0 0 0 OA イエス・キリストの信実か、イエス・キリストへの信仰か? ーロマ三・二二の釈義的考察
- 著者
- 原口 尚彰
- 出版者
- 日本基督教学会
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.76-95, 2015 (Released:2017-04-21)
- 参考文献数
- 1
The prepositional phrase dia. pi,stewj vIhsou/ Cristou/ in Rom 3:22 modifies dikaiosu,nh de. qeou/(the righteousness of God). The implied subject of pi,stij is Christ and the genitive noun vIhsou/ Cristou/ is used subjectively. The phrase does not mean “the faith in Jesus Christ” but “the faithfulness of Jesus Christ.” The faithfulness of God (Rom 3:3) consists in the fulfillment of his words of promise. The faithfulness of God was realized by the faithful action of the Son of God, namely, Christ (cf. I Cor 1:18-20). Christian Faith is defined as a belief in the fulfillment of the promise of God through Christ’s faithful act (Rom 3:28; Gal 3:2, 5, 7). It is a response to the faithfulness of God revealed by that of Christ. We can conclude that the thesis of justification by faith (Rom 3:21, 28; Gal 2:16) is not based on anthropology but on Christology.
2 0 0 0 OA 管理職がCMSによる学校Webサイトから発信した情報の特徴
- 著者
- 森下 孟 東原 義訓
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.Suppl., pp.181-184, 2008-02-10 (Released:2016-08-04)
- 参考文献数
- 11
本研究では,CMSによって管理職が発信する学校Webサイトの特徴を明らかにするために,更新状況と発信された情報の種類を分析した.CMSにより,容易に発信を開始でき,日常的に発信されること,また,管理職が発信することで,児童・生徒の日々の様子,教員・保護者の活躍,管理職の考えが発信されるようになるという特徴が明らかになった.