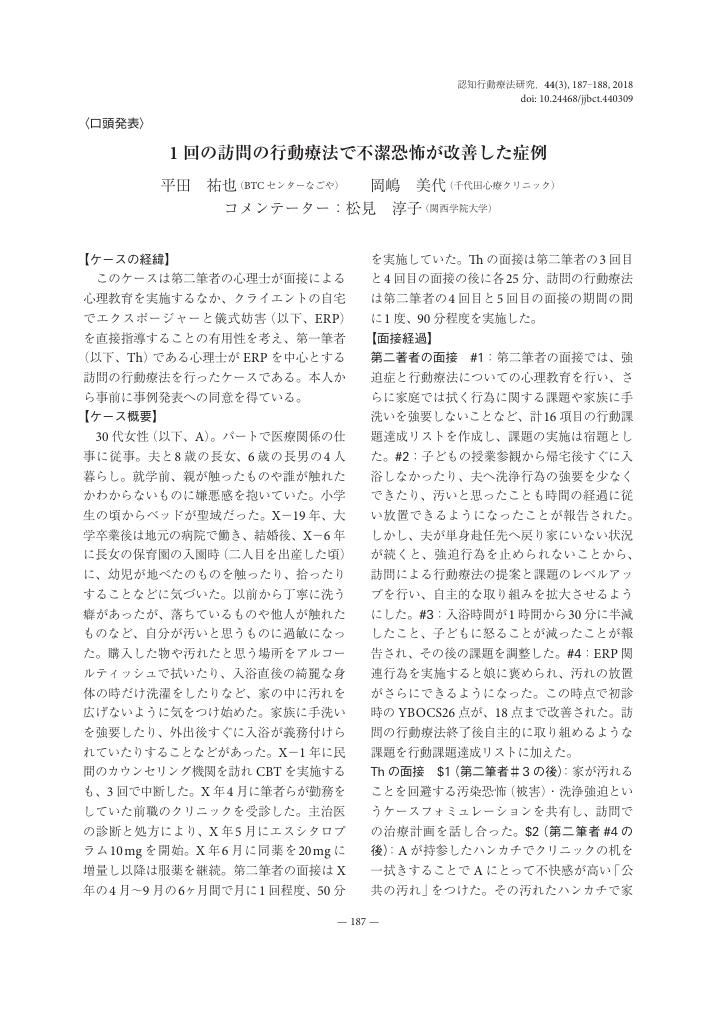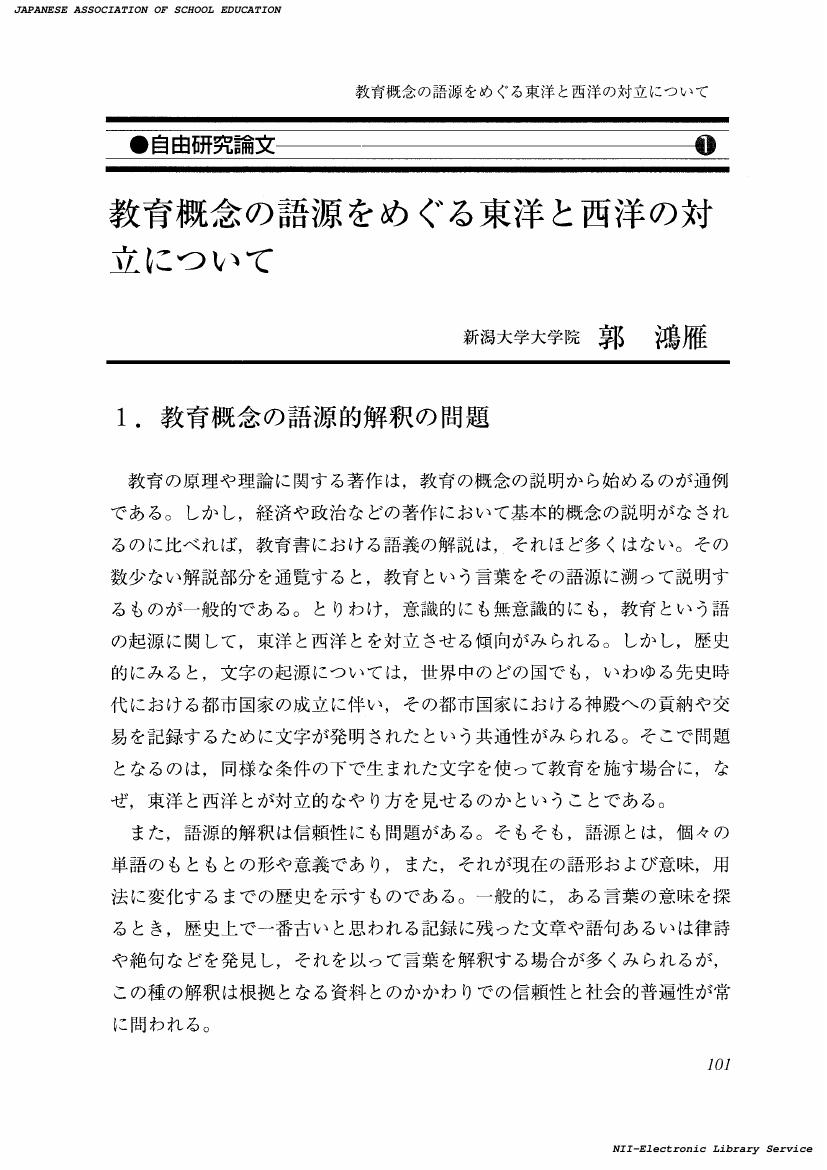2 0 0 0 OA 1回の訪問の行動療法で不潔恐怖が改善した症例
- 著者
- 平田 祐也 岡嶋 美代
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.187-188, 2018-09-30 (Released:2019-04-05)
2 0 0 0 OA 家族介護と公的介護に対する選好度の規定要因および関係性について
- 著者
- 渡辺 匠 唐沢 かおり 大髙 瑞郁
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.11-20, 2011 (Released:2011-08-30)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 4
本研究では,家族介護と公的介護に対する選好度の規定要因および関係性について検討を行った。一般成人331人を対象とした調査研究の結果,家族介護意識が家族介護・公的介護に対する選好度を規定していること,および,両者の選好度の間には背反的な関係があることが明らかになった。具体的には,調査対象者が被介護者の立場に立って回答した際に,家族介護への選好は介護サービス等の公的介護の利用抑制につながり,介護への態度が公的介護導入を制限する要因になることが認められた。一方,家族介護に伴う負担の懸念が高い場合は公的介護利用を志向して,介護サービスに対する税金使用への賛意が高まることが示唆された。しかし,以上の仮説モデルは心理的負債感によって調整されており,心理的負債感が低い人は返報義務を感じにくいために,介護受容における選択的選好や公的介護を利用する上での積極的関与が観察されなかった。以上の結果に基づき,介護選択と介護政策に対する態度の関連性や,介護受容における家族介護意識と心理的負債感の役割について議論した。
2 0 0 0 OA 疲労に至る等尺性運動後の筋硬度回復に対する振動刺激の効果
- 著者
- 松原 由未子 粟井 瞳 木村 護郎 今野 宏亮 徳元 仁美 佐々木 誠
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.341-345, 2004 (Released:2005-01-29)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 10 2
本研究の目的は,緊張性振動反射による興奮性効果と振動刺激による抑制性効果のいずれが,筋疲労時の筋硬度に影響するかを明らかにすることである。健常な学生20名(平均年齢24.4歳)を対象に,筋の疲労に至る等尺性運動直後に5分間,105 Hzの振動刺激を与える場合と振動刺激を与えない場合の筋硬度の変化を比較検討した。その結果,最大努力での等尺性運動によって筋疲労が生じ,これに伴って増した筋硬度は,振動刺激を与えることによって5分以上15分未満の間で回復が遅くなることが示された。振動刺激は疲労した筋に対して,緊張性振動反射による興奮性効果が優位に影響し,これに加えて,遮断された血流の除去作用の低下による疲労代謝物質の局所への停滞を増長することで,筋硬度を低下・回復させるのに有効に作用しないものと推察された。しかし,運動後15分には運動前と同程度の筋硬度に回復したため,筋硬度の増大は一過性であり,比較的早く影響がなくなるものと考えられた。
2 0 0 0 OA 組合せ論的ゲーム概説
- 著者
- 小林 欣吾
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.28-43, 2020-07-01 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 8
組合せ論的ゲーム理論の礎とも目されるE.R. Berlekamp, J.H. Conway, R.K. GuyによるWinning Ways for Mathematical Playsという今や古典的な名著の翻訳を昨年の秋に完了した.その機会に合わせてSITA2019霧島のワークショップにおいて講演したので,そのときの話題を中心に組合せ論的ゲームを解説する.組合せ論的ゲームというのは,2人のプレーヤが交互に着手し,ゲームの規則,勝敗の判定法など必要となる情報はお互いに完全に分かり合っており,偶然性は入らないゲームをいう.そのようなゲームは子供のお遊びのチック・タック・トウ(マルとバツ),点と箱などから,囲碁,将棋,チェスなどという高度の戦略を必要とするゲームまで広範囲にわたっている.ゲームの勝敗を知るためには,局面の値を決定することが重要である.そのような値は単に数だけでは表現できず,Conwayの発案になる実数を拡張した超限実数という概念も顔を見せてくる.
- 著者
- 森田 成也
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.108-110, 2011-07-20 (Released:2017-04-25)
2 0 0 0 OA 『先師金言要集』とアンダルズ文献研究序説 (下)
- 著者
- 伊藤 義教
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.15-31,104, 1964-10-30 (Released:2010-03-12)
This article is composed of three parts. In the 1st part, the writer has given a new translation of Citak Handarz i Poryotkesan. A new translation may be justified for ex. in §33 (cf. p. 15, n. 36), §54 (cf. p. 16, n. 47) and the beginning of §32: be pat han i χves hukunisnih “if not through his own good deeds” which should be taken as the last constituent of §31. In the 2nd part, the writer points out a morphologic relation between the early Achaemenian inscriptions and documents on the one hand, and the Andarz-literature on the other: in other words, Dar. Naqs-i-Rostam inscriptions as well as Xenophon's Cyropaedeia VIII 7, 1-28 are nothing but a sort of combination of historiography and andarz. It is interesting to note that parallelisms can be found between Dar. NRa 11. 56-58: martiya hya Auramazdaha framana hauv-taiy gasta ma θadaya and Citak Handarz i Poryotkesan §20: apak hamak vehan pat dat-χup-sandakih estatan “With all the good people one must stand in the situation that the Law seems (sandakih<sand-“videri”) agreeable (to himself)”. The 3rd and last part is a short survey of the Andarz-literature, leaving behind the problem of what development in thought and spirit this genre of literature has ever made.
2 0 0 0 OA 『先師金言要集』とアンダルズ文献研究序説 (上)
- 著者
- 伊藤 義教
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-17, 1964-08-15 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 市川 瑠美子 小室 竜太郎 井端 剛 正田 英雄 飯田 さよみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.23-28, 2012 (Released:2012-02-09)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
症例は64歳男性.54歳時に2型糖尿病と診断されボグリボース開始となったが10年後に血糖コントロール不良のため糖尿病教育入院となりインスリン強化療法を施行した.抗GAD抗体陰性,尿中C-peptide(CPR)は保たれており2相性インスリンアナログ製剤朝夕2回注射にて退院し良好な血糖コントロールが維持できた.ところが退院後3ヶ月の定期診察日に受診し,帰宅後夕食前血糖が突然562 mg/dlに上昇した.血糖急上昇後1ヶ月の血中CPR 0.10 ng/ml以下,4ヶ月の1日尿中CPR 0.95 μg以下であった.抗GAD抗体陰性であったが,好酸球増多,インスリン抗体陽性を認めた.高血糖が続き再度インスリン強化療法に変更したが血糖コントロールは難渋した.本例は2型糖尿病でインスリン導入後良好な経過中,血糖値上昇の日をとらえられた程の突然のコントロール悪化を認め,インスリン分泌能枯渇をきたした症例と考えられたので病態を考察し報告する.
- 著者
- Tatsuki TSUJIMORI
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.5, pp.217-226, 2017 (Released:2017-11-15)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 13 14
Paleozoic jadeitite–bearing serpentinite–matrix mélange represents the oldest mantle wedge record of a Pacific–type subduction zone of proto–Japan. Most jadeitites are fluid precipitates (P–type), but some jadeitites are metasomatic replacement (R–type) which preserve relict minerals and protolith textures. The beauty and preciousness of some gem–quality, semi–translucent varieties of jadeitites in the Itoigawa–Omi area led to the designation of jadeitite as the national stone of Japan by the Japan Association of Mineralogical Sciences. Zircon geochronology indicates jadeitite formed prior to Late Paleozoic Renge metamorphism that formed blueschist and rare eclogite. For example, in the Itoigawa–Omi and Osayama localities, older jadeitites and younger high–pressure/ low–temperature metamorphic rocks in a single mélange complex imply different histories for the subduction channel and jadeite–bearing serpentinite–matrix mélange. This suggests that the jadeitite–hosted mélange (or serpentinized peridotite) can stay within the mantle wedge for a considerable time; thus recrystallization, resorption, and re–precipitation of jadeitite can continue in the mantle wedge environment. Therefore, studies of Paleozoic jadeitites in Japan have great potential to elucidate the earliest stages of orogenic growth (oceanward–accretion and landward–erosion) associated with the subduction of the paleo–Pacific oceanic plates, and to test geophysical observations of modern analogues from a mixture of fossilized mantle wedges and subduction channels.
2 0 0 0 OA 教育概念の語源をめぐる東洋と西洋の対立について
- 著者
- 郭 鴻雁
- 出版者
- 日本学校教育学会
- 雑誌
- 学校教育研究 (ISSN:09139427)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.101-112, 1997-08-31 (Released:2017-07-27)
2 0 0 0 OA 複数台の産業ロボット間における接近速度に基づく干渉チェック方式開発
- 著者
- 白土 浩司
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.697-702, 2013 (Released:2013-10-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
In FA industry, recently, it has been getting more and more difficult for system integrators to check all collision cases among robots and peripherals before the operation. It is because that robotic production system gets more complex and intelligent, therefore, robots sometimes move on the defferent trajectories and timing in each bin picking motion or recovery sequence from irregular state. A new on-line collision check method for robots is proposed by using each approach speed among the collision check models. We show the algorithm of this method and confirm the effect of it by simulation.
2 0 0 0 OA 京都府内の大学の学生食堂における食事と食情報の提供実態
- 著者
- 高畑 彩友美 小谷 清子 吉本 優子 福田 小百合 尾崎 悦子 東 あかね
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.5, pp.293-301, 2021-10-01 (Released:2021-11-24)
- 参考文献数
- 33
【目的】京都府内の大学の学生食堂において,行政が推進する地産地消・食環境整備事業の登録と,食事と食情報の提供実態を明らかにし,大学生の健康増進のための食環境改善について検討すること。【方法】京都府内の全34大学11短期大学の全72食堂の食堂運営者を対象とした自記式質問調査を2017年に実施した。運営主体によって組合事業組織が運営する食堂(以下,「組合」)と,一般事業者が運営する食堂(以下,「一般」)に区分,さらに,行政が推進する食環境整備事業への登録状況から,登録群と非登録群に分けて比較した。調査項目は,食環境整備事業への登録,食事提供の形態,食事の内容,食・健康情報の提供内容等の12項目である。【結果】63食堂(「組合」33件,「一般」30件, 回答率87.5%)から回答を得た。行政が推進する食環境整備事業への登録は「組合」20.0%,「一般」34.5%であった。「一般」では非登録群と比較して,登録群では野菜料理,米飯量の調節,魚料理,定食の提供の割合が有意に高値であった。食情報の提供の割合は,登録群,非登録群間に差はなく「一般」より「組合」で高値であった。【結論】食環境整備事業への登録が「一般」での健康的な食事の提供と関連している可能性が示唆された。今後,行政,大学及び食堂運営者が連携し,学生食堂の食環境の改善と新しい形態の食情報提供により,学生の健康増進を図ることが望まれる。
2 0 0 0 OA 気体定数(どうやってそれを求めたの 3)
- 著者
- 高田 誠二
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.9, pp.574-578, 1998-09-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
気体の状態方程式に現われる定数R(いわゆる気体定数)は, 教育上どのように扱われているか-それを概説した上で, 計測上の問題を吟味し, 併せて, 定数の意味, 記号および数値の科学史上の知見を紹介する。
2 0 0 0 OA 血液検査による胃癌検診―リスク検診の現状と問題点を巡って―
- 著者
- 井上 泉 岡 政志 一瀬 雅夫
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.6, pp.477-484, 2020-06-20 (Released:2020-06-20)
- 参考文献数
- 40
H.pylori感染胃炎を中核とする胃癌発生の自然史に関する理解がすすみ,癌発生リスクの把握が可能になって来た.その結果,胃癌検診効率化を視野に,血液検査によるH.pylori感染胃炎ステージ診断・胃癌リスク評価に基づくリスク検診が検討されている.いまだ理論的な段階に留まるものであるが,今後,安定したシステムの登場が期待される.“いわゆるABC検診”に関しては,受診者の不利益を回避する上で,現状のシステムの導入には慎重であるべきで,実施可能なシステム・責任ある体制の構築のために,充分な検討が必要である.その他,本稿では血液検体による胃癌診断の現状・検診導入の可能性について概説する.
2 0 0 0 OA 雜録
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.220, pp.106-115, 1905 (Released:2013-05-14)
2 0 0 0 OA 雜録
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.227, pp.285-302, 1905 (Released:2013-05-14)
2 0 0 0 OA 台頭する中国のパブリック・ディプロマシー(公共外交)
- 著者
- 張 雪斌
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.18-37, 2015-07-31 (Released:2015-08-11)
- 参考文献数
- 86
After the end of the Cold War, many countries reviewed and reconsidered their public diplomacy (PD), recognizing the increasing importance of engagement with foreign nations and international opinion. With the rapid rise of China, public diplomacy (gonggong waijiao) became a very important concept in China’s national strategy and foreign policy during earlier periods of the 21st century. Recently, scholars within and outside China are paying attention to the purpose and features of China’s PD, due to the expanding presence of China’s PD and its soft power. However, questions such as “what are the factors that drive China to pursue PD?” or “how have the concept of China’s PD changed?” remain unanswered. This article analyzed the discourses of Chinese political elites and foreign policy experts through the perspectives of realism, constructivism, and neo-classical realism. As many scholars have mentioned, PD has been recognized as an important asset to enhance soft power and influence for China in the competition with “rivals” such as the US and Japan. The concept of PD, however, did not exist in official documents nor foreign strategy discourses until the early 2000s. This suggests that the appearance and development of China’s PD cannot be described only in the context of balance of power. It is also difficult to explain the developments of China’s PD as a process of complex learning through the view of constructivism. It is clear that Chinese political elites and foreign policy experts are learning about PD and even the concept of “new PD” developed in developed countries, which emphasizes that the role and autonomy of non-governmental actors are essential to the effectiveness and credibility of PD in the era of globalization, and they already have full understanding of the implications of PD from the discourses outside China. Chinese political elites and foreign policy experts, however, refrain from allowing the autonomy of non-governmental actors despite their important role in China’s current PD. Therefore, the process of change in China’s concept of PD should be explained as “simple learning” rather than “complex learning.” This article argues that the view of neo-classical realism is the most effective to comprehend China’s PD. Chinese elites’ perceptions of the international and domestic environment are the essential factor that has changed the concept of China’s PD.
2 0 0 0 OA 胆嚢にアミロイド沈着の見られた胆石症の1例
- 著者
- 溝口 哲郎 樋高 克彦 久次 武晴 宮原 晋一
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.7, pp.1419-1422, 1989-07-25 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 1
慢性関節リウマチに罹患している60歳の女性が胃生検をきっかけにアミロイドーシスと診断された.この患者は,1年前に胆石症のために胆嚢摘出術をうけており,その摘出胆嚢の再検でもアミロイドの沈着が証明された.この症例は通常の胆石症と異なり,貧血,低栄養状態,下痢,腹部単純X線撮影における腸閉塞様所見などを示し興味ある経過をとった.その後,腎機能障害と徐脈を呈し,慢性関節リウマチに続発した全身性アミロイドーシスと診断された.
2 0 0 0 OA 九九学習で誤答率の高い九九の要因と特異数 通常の学級の児童と発達障害児の九九学習結果より
- 著者
- 高畑 英樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本LD学会
- 雑誌
- LD研究 (ISSN:13465716)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.354-364, 2018 (Released:2020-12-03)
- 参考文献数
- 35
誤答率の高い九九は,通常の学級及び発達障害児を対象とした結果とも,4(し)と7(しち),7(しち)と8(はち)の音韻が似た数字の入っている九九が多かった。また,2月の段階では,7×6と6×7,7×4と4×7のように,交換法則の成り立つ九九をセットで間違えている可能性が高かった。通常の学級と比べて,発達障害児の九九学習における誤答の特徴をあげるとすれば,被乗数が7,8,9と九九学習後半で学習する数が多かった。特異数については,通常の学級では,1と5の正答数が高くなっていることから,かけ算九九において1と5は正答率が高く機能する特異数であることが示唆された。発達障害児のかけ算九九において,正答率が高く働く数字として機能する特異数は,1のみであった。通常の学級で正答率の高い特異数として示唆された5の数字が,被乗数または乗数に含まれる九九では,誤答率の高いものが2つあった。
2 0 0 0 OA 1. キャプテンシステムとキャプテンプロトコル
- 著者
- 小林 幸雄
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.400-407, 1985-05-20 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2