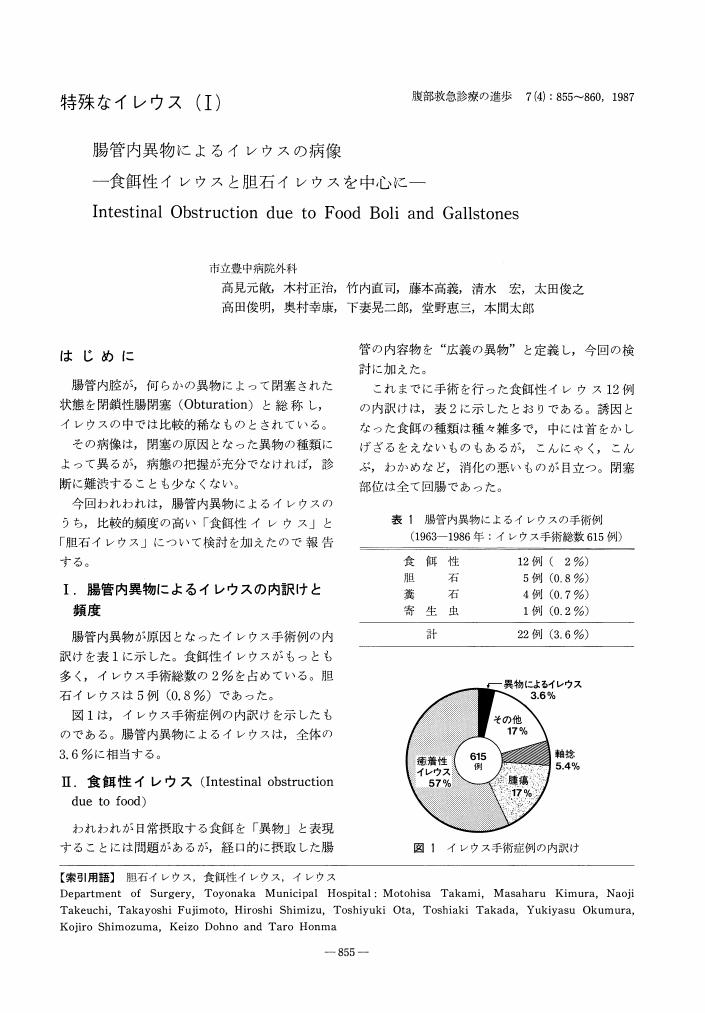2 0 0 0 OA 腸管内異物によるイレウスの病像
2 0 0 0 OA 自治医大外科教室におけるイレウス症例の検討 ―特にイレウスによるショックについて―
2 0 0 0 OA 小児消化管の超音波診断
2 0 0 0 OA 公教育の構造変容
- 著者
- 小玉 重夫
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.21-38, 2002-05-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 1
The 1990s were a turning point in world history; as Eric Hobsbawm wrote in his recent book, the “short twentieth century” ended in the early 1990s. With regard to public education, not only in Europe and North America, but in Japan as well, the structure of the public education system underwent dramatic change during the 1990s.In this paper I examine the characteristics of this change. The dominant feature of the change in the 1990s has often been conceptualized as “liberalization, ” or the “deregulation” or “marketization” of public education. However, this conceptualization does not adequately grasp the political aspect of the change, as Chantal Mouffe demonstrated when she termed it “the return of the political, ” or Nancy Fraser when she called the dilemma of justice in a “post-socialist” age one that was moving “from redistribution to recognition.” Focusing on this political aspect of the change in public education in the 1990s, I clarify the specificity of the historical context of this change.As in the Western countries, opportunities for public education in Japan expanded to all areas of society during the 1960s. There was, however, an important difference in the characteristics of this expansion between the West and Japan. In the West, it was initiated by the policy of the welfare state. In Japan, by contrast, the role of the welfare state was less important, and was replaced by the depoliticized triangle of family, school, and private enterprise.In the 1990s, Japan experienced major social and political upheavals. The “bubble economy, ” which had prevented the manifestation of economic crisis, burst in the early years of the decade. The depoliticized triangle of family, school, and private enterprise, which had replaced the welfare state, fell into a crisis of legitimacy.It was at this point that the triangle began to break down, and the need arose for an alternative to it. In this situation, the actual possibility emerged of a return of “the political.” In order to seek this possibility, it is necessary to reconstruct the space of political significance as well as democratic citizenship. The task of public education here should be focused on political life, which is, as Giorgio Agamben cited, to be distinguished from biological life. This is one of the most important points in the restructuring of public education.
2 0 0 0 OA 都道府県・政令指定都市におけるペアレントメンターの養成及び活動に関する実態調査
- 著者
- 原口 英之 小倉 正義 山口 穂菜美 井上 雅彦
- 出版者
- NPO法人 日本自閉症スペクトラム支援協会 日本自閉症スペクトラム学会
- 雑誌
- 自閉症スペクトラム研究 (ISSN:13475932)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.51-58, 2020-02-29 (Released:2021-02-28)
- 参考文献数
- 5
全国の都道府県と政令指定都市(以下、指定都市)におけるペアレントメンター(以下、メンター)の養成及び活動の実態を調査し、今後の自治体でのメンターの養成及び活動の普及に向けた課題を検討した。都道府県39箇所(83%)と指定都市16 箇所(80%)から回答を得た結果、個々の自治体の取り組みの実態にはばらつきがあるものの、都道府県、指定都市の実態には概ね共通する部分が多いことが明らかとなった。都道府県、指定都市ともに、5 ~6 割の自治体でメンターの登録制度があり、6 ~7 割の自治体で養成研修修了者への研修が実施されていた。メンターの活動は、6 ~7 割の自治体で実施され、グループ相談、保護者向け研修、保育者向けの研修が多く実施されていた。また、メンター活動の予算のある自治体は6 割、活動の謝礼・報酬のある自治体は4 ~5 割、コーディネーターが配置されている自治体は4 割であった。一方、養成研修の修了者のうちメンターとして登録し活動する人数の割合、養成研修の実施状況、活動評価の方法、情報交換・協議の場の有無については、都道府県、指定都市で違いが見られた。本研究の結果は、都道府県と指定都市、さらには市町村におけるメンターの養成と活動を評価、検討する上での基礎資料となり得るものである。今後、全国でメンターの養成及び活動の普及を目指すためには、メンター養成と活動の取り組みの有無に影響する要因、取り組みを促進するための要因について抽出することが必要である。
2 0 0 0 OA 「算数指導法を語る」(座談会)
- 出版者
- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)
- 雑誌
- 算数教育 (ISSN:04030427)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.17, 1953 (Released:2021-10-01)
2 0 0 0 OA ラクウショウ含有タキソジオンによるBCR-ABL陽性白血病細胞のアポトーシス誘導機構
- 著者
- 内原 脩貴 多胡 憲治 多胡 めぐみ
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.153, no.4, pp.147-154, 2019 (Released:2019-04-11)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 2
BCR-ABLは,慢性骨髄性白血病(CML)や急性リンパ芽球性白血病(ALL)の原因遺伝子産物であり,転写因子STAT5やキナーゼAktの活性化を介して強力な形質転換能を示す.BCR-ABLを標的とした分子標的薬イマチニブの開発により,CMLやALLに対する治療効果は劇的に改善された.しかしながら,イマチニブの継続的な投与により,bcr-abl遺伝子にイマチニブ耐性を示す二次的な突然変異が生じることも報告されている.これまでに,イマチニブ耐性CMLやALLに対する第二世代のBCR-ABL阻害薬として,ニロチニブやダサチニブが開発されているが,BCR-ABLのATP結合領域に存在するT315I変異は,これらの第二世代のBCR-ABL阻害薬に対しても抵抗性を示すため,薬剤耐性を克服した新規の白血病治療薬の開発が望まれている.我々は,ヒノキ科ヌマスギ属の針葉樹であるラクウショウの球果から抽出されたアビエタン型ジテルペン化合物であるタキソジオンが,細胞内の活性酸素種(ROS)を産生することにより,BCR-ABL陽性CML患者由来K562細胞のアポトーシスを誘導することを見出した.タキソジオンは,ミトコンドリア呼吸鎖複合体Ⅲの活性を阻害することにより,ROSの産生を誘導した.また,タキソジオンは,ROSの産生を介して,BCR-ABLやその下流シグナル分子であるSTAT5やAktをミトコンドリアに局在させ,これらの分子の活性を阻害するというユニークな機序により,BCR-ABL陽性細胞のアポトーシスを誘導することを新たに見出した.さらに,タキソジオンは,T315I変異を有するBCR-ABL発現細胞に対しても強力な抗腫瘍活性を示すことが明らかになった.我々の研究成果は,タキソジオンがBCR-ABL阻害薬に耐性を示すCML,ALLの新たな治療薬として応用できる可能性を示すと共に,BCR-ABL以外の原因遺伝子に起因する様々な腫瘍性疾患に対する治療薬開発においても重要な手掛かりとなると期待される.
2 0 0 0 OA チーム医療によるアルブミンの国内自給推進について
- 著者
- 牧野 茂義
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.515-521, 2015-12-20 (Released:2016-02-13)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA Coronary Sinus Tumor/Thrombus Associated With Renal Cell Carcinoma With Inferior Vena Cava Invasion
- 著者
- Hiroshi Yonekura
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-21-0137, (Released:2021-11-06)
2 0 0 0 OA 神経毒性試験
- 著者
- 高橋 宏明 高田 孝二
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.6, pp.462-467, 2008 (Released:2008-06-13)
- 参考文献数
- 8
農薬などの化学物質の安全性評価の分野では,脳神経系の機能,形態,発達への影響を体系的に評価するガイドラインが整備されている.その特徴は,一般毒性試験を1次スクリーニング試験と位置づけ,成獣期ならびに発達期のガイドラインを揃えることによって,脳神経系への影響を段階的に評価することにある.本稿では,神経毒性に関連するガイドラインを紹介し,世界的な標準であるOECDガイドラインに基づいて哺乳動物を対象にした神経毒性試験を解説した.
2 0 0 0 OA 重力感受性を評価する検査 Head Tilt SVV の開発と臨床応用
- 著者
- 塩崎 智之 和田 佳郎 伊藤 妙子 山中 敏彰 北原 糺
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.274-280, 2020-08-31 (Released:2020-10-01)
- 参考文献数
- 12
There are patients with floating dizziness who do not show abnormalities in current vertigo balance tests. We developed a clinical examination to quantify gravity perception as a first step to test our hypothesis that a gravity perception disturbance is the cause of floating dizziness. The gravity sensitivity can be measured accurately by adding the head tilting condition to the original subjective visual vertical (SVV) test. We named this test the Head Tilt SVV (HT-SVV). The most important measurement item in HT-SVV is head tilt perception gain (HTPG). HT-SVV measurements in 329 healthy subjects yielded an average value and standard deviation of 1.02±0.12 and a reference value of 0.80-1.25 for HTPG, and a difference between the left and right HTPG of 4.7±3.7%, i.e.,<10.0%. We could not detect age-related changes in gravitational sensitivity by the original SVV, but found that HTPG, determined by HT-SVV, increased with age. A significantly higher rate of subjective dizziness was noted in patients who tested positive in the HT-SVV than in those who tested negative among patients who developed floating dizziness after BPPV. We would like to clarify the clinical significance of the test method and establish the concept of gravitational susceptibility disorder, although a number of relevant issues still remain to be clarified.
2 0 0 0 OA 日本の国民線量―特に外国との比較―
- 著者
- 市川 龍資
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.12, pp.927-938, 2013 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4 4
私達は常に種々の原因で放射線を受けている。日本国民が受けている自然及び人工の線源からの被ばく線量は全体で国民1人あたり年間5.98mSvの実効線量と推定された。このうちの大部分を占めるのは,自然放射線の2.1mSv/年と医療被ばく線量の3.87mSv/年の二つである。日本と欧米諸国との国民線量の違いは,日本人のラドンの線量が比較的少ないこと,そして食物からの210Po摂取による体内被ばく線量の大きいことである。その原因は日本人の魚介類摂取量の多いことによっている。魚介類は210Po含有量が多い故である。
2 0 0 0 OA JADER における医師および薬剤師による有害事象報告の比較
- 著者
- 豕瀬 諒 髙谷 瑞穂 村木 優一
- 出版者
- 一般社団法人 日本医薬品情報学会
- 雑誌
- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.135-140, 2020-11-30 (Released:2020-12-15)
- 参考文献数
- 13
Objective: In Japan, healthcare professionals are required to report the adverse drug events that occur with the use of medicines to the Minister of Health, Labor, and Welfare. The reported information is collected in the Japanese Adverse Drug Event Report database (JADER) and is freely available. There are no reports that evaluated the adverse events (AEs) in JADER based on the need for a physician’s diagnosis. This study classified AEs by pharmacists or physicians in JADER based on the need for a physician’s diagnosis and evaluated the differences in their contents.Methods: AEs reported by pharmacists, physicians, pharmacists and physicians in the economic years 2004 to 2017 in JADER were collected annually, and the trends were compared. The AEs of methotrexate in 2017 were classified into two groups based on the need for a physician’s diagnosis. The necessity of a physician’s diagnosis was judged by two senior pharmacists and compared using the chi-squared test.Results: The number of AEs reported by pharmacists and physicians from 2004 to 2017 increased from 689 to 7,127 and from 20,933 to 39,382, respectively. Among the AEs of methotrexate in 2017, AEs requiring physician’s diagnosis reported by pharmacists were 337 events and physicians were 2,413 events. Whereas, AEs that did not require a physician’s diagnosis reported by pharmacists were 172 events and physicians were 321 events. Physicians had significantly more AEs requiring diagnosis than pharmacists did (p< 0.0001).Conclusion: The reports of pharmacists with JADER have fewer AEs with the diagnosis than those of physicians.
2 0 0 0 OA 水平内外転運動における肩甲骨の役割
- 著者
- 芝野 康司 菅本 一臣
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.754-757, 2016-10-18 (Released:2016-11-17)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
肩関節運動は肩甲骨と上腕骨の共同運動であり,またリハビリテーション(以下,リハ)においてもその役割は重要視されている.しかし,肩甲骨の動きは外転運動などでは明らかにされているが,水平内外転運動に関しては,あまりよく知られていない. また肩関節外旋位での水平内外転運動は,肩関節脱臼や投球動作のcocking phaseに相当し,脱臼術後のリハにおいても肩甲骨の動きが不十分であれば,可動域制限をきたす.健常人の肩関節水平内外転運動における肩甲骨の3次元動態解析を行い,肩甲骨の動態を解明することにより,肩関節の機能改善につながることを期待する.
- 著者
- 青木 康彦 野呂 文行
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.2-10, 2020-08-20 (Released:2021-08-20)
- 参考文献数
- 16
研究の目的 本研究では、発達障害児2名を対象に80回の随伴ペアリングを実施し、称賛が条件性強化子として成立し、維持するかを検討した。場面 大学のプレイルームで行った。対象児 発達障害のある幼児2名であった。行動の指標 “両手合わせ”、“ハイファイブ”の生起頻度であった。研究計画 “両手合わせ”にABCBデザイン、その後、コメントの条件性強化子成立、維持を検討するため、“ハイファイブ”にABデザインを用いた。介入 標的行動に随伴させて日常生活で聞くことが少ないコメント(中性刺激)を称賛として与え、同時にお菓子(強化子)を対提示した。結果 2名中2名で随伴ペアリング前の称賛期よりも随伴ペアリング後の称賛期において“両手合わせ”の生起頻度が多かった。また、2名中1名において随伴ペアリング期後の称賛期において“両手合わせ”の生起頻度は高頻度で6ブロック維持し、随伴ペアリングを行っていない“ハイファイブ”においても、消去期よりも称賛期において生起頻度が多かった。結論 80回の随伴ペアリングにより2名中2名で称賛コメントが条件性強化子として成立し、2名中1名で称賛コメントの条件性強化子の強化価が維持するものであった。
- 著者
- 新庄 正宜 岩田 敏 佐藤 吉壮 秋田 博伸 砂川 慶介
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.5, pp.582-591, 2012-09-20 (Released:2013-04-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 11 14
2009 年1 月から2010 年12 月までの2 年間に全国95 施設から小児細菌性髄炎314 症例(男児186,女児124,性別未報告4 例)が報告された.年齢別では0 歳児が51.2%(161/314)と半数を占めた.原因菌として,Haemophilus influenzae(1 カ月~5 歳)が53.2%(167/314)と最も多く,次いでStreptococcus pneumoniae (1 カ月~12 歳)が24.2%(76/314),Streptococcus agalactiae(4 カ月以下のみ),Escherichia coli(3 カ月以下のみ)と続いた.耐性菌の率は,H. influenzae で50.1%(78/153),S. pneumoniae で63.0%(46/73)であった.初期治療薬は,4 カ月未満ではampicillin(ABPC)+セフェム系薬ならびにカルバペネム系薬+その他のβ ラクタム系薬の2 剤を併用した症例が77.8%(42/54)と多く,4 カ月以降ではカルバペネム系薬+その他のβ ラクタム系薬の併用が76.4%(198/259)を占めた.最終治療薬としては,H. influenzae でcefotaxime(CTX)もしくはceftriaxone(CTRX),S. pneumoniae でカルバペネム系薬の単剤が最も多かった.致死率は2.0%(6/305)であった.インフルエンザ菌b 型ワクチン(以下,Hib ワクチン)を接種したのは 5 名のみで,いずれもH. influenzae 髄膜炎以外の髄膜炎を発症した.7 価肺炎球菌結合型ワクチン(以下, PCV7)の接種者はいなかった.Hib ワクチン,PCV7 の普及していない現時点では,小児細菌性髄膜炎の特徴に,ここ数年間大きな変化はなかった.
2 0 0 0 OA 温室栽培ランに生息するササラダニ類について
- 著者
- 青木 淳一
- 出版者
- The Acarological Society of Japan
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.7-13, 1992-05-25 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 3
栃木県宇都宮市上横田町にある温室内で栽培されているランの一種(Vanda)の茎・葉・花および培地から多数のササラダニ類が発見され,調査の結果,それらはパナマ,コロンビア,ヴェネズエラから知られるMochlozetes penetrabilis Grandjean(マルコバネダニ,新称),グァテマラから知られるPeloribates grandis(Willmann)(オオマルコソデダニ,新称),日本南部に分布するScheloribates decarinatus Aoki(ミナミオトヒメダニ,新称),および新種Hemileius clavatus(イムラフクロコイタダニ,新称)の4種からなることがわかった。これらのダニはランの輸入先であるタイ国から植物体に付着して移入されたものと思われる。今のところ植物に対する害の有無は不明であるが,ダニ体内に生きた植物に由来すると思われるものは見られず,一部の個体からは多量の菌類の胞子が見つかったことから,ランの植物体上や培地に生育する菌源を栄養源としているものと推定される。
2 0 0 0 OA 尼崎で起こりかけた宗論
- 著者
- 天野 忠幸
- 出版者
- 尼崎市立歴史博物館
- 雑誌
- 地域史研究 (ISSN:09108661)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.120, pp.130-134, 2021 (Released:2021-11-04)
- 著者
- Kenichi Kawano Fumiaki Yokoyama Kouhei Kamasaka Jun Kawamoto Takuya Ogawa Tatsuo Kurihara Shiroh Futaki
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.11, pp.1075-1082, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 4
Extracellular vesicles (EVs) have emerged as important targets in biological and medical studies because they are involved in diverse human diseases and bacterial pathogenesis. Although antibodies targeting the surface biomarkers are widely used to detect EVs, peptide-based curvature sensors are currently attracting an attention as a novel tool for marker-free EV detection techniques. We have previously created a curvature-sensing peptide, FAAV and applied it to develop a simple and rapid method for detection of bacterial EVs in cultured media. The method utilized the fluorescence/Förster resonance energy transfer (FRET) phenomenon to achieve the high sensitivity to changes in the EV amount. In the present study, to develop a practical and easy-to-use approach that can detect bacterial EVs by peptides alone, we designed novel curvature-sensing peptides, N-terminus-substituted FAAV (nFAAV) peptides. The nFAAV peptides exerted higher α-helix-stabilizing effects than FAAV upon binding to vesicles while maintaining a random coil structure in aqueous solution. One of the nFAAV peptides showed a superior binding affinity for bacterial EVs and detected changes in the EV amount with 5-fold higher sensitivity than FAAV even in the presence of the EV-secretory bacterial cells. We named nFAAV5, which exhibited the high ability to detect bacterial EVs, as an EV-sensing peptide. Our finding is that the coil–α-helix structural transition of the nFAAV peptides serve as a key structural factor for highly sensitive detection of bacterial EVs.
- 著者
- 野田 一郎
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.53-58, 1958-03-01 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 6 9
アブラムシにおける胎生雌の型決定には温度,光その他いろいろの要素が関係しているようであるが,ムギ類の害虫であるキビクビレアブラムシRhopalosiphum prunifoliaeの場合には高棲息密度と絶食が大きな影響力を持っている(野田,1954, 1956)。これら諸要素の作用と有翅型出現の関係を明らかにするためには,まず型決定の臨界期を明確にしておくことが先決問題である。本実験においては上述の2要素(高棲息密度と絶食)の作用を利用して,このアブラムシにおける前記臨界期と生翅の最盛期を明らかにすることができた。実験はすべて暗黒下定温25°Cで行った。その結果を要約すると次のとおりである。1) 有翅型は胎生された直後から生後38.5時間目(これは第1回脱皮直後から起算すると10時間目にあたる)以内の間に決定される。この臨界期を経過した後においては外部からの刺激の影響を受けることがない。2) 理論上の生翅の最盛期は生後21時間目である。すなわち幼虫第1令後半期の半ばごろである。3) 50%以上の幼虫が5時間の絶食によって有翅型に変り得る時期は,理論的には生後14.5時間目から生後27.5時間目までの間である。この時期は幼虫第1令の中期から後期に相当する。4) 絶食の有翅型出現に対する影響力は,高棲息密度のそれよりも一般に大きいようである。5) 同一の生育途上にある幼虫を絶食させた場合には,絶食期間の長いほど有翅型出現率が高くなる。6) しかるに生後15時間または20時間経過した幼虫を5時間絶食させた場合と,生直後の幼虫または生後5時間経過したものを15時間絶食させた場合とを比較すると,後者のほうがはるかに絶食時間が長いにもかかわらず,有翅型出現率はかえって低位である。これは生育初期に絶食の刺激を加えると,SHULL (1942)が暗示したように生翅に関係あるホルモンの分泌などに,変調をきたすためではないかと考えられる。