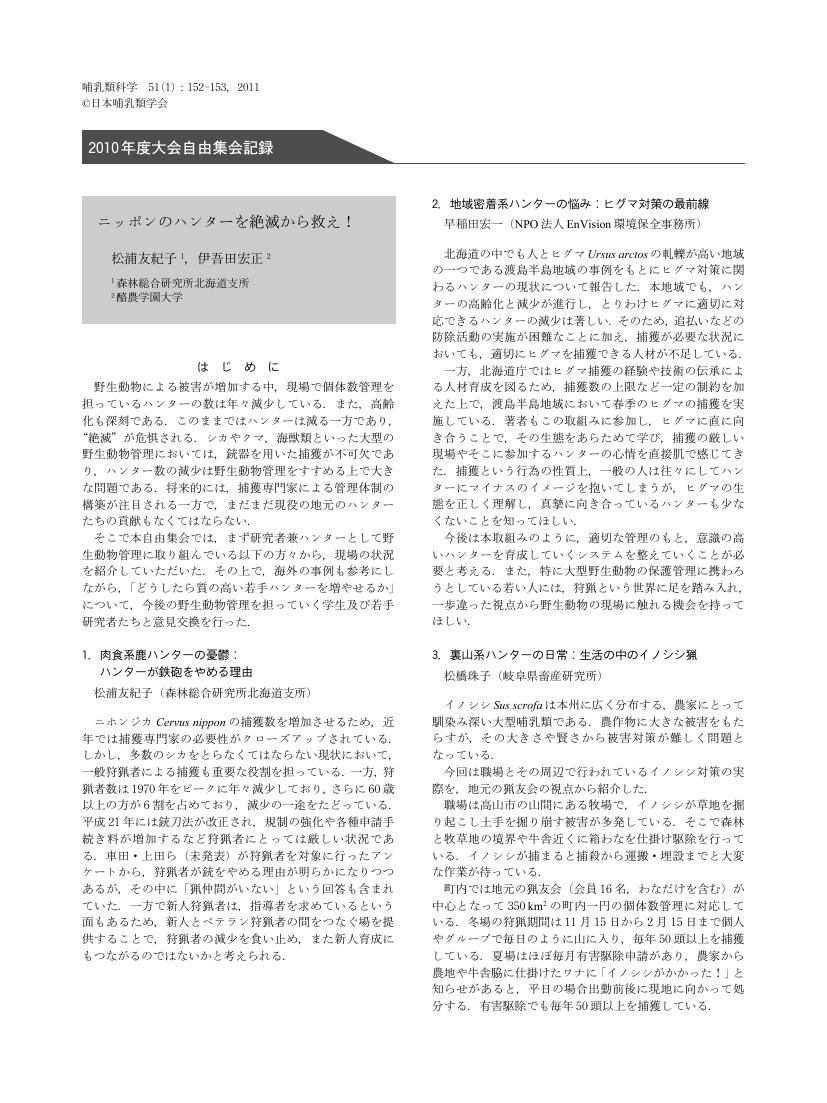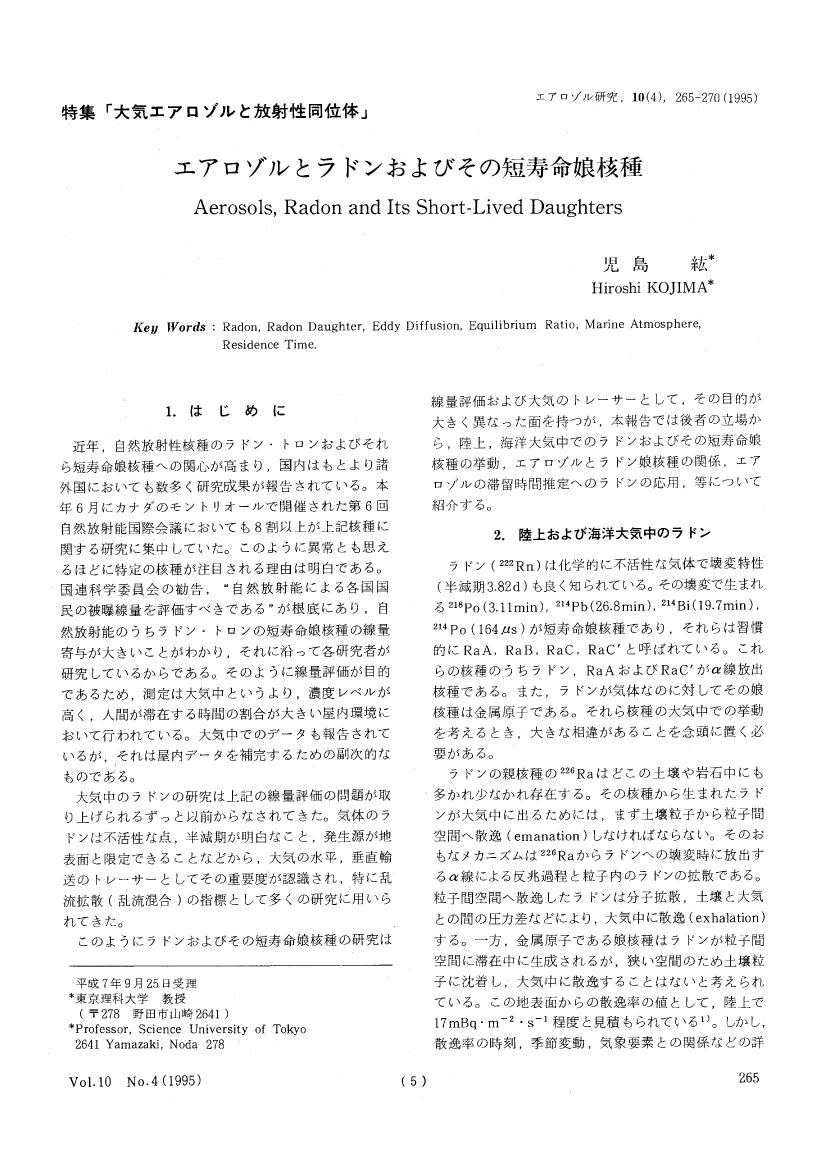本科研2年目そして最終年度にあたる本年は、それまでの研究成果を公表していくことが目標であり、一応その目標達成することはできたと判断する。女性が十八世紀末において福音主義を受容していく過程で、宗教的な要素ばかりではなく、感受性文化の中で受容し、さらに慈善活動や消費活動といった社会行動へと応用し、さらには日記や詩、小説といった文学においても宗教的感性を発露させていったことは重要な意義を持つことを確認した。文学において宗教的要素は軽視される傾向が強いが、とくに十八世紀後半からのイギリスにおいて福音主義の及ぼした影響は広範囲かつ甚大であり、それが行動様式のみならず言説上にもはっきりとした痕跡を残しているのは当然といえば当然なのだが、クエーカーの女性はもちろんのこと、ユニタリアン派の女性の言説においても露骨に政治的な意味をもってその痕跡が残っているのは学術上新しい発見であったと言ってよい。また、ハナ・モアのような国教会福音主義者たちの言説には、福音主義が単に慈善や政治イデオロギーと結びついているのではなく、女性たちを「公共圏」へと参画させる推進力を保持していることが証明できた。一年のほとんどを国内における資料調査を行いながら、学会発表は論文執筆に費やした。ノリッジの女性たちの文学作品と福音主義の影響、およびフランシス・バーニーの小説における慈善と福音主義の関係については、12月末から調査・研究をはじめ、2月に3週間にわたる海外資料調査を行って国内にない資料調査を行った。それらについての論考は現在投稿中であり、来年度に公表される予定である。
1 0 0 0 ひずみを許すユニバーサル符号化
- 著者
- 金谷 文夫
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.6, pp.691-697, 2001-06-01
- 被引用文献数
- 1
本論文では, 最初にひずみを許すユニバーサル符号化の基礎となるレートひずみ理論の中心概念であるひずみを許す符号化定理について概説する.次いでひずみを許すユニバーサル符号の存在定理について概説し, 最後に最近のひずみを許すユニバーサル符号化アルゴリズムの研究状況の一端を紹介する.
1 0 0 0 「findout」
- 著者
- 岡崎 弘美
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 日本計算機統計学会シンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.75-76, 1992-10-15
1 0 0 0 OA テレビジョン・フォークロア--テレビ受像機の民俗学、その今日的意義と学問的系譜
- 著者
- 飯田 豊
- 出版者
- 福山大学
- 雑誌
- 福山大学人間文化学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.45-61, 2009-03
- 著者
- 吉本 成香
- 出版者
- 新樹社
- 雑誌
- 月刊トライボロジー (ISSN:09146121)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.6, pp.36-39, 2007-06
1 0 0 0 OA 堆肥施用が茶園土壌の硝酸態窒素濃度に及ぼす影響
1 0 0 0 OA 群馬県における地下水硝酸性窒素濃度低下に関する考察
- 著者
- 堀越 壮一 飯島 明宏 冨岡 淳 関 順司 加藤 政彦 小澤 邦壽
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.283-286, 2007 (Released:2010-01-09)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 2
Recently, nitrate-nitrogen (NO3-N) pollution in groundwater was identified as a serious problem in Gunma prefecture. The rate of satisfying the environmental quality standard(EQS) for NO3-N concentration in Gunma prefecture was lowest in Japan from 2000 to 2004. However, a significant decrease in NO3-N concentration was observed in 2005. Therefore, the factors contributing to the decrease were statistically examined. The results suggest that the area of dry field, livestock head count, and agricultural population significantly contributed to the decrease in NO3-N concentration. The enforcement of the Law on Promoting Proper Management and Use of Livestock Excreta might reduce NO3-N discharge into groundwater.
1 0 0 0 OA ニッポンのハンターを絶滅から救え!
1 0 0 0 OA 生物多様性保全に向けたニホンジカの個体数管理
1 0 0 0 OA 売り声文化その社会的考察
- 著者
- 小池 保
- 出版者
- 尚美学園大学
- 雑誌
- 尚美学園大学芸術情報学部紀要 (ISSN:13471023)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.47-67, 2006-11-30
かつての売り声は、なぜ日本人の心の原風景に流れるBGMとなり得たのか—— 心に響く表現が、どのように工夫されていたのか、音声分析を用いながら考察を重ねるうち、売り声が「市井の詩」となり得たいくつかの条件をはじめ、高いコミュニケーション力を備えていることが明らかになってゆく。やがて、拡声器で売り声を聞かせる時代が到来する。なぜ拡声器が用いられたのか、日本人の住まい方の構造変化にまつわる問題点が見えてくる。その点に注目しながら探るうちに、戦後に起こったコミュニケーション上のパラダイム・シフトとの関係が浮かび上がる。日本人に親しまれた売り声の文化は、事実上、消えてしまった。しかし、それは生活の片隅でさえずっていた小鳥がいなくなったというレベルの、ささいな出来事ではなかった。忍び寄る気体の毒性をいち早く知らせる、カナリアの死であったのかもしれない。
1 0 0 0 超知能機械たち
- 著者
- 稲吉 宏明 翻訳:稲吉宏明
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.11, pp.1106-1109, 2001-11-15
本コラムは[通常のACM SIGGRAPH 誌中の "visfiles" コラムで取り上げている]情報可視化(visualization)についてではなく,機械知能についてである.Ray Kurzweilの SIGGRAPH 2000でのこのテーマに関する基調講演はとても好評で,彼はその翌日,議論を続けるために再招待されたほどである.このことからも分かるように本テーマについては,多くの人が興味を持っているようである.
1 0 0 0 OA 「風流線」の背景
- 著者
- 上田 正行
- 出版者
- 金沢大学
- 雑誌
- 金沢大学文学部論集. 文学科篇 (ISSN:02856530)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-43, 1987-02-25
- 著者
- 金子 絵里乃
- 出版者
- 一般社団法人日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.43-59, 2007-02-28
本研究では,小児がんで子どもを亡くし,SHG/SGに参加した経験をもつ母親15人の悲嘆過程を分析し,分析結果から得られた知見を基に考察を行った.分析の結果,グループに参加する前については,「解放感を抱く」「ショックを受ける」「身のおき所を失う」「現実を受け入れられない」「人と疎遠になる」「家族関係の変化」という6つのカテゴリーが見いだされた.グループに参加した背景については,「黙された悲嘆」と「参加への踏み出し」という2つのカテゴリーが見いだされた.グループに参加したときについては,「現実を直視する」「固定観念を取り外す」「生きる力を見いだす」「自己の変化を認識する」「悲嘆が深まる」という5つをカテゴリーが見いだされた.グループに参加した後については,「バランスを保ちながら生活する」「子どもとのつながりを維持する」「気持ちを立て直す」という3つのカテゴリーが見いだされた.
1 0 0 0 OA バーナード・リーチと民藝運動に関する比較文化的研究
本研究はイギリスの芸術家バーナード・リーチ(1887-1979)の活動と、柳宗悦(1889-1961)が主導した日本の民藝運動を題材として、対抗産業革命counter-Industrial Revolutionという観点から20世紀の日英の文化史を振り返った。リーチと柳、及びその周辺の人々は、芸術と生活という観点から、産業革命がもたらす負の要素を批判・是正することを工芸分野において試み、ある程度の成果を上げた。本研究は、リーチ、柳らが携わった対抗産業革命の理念とその実践を解明し、対抗産業革命という視点が20世紀の文化史研究に有効であることを確かめた。
1 0 0 0 IR 書想 : 図書館報附録. 第33号
- 著者
- ナラキョウイクダイガクフゾクトショカン 奈良教育大学附属図書館
- 出版者
- 奈良教育大学附属図書館
- 雑誌
- 書想 : 図書館報附録
- 巻号頁・発行日
- vol.33, 1977-12
ハワイ・セミナーで学んだもの(一) 佐藤秀志/ハッタギ 川本崇雄/蛇足 山口満/井伏鱒二さんの手紙 山内洋一郎/島木健作の「礎」について 石井滋規
1 0 0 0 IR 不登校の親の会はセルフヘルプ・グループか?--北海道の23団体を対象として
- 著者
- 菊地 千夏
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院
- 雑誌
- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)
- 巻号頁・発行日
- no.110, pp.23-47, 2010
- 著者
- 三枝 壽勝
- 出版者
- 東京外国語大学
- 雑誌
- 総合文化研究 (ISSN:18831109)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.25-35, 1998
1 0 0 0 直腸癌術後に発生した腸閉塞をきたした腸間膜脂肪織炎の1例
- 著者
- 田中 千弘 松村 幸次郎 樫塚 登美男 佐野 純 天岡 望
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 = The journal of the Japan Surgical Association (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.12, pp.3168-3171, 1998-12-25
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 12
- 出版者
- 鉄道図書刊行会
- 雑誌
- 鉄道ピクトリアル (ISSN:00404047)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.44-57, 2008-02