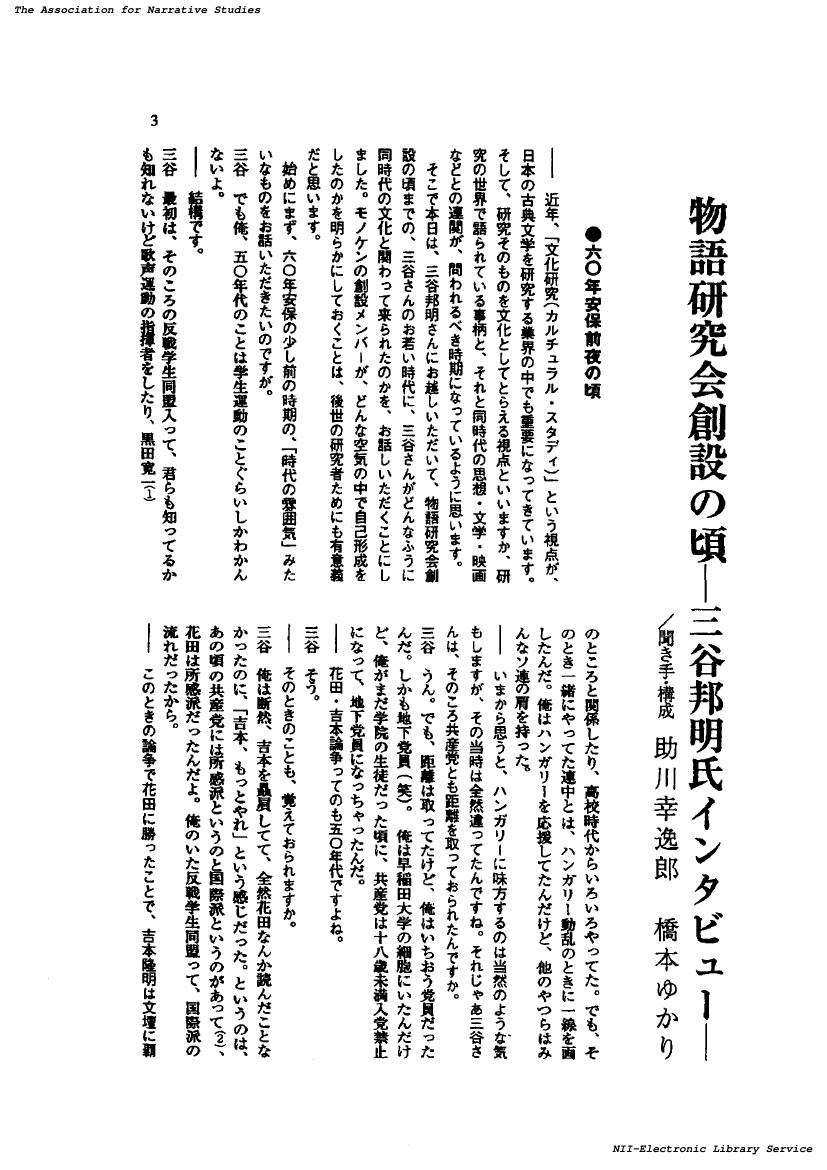4 0 0 0 OA 足利義満の青海波 : 「中世源氏物語」の〈領域〉(<特集>年間テーマ「区分・領域」)
- 著者
- 三田村 雅子
- 出版者
- 物語研究会
- 雑誌
- 物語研究 (ISSN:13481622)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.55-70, 2001-03-30 (Released:2018-03-27)
4 0 0 0 OA 『土佐日記』における「パロディー」(<特集>年間テーマ「区分・領域」)
- 著者
- 佐藤 美弥子
- 出版者
- 物語研究会
- 雑誌
- 物語研究 (ISSN:13481622)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.22-32, 2001-03-30 (Released:2018-03-27)
4 0 0 0 OA 物語研究会創設の頃 : 三谷邦明氏インタビュー
- 著者
- 助川 幸逸郎 橋本 ゆかり
- 出版者
- 物語研究会
- 雑誌
- 物語研究 (ISSN:13481622)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-11, 2001-03-30 (Released:2018-03-27)
4 0 0 0 OA 植民地下朝鮮におけるスポーツとメディア
- 著者
- 森津 千尋
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.89-100, 2011-03-20 (Released:2016-09-13)
- 参考文献数
- 24
本稿では、文化政治期において、総督府機関紙であった『京城日報』が、その政治的立場から「内鮮融和」政策の一環としてスポーツ大会を開催し、また紙面でも統治者側の視点から大会を報じていた点について検討する。 『京城日報』は野球・庭球を中心とした全国大会を継続的に主催し、その大会には多数の朝鮮人選手が参加していた。さらに紙面では、試合に関連する記事はもちろん、その他関連イベントや祝広告が掲載され、朝鮮スポーツ界における大会の重要性が強調された。 また『京城日報』は、定期的に日本チームとの招聘試合も主催していた。主に6 大学野球のチームが招聘されたが、試合を報じる記事では、日本チームの技術・能力の高さが称えられ、朝鮮チームの「憧れ」「手本」として位置づけられていた。 このようにメディアの送り手として、『京城日報』が「内鮮融和」を推進する統治者側の立場からスポーツ大会を開催し、また紙面でも統治者側の視点から大会や試合について語っていたことが本稿では明らかになった。
4 0 0 0 OA 大東亜戦争海軍戦記
- 著者
- 大本営海軍報道部 編纂
- 出版者
- 興亜日本社
- 巻号頁・発行日
- vol.第4輯, 1944
- 著者
- Aurora Simionescu Norbert Werner 満田 和久
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.10, pp.707-711, 2014-10-05 (Released:2019-08-22)
銀河団は,差し渡し数百万光年の空間に数十個から1,000個もの銀河が集中している宇宙最大の天体です.普通の物質(バリオン)に限ると,銀河団の主たる構成要素は実は銀河ではなく,温度数千万度の高温ガスです.銀河団中のバリオンのほとんどは,X線を発する高温ガスとして銀河と銀河の間の空間に存在します.銀河団は,X線を放射する高温ガスの海の中に個々の銀河が浮かんでいるような天体と言えるでしょう.「すざく」衛星は,2005年に日本が打ち上げたX線天文衛星であり,現在も,世界中に開かれた国際X線天文台として活用されています.「すざく」衛星は,特に,天球面上に広がった表面輝度の低い放射を検出する感度に優れています.我々はこの特長を活かし,距離2.5億光年という近傍にあるペルセウス座銀河団の大規模観測を行いました.すべての銀河団の中で最も明るく,大きく広がったこの銀河団は,詳細な研究には最適です.X線観測からは銀河団の淡いガスの密度や温度を始めとする多くの重要な物理量を得ることができます.今回,「すざく」を用いたペルセウス座銀河団の大規模マッピング観測により,銀河団の中心から銀河団の縁であるビリアル半径に至るまでの高温ガス(バリオン)の分布を精密に得ることができました.その結果,銀河団の縁では,エントロピー分布は理論が予測するよりも平坦であり,密度は理論予測や電波観測で得られた値よりも高いことが初めて明らかになりました.この矛盾は,宇宙の大構造から銀河団に落ちてくるガスが塊を作って存在しており,熱化されるビリアル半径を通過した後も,この塊が残ると考えると説明できることがわかりました.さらに,ペルセウス座銀河団の広い範囲にわたって鉄の組成比を調べたところ,その場所ごとのばらつきが非常に小さく,ほとんど一様であることを発見しました.重元素の発生源である星の分布とは相関していません.1,000万光年にもおよぶ広い範囲について鉄の割合がほぼ一様であることから,鉄のほとんどは,銀河団が形成された時代よりも前に宇宙に大きく広がり,よく混ざっていたと考えられます.銀河団の誕生は宇宙誕生から約40億年後(いまから約100億年前)だと考えられているので,いまから100億年以上前に,鉄などの重元素が星々から大量にまき散らされ,宇宙中に拡散した時代があり,現在の宇宙に広がるほとんどの重元素はその時代にまき散らされたものであると考えるのが妥当です.数多くの星が生まれ,巨大ブラックホールが急成長したこの時代,星々から生み出された重元素は,超新星爆発や銀河中心の超巨大ブラックホールによって引き起こされた銀河からの強い風に乗って宇宙中に拡散して行ったと考えられます.
4 0 0 0 1.ダニ媒介性感染症
- 著者
- 夏秋 優
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.12, pp.2493-2501, 2019-11-20 (Released:2019-11-20)
- 参考文献数
- 28
ダニ媒介性感染症のうち,マダニが媒介する日本紅斑熱,重症熱性血小板減少症候群,ダニ媒介性脳炎,ライム病,そしてツツガムシが媒介するつつが虫病について,疾患の概要と診断のポイントなどを述べた.これらは四類感染症に指定されており,適切な診断と対応を要する重要な疾患である.皮膚科医が初期対応をする機会が多く,正確な知識と判断が要求される.
4 0 0 0 OA 小規模自治体における在宅育児手当の意義 ―鳥取県内6町の事例から―
- 著者
- 安藤 加菜子
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.133-144, 2019-11-30 (Released:2021-12-02)
- 参考文献数
- 32
在宅育児手当は,保育所を利用せず乳幼児を在宅で育児することに対し現金を給付する政策であり,近年いくつかの自治体で導入が進む。 そもそも親自らが子どもを育てることを支援する政策としては,育児休業や育児休業給付があるが,この支援は対象外となる親も多い。在宅育児手当にはこの限定性を補うことが期待されうるが,課題もある。その課題とは,あらゆる親の在宅育児を支援することに対する正当性の確保が難しいことと,こうした支援が母親の就労を阻害することへのリスクである。 本論文では,在宅育児手当政策を先進的に導入した鳥取県内の6つの町の事例に注目し,同地域の在宅育児手当の意義を検討した。検討の結果,同地域の在宅育児手当は,上に挙げた2点の課題をクリアし,従来型の育児支援政策の利用限定性を補完しながら,地域で働き次世代を育てる人々を支援する政策であることが示された。
4 0 0 0 OA 1782年天明小田原地震の津波に対する疑問 史料の再検討
- 著者
- 石橋 克彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.291-302, 1997-12-12 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
The 1782 August 23 Ten'mei Odawara earthquake, magnitude 7.2-7.3, is one of the three M7-class earthquakes that occurred beneath the Odawara area on the northwestern coast of Sagami Bay, the Pacific coast of central Japan, since the 17th century. Two other events, the 1633 Kan'ei and 1853 Ka'ei Odawara earthquakes, were definitely accompanied by tsunamis and their rupture zones are estimated to have lain just beneath Odawara, a seashore city in the area, extending both inland and offshore directions. This estimation is in agreement with the fact that the 1633 and 1853 earthquake ground motions at Odawara were very strong. On the other hand, the 1782 Ten'mei Odawara earthquake had been considered to have been non-tsunamigenic after critical readings of historical documents by a few investigators, and its source region had been inferred to be situated inland north of Odawara city. TSUJI (1986), however, claimed that the 1782 earthquake generated a tsunami and estimated that the tsunami height was 4 m at a fishing village, Ajiro, based on the examination of two newly found historical documents. He estimated a nearly 30 km-long tsunami source region south off the Odawara coast in addition to the inland rupture zone. Tsuji's interpretation yields a north-south extent of faulting too long to be consistent with an M7-class earthquake. It also conflicts with the fact that the 1782 earthquake ground motion was not the heaviest at Odawara, which strongly suggests that Odawara was not just above the rupture zone. TSUJI (1986) reported at the same time that Atami, a seaside town between Ajiro and Odawara, was not struck by a tsunami in 1782, which seems unreasonable from the viewpoint of tsunami behavior; actually, at the time of the 1633 earthquake the estimated tsunami height at Atami was 4-5 m, whereas that at Ajiro was 3-4 m. Whether the 1782 Ten'mei Odawara earthquake generated a tsunami or not is very important for not only the estimation of its rupture zone, but also the seismotectonics of the series of Odawara earthquakes. TSUJI (1986) drew his conclusion by very intricate interpretation of two historical documents which don't give any explicit description of a tsunami at Ajiro in 1782 at all. In this paper I reexamine the two documents more carefully and address the difficulties in Tsuji's conclusion. By referring to various materials describing the history of Ajiro village from the 17th to the mid-19th centuries, I clarify that TSUJI (1986) misread vague, rather general, descriptions of huge waves due to storms as a tsunami. Thus, I reject the suggestion that the 1782 Ten'mei Odawara earthquake generated a tsunami, and I conclude that its source region is inland north of Odawara city.
4 0 0 0 OA てんかんに随伴する精神症状
- 著者
- 山田 了士
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会
- 雑誌
- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.27-34, 2011-01-15 (Released:2014-10-11)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
近年の精神科医にとって,てんかんは徐々にその守備範囲から外れつつある。しかしてんかんをもつ患者において,不安・抑うつや幻覚妄想などの精神症状はかなり高い頻度で合併し,その生活の質にとって最も重要な臨床因子の一つである。自殺もまた,てんかんをもつ患者で頻度が高いことを考えると,精神症状を丁寧にスクリーニングし,治療することの意義は大きい。このように,てんかんの診療において精神科医の果たすべき役割は非常に大きいが,てんかんに伴う精神症状をよく理解している精神科医は必ずしも多くないと思われる。本稿ではてんかん自体に併発する精神症状や,抗てんかん薬などの治療によって惹起される精神症状について概説し,てんかん診療に重要な役割をもつと考えられる総合病院精神科医の理解を得たい。
- 著者
- 大澤 朋子 栗本 康司 土居 修一
- 出版者
- 公益社団法人 日本木材保存協会
- 雑誌
- 木材保存 (ISSN:02879255)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.44-59, 2023 (Released:2023-06-01)
- 参考文献数
- 27
わが国の木造住宅の床下環境は構法の変遷とともに変化しており,現在は床下土壌現しよりも床下防湿コンクリート打ちが主流で,寒冷地を中心に床下換気孔を持たない基礎断熱工法も広まってきている。そこで本研究では,居住者のある住宅を対象に,至近に建つ4棟の木造住宅の床下温湿度を1年間実測する調査,新しい基礎仕様である基礎断熱の木造住宅1棟の床下等の温湿度および木材含水率を17年間の長期にわたり実測する調査の2つを行い,異なる基礎仕様が土台等の床下木材に与える影響を検討した。その結果,基礎断熱の住宅の床下環境はいずれも年間を通して相対湿度40~80%の低湿に保たれており,床下木材が高含水率となる危険性はなかった。一方,床下換気孔を持つ在来型の基礎の場合は夏季に相対湿度が80%を超える高湿度期間が確認され,床下木材が高含水率となる懸念があった。さらに床下防湿コンクリート打ちの住宅は床下土壌現しの住宅よりも高湿度の影響が大きく,これは床下が低温となることに起因することが分かった。
4 0 0 0 IR 『切腹之切紙』 -江戸時代の切腹故実書-
- 著者
- コルネーエヴァ スヴェトラーナ
- 出版者
- 帝京大学文学部日本文化学科
- 雑誌
- 帝京大学文學部紀要 (ISSN:13497588)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.59-83, 2021-03-31
4 0 0 0 OA 舵取機の技術的変遷と現状
- 著者
- 篠原 直志
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.75-78, 1989-02-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 西川 尚紀 岩井 啓輔 黒川 恭一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CPSY, コンピュータシステム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.168, pp.49-54, 2009-07-28
- 被引用文献数
- 3
近年,GPUを用いた高性能計算が注目されている.GPUは,価格性能比に優れ,並列度の高いアプリケーションでは,安価なシステムで高い効果を発揮することができる.最近の世代のGPUでは整数・論理演算命令がサポートされ,同演算を用いたアプリケーションの実装が可能になった.本稿では,GPUを用いて暗号アルゴリズムDESに対するパスワードクラックを実装した結果について報告する.実装したプログラムでは,一度のジョブ発行で2^<35>乗個の鍵空間を探索することが可能である.DESの鍵空間に対しては,NVIDIA Geforce GTX 285を用いて約7.4時間,Intel Core i7-920 2.66GHzと比較して約9倍の速度で鍵探索が可能であった.その結果を元に,GPUの高速性を生かした暗号アルゴリズムに対するパスワードクラックの可能性を検討する.
4 0 0 0 OA Implementing Open-Source CUDA Runtime
- 雑誌
- 第54回プログラミング・シンポジウム予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp.81-86, 2013-01-11
Graphics processing units (GPUs) are the state of the art embracing the concept of many-core technology. Their significant advantage in performance and performance-per-watt compared to traditional microprocessors has facilitated development of GPUs in many compute applications. However, GPUs are often treated as ``black-box'' devices due to proprietary strategies of hardware vendors. One of the greatest challenges of this research domain is the in-depth understanding of GPU architectures and runtime mechanisms so that the systems research community can tackle fundamental problems of GPUs. In this paper, we present an open-source implementation of CUDA runtime, which is the most widely-recognized programming framework for GPUs, as well as a documentation of ``how GPUs work'' investigated by our reverse engineering work. Our implementation is based on Linux and is targeted at NVIDIA GPUs.
4 0 0 0 OA 抑肝散はグルタミン酸による神経毒性に対して保護作用を示す
- 著者
- 小西 徹
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.802, 2015 (Released:2018-08-26)
- 参考文献数
- 4
近年,幻覚・暴言・攻撃的行動・不安といった認知症の周辺症状(behavioral and psychological symptoms of dementia:BPSD)に対して抑肝散が有効であることが報告され,大規模臨床試験におけるデータも集積されてきている.抑肝散のBPSDに対する作用機序の1つに,グルタミン酸(Glu)過剰による毒性から神経細胞を保護する作用が考えられている.神経毒性発現のメカニズムにはNMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸,N-methyl-D-aspartic acid)型グルタミン酸受容体を介するものと,システムXc-(シスチン/グルタミン酸アンチポーター)を介するものが提唱されている.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Iwasaki K. et al., J. Clin. Psychiat., 66, 248-252 (2005).2) Matsuda Y. et al., Human Psychopharmacol., 28, 80-86 (2013).3) Kawakami Z. et al., Neurosci., 159, 1397-1407 (2009).4) Kanno H. et al., PLoS One., 9, e116275 (2014).
4 0 0 0 OA ワシントン首都計画の歴史と意義
- 著者
- 石川 幹子
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.37-52, 1992-06-05 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 42
The purpose of this paper is to analyze the development history of the Capital City of Washington, especially forousing on the McMillan Plan in 1902.The following three. points have been clarified.First, the McMillan Plan caused a nation-wide civic art or civic improvement movement, and finally, it created the professional field of the city planning. Second, the concept of the park system was established as the fundamental structure of the city and it gave a great influence in the development of the metropolitan park system and the green-belt concept. Third, through the study of the Mall, it was clarified that the characteristic of the civic landscape which symbolized the nation was its flexibility and freedom.
4 0 0 0 OA 先行研究を引用する際の引用文の文末表現
- 著者
- 清水 まさ子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, pp.52-66, 2010 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 21
本稿では論文において先行研究を引用している文の文末のテンス・アスペクトに着目し,それらを量的に調査し,それらがどのように用いられ,さらに引用節の形式との間に何らかの関係性を持っているかについて考察した。その結果,テイル形文末引用文は当該の論との間に論理性を生み出し,タ形文末引用文はタクシス的に働き,時系列的に論を進める際に用いられていることが明らかになった。さらに特定のテンス・アスペクトは,特定の引用節の形式とともに出現する傾向があることがわかった。テイル形文末の場合,①事柄フォーカス引用文の「と」以外+間接引用文,②著者フォーカス引用文の「と」+間接引用文,③著者フォーカス引用文の「と」以外+間接引用文という3つの引用節の形式と共に多く出現していた。またタ形文末の場合は,著者フォーカス引用文の「と」以外+間接引用文という引用節の形式と共に多く出現していた。
4 0 0 0 OA 鎮痛剤〔フェナセチン誘導体〕常用により発生したと思われる尿路上皮悪性腫瘍の夫婦症例
- 著者
- 宮内 武彦 丸岡 正幸 長山 忠雄 若月 進
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.12, pp.1908-1911, 1990-12-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 8
鎮痛剤〔フェナセチン誘導体〕の常用によると思われる尿管腫瘍の夫婦症例を経験した. 症例は66歳の妻と70歳の夫で, 2人とも頭痛持ちのため妻は45歳頃, 夫は55歳頃よりノーシンを1~2包/日随時服用した. 推定総摂取量は4kgと2.5kgであった.妻は1985年1月2日血尿で来院, 左尿管腫瘍の診断で2月13日左腎尿管摘出膀胱部分切除術施行, 6月11日膀胱内に腫瘍再発, 7月26日膀胱全摘尿管皮膚移植術施行. 1988年12月28日癌死した.夫は1987年3月頃血尿, 8月4日来院, 左尿管腫瘍の診断で8月26日左腎尿管摘出術施行, 11月19日膀胱内に腫瘍再発, 経尿道的手術を施行したが, 再発のため1988年4月22日膀胱尿道全摘右尿管皮膚移植術施行, 7月腹腔内, 腹壁に転移が発生し, 10月15日癌死した.