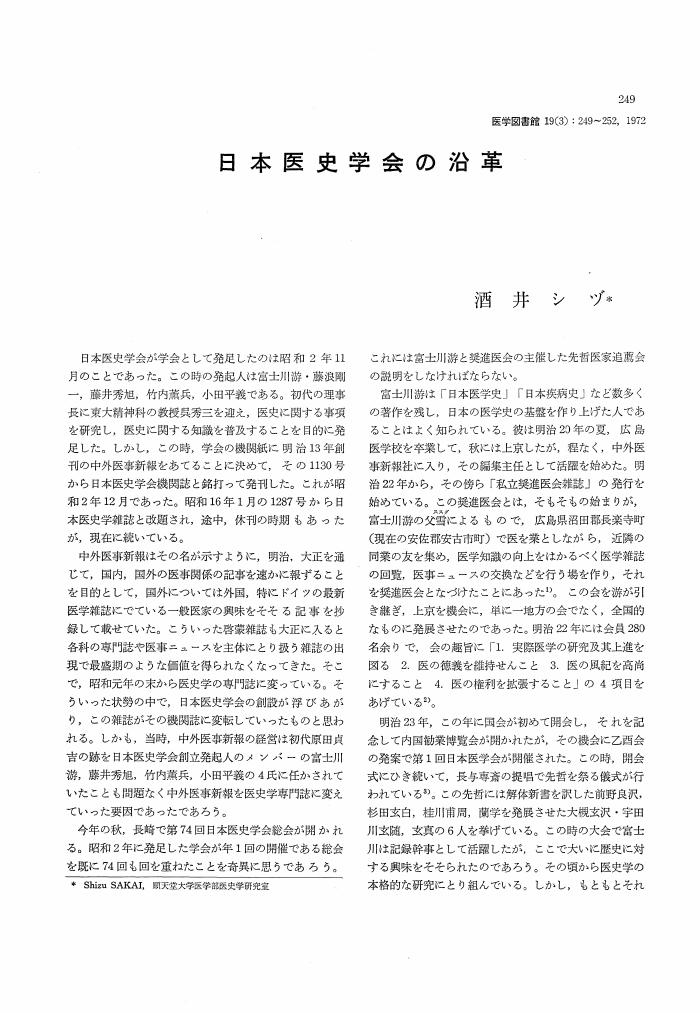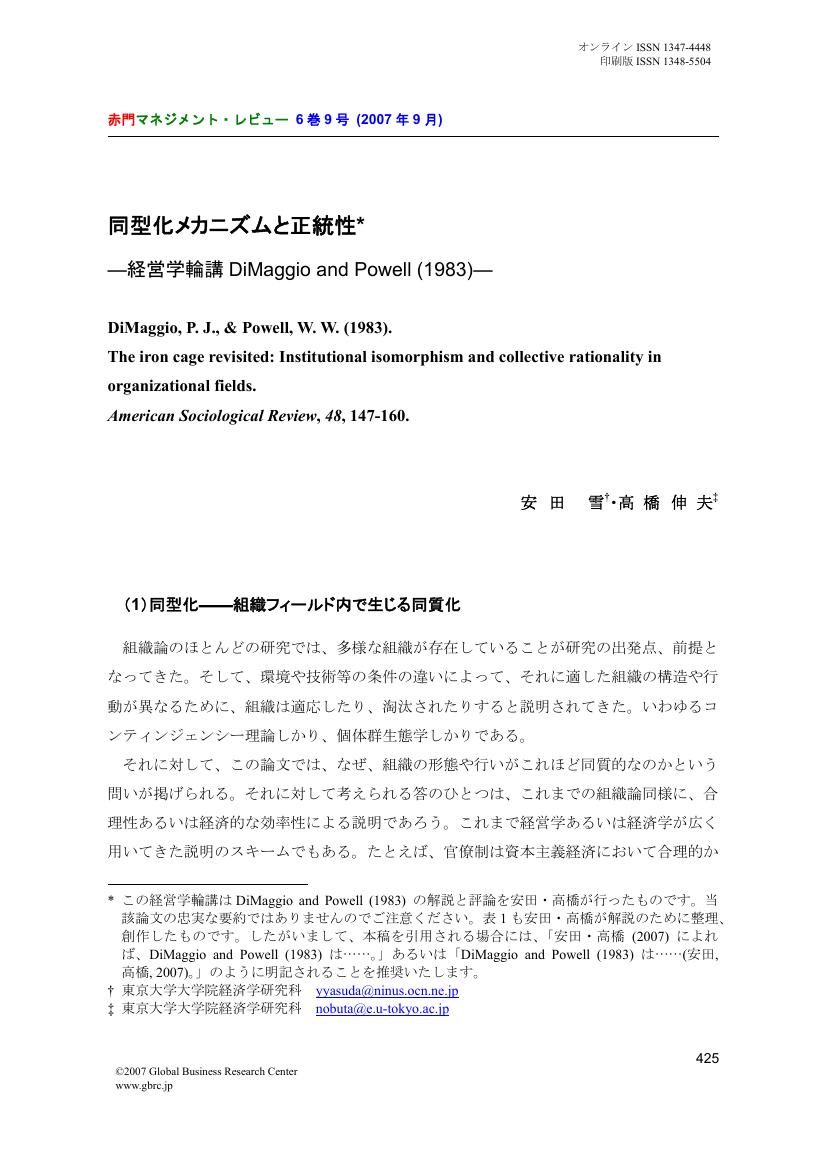4 0 0 0 OA 株式年鑑
- 著者
- 大阪屋商店調査部 編
- 出版者
- 大同書院
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和9年度, 1934
4 0 0 0 OA レーザーの量子論
- 著者
- 廣岡 正彦 砂川 重信
- 出版者
- The Laser Society of Japan
- 雑誌
- レーザー研究 (ISSN:03870200)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.14-24, 1986-01-28 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 12
4 0 0 0 OA カザフスタン共和国のナウルズ (НАУРЫЗ) に見る食の文化的・歴史的特徴
- 著者
- 岩垣 穂大 齋藤 篤 Amantay Zhanar 下田 妙子 扇原 淳
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.254-260, 2014-03-31 (Released:2014-04-28)
- 参考文献数
- 23
今回の調査によってカザフのナウルズおよびコジェに見る文化的特徴と歴史的変容について以下のことが明らかになった。(1) 独立後, ナウルズはカザフ国内最大級の祝祭であり, 民族の伝統的なイベントとして現在に受け継がれている。誰でも祭りに参加することができるよう, 広場では無料でコジェが配られていたり, さまざまな民族の音楽やダンスが披露されていたりした。その他, 中央アジアの伝統料理であるシャシリクやバウルサックを売る店も見られ, 食や伝統芸能を通してカザフ人の世代間交流や, 異なる民族同士の交流が図られていた。(2) ナウルズが近づくと各家庭でコジェ作りが行われ, 家族・親戚・友人の往来が始まる。コジェに入れる具材は地域の特産によって少々異なるが, 7つ (以上) の食材を入れることと, 白色の食材を入れ全体の色を整えることはすべての家庭で共通していた。コジェに使われる食材はカザフの食卓には欠かせない馬肉や, 穀物類が中心でカザフの日常生活をよく表すものであった。コジェを白色の食材で整える理由は, 白が家畜の乳の色であり, 新年を迎えるにあたって一家の繁栄や幸福を願うからであった。(3) インタビュー対象者の出身地域によってナウルズを公に祝いコジェ作りも行っていた家庭, 家の中だけでコジェを作り祝っていた家庭, 全く祝わず, コジェも作らなかった家庭の3つに分けられた。ソ連との地理的・心理的距離や政治的影響力, カザフ人の人口密度が影響している可能性が指摘された。独立後, 伝統を復興させるために都市部でナウルズを教える, コジェを無料で配るなどの活動も行われ, 現在のナウルズの基盤となった。 調査の中で, 都心部と農村部でのナウルズの祝い方やコジェに加えられる材料が異なることがたびたび指摘された。そのため, 今後農村部を含めたカザフ国内全体の調査が必要である。また, より詳細で信頼性のある調査にしていくために調査員を増やし, インタビューを継続することが必要である。カザフ社会の時代の流れに呼応する文化の変容を見守りつつ, 調査で得られたデータをもとに, カザフの伝統的な祝祭と食文化についてさらに深く体系的に明らかにしていきたい。
4 0 0 0 OA 水族館における設備・維持管理に関する調査研究
- 著者
- 田中 毅弘
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.76, pp.1-9, 2000-01-25 (Released:2017-09-05)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 4
世界中の珍しい水生生物を間近に見たいという願望から生まれた水族館は,その時代の人々のニーズに応えながら施設の形や機能を変化させてきた.本研究では,水族館における設備・維持管理がどのように行われているかについて,全国動物園水族館協会に登録のある47都道府県に設置されている水族館を対象に,設備・維持管理およびそれらに関連した省エネルギー対策,防災・防犯対策,水族館の特徴ともいえる水槽や飼育などに関する設備・維持管理の内容を考慮して17の設問によるアンケート調査を行い,それらの分析結果から傾向と特徴をまとめた.
4 0 0 0 OA 粟島共同調査報告 (その1)
4 0 0 0 OA 日本医史学会の沿革
- 著者
- 酒井 シヅ
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本医学図書館協会
- 雑誌
- 医学図書館 (ISSN:04452429)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.249-252, 1972-09-01 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 3
4 0 0 0 OA 東京帝国大学旧蔵標本の採集年次情報の復元
- 著者
- 加藤 克
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.123-132, 2017 (Released:2017-11-16)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
生物学標本の蓄積は,当該種の形態的,地理的分布の歴史的変遷に貢献するが,古い時代に採集された標本には,採集データが付属しない場合があり,有効に利用できないことがある.本研究では,採集年次不明の山階鳥類研究所所蔵ヤマゲラPicus canus標本(YIO-23324)を対象に,付属ラベルの利用年代の考察と採集者のフィールドノートの記載情報を利用してその採集年次情報の復元を試み,研究資源としての標本価値の向上を目的とした.この結果,標本の旧蔵機関である帝国大学で利用されていたラベルの付属から1885年以前の採集標本であること,ラベルに記載されている「ブラッキストン」という採集者名と日本の鳥学の近代化に貢献したThomas Blakistonのフィールドノートの照合から,1881年5月にBlakistonによって採集された標本である可能性が高いことを示した.この結果を援用することで,山階鳥類研究所に所蔵されている帝国大学旧蔵標本のうち,採集年次が判明しない標本の一部についても19世紀収集標本であることを裏付ける情報を整理した.以上の結果に基づき,古い標本を利用した研究の健全な遂行の上では,コレクションヒストリーの解明と,標本情報の再検討研究の継続が必要であることを提言した.
4 0 0 0 OA 国立科学博物館所蔵オーストラリア産骨格標本の採集情報の復元
- 著者
- 加藤 克
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.61-72, 2018-08-31 (Released:2018-08-31)
- 参考文献数
- 18
Value of specimens as research materials is secured by their collection information. This research attempted to restore collection information of a mammal skeletal specimen stored in the National Museum of Nature and Science with insufficient collection data by clarifying its collection history. The specimen was presented to the Tokyo Imperial Museum in 1906 from the Australian Museum, where we found the information for the specimen including the collection locality, cataloging date, collector’s name, and the catalog number of the Australian Museum. The restoration of collection information improved the value of the specimen. And the continuation of the restoration effort like this study contributes to the improvement of the global biodiversity information.
4 0 0 0 OA モーアシビ (毛遊び) と風俗改良運動に関する一考察
- 著者
- 井谷 泰彦 Itani Yasuhiko
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 : 別冊 (ISSN:13402218)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.129-140, 2013-03-30
4 0 0 0 OA 検察官上訴の研究:二重の危険の原理の観点から
- 著者
- 髙倉 新喜
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.71-96, 1994-11
- 著者
- Sakurai Yoshihide
- 出版者
- Nanzan institute for Religion and Culture
- 雑誌
- Japanese journal of religious studies (ISSN:03041042)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.317-334, 2010
Japan presents a useful case for studying new religious movements and their development of public relations and growth strategies , not only because there are large numbers of new religious movements in Japan, but also for the presence of controversial movementssuch as Aum and the Unification Church. The strategies employed in recruitment and fundraising have become increasingly important for such movements in Japan—as well as for research on these movements—in the wake of the ―Aum Affair.‖ This paper will focus on the strategy employed by the Unification Church which is broadly perceived as a social problem.
- 著者
- 魏 啓為 佐野 史典 秋元 圭吾 日渡 良爾 飛田 健次
- 出版者
- 一般社団法人 エネルギー・資源学会
- 雑誌
- エネルギー・資源学会論文誌 (ISSN:24330531)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.170-179, 2019 (Released:2019-09-10)
- 参考文献数
- 20
This paper analyzed Japan’s fusion energy development scenarios by using a global energy systems model considering a combination of uncertainties of future socioeconomic development, CO2 emission pathways corresponding to the long-term target of the Paris Agreement and future fusion power plants. Fusion power plants will be installed in Japan and could contribute about 20% on average in power sector in the latter half of the century because of the limited-potentials of affordable renewable energies and carbon capture and storage in Japan. The benefit of fusion introduction in Japan is estimated to be about 10 billion US$/yr on average in 2050-2100. Its value increases with reduction of the capital costs of future fusion power plants, lower penetration of fission power plants and deeper decarbonization pathways. When considering unique characteristics of fusion energy development, i.e., long-term and large-scale projects and DEMO as a single step between ITER and a first commercial plant, demonstration and prospect of economic viability under DEMO projects becomes critically important. This systems analysis also suggests that an alternative option of fusion energy which directly produces hydrogen by high-temperature steam electrolysis could become economically attractive.
- 著者
- 陶山 佳久 鈴木 準一郎 蒔田 明史
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.97-106, 2010-03-31 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
近年のDNA分析技術の発展を背景としたジェネット識別データ等の蓄積により、タケ・ササ類の一斉開花に関する新たな視点が加わり、関連する議論を整理する必要があると考えられた。そこで本稿では、タケ・ササ類の一斉開花に関して、いくつかの用語の定義と仮説の提唱を行った。まず一斉開花の概念を整理し、開花の個体性と規模を明確に分けて表現することとし、「同調開花」、「単独開花」、「広域開花」および「小規模開花」という用語の使用を提唱した。次に、ジェネット混在型の空間分布構造が、タケ・ササ類の一斉開花性を強化する要因の一つになりうることを指摘し、「ジェネット混在型競争回避仮説」として提唱した。また、典型的な一回繁殖・一斉開花性には合致しない現象として「再開花」、「開花後生残稈」、「再生稈」、「小規模開花」、「一斉前小規模開花」および「一斉後小規模開花」に注目し、これらが一回繁殖・一斉開花性のリスク回避(保険)システムとして機能しうることを指摘した。最後に、個体群内に生じる可能性のある長周期開花性の突然変異は、長寿命クローナル植物のジェネット混在型高密度優占個体群において固定されやすいことを説明し、長期待機型一斉開花性の進化メカニズムの一つとして考えられることを提案した。
- 著者
- 安田 雪 高橋 伸夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.9, pp.425-432, 2007-09-25 (Released:2018-03-05)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 6
4 0 0 0 OA 難消化性デキストリンの血糖値抑制効果と糖負荷の関係
- 著者
- 別府 秀彦 渡邊 治夫
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.3-14, 2011-03-10 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
Human clinical studies have yielded a great number of findings on the suppressive effect of indigestible dextrin on glucose absorption. The suppressive effect tends to be marked in subject groups whose blood glucose is at high levels in blood tests and the degree of suppression may vary depending on the saccharide species used for loading. The following is a summary review of the suppressive effect of indigestible dextrin as reported in scientific papers.1) In starch loading tests, although a significant difference in the degree of blood glucose suppression by indigestible dextrin is seen in groups whose blood glucose values after placebo ingestion are higher than average, no such difference is commonly observed in low-value groups.2) When groups with high and low blood glucose values before testing are classified in the same starch loading study, however, a significant difference is observed even in low-value groups, as the low-value group includes subjects in the placebo group with higher blood glucose values showing higher peak values at testing.3) In sucrose loading tests, the significant difference was observed more clearly not only in high-value groups but also in low-value groups. Since the inhibitory action of indigestible dextrin is strong on α-glucosidase when it binds to sucrose in order to hydrolyze into glucose and fructose, it appears certain that suppression of glucose absorption into the blood takes place.4) When maltose loading was carried out in twelve healthy young subjects (mean age: 21.4±0.51) in a preliminary study, there was a significant difference in the degree of blood glucose suppression in the groups with higher than average blood glucose level. However, no significant difference was found in another test, in which maltose was loaded to 13 adult subjects (mean age: 54.4±5.5). Although the glucose absorption at maltose hydrolysis in α-glucosidase reaction may be inhibited by indigestible dextrin like as that at starch hydrolysis, the results of the maltose loading test were varied.5) Since α-glucosidase is distributed over the small intestine wall, in order to inhibit co-transportation of the glucose into the blood in the hydrolysis of disaccharide by α-glucosidase, it is necessary for indigestible dextrin to also be distributed quickly over the same small intestine wall. If the loaded foods are taken in slowly, blood glucose level will describe a gradually increasing curve over time; similarly, if indigestible dextrin is taken in slowly, the distribution of the indigestible dextrin to the intestinal wall will be slow and inefficient for inhibition of glucose absorption.
4 0 0 0 OA 英米文学鳥類考:カワセミについて
- 著者
- 桝田 隆宏 Takahiro Masuda
- 雑誌
- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.147-187, 2008-08-01
- 著者
- 門下 祐子
- 出版者
- 東洋大学福祉社会開発研究センター
- 雑誌
- 福祉社会開発研究 (ISSN:2189910X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.5-17, 2022-03
4 0 0 0 OA COVID-19パンデミックと 公衆衛生倫理の三つの課題
- 著者
- 児玉 聡
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.4-11, 2021-09-28 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 16
COVID-19(新型コロナウイルス感染症) のパンデミックについて、生命倫理学が検討すべきなのはパンデミック対策の倫理性、すなわちパンデミック対策のために行われる政策や活用される科学技術の持つ倫理的・法的・社会的含意である。本稿では主に公衆衛生的な側面に議論を絞り、市民的自由の制限、公平な資源配分、予防行動の責任という三つの倫理的課題について論じる。これらは生命倫理学においてこれまでにも議論されてきた問題であるが、今回のパンデミックにおいて、改めてその重要性が浮き彫りになったものと言える。いずれも直ちに答えの出せる問題ではなく、本稿でも主に課題を説明するだけに留まるが、理論的かつ実践的な課題として今後十分な議論が必要である。今回のパンデミックを受けて我々にできることは、生命倫理学の観点からパンデミック対策を詳細に吟味することにより、この経験から少しでも多くの教訓を学び、次回以降のパンデミック対策に活かすことである。