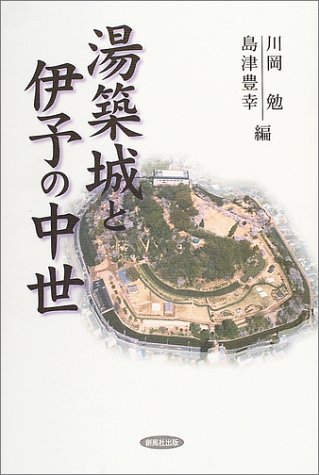4 0 0 0 続・幕末の洋学事情--近代の発信地,長崎と蘭医と近代教育
- 著者
- 杉本 つとむ
- 出版者
- 早稲田大学図書館
- 雑誌
- 早稲田大学図書館紀要 (ISSN:02892502)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.1-55, 1995-12
4 0 0 0 OA 歩行分析の基礎—正常歩行と異常歩行—
4 0 0 0 OA 1/f ゆらぎの物理
- 著者
- 武者 利光 北原 和夫
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.1688-1695, 1989-12-10 (Released:2009-02-09)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
本稿では, 1/f; ゆらぎの実験・理論の現状を概説するとともに,非平衡統計物理としての問題点を指摘する.特に,線形応答係数のエネルギー損失に関わる部分が1/fゆらぎをしていることに注目する.また, Hooge の式の解釈として,電子は独立にフォノンによって散乱されるが,フォノン自体は長距離相関をもって1/f ゆらぎをしていることを述べる.
- 著者
- 木下 一雄
- 出版者
- 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科
- 雑誌
- 名寄市立大学社会福祉学科研究紀要 (ISSN:21869669)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.49-61, 2018-03
多くの精神障害者は働きたいという希望とその力を持っている。しかし、地域社会の精神障害者に対する理解不足や適切な支援がなされていないこと、関係機関や企業等のネットワークと連携が不足していることが、精神障害者の就労を困難にしていると考えられる。 精神障害者の就労促進のためには、精神障害者が今まで暮らしていた地域で、自分らしく当たり前に生活していくことが出来る地域社会環境を構築することが必要であり、そのような環境を実現するための知見の一助とすべく、K市障がい者就業・生活支援センター職員に対する聞き取り調査を行った。 調査対象のK市は、病院と就労支援センターが共同して支援体制を構築する活動を進めている先進地域である。今後、周辺地域の過疎化が進んでいくとともに必要になる広範な地域を支援していくための有効な方策についての手がかりにつながって行く知見を得ることができると考え、調査対象地域とした。 精神障害者の社会復帰を困難にしている現状を明確にし、精神障害者を取り巻いている課題や問題点とどのような支援をしていくことが求められているかについて検討した。
4 0 0 0 OA ぬばたまの夢やは実在を思はする『神の左手悪魔の右手』 -楳図かずおと世界の創造-
- 著者
- 高橋 明彦
- 出版者
- 金沢美術工芸大学
- 雑誌
- 金沢美術工芸大学紀要 (ISSN:09146164)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.115-134, 2011-03-31
4 0 0 0 OA センター試験利用による私立大学出願の特徴と年次推移
- 著者
- 内田 照久 橋本 貴充
- 出版者
- 日本テスト学会
- 雑誌
- 日本テスト学会誌 (ISSN:18809618)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.79-97, 2019 (Released:2019-08-18)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
センター試験を利用した私立大学出願の特徴を分析した。はじめに,多数の私立大学に出願する出願者の年次推移を検討した。(1) 散発的点在期(H20~23 年度)は,特定地域への局在性は見られず,散発的に点在していた。(2) 被災地局在期(H24~27 年度)は,東日本大震災の被災地域で急増し,3 年程で沈静化した。 (3) 膨張的拡大期(H28~29 年度)は,首都圏で先行して急増し,他の地域にも拡大していた。この (3)の背景として,大規模私立大学での (a) 複数学部のセット受験時の検定料の低廉化,(b) インターネット出願による手続きの簡素化,の2 点が誘因とされた。一方で,センター試験で私立大学に出願する実人数は,全国総計では増加していたが,18 歳人口の減少傾向が著しい過半数の県では逆に減少しており,地域間での対照的な動向の違いが明らかになった。
4 0 0 0 OA 糖質制限ダイエットを考える
- 著者
- 安居 光國
- 出版者
- SAMA企画
- 雑誌
- Rikatan : 理科の探検
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.80-81, 2016-04
特集 : ニセ科学を斬る! 2016
4 0 0 0 IR 社会的養護の可能性と地域子育て支援 ―児童家庭支援センターの取り組みから―
- 著者
- 大澤 朋子
- 出版者
- 実践女子大学
- 雑誌
- 実践女子大学生活科学部紀要 = Bulletin of Jissen Women's University Faculty of Human Life Sciences (ISSN:24336645)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.1-10, 2021-03-19
本論文は、先進的な取り組みを行う児童家庭支援センターへのインタビュー調査を通して、地域子育て支援の意図や実践を分析し、児童家庭支援センターが担うべき地域子育て支援のあり方を検討することを目的とした調査研究である。分析の結果、大カテゴリー10、中カテゴリー29、小カテゴリー70 を抽出した。社会的養護機関の機能と専門性を活用しながら、複数の事業を一体的に運用するなかで職員のスキルが向上し、地域へのまなざしも醸成されることがわかった。小さな実践を積み重ねながら、目の前の困っている人を助けに行くフットワークの軽さが民間の利点であった。社会的養護の機能が子どもの養育からソーシャルワークへと抜本的に変わる可能性が示唆されたが、子どもの権利擁護と利用者の自己決定の尊重が支援の原則であると認識されていた。
4 0 0 0 OA ルターと自然法の問題 後期スコラ思想との関連で
- 著者
- 伊藤 平八郎
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, pp.127-134, 1992-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 23
- 著者
- Ying Zou Hongying Guo Yuyi Zhang Zhengguo Zhang Yu Liu Jiefei Wang Hongzhou Lu Zhiping Qian
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020.03086, (Released:2020-04-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 73
To investigate the characteristic of coagulation function in 303 patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19), we evaluated the correlation between coagulation function and disease status. We retrospectively analyzed 303 patients diagnosed with COVID-19 and evaluated the clinical data of 240 patients who were discharged. The coagulation function of the two groups (mild and severe) was compared. Compared with the mild group, majority of patients in the severe group were male (76.9% vs. 49.8%) and elderly (median age 65 vs. 50), and the proportion with chronic underlying diseases was higher (73.1% vs. 36.1%). There were 209 abnormalities (69.0%) of coagulation parameters in 303 patients admitted to hospital. Comparison of various indexes of coagulation function between the two groups in admission, the proportion of abnormal coagulation indicators in the severe group was higher than that in the mild group (100% vs. 66.1%). The median coagulation parameters in the severe group were higher than those in the mild group: international normalized ratio (1.04 vs. 1.01), prothrombin time (13.8 vs. 13.4) seconds, activated partial thromboplastin time (43.2 vs. 39.2) seconds, fibrinogen (4.74 vs. 4.33) g/L, fibrinogen degradation products (2.61 vs. 0.99) µg/mL, and D-dimer (1.04 vs. 0.43) µg/mL, the differences were statistically significant (p < 0.05). Coagulation dysfunction is common in patients with COVID-19, especially fibrinogen and D-dimer elevation, and the degree of elevation is related to the severity of the disease. As the disease recovers, fibrinogen and activated partial thromboplastin time also return to normal.
4 0 0 0 OA 1920 年代後半の時代劇映画における音楽伴奏の折衷性 ─―和洋合奏・選曲・新作曲―─
- 著者
- 柴田 康太郎
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.1-16, 2018 (Released:2019-10-15)
1920年代において、日本のサイレント映画は西洋音楽の土着化と舞台から映画へという同時代的な転換との複合的な帰結による改革のなかにあった。当初、1910年代の日本映画は歌舞伎の強い影響下にあった。当時の邦画は舞台劇の一種の安価な代用品とみなされており、ロングショット、長廻し、固定カメラで撮影されていた。音楽演出においても三味線や太鼓などの伝統的邦楽器によって歌舞伎の舞台劇を模倣することが目指されていた。ところが1920年頃になるとこうした舞台志向の映画は、クロースアップやクロスカッティング等の映画に必要な技法を追求せず、古臭い物語に安住することで批判されるようになった。そして新しい邦画を模索する純映画劇運動のなかで、伴奏音楽もまた、洋楽と洋画伴奏のもとで再編成されることになる。しかもこの動きは、歌舞伎などの伝統の根強い時代劇においても浸透し、洋楽合奏や和洋合奏による古典邦楽曲や輸入洋楽曲の演奏、さらには新作伴奏曲をともなって上映されるようになるのである。本論文は、東京における日活の封切館であった浅草富士館や神田日活館の興行実態や伴奏曲をめぐる言説、および伴奏譜の資料考証を交え、複合的にこの再編成のありようを捉え直す試みである。まず浅草富士館の支配人三宅巌の試行錯誤に注目し、歌舞伎的伝統の根強い富士館でどのように洋楽合奏や和洋合奏が導入されたのかを考察する。次いで残る2節では、現存する楽譜資料や同時代の言説の検証により、1926年頃の時代劇伴奏のレパートリー、そして時代劇伴奏の代表的作曲家のひとりであった松平信博の1927年以後の実践を考察し、1920年代後半にどのように楽曲と編成における邦楽と洋楽の折衷ないし再編成が進んだのかを示す。
4 0 0 0 社会的包摂戦略としてのワークフェアの限界と参加所得
- 著者
- 志賀 信夫
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.165-176, 2013-10-30
社会的排除という言葉が使われ始めて久しいが,この社会的排除への取り組みに関する言説をLevitas[2005]は三つに類型化した。現実の社会的包摂戦略はこのなかでも「仕事」を契機として排除された者を統合しようとする言説をその基礎としている。ヨーロッパにおけるワークフェア戦略がまさにそれである。宮本[2006 ; 2009]はワークフェアとアクティベーションを区別し,後者を肯定的に評価している。確かにそれは,実存する社会的包摂戦略のなかではモデルとされるべきものである。しかし,本稿ではこのアクテイベーションの限界を批判的に検討しその連続性において,Lister[2004=2011]が紹介している「社会的包摂ではなく社会参加を」という要求に沿った新たな戦略への結節点を模索する。その際に新たな道の一つとしてAtkinson[1995=2011 ; 1998]の提案する「参加所得」を挙げ,これが必ずしもベーシック・インカムの妥協ではなく,包摂戦略の積極的代替案であることに触れていく。
4 0 0 0 OA 各種速度条件下の歩行・走行における筋活動量と酸素需要量の関係
- 著者
- 後藤 幸弘
- 出版者
- 関西医科大学医学会
- 雑誌
- 関西医科大学雑誌 (ISSN:00228400)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.353-383, 1983-06-20 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 71
The purpose of this study is to examine the relationship between the amount of muscle electrical activity and oxygen requirement as to the speed changes in walking and running, and also to determine electromyographically the optimum speed and the metabolic intersection speed of walking and running, that were reported by former investigators.Twenty-two young trained male adults participated in the experiment. They were all athletes who belonged to university sports clubs.EMG activity in the right leg w as measured through two surface electrodes placed 2.5cm apart on the belly of each muscle as shown below. The following muscles were monitored in all subjects.Tibialis anterior (T.A.), Soleus (So.), Gastrocnemius (L.G.), Vastus medialis (V.M.), Rectus femoris (R.F.), Biceps femoris (B.F.), and Gluteus maximus (G.M.).The subjects O.O. and U. E. had additional muscles monitored as described below:Rectus abdominis (R.A.), Sacrospinalis (Sac.), Deltoid anterior portion (D.A.), Deltoid posterior portion (D.P.), Triceps brachii (T.B.), and Trapezius (Trape).The EMG signal was amplified and recorded by a multipurpose electr oencephalograph (San-ei Type IA-14) (paper speed: 3cm/sec, sensitivity: 6 mm/O.5mV, time constant: 0.01 sec). Simultaneously it was integrated with a Miller's circuit (Nihonkouden Integrator RFG-5).
4 0 0 0 OA 情報学は哲学の最前線
- 著者
- ⻑尾 真
- 出版者
- アカデミック・リソース・ガイド
- 雑誌
- LRG : library resource guide (ISSN:21874115)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.10-76, 2019
English version: "Informatics is the Forefront of Philosophy" http://hdl.handle.net/2433/244173
4 0 0 0 OA 逢ひても逢はぬ恋のひとつにてもあらず : 『とりかへばや』宰相中将の恋心について
- 著者
- 片山 ふゆき
- 出版者
- 北海道教育大学語学文学会
- 雑誌
- 語学文学 (ISSN:24358754)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.38-48, 2022-12
4 0 0 0 社会正義とソーシャルワーク倫理に関する一考察
- 著者
- 田川 佳代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.1-12, 2018-07-20
社会正義の思想は,正義の諸概念や諸構想に依拠する.どのような正義の構想に依拠するかを曖昧にすることは,実現しようとする正義を玉虫色のものにする.ソーシャルワークが擁護すべき社会正義とは何か.ソーシャルワークにおいて実現しようとする正義は何であるか.社会正義の広範な理論の検討を踏まえ,議論の輪郭を描くことが課題である.本稿では,まず,広範囲に及ぶ社会正義の意昧について調べる.配分的正義の議論を乗り越え,現代のソーシャルワークに要請されている抑圧や文配を除去し,搾取や社会的不正義を克服するのにふさわしい,ソーシャルワークにおける社会正義の諸概念や諸構想を検討する.ポスト近代,ケアの倫理,反抑圧といった新たな社会理論からの異議申し立てを,ソーシャルワークはどう受け止めるのか.ソーシャルワークの理論的変遷を辿りつつ,考察を試みる.
4 0 0 0 OA Balloon Kyphoplasty後隣接椎体骨折の臨床的意義とその予測
- 著者
- 高橋 真治 星野 雅俊 中村 博亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
- 雑誌
- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.5, pp.811-819, 2020-05-20 (Released:2020-05-20)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
Balloon kyphoplasty(BKP)後に隣接椎体骨折が生じることはよく知られているが,その危険因子や予測については報告が限られている.また,その臨床的意義も報告により異なる.我々は隣接椎体骨折が及ぼす影響およびその発生を予測する因子を受傷後2ヶ月以内にBKPを実施した症例で検討した.本著ではその研究を中心に,隣接椎体骨折が臨床的に及ぼす影響,またその予測に関して文献をレビューした.
4 0 0 0 OA Synecological farming: Theoretical foundation on biodiversity responses of plant communities
- 著者
- Masatoshi Funabashi
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.213-234, 2016-09-30 (Released:2016-11-18)
- 参考文献数
- 225
- 被引用文献数
- 7 11
A novel farming method, namely synecological farming (synecoculture in short), based on theory and observation of synecology has been proposed as total optimization of productivity, product quality, environmental load and adaptation capacity to climate change. Synecoculture is designed on a variety of environmental responses within ecological optimum in high-density mixed polyculture where various edible species were intentionally introduced. The whole methodology can be considered as anthropogenic augmentation of ecosystem functioning that promotes dynamic biodiversity–productivity relationship prevalent in natural ecosystems.In this review we summarize the theoretical foundation to provide a systematic definition of synecoculture and clarify the relationship with existing farming methods. We also collate previously reported analyses of organic and mineral components in farm products, and outline their physiological characteristics and functions in response to culture environments.