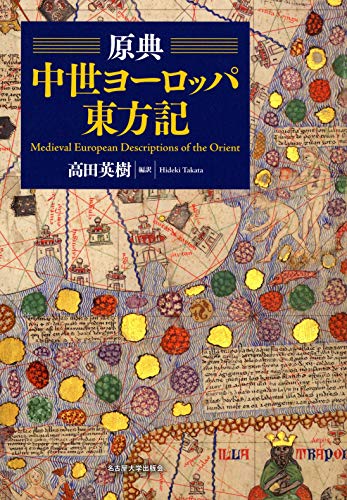4 0 0 0 OA イタリア語の動詞副詞結合
- 著者
- 猪浦 道夫
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.177-196, 1989-10-20
La lingua italiana, come le lingue romancia e portoghese, possiede la "combinazione verbo-avverbio", la maggioranza della quale e nata sotto l'influenza delle lingue germaniche. Questa combinazione dovrebbe essere riferita in una certa maniera nella grammatica della lingua italiana moderna, giacche le combinazioni verbo-avverbio nella lingua italiana non sono trascurabili, anche se sono poche paragonate, per esempio, con quelle in inglese. Vediamo subito che questo tipo di vocabolario a indiscutibilmente colloquiale nel iivello di linguaggio, come in inglese. La linea di demarcazione fra la "combinazione verbo-avverbio" e il verbo semplice con un avverbio di luogo non e sempre chiara, e vi troviamo diversi gradi di maturita come una sola parola. Mi sembra che un ulteriore studio sia necessario per poter dare una definizione razionale per l'elemento di vocabolo che si puo chiamare la "locuzione verbale".
4 0 0 0 OA 2001年9月11日 : WTCはなぜ倒壊したのか?
- 著者
- 川口 淳
- 出版者
- 三重大学工学部技術部
- 雑誌
- 技術官等による技術報告集 (ISSN:13481991)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.2-10, 2003-02-01
4 0 0 0 IR 子ども時代のネグレクト体験の報告は大学生の痛み体験と関連している
- 著者
- 古川 真由 有村 達之
- 出版者
- 九州ルーテル学院大学人文学部心理臨床学科
- 雑誌
- 心理・教育・福祉研究 : 紀要論文集 = Japanese journal of psychology, education and culture
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.85-94, 2021-03-31
児童虐待が成人後の痛み体験と関連することが近年報告されている。本研究では大学生を対象に児童虐待の一側面であるネグレクトの体験と痛み体験との関連性について調査を行った。方法:80名の大学生が年齢,性別,痛みの罹病期間,子供時代のネグレクト体験,痛み強度,痛みの感覚的側面,感情的側面,痛みによる生活障害,抑うつ,不安,痛みの破局化についての質問紙調査に参加した。結果:ネグレクト体験は痛み強度,痛みの感覚的側面,感情的側面と有意に相関していた。これらの関連は人口統計学的変数および痛みの破局化をコントロールした後も有意であった。しかし,ネグレクト体験と痛みの生活障害との関連は,人口統計学的変数と痛み強度,痛みの破局化をコントロールした後では有意でなくなった。ネグレクト体験は抑うつおよび不安とは関連していなかった。結論:これらの知見は( 1 )子供時代のネグレクト体験が大学生の痛み体験に影響する可能性,( 2 )ネグレクト体験と痛みによる生活障害の間の関連性を痛み強度が媒介する可能性を示唆している。
4 0 0 0 OA 条件不足で解けない入試問題
- 著者
- 藤島 一満
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.168-171, 1990-09-10 (Released:2017-02-10)
重力が作用している場合の衝突については,衝突する時間が短いので重力の影響は無視できるという前提条件がなければ,この場合に運動量保存の法則が適用できるかどうかといったことについて高校生に判断させることは,高校教科書の記述の文脈からいって無理なことではないかと思う。この種の問題が最近の入試に頻出されているが,そのいずれにも「重力の影響は考えなくてもよい」という前提条件が述べられていない。このことについて出題大学あてに送った質問状の回答に「すべて衝突においては,たとえ重力が働いていても,常に運動量保存の法則が成立するというのが初等物理の約束である。だから重力の影響について前提条件は不用である」とあった。これでは,高校教育についての配慮がまったくない,といえるのではないか。
4 0 0 0 OA 持続的な小規模ゲーム開発の可能性 -同人・インディーズゲーム制作の質的データ分析-
- 著者
- 七邊 信重
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.171-183, 2009 (Released:2019-10-01)
- 被引用文献数
- 1 1
本研究は、日本の同人・インディーズシーンにおけるゲーム制作の特徴と、これを持続的に可能にしている社会経済的条件、およびここから多様な表現が生み出されている要因を、質的データ分析によって解明することを試みたものである。インタビューデータのコード化の結果、同人・インディーズ のゲーム制作には、1志向性、2自律性、3柔軟性、4開発スピード、5ユーザーとの距離、6売上・ 収入において特徴があることが明らかになった。さらに、1数千本~1 万本程度の売り上げでペイライ ンを越えるビジネスユニットとエコシステムが形成されていること、2このエコシステムの中で、制作 者の個性を反映した尖った作品が持続的に開発されていることが示された。この結果は、日本における 持続的な小規模ゲーム開発の社会的・経済的可能性を示唆している。
4 0 0 0 OA 運動のコツを伝えるスポーツオノマトペ
- 著者
- 吉川 政夫
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.215-220, 2013 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
オノマトペとは擬音語・擬態語を意味するフランス語である.擬音語・擬態語は五感による感覚印象を言葉で表現する言語活動である.筆者らは運動・スポーツ領域で活用されている擬音語・擬態語をスポーツオノマトペと名付けた.運動・スポーツ領域でオノマトペが使用される場合,運動の「コツ」を表現する際の言葉として使用されることが多い.具体的には,動きのパワー,スピード,持続性,タイミング,リズムを表現する言葉として使われていることが筆者らの調査結果の分析から明らかになった.本稿では,アスリートを対象とした調査から得られた運動・スポーツ領域で使用されているスポーツオノマトペの特性,発声されたスポーツオノマトペの音響分析結果から得られた特性,アスリートと指導者に対する意識調査結果と実験結果に基づくスポーツオノマトペの導入効果,運動のコツを伝えるスポーツオノマトペの可能性について言及した.
長小腸移植の短期成績は急性拒絶の制御が可能となり改善したものの、長期成績は肝臓、心臓移植などにはいまだ及ばない。その理由の一つが慢性拒絶によって移植小腸が機能不全となることである。しかしながら小腸移植における慢性拒絶の作用機序はいまだに明らかになっていない。近年、間葉系幹細胞による免疫制御が臓器移植の慢性拒絶に効果があることがわかってきた。そこで我々はラット小腸移植後慢性拒絶モデルを作成し、HMGB1ペプチドを投与し、同様に慢性拒絶抑制・治療を目指す。本研究は小腸移植における慢性拒絶作用機序の解明につながるだけでなく、小腸移植後の患者の長期生存を可能とする、再生誘導医薬の創薬を可能にする。
4 0 0 0 卜純追考
- 著者
- 竹島 一希
- 出版者
- 大阪俳文学研究会
- 雑誌
- 大阪俳文学研究会会報 (ISSN:02891077)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.1-8, 2011-10
4 0 0 0 OA 文学作品を読む自閉スペクトラム症者:「脳の多様性」と「当事者批評」
- 著者
- 横道 誠
- 出版者
- エスノグラフィーとフィクション研究会
- 雑誌
- パハロス = PÁJAROS (ISSN:2435905X)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.70-90, 2021-09-30
- 著者
- Yo Akiyama Manabu Kanazawa Maiko Iwaki Tamaki Hada Yumika Soeda Ryosuke Otake Kenta Kashiwazaki Yuriko Komagamine Natsuko Murakami Atsushi Takaichi Noriyuki Wakabayashi Shunsuke Minakuchi
- 出版者
- Japan Prosthodontic Society
- 雑誌
- Journal of Prosthodontic Research (ISSN:18831958)
- 巻号頁・発行日
- pp.JPR_D_22_00100, (Released:2023-02-02)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
Purpose: Although digital removable partial dentures have been previously described, there have been no reports on how to fabricate them in one piece. This study proposes a new method for fabricating patient-specific digital removable partial dentures using a custom plate.Methods: First, a gypsum model was scanned using a laboratory scanner and a removable partial denture was designed using computer-aided design (CAD) software based on standard tessellation language data. The metal clasp was fabricated from Ti-6Al-4V using a 3D printer. For custom plate fabrication, a resin plate frame was designed using computer-aided design (CAD) software and fabricated using a 3D printer. An artificial tooth and metal clasp were fixed on the base surface of the frame, an auto-polymerizing resin was poured into the frame for the denture base, and the artificial tooth and metal clasp were packed to form a custom plate. The plate was cut using a milling machine. Subsequently, the support attached to the denture was removed and polished for complete fabrication of the denture.Conclusions: Our novel removable partial denture fabrication method is more efficient than the conventional method. The obtained removable partial dentures demonstrated satisfactory accuracy.
4 0 0 0 OA コンテンツツーリズムとインバウンド-現実空間・情報空間・虚構空間の移動を考える
- 著者
- 岡本 健
- 出版者
- 公益財団法人 国際交通安全学会
- 雑誌
- IATSS Review(国際交通安全学会誌) (ISSN:03861104)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.51-57, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 20
まず、コンテンツツーリズムについて、政策的な注目、社会に浸透していった経緯、研究的関心を整理する。その際、筆者のこれまでの研究成果を交えながら紹介していく。次に、コンテンツ産業市場やアニメ産業市場の動向を整理することで、インバウンド振興の可能性について論じる。最後に、コンテンツツーリズム研究から導き出された空間概念を用いて、今後の研究および実践の課題を示すとともに、コンテンツのアーカイブとデータベースの整備の必要性を述べる。
- 著者
- 河邉 貴子
- 出版者
- 日本保育学会
- 雑誌
- 保育学研究 (ISSN:13409808)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.296-305, 2015-12-25
本稿の目的は,子どもの育ち合いを考える際には関係論的な視点だけでなく,文化的実践としての遊び理解の視座が必要であると論じることである。子どもは身近な環境にかかわることによって,環境の潜在的可能性を引き出しつつ,遊びの課題を生成し,そのことによって遊びの状況を絶えず更新している。このようなプロセスが保障される遊びこそ質の高い遊びであり,育ち合いが保障される。保育者は子どもの遊び課題と遊びの状況を理解し,援助の方策を考える必要がある。
- 著者
- 木戸 宜子 小原 眞知子 福山 和女 福山 和女
- 出版者
- 愛知県立大学『社会福祉研究』編集委員会
- 雑誌
- 社会福祉研究 = Social welfare studies (ISSN:13457179)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.11-22, 2021-11
4 0 0 0 OA 日本の地域産業連関表作成の現状と課題
- 著者
- 石川 良文
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1-2, pp.3-17, 2016-01-31 (Released:2016-03-10)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2 6
我が国で初めて地域産業連関表が作成されてから半世紀以上が経過し,現在では比較的大きなブロック単位から市町村レベルまで数多くの地域産業連関表が整備されるようになった.この状況は地域産業連関分析の発展と実際の政策分析ニーズに応えるために喜ばしい状況であると言える.しかし,今後永続的に地域産業連関表が作成され,各方面で活用されるためには今一度その作成の経緯と実態を明らかにし,今後の産業連関表作成の課題を検討する必要がある.本稿では,全国の都道府県,政令指定都市に対して行った実態調査を踏まえ,地域産業連関表の整備状況を概観すると共に今後の作成上の課題を検討する.
4 0 0 0 OA 長島町フィールドワークの記録
- 著者
- 荒武 賢一朗
- 出版者
- 関西大学文化交渉学教育研究拠点(ICIS)
- 雑誌
- 周縁の文化交渉学シリーズ8 『天草諸島の歴史と現在』
- 巻号頁・発行日
- pp.47-50, 2012-03-31
4 0 0 0 OA Potassium-selective channelrhodopsins
- 著者
- Elena G. Govorunova Oleg A. Sineshchekov John L. Spudich
- 出版者
- The Biophysical Society of Japan
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- pp.e201011, (Released:2023-02-04)
- 被引用文献数
- 1
Since their discovery 21 years ago, channelrhodopsins have come of age and have become indispensable tools for optogenetic control of excitable cells such as neurons and myocytes. Potential therapeutic utility of channelrhodopsins has been proven by partial vision restoration in a human patient. Previously known channelrhodopsins are either proton channels, non-selective cation channels almost equally permeable to Na+ and K+ besides protons, or anion channels. Two years ago, we discovered a group of channelrhodopsins that exhibit over an order of magnitude higher selectivity for K+ than for Na+. These proteins, known as “kalium channelrhodopsins” or KCRs, lack the canonical tetrameric selectivity filter found in voltage- and ligand-gated K+ channels, and use a unique selectivity mechanism intrinsic to their individual protomers. Mutant analysis has revealed that the key residues responsible for K+ selectivity in KCRs are located at both ends of the putative cation conduction pathway, and their role has been confirmed by high-resolution KCR structures. Expression of KCRs in mouse neurons and human cardiomyocytes enabled optical inhibition of these cells’ electrical activity. In this minireview we briefly discuss major results of KCR research obtained during the last two years and suggest some directions of future research.
4 0 0 0 OA 複眼のタイルパターンを決める幾何学機構
- 著者
- 佐藤 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.334-337, 2022 (Released:2023-01-25)
- 参考文献数
- 7
複眼の六角形タイル構造は物理的に安定と言われ,細胞形態が物理的制約に従って決められているという考えと合致する.しかし,ある種の変異体においては物理的に不安定な四角形タイルに変化する.ハエの複眼が六角形および四角形タイルを示す機構を解明することにより,細胞形態を幾何学的に制御するメカニズムを明らかにした.
4 0 0 0 OA 中上級レベルの「討論会」における準備活動の効果 : アイスブレーキングとプレ討論会
- 著者
- 柳田 直美
- 出版者
- 日本語教育方法研究会
- 雑誌
- 日本語教育方法研究会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.34-35, 2008-09-20
This study reports on the effects of preparation activities of ice breaking and pre-debate for debate in intermediate intensive Japanese class. The process of ice breaking involved self introduction, interviewing each others and reporting to class about the interview. Not only were the students able to express their opinions freely, but they also able to form the foundations for debate which are "listening to and understanding others" and "speaking plainly to the audience". Pre-debate makes students notice the importance of respect for others' opinions, cooperation in the group, and using suitable ways to express their opinions.