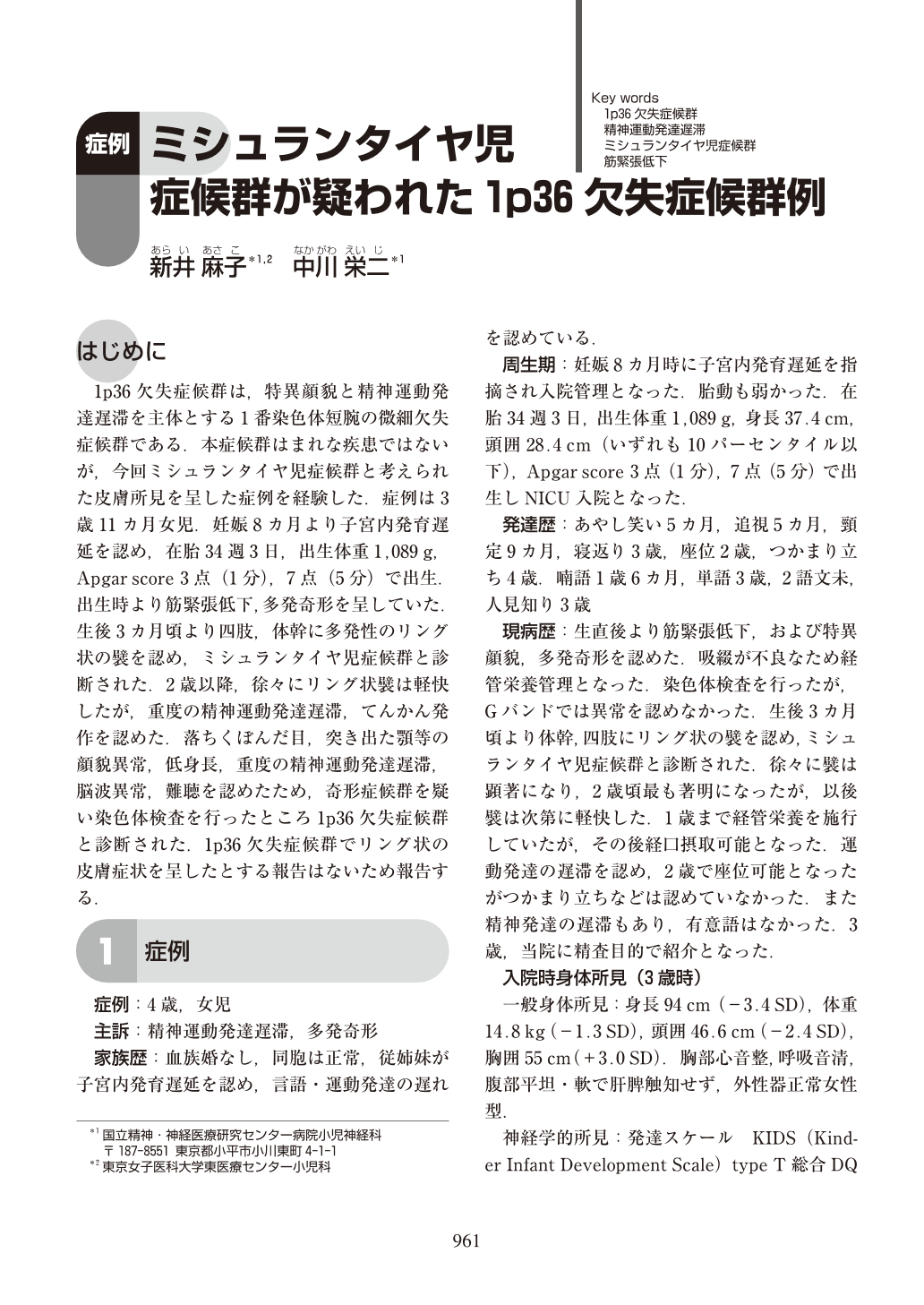4 0 0 0 OA タンザニア未電化地域における小規模な太陽光発電の利用実態と不適正利用による問題
- 著者
- 岡村 鉄兵 黒崎 龍悟
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.110-121, 2021-09-23 (Released:2021-09-23)
- 参考文献数
- 8
太陽光発電による小規模な独立型電源(Solar Home System、以下SHS)は系統電力網が整備されていない地域で、安価に再生可能エネルギーによる電化が可能と期待され、アフリカ農村において2000年頃から急速に普及が進んでいる。しかし、SHSの世帯レベルの電気の利用状況に着目した事例研究は少なく、住民が問題を抱えるに至る要因やそれによって農村住民にもたらされる影響は明らかにされていない。そこで本稿では、タンザニア南西部の農村での現地調査をとおして、SHSの普及状況と不適正利用の実態とその要因を明らかにした。調査はSHSを所有する32世帯とSHS販売者へのヒアリング調査、およびSHSを所有する世帯から10世帯を抽出してデータロガーによる出力測定をおこなった。結果、ほとんどの世帯がシステムの要となるバッテリーの管理に問題を抱えており、そのための経済的損失が示唆された。アフリカの電化状況や関連政策の評価はこのような利用の実態をふまえることが不可欠である。
4 0 0 0 OA ナイジェリア人ディアスポラとブハリ政権
- 著者
- 島田 周平
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.122-132, 2021-09-23 (Released:2021-09-23)
- 参考文献数
- 33
ナイジェリアはサハラ以南アフリカのなかで最大のディアスポラ送出国であり、彼らからの送金受入れ額でも突出した国である。ディアスポラの送金額は政府にとって無視できないものであり彼らの政治的発言力も高まってきている。ディアスポラと政府の関係はつねに良好なわけではない。2期目に入ったブハリ政権に対するディアスポラの批判は高まっている。ひとつは国際派的視点からの政治的民主化要求や強権政治批判であり、いまひとつは民族派的視点からの分離独立の要求である。ブハリ政権は、国際派ディアスポラの民主化要求や人権擁護の要求に対しては、国内の反政府運動との連携を阻止するため銀行口座の凍結やSNSの規制などを実施した。また独立を目指す政治組織IPOBに対しては、民族派ディアスポラも含めて徹底的に抑え込む方針で臨み、彼らと国内(東部)の政治家や伝統的支配者との分断を図ってきた。ブハリ政権は、ディアスポラの活動が国内の反政府運動や独立運動と連携することがないよう細心の注意を払ってきた。それが今後も可能かどうかは注視が必要である。
4 0 0 0 IR ベンヤミン「歴史の概念について」再読 -新全集版に基づいて (一) -
- 著者
- 鹿島 徹
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第1分冊, 哲学 東洋哲学 心理学 社会学 教育学 (ISSN:13417517)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.三-二〇, 2013-02-26
4 0 0 0 OA 英語論文の採択確率を上げるためにできること(<特集>国際会議に通すための英語論文執筆)
- 著者
- 松尾 豊 Yutaka Matsuo
- 雑誌
- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.373-379, 2008-05-01
4 0 0 0 IR フロベールとワイルド : 『ヘロディアス』と『サロメ』における文体とリズム
- 著者
- 大鐘 敦子
- 出版者
- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会
- 雑誌
- 慶應義塾大学日吉紀要. フランス語フランス文学
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.113-126, 2006-03
十九世紀末に一世を風靡したファム・ファタルの代表『サロメ』といえば、誰しもが思い浮かべるのはオスカー・ワイルドの戯曲である。ワイルドはビアズリーの挿絵にはじめはそれほど乗り気ではなかったと言われているが、そのモノクロの挿絵はワイルドの『サロメ』の妖艶さや退廃的、破滅的、悪魔的側面を全面に押し出して、読者や未来の観衆の関心を引き寄せることになった。しかしこれを遡ること十六年、ギュスターヴ・フロベールが最晩年の短編『ヘロディアス』においてサロメのダンスを初めて言語化することに成功したことや、ワイルドがフロベールに多大な影響を受け、意識的に初稿をフランス語で書いていたことは意外に知られていない。 『サロメ』は、1891年11月から12月にかけてオスカー・ワイルドのパリ滞在中にフランス語で書かれ、1893年にパリで出版された。本国では上演禁止となり、ロンドンでの出版は1894年となった。ワイルドはフランス文学に精通し、パリの文壇や社交界にも出入りし、ジッド、マラルメ、ピエール・ルイスなどと親しく交流して、マラルメの"火曜会"にも二度顔を出していることが知られている。 当時すでにフロベールは他界していたわけだが、ワイルドはフロベールを文学の師として、美学的にも仰いでいたことが書簡に残された証言からわかる。1888年のW. E. Henley 宛の手紙では、英語で散文を書くためにフランスの散文を勉強していることを述べ、「そう、フロベールこそわが師なのだ。そして『誘惑』の英訳が成功したなら、私は第二のフロベールになれるし、それ以上のものになるだろう。」と『聖アントワーヌの誘惑』の翻訳について意欲を燃やしている。また1890年には、Scots Observer の編集者への手紙で美学的問題に触れ、『ボヴァリー夫人』と『サランボー』を引き合いに出しながら、「フロベールは言葉の日常的な感覚において正しいだけでなく、芸術的にも正しかった。そしてそれがすべてなのだ。」と全面的に尊敬の念を表している。投獄中に友人に読書用の本を依頼した際にも、フランス語文献リストの筆頭にフロベールの La Tentation de saint Antoine, TroisContes, Salammbô を挙げている。一方、Pascal Aquien はフロベールとの関係について、サランボーの名前や巫女というアイデンティティー、ユダヤ人たちの議論、「サロメ」と「ヘロディアス」という主人公たちの名前の拝借、『ヘロディアス』の「ヨカナン」「マナエイ」から「ヨカナン」「ナアマン」という命名をしたことなど、かなり影響があったことを指摘している。 『サロメ』に関するワイルドの証言で特にフロベールに関係あるものを挙げておきたい。まず第一に挙げられるのは、1890 年のエドガー・ソルタスによる挿話で、サロメについて書くと宣言していたワイルドが、ある晩ピカデリーのレストランでソルタスと食事をした後、連れ立ってフランシス・ホープのアトリエをたずねたところ、逆立ちしたヘロディアスの版画が、まさにフロベールの作品のように描かれており、 « La bella donna della mia mente »(「わが夢見る麗しき女性よ!」)と叫んだという話。第二は、アメリカの象徴派詩人スチュアート・メリルとムーラン・ルージュに行ったときの挿話で、ルーマニア娘のアクロバット的な逆立ちの踊りを見たワイルドが、執筆中の劇の中のサロメのダンスを踊ってもらおうと思い、「フロベールの物語でのように、あの娘に逆立ちのダンスをしてほしいんだ。」と言ったという話である。どちらも注目されるのは、ワイルドがフロベールのサロメのダンスの「逆立ちの踊り」にとても惹かれていたということである。また、サランボーへの賛美も惜しまず、ビアズリーの挿絵について批判する際に「僕のサロメはサランボーの妹だ」という表現すらしている。 『ヘロディアス』の中でサロメの踊りの初の言語化に挑んだフロベールの先駆性と象徴性を論じた拙論では、その「逆立ちのポーズ」に読み取れるユダヤ教的世界観からキリスト教的世界観への逆転というメタファーを指摘したが、ワイルドが果たしてフロベールのサロメの「逆立ちの踊り」にこうした意味を読み取っていたかは定かではなく、踊りのト書きにも逆立ちのポーズへの言及はない。その代わり、ワイルドのサロメでは「七枚のヴェールの踊り」というメタファーと月のメタファーが全面に押し出されている。ことにワイルドがサロメを一幕物の劇にしたことから、登場人物の科白の文体が重要な位置を占めており、後にその作品の芸術性は、音楽性としてシュトラウスのオペラが証明することになった。以下、本稿ではワイルドのサロメの文体とリズムをフロベールのそれと比較しながら、『ヘロディアス』のサンボリスムから『サロメ』の世紀末文学への変遷をみることとする。
4 0 0 0 近江史料シリーズ
- 著者
- 滋賀県地方史研究家連絡会 編
- 出版者
- 滋賀県立図書館
- 巻号頁・発行日
- vol.7, 1990
4 0 0 0 OA ロマネスク彫刻における三面像の意味 : ウンブリア州、ラツィオ州の例に関する一考察
- 著者
- 尾形 希和子
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.198-222, 1992-10-20
Sui portali delle chiese romaniche, spesso i tralci di vite o di acanto avvolgenti uccelli, belve, mostri e uomini (tralci abitati) sono scolpiti lungo gli stipiti e archivolti e/o architravi. Tutto insieme rappresenta il mondo da redimere attraverso il sacrificio di Cristo. Alcuni tralci escono dalla bocca di animali (lupi, leoni, pantere, ecc.), simboli del tempo che tutto divora e sputa. Nelle chiese romaniche del Lazio e dell' Umbria si trovano i volti trifronti al posto di questi animali temporali. L' esempio della chiesa di S. Pietro a Tuscania mostra, in un biforio a sinistra del rosone sulla facciata, due figure trifronti con le caratteristiche di Satana, una con le corna e l' altra con un serpente in mano. Altre figure trifronti, una al Duomo di Spoleto, una sulla lunetta del museo civico spoletino e l' altra all′ intradosso dell' architrave del duomo di Civita Castellana non dimostrano questa natura demoniaca dei tricefali di Tuscania, ma invece, a mio avviso hanno ancora il significato del tempo che crea il mondo. Il volto trifronte o tricefalo, che ha le sue origini remote nell' immagine degli dei pagani del sole, e usato per simboleggiare il tempo, e nel tardo medioevo e nel Rinascimento si trasforma nelle immagini della "prudenza" frequenti in quel periodo. Anche Giano italico, il dio del passaggio e l' iniziazione viene rappresentato con due facce e a volte anche con tre. Saturno il secondo re dell' Italia nell' eta primordiale fu anche il dio dell "inizio", in quanto insegno l' agricoltura agli uomini e li civilizzo. Noi troviamo le immagini di questi due primi re dell' Italia mitica in "Annus"(dominatore dell' anno ciclico e del tempo, al centro del ciclo dei lavori di 12 mesi o dei 12 segni zodiacali) nei calendari illustrati, nei pavimenti musivi delle chiese e nei cicli sculturali che ornano i portali delle chiese dell' epoca romanica. Inoltre "Annus" circondato dai 12 mesi e le quattro stagioni, viene associato al Cristo con quattro evangelisti e 12 apostoli. Cristo veniva simboleggiato dal rosone aperto sulla facciata delle chiese romaniche soprattutto nell' area del Lazio-Umbria. Rosone-sole-Cristo cosmocrator-Annus sono immagini intercambiabili tra di loro. Il sole e il tempo possono essere rappresentati con tre facce o tre teste. Anche il Cristo ha tra le sue raffigurazioni un' immagine tricefala come "Trinita". La concezione di Trinita e legata alla Creazione del mondo, e cosi il volto trifronte vomitante i tralci da due bocche laterali puo avere il significato del tempo che crea il mondo. Il volto trifronte che ha l' aspetto di "Green Man", la maschera divoratrice e vomitatrice dei tralci del mondo, era correlata con la forza della natura e la fecondita che fa rinascere la vegetazione. Il romanico fu un periodo in cui si cerco di unire il profano al sacro, il ricordo del passato (di Roma antica) al presente mondo cristiano, dove gli dei antichi italici potevano ancora avere il loro carattere benevolo prima di divenire esseri demoniaci come avvenne piu tardi. Il tempo profano durante il quale si svolgono i lavori dei contadini, era integrato nel tempo sacro delle chiese. Poiche tutto il medioevo era sostentato grazie alla terra, i contadini vennero considerati importanti e la rivalutazione del lavoro agricolo fu resa piu chiara. E soprattutto nel Lazio e Umbria posti non lontani da Roma, citta di antichi italici, paiono sopravvivere le immagini di Giano e Saturno come il tempo, datore della vita alla vegetazione. Il volto trifronte, immagine collegata con il sole, Giano, Saturno e Cristo, poteva quindi simboleggiare il tempo anche nel contesto cristiano del XII secolo.
4 0 0 0 創作舞踊における身体の動きに関する研究
4 0 0 0 OA 中枢神経系の後遺症を残した低血糖昏睡3例の臨床像
- 著者
- 垣屋 聡 稲垣 朱実 三浦 奈穂子 伊佐治 美穂 近藤 正樹 本美 善英 板津 武晴
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.267-273, 2006 (Released:2009-01-19)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 3
中枢神経系の後遺症を残した低血糖昏睡3症例を報告する.症例1は79歳,女性.一過性脳虚血発作の既往と4期の腎症を認めていた.グリベンクラミド3.75 mg, アカルボース300 mg内服.入院時血糖値32 mg/dl, 約8時間の昏睡.頭部MRIの拡散強調像で右放線冠に高信号領域を認めた.血糖回復するも痴呆の進行を認め,肺炎,腎不全を併発し永眠された.症例2は61歳,男性.狭心症の既往がある.グリメピリド6 mg, アカルボース300 mg内服.入院時血糖値17 mg/dl, 約5時間の昏睡.頭部MRIはラクナ梗塞のみであった.血糖回復後も意欲の低下および記銘力の障害を残した.症例3は71歳,男性.パーキンソン病を合併.グリベンクラミド5 mg内服.入院時血糖値38 mg/dl, 約4時間の昏睡.頭部MRIは両側の放線冠,頭頂葉の大脳皮質に拡散強調像にて高信号領域を認め,血糖回復後も構音障害,見当識障害を残した.高齢者で動脈硬化性疾患や神経変性疾患を合併する場合,比較的短時間の低血糖昏睡でも中枢神経系の後遺症を残す可能性があり,スルホニル尿素薬の治療には注意が必要であると考えられた.また,低血糖脳症の診断に,頭部MRI拡散強調像は有用であると考えられた.
4 0 0 0 IR 〈哭き女〉考―中国・寧波市鄞州区農村部の喪葬における《孟姜女》の調べをめぐって―
- 著者
- 木村 直弘
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- 女性・ヒロイン・社会 社会と時代の表象における女性像
- 巻号頁・発行日
- pp.169-185, 2011-02-28
4 0 0 0 IR 志賀親朋書翰集翻刻(1)
- 著者
- 沢田 和彦 畠山 雄三郎
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.203-222, 2021
本号から数回にわたって長崎市の長崎歴史文化博物館所蔵の『東京親朋書翰綴込』の翻刻を連載する。志賀親朋は本邦最初のプロのロシア語通詞である。第一回は文久元(一八六一)年二月十五日から八月十八日までの書翰計十一通を紹介する。
4 0 0 0 OA 怒り状態の心理・生理反応
- 著者
- 木下 順
- 出版者
- 国学院大学
- 雑誌
- 国学院大学紀要 (ISSN:02865823)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.69-91, 2010
4 0 0 0 OA アート・ドキュメンテーションの来し方と行く方 ──次世代の担い手を探る
- 著者
- 赤間 亮 波多野 宏之 本間 友
- 出版者
- アート・ドキュメンテーション学会
- 雑誌
- アート・ドキュメンテーション研究 (ISSN:09179739)
- 巻号頁・発行日
- vol.27.28, pp.18-33, 2020-05-31 (Released:2021-06-23)
本稿は、JADS 30周年記念企画行事 第12回秋季研究集会(2019年11月16、17日)の2日目に行われた鼎談の記録である。鼎談においては、JADS創設に関わった初代幹事長/初代会長・波多野宏之氏を迎え、JADSの歴史、アート・ドキュメンテーションの必要性、対象とするアートの範囲について活発な議論が交わされた。
4 0 0 0 ミシュランタイヤ児症候群が疑われた1p36欠失症候群例
症例は4歳女児で、生直後より筋緊張低下、および特異顔貌多発奇形を認めた。吸綴が不良なため経管栄養管理となった。生後3ヵ月頃より体幹、四肢にリング状の襞を認め、ミシュランタイヤ児症候群と診断した。徐々に襞は顕著になり、2歳頃最も著明になったが、以後次第に軽快した。1歳まで経管栄養を施行したが、その後経口摂取可能となった。運動発達の遅滞を認め、2歳で座位可能となったが、つかまり立ちなどは認めていなかった。また精神発達の遅滞もあり、有意語はなかった。FISH解析を行ったところ、46,XX,ish del(1)(p36.3)(D1Z2-)と染色体異常を認め、1p36欠失症候群と確定診断した。4歳時に朝食中に突然無呼吸、チアノーゼが出現、脳波検査にて両側後頭部に高振幅徐波、右前頭・中心部に棘波を認めた。てんかんによる無呼吸と診断し、抗てんかん薬内服となった。4歳になり、つかまり立ち、伝い歩きを認めるようになったが、有意語は出現していない。
- 著者
- 賴 美麗
- 出版者
- 別府大学日本語教育研究センター
- 雑誌
- 別府大学日本語教育研究 別府大学日本語教育研究センター紀要 (ISSN:21871000)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.3-13, 2015