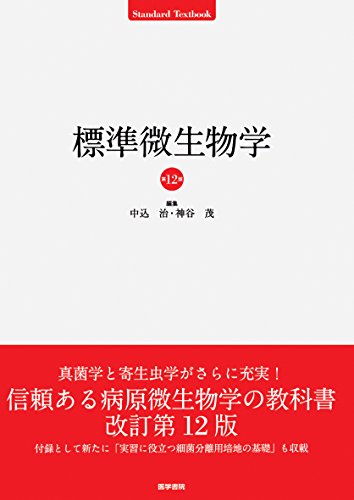4 0 0 0 OA ユーモアに対する態度と攻撃性及び愛他性との関係
- 著者
- 上野 行良
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.247-254, 1993-10-30 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 11 14
This study investigated the attitude towards humor and the relationship among the attitude, aggression and altruism. Four hundred and seven subjects answered the questionnaires consisting of (1) items about attitude toward humor, (2) items about aggression and altruism, and (3) items about humorous statements, frequently heared in negative situations. Factor analysis revealed that the attitude toward humor consists of two factors; (a) preference for aggressive humor and (b) preference for playful humor. The former is related to aggression and altruism, while the latter is related to altruism only. The items about humorous statements frequently heard in negative situations suggested that preference for aggressive humor is related to aggressive behavior, while preference for playful humor is related to moderation of the atomosphere.
4 0 0 0 OA 研究のスポット
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.11, pp.733-738, 2004-11-25 (Released:2009-05-25)
- 被引用文献数
- 3 1
4 0 0 0 OA 5.高齢者の多病性と降圧薬の選択
- 著者
- 海老原 孝枝 大類 孝 海老原 覚 辻 一郎 佐々木 英忠 荒井 啓行
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.448-451, 2007 (Released:2007-09-06)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2
Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor plays an important role not only as an antihypertensive drug but also for prevention of various complications related to geriatric syndrome. Pneumonia in the disabled elderly is mostly due to silent aspiration of oropharyngeal bacterial pathogens to the lower respiratory tract. Aspiration is related to the dysfunction of dopaminergic neurons by cebrovascular disease, resulting in impairments in both the swallowing and cough reflexes. ACE inhibitor can increase in the sensitivity of the cough reflex particularly in older post-menopausal women, and improvement of the swallowing reflex. In a 2-year follow-up study in stroke patients, patients who did not receive ACE inhibitors had a higher risk of mortality due to pneumonia than in stroke patients who were treated with ACE inhibitor. Moreover, the mortality of pneumonia was significantly lower in older hypertensive patients given ACE inhibitors than in those treated with other antihypertensive drugs. On the other hand, we found a new benefit of ACE inhibitor on the central nervous system. The mortality in Alzheimer's disease patients who received brain-penetrating ACE inhibitor was lower than in those who received other antihypertensive drugs. In a 1-year follow-up study, cognitive decline was lower in patients receiving brain-penetrating ACE inhibitors than in patients receiving a non-brain-penetrating ACE inhibitor or a calcium channel blocker. Brain-penetrating ACE inhibitors may slow cognitive decline in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. ACE inhibitor might be effective for the disabled elderly, resulting in the prevention of aspiration pneumonia and Alzheimer's disease for the elderly.
- 著者
- NAOE Hiroaki MATSUMOTO Takanori UENO Keisuke MAKI Takashi DEUSHI Makoto TAKEUCHI Ayako
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-019, (Released:2020-02-03)
- 被引用文献数
- 1
This study constructs a merged total column ozone (TCO) dataset using 20 available satellite Level 2 TCO (L2SAT) datasets over 40 years from 1978 to 2017. The individual 20 datasets and the merged TCO dataset are corrected against ground-based Dobson and Brewer spectrophotometer TCO (GD) measurements. Two bias correction methods are used: simple linear regression (SLR) as a function of time and multiple linear regression (MLR) as a function of time, solar zenith angle, and effective ozone temperature. All of the satellite datasets are consistent with GD within ±2-3%, except for some degraded data from the Total Ozone Mapping Spectrometer/Earth Probe during a period of degraded calibration and from the Ozone Mapping and Profiling Suite (OMPS) provided from NOAA at an early stage of measurements. OMPS data provided from NASA show fairly stable L2SAT-GD differences. The Global Ozone Monitoring Experiment/MetOp-A and -B datasets show abrupt changes of approximately 8 DU coincident with the change of retrieval algorithm. For the TCO merged datasets created by averaging all coincident data located within a grid cell from the 20 satellite-borne TCO datasets, the differences between corrected and uncorrected TCOs by MLR are generally positive at lower latitudes where the bias correction increases TCO because of low effective ozone temperature. In the trend analysis, the difference between corrected and uncorrected TCO trends by MLR shows clear seasonal and latitudinal dependency, whereas such seasonal and latitudinal dependency is lost by SLR. The root mean square difference of L2SAT-GD for the uncorrected merged datasets, 8.6 DU, is reduced to 8.4 DU after correction using SLR and MLR. Therefore, the empirically corrected merged TCO datasets that are converted into time-series homogenization with high temporal-resolution are suitable as a data source for trend analyses as well as assimilation for long-term reanalysis.
4 0 0 0 IR 三匹獅子舞の分布
- 著者
- 笹原 亮二
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告 (ISSN:0385180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.171-236, 2001
4 0 0 0 秩父産ガロアムシに関する研究
- 著者
- 福島 義一
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 秩父自然科学博物館研究報告 (ISSN:05291305)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.31-38, 1966-03
4 0 0 0 OA East Asian-Australian Monsoon Variations and Their Impacts on Regional Climate during Boreal Summer
- 著者
- CHEN Wei GUAN Zhaoyong YANG Huadong XU Qi
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-014, (Released:2019-12-08)
- 被引用文献数
- 6
The East Asian summer monsoon (EASM) and the Australian winter monsoon (AWM) are two important components of the Asian-Australian monsoon system during boreal summer. The simultaneous variations of these two monsoons would have remarkable impacts on climate in the Asian-Australian region. Using the reanalysis datasets, we investigate the mechanisms of variation and impacts of East Asian-Australian Monsoons (EAAMs). The singular value decomposition (SVD) is performed of the June-July-August (JJA) mean anomalous zonal wind for AWM as left field and JJA mean anomalous meridional wind for EASM as the right field after both El Niño-Southern Oscillation (ENSO) and India Ocean Dipole (IOD) signals are filtered out. Our results demonstrate that AWM and EASM are closely related to each other as revealed by the first leading SVD mode. The anomalously strong (weak) EAAMs correspond to anomalously strong (weak) AWM and EASM to the south of 30°N. When EAAMs are anomalously strong, cold sea surface temperature anomaly (SSTA) appears in regions near northern and northeastern coasts of Australia whereas the warmer SSTA appears in the northwestern tropical Pacific and South China Sea. The colder SSTA is associated with the upwelling of cold water from below induced by equatorial easterly anomalies, reinforcing the anticyclonic circulation over Australia through the Matsuno/Gill-type response whereas warm SSTA appears in the northwestern tropical Pacific and South China Sea as a result of oceanic response to the intensified northwest Pacific subtropical anticyclonic circulation. The EASM couples with AWM via the anomalous easterlies near equator in the Maritime Continent (MC) region and the slanted vertical anomalous circulations. In the years with strong EAAMs, precipitation decreases in northern Australia and over areas from the western Pacific to Bohai Sea and Yellow Sea of China. Meanwhile, the western MC and the southeastern China experience more than normal precipitation.
4 0 0 0 OA 不安定な状況下における小殿筋筋活動の比較
- 著者
- 室伏 祐介 川上 照彦 岡上 裕介 永野 靖典 池内 昌彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0390, 2017 (Released:2017-04-24)
【緒言】股関節安定化機構である股関節深層筋に着目した報告が散見され,深層筋である小殿筋は股関節に安定をもたらす働きがあるとされている。PETやMRIを用いた研究では,歩行や片脚立位時には中殿筋よりも小殿筋の活動が高いと報告されており,変形性股関節症でみられる股関節外転筋機能不全に対しては,深層筋の働きを考慮しなくてはならない。また,我々は小殿筋にワイヤ電極を留置し,小殿筋の筋活動を分析してきた。その結果,歩行立脚期において小殿筋は中殿筋と同等の筋活動量を示していることを報告し,筋電図学的にも小殿筋が股関節の安定に関与していることが示唆された。さらに,小殿筋の筋線維の走行は,中殿筋よりも求心位方向を向いており,解剖学的にも安定性に関与していると考えられる。今回,小殿筋が股関節の安定性に関与しているかさらに検討をすすめるために,不安定な状況下における小殿筋の筋活動を比較することである。【方法】対象は,健常成人13名(男性7名,女性6名)である。被検筋を小殿筋と中殿筋とし,電極の留置場所は,小殿筋が腸骨稜の中点と大転子を結んだ中点に,中殿筋が腸骨稜の中点より2.5cm遠位に留置した。ワイヤ電極は,ウレタンコーティングされた直径0.1 mmのステンレス線で,先端の0.5 mmだけコーティングを剥がし通電できるようにし,電極間距離は2 mmになるように貼り合わせ,双極誘導ができるようにしている。1本のワイヤ電極は22 Gのカテラン針に通した後,ガス滅菌処理をして使用した。なお,電極の留置は整形外科医が行っている。測定課題は,平地での片脚立位,バランスクッション上での片脚立位,半球上での片脚立位を各5秒間行った。解析は,片脚立位の開始と終了の1秒を除く3秒間の積分値を算出した。積分値の算出には,BIMUTASを使用し,20-1000 Hzのバンドパスフィルターを通した後に解析を行った。また,算出した積分値は,最大随意収縮時の値に対する相対値にて比較を行った。【結果】平地での片脚立位,バランスクッション上での片脚立位,半球上での片脚立位とより不安定な状況になると,有意差は認めなかったが筋活動量が増加した。また,性別ごとに比べると,女性では不安定な状況が増すと小殿筋の筋活動量が有意に高くなった(p<0.05)。さらに男女の差を比較すると,半球上での片脚立位においは,小殿筋の筋活動量が男性より女性の方が有意に高くなった(p<0.05)。【考察】片脚立位を保持するためには,支持面が不安定になると股関節を安定させる必要がある。よって,小殿筋の筋活動量が上がったものと考えられる。また,この傾向は女性においてより顕著にみられた。本邦の変形性股関節症例は多くが二次性であり,また,発育性股関節形成不全の多くは女性である。よって形態学的にも女性の方が股関節の安定は保たれにくく,その代償としてより小殿筋の筋活動が必要となったのではないかと考えられる。
- 著者
- 片桐 由美子 矢崎 高明 井上 宜充 高篠 瑞穂 久合田 浩幸 田村 拓也
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.A0434, 2008
【目的】臨床では腹臥位が困難な症例に対し、背側の筋を働かせる目的で背臥位でのブリッジ運動や膝関節伸展位での股関節伸展運動を行うことがある。今回はブリッジ課題と背臥位での股関節伸展課題の体幹・下肢の筋活動を比較・検討したので報告する。<BR>【方法】対象は健常男性10名(27.4±4.22歳)。筋活動電位は日本光電マルチテレメーターシステムWEB-5500を用い表面電極にて導出した。測定筋は右側の腹直筋、外腹斜筋、傍脊柱筋、大腿直筋、大殿筋、中殿筋、半腱様筋とした。測定課題は背臥位・両膝関節屈曲120°の両脚ブリッジ課題(WB)、背臥位・両股関節屈曲20°・膝関節伸展位で足部を台にのせた位置からの股関節伸展課題(HE)とした。最終肢位は両課題とも股関節が中間位まで殿部を挙上した位置とした。それぞれ最終肢位を5秒間保持し、その中から安定した3秒間のデータを採用した。各筋についてDanielsの徒手筋力テストの抗重力肢位での最大等尺性収縮値をMVCとし、WBとHEにおける各筋の%MVCを算出した。有意差の判定はWilcoxonの符号順位和検定を使用した(p<0.05)。<BR>【結果】各筋の筋活動はWBでは傍脊柱筋55.03±17.63%、中殿筋31.35±33.16%、大殿筋44.88±30.04%、大腿直筋14.78±16.24%、半腱様筋20.27±12.79%。HEでは傍脊柱筋83.83±28.76%、中殿筋49.13±30.36%、大殿筋64.43±42.70%、大腿直筋25.65±15.07%、半腱様筋77.23±51.75%。全ての筋でHEの方がWBよりも高い値を示し、有意差は傍脊柱筋、中殿筋、大腿直筋、半腱様筋で認められた。<BR>【考察】ブリッジ課題は股関節周囲筋へのトレーニング効果が少なく背筋群での効果が高いといわれているが、今回のわれわれの実験では大殿筋および中殿筋において、どちらも30%以上の高値を示し、筋力増強が期待できることが示唆された。HEでは傍脊柱筋83%、大殿筋64%、半腱様筋77%と全ての背側の筋で高値を示し、中でも半腱様筋と傍脊柱筋は有意に高かった。挙上する際の肩甲帯~足部の距離がHEはWBよりも長い。殿部を挙上する高さが異なるため一概には言えないが、この長さの影響で背側筋群に高値結果が出たと考えた。そのひとつとしてHEでは膝関節伸展位のため二関節筋である半腱様筋は股関節伸展筋としても働きWBより筋力が発揮されたと考えた。また、HEでは体幹を挙上させる際に、半腱様筋、中殿筋が股関節固定筋として働いたためWBよりも高値を示したと考えた。
- 著者
- MISAKI A.
- 出版者
- Tokai University Press
- 雑誌
- Cephalopods-Present and Past
- 巻号頁・発行日
- pp.223-231, 2010
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA WS4-2 サイトカインストームに対するIL-6阻害療法の可能性
- 著者
- 田中 敏郎
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.291b, 2015 (Released:2015-10-25)
現在,関節リウマチ,若年性特発性関節炎,キャスルマン病に対する治療薬として承認されているヒト化抗IL-6受容体抗体トシリズマブは,他の様々な慢性に経過する免疫難病にも新たな治療薬となる可能性があり,臨床試験が進められている.また,最近,キメラ抗原受容体を用いたT細胞療法に合併するサイトカイン放出症候群にもトシリズマブが著効することが示され,IL-6阻害療法は,サイトカインストームを呈する急性全身性炎症反応に対しても新たな治療手段となる可能性がある.サイトカインストームには,サイトカイン放出症候群,敗血症ショック,全身性炎症反応症候群,血球貪食症候群やマクロファージ活性化症候群など含むが,特に敗血症ショックでは,病初期のサイトカインストームとその後の二次性の免疫不全状態により,予後が極めて悪く,しかし有効な免疫療法がないのが現状である.敗血症患者ではIL-6は著増し,IL-6の血管内皮細胞の活性化,心筋抑制や凝固カスケードの活性化等の多彩な作用,また,同様な病態を呈するサイトカイン放出症候群に対するトシリズマブの劇的な効果を見ると,IL-6阻害は敗血症に伴う多臓器不全に対して有効な治療法となる可能性がある.しかし,現在,トシリズマブは重篤な感染症を合併している患者には禁忌であり,どのように挑戦するのか,症例(報告)の解析,患者検体,動物モデルを用いた我々のアプローチを紹介したい.
4 0 0 0 OA ハワイ・北米における日本人移民および日系人に関する資料について(4)
- 著者
- 神繁司
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.54, 2001-03-29
- 著者
- 平川 毅彦 Hirakawa Takehiko
- 出版者
- 新潟青陵学会
- 雑誌
- 新潟青陵学会誌 (ISSN:1883759X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.1-10, 2016-03
This paper undertakes a theoretical discussion of Shigeo Okamura's Chiiki fukushi-ron("Theory of Community-based Welfare," published 1974)with the aim of clarifying the challenges inherent in one ofthe theory's key concepts, namely that of the "Welfare Community." Although not so as to radically upset its claims, the conceptual definition and deployment of the Welfare Community has been accompanied by the recognition of certain "fluctuations" in its fundamental logic. Informed by a specifically social-welfare perspective and reconstructed based on subjective and individual principles, the Welfare Community concept can encompass possibilities for local communities in everyday life and the overall social context by focusing on the life challenges faced by specific individuals. In contemporary society, which is growingever more diverse, complex, and all-encompassing, the Welfare Community concept represents an intelligent tool that enables individuals to lead lives of convention amidst diversity. For anyone to be able to master the use of this tool is both the aim of the Welfare Community concept and a future challenge for local communities.本論は、岡村重夫の『地域福祉論』(1974年)をテキストとして、鍵概念となる「福祉コミュニティ」についての理論的検討を行い、その内在的課題を明らかにした。その主張を根底から覆すようなものではなかったが、福祉コミュニティの定義及び展開の中で、柱となる論理に「ゆらぎ」が認められた。社会福祉固有の視点を貫き、主体的・個別的な原則のもとに再構成された福祉コミュニティ概念は、生活課題を抱えた具体的な個人を中心として、日常生活の場である地域社会の在り方と、それをとりまく全体社会を視野におさめることができる。「福祉コミュニティ」は、多様化・複雑化、そして大規模化する現代社会にあって、一人ひとりが「多様なままで」「あたりまえの生活」を営むことを可能にするための知的ツールである。だれもがこのツールを使いこなすことができるようになること、それが「福祉コミュニティ」の目的であり、その先にある「地域社会」の課題である。
- 著者
- Masato Sugi Yohei Yamada Kohei Yoshida Ryo Mizuta Masuo Nakano Chihiro Kodama Masaki Satoh
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-012, (Released:2020-03-19)
- 被引用文献数
- 31
In relation to projections of tropical cyclone (TC) frequency in a future warmer climate, there is a debate on whether the global frequency of TC seeds (weak pre-storm vortices) will increase or not. We examined changes in the frequency of TC seeds by occurrence frequency analysis (OFA) of vortex intensity (vorticity or maximum wind speed). We directly counted the number of vortices with various intensities in high resolution global atmospheric model simulations for present and future climates. By using the OFA we showed a clear reduction of the occurrence frequency of TC seeds and relatively weak (category 2 or weaker) TCs in a future warmer climate, with an increase in the frequency of the most intense (category 5) TCs. The results suggest that the OFA is a useful method to estimate the future changes in TC frequency distribution ranging from TC seeds to the most intense TCs.
本稿はフーコーが『生政治の誕生』で展開した議論を参照し,ネオリベラリズムをアントレプレナー的な主体化をうながす権力として分析するとともに,この権力が作動する条件として,ネオリベラリズムが心理的な暴力を活用する側面に着目する.<br>まずネオリベラリズムを権力ととらえるフーコーの議論から,ネオリベラリズムが主体を自己実現的なアントレプレナーとみなす考え方に立脚している点を明らかにするとともに,アントレプレナー的な主体化にともなうさまざまな問題や困難を指摘する.次にアントレプレナーへのあこがれが,その実現が困難な人々――フリーターなどの不安定な立場の者――にも見られることに着目し,アントレプレナーへの志向がかならずしも実現可能性の客観的な条件に規定されるわけではなく,彼らの現実への不満に根ざしていることを指摘する.最後に,ナオミ・クラインのショック・ドクトリン議論を参照し,この不満(絶望)を生産する権力としてネオリベリズムをとらえなおす.ここからネオリベラリズムの主体が「アントレプレナー」であるとともに「被災者」であることを明らかにし,社会の「心理学化」のもう1つの側面を指摘する.
4 0 0 0 OA ゲノムワイド関連マッピング (<連載3>始めよう!エコゲノミクス(2))
- 著者
- 山道 真人 印南 秀樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.105-113, 2009-03-30 (Released:2016-10-08)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 5