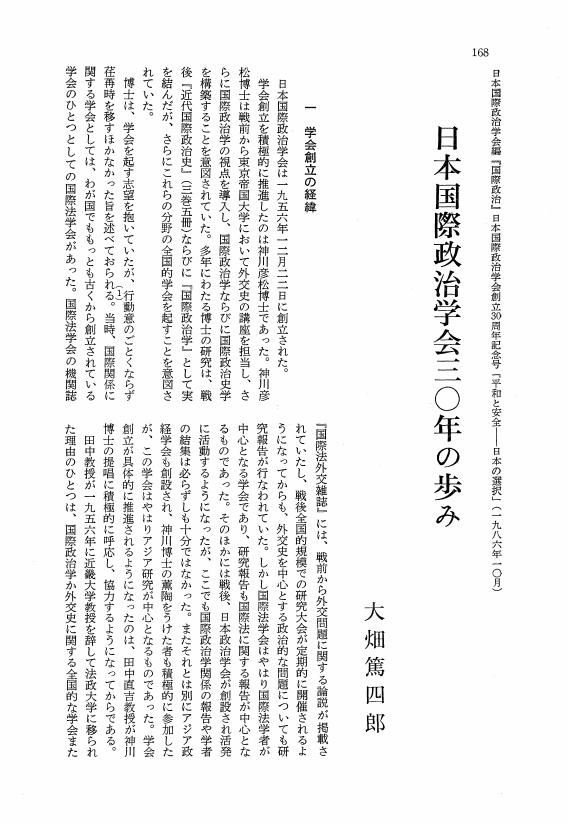3 0 0 0 OA ミルクアレルギー児におけるビオチン欠乏症の問題
- 著者
- 今井 孝成 海老澤 元宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.1614-1620, 2011-12-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 5
3 0 0 0 OA Ta波の成因とその病的意義
- 著者
- 小野 克重
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.35-39, 2022-03-04 (Released:2022-03-17)
- 参考文献数
- 11
3 0 0 0 OA 研究の視点をもつための基礎トレーニング
- 著者
- 三明 淳一朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.31-34, 2022-03-04 (Released:2022-03-17)
- 参考文献数
- 4
3 0 0 0 OA 日本国際政治学会三〇年の歩み
- 著者
- 大畑 篤四郎
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.Special, pp.168-193, 1986-10-18 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 上野 恵子 西岡 大輔 近藤 尚己
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-070, (Released:2021-10-29)
- 参考文献数
- 29
目的 近年,生活保護制度の被保護者への健康管理支援の重要性が指摘され,施策が打たれている。本研究は,2021(令和3)年に全国の福祉事務所で必須事業となった「被保護者健康管理支援事業」に対して福祉事務所が抱える期待や懸念,および国・都道府県への要望を明らかにすることを目的とした。方法 2019年11月,機縁法により選定された23か所の福祉事務所に,質問紙調査を依頼した。質問紙では,健康管理支援事業の実施に際して期待する点ならびに懸念する点,国・都道府県から受けたい支援を自由記述で回答を求めた。次いで2019年11月から2020年2月にかけて,福祉事務所でヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査では,質問紙項目に記載が不十分な回答,回答の補足事項や不明点を調査票の内容に沿って聞き取りを実施した。結果 16か所の福祉事務所から調査票の回答およびヒアリング調査の承諾を得た(同意割合69.6%)。福祉事務所担当者は健康管理支援事業が被保護者の健康意識・状態を改善し,被保護者のみならず他住民への取り組みとしても実施されることを期待していた。また,困難を感じている点として,実施体制の構築,事業の評価指標・対象者の設定,保健医療専門職の確保が示唆された。国・都道府県への要望としては,評価指標・基準の提示,標準様式の提供,参考となる事業事例の紹介,福祉事務所間や地域の他の関係機関との連絡調整,情報共有の場の提供,財源の確保などが挙げられた。結論 健康管理支援事業の円滑な実施を推進するためには,自治体と国ならびに都道府県が連携を深めるとともに,重層的な支援体制の構築が求められている。
3 0 0 0 OA 新興地域の統計事情 第1回 インド
- 著者
- 東川 繁
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.675-680, 2012-12-01 (Released:2012-12-01)
- 著者
- 冨安 皓行
- 出版者
- 国立大学法人 大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター
- 雑誌
- 未来共創 (ISSN:24358010)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.3-30, 2021 (Released:2021-07-08)
本研究は、米国に住む「日本人ゲイ」が性的マイノリティ性と人種・民族的マイノリティ性という二つのマイノリティ性をどのように経験してきたのかについて記述することを目的とする。本研究は語る内容のみならずどのように物語るかという語り方、すなわち物語/語りのナラティブとしての側面に着目し、カリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアに住む三名の「日本人ゲイ」の物語/語りを提示・分析する。三名の物語/語りは「オカマ」のような話し方によるいじめについての話や、日本企業の異性愛中心性についての話、日本と米国どちらに住み続けるかについて思案するような話を含んでいる。これらの話は既存の研究の指摘と多分に重なり合う。 ときに「日本人ゲイ」たちの物語/語りは両義性や矛盾を含む。たとえば一方で人種的・民族的マイノリティ性をもつ性的マイノリティが向き合う差別について語りながらも他方で自身の「成功」について示すことや、「悲惨」なものとして語りうる物語をさまざまな工夫を通して「悲惨」な物語として語らないことなどの例がみられる。本研究はこれらの物語/語りのもつ意味や役割について考察した。
- 著者
- 原田 幹生 宇野 智洋 佐々木 淳也 村 成幸 高木 理彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本整形外科スポーツ医学会
- 雑誌
- 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 (ISSN:13408577)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.22-26, 2022 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 9
小中学野球選手の睡眠を調べ,肩肘痛や投球パフォーマンスとの関係を検討した.野球肘検診に参加した小中学野球選手80名を対象として,アンケートを用いて,投球時の肩肘痛,投球パフォーマンス(KJOCスコア),および睡眠を調べた.肩肘痛を41名(51%)に認め,KJOCスコアは平均91点(38~100)であった.肩肘痛は,睡眠の質がとても良い選手(29%)に比べ,それ以外の選手(63%)で有意に多かった(p<0.05).睡眠において,就眠中の寒さ暑さ,睡眠時間が7時間以内,眠気による授業の支障,および起床時のすっきり感がKJOCスコアの低下と関連していた(いずれもp<0.05).適切な睡眠により,肩肘痛の予防や投球パフォーマンス低下の予防に繋がる可能性がある.
- 著者
- 米原 善成
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2018-08-24
本研究では、アホウドリ類を対象として、ダイナミックソアリングと呼ばれる省エネルギーの滑空飛行法のメカニズムの解明を目標とした。ダイナミックソアリングとは、海上の風速勾配を利用して、羽ばたくことなく持続的に滑空飛行する飛行様式である。実際にダイナミックソアリングを行うアホウドリ類の飛行データを得るために、野外調査を実施した。2019年1月~4月にかけて、亜南極域クロゼ島で繁殖する世界最大の飛ぶ鳥であるワタリアホウドリに、3軸加速度、3軸角速度、GPS(位置と速度)、気圧を高解像度で記録できる装置を合計20台装着し、回収した。得られたデータから、状態空間モデルを用いて、アホウドリの3次元的な飛行経路や姿勢の変化を計算した。実データと比較するために、理論的なダイナミックソアリングによる飛行方法を数値計算によって求めた。滑空する鳥をグライダーに近似し、運動方程式に基づいた最適制御問題を解くことで、与えられた風速勾配のもとで理論的に最もエネルギー効率の良い飛び方を求めた。実際の海上では波や突風などによって時々刻々と風環境が変わると考えられる。風速勾配の形状を変化させると、それに応じて理論的に最適な飛行経路、姿勢の変化なども変わることがわかった。次年度は、アホウドリの3次元的な飛行経路や姿勢を飛行モデルと比較することで、エネルギー獲得メカニズムや異なる風環境に応じたアホウドリのダイナミックソアリングによる飛行戦略を研究する計画だったが、初年度で中断した。
3 0 0 0 OA 紙おむつ着用が幼児歩行に及ぼす影響
- 著者
- 須藤 元喜 上野 加奈子 大野 洋美 植田 章之 豊島 晴子 矢田 幸博
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.33-38, 2010-05-25 (Released:2017-07-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
Many infants wear paper diapers during the gait-forming period. We measured electromyography during walking in 10 infants under 3 conditions, and analyzed the motion: naked, wearing a paper diaper, and wearing a paper diaper containing physiological saline. The gait test was repeated in the same infants after 4 months to investigate changes in the influence of paper diapers. In the first test, the muscle burden was not significantly increased by wearing a paper diaper alone, but that on the biceps femoris was significantly increased by a paper diaper containing saline. In the second test 4 months later, the burden on the biceps femoris due to a paper diaper and that containing saline were significantly decreased. Motion analysis detected the minimum distance between the bilateral knees was significantly broadened when wearing a diaper containing saline in the second test.
3 0 0 0 立法情報 ロシア ゲイ・プロパガンダ禁止法の成立
- 著者
- 小泉 悠
- 出版者
- 国立国会図書館調査及び立法考査局
- 雑誌
- 外国の立法. 月刊版 : 立法情報・翻訳・解説
- 巻号頁・発行日
- no.256, pp.16-17, 2013-08
3 0 0 0 OA 社会性昆虫における繁殖制御の生理・分子メカニズム
- 著者
- 佐々木 謙
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.3-9, 2010 (Released:2011-04-27)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1
社会性昆虫に見られる成虫期の表現型多型はカーストと呼ばれ,繁殖や巣内の仕事の効率を高めるために進化した性質であると考えられている。カーストの形態分化は幼虫期の神経・内分泌系による作用と異なる遺伝子発現を通して起こる。近年,カースト間で異なる栄養代謝系の遺伝子発現に関する研究が進み,カースト特異的な内部・外部形態への分化が分子レベルで解明されつつある。非繁殖個体であるワーカーは,繁殖個体不在の条件下において,成虫期の外部形態を維持したまま,一部の内部器官や行動を可塑的に繁殖型に転換することができる。カーストの転換に伴う行動変化は脳の生理的変化の結果生じるが,その行動変化は脳の構造にまで影響を与え,最終的にはカーストに特殊化した脳をつくり出す可能性がある。このようなカースト分化や転換における基本的な生理・分子メカニズムは,多くの社会性をもつハチ目で共通していると考えられる。その一方で,社会性の進化の程度により,生殖腺刺激ホルモンの制御機構が種間で異なる例も見つかっている。本稿では,社会性昆虫における繁殖制御メカニズムを紹介するとともに,その内分泌メカニズムの進化についても議論したい。
3 0 0 0 OA 誰にも出来るパンの製造法
3 0 0 0 OA 研究室だより:電気通信大学 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 菅研究室
- 著者
- 菅 哲朗
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.4, pp.NL4_2, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)
3 0 0 0 OA 「一致」という用語にまつわる間題点とジェンドリンによる解決案
- 著者
- 田中 秀男
- 出版者
- 日本人間性心理学会
- 雑誌
- 人間性心理学研究 (ISSN:02894904)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.29-38, 2015-09-30
一般に、カール・ロジャーズは、ウィスコンシンでの統合失調症治療プロジェクトを経て、それまで以上にセラピストの「一致」した態度を重視するようになったと言われている。その一方、ユージン・ジェンドリンは、当プロジェクトの重要な論客であったにもかかわらず、「一致」という用語を使うことがごくまれである。本稿では、ジェンドリンが「一致」という用語にどのような間題点を感じ、解決を図ろうとしたのかを、彼の初期の主著『体験過程と意味の創造』の観点から解明する。この解決案により、フォーカシングにおける「ぴったり」という言葉を使う際に陥りがちな誤解を防ぐための留意点を提示する。
- 著者
- Kana Watanabe-Toma Jin Murata Tetsuo Ohi-Toma
- 出版者
- The Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.281-287, 2021-10-31 (Released:2021-11-27)
A new variety, Aristolochia kaempferi Willd. var. laevipes Watan.-Toma & Ohi-Toma (Aristolochiaceae), is described. The variety is distinguished from var. kaempferi by having glabrous pedicels. This new variety is disjunctly distributed in the Ise-Shima region of the Kii Peninsula and the northeastern part of the Owari region of central Honshu, Japan. Moreover, we newly confirmed the presence of A. kaempferi var. kaempferi in the central part of the Kii Peninsula and the Owari region based on flowering individuals in natural populations and in cultivation. Aristolochia kaempferi var. kaempferi and A. tanzawana were in proximity with A. kaempferi var. laevipes in the Owari region.
- 著者
- Koki Sugimoto Ryota Hosomi Takaki Shimono Seiji Kanda Toshimasa Nishiyama Munehiro Yoshida Kenji Fukunaga
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.7, pp.965-977, 2021 (Released:2021-07-01)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 2
Due to the growing demand of n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) as supplements and pharmaceutical products worldwide, there are concerns about the exhaustion of n-3 PUFA supply sources. We have successfully prepared high-quality scallop oil (SCO), containing high eicosapentaenoic acid and phospholipids contents, from the internal organs of the Japanese giant scallop (Patinopecten yessoensis), which is the largest unutilized marine resource in Japan. This study compared the cholesterol-lowering effect of SCO with fish oil (menhaden oil, MO) and krill oil (KO) in obese type II diabetic KK-A y mice. Four-week-old male KK-A y mice were divided into four groups; the control group was fed the AIN93G-modified high-fat (3 wt% soybean oil + 17 wt% lard) diet, and the other three groups (SCO, MO, and KO groups) were fed a high-fat diet, in which 7 wt% of the lard in the control diet was replaced with SCO, MO, or KO, respectively. After the mice were fed the experimental diet for 42 days, their serum, liver, and fecal lipid contents as well as their liver mRNA expression levels were evaluated. The SCO group had significantly decreased cholesterol levels in the serum and liver; this decrease was not observed in the MO and KO groups. The cholesterol-lowering effect of SCO was partly mediated by the enhancement of fecal total sterol excretion and expression of liver cholesterol 7α-hydroxylase, a rate-limiting enzyme for bile acid synthesis. These results indicate that dietary SCO exhibits serum and liver cholesterol-lowering effects that are not found in dietary MO and KO and can help prevent lifestyle-related diseases.
- 著者
- Yuya Matsuda Shunsaku Nakagawa Ikuko Yano Satohiro Masuda Satoshi Imai Atsushi Yonezawa Takashi Yamamoto Mitsuhiro Sugimoto Masahiro Tsuda Tetsunori Tsuzuki Tomohiro Omura Takayuki Nakagawa Toyofumi Fengshi Chen-Yoshikawa Miki Nagao Hiroshi Date Kazuo Matsubara
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.397-402, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3
Invasive Aspergillus infection is a major factor for poor prognosis in patients receiving lung transplantation (LT). An antifungal agent, itraconazole (ITCZ), that has antimicrobial activity against Aspergillus species, is used as a prophylactic agent against Aspergillus infection after LT. ITCZ and its metabolite, hydroxyitraconazole (OH-ITCZ), potently inhibit CYP3A and P-glycoprotein that metabolize or excrete calcineurin inhibitors (CNIs), which are the first-line immunosuppressants used after LT; thus, concomitant use of ITCZ and CNIs could induce an increase in the blood concentration of CNIs. However, no criteria for dose reduction of CNIs upon concomitant use with ITCZ in LT recipients have been defined. In this study, the effect of ITCZ and OH-ITCZ on the blood concentrations of two CNIs, tacrolimus and cyclosporine, after LT were retrospectively evaluated. A total of 39 patients who received LT were evaluated. Effects of ITCZ and OH-ITCZ on the concentration/dosage (C/D) ratio of tacrolimus and cyclosporine were analyzed using linear mixed-effects models. The plasma concentrations of OH-ITCZ were about 2.5-fold higher than those of ITCZ. Moreover, there was a significant correlation between the plasma concentrations of ITCZ and OH-ITCZ. Based on parameters obtained in the linear regression analysis, the C/D ratios of cyclosporine and tacrolimus increase by an average of 2.25- and 2.70-fold, respectively, when the total plasma concentration of ITCZ plus OH-ITCZ is 1000 ng/mL. In conclusion, the plasma levels of ITCZ and OH-ITCZ could be key factors in drawing up the criterion for dose reduction of CNIs.
- 著者
- 清水 右郷
- 出版者
- 一般社団法人日本リスク学会
- 雑誌
- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.111-121, 2019-10-25 (Released:2019-10-24)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
Philosophers of science have distinguished epistemic values from other values. The former are relevant to scientific evaluation, while the later are legitimate bases to address ethical, social, and political issues. Given such a classification, experts should normally respect both scientific rationality and ethical soundness. How about situations where these values are conflicting? If the priority of epistemic values could be a cause of ethical issues, what is right action? This is the central theme of the controversy over randomized controlled trial and clinical equipoise. From the existing literature on the controversy, I found out two types of strategies to resolve the dilemma. After looking into how epistemic values and ethical values relate in each strategy, I will make a few general suggestions about norms for scientific research.