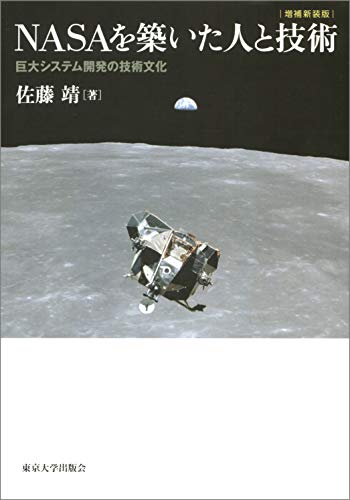3 0 0 0 NASAを築いた人と技術 : 巨大システム開発の技術文化
3 0 0 0 IR 水上勉文学における<環境の表象>の解体と構築―エコクリティシズムの観点から
- 著者
- 賀 樹紅 He Shuhong
- 出版者
- 金沢大学
- 巻号頁・発行日
- 2019
博士論文要旨Abstract
3 0 0 0 OA 羅城門渡辺綱鬼腕斬之図
3 0 0 0 人手評価を考慮した強化学習に基づくニュース見出し生成
3 0 0 0 OA 研究者教員と実務家教員の大学における役割と教師発達観
- 著者
- 姫野 完治 長谷川 哲也 益子 典文
- 出版者
- 日本教師学学会
- 雑誌
- 教師学研究 (ISSN:13497391)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.25-35, 2019 (Released:2019-07-08)
本研究は,今後の教員養成・採用・研修を担う教師教育者の在り方を検討する上で基盤となる教師教育者の職務内容や教師発達観等を解明することを目的とする。そのため,国立教員養成系大学・学部および大学院において教員養成に携わっている研究者教員と実務家教員を対象として質問紙調査を行い,学校等における勤務の「経験なし研究者教員」と「経験あり研究者教員」,そして「実務家教員」の3群に分けて比較検討した。その結果,相対的に「実務家教員」は教育にかける時間が多いこと,「実務家教員」は授業や他機関との連絡調整において研究者教員と連携していること,「研究者教員」と比べて「実務家教員」の職務内容や教師発達観には,同僚性やコミュニティとの関わりが反映されていること等が明らかになった。
3 0 0 0 OA 生体侵襲と好中球細胞死,そして細胞死による凝固・炎症の制御
- 著者
- 射場 敏明
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.1-7, 2017 (Released:2017-06-20)
- 参考文献数
- 28
生体侵襲に伴い,さまざまな種類の細胞において,いろいろな細胞死が誘導される.これらの細胞死が,侵襲の緩和やさらなる増幅にかかわっていることが知られるようになったのはごく最近のことである.細胞死形態についても,かつてはアポトーシスとネクローシスというシンプルな対立構図で理解されていたが,最近の研究では未知のものまで含めて多数の細胞死形態が存在していることが明らかにされており,パラダイムシフトが生じている.特に炎症の最前線で機能する好中球については,2004 年にneutrophil extracellular traps(NETs)放出を伴う新たな細胞死形態であるNETosis が報告され,近年注目を集めている.ここでは特に侵襲とそれに対する生体反応に深くかかわっている好中球の細胞死に関する最近の知見をまとめ,併せて生体侵襲や血液凝固との関連を解説する.
3 0 0 0 海洋情報業務用船 (海上保安庁船艇の全容)
3 0 0 0 OA 緑青 (塩基性炭酸銅) のラットによる急性及び慢性経口毒性試験
- 著者
- 落合 敏秋 臼井 章夫 松本 清司 関田 清司 内藤 克司 川崎 靖 降矢 強 戸部 満寿夫
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.6, pp.605-616_1, 1985-12-05 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 2
緑青の主成分とされる塩基性炭酸銅の急性及び慢性経口毒性試験をSlc: Wistarラットを用いて行った. 急性毒性試験で, LD50値は雄: 1350mg/kg, 雌: 1495mg/kgであった. 慢性試験では0, 70, 220, 670及び2000ppm塩基性炭酸銅添加固型飼料を12か月間投与した. 2000ppm群で体重増加抑制 (雄, 雌), 血清GOT,GPT, LDHの上昇が実験期間を通して観察された. 組織学的には, 雌雄2000ppm群で肝臓の単細胞壊死の発現数が有意に増加した. 以上, 塩基性炭酸銅の2000ppmはラットに肝臓障害を起こすものと結論された.
3 0 0 0 IR 博物館批判の論点に関する一考察 : 文化学習基盤としての博物館に向けて
- 著者
- 新藤 浩伸
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース内『生涯学習基盤経営研究』編集委員会
- 雑誌
- 生涯学習基盤経営研究 (ISSN:1342193X)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.17-31, 2011
日本において博物館は, 施設建設が一定の成果をみた現在, 財政難等の様々な課題に直面しつつも,制度改革の途上にある。しかし, 制度改革の途上にある現在だからこそ必要な「博物館とは何か」という根本的な問いは, 博物館学が多領域にわたることなどから十分とはいえない。これに対し本論では,第一に, 議論の前提として近年の博物館の現状および制度改正の動向を, 背景にある状況とともに概観する。第二に, 近代国家の機関としての博物館に向けられた批判の論点をふまえ, それにこたえていくにあたり,(1)公共施設としての意味, (2)コレクションと場所としての意味, (3)博物館において学ぶことの意味という観点から検討する。そして第三には, 近年の文化施設研究, および文化の視点からの教育学研究の検討を通して, 生涯学習社会における文化学習基盤としての博物館のあり方について展望的に考察する。論文/Theses
3 0 0 0 OA 動作行動開発のための物理エンジンSpringhead
- 著者
- 長谷川 晶一 三武 裕玄 田崎 勇一
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.9, pp.841-848, 2012 (Released:2012-12-15)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 5
3 0 0 0 バナー制作のための背景を考慮した自動テキスト配置
- 著者
- 大峠 和基 大谷 まゆ
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)
- 巻号頁・発行日
- 2020-04-01
3 0 0 0 IR 言語聴覚士 (国家資格) 誕生までの概略とその養成
- 著者
- 山口 富一
- 出版者
- 新潟医療福祉大学
- 雑誌
- 新潟医療福祉学会誌 (ISSN:13468774)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.36-42, 2005-03-14
言語聴覚士 (ST) の分野である聴覚障害 (児) 者に対することばの指導やコミュニケーション方法獲得に対する取り組みは古くから行われてきている。国内外の取り組みの歴史と専門職としての言語聴覚士誕生の経緯と、日本における言語聴覚士の国家資格制度が遅れたいきさつを年代を追って、関係諸団体の主張と対立・意見調整の過程を振り返る。言語聴覚士の活躍する多様な職場と多様な養成機関の並存という現状を踏まえての養成が必要と考える。
3 0 0 0 OA ボードリヤール『消費社会の神話と構造』邦訳の回想
- 著者
- 塚原 史
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 人文論集 (ISSN:04414225)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.39-55, 2016-02-20
3 0 0 0 OA 構造色によるカラーリング
- 著者
- 石崎 貴裕
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.11, pp.747, 2010-11-01 (Released:2011-05-31)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 吉田 和枝 谷川 町子 大西 君枝
- 出版者
- 日本看護協会出版会
- 雑誌
- 日本看護学会論文集 地域看護 (ISSN:13478257)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.6-8, 2006
3 0 0 0 OA in vitroにおける重炭酸イオンがエナメル質および象牙質の再石灰化に及ぼす影響
- 著者
- 田中 景子 飯島 洋一 高木 興氏
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.215-221, 1999-04-30 (Released:2017-11-11)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
エナメル質ならびに象牙質の脱灰病変に,重炭酸イオンを作用させることによって,再石灰化の過程にどのような影響を及ぼすかをin vitroで検討した。試料には50歳代の健全小臼歯を用いた。脱灰は0.1M乳酸緩衝液(Ca 3.0mM, P 1.8mM, pH 5.0)で7日間行い,続いて再石灰化溶液(Ca 3.0mM, P 1.8mM, F 2ppm,pH 7.0)に7日間浸漬した。この再石灰化期間中,8時間ごとに再石灰化溶液から取り出し,30分間,4種の異なった重炭酸イオン溶液(0.0, 0.5, 5.0, 5O.OmM)に浸漬した。薄切平行切片を作成し,マイクロラジオグラフによってミネラルの沈着を評価した。エナメル質では重炭酸イオン濃度の増加に伴って,病変内部に再石灰化が発現する傾向が認められたが,統計学的な有意差はなかった(p=0.09)。一方,象牙質では表層に限局した再石灰化が認められた。特に5.0mM群では著明であったが,エナメル質と同様,統計学的な有意差は認められなかった(p=0.08)。エナメル質と象牙質で異なる再石灰化の所見が発現した理由は,重炭酸イオンの浸透性の違いによるものであると推察される。
- 著者
- Akihiko Nakamura Kei-ichi Okazaki Tadaomi Furuta Minoru Sakurai Jun Ando Ryota Iino
- 出版者
- The Biophysical Society of Japan
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- pp.BSJ-2020004, (Released:2020-06-09)
- 被引用文献数
- 5