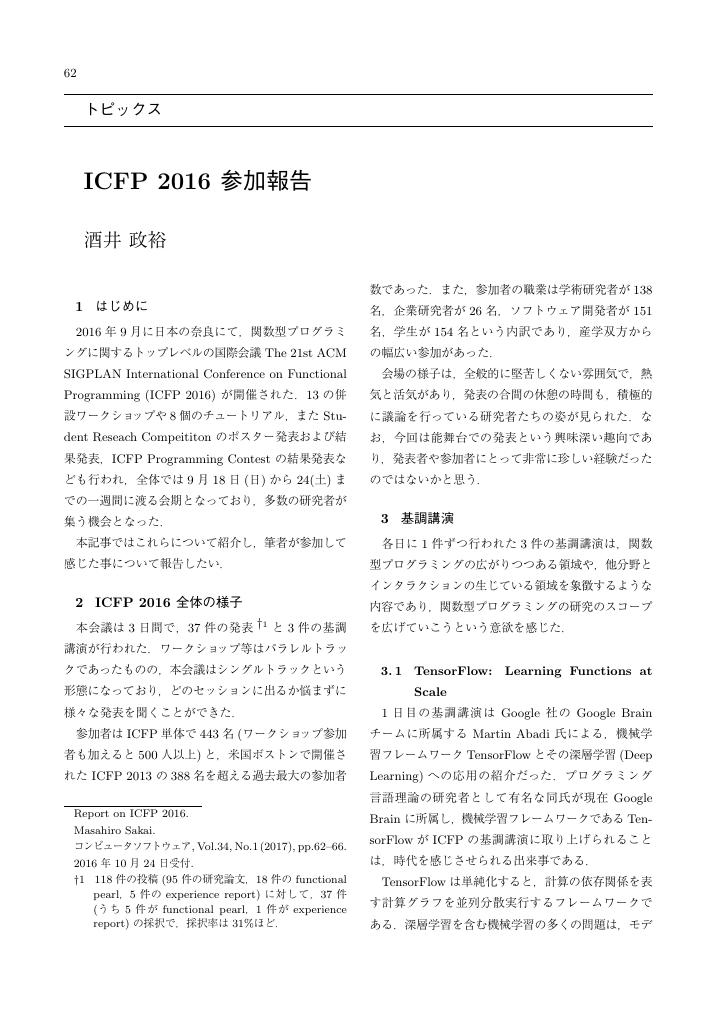- 著者
- 沓脱 和人 今井 和昌
- 出版者
- 参議院事務局
- 雑誌
- 立法と調査 (ISSN:09151338)
- 巻号頁・発行日
- no.349, pp.72-88, 2014-02
- 著者
- 防衛省防衛力の実効性向上のための構造改革推進委員会
- 出版者
- 自由民主党資料頒布会
- 雑誌
- 政策特報
- 巻号頁・発行日
- no.1388, pp.8-110, 2011-11-01
3 0 0 0 基盤的防衛力構想と動的防衛力
- 著者
- 戸蒔 仁司
- 出版者
- 北九州市立大学
- 雑誌
- 基盤教育センター紀要 (ISSN:18836739)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.15-94, 2011-03
3 0 0 0 IR 中世日本に於ける四書の受容と学風の転換
- 著者
- 楊 洋
- 出版者
- Kyoto University (京都大学)
- 巻号頁・発行日
- 2016
文博第722号
3 0 0 0 IR 倉橋由美子文学における女性像および女性論についての研究
- 出版者
- 九州大学
- 巻号頁・発行日
- 2016
元資料の権利情報 : Fulltext available.
- 著者
- 頼経 かをる 永山 くに子
- 出版者
- 日本母性衛生学会
- 雑誌
- 母性衛生 (ISSN:03881512)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.120-128, 2011-04
<目的>生後3ヵ月間における乳児の泣きをめぐる母親の体験を記述すること。<方法>初産婦1名の語りからナラティブ・アプローチを活用し質的記述的に分析を行った。データ収集は生後2週間,1ヵ月半,3ヵ月前後に半構成面接と参加観察を行った。<結果・考察>【泣きへの戸惑い】【乳児の欲求・感情の汲み取り】【泣きへの対処】【泣きの特徴をつかむ】【泣きやまないことへの自分なりの解釈】【泣きに対する余裕の自覚】【乳児の成長・発達への気づき】【自分の欲求や否定的感情との葛藤】の8つのカテゴリーを抽出した。そして,3ヵ月間の乳児の泣きをめぐる母親の体験を1つの物語として記すことを試みた。そのなかでは,母親は乳児の泣きに対し混乱や葛藤を抱えつつも,乳児の要求に応えようとさまざまな対応を試みながら母子相互に成長していく過程がみられた。
- 著者
- 川瀬 綾子 森 美由紀 北 克一
- 雑誌
- 情報学 (ISSN:13494511)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.82-92, 2016
3 0 0 0 IR 地域包括支援センター職員の専門性と実用的スキルに関する考察
- 著者
- 田中 八州夫
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 同志社政策科学研究 (ISSN:18808336)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.139-153, 2012-03
- 被引用文献数
- 1
研究ノート(Note)地域包括ケア研究会2009年度報告書において公表された「地域包括ケアシステム」は、医療・介護・予防・生活支援・すまいの5つを軸とした社会資源を活用することにより、高齢者が安心して住み続けることのできる地域をつくることを目標としている。この地域包括ケアシステムは、第5期介護保険事業計画のグランドデザインとして位置づけられ、システムを推進する中心的な役割を果たすのが地域包括支援センターである。本論文では、地域包括支援センターのおもな業務である「介護予防支援」「総合相談」「虐待防止・権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント」のうち、地域包括ケアシステムにおける「総合相談」の重要性を明確にする。そして、地域包括支援センターの運営形態及び地域包括支援センターを構成する「保健師」「社会福祉士」「主任ケアマネジャー」の3職種の現状と課題を明らかにする。そしてその課題に対し、運営形態に関する改善策及び今後地域包括支援センターの職員に必要とされる資質・スキルについて検討していく。
- 著者
- 小出 晃 佐藤 一雄 田中 伸司 加藤 重雄
- 出版者
- 公益社団法人精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.547-551, 1995-04-05
- 被引用文献数
- 1 8
The use of hemispherical concave specimen is proposed to evaluate orientation-dependent etch rate of single crystal silicon. Etch rate is calculated from dimensional change of the hemisphere during etching. Etch rate distribution to the total orientation has been obtained for the etchant of 40wt%KOH aqua solution. The orientation showing maximum etch rate was [110] at 40°C. It deviates from [110] with an increase of temperature. The maximum point seems to move toward [320]. This fact indicates that the etched profile varies with etching temperature even when the etchant and the initial masking pattern are the same. The effect of temperature on the etch profile is experimentally proved. Variation in etch profile according to the change in temperature is theoretically explained by the etch rate data.
3 0 0 0 OA ICFP 2016参加報告
- 著者
- 酒井 政裕
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.1_62-1_66, 2017-01-25 (Released:2017-03-25)
- 著者
- Camilo Barrios-Perez Julian Ramires-Villegas Alexandre Bryan Heinemann
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会講演会要旨集 第243回日本作物学会講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.119, 2016 (Released:2017-03-27)
3 0 0 0 OA 貨幣価値変動会計の研究
- 著者
- 高橋 豊蔵
- 出版者
- 大東文化大学
- 雑誌
- Research papers
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-29, 1986-11-15
1. 序論 この小論は, イギリスおよびアメリカにおける貨弊価値変動会計についてとりあげたものである。2. イギリスにおける貨幣価値変動会計2. a第二次世界大戦後のインフレーション会計イギリスにおいては、第一次世界大戦 (1914〜1918) 後はドイツ フランスアメリカの場合と異なり物価指数は上昇したものの1920年を頂点として急速に下落しはじめ1932年には戦前を下まわったためインフレーションに関する文献もあらわれなかった。しかし、第二次世界大戦 (1939-1945) 後は, インフレーションの影響を大きく受けたためインフレーション会計の多くの文献をみることとなった。それは次のごとくである。1945年の所得税法ICAEW (The Institute of Charterd Accountant in England and Wales) の勧告書12号 (1949) ICAEWの勧告書第15号 (1952年) これらの共通点は固定資産と棚卸資産をその中心に置いている点にある。ACCA (The Association of Certified and Corporate Accountants) の「貨弊購買力の変動と会計 (1952)」では取替価格についてとりあげている。2. bサンデランズ, レポート (1975) 本報告書においてはカレントコスト会計を提唱し, 一般物価変動会計を否定したことから、イギリスのインフレーション会計の基本方向は一転することとなった。2. c現在原価会計 これを計算例によって示したのが現在原価会計でサンデランズレポート第12章と第13章によっている。その後1976年に組織されたモーペス・グループのED (exposure draft) 18号の発表とそれに対する批判, ついで会計基準報告委員会は (1) ハイド委員会による簡潔な暫定ガイドライン (1978年から上場会社に適用) と (2) モーペス・グループによるかなり簡素化し、また公表物価指数の使用と従来の財務諸表を重視する改定恒久基準 (1979年から大企業に適用) の2本立で臨んでおり、この両方式のカレント・コストによる修正は (1) 減価償却と (2)在庫評価格益の2項目に限り, さらに (3) の貨幣項目の修正は議論の余地があるというのが実情のようであり, この (3) についての結論がでるのには多くの時間を要することが予想される。3. アメリカにおける貨幣価値変動会計3. aインフレーション会計の現状アメリカのインフレーション会計研究の展開過程は2つの系譜に分けられる。第1の系譜は3bでとりあげる一般購買力修正会計であり, 第2の系譜は, 3cでとりあげる取替原価会計である。3. b一般購買力修正会計 イギリスのインフレーション会計については第一次世界大戦 (1914〜1918年) 後には文献にみるべきものがなかったが, アメリカにおいてはスウイニーによる研究が1927年以降, 多くの諸論文となって示された。そして1936年にこれらの成果をまとめた Stabilized Accounting として発表されたのである。スウイニーはアメリカにおけるインフレーション下において名目貨幣計算がもたらす経済的矛盾によって生じた計算的混乱を避けるため, 企業は一般購売力の維持とその拡大を図るため, 一般物価指数を安定物価基準にとって貨幣価値変動を考慮した場合の純損益を計算し, もって経営の指針とすべきだとしたのである。しかし, スウイニーの研究は当時引続き試みられなかった。だが1974年に至ってFASBC (財務会計基準審議会) が, 「一般購買力単位による財務報告」を発表したのを始めとした諸論文によって, 一般購買力単位による会計情報が実際に適用される段階に進むかにみられていたのである。3. c取替原価会計 第2の系譜である取替原価会計についてはE.O.エドワーズとP.W.ベルによる「意志決定と利潤計算」(1961年) がまずあげられるが, 1976年3月に, SEC (証券取引委員会) は会計連続通牒190号で、同年12月25日以降に終了する事業年度から一定の規模の企業に対し, 特定項目の取替原価法の開示を義務づけた。したがって取替原価会計が, SECが取替原価に関する情報を一部の特定項目に限定しているが開示させる方向に動いたことは, SECがこれまで取得原価主義会計を制度的に実施してきただけに, アメリカの公表財務諸表制度がこれを契機として転換する可能性を示唆しているかにみえる。
3 0 0 0 OA 女性の雑誌愛読傾向のネットワーク図化
- 著者
- 新藤 透 津谷 篤 伴 浩美
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.409-417, 2015 (Released:2015-08-28)
- 参考文献数
- 21
This paper discusses the changes of magazines which women read according to the age using figures of the network, which we got from the answers to questionnaire of women's junior college students. The link of the network expresses frequent combinations of magazines read in the same period or frequent changes of magazines which women read. This paper covers fashion magazines, comic magazines and animation magazines. At first, it is found that the combination of magazines with a similar property are read in the same period. Next, changes of magazines which women read is clarified. 51.22%, 28.66%, and 19.51% of the college students read “Chao,” “Ribon,” and “Nakayoshi” in their childhood, respectively. Readers of “Chao” and those of “Ribbon” come to read fashion magazines or boys' comics for teenagers, and then street fashion or girly fashion magazines. “Nakayoshi” readers, however, tend to continue reading comic magazines sequentially.
3 0 0 0 OA 世代交替を迎えるインドネシア仏教界 : アシン・ジナラッキタ師の葬儀に参列して
- 著者
- 木村 文輝
- 出版者
- 愛知学院大学
- 雑誌
- 禅研究所紀要 (ISSN:02859068)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.139-162, 2003-03-31
- 著者
- 黒木 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, 2013
- 著者
- 長谷中 崇志 高瀬 慎二
- 出版者
- 名古屋柳城短期大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:13427997)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.101-108, 2014-12-20
本研究では、地域福祉計画の評価指標の開発にむけた基礎的分析として、A市における調査データを基に、ソーシャル・キャピタルと社会経済的地位(所得・学歴)を取り上げ、それらと身体的・精神的健康度や幸福度との関連を明らかにすることを目的とする。今回の分析では、健康の指標として、国内外の多くの先行研究において生命予後や日常生活動作能力(ADL)予後の予測妥当性が示されている「主観的健康感」に焦点をあてて検証した。その結果、以下の3点の知見が得られた。(1)ソーシャル・キャピタルの構成要素である「信頼」が健康と関連していること。(2)所得が多いほど、幸福感が高く、主観的な健康度も高く評定される傾向にあり、所得の格差が個人の幸福感や主観的な健康感にも影響している可能性が示唆されたこと。(3)学歴が長くなるほど、主観的な健康度は高くなるが、精神的疲労・ストレスも高くなる傾向にあること。