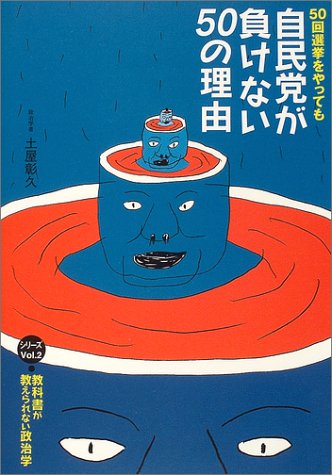2 0 0 0 OA 現代社会における科学的主張を読み解く科学メディアリテラシーを育成する教育実践
- 著者
- 松峯 笑子 舟生 日出男 鈴木 栄幸 久保田 善彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.103-108, 2021-12-19 (Released:2022-01-20)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
我々の身の回りは科学に関連する情報で溢れているが,全ての科学情報が正しいとは限らない.より良い意思決定のためには,科学ニュースを正確に読み取る科学メディアリテラシーが必要であるが,未だ注目されていない.それを受けて筆者らは,「科学メディアリテラシーを俯瞰するチェックリスト」を活用した教育実践をデザインし,少人数を対象として試験的に実施した.そこで挙がった改善点から,今回より多くの学生を対象として,チェックリストが科学ニュースの評価に与える影響を確かめた.実践の結果,チェックリストが,科学ニュースを評価する際の批判的視点を持つ指標となり,科学ニュースの評価に影響を与えることが分かった.また,科学やメディアの認識が低く,事例を肯定的に捉える学生がチェックリストを使用したタイミングで批判的視点を持っていたことから,科学ニュースを正確に読み取るために必要な認識の補助的な役割を果たしていると考えられる.
2 0 0 0 通貨原理の研究
- 著者
- トマス・トゥィク 著
- 出版者
- 日本評論社
- 巻号頁・発行日
- 1948
2 0 0 0 IR 17世紀における印刷術の発展とフランス食文化
- 著者
- 松本 孝徳 持田 明子
- 出版者
- 九州産業大学国際文化学会
- 雑誌
- 九州産業大学国際文化学部紀要 (ISSN:13409425)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.81-105, 2004-03
2 0 0 0 OA RS ウイルス感染に伴う小児急性中耳炎の臨床像
- 著者
- 臼井 智子 増田 佐和子
- 出版者
- 日本小児耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.17-22, 2012 (Released:2012-12-28)
- 参考文献数
- 8
RSV 感染症により入院治療を行った24例のうち,急性中耳炎を合併した18児を対象とし,年齢,重症度,臨床症状,鼓膜所見,検出菌や治療,経過を検討した。RSV 感染に合併した急性中耳炎児の初診時月齢は,0 ヵ月から 3 歳 5 ヵ月,平均12.3ヵ月,中央値11.5ヵ月であった。2 歳以上に比べ 2 歳未満で有意に中耳炎の合併率が高く,軽症は 7 例,中等症は 3 例,重症は 8 例であった。抗菌薬投与や鼓膜切開術を行わずに急性中耳炎が治癒したものは 2 例のみであり,軽症,中等症の 4 例で翌日に増悪を認め,そのうち 1 例は治癒後にも再燃を認めた。上咽頭からは12例,中耳貯留液からは 1 例で細菌が検出されており,重症度や経過との関連は認められなかった。細気管支炎により入院での全身管理を要する RSV 感染は低年齢児に多い。中耳炎を認めた場合,翌日に悪化することもあるため,軽症であっても連日の注意深い観察と小児科医との連携が必要であると考えられた。
2 0 0 0 OA XTetraの開発と授業実践による評価
- 著者
- 大門 巧 大西 建輔 青山 浩
- 雑誌
- 情報教育シンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, pp.216-223, 2021-08-21
我々は,DNCL のブラウザ上での実行環境として Tetra を開発したが,高等学校での授業で使用するためには,機能の充実を図ることが必要であった.そこで,Tetra を改良した DNCL のブラウザ上での実行環境である XTetra を開発した.XTetra には,従来の Tetra の機能に加え,コンソールからの標準入力,描画関数,エディタのシンタックスハイライト機能が実装されている.高等学校において,Scratch の使用経験のあるクラスと,使用経験のほとんどないクラスで XTetra を用いた授業を実施し,アンケートを用いて処理系の評価をおこなった.その結果,Scratch の使用経験のあるクラスの理解度が使用経験のないクラスと比較して高くなった.また,XTetra はビジュアルプログラミング言語の要素とテキストベースのプログラミング言語の要素の両方を備えているため,ビジュアルプログラミング言語でのプログラミング経験のある生徒の理解を高める効果が期待できるという仮説が立った.
2 0 0 0 OA E..M.シオランについて
- 著者
- 山中 哲夫
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学 (ISSN:13414615)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.97-103, 1998-03-02
2 0 0 0 OA 医療・工業分野での放射線計測
- 著者
- 黒澤 忠弘
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.8, pp.509-513, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 12
放射線は,その特性を生かしてさまざまな分野で活用されています.特に放射線治療や診断といった医療分野,また非破壊検査や滅菌といった工業分野で幅広く利用されています.これら放射線の利用においては,放射線の発生源のみならず,放射線の計測技術も重要な要素となっています.本稿では,医療,工業分野における放射線利用の現状や将来の展望,またそれぞれに必要となってくる放射線計測について紹介したいと思います.
2 0 0 0 OA ごんはなぜ言葉を話すのか? : 「歴史を哲学する」ことで「ごんぎつね」を読みなおす
- 著者
- 渡辺 哲男
- 出版者
- 滋賀大学教育学部
- 雑誌
- 滋賀大学教育学部紀要, Ⅱ, 人文科学・社会科学 (ISSN:13429264)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.29-40, 2011
- 著者
- 谷 修祐 小嶋 光明 小野 孝二 伴 信彦 甲斐 倫明
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第54回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.249, 2011 (Released:2011-12-20)
放射線によって引き起こされるC3H/HeNマウスの急性骨髄性白血病(Acute Myeloid Leukemia: AML)は、低線量でのヒトの白血病リスクを考える上で重要な実験モデルである。AMLを起こしたマウスの造血幹細胞では2番染色体の欠損およびその染色体に存在するSfpi1遺伝子の突然変異が確認されており、これらは骨髄の分化に重要な役割を持つPU.1の転写を抑制してAMLの発症に至ることが考えられている。しかし、AMLにおけるSfpi1遺伝子の突然変異について、ほとんどは点突然変異に起因し、その主な変異であるC:GからT:Aへのトランジションは自然突然変異によって生じるため、放射線によって発症する白血病のリスクを考えるためには2番染色体の欠損以外に放射線が自然突然変異率への影響を考慮する必要がある。自然突然変異は細胞が分裂する際に低確率で生じるものであるため、造血幹細胞を頂点とした各造血細胞の動態、および放射線の影響によってその動態がどのように変化するかを考慮することが重要である。本研究ではC3H/HeNマウスを用いた放射線照射実験より得られた造血幹細胞そして前駆細胞の分化、分裂のパラメータを元に、造血組織の各種動態を数理モデルで表し、各細胞数の時間的変化、およびその分裂回数をシミュレーションによる計算で求めた。また、Sfpi1遺伝子の自然突然変異確率に着目し、シミュレーションで得られた結果をもとに放射線によるマウスAML発症リスクを計算し、実験データと比較したので報告する。
2 0 0 0 OA イプセン作『人民の敵』(En folkefiende) : 異文化社会学的視点(inter-socio-cultural perspective) (成城学園創立100周年記念号)
- 著者
- 毛利 三彌
- 出版者
- 成城大学文芸学部
- 雑誌
- 成城文藝 = The Seijo Bungei : the Seijo University arts and literature quarterly (ISSN:02865718)
- 巻号頁・発行日
- no.240, pp.103-139, 2017-06
2 0 0 0 OA 八戸市民の毛髪中水銀濃度と魚介類摂取について
- 著者
- 吉田 稔 久保 涼子 三迫 智佳子 鈴木 志乃舞 工藤 綾香 蜂谷 紀之 安武 章
- 出版者
- 一般社団法人 日本微量元素学会
- 雑誌
- Biomedical Research on Trace Elements (ISSN:0916717X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.170-175, 2013 (Released:2013-10-29)
- 参考文献数
- 13
This survey aimed to determine the levels of mercury in the scalp hair of residents of Hachinohe City in relation to their fish/seafood consumption to assess the risk of methylmercury exposure among the population. A total of 363 individuals (73 males and 290 females) residing in Hachinohe City (Aomori, Japan) provided scalp hair samples and completed a questionnaire. The geometric mean levels of mercury in the scalp hair were 2.52 and 1.91 μg/g in males and females, respectively, and 1.36 μg/g in females aged 15-49 years (n=80). The percentage of females of this generation with a hair mercury level above 2.2 μg/g (corresponding to the WHO's provisional tolerable weekly intake for methylmercury) was 21%, which was lower than the mean of 25% for residents of 10 regions across Japan. The Hachinohe residents consumed a mean of 108 g/day of fish/seafood (which was higher than the mean of 80.2 g/day for the overall Japanese population), consisting mainly of salmon, squid, mackerel, saury, and Atka mackerel. These results demonstrated that the hair mercury level of the residents of Hachinohe City was not so high as the higher consumption of fish/seafood compared with the national average, indicating that the risk of methylmercury exposure through increased fish/seafood consumption among Hachinohe City residents is not particularly high compared with the national level.
- 著者
- 熊谷,明泰
- 出版者
- 環日本海学会編集委員会
- 雑誌
- 環日本海研究
- 巻号頁・発行日
- no.7, 2001-11-05
2 0 0 0 なんでもわかる将棋宝典
2 0 0 0 50回選挙をやっても自民党が負けない50の理由
- 著者
- 吉田 航太
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.385-403, 2018 (Released:2019-05-12)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
本論文は、インドネシア東ジャワ州スラバヤ市で日本人技術者が開発した廃棄物堆肥化技術の事例を通じて、インフラ/バウンダリーオブジェクトというテクノロジーの二つのモードの差異を明らかにするものである。スーザン・L・スターのインフラストラクチャーの議論はバウンダリーオブジェクト論と連続性があり、前者は後者の発展型とされる。しかし、両者の間には解釈の対象としての象徴と、実践の対象としての道具という断絶が存在しており、インドネシアでの開発事業で 新たに誕生した生ゴミ堆肥化技術の事例の分析からこのことを明らかにする。スハルト政権崩壊後に発生した埋立処分場の反対運動をきっかけに、スラバヤ市は深刻なゴミ問題に悩まされた。これに取り組む開発プロジェクトが開始され、日本人技術者が開発したコンポスト手法がひとつのテクノロジーとして結実するに至った。このテクノロジーはスムーズに開発に成功したが、その後のインフラ化で困難に直面している。この事例から、スター的な協働のネットワークが長期の時間性に耐えなければならないという問題を抱えていること、テクノロジーが確固とした象徴的価値を獲得しなければならないことを議論する。
2 0 0 0 OA 昭和57年8月三重県中南勢 (嬉野町, 美杉村) 災害
- 著者
- 田中 義紘 内山 敦史
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.89-91_2, 1998-01-15 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 ロシア文化研究
- 著者
- 早稲田大学ロシア文学会 編
- 出版者
- 早稲田大学ロシア文学会
- 巻号頁・発行日
- no.7, 2000-03
2 0 0 0 OA 関西縄文社会の地域的特色とその背景
- 著者
- 瀬口 眞司
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.208, pp.191-213, 2018-03-09
関西地方の縄文社会の地域的特色,それを醸し出した要因や背景を問うた。議論のポイントは,〈資源の収穫期間の長さ〉と〈資源利用の方向性と強化の程度〉である。そこで,出土堅果類,打製石斧数,磨製石斧数,堅果類貯蔵量の数量的分析などを行った。結果,東日本に比べ,遺跡出土の堅果類はより多様で,収穫期間もより長く,集約的な労働編成の必要性が低かった可能性を改めて見いだした。また,土地・森林の開発強化には消極的で,資源利用の強化の程度も低く抑えられていたことも見いだせた。関西縄文社会の集団規模は極小さく,求心的な社会構造も生まれていないが,それは資源環境が貧しいからではなく,集団の求心性よりも世帯の自律性が優先され続け,社会の階層化や財・権力の集中にブレーキをかける仕組みが保持されていたからであり,収穫期間がより長い森林資源環境が,その地域的特色の維持を支えていたと考えられる。
2 0 0 0 OA 有尾両生類における種分化と種間干渉:種の形成とその維持機構の解明に向けて
- 著者
- 吉川 夏彦
- 出版者
- 独立行政法人国立科学博物館
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-01
日本産ハコネサンショウウオ属を対象として日本列島の有尾両生類の種分化及びその維持機構の解明を目指して研究を行った。ハコネサンショウウオ属の複数種で共通して使用可能なマイクロサテライトマーカー18遺伝子座を開発した。東北本州からは本属の2新種(バンダイハコネサンショウウオ、タダミハコネサンショウウオ)を記載し、分類学的整理を行った。東北地方南部に分布する4種の分布境界・同所的分布域で集団遺伝構造を調査し、本属の種分化と二次的接触、およびその後の種間関係について調査を行い、系統地理学的な考察を行った。