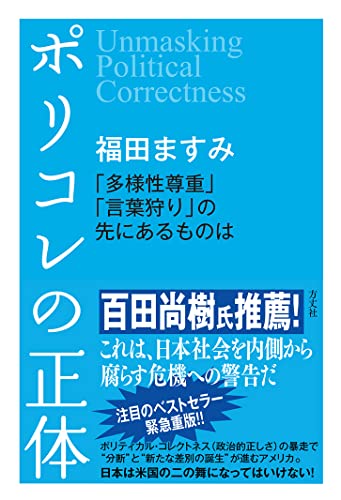2 0 0 0 OA 凝着説に基づく物体表面の弾性変形を考慮した摩擦音の生成手法の提案
- 著者
- 中塚 貴之 森島 繁生
- 雑誌
- 第78回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.1, pp.187-188, 2016-03-10
CG映像における効果音の多くは実際の音を録音したものが使用されている. しかし, 実録に基づく効果音の作成には多くの労力を要するため, シミュレーション環境下で効果音を生成することに対する需要は高い. 本研究では, 効果音の中でも身近な摩擦音を物体の運動シミュレーションに基づいて生成することを目的とする. 提案手法では,近似モデルを用いて物体表面が他物体と接触する時に生じる弾性変形を表現する.弾性変形によって物体表面の振動が形成する音圧分布の空間伝播に基づき摩擦音を生成する.さらに, 近似モデルのパラメタを調整することにより, CG映像の見た目の印象に合致した摩擦音の生成を可能とする.
2 0 0 0 OA 無産階級の画家ゲオルゲ・グロッス
2 0 0 0 OA 大脳皮質パルブアルブミン陽性ニューロンと統合失調症の認知機能障害
- 著者
- 橋本 隆紀 金田 礼三 坪本 真
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.32-40, 2017 (Released:2018-10-22)
- 参考文献数
- 58
統合失調症では,作業記憶,学習,知覚情報処理などの認知機能障害が持続し,予後に大きな影響を与えている。認知機能は,大脳皮質の複数の領域を含む神経ネットワークにおける情報処理とその可塑性により担われている。大脳皮質では,離れた領域間を連絡する興奮性の錐体ニューロンと,領域局所のニューロン活動を調整する抑制性ニューロンが,シナプスを介して神経ネットワークを構成する。パルブアルブミン(parvalbumin,PV)を発現するPVニューロンは,抑制性ニューロンのサブタイプである。個々のPVニューロンは,近傍および離れた領域にある多くの錐体ニューロンから収束的に興奮性シナプスを受け,近傍の数百に上る錐体ニューロンの細胞体に強力な抑制性シナプスを形成しそれらの発火のタイミングを制御する。また,お互いに抑制性シナプスを形成するPVニューロン群は周期的に同期発火する。このような特性により,PVニューロンは周期性を持った神経活動(オシレーション)の形成とその領域間の同期を担っている。オシレーションは神経ネットワークを構成する各領域および領域間における効率的な情報処理を促進する。さらに発達期や学習において,PVニューロンはその活動性を一過性に低下させることで,神経ネットワークを脱抑制し可塑的変化を誘導する。 統合失調症では,死後脳の分子病理学的研究によりPVニューロンの変化を示す所見が多く得られ,生存中の患者から得られるオシレーションの異常所見と一致する。PVニューロンの変化がオシレーションの異常を引き起こし認知機能障害に結びついている可能性は,統合失調症と同様の変化をPVニューロンに遺伝子操作で導入した複数のマウスモデルで検証されている。
2 0 0 0 OA 牛乳アレルギー患者におけるカゼイン,βラクトグロブリン感作に関する研究
- 著者
- 中野 泰至 下条 直樹 森田 慶紀 有馬 孝恭 冨板 美奈子 河野 陽一
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.117-122, 2010-02-28 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
【目的・方法】今回小児牛乳アレルギー患者における主要アレルゲンを明らかにすることを目的として後方視的な解析を行った.牛乳特異IgE値陽性で牛乳摂取により何らかの即時型症状を呈した115名の患者を対象としてBLG,カゼインに対する感作率を解析した.特異IgEがクラス2以上を陽性とした.また牛乳アレルギーの主要抗原と他の食物アレルゲン,吸入抗原への感作の違い,寛解との関連についても解析を行った.【結果】牛乳特異IgE値がもっとも高値であった血清でのカゼイン特異IgE値は,BLG特異IgE値よりも有意に高値であった.カゼイン特異IgE陽性者は107人(97.3%),BLG特異IgE陽性者は51人(46.4%),両方とも陽性だった者は48人(43.6%)であり,カゼイン単独感作群(C群)とカゼイン,BLG両方感作群(C/B群)に大別された.C群とC/B群での鶏卵への感作率を比較すると,C群とC/B群では差がなかったが,特異IgE値はC/B群の方が有意に高かった.吸入抗原に関しては両群で感作率,特異IgE値ともに差は認められなかった.C群に比べてC/B群は,3歳の時点での牛乳アレルギーの寛解が有意に少なかった.【結語】今回の解析から,本邦の牛乳アレルギーにおいても主要アレルゲンはBLGよりもむしろカゼインであると考えられた.複数の牛乳アレルゲン感作は,経消化管感作の起こりやすさを反映する可能性が考えられた.また複数の牛乳アレルゲンへの感作は牛乳アレルギーの寛解のしづらさとも関与していると考えられた.
- 著者
- 小嶋 文 久保田 尚
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.869-879, 2008-09-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 5 6
本研究では、参加に積極的な住民であれば、自らの手で身近な交通環境を改善することのできる対策として、「抜け道MM」を提案した.車利用者に自発的な交通行動の変化を期待するモビリティ・マネジメント (MM) の手法を援用し、社会心理学の要素を取入れたコミュニケーション技術を用いて、住民から自ら抜け道利用ドライバーに生活道路の通行をやめるよう訴える実験を行った。実験実施後の交通調査からは、実験後1ヶ月に渡って交通量に約1割の削減が見られた。意識調査の結果からは、本実験が抜け道利用者の迷惑の自覚を高めた結果が見られた。また、-参加しない住民からの反対は見られず、意欲のある住民には取組みやすい対策と考えられた。
- 著者
- 髙丘 有季乃 湯地 宏樹 Yukino TAKAOKA Hiroki YUJI
- 出版者
- 鳴門教育大学地域連携センター
- 雑誌
- 鳴門教育大学学校教育研究紀要 = Bulletin of Center for Collaboration in Community Naruto University of Education (ISSN:18806864)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.129-136, 2022-02
保育においては,子どもの評価のためにドキュメンテーションなどの記録をとることが求められている。本研究は,保育者にインタビュー調査を行い,テキストマイニング分析によって,保育者のドキュメンテーションや子どもの評価に対する考えの特徴を明らかにするものである。インタビューのデータをKHCoderを用いて分析した結果,階層的クラスターによって10個の特徴に分類された。子どもの姿の振り返りの手立てとして記録を工夫していること,家庭との連携や小学校の先生との共有手段としていることなどが明らかになった。これらの結果を踏まえ,保育現場で有効なドキュメンテーションの開発に役立てたい。
2 0 0 0 OA 保育者や教員志望学生の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の評価に関する研究
- 著者
- 湯地 宏樹 髙丘 有季乃 湯地 由美 Hiroki YUJI Yukiko TAKAOKA Yumi YUJI
- 出版者
- 鳴門教育大学
- 雑誌
- 鳴門教育大学研究紀要 = Research bulletin of Naruto University of Education (ISSN:18807194)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.313-326, 2022-03-31
The purpose of this study is to clarify how childcare teachers and students at teacher education universities evaluate the “Ideal Image by the End of Childhood,” “qualities and abilities,” “proactive and dialogic deep learning,” and the “five areas” in the National Curriculum Standard for Kindergartens after watching videos of kindergarten children. The study showed a significant difference in the evaluations by teachers and students, but no significant difference in evaluations by teachers at kindergartens, nursery schools, and centers for early childhood education and care. However, there was a difference based on their years of experience. The “Ideal Image by the End of Childhood” was classified into “items that are easy to observe” and “items that are not easy to observe”. Due to multiple regression analysis, the path coefficients of “qualities and abilities”, “proactive and dialogic deep learning”, and “five areas” were significant. The results suggest that it may be effective for students to practice comprehensive and related evaluation of children, such as by watching videos of children in kindergarten.
2 0 0 0 OA 人は他者に視点取得されたと思うとき,共感されたと感じるか:認知と感情を区別した検討
- 著者
- 鈴木 雄大 山川 樹 坂本 真士
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021, (Released:2022-03-16)
- 参考文献数
- 12
本研究では,感情的視点取得(i.e., 他者の視点にたって,その人の感情を想像すること)と認知的視点取得(i.e., 他者の視点にたって,その人の考えを想像すること)を区別し,これらを他者にされたと知覚すること(i.e., 被感情的視点取得の知覚と被認知的視点取得の知覚)が被共感の知覚に及ぼす影響を検討した。参加者は自身の意見を述べるエッセイを書くよう求められ,それを読んだ別の参加者(実際には存在しなかった)が感情的視点取得および認知的視点取得をしたかどうかがフィードバックされた。その結果,被感情的視点取得の知覚および被認知的視点取得の知覚は,ともに被共感の知覚を促進することが示された。ただし,被共感の知覚を生じさせるかどうか検討したところ,被感情的視点取得の知覚のみが被共感の知覚を生じさせることが示唆された。他者に感情的視点取得および認知的視点取得をされることの効果について考察した。
2 0 0 0 OA 桂離宮神話 グローバル・ヒストリー概観
- 著者
- 江本 弘
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.781, pp.1115-1122, 2021 (Released:2021-03-30)
- 参考文献数
- 3
The start of the myth-making of the Katsura Imperial Villa as the acme of architectural aesthetics dates back to the early 1920s when the German-speaking world was beginning to be concerned about the pioneering nature of Japanese traditional dwelling’s wooden frame structure for its flexibility, openness, and close relationship of building and nature that preceded Western modernism. Manifestations of this line of interest involve Wasmuths Monatshefte für Baukunst’s earliest attention (1921/22) to a Japanese house being “full of inspiration for European architects,” and Bruno Taut’s reference in his Die Neue Wohnung in 1924. As those attempts were almost autonomous within the German-reading continent without sufficient reach to visual materials, ensuing interaction with the Japanese architectural world from the latter half of the 1920s greatly enhanced their knowledge production. The visit of the members of Bund Deutcher Architekten in Japan would result in the first introduction of Katsura as an intrinsically modern antiquity in the special issue of Die Form in July 1933. It was that the domestic modernist reevaluation of Katsura from Hideto Kishida’s mention in the end of the 1920s surreptitiously crossed an ocean to meet similar, but an even earlier search for a Japanese icon of the German-reading world of architecture. Bruno Taut emigrated to Japan simultaneously, and his literary propagations of Katsura’s modernity would be made from 1934 in Japanese, German, French, and English. But his words appeared to have told little to the indifferent French-reading world, and much less to German-reading world than Tetsuro Yoshida’s elaborate Das japanische Wohnhaus (1935); an influential work that met the exact demands by native professionals to a prompt number of reviews. Taut, in short, had an ephemeral effect just within Japanese audiences, however enormous it was. Given this circumstance, Japanese admiration of Katsura would become somewhat religiose in its reconstruction period after WWII, for it was naturally chosen as the appealing international symbol to promote Japanese modernity in line with the modern history of Euro-American architecture. The promotion, of course, firstly made towards American audiences: Ryuichi Hamaguchi in Architectural Forum (January 1953), Yoshinobu Ashihara in House+Home (June 1954), respectively stressed upon the significance of Katsura in the Western history of modern architecture; bibliographical pursuits from the Japanese architectural profession almost all followed this line at that time. While the postwar global Japonism starting from the U.S.-oriented, U.S-centric knowledge production would have something to tell centrifugally, the German-speaking world’s lasting interest in Japanese traditional architecture led Werner Blaser to come to Japan through Mies’s IIT, after which Blaser would publish Tempel und Teehaus in Japan (1955) that heavily relied upon Katsura and Mies that would soon be published in English and French (1956). Max Bill’s Italian Ludwig Miës van der Rohe (1955) was another witness to visually explain Mies’s aesthetic through Katsura. The myth of Katsura’s modernity had been thus formed well before Italian Architettura Cantiere (1960) featured Walter Gropius’s praise of Japanese architecture just before he and Kenzo Tange would publish Katsura: Tradition and Creation in Japanese Architecture in the same year. And those modernists’ interpretation of Katsura was contemporaneously rivaled by House Beautiful’s special issue on “Discover Shibui” (August 1960); Elizabeth Gordon, the anti-Miesian editor, set Katsura on the cover of the issue to deduce and trumpet yet another aesthetic from the same source as her enemy’s sympathizers.
2 0 0 0 OA 単身赴任者の性格が食物摂取状況に及ぼす影響について
- 著者
- 原田 まつ子 相良 多喜子 宇和川 小百合 塩入 輝恵 斎藤 禮子 平山 智美 西村 純一 苫米地 孝之助
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.403-411, 1995 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 24
石川県金沢市内に在住する単身赴任の男性37人を対象に, 健康状態, 栄養素及び食品群別摂取量状況調査, 性格調査 (谷田部・ギルフォード法) を行い, 単身赴任歴3年未満と3年以上, 性格の情緒安定因子と向性因子の性格特性とこれらとの関連を検討し, 次の結果を得た。1) 単身赴任歴の3年未満の者は, 3年以上に比べて“風邪をひきやすい”と回答した者が多く (p<0.05), 関連の度合が大きい。2) 単身赴任歴の3年未満の者は, 3年以上に比べて, 栄養素の摂取量でみると, ビタミンAを除く全ての栄養素が低値であり, 食品群別において, 特に緑黄色野菜の摂取量が少ない (p<0.05)。3) 情緒不安定な者は平均または安定な者に比べ, また, 積極型の者は平均または消極型の者に比べ“風邪をひきやすい”と回答した者が多く, 有意差が認められた (p<0.05)。4) 栄養素及び食品群別摂取量では, 情緒不安定な者は鉄, 野菜類の摂取量が有意に少なく, また, カルシウム, ビタミンC, 豆類も野菜類と同様に, 情緒不安定の者のほうが摂取量が少なかった。一方, 積極型は平均または消極型に比べ, 脂質量が多く, 緑黄色野菜の摂取量は有意に低値で, ビタミンCは少なかった。5) 性格特性の情緒安定因子とは, カルシウム, 鉄, 豆類, 野菜類が, また, 向性因子には脂質, ビタミンC, 乳類, 緑黄色野菜とに関連が認められた。
2 0 0 0 OA 妊婦スポーツの安全管理指針
- 著者
- 越野 立夫
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.124-128, 2003 (Released:2003-04-22)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 4 5
In recent years with ever-increasing numbers of pregnant women wanting to participate in sport activities, the question as to how safe maternal exercise is for mother and fetus has become more important. The effects of pregnancy on maternal cardio-respiratory system include increases in oxygen consumption, cardiac output, heart rate, stroke volume, and plasma volume. The increase in oxygen reserve seen in early pregnancy is reduced later, suggesting that maternal exercise may present a greater physiological stress in the third trimester. The aims of this article are 1) to comment on the evidence relating to the health risks and benefits of physical activity for pregnant women and their unborn fetuses and 2) to realize guidelines for management of maternal exercise. In the absence of either obstetric or medical complications, pregnant women can continue to exercise and derive related benefits. The type, intensity, frequency, and duration of the exercise seem to be important determinants of its beneficial effects. Evidence suggests that weight-bearing exercise produces a greater decrease in oxygen reserve than non weight-bearing exercise. Furthermore, to maintain a heart rate below 150 beats per minute during pregnancy, the intensity of weight-bearing exercise must be reduced. In addition, depending on the individual's needs and the physiologic changes associated with pregnancy, women may have to modify their specific exercise regimens. Although increases in the frequency of uterine contractions have been observed during physical activities, changes are often minimal. In response to moderate exercise, the increase in frequency of uterine contractions is gestation dependent and significant in the third but not in the second trimester. The physiological adaptations to exercise during pregnancy appear to protect the fetus from potential harm and, while an upper level of safe activity has not been established, the benefits of continuing to be active during pregnancy appear to outweigh any potential risks. All decisions about participation in physical activity during pregnancy should however be made by women in consultation with their medical advisers.
- 著者
- 山野 美鈴 芝池 博幸 井手 任
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.587-590, 2004-03-31
- 被引用文献数
- 6 6
Relationships between landscape structures and distribution patterns for dandelions (Taraxacum) were examined in Tsukuba city, Ibaraki Pref. By using molecular analysis, collected samples were discriminated as "native dandelions", "introduced dandelions", "tetraploid hybrids", "triploid hybrids", and "androgenesis hybrids". 32 sampling sites were grouped into five landscape types according to their similarities of land uses. The native dandelions mainly occurred at satoyama landscape. In contrast, hybrid dandelions (tetraploid hybrids) mainly occurred at urbanized areas and bare lands. Vegetation survey was also conducted at 20 sampling sites, and their components were summarized by DCA analysis. Positive correlation was found between the frequency of native dandelions and vegetation of forest floor and margin, and negative correlation between the frequency of tetraploid hybrids and vegetation of open habitats. Based on the results obtained, it was suggested that native dandelions tended to exist in the landscape containing more forest margin, whereas tetraploid hybrids in landscape containing more developed and/or vacant lands. Role of dandelions as environmental indicator species was discussed.
2 0 0 0 OA 啓蒙期歴史学とルソーの叙述 歴史知的考察
- 著者
- 石塚 正英
- 出版者
- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室
- 雑誌
- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.1-16, 2022 (Released:2022-04-28)
2 0 0 0 OA 江戸日本橋町人地における幕藩制的構造の確立 : 江戸町人地の研究 (1)
- 著者
- 玉井 哲雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.252, pp.137-144, 1977-02-28 (Released:2017-08-22)
Contents 1. Plotting of Residential Areas and the Streets in Yedo 2. Residential Areas for Townsmen 3. Kokenzu (Map of the Residential Areas for Townsmen)
2 0 0 0 OA 室内飼育におけるナナホシテントウ幼虫の共食い習性
- 著者
- 高橋 敬一
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.201-205, 1987-08-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 15 16
餌アブラムシの有無がナナホシテントウ幼虫の共食いに与える影響を各種の発育ステージの組合せについて調査した。1) アブラムシを与えないといずれの齢期の幼虫も卵を共食いしたが,アブラムシを与えると3齢以上の齢期では卵の共食いはみられなかった。しかし,1, 2齢期ではその場合でも若干の共食いが見られた。2) 幼虫間での共食いはアブラムシを与えないと2齢以上の齢期で多く起こったが,アブラムシを与えるとほとんどみられなかった。アブラムシさえ十分にあれば,幼虫の齢構成や飼育密度の違いは共食いの原因にはならないと思われる。3) 蛹に対する共食いは,アブラムシの有無にかかわらずほとんど起こらなかった。
2 0 0 0 OA 補体制御因子と腎疾患
2 0 0 0 OA 和歌山県における明治前期地籍図の保存状況(明治地籍図の集成的研究)
- 著者
- 額田 雅裕
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.163, pp.427-438, 2011-03-31