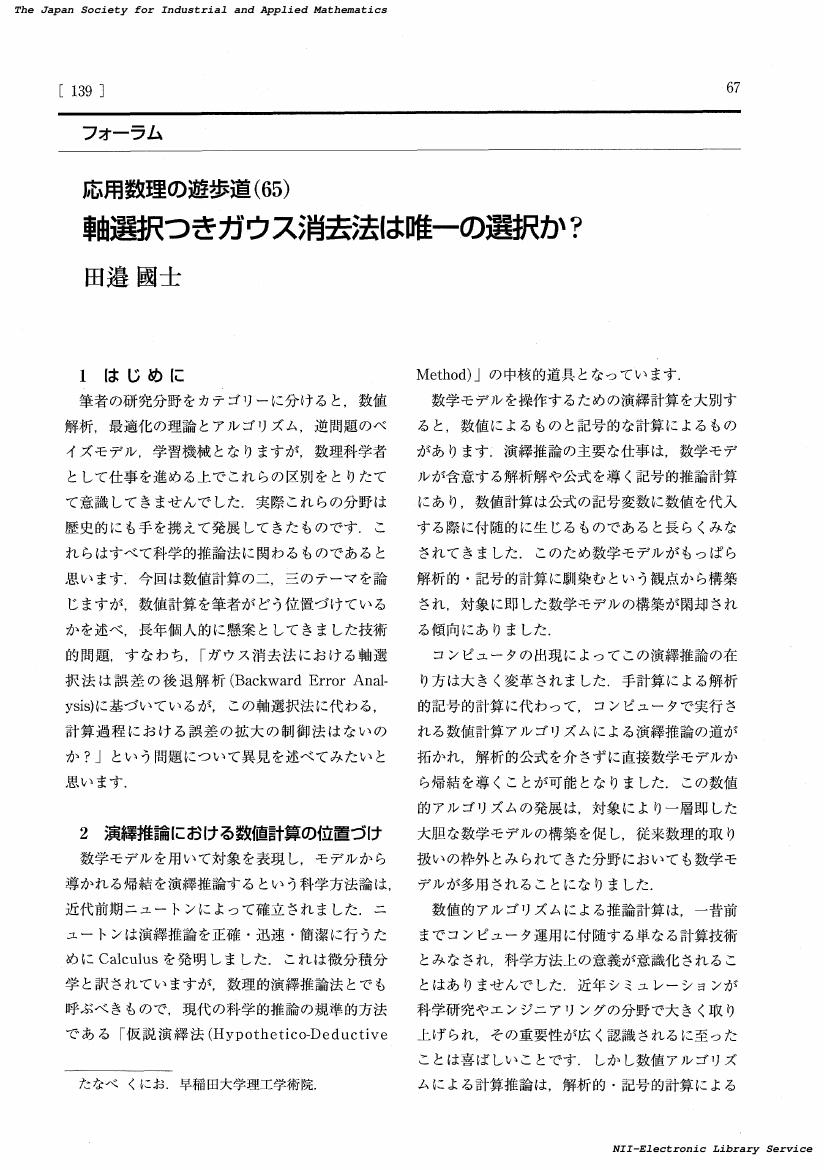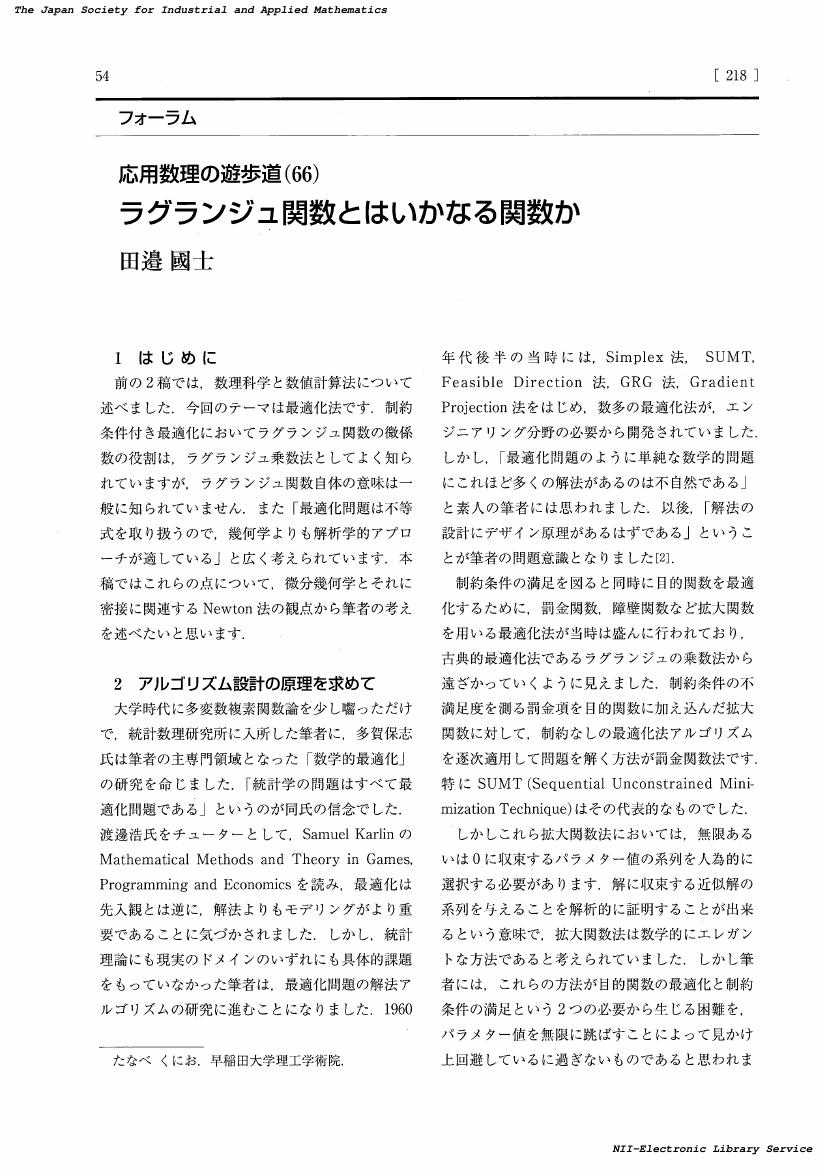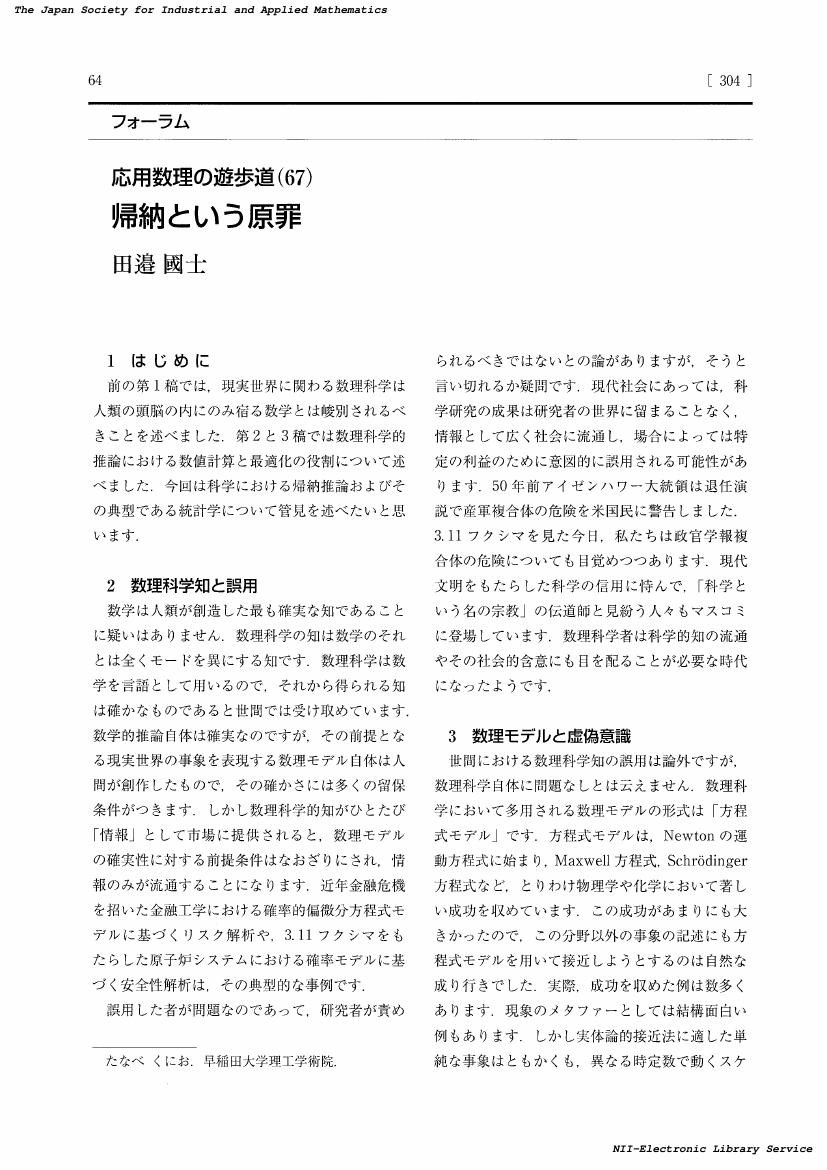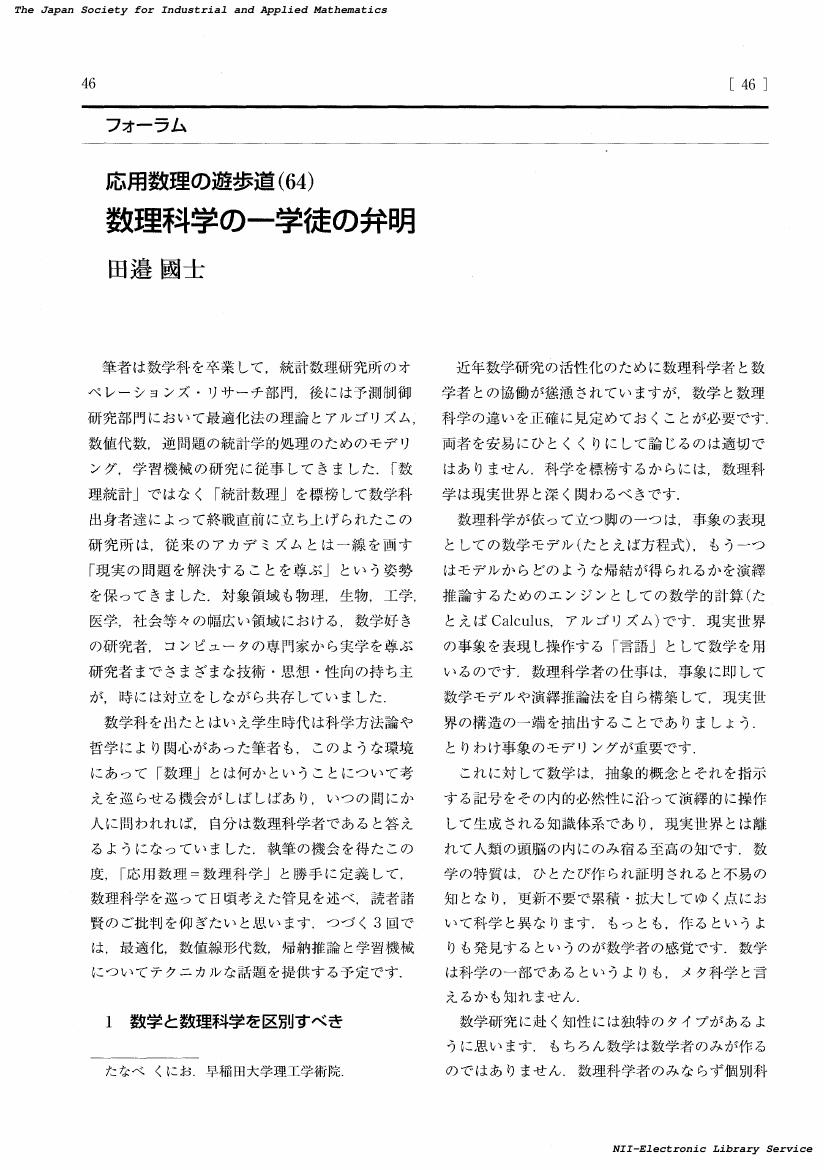2 0 0 0 生きものの記録 : 艶説
2 0 0 0 OA 草間彌生とミニマリズム : 鑑賞者と時間
- 著者
- 三上 真理子
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.70-83, 2005-03-31 (Released:2017-05-22)
Yayoi Kusama herself is not a minimalist, but she did have contact with minimal artists such as Donald JUDD and Eva HESSE. Judd praised Kusama's Infinity Net Paintings from the start, especially her obsessional repetition. According to Judd, the new art trend of the 60s were represented by three-dimensional works which were neither paintings nor sculptures. Kusama's Compulsion Furniture was one of them and Judd himself was making such works. On the other hand, Michael FRIED attacked minimal art because Specific Objects, as Judd had called them, had objecthood, and even though one looks at such works which depend on installation, all the viewer can feel is his or her own duration. Then, what kind of time can we experience by appreciating Kusama's works? Comparing Kusama's works with Hesse's ones and so on, the relation of repetition and time is explained in order to describe the originality of Kusama's works.
2 0 0 0 OA 軸選択つきガウス消去法は唯一の選択か?(応用数理の遊歩道(65))
- 著者
- 田邉 國士
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.139-143, 2011-06-24 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 OA ラグランジュ関数とはいかなる関数か(応用数理の遊歩道(66))
- 著者
- 田邉 國士
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.218-222, 2011-09-27 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 帰納という原罪(応用数理の遊歩道(67))
- 著者
- 田邉 國士
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.304-309, 2011-12-22 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 数理科学の一学徒の弁明(応用数理の遊歩道(64))
- 著者
- 田邉 國士
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.46-49, 2011-03-25 (Released:2017-04-08)
2 0 0 0 IR オベロンとシェイクスピア
- 著者
- 平岩 紀夫
- 出版者
- 愛知教育大学外国語研究室
- 雑誌
- 外国語研究 (ISSN:02881861)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.13-25, 1973-03
2 0 0 0 OA デザインという行為のデザイン
- 著者
- 藤井 晴行 中島 秀之
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.403-416, 2010 (Released:2011-03-08)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 6
We try to generate something new by interrogating ourselves on the notion of design science and on the notions derived during designing the design science. At the very beginning of designing, we introduce the notion of designing as an activity of constructing a new system. Then, first, we generate a hypothetical model of such a constructive process as repetitions of the cycles of synthesis (or, generation), analysis, and focusing towards a preferred situation. Second, we analyze the model with reference to processes of making artifacts. Third, on the basis of the analysis, we give ourselves the direction to the sophistication of the model and introduce the variables that should complement the model. We repeat the loop of the first, the second, and the third. As implied above, we design the model of the constructive process and apply the model to our activity of designing the model.
2 0 0 0 OA エゾシカ肉のおいしさのリアルタイム計測
- 著者
- 武山 真弓 佐藤 勝 安井 崇 横川 慎二
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 C (ISSN:13452827)
- 巻号頁・発行日
- vol.J103-C, no.9, pp.387-394, 2020-09-01
野生鳥獣の駆除とジビエ利活用が全国的な展開を示す中,北海道ではエゾシカの食用としての利用は1割程度であることから,ジビエ利活用促進のための新たな取り組みが必要不可欠である.我々は,電気的な特性からエゾシカのおいしさを評価し,その解析に従来難しいとされてきた等価回路モデルを選定しなくても簡易な近似で等価回路モデルと遜色ない解析結果が得られるという新たな手法を見出した.更に,従来の化学的な手法や官能検査によるおいしさ評価も行い,電気的な特性との相関について検討した.我々の提案する手法は,リアルタイム計測であることから,食品分野などへの応用が大いに期待される.
2 0 0 0 OA 1人1台タブレット端末環境における学校放送番組活用のための手立て
- 著者
- 今野 貴之
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.Suppl., pp.101-104, 2017-01-15 (Released:2017-03-06)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
本稿では,1人1台タブレット端末環境における学校放送番組活用のための教師の手立てを明らかにすることを目的とした.学校放送番組の「未来広告ジャパン!」を用いて授業実践を行った大阪の私立K小学校5年生を事例とした.事例の分析の結果,教師の手立てとして,学校における番組利用のルールと,集団の活動におけるタブレット端末利用のルールを設定していることがわかった.また,これらの手立てはタブレット端末の家庭への持ち帰りと,探究的な学習の時間的制約が影響していることが考察された.
2 0 0 0 OA フランスにおけるマンガ事情
- 著者
- 川又 啓子
- 出版者
- 京都産業大学マネジメント研究会
- 雑誌
- 京都マネジメント・レビュー (ISSN:13475304)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.79-100, 2009-06
はじめにⅠ 日本におけるマンガの現状 1. 2008年のマンガ市場 2. 日本のマンガ消費の特徴Ⅱ フランスにおけるマンガの現状 1. バンド・デシネ(bande dessinée=BD)とはなにか 2. BDとマンガ 3. フランスのマンガ市場 4. フランスのマンガ関連イベント 6. フランスにおける文化消費の特徴むすびにかえて参考文献
- 著者
- 米倉 寛 武田 親宗 名原 功
- 出版者
- 克誠堂出版
- 雑誌
- 麻酔 = The Japanese journal of anesthesiology : 日本麻酔科学会準機関誌 (ISSN:00214892)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.S191-196, 2021-11
2 0 0 0 OA 新渡戸稲造の朝鮮亡国論
- 著者
- 権 錫永
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, pp.37-60, 2008-11-28
- 著者
- 藤村 龍雄
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.111-125, 1972-12-25 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 19
2 0 0 0 北京大学蔵西漢竹書『趙正書』訳注
- 著者
- 早稲田大学簡帛研究会
- 出版者
- 早稲田大学東洋史懇話会
- 雑誌
- 史滴 (ISSN:02854643)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.71-106, 2018-12
2 0 0 0 OA タル・ベーラの『ファミリー・ネスト』(1977)における空間表象をめぐって
- 著者
- モルナール レヴェンテ
- 出版者
- 北海道大学大学院文学院
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:24352799)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.33-50, 2021-03-31
ハンガリー出身のタル・ベーラは世界的に知られている映画作家ではあるが,1989年前の作品群,とりわけ1977年の長編デビュー作『ファミリー・ネスト』とそれに続く『ザ・アウトサイダー』(1980年)と『プリファブ・ピープル』(1982年)は十分に研究されているとは言い難い。その原因の一つは,当時の映像を入手し確認することは非常に困難という現実的なことだが,理論上の問題もある。それらの作品は形式上で当時のドキュメンタリー映画運動に属しているため,分析するにあたって,その映画運動も精査する必要がある。1970年代において,バラージュ・ベーラ撮影所(本稿はBBSと略記する)所属の若手映画監督らは,社会主義国家ハンガリーの「人生の現実」を洗い出そうとしていた。そのために,社会科学の調査方法を最大限に活かした独特な映画形式を創り上げた。監督上昇を目ざしたタル・ベーラ自身もその表現形式を採用した。以上により,本稿の目的は二つある。まずは,BBSのドキュメンタリー映画形式〈社会(科学)主義映画〉の特質に触れる上で,初期タルのナラティヴ,演出,カメラワーク,編集等々を分析する。さらには,デビュー作『ファミリー・ネスト』にみられる映画空間の問題をめぐって,タルの独特な映画的世界を構築する方法がすでに本作品においてすら ─その胚型であるが─ 姿をみせていることを明らかにする。
2 0 0 0 児童虐待に対する刑事法の新たな役割
- 著者
- 三枝 有
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.66-78, 2003
The act of child abuse is often performed by the protector of the abused child under the veil of "discipline", so the abuser does not have the strong sense of guilt, nor is the abused conscious of the fact that he or she is the target of a crime. That is why child abuse is called "a hidden crime". Most of the acts of child abuse are performed behind closed doors and continue for a certain period of time. In most cases such acts are not discovered by an outsider easily. Moreover the act of child abuse is performed between the special relationship such as the relationship of a parent and a child, so that it is difficult for the abused children to recognize themselves as a victim and the children tend to be resigned to their situation. Not only that, the abused children often form the sense of guilt because they feel they are also responsible for such an act. In 1961 C.H. Kempe advocated "the Battered-Child Syndrome" concerning the actual conditions of child abuse which has the special characteristic of a hidden crime. Nearly 40 years later, finally in Japan, "the Law concerning the Prevention and Others of Child Abuse (the Child Abuse Prevention Law)" was passed and effected at the plenary session of the House of Representatives on May 17, 2000. Since the enforcement of the Law, the number of acknowledged cases of child abuse and the number of arrests have been increasing rapidly, so it is true that the very enactment of the Law has promoted the notifications of child abuse cases and the arrests of abusers. It is also true that in the Japanese society where Confucian ideas still remain in people's mind, like in Korea, child abuse by its own parent was a taboo which we should not talk about or even think about. However, realities were opposite. In this paper, I will discuss the role that criminal punishment should play to prevent child abuse, while grasping the actual conditions of child abuse today and the Japanese ideas that have led to such conditions. As a conclusion I would like to propose the active introduction of punitive provisions of the laws by demonstrating that conventional punishment which emphasizes its function of sanction should emphasize its function of forming the new sense of norms in child abuse and furthermore that punishment should actively perform its supplementary function to facilitate welfare-oriented intervention by the government going beyond its general preventive function. Contents 1. Introduction-Actual Conditions of Child Abuse 2. The Abuse Prevention Law and Punishment 3. The Role of the Criminal Law in Child Abuse 4. Conclusion-the New Function of the Criminal Law