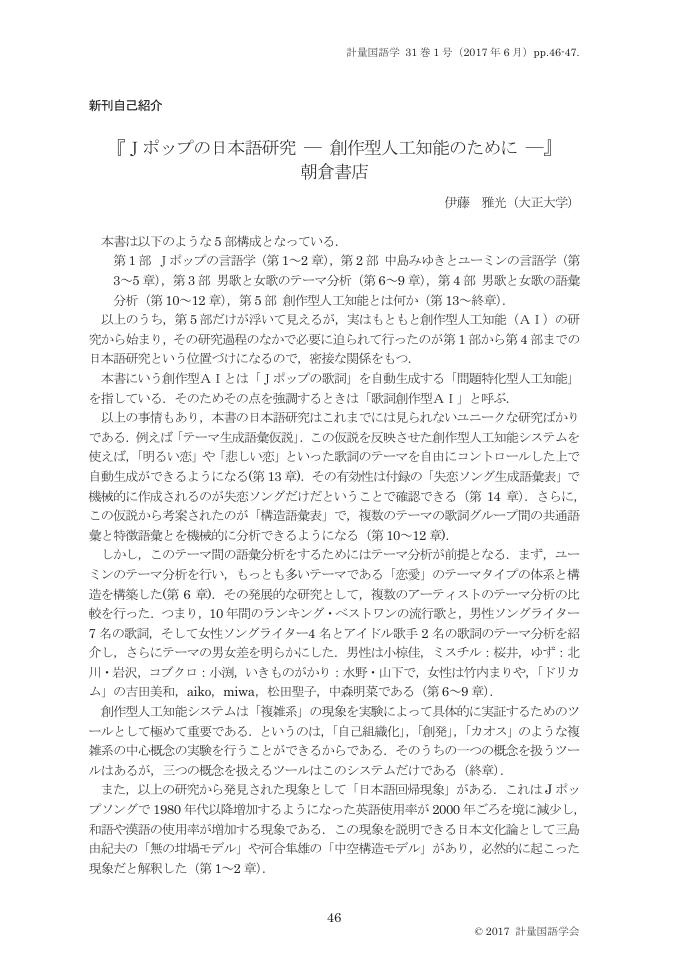2 0 0 0 OA 慢性腎不全患者におけるデバイス治療
- 著者
- 石川 利之
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.340-345, 2012 (Released:2015-07-16)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
デバイス植込み症例において,腎不全は手術合併症,生命予後に大きな影響を及ぼす.腎不全があるとデバイス植込みに伴う血腫・感染のリスクが増大し,腎障害の程度が増すに従って危険性が高まる.特に,末期腎疾患では出血性合併症・感染が高率にみられる.植込み型除細動器症例において,腎疾患のある群は腎疾患のない群と比べ,心不全の有病率は高く心不全による入院回数は多く,生存率は低値である.近年,QRS幅の延長した重症心不全症例に対する心臓再同期療法(CRT)の有効性が示されているが,腎不全はCRTを施行した心不全患者の予後規定因子である.しかし,腎不全においてもCRTのレスポンダーの予後は非腎不全例と変わらず,CRT後に腎機能低下の進行が抑制された症例では左室のリバースリモデリングがもたらされ,予後改善効果が期待できる.デバイス植込み手術に際して,人工透析のシャントはデバイス植込み部位の決定時に問題となる.デバイス植込み症例に高率に合併する心房細動は脳梗塞の頻度を高めるが,ワルファリンの使用は脳卒中の頻度を著しく増加させるので,原則禁忌とされる.ワルファリン使用下のデバイス植込み手術は血腫・感染の危険因子となるが,手術時のヘパリン置換は,それ以上にリスクが高いとされ,むしろワルファリン投与継続下の手術がすすめられている.
2 0 0 0 OA 異色の宣教師、フルベッキ
- 著者
- 大島 一元
- 出版者
- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会
- 雑誌
- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.40-42, 2008 (Released:2008-04-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 百家高評伝
- 著者
- 久保田高三 (潜竜) 編
- 出版者
- 文寿堂書林等
- 巻号頁・発行日
- vol.第3編, 1895
- 著者
- 村松 常司 村松 園江 秋田 武 〔他〕
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告 芸術・保健体育・家政・技術科学 (ISSN:03887367)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.p75-86, 1995-02
- 被引用文献数
- 1
青年期女性を対象にして,日常生活行動様式やBreslowの7つの健康習慣(ライフスタイル)と喫煙習慣との関連を調査し,さらに,性格特性がそれらにどう関連しているかを追究することを目的とし,無記名質問紙法により,平成4年9月~11月に調査を行い,以下に示す成績を得た。(1)対象の喫煙者率は7.5%であり,両親の喫煙とは関連は認められなかった。(2)喫煙者は自動車運転を楽しむ,コーヒーや酒を飲む,化粧をする,流行として女性の生き方を取り入れる,周囲の目を気にしないなどの外向的な行動パターンをとっていることが認められた。(3)喫煙者は毎日朝食をとらない,睡眠時間が短い,栄養のバランスに気をつけないなど,健康に対する価値づけが低いということが認められた。(4)喫煙者は喫煙に対して肯定的な認識を持ち,非喫煙者は喫煙に対して否定的であった。喫煙者,非喫煙者間で最も喫煙に対する認識に差がみられたのは,情緒的意識(精神が集中できる,落ち着くなど)であった。(5)喫煙者のエゴグラムではFC(自由奔放さ)が高く,A(客観的判断力),AC(順応性)が低かった。つまり,天真爛漫で活発だが協調性に欠ける。それに比較して,非喫煙者のエゴグラムではA,ACが高く,FCが低かった。すなわち非喫煙者は社会適応度が高いことが認められた。以上のことから,青年期女性の喫煙習慣とライフスタイル,性格特性にはそれぞれ関連があることが示唆された。
2 0 0 0 IR ポリヴェーガル理論からみた精神療法について
- 著者
- 花澤 寿
- 出版者
- 千葉大学教育学部
- 雑誌
- 千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.329-337, 2019-03
[要約] ポリヴェーガル理論(多重迷走神経理論)は,進化論と神経生理学に基づき,Porges が提唱した自律神経系の適応反応に関する新しい理論である。この理論によると,哺乳類が獲得した新しい自律神経である腹側迷走神経と,それと連係協働する脳神経群が形成する腹側迷走神経複合体が,より原始的な自律神経(交感神経系,背側迷走神経系)をコントロールすることにより,最も適応的なストレス反応が可能になる。腹側迷走神経複合体が司るのは,人と人とのつながりと,安全・安心の感覚を結びつける社会的関わりシステムである。治療者と患者の関係性が重要な意味を持つ精神療法を,ポリヴェーガル理論を基礎において検討することにより,精神療法一般に共通する理論的基盤と実践的方法論が得られる可能性について考察した。
2 0 0 0 OA ビタミンK2の光異性化における励起の波長依存性
- 著者
- 高橋 一正 宇田川 毅 草葉 義夫 村松 岳彦 天野 壮泰 谷岡 慎一 市野 富雄 中野 清志 村上 一方 畔 和夫 奈良部 幸夫 今井 昭生 小西 優介 天田 巌
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1989, no.9, pp.1571-1575, 1989-09-10 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 4
波長可変レーザー装置を用いてcis-ビタミンK2(cis-VK2)→trans-ビタミンK2(trans-VK2)の光異性化反応を試みた。cis-VK2またはtrans-VK2の溶液に紫外から可視領域のレーザー光を照射し,それぞれの異性化量を測定した。その結果,cis-5-VK2→trans-VK2の異性化に有効な波長は280~460nmであり,とくに435と355nmが高い異性化率を示した。trans-VK2→cis-VK2の異性化反亦も同時に進行するがその速度は遅く,光平衡組成はtrans-VK2/cis-VK27/3となった。また異性化反応は溶媒の影響を受け極性溶媒よりも無極性溶媒が有効であった。cis-VK2→trans-VK2の異性化はテトラプレニル側鎖中のナフトキノン骨格にもっとも近い二重結合で起こり,他の二重結合部では起こらず選択的反応である。窒素雰囲気下でのおもな副生成物はメナクロメノロ一ルであった。これらの結果から異性化反応過程を推定した。
2 0 0 0 OA 総合格闘技における負傷の実態と傾向―試合現場におけるリングドクターの診断結果から―
- 著者
- 松宮 智生
- 出版者
- 国士舘大学体育・スポーツ科学学会
- 雑誌
- 体育・スポーツ科学研究 (ISSN:18809316)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, 2013
2 0 0 0 IR 迷走する1920年代のハリウッド
- 著者
- 小林 憲夫 KOBAYASHI Norio
- 出版者
- 駒沢女子大学
- 雑誌
- 駒沢女子大学研究紀要 (ISSN:13408631)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.73-88, 2014-12
2 0 0 0 OA 東京銀街小誌
- 著者
- 関梅痴 (槎盆子) 著
- 出版者
- 山田孝之助
- 巻号頁・発行日
- vol.初篇, 1882
- 著者
- 鈴木 明美
- 出版者
- 名古屋市立大学
- 雑誌
- 人間文化研究 (ISSN:13480308)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.13-24, 2008-06
本稿は、明治期に渡豪した初期移民、柏木坦の半世紀にわたる足跡を考察し、オーストラリアにおける日本人移民史の一端を明らかにすることを目的とする。オーストラリアにおける日本人移民は、北部のトレス海峡に位置する木曜島で真珠貝採取業に従事した自由・契約労働移民とクィーンズランド州のサトウキビ農園で契約労働に従事した人々に大別できる。移民のなかには、オーストラリアに定住し、実業家となったり、契約労働期間終了後に別の事業に従事した人々がいる。これらの人々は、連邦結成後、白豪主義が導入されたオーストラリアで、外国人登録をして生活していたが、第二次世界大戦開戦と同時に、「日本人」であることを理由に、「敵性外国人」として強制収容された経験を持つ。終戦後、ほとんどの「日本人」が本国送還されたが、木稿で取り上げる柏木坦は、オーストラリア人の妻とオーストラリア生まれの娘がいたことなどを理由に、残留を許可された少数の「日本人」のうちの一人である。和歌山県出身の柏木は、木曜島で日本人コミュニティーのリーダー的存在として活躍後、ブリスベンで実業家として成功した。オーストラリア連邦公文書館には、敵性外国人として強制収容された「日本人」の個人ファイルが保管されており、一部を除いて公開されている。木稿は、公文書館のファイルをもとに、オーストラリアにおける日本人移民史を個人の記録から読み解こうとするものである。
- 著者
- Shin-ichiro Agake Fernanda Plucani do Amaral Tetsuya Yamada Hitoshi Sekimoto Gary Stacey Tadashi Yokoyama Naoko Ohkama-Ohtsu
- 出版者
- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.ME21060, 2022 (Released:2022-01-27)
- 参考文献数
- 61
- 被引用文献数
- 3
Spores are a stress-resistant form of Bacillus spp., which include species that are plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). Previous studies showed that the inoculation of plants with vegetative cells or spores exerted different plant growth-promoting effects. To elucidate the spore-specific mechanism, we compared the effects of viable vegetative cells, autoclaved dead spores, and viable spores of Bacillus pumilus TUAT1 inoculated at 107 CFU plant–1 on the growth of the C4 model plant, Setaria viridis A10.1. B. pumilus TUAT1 spores exerted stronger growth-promoting effects on Setaria than on control plants 14 days after the inoculation. Viable spores increased shoot weight, root weight, shoot length, root length, and nitrogen uptake efficiency 21 days after the inoculation. These increases involved primary and crown root formation. Additionally, autoclaved dead spores inoculated at 108 or 109 CFU plant–1 had a positive impact on crown root differentiation, which increased total lateral root length, resulting in a greater biomass and more efficient nitrogen uptake. The present results indicate that an inoculation with viable spores of B. pumilus TUAT1 is more effective at enhancing the growth of Setaria than that with vegetative cells. The plant response to dead spores suggests that the spore-specific plant growth-promoting mechanism is at least partly independent of symbiotic colonization.
2 0 0 0 OA 東京大都市圏における職業構成の空間的パターンとその変化
- 著者
- 小泉 諒
- 出版者
- 東北地理学会
- 雑誌
- 季刊地理学 (ISSN:09167889)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.61-70, 2010 (Released:2012-08-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 6
近年の東京大都市圏の空間構造とその変化については,とくに都市地理学と都市社会学において多くの研究が蓄積されてきた。しかしその多くは市区町村単位の分析であり,また空間的パターンの把握については不十分である。そこで本研究は,1995年と2005年の地域メッシュ統計を用いて,職業構成からみた東京大都市圏の居住の空間的パターンと変化を捉え直し,人口動態との関連でその背景を探ることを目的としたその結果,市区町村単位で分析した職業構成は,都市社会学の先行研究が指摘するセクターパターンから同心円パターンへの変化がある程度認められた。メッシュ単位での分析でも,東京都心から15km圏内と30 km圏外の外周部については,これと同様の傾向が確認された。これは,東京都心部での住宅供給の増加によるホワイトカラー層の人口回帰を反映したものと考えられる。しかし,メッシュ単位での結果では,15∼30km圏で鉄道路線に沿った放射状パターンがみられ,郊外では鉄道からの距離による職業構成の居住分化が強まってきている。これは,市区町村単位での分析では見いだせなかった傾向で,郊外住宅地の居住分化と社会的分極化が同時進行していることを示唆している。
2 0 0 0 OA 『Jポップの日本語研究 — 創作型人工知能のために —』 朝倉書店
- 著者
- 伊藤 雅光
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.46-47, 2017-06-20 (Released:2018-08-01)
2 0 0 0 IR 介護保険制度のケアモデルと認知症高齢者グループホーム実践の展開
- 著者
- 矢澤 澄子
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.85-116, 2008-09
Japanese society has been facing elder care crisis since the 1980's epitomized by a so-called "nursing hell" which has resulted from a care service shortage for the increasing number of elderly people. The national elder care insurance system commenced in 2000 as a response to the above situation. It was a paradigm change to the social care of elderly people, from a limited adminis-trative service by the government, to a social care insurance system with individual choice and mutual help by contract with the government.This article examines the basic idea of a care model for the elder care insurance system (a care model for 'decent life' for elderly people) and attempts to discover influences from the ideas and practice of group homes for elderly people with dementia developed in local areas since the 1980's prior to the institutionalization of the elder care insurance system. The article also analyses the gap between the idea of a care model for the elder care insurance system and the reality of care workers facing difficulties in workplaces, based on empirical research of care workers in group homes. The research was based on a questionnaire designed by our research group in 2006, and sent by mail to 1382 workers all over Japan.In conclusion, the paper proposes the necessity of re-examining and improving the design and contents of the elder care insurance system, in order to realize its original ideas and purpose as the national social care system, by strengthening public responsibility and financial support at the national as well as local level. It is the only way to maintain a high quality of elder care service in the system and respond to the sincere desires of care workers who work diligently for long hours and receive low salaries.少子高齢化と「介護の危機」(ケアの危機)が進行するなか、日本では2000年を起点としていわゆる社会福祉基礎構造改革により、高齢者介護サービスは、措置制度から介護保険制度(自由契約制度)へとパラダイム転換を行った。本論文は、日本の社会的介護(ソーシャル・ケア)の要を担う介護保険制度の理念、目標像がどのように明確化され制度化されてきたのかについて、特に制度の理念・目標像の構築に大きな影響を与えてきた、認知症高齢者グループホーム実践(認知症対応型共同生活介護)の展開過程との関連に注目して考察する。また制度の運用と改変の過程で顕在化してきた理念・目標像と運用・実践の間の矛盾や、2005年の制度改正以降とくに深刻化している理念・目標像と利用者の選択権や現場ケアワーカーの労働実態との間に広がる乖離の中身についても全国調査に基づき検証する。論文では日本の介護保険制度の形成・改変過程を見据え、制度の理念・目標像、介護保険政策の展開、介護現場の実態の3者を相互に関連づけながら、制度の成熟と「望ましいケア実践」にむけて何が問われているかを明らかにする。いま多くの認知症高齢者グループホームでは、介護保険制度の運用と改正の負の影響を受け、ケアワーカーたちが利用者と制度の狭間で苦悩し、他の介護施設と同様にホーム運営(経営)の瀬戸際で解決すべき複雑な困難に直面している。介護保険の「お年寄りをどんどん切り捨てる」「机の上だけて決められている制度」と「介護実践の場」の現状との間にある大きな乖離は早急に埋める必要がある。そのために国・地方自治体は、現場の声にしっかり耳を傾け、制度の改善・改革にむけてどのように有効な政策的対応をとりうるのかに真剣に立ち向かうことが求められている。
2 0 0 0 OA 昆虫視細胞の分光感度
2 0 0 0 IR 介護事業利用者の介護サービス選択に関する調査研究
- 著者
- 池田 幸代 イケダ ユキヨ Yukiyo Ikeda
- 雑誌
- 東京情報大学研究論集
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.53-67, 2012-03-01
本研究では、介護事業サービスを提供する企業が安定した経営を行うために、現在直面する問題を解決することを目的としている。その中で、ここでは介護事業所が利用者をいかにして確保するかに着目した。調査では、主にデイサービスや訪問介護サービスを提供している東京都内の介護事業所の利用者を対象に、インタビュー調査を実施した。それによると利用者は第三者評価などの公開された情報を利用して、介護事業所の選択を行っているのではなく、ケアマネージャーや知り合いによる紹介によって事業所を選択していることが明らかとなった。介護保険制度が導入された当初、利用者の自由意思に基づく選択が行われるとみられていたが、実はそうではないことがわかる。そこで本研究では、利用者確保のために、介護事業所がどのような対策をとるべきかを考える。The purpose of this research is to solve the problems currently faced by public nursing-care service providers for their stable business operation. In the interview survey, it gave most attention to service users of day-care service and attendant service providers in Tokyo area. The result shows that those users did not choose the providers by utilizing the open information which is guaranteed by the third-party evaluation, but often times being introduced by care-managers or acquaintances. When nursing-care insurance system was launched, it was estimated that choice of the service becomes free contract, but the result shows to the contrary. Based on this finding, this paper considers the measures to be taken by public nursing-care service providers to attract service users by understanding customer needs and effective marketing activities.
2 0 0 0 IR 江戸時代における蝶の文様表現 : 『小袖模様雛形本』を中心に
- 出版者
- 京都
- 雑誌
- 同志社女子大学生活科学 = DWCLA human life and science (ISSN:13451391)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.46-57, 2013-02-20
This paper looks at the Kosode Moyo Hinagatabon published during the Edo Period, and discusses the characteristics and changes of butterfly patterns drawn on kosode. The appearance of butterfly patterns peaked in the late 1680s and early 1700s, and later increased slightly to its highest number in 1800. Depictions of butterfly patterns can be generally divided into ageha chou and fuse chou, with further changes visible in the detail of the shapes, showing variety. There were also allegorical patterns that combined with other patterns to symbolize a sense of season, drawing from literature of that time. In sum, it appears that there is much commonality among popular designs of kosode patterns.原著論文
- 著者
- Mami ADACHI Hirotaka IGARASHI Minoru OKAMOTO Takashi TAMAMOTO Yasutomo HORI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-0201, (Released:2022-01-26)
- 被引用文献数
- 2
A 10-year-old female Cavalier King Charles Spaniel presented with hematuria, pollakiuria and skin rash. Based on the histopathological and cytological examination of the skin and bladder mucosa, the dog was diagnosed with large granular lymphocytic (LGL) lymphoma of the bladder and skin. The dog responded well to the initial chemotherapy with nimustine for 3 months. Since recurrence of skin erosion and bladder wall thickening were observed, the dog was subsequently administered chemotherapy with other anticancer drugs, including chlorambucil, vincristine, doxorubicin, L-asparaginase, cytosine arabinoside, and cyclophosphamide. The dog survived for 11 months and died due to tumor-related disseminated intravascular coagulation. This is the first report of a canine case of LGL lymphoma in the skin and bladder.