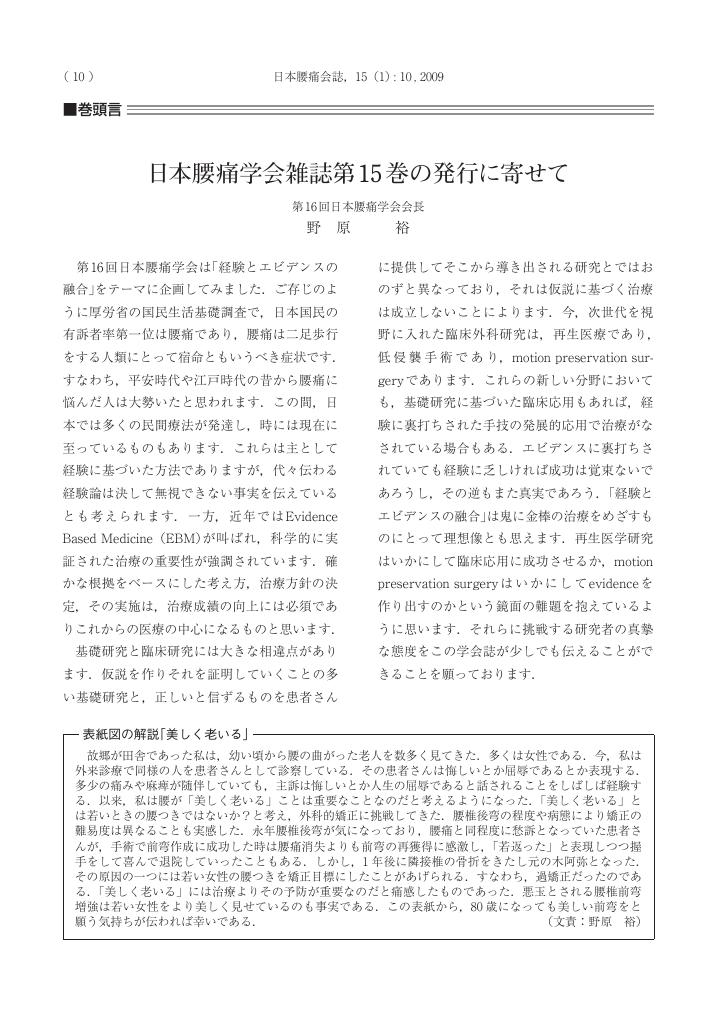2 0 0 0 OA 琉球貿易図屏風・経済学部附属史料館所蔵
- 著者
- 岩崎 奈緒子
- 出版者
- 滋賀大学広報委員会
- 雑誌
- しがだい : 滋賀大学広報誌
- 巻号頁・発行日
- no.創刊号, pp.9, 2000-03
2 0 0 0 OA ファーストクラス継続をもつ仮想機械
- 著者
- 西崎 真也 植田 友幸
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- 日本ソフトウェア科学会大会講演論文集 日本ソフトウェア科学会第20回記念大会 (ISSN:13493515)
- 巻号頁・発行日
- pp.6, 2003 (Released:2003-12-17)
従来,関数型言語のためのバイトコードを解釈する仮想機械として、SECDマシンやCAMマシンなど多くのものが提唱され,それらに基づく実装や理論的な側面に関する研究がなされてきた.本論文では,SECDマシンを単純化した仮想機械SAM(Simple Abstract Machine)を提唱する.変数参照機能を単純化することにより,仮想機械におけるファーストクラス継続を簡潔に扱うことが可能になっている。
2 0 0 0 OA Note on Hoplitoplacenticeras from Hokkaido
- 著者
- Tatsuro MATSUMOTO
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.8, pp.249-252, 1982 (Released:2006-10-10)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 大学生のもつ「死」のイメージ : テキストマイニングによる分析
- 著者
- 藤井 美和 Miwa Fujii
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- no.95, pp.145-155, 2003-10-28
2 0 0 0 OA 流動様式測定と流れの可視化計測
- 著者
- 松井 剛一
- 出版者
- 日本混相流学会
- 雑誌
- 混相流 (ISSN:09142843)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.24-38, 2000-03-15 (Released:2011-02-22)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
Because “flow pattern” relates closely to design parameters of plant such as pressure drop and heat transfer coefficient, better knowledge of the flow pattern leads not only to deep understanding of the flow but also to accurate prediction of the parameters or to safe operation of plant. Therefore, “flow pattern” is an important and fundamental parameter as well as void fraction. Nevertheless the flow pattern has been judged mostly on a basis of visual observation. Therefore, it is desired to identify the flow pattern objectively and quantitatively.Here, identification of flow pattern using differential pressure fluctuations is described. Behaviors of statistical parameters are discussed in the statistical parameter spaces. And also recent flow visualization methods using fast X-ray CT and HPIV are described.
2 0 0 0 OA 日本腰痛学会雑誌第15巻の発行に寄せて
- 著者
- 野原 裕
- 出版者
- 日本腰痛学会
- 雑誌
- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.10, 2009 (Released:2009-12-19)
- 著者
- 安藤 信雄
- 出版者
- 中部学院大学総合研究センター
- 雑誌
- 中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要 (ISSN:1347328X)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.69-78, 2018-03
- 著者
- 村田 浩一
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.41-47, 2019
<p> 日本に初めて誕生した動物園は,フランス革命直後の1794年に開園したパリ国立自然史博物館内の植物園附属動物園(Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes)をモデルにしている。幕末にそこを訪れた田中芳男や福澤諭吉は,西欧文化や博物学の奥深さに驚いたことだろう。当時の動物園(メナジェリー)には,ラマルク,サンチレール,そしてキュヴィエなど,現在もなお名を馳せている学者たちが関与していた。動物園の歴史が,博物学や動物学や比較解剖学などの学術研究を基盤としている証左である。しかし,本邦の動物園は,その基盤の重要性を認識していた形跡が明治時代の文書である「博物館ノ儀」に認められるにも関わらず,上野公園に動物園が創設されて以降とくに戦後の発展過程において継承されることなく現在に至っている。国内動物園で学術研究が滞っているのは,研究環境が十分に整っていないことが原因であるのは確かだ。だが,それだけだろうか? 現今の停滞を打開するために日本の動物園関係者が必要とするのは,200年以上に及ぶ動物園における学術研究の歴史を背負い,時代に応じた新たな研究を興し,その成果を世界に向けて発信する覚悟ではないかと思う。動物園が歴史的に大切にしてきた"研究する心"を持って新たな未来を切り開くために闘い続けるべきであろう。</p>
- 著者
- 大田 康博 Ota Yasuhiro
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学商学論叢 = Fukuoka University Review of Commercial Sciences (ISSN:02852780)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3-4, pp.301-335, 2019-03
2 0 0 0 OA 忘れ物を防ぐために利用可能な資源の中身の学年差
- 著者
- 小林 敬一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.297-305, 1995-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 15
Various resources can be used to prevent from forgetting things: for example, habitual actions to use external memory devices, metamemory knowledge of external memory devices, script knowledge for planning, and others' aids. The availability of the resources is not equal for anyone, however. The purpose of the present study was to examine developmental changes in contents of the available resources and the relationships among the resources for elementary school children in their homes. The questionnaires concerning the resources were administered to seventy second graders, sixty-six fourth graders, seventy-one sixth graders, and their parents. As results, the children's knowledge increased with grades, while parental aids decreased with grades. Significant (marginally significant) correlation between children's knowledge and parental aids were found in fourth graders only. Moreover, there was a significant (marginally significant) correlation between children's habitual actions to put the room in order and children's script knowledge in fourth and sixth graders, although differences in habitual actions among graders were not significant.
2 0 0 0 OA 食材研究(2) : 翻車魚(マンボウ)の料理
- 著者
- 鳥居 久雄
- 出版者
- 名古屋文化短期大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:09148353)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.41-48, 2014-03-05 (Released:2016-12-29)
2 0 0 0 OA TEST1 大学入試センター試験リスニングテストの波及効果 : 茨城大学入学者の英語学習と大学英語カリキュラム改革への影響(Testing,国際交流「新」時代における大学英語教育カリキュラム刷新)
- 著者
- 斉田 智里
- 出版者
- 一般社団法人大学英語教育学会
- 雑誌
- JACET全国大会要綱
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.195-196, 2009-08-28
2 0 0 0 OA 投球時痛を有する中学生野球選手の身体機能の特徴
- 著者
- 遠藤 康裕 坂本 雅昭
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.303-308, 2019 (Released:2019-06-25)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕簡易的なテストを用いて機能評価を行い,投球時痛を有する選手の身体特徴を明らかにすることを目的とした.〔対象と方法〕対象は中学生野球選手27名とし,投球時痛の有無で2群に分けた.テストは,ショルダーモビリティ,Finger Floor Distance,Heel Buttock Distance(HBD),股関節内旋,しゃがみ込み,片脚立位,フォワードベンド,フォワードベンチ,サイドベンチとした.〔結果〕疼痛群では対照群に対して,HBD,股関節内旋,フォワードベンドで有意に陽性者が多かった.〔結語〕投球時痛を有する選手では,大腿四頭筋柔軟性低下,股関節内旋可動域制限,動的立位バランスの低下を有することが示唆された.
2 0 0 0 IR 自著を語る モンゴルにおける福音派の事例を通して見えてくるもの
- 著者
- 滝澤 克彦
- 出版者
- 東北大学大学院文学研究科宗教学研究室
- 雑誌
- 東北宗教学 (ISSN:18810187)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.101-108, 2015
自著を語る
2 0 0 0 OA オフセット輪転機による騒音, 振動とその対策
- 著者
- 原 剛
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.002-007, 2007 (Released:2010-02-15)
Although Japanese environmental regulations, and health and safety laws set tolerance levels for noise and vibration generated by printing presses, maintaining these levels in web offset presses are becoming increasingly difficult. This is particularly true in terms of noise, as today's presses tend to be larger and provide faster running speeds for the purpose of improving productivity. The most effective means for reducing noise levels is to enclose the entire web press or the printing unit and folder sections of the press in soundproofing barriers. Laying the proper foundation to support the press is essential for minimizing vibration of buildings within the printing plant. Mechanically induced problems with the press can lead to excessive noise and vibration, and daily maintenance is also necessary to protect the press equipment and alleviate these problems.
2 0 0 0 IR 弁護士 原田敬吾とバビロン学会の設立
- 著者
- 森 征一
- 出版者
- 慶應義塾福澤研究センター
- 雑誌
- 近代日本研究 (ISSN:09114181)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.161-179, 1987
福澤門下生特集
2 0 0 0 OA 自然科学系分野における分野間引用関係経年変化の分析
- 著者
- 児玉 閲
- 出版者
- 情報メディア学会
- 雑誌
- 情報メディア研究 (ISSN:13485857)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-17, 2018-05-11 (Released:2018-05-11)
- 参考文献数
- 10
本研究では,自然科学系分野における分野間引用関係の経年変化を明らかにすることを目的とした.Journal Citation Reports 2001-2009 年 Science Edition で継続収録されている 4,463 誌を 22 分野に分類し,分野間引用数を集計した.分野間引用数は,引用元分野と被引用分野の両方の論文数で規格化した(以下,NC(Normalized Citations)と呼ぶ).NC の変化率に有意な相関があり,且つ,被引用分野へ一定の引用数がある引用元-被引用分野の組を抽出した.NC 変化率が正の値(増加傾向)が 14 組,負の値(減少傾向)が 42 組であった.減少傾向に寄与している分野は,Multidisciplinary,Molecular Biology & Genetics など,生命科学分野が多くみられたが、対象とした 4,463 誌以外への引用が増え,引用する雑誌に広がりがあることが分かった.規格化によって、分野による規模(論文数) の影響が排除されていることを確認した.
2 0 0 0 雑談のポイントとしての「リアクション」
- 著者
- 才田 いずみ 稲飯 亜有美
- 出版者
- 日本語教育方法研究会
- 雑誌
- 日本語教育方法研究会誌 (ISSN:18813968)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.76-77, 2019 (Released:2019-07-02)
- 参考文献数
- 7
It is essential for Japanese language learners to have sufficient skills to conduct casual conversations with native speakers to develop their language proficiency as well as their personal networks. The analysis of casual conversations in contact situations shows us the reaction to "iisashi" ―the suspended sentences or the sentence-ending ellipsis is one of the critical points for the smooth interactions and even a learner in advanced level needs practice to give proper reaction to it.