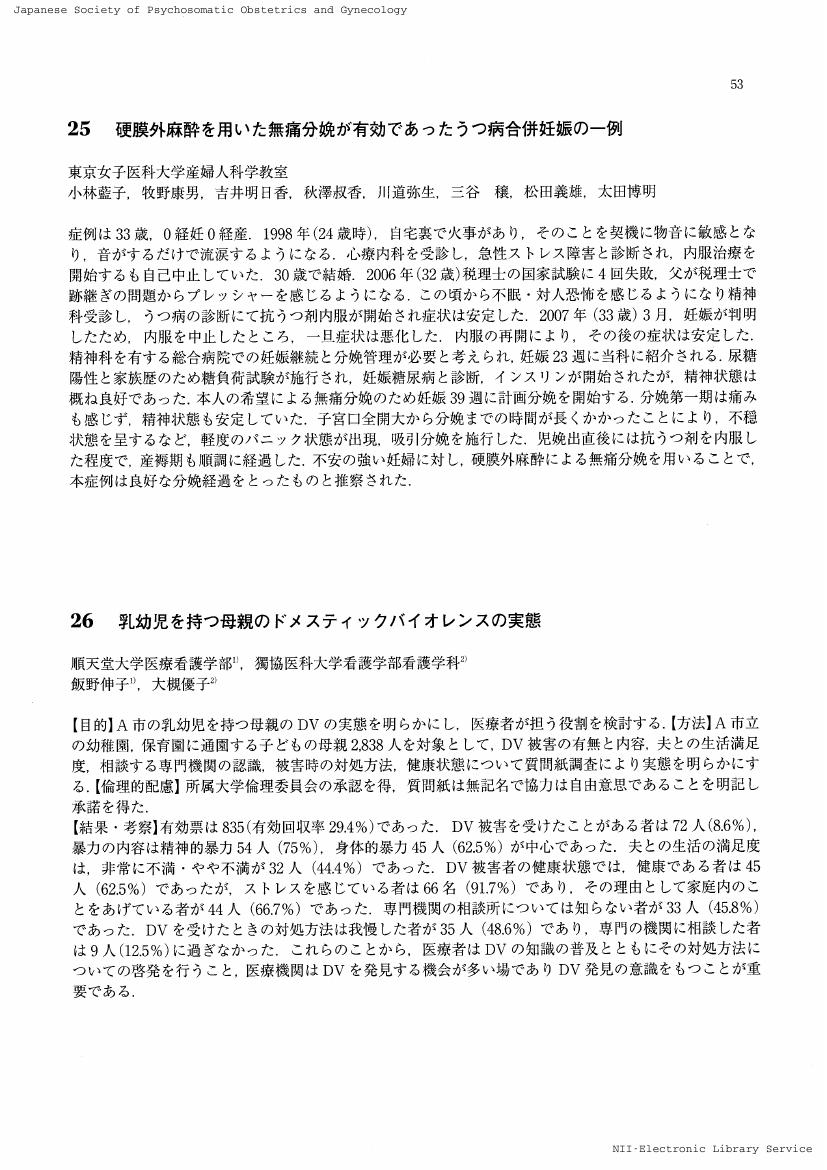2 0 0 0 OA 神戸女学院所蔵資料に見る由起しげ子の音楽教育歴
- 著者
- 津上 智実 Motomi TSUGAMI
- 雑誌
- 女性学評論 = Women's Studies Forum
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.65-86, 2017-03-20
本論では、戦後初の芥川賞受賞作家として知られる由起しげ子(1900~1969)について、神戸女学院音楽部在学時(1918~1921)とその前後の音楽教育歴の輪郭を、本学所蔵資料によって描き出すことを目的とする。「由起しげ子」は本名を「伊原(旧姓、新飼)志げ」と言う。新飼志げは17歳の1918年4月に神戸女学院音楽部に入学し、20歳の1921年1月に中退している。ここでは、1)音楽部在学時の音楽教育、2)山田耕筰(1886~1965)との師弟関係、3)山田耕筰との交流を示す資料について、その概略を描き出す。1)神戸女学院大学図書館所蔵の「音楽レッスン帳」(1907~1923)によれば、新飼志げは1918年春学期と秋学期、1919年冬学期の3学期間にピアノとオルガンと歌のレッスンを並行して受けており、その教材は主に初学者用のものであったと判明した。幼少期にピアノを習う機会を与えられなかったため、必ずしも手が回る弾き手ではなかったようである。2)山田耕筰との師弟関係については、特にその始まりがいつであったかという点で先行研究には大きなばらつきが見られるが、関連史料を精査した結果、1917年2月25日の大阪ホテルでの出会いが最初で、その際に新飼は山田に弟子入りを許されたというのが一番事実に近いという結論に達した。「由起しげ子文庫」には新飼の作曲作品は含まれておらず、対位法の勉強の跡を示す簡単な譜例とメモが残されているだけである。3)由起の長期入院と結婚・渡欧によって作曲の勉強は放棄されたが、それでも山田との交流は生涯にわたって続いたことが、「由起しげ子文庫」所蔵の山田耕筰の署名と献辞入りの出版譜や書簡、また後年の両者の執筆物から明らかとなった。
2 0 0 0 幻想と戦争と--中井英夫論
- 著者
- 松崎 美恵子
- 出版者
- 福岡女子短期大学国語国文学会
- 雑誌
- 大宰府国文 (ISSN:02864401)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.32-39, 2000-03
2 0 0 0 <i>γ</i>-アミノ酪酸の経口摂取による皮膚状態改善効果
- 著者
- 外薗 英樹 上原 絵理子
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.306-311, 2016
- 被引用文献数
- 7
<p>GABA摂取が肌質,並びに,睡眠の質に及ぼす影響を評価することを目的として,肌荒れを自覚し,疲労や睡眠の不調を感じている成人女性を対象に,二重盲検並行群間試験を実施した.その結果,GABA摂取群において頬の皮膚弾力性指標がプラセボ摂取群と比較して有意に改善した.睡眠の質の評価においてはGABA摂取群とプラセボ摂取群の両群ともに摂取開始後に改善がみられたが,有意な群間差はみられなかった.本試験の結果から,GABAの摂取は日頃から疲労や睡眠の不調を感じ,肌荒れの自覚がある成人女性の頬の粘弾性の悪化を抑制する可能性が示された.</p>
2 0 0 0 OA 「ハビトゥス」概念の行為論的射程
- 著者
- 村井 重樹
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.35-51,236, 2008-02-29 (Released:2015-06-06)
- 参考文献数
- 34
This paper aims to reconsider the concept of practice (pratique) in a present that is filled with uncertainty. To accomplish this, it will be useful to examine Bourdieu’s theory of practice (la théorie de la pratique) and his concept of habitus. According to Bourdieu, practice is produced by an embodied habitus, which includes practical hypotheses (hypotheses pratiques) accompanied by the past and the future, and which is engendered by social structures. Hence, habitus is the key to an understanding of practice, not only for Bourdieu, but for us as well. However, it seems that his definition of the relation between habitus and practice excessively restricts the range of practical action (practice). In fact, Bourdieu’s habitus finds its reality in an embodied past, and for this reason he is unable to sufficiently consider the significance of an uncertain present in practice. In contrast, Mead claims that “reality exists in a present” and recognizes that the uncertain present is important to our understanding of practice. According to Mead, past and future are oriented in the present, and novelty is found in it. That is, the present is also a site for the reformulation of meaning. In particular, this will be true for problematic situations which cannot be adequately illustrated using Bourdieu’s habitus. Through this examination of practice from the perspective of an uncertain present, I will try to demonstrate that habitus must be connected with the novelty of the present, and that practical hypotheses are questioned and reconstructed through the novelty that is in the present.
2 0 0 0 OA ボアソナード氏起稿 ABC順 字類撮録表 民法草案 人権之部
- 著者
- Sachie Kanada Hidenori Aiki Kazuhisa Tsuboki Izuru Takayabu
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2019-044, (Released:2019-11-07)
- 被引用文献数
- 8
From 16 to 23 August 2016, typhoons T1607, T1609, and T1611 hit eastern Hokkaido in northern Japan and caused heavy rainfall that resulted in severe disasters. To understand future changes in typhoon-related precipitation (TRP) in midlatitude regions, climate change experiments on these three typhoons were conducted using a high-resolution three-dimensional atmosphere–ocean coupled regional model in current and pseudo-global warming (PGW) climates. All PGW simulations projected decreases in precipitation frequency with an increased frequency of strong TRP and decreased frequency of weak TRP in eastern Hokkaido. In the current climate, snow-dominant precipitation systems start to cause precipitation in eastern Hokkaido about 24 hours before landfall. In the PGW climate, increases in convective available potential energy (CAPE) developed tall and intense updrafts and the snow-dominant precipitation systems turned to have more convective property with less snow mixing ratio (QS). Decreased QS reduced precipitation area, although strong precipitation increased or remained almost the same. Only TRP of T1607 increased the amounts before landfall. In contrast, all typhoons projected to increase TRP amount associated with landfall, because in addition to increased CAPE, the PGW typhoon and thereby its circulations intensified, and a large amount of rain was produced in the core region.
2 0 0 0 キイロショウジョウバエ概日時計機構における温度感受性振動系の解析
本研究ではキイロショウジョウバエ概日活動リズムを制御する時計機構に関して、(1)温度感受性時計がどのような機構で振動するのか、また、(2)温度感受性時計が光感受性時計とどのように協調して概日リズムを制御するのかの2点について解析を行い、以下の成果を得た。恒明温度周期下から恒明恒温条件への移行でリズムが数サイクル継続すること、恒明下で20℃への単一温度変化でリズムが誘発されることがわかった。温度ステップ変化後、PER、TIMともに周期変動が誘発されることから、温度のステップ変化が、PER、TIMなど時計分子の量的変動を介して概日時計の振動を誘発することが示唆された。無周期突然変異系統での実験結果から、温度による振動にはCYC、CLKが必要であることも示唆された。PERの発現を指標として温度周期下で駆動する時計細胞を探索し、脳側方部ニューロン群(LNs)でPERが低温期に発現することが示された。LNを欠失したdisco系統では、温度周期下でも内因的な活動リズムは発現しないことから、上記の結果とあわせて、LNが温度周期下でのリズム発現に主要な役割を担うことが示唆された。クリプトクロームの機能欠損をもつcry^b系統では恒明条件下で長周期(LPC)と短周期(SPC)の2つのリズムを発現する。抗PER抗体を用いた免疫組織化学の結果は、SPCはLNと一部の脳背側部ニューロン群(DN)が、LPCは残りのDNによって制御される可能性を示唆した。光周期と温度周期への同調実験の結果、SPCはより温度同調性が強く、LPCは光同調性の振動体により制御される可能性が示唆された。この結果は、温度周期下でのリズム発現にLNが主要な役割を担うことともよく一致する。cry^b系統の行動リズムの解析から、SPCとLPCは相互作用により通常同調するが、SPCがLPCに対してより強力な同調作用を持つことがわかった。
2 0 0 0 OA 浜松の民芸運動の現代的評価に向けて
- 著者
- 黒田 宏治 阿蘇 裕矢 クロダ コウジ アソ ユウヤ Kohji KURODA Yuya ASO
- 雑誌
- 静岡文化芸術大学研究紀要 = Shizuoka University of Art and Culture bulletin
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.149-152, 2013-03-31
浜松の民芸運動は、浜松の新たな文化やデザインのアイデンティティとなる可能性がある。本稿では、浜松の民芸運動について、郷土史家へのインタビューと地元資料に基づく概略年表整理を行った。浜松の民芸運動の現代的評価に向けて、引き続き研究調査を行っていきたい。
2 0 0 0 女子体育
- 著者
- 日本女子体育連盟 編
- 出版者
- 日本女子体育連盟
- 巻号頁・発行日
- vol.10(11), no.112, 1968-11
2 0 0 0 OA 胎児,出生児からみた無痛分娩
- 著者
- 林 玲子
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.331-336, 2012 (Released:2012-07-05)
- 参考文献数
- 23
分娩の痛みは個人差があるが,陣痛の刺激により母体の血圧上昇,過呼吸を生じるような場合は二次的に臍帯血管の収縮,子宮胎盤血流低下をきたし,さらには間接的に胎児への酸素供給低下などの影響を起こしうることがわかっている.よって硬膜外麻酔による無痛分娩は,母体の痛みを取り除くだけではなく胎児に起こりうる二次的な悪影響を防ぐことが可能である.母体への硬膜外麻酔が与える胎児・新生児への影響は直接的,間接的なものが考えられるが,臍帯血流の維持を念頭に硬膜外麻酔による合併症の早期発見がなされるような麻酔管理が行われていれば,麻酔の利点を最大限に胎児・新生児に還元することが可能である.
2 0 0 0 OA 無痛分娩に求められる硬膜外麻酔
- 著者
- 天野 完
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.237-242, 2008 (Released:2008-04-16)
- 参考文献数
- 16
分娩時の不安感, 疼痛など過度のストレスによって, 過換気により酸素解離曲線は左方移動し, カテコールアミンの遊離などから子宮胎盤血流量は減少する. 胎児にとっては低酸素負荷となり, 特にハイリスク妊娠は無痛分娩の適応となる. 無痛分娩には母児にとって安全で, 十分な効果が得られ, 分娩予後や周産期予後に影響しない方法が望ましく, 硬膜外麻酔が第一選択の方法である. 低濃度局所麻酔薬とオピオイドを併用した持続硬膜外麻酔が主流となりつつあるが, PCEA (patient-controlled epidural analgesia) やCSEA (combined spinal-epidural analgesia) も行われている.
2 0 0 0 OA 周産期センターに麻酔科医のポジションを得た意義
- 著者
- 坊垣 昌彦
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.232-237, 2017-03-15 (Released:2017-04-21)
- 参考文献数
- 2
東京大学医学部附属病院は2011年4月から総合周産期母子医療センターに指定されているが,産科からの要望により2013年4月に麻酔科専門医を配置するための講師ポストが新設され,これを契機に周産期医療に麻酔科がより積極的に関与することが求められるようになってきている.本稿では,筆者が周産期センターのポジションを得てからの約2年間で東大病院での周産期医療がどのように変化してきたかを振り返り,周産期センターに麻酔科医のポジションを得た意義について検討を加えた.他施設での周産期医療の安全性向上のために参考としていただければ幸いである.
- 著者
- 飯野 伸子 大槻 優子
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1-2, pp.53, 2008-06-30 (Released:2017-01-26)
2 0 0 0 OA 日米におけるアクティブ・ラーニング論の成立と展開
- 著者
- 西岡 加名恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.3, pp.311-319, 2017 (Released:2018-04-27)
- 参考文献数
- 65
2 0 0 0 OA 福井県の海底文化財に関する調査
- 著者
- 佐々木 達夫 田中 照久 田﨑 稔也 渡邉 玲
- 出版者
- 金沢大学人文学類歴史文化学コース 大学院人間社会環境研究科 考古学研究室
- 雑誌
- 金大考古 = The Archaeological Journal of Kanazawa University
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.1-13, 2011-01-01
金沢大学人間社会研究域歴史言語文化学系
2 0 0 0 OA IV 社会学とリフレクシヴィティ
- 著者
- 宮本 孝二
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.35-45,131, 2000-05-31 (Released:2016-11-02)
This paper aims to discuss the identity and capacity of sociology as a discipline by referring to Anthony Giddens'social theory. Modern sociology has been specialized into many fields,and social theory which consists of general and macro theory has become only one of them. But we must remember that sociology was born as social theory which had grand and reflexive perspective on modernity. Now when we rethink the identity and capacity of sociology, we are faced with the task of reconstructing social theory. Anthony Giddens, who is one of the leading practioners of contemorary social theory, has constructed the strucrturation theory as a general theory and the theory of modernity as a macro theory, and he is participating in British politics as an adviser to the Labour Party. As he has created a social theory that explores a very wide range of social theories, we can reconstruct social theory by examining his one. To introduce his works briefly and summarize the essential points in it, this paper focuses on the theory of reflexivity. Because reflexivity is not only one of his central concepts, but also the true nature of social theory produced by human reflexive activities. First, I overview the disucssion of reflexiviy in the development of Giddens'social theory. He places an active and reflexive person producing and reproducing social institutions at the center of his social theory and modern society. Second, his theory of reflexivity is arranged into three categories, which are (1) reflexive agent, (2) consequences of reflexive agencies and (3) sociology as a medium of instituutional reflexivity. Third, directions of revising his social theory are showed.His social theory can be reconstructed as a theory of powers. Powers are (1) capabilities of reflexive agent, (2) resources of reflexive agencies and (3) media of instituutional reflexivity.
2 0 0 0 OA YOSAKOI ソーラン祭り参加による感情とメンタルヘルスの改善
- 著者
- 侘美 靖 森谷 きよし
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.117-129, 2006 (Released:2007-03-13)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
本研究は,北海道の YOSAKOI ソーラン祭り参加者を対象に,練習及び祭りへの参加による感情及びメンタルヘルスの向上について調査することを目的とした.POMS テストの結果,約 4ヶ月の練習期間中にオーバートレーニングの様子は認められなかった.踊り練習前後の感情変化を Mood Check List-Short Form 1 により測定した結果,5, 15, 25回目練習日のいずれの時期においても快感情得点は練習後に有意に向上した.練習前に比べ練習後にリラックス感得点が有意に向上したのは15回目練習日以降であったが,対照群より低いレベルの変化であった.不安感得点に有意な変化は認められなかった.精神的健康パターン診断検査の結果,練習開始期に比べ,祭り後の心理的・社会的ストレス度は改善していた.YOSAKOI ソーラン祭りと練習への参加は,北国住民の感情及びメンタルヘルス改善に対する効果が期待される.