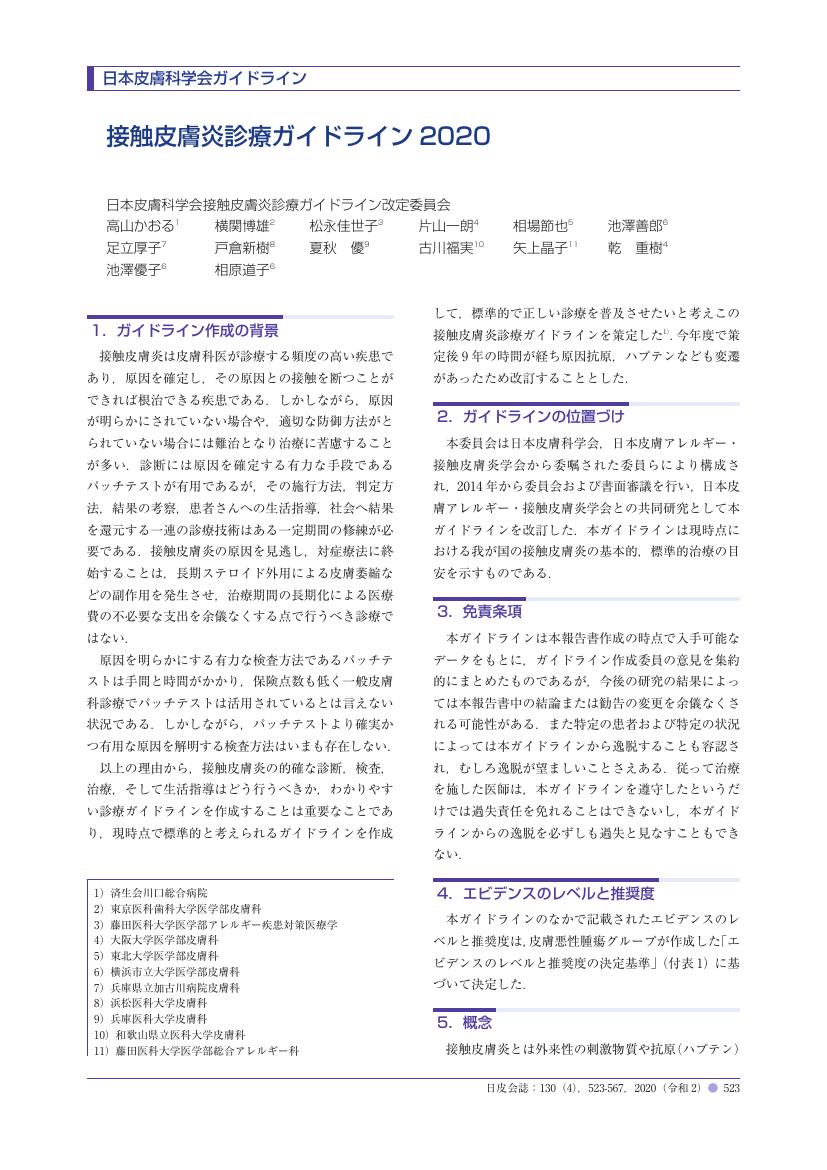29 0 0 0 OA アニメにおける表現の維持と越境 : 入射光・レンズフレアの調査に基づいて
- 著者
- 小倉 健太郎
- 出版者
- 成城大学文芸学部
- 雑誌
- 成城文藝 = The Seijo Bungei : the Seijo University arts and literature quarterly (ISSN:02865718)
- 巻号頁・発行日
- no.233, pp.96-73, 2015-12
- 著者
- 岩本 拓也 小倉 加奈代 西本 一志
- 雑誌
- 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.16, pp.1-8, 2012-10-25
恋人間の愛着行動 (いわゆる 「いちゃいちゃ」) は,幸福感を得るためや相手との関係をより良いものにするために重要な行為である.恋人達の多くは,常に愛着行動をとりたいと願っている.しかしながら公共空間では,目の前にパートナーがいるにもかかわらず愛着行動を行うことができない.従来の恋愛支援技術の研究は,遠距離恋愛者を対象に研究開発が進められてきたが,近距離恋愛者に対しても支援すべき課題が残されていると考える.そこで我々は,公共空間内での対面状況において,周囲に不快感を与えることなく愛着行動を行えるメディアの研究開発を進めている.本稿では,このメディアの実現に向け,どのような種類の行動を伝え合うことが有効かに関する基礎的検証を行う."Acting cozy" is important for lovers to feel happiness and to improve their relationships much better. Many lovers desire to always act cozy. However, it is actually difficult to act cozy in a public space although they are together there. Whereas the ordinary research efforts have attempted to mainly support long-distance lovers, there are also several issues to be solved even for short-distance lovers. Accordingly, we have been studying a medium that allows the short-distance lovers who stay together to convey cozy actions even in the public space without disgusting people around them. This paper investigates what kind of cozy actions should be transmitted between the lovers being together in the public space.
28 0 0 0 OA 基礎代謝の季節変動について
- 著者
- 島岡 章 町田 和彦 熊江 隆 菅原 和夫 倉掛 重精 岡村 典慶 末宗 淳二郎
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.3-8, 1987-04-01 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 4
Seasonal variation of basal metabolism was measured on seven young male (the Ground Self-Defence Force Officials) aged 19-26 for twelve months (from March 1983 through February 1984) at the Beppu Post in Oita. The results are as follows:The basal metabolism fluctuates like sine curve. The highest value (5.2% higher than the annual mean) is obtained in April and the lowest (5.8% lower) is in October. Therefore, the annual deviation in the basal metabolism was 11.0% from the annual mean. The annual mean basal metabolism corrected to twenties, is 39.9 kcal/m2/hr, and this value is 6.6% higher than the reference value (37.5 kcal/m2/hr) . In Japanese, it has been accepted that basal metabolism is lower in summer and higher in winter, and the reasons of the seasonal variation are explained by the wide range of the temperature throughout the year, and by the lower ratio in fat intake. Our results generally agree them.
28 0 0 0 OA 液水/液酸エンジンの開発
- 著者
- 棚次 亘弘 成尾 芳博 倉谷 健治 秋葉 鐐二郎 岩間 彬 TANATSUGU Nobuhiro NARUO Yoshihiro KURATANI Kenji AKIBA Ryojiro IWAMA Akira
- 出版者
- 宇宙科学研究所
- 雑誌
- 宇宙科学研究所報告. 特集: 液水/液酸エンジンの開発研究報告 (ISSN:02859920)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.55-106, 1983-03
The Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) has developed the two thrust level of LH_2/LOX propulsion system; one is the 7-ton thrust level one and the other is the 10-ton thrust level one. The 7-ton thrust level engine was aimed at usimed at using for the second stage of the Mu vehicle. And the 10-ton thrust level engine is planned to back up the H-1 project being performed by the National Space Development Agency (NASDA). The both engines are the gas generator cycle which consists of the tubular wall thrust chamber, the "ISAS Arrangement" turbopump, the "reverse-flow" type gas generator and the solidpropellant turbine spinner. The development of the 7-ton thrust level engine has started in 1976. By 1980 have almost finished the development tests of its major components. In early 1980 the engine system has been integrated and then the verification tests have been carried out. On the other hand, the development study of the 10-ton thrust level engine started in 1979. In midyear 1981 the engine system has been completed. The both engines were combined with the battle-ship type of tank system, and stage firing tests were carried out successfully from Sep. 1981 through Apr. 1982. The 7-ton thrust level engine worked well within the range from 78% to 1l8% of its rated power. And the 10-ton thrust one worked well within the range from 75% to ll3%. In the present paper, an outline of the LH_2/LOX engine systems developed in ISAS, the progress in the establishing of an operation of engine systems and the performance capability of two systems are described.
28 0 0 0 IR 『百鬼夜行絵巻』に描かれた妖怪と仏教
- 著者
- 名倉 ミサ子
- 出版者
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科
- 雑誌
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集(日本文化編) = Bulletin of the Graduate School of International Cultural Studies, Aichi Prefectural University (Japanese Culture) (ISSN:18847536)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.15-28, 2017-03-24
28 0 0 0 OA 多喜二書き込み、および小林多喜二伝 補 5
- 著者
- 倉田 稔
- 出版者
- 小樽商科大学
- 雑誌
- 商学討究 (ISSN:04748638)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.1-36, 2006-03-24
- 著者
- 倉橋 弘 柿沼 進
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.167-200, 2015-12-25 (Released:2016-06-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 3
日本産のニクバエ全種の検索表を作成するために,ニクバエの標本を再検討したところ,新たに本州(千葉県)より採集されたニクバエが新属新種であることがわかったので,パペニクバエ属キサラズニクバエPapesarcophaga kisarazuensis Gen. nov., sp. nov.として記載した.日本昆虫目録(倉橋,2014)には36属119種が記録されているが,その後に2種ワタナベギングチヤドリニクバエOebalia pseudopedicella Kurahashi & Kakinuma, 2014とタテヤマギングチヤドリニクバエO. pseudoharpax Kurahashi & Kakinuma, 2014が記載されたので,キサラズニクバエを含めると日本産ニクバエは122種となった.ニクバエは外形がよく似ており,特に,ニクバエ亜科のニクバエでは,これまで,主に雄の外部生殖器の形態が種の分類に使われてきたが,外形でも出来るだけ属や種が検索できるように試みて,122種の検索表を作製した.チェックリストは著者らの調べた標本に基づいて作製し標本のデ-タも付した.属の数については亜属からもとの属位にもどしたものもあり43属となった.
27 0 0 0 眼球使用困難症候群としての眼瞼痙攣
- 著者
- 若倉 雅登 山上 明子 岩佐 真弓
- 出版者
- 日本神経眼科学会
- 雑誌
- 神経眼科 (ISSN:02897024)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.421-428, 2017-12-25 (Released:2018-01-29)
- 参考文献数
- 10
眼球や第一次視覚野までの経路が正常だとしても,例えば何らかの原因で開瞼が不能であればその機能を利用できない.我々はこうした症例を,医学的分類というより,当該患者が何に不都合を感じているかという観点から「眼球使用困難症候群」と名づけた.この症候群は,そうした不都合を有する病態に広く用いたいと考えるが,同症候群の命名のきっかけになった最重症の8症例を提示し,それらの臨床的特徴を明らかにする.8例に共通するのは,微細な光に過敏に反応し,眼球の激痛や高度の羞明に常時悩まされている点である.8例はいずれも,暗い部屋でも閉瞼するだけでなく,アイマスクや遮光眼鏡の使用は日々の生活で常に必需であった.大半の症例はジストニアのような動的異常よりも感覚異常のほうが目立った.一部の症例は,線維筋痛症を含む身体痛,舌痛症,顎関節症や抑鬱を合併していた.また,向精神薬の連用や離脱,頭頸部外傷や何らかの脳症などが契機となって発症していた.このように,全例眼瞼痙攣の最重症例と類似点があるが,完全に一致するかは今後の問題である.眼瞼痙攣は神経科学では局所ジストニアとして理解されているが,本質は,眼球使用ができないことにある.それゆえ,眼球使用困難症候群の一部を成すものとして扱い,特に高度なものは視覚障害者として扱うのが妥当であることを主張する.今回提示した8例以外にも,眼球使用困難症候群はさまざまな場合があると考えられ,症候発現に関する因子も種々であろう.日常生活において高度の不都合があるにもかかわらず,日本の現今の障害者福祉法では,視力のみ及び視野でしか評価しないために,視覚障害として認定されない.このように,眼球使用困難症候群では福祉的救済が必要であるにもかかわらず,法的にこのような障害が想定されていないことが問題点であることを,臨床医学の立場から指摘した.
27 0 0 0 OA 接触皮膚炎診療ガイドライン2020
27 0 0 0 OA 『百鬼夜行絵巻』に描かれた妖怪と仏教
- 著者
- 名倉 ミサ子
- 出版者
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科
- 雑誌
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集(日本文化編) = Bulletin of the Graduate School of International Cultural Studies, Aichi Prefectural University (Japanese Culture) (ISSN:18847536)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.15-28, 2017-03-24
27 0 0 0 OA 宮崎県北川の河川感潮域に造成した人工ワンドにおける魚類,カニ類,甲虫類の定着状況
- 著者
- 中島 淳 江口 勝久 乾 隆帝 西田 高志 中谷 祐也 鬼倉 徳雄 及川 信
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.183-193, 2008 (Released:2009-03-13)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 6 3
宮崎県延岡市の五ヶ瀬川水系北川の河川感潮域に人工的に造成されたワンドにおいて,2001年から2006年にかけて,生物の定着状況について調査を行った.人工ワンドは,従来あった天然の既存ワンドが河川改修により失われるため,その代替環境として,その上流の河川敷を,間口50m,奥行き400mにわたって新たに掘削して造成されたものである.1.調査の結果,72種の魚類,12種のカニ類,7種の甲虫類が採集され,合計91種の生物の生息場所として機能していることが明らかとなった.2.ワンドの底層は年を追う毎に起伏が生じ,平坦に造成された底層は5年後には浅い場所と深い場所で約100cmもの差が生じていた.塩分躍層は,満潮時,干潮時ともに水面下1mより深い水深で生じていた.3.ワンドの奥部には泥干潟やコアマモ域が自然に生じ,それらの環境を好む魚類,カニ類,甲虫類が定着した.4.従来あった天然の旧ワンドと人工ワンドにおいて,夏季に出現した魚類種数に大きな違いはなく,人工ワンドが旧ワンドの代替環境として十分に機能しているものと考えられた.5.感潮域において生物多様性保全を目的とした人工ワンドを今後造成する際には,安定した塩分躍層が出来るように,干潮時でも1m以上の水深を確保する構造にすること,水際域や干潟が自然に出来るように,造成時に緩傾斜区間を多く配置すること,また,ヨシ植生域をなるべく残すこと,など多様な環境構造を創出することを意識して設計することが特に重要と考えられた.
27 0 0 0 IR 『現代存在論入門』のためのスケッチ(第1部)
- 著者
- 倉田 剛
- 出版者
- 九州国際大学
- 雑誌
- 九州国際大学教養研究 (ISSN:13410504)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.119-171, 2009-07
26 0 0 0 OA 諸外国の給付付き税額控除の概要
- 著者
- 鎌倉治子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.678, 2010-04-22
26 0 0 0 OA この本! おすすめします 日本(人)にとって,科学とは?
- 著者
- 佐倉 統
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.757-760, 2018-01-01 (Released:2018-01-01)
26 0 0 0 未利用資源「キャベツの芯」の成分とそのギョウザたねへの活用
- 著者
- 工藤 美奈子 小泉 昌子 山本 遼 倉田 幸治 千代田 路子 有泉 雅弘 峯木 眞知子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.664-672, 2021
<p> キャベツは, カット野菜の需要に伴い、食品企業において食品ロス対策の重要な野菜であり、家庭でも食品ロスとして問題になる. 食品ロス対策としてキャベツの有益な利用方法を見出すことを目的として, キャベツの芯部の活用方法について検討した.</p><p> キャベツの芯部の特性を把握するために, キャベツを葉部, 芯部, 芯上部, 維管束部, 中心部, 芯周辺葉部に分けて重量を測定した. また, これらの部位の一般成分, 遊離アミノ酸, 糖分, においの成分を測定した。芯の維管束部には好まれないにおいがあったため, 10種の調味料および香辛料を添加した液を用いて, キャベツの芯のにおい抑制効果を検討した。その結果より, 味の好みについて高い値を示した3種の調味料および香辛料を添加した液を用いてギョウザ試料を調製した。ギョウザのたね試料のテクスチャーと水分含有率を測定後, ギョウザ試料の官能評価を実施した.</p><p> 重量測定より, 芯部の重量は採取時期による差がみられないことが明らかとなった. 成分分析より, 芯部は葉部と比較して, 糖含量全体で1.5倍, スクロースを9.3倍含有し, 糖含量が多いため甘いことが示唆された. ギョウザたねに活用するには, 白ワインやローリエ, 味噌の使用が味の好みの向上に効果的であった.</p><p> 本研究より, キャベツの芯部は特性を考慮すると有益に活用できる部位であり, ギョウザへの活用を示唆し, 食品ロス削減に寄与できる未利用資源であることが判明した.</p>
26 0 0 0 OA ニーチェ哲学における女性というメタファー
- 著者
- 大倉 朋子
- 雑誌
- 哲学会誌 (ISSN:03886247)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.25-48, 1998-07-01
- 著者
- 高倉文紀〔ほか〕著 小松克彦オフィスK21編
- 出版者
- ティーツー出版
- 巻号頁・発行日
- 1999
26 0 0 0 OA 国内外来種となった絶滅危惧種:その取り扱いと保全をめぐって
- 著者
- 鬼倉 徳雄 渡辺 勝敏
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.143-148, 2016-11-05 (Released:2018-06-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
26 0 0 0 OA ストレッチングの筋疲労回復に関する研究
- 著者
- 坂上 昇 大倉 三洋
- 出版者
- 学校法人高知学園 高知リハビリテーション学院
- 雑誌
- 高知リハビリテーション学院紀要 (ISSN:13455648)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-7, 2001-03-31 (Released:2018-08-29)
- 参考文献数
- 9
ストレッチングはスポーツ活動後に疲労回復を促し,障害予防,パフォーマンスの維持・向上といった目的で実施されている.しかし,その実施状況は決して高率ではなく,その原因はストレッチングの効果が十分に理解されていないためと考えられる.そこで本研究は,健常成人男性4名(平均年齢20歳)を対象に,ストレッチングの筋疲労回復効果について検討した.自転車エルゴメーター(COMBI社製;POWERMAX-VⅡ)による30秒間全力駆動を主運動として,その後10分間の休息を取らせることを2セット行った.その休息時に安静臥位,軽運動,ストレッチングを実施した.検討指標として筋柔軟性,血中乳酸値,作業能力,アンケートを取り上げた.筋疲労による筋柔軟性低下の予防効果については軽運動が効果的であり,ストレッチングは大腿直筋においてはあまり効果がなく,ハムストリングスにおいても安静臥位とあまり差がない傾向を示した.血中乳酸値の回復については,ストレッチングは安静臥位と比較すると低い傾向にあるがその回復傾向には差が見られなかった.作業能力の回復については軽運動が比較的良く,ストレッチングが低い傾向を示した.このように,激運動後の筋疲労回復に対してストレッチングは全ての指標において安静臥位とあまり差がなく,効果的でない傾向を示した.今回の結果は,運動後の筋疲労の速やかな回復という観点では,一般的に認識されているストレッチングの効果を否定する結果となった.しかし,今回の結果は,ストレッチングが身体に与える影響を全て否定するものではない.