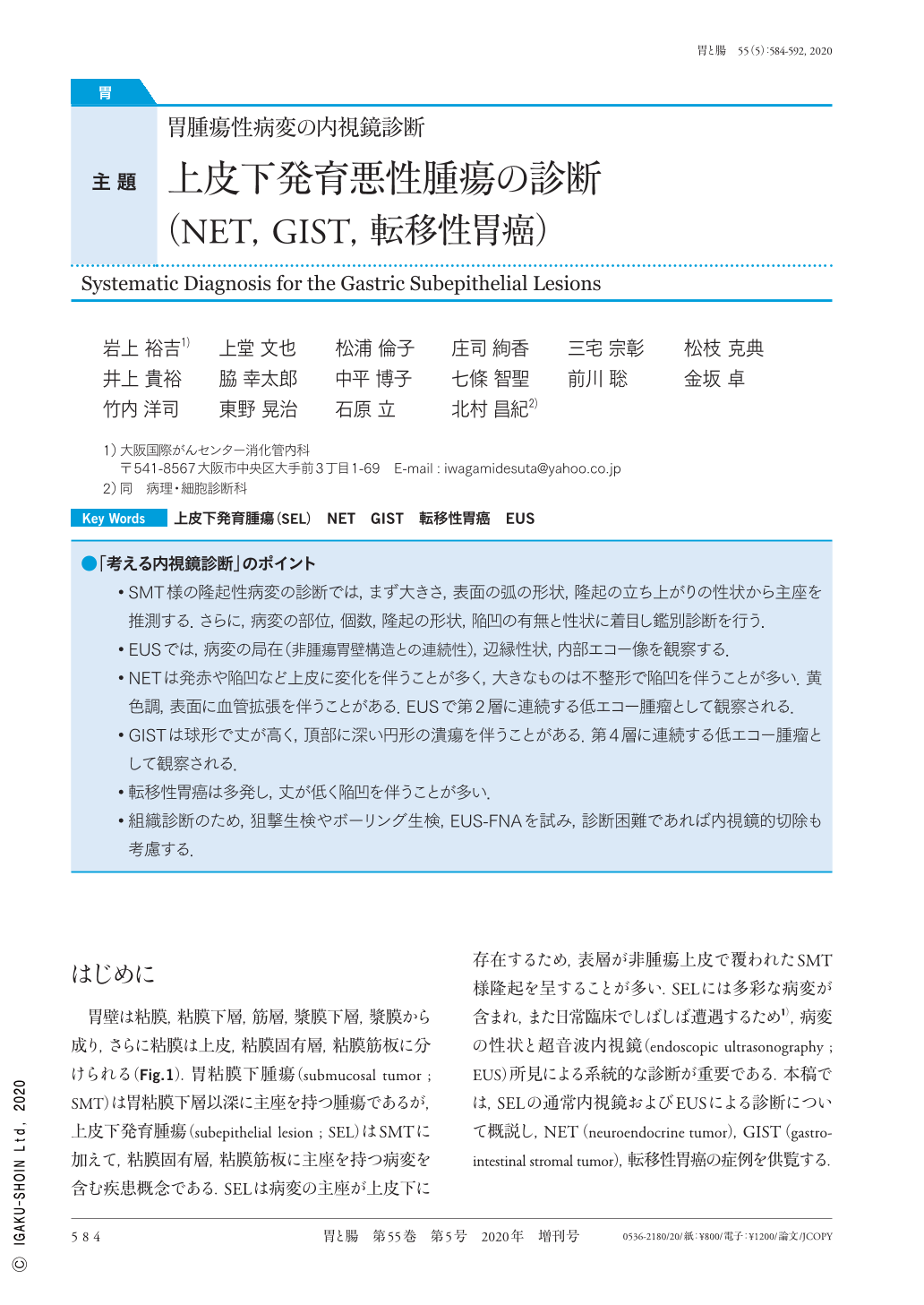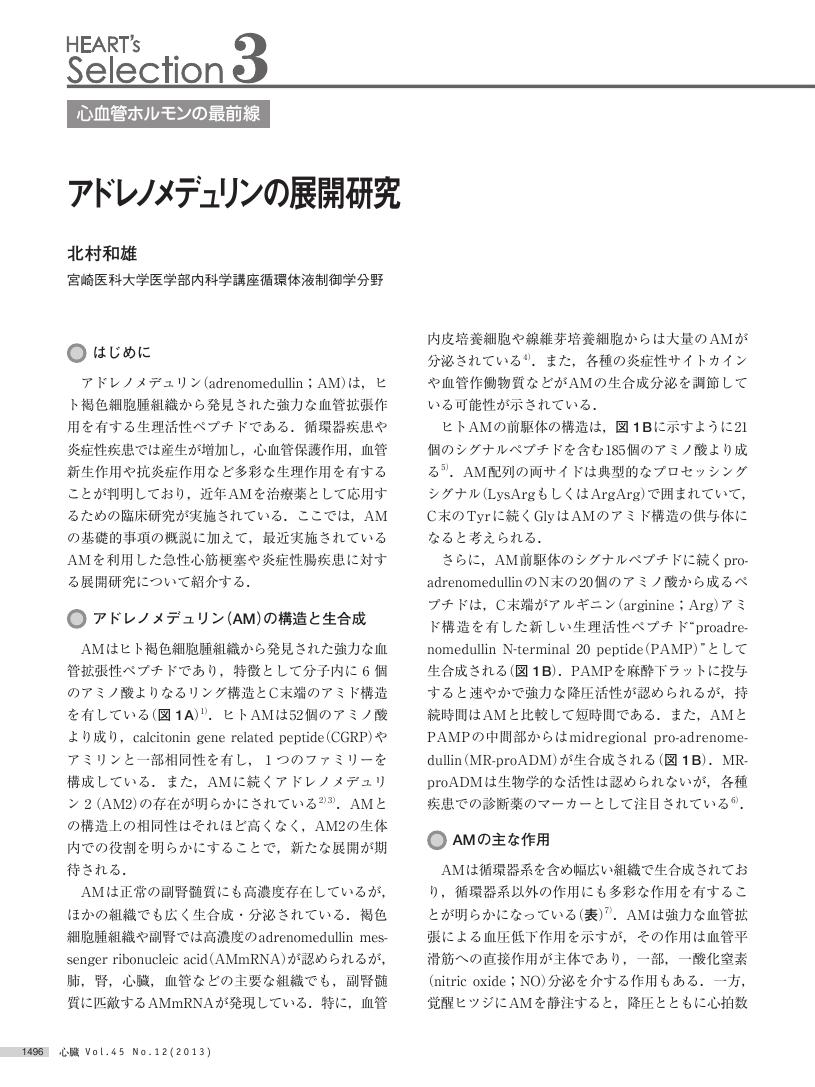- 著者
- 高齢者のための健診・予防医療のあり方検討委員会 津下 一代 北村 明彦 德田 治彦 森山 優 吉村 典子 辻川 明孝 小川 郁 吉田 正貴 福井 敏樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.712-748, 2022 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 67
5 0 0 0 OA 日本産淡水魚類の分布域形成史
- 著者
- 渡辺 勝敏 高橋 洋 北村 晃寿 横山 良太 北川 忠生 武島 弘彦 佐藤 俊平 山本 祥一郎 竹花 佑介 向井 貴彦 大原 健一 井口 恵一朗
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.1-38, 2006-05-25 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 247
- 被引用文献数
- 6
The biogeography of freshwater fishes in Japan was reviewed in terms of achievements and perspectives. In the last three decades, biogeographic studies have changed from earlier descriptions of the freshwater fish fauna, based on the Linnean classification system, to phylogenetic approaches using various molecular markers. Especially, the phylogeographic approach, which explores the formation of geographic distribution patterns of genealogical lineages within species, has become predominant. Analyses of genuine freshwater fishes have disclosed their speciation and dispersal patterns throughout temperate East Asia since the Neogene, along with the formation of the Japanese Archipelago. In particular, molecular clocks of mitochondrial DNA have played an important role in examinations of biogeographic relationships between the Japanese Archipelago and Chinese continent/Korean Peninsula, and vicariance by Fossa Magna in central Honshu Island. Patterns of range expansion through the sea and landlocking in coldtemperature euryhaline fishes have indicated their speciation and distribution dynamics under the fluctuating climatic conditions of the Plio-Pleistocene. Likewise, phylogeographic implications of unusual biological entities arising from interspecific hybridization or gynogenesis have been discussed. Nevertheless, despite the emphases given to some groups, the present knowledge of phylogeographic patterns of Japanese freshwater fishes is for the most part still insufficient for quantitative analyses of the overall history of the freshwater fish fauna and geographic regions of Japan. Improved research techniques and methodologies for the integration of findings from multiple taxa and/or genes are essential. Further, evolutionary formation of distributional ranges should be considered together with ecological biogeography, including the processes of local adaptation, interspecific interaction and extinction. Modern day disturbances of freshwater fish distributions, including fish transportation, are rapidly leading to artificial distribution patterns and extinctions. Exhaustive phylogeographic analyses should be necessary as a primary requirement for conserving freshwater fish biodiversity in Japan.
- 著者
- 永田 貴聖 有薗 真代 堀江 有里 北村 健太郎 山本 崇記
- 出版者
- 立命館大学生存学研究センター
- 雑誌
- 生存学研究センター報告
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.222-293, 2010-11
5 0 0 0 OA 原色日本植物図鑑草本編III(単子葉類)に発表した新名及び新見解
- 著者
- 岩上 裕吉 上堂 文也 松浦 倫子 庄司 絢香 三宅 宗彰 松枝 克典 井上 貴裕 脇 幸太郎 中平 博子 七條 智聖 前川 聡 金坂 卓 竹内 洋司 東野 晃治 石原 立 北村 昌紀
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.584-592, 2020-05-24
●「考える内視鏡診断」のポイント・SMT様の隆起性病変の診断では,まず大きさ,表面の弧の形状,隆起の立ち上がりの性状から主座を推測する.さらに,病変の部位,個数,隆起の形状,陥凹の有無と性状に着目し鑑別診断を行う.・EUSでは,病変の局在(非腫瘍胃壁構造との連続性),辺縁性状,内部エコー像を観察する.・NETは発赤や陥凹など上皮に変化を伴うことが多く,大きなものは不整形で陥凹を伴うことが多い.黄色調,表面に血管拡張を伴うことがある.EUSで第2層に連続する低エコー腫瘤として観察される.・GISTは球形で丈が高く,頂部に深い円形の潰瘍を伴うことがある.第4層に連続する低エコー腫瘤として観察される.・転移性胃癌は多発し,丈が低く陥凹を伴うことが多い.・組織診断のため,狙撃生検やボーリング生検,EUS-FNAを試み,診断困難であれば内視鏡的切除も考慮する.
5 0 0 0 OA 中鎖脂肪酸トリグリセリドが有効であつた総胆管結石症に肝硬変症を伴つた症例
- 著者
- 北村 次男 中川 史子 堀内 成人 清永 伍市 乾 久朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.7, pp.628-633, 1970-07-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
46才の男. 33才ころより発熱,右下肋痛,黄疸の典型的な胆石発作をくり返えし,内科的な治療により一時軽快していた.約2年前より発作が頻発するようになつた.腹腔鏡と肝生検で肝硬変を発見,炎症症状も残存するためゾンデ療法を主とした内科的治療を行なつたが軽快しなかつた.食餌脂肪源としてトリオクタノインを33%に含有する粉末(以下MCT末と略)を1日120G与えたところ,体重が46.5kgから4カ月目には53.5kgと著明に増加した.胆石発作も3力月間は全く発生せず,その後1カ月に1~3回の発作が見られたが, MCT末投与前に比してその頻度は少なかつた.血清アルカリフォスファターゼ値もMCT末投与7カ月目から正常範囲になつた.この時点で再度腹腔鏡検査を行なつたところ肝硬変は前回とほゞ変らず,同時に行なつた直接胆のう造影により総胆管結石を確認し,その摘出に成功した.
5 0 0 0 OA 映画女優・司葉子に聞く― スター女優と衣裳の関係―
- 著者
- 志村 三代子 北村 匡平
- 出版者
- 都留文科大学
- 雑誌
- 都留文科大学研究紀要 = 都留文科大学研究紀要 (ISSN:02863774)
- 巻号頁・発行日
- no.85, pp.287-296, 2017-03-01
紹介・インタビュー
5 0 0 0 OA 社会福祉で用いられる外来語(その2)
- 著者
- 北村 和子 池添 博彦
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.37-47, 2009-03-31
現在、社会福祉の領域では多くの外来語が使用されている。その多くは英語からの借用語であるが、その他からの借用語も認められる。 用いられる外来語の語源について、ラテン語(羅語)およびギリシャ語(希語)まで遡って調べてみた。ゲルマン語からの借用語は英語の他にドイツ語を、ロマンス語からの借用語は相当するフランス語、イタリア語またはスペイン語を示した。 外来語は借用される過程で意味の変容を生ずることがあるので、それについても論じている。
5 0 0 0 OA 煎液にmicroRNA? 金銀花由来microRNAのウイルス増殖抑制作用
- 著者
- 北村 雅史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.440, 2020 (Released:2020-05-13)
- 参考文献数
- 5
スイカズラ(Lonicera japonica)は北海道から九州および朝鮮半島,中国に分布するつる性の常緑低木である.金銀花はスイカズラの花を基原とした生薬で,5〜6月に咲く白い花が数日経過すると黄色く変化し,白と黄の花が咲いている姿から名づけられている.金銀花は清熱,解熱作用を期待し使用され,臨床では炎症や細菌性疾患によく用いられている.金銀花が配合される「銀翹散」は,清時代の医学書「温病条弁」に収載されている薬方であり,この銀翹散に基づく処方「銀翹解毒散」のエキスにインフルエンザウイルス増殖抑制効果が報告されている.今回,Huangらは金銀花由来のmicroRNA(miRNA)が水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)の複製を阻害することを明らかにしたので紹介したい.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) 中薬大辞典,小学館,東京,1985, pp.523-526.2) Miyazaki T., Nihon Yakurigaku Zasshi, 140, 62-65(2012).3) Huang Y. et al., J. Neurovirol., 25, 457-463(2019).4) Zhang L. et al., Cell Res., 22, 107-126(2012).5) Zhou Z. et al., Cell Res., 25, 39-49(2015).
5 0 0 0 OA オピオイドによる内分泌機能異常
- 著者
- 田渕 優希子 安田 哲行 北村 哲宏 大月 道夫 金藤 秀明 井上 隆弥 中江 文 松田 陽一 植松 弘進 真下 節 下村 伊一郎 柴田 政彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.17-23, 2013 (Released:2013-03-22)
- 参考文献数
- 38
近年,非がん性慢性痛に対するオピオイド処方の選択肢が広がったことにより,オピオイドによる内分泌機能異常発症に留意する必要性がある.内分泌機能異常としては性腺機能低下症が最も多いが,副腎機能低下症や成人GH(成長ホルモン)分泌不全症の報告例も散見される.これらの内分泌機能異常は単に患者のQOLを低下させるのみならず,さまざまな代謝異常,臓器障害を呈し,時に生命の危機にかかわる病態へと進展することもある.現時点で,これらの内分泌機能異常がどのような患者に惹起されやすいかは明らかではなく,また内分泌異常の診断も必ずしも容易ではない.しかし,これらの内分泌機能異常はオピオイドの減量,中止,あるいは非オピオイド系鎮痛薬への変更,ホルモン補充療法により改善可能な病態であることから,オピオイド投与中の患者において決して見逃してはならない副作用の一つと考えられる.オピオイドによる内分泌機能異常について基礎医学的および臨床医学的見地から解説する.
- 著者
- 北村 行伸
- 出版者
- 日本証券アナリスト協会
- 雑誌
- 証券アナリストジャーナル (ISSN:02877929)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.28-37, 2011-01
5 0 0 0 IR 藤原実方雑考
- 著者
- 北村 杏子
- 出版者
- 青山学院女子短期大学
- 雑誌
- 青山學院女子短期大學紀要 (ISSN:03856801)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.63-81, 1979-11-10
5 0 0 0 日本人英語学習者の英文エッセイのエラーがエッセイ評価に及ぼす影響
- 著者
- 北村 まゆみ
- 出版者
- 全国英語教育学会
- 雑誌
- 全国英語教育学会紀要 (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.169-184, 2011
The purpose of this paper is to examine whether errors affect the quality of essay writing by Japanese EFL university students. Using a decision tree analysis, a total of 134 essays on two topics from a corpus written by Japanese university students were selected and analyzed. The results showed that the ratio of errors per word was not an influential predictor affecting writing quality in essays on the topic "school education," whereas it was a predictor of essay scores in the case of the other topic, "money." Our qualitative analysis also revealed that students at the Middle level produced sentence fragments and even learners at the High level made frequent errors in subject-verb agreements. These results suggest that errors have some influence on essay evaluation.
5 0 0 0 OA アドレノメデュリンの展開研究
- 著者
- 北村 和雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.12, pp.1496-1502, 2013 (Released:2014-12-27)
- 参考文献数
- 25
5 0 0 0 OA 『水左記』の研究 ―康平七年閏五月~六月―
- 著者
- 北村 安裕 久米 舞子 黒須 友里江 重田 香澄 堀井 佳代子
- 出版者
- 岐阜聖徳学園大学
- 雑誌
- 岐阜聖徳学園大学紀要 教育学部編 = The annals of Gifu Shotoku Gakuen University. Faculty of Education (ISSN:13460889)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.90-75, 2021-02-28
5 0 0 0 OA CHI 2021のGeneral Chairを引き受けることになった経緯
- 著者
- 北村 喜文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.10-14, 2021-03-31 (Released:2021-05-01)
- 参考文献数
- 20
5 0 0 0 IR 『水左記』の研究 : 康平七年正月~四月
- 著者
- 北村 安裕 磐下 徹 堀井 佳代子 宮川 麻紀
- 出版者
- 岐阜聖徳学園大学
- 雑誌
- 岐阜聖徳学園大学紀要. 教育学部編 = The annals of Gifu Shotoku Gakuen University. 岐阜聖徳学園大学教育学部紀要委員会 編 (ISSN:13460889)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.86-69, 2020
5 0 0 0 さつまいもの加熱調理について
- 著者
- 山口 美代子 樋上 純子 北村 由香里
- 出版者
- 園田学園女子大学
- 雑誌
- 園田学園女子大学論文集 (ISSN:02862816)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.329-337, 1994-12-30
- 被引用文献数
- 3
1.さつまいもの糖化の適温は,65℃前後であった。2.さつまいもの糖化酵素の糊化デンプンに対する活性適温は,55℃前後であり調理の際の糖化適温とは,一致しなかった。3. 65℃での糖化酵素の作用は10分以内にほぼ完了した。4. 65℃前後の通過時間と糖の生成量との間には関連が認められた。5.各種加熱方法による生成糖量は,生いも1g当たりに換算すると乾式加熱よりも湿式加熱の方が多かった。6.生成糖量が少ないにもかかわらず,焼きいもが甘く感じられるのは蒸発水分が多く糖が濃縮されたためと考えられる。