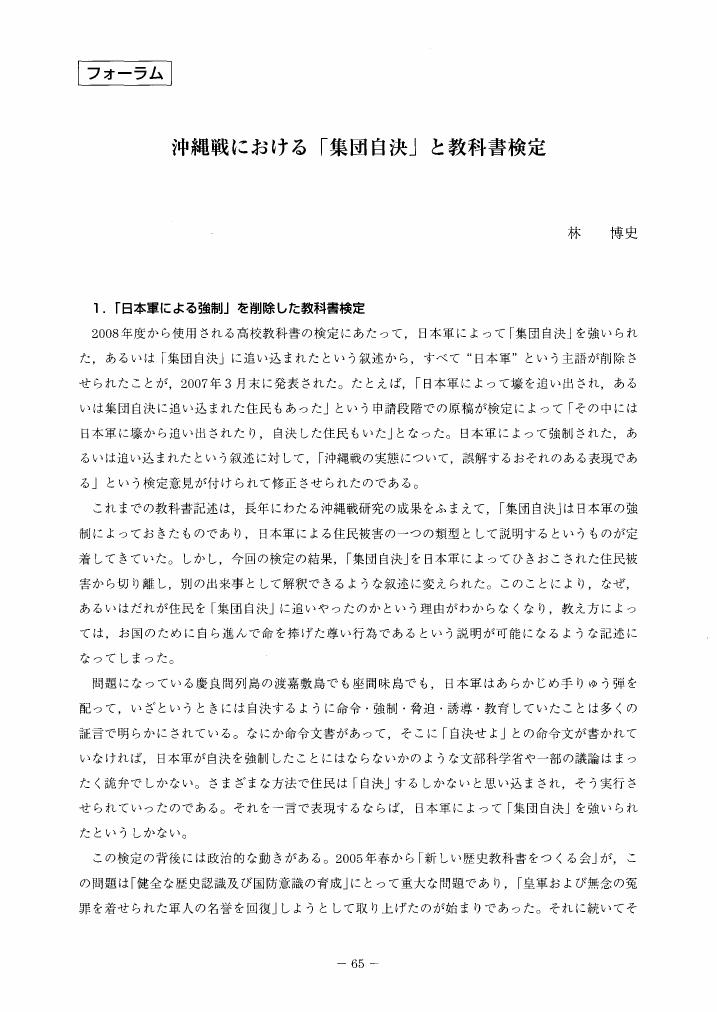73 0 0 0 煎餅を用いた食塊形成能力からみた咀嚼能力評価法
- 著者
- 本間 済 河野 正司 武川 友紀 小林 博 櫻井 直樹
- 出版者
- 日本顎口腔機能学会
- 雑誌
- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.151-160, 2004-04-30
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 8
咀嚼能力を評価するには,粉砕から食塊形成および嚥下までの全過程を観察する必要がある.しかし,これまで種々行われてきた咀嚼能力の評価方法は,その大半が粉砕能力評価を主体とした評価法であった.そこで,食塊形成能力を含めた咀嚼能力を簡易に評価できる方法を考案し,有効性の検討を行うことを目的として以下の実験を行った.食塊形成能力の指標を唾液分泌能力と舌側移送能力の2つと考え,吸水量の異なる煎餅における嚥下までの咀嚼回数が,それら食塊形成能力と,どのような関係にあるかの検討を行った.被験者は,健常有歯顎者(男性14名,女性7名)とした.舌側貯留率と粉砕度は,ピーナッツを一定回数咀嚼させ計測した.また,唾液分泌量と煎餅の嚥下までに要した咀嚼回数を計測し,それぞれの相関を求めた.結果:1.唾液分泌量と煎餅の初回嚥下までの咀嚼回数との間に負の相関が認められ,唾液分泌能力の高い者は座下までの咀嚼回数が少ない事が認められた.2.ピーナッツの舌側貯留率と煎餅の初回嚥下までの咀嚼回数との間に負の相関が認められ,舌側移送能力の高い者は嚥下までの咀嚼回数が少ない事が認められた.3.上記の関係は,吸水性の高い煎餅で顕著であった.以上の事より,吸水性の高い煎餅の初回嚥下までの咀嚼回数を計測するこの評価法は,食塊形成に密接な関係がある唾液分泌能力および舌側移送能力を予想する事ができた.この方法によりチェアサイドで食塊形成能力を含めた咀嚼能力を簡便に評価できることが分かった.
58 0 0 0 OA 底生動物から見た小水力発電による減水が渓流生態系に及ぼす影響評価
- 著者
- 大山 璃久 佐藤 辰郎 一柳 英隆 林 博徳 皆川 朋子 中島 淳 島谷 幸宏
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.II_135-II_141, 2019 (Released:2020-03-16)
- 参考文献数
- 22
小水力発電は有望な分散型の再生可能エネルギーであり,日本各地への導入が期待されている。小水力発電は環境負荷が小さいと考えられているが,減水区間が生じるため,河川生態系の影響を正しく評価しておく必要がある.本研究では,小水力発電による減水が渓流生態系にどのような影響を与えるのかを定量的に明らかにするため,底生動物を指標として渓流のハビタット類型ごとに減水の影響度合いを評価した.研究の結果,加地川では,全ての渓流ハビタットにおいて減水による底生動物個体数,分類群数,及び生物の群集構造への影響は認められなかった.加茂川では,一部ハビタットにおいて減水区間の底生動物個体数及び分類群数が減少しており,生態系の変質が示唆された.原因として,砂防堰堤から取水されるため,土砂供給量減少が考えられた.
29 0 0 0 OA 数理社会学ワンステップアップ講座 統計学・計量社会学をどう教えるか:
- 著者
- 神林 博史
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.177-187, 2017 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 7
29 0 0 0 IR マニラ戦とベイビューホテル事件
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 関東学院大学経済学部教養学会
- 雑誌
- 自然・人間・社会 (ISSN:0918807X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.49-83,
1945年2月から3月にかけてのマニラ戦における日本軍の残虐行為はよく知られている。しかしその中で日本軍がマニラの中心にあるエルミタ地区の女性たち数百人をベイビューホテルとその近くのアパートメントに監禁し、数日にわたって日本兵たちが次々と強かんを繰り返した事件は有名であるにもかかわらずまったく研究がない。米軍は事件直後に100人以上の関係者から尋問調書をとり、膨大な捜査報告書を残しており、そこから事件の全体像を明らかにした。同時に日本軍の史料はほとんど残っていないが、関連する日本軍部隊について検討し、他の残虐行為との関連を検討したうえで組織的な犯罪であったことを示した。
19 0 0 0 OA 変異するダーウィニズム : 進化論と社会
15 0 0 0 OA 沖縄戦における「集団自決」と教科書検定
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 現代史研究会
- 雑誌
- 現代史研究 (ISSN:03868869)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.65-70, 2007-12-25 (Released:2018-06-28)
- 参考文献数
- 8
15 0 0 0 OA 咬合機能時にみられる胸鎖乳突筋の活動様相
- 著者
- 河野 正司 吉田 恵一 小林 博 三浦 宏之
- 出版者
- 社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.764-769, 1987-06-01 (Released:2010-08-10)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 7 3
Many TMJ patients who have occlusal interferences often complain of pains in the sternocleidomastoid muscle. The pain occurs mainly in the insertion of the muscle (SCM-I) rather than in the middle of the muscle (SCM-M). In order to investigate a causative mechanism of pain in the sternocleidomastoid muscle in relation to occlusion, the activities of sternocleidomastoid and masticatory muscles were studied by means of EMG during functions in relation to the occlusal contact on six normal subjects. EMG activities of temporal, masseter, SCM-I and SCM-M were recorded by surface and needle electrodes.EMG activity was recorded from SCM-I in accordance with the activity of the masticatory muscles during tapping, clenching, and mastication. On the other hand little activity was registered from SCM-M. The amplitude of the EMG of SCM-I increased as the occlusal force increased. During chewing the sternocleidomastoid muscle was functioning more actively on the working side than on the non-working side.
14 0 0 0 OA 高次元場の理論の広がり
- 著者
- 林 博貴 八木 太
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.12, pp.796-804, 2022-12-05 (Released:2022-12-05)
- 参考文献数
- 27
我々は通常,空間3次元と時間1次元からなる4次元時空に住んでいると考えている.しかし,素粒子をより根源的な理論から統一的に扱おうとする試みの中で,我々の住む世界が実は極小サイズの余剰次元を含む5次元以上の時空である可能性が指摘されている.実際,素粒子理論を記述する枠組みである場の理論は,高次元時空についても古くから盛んに研究されている.ところが,高次元の場の理論は,典型的には高エネルギーにおいて相互作用が強くなるために量子補正の理解が困難であり,未だにわからないことも多い.例えば,あるラグランジアンによって指定された高次元場の理論が,すべてのエネルギースケールで予言能力を持つような問題のない理論かどうか自体がすでに非自明である.超対称性を持つ場の理論においては,摂動計算による量子補正の形が厳しく制限されるため,この問題に関してある程度信頼できる議論が可能になる.1996年頃のSeibergらによる研究では,有効結合定数の計算に基づき,各々の5次元超対称ゲージ理論について,前述の意味での問題のない理論であるかどうかの分類が行われた.高次元場の理論の研究においては,超弦理論を用いたアプローチもまた,長年にわたり重要な役割を果たしてきた.例えば,Dブレーンを用いて,超対称ゲージ理論を構成する手法がある.特に,5ブレーンウェブと呼ばれるものを用いることにより,多くの5次元超対称ゲージ理論が構成され,その分類や性質が議論されてきた.場の理論的手法と超弦理論的手法は超対称ゲージ理論の研究において相補的な役割を果たすため,ともに必要不可欠な存在である.ところが,両者には5次元超対称ゲージ理論の分類に関して一部食い違いがあり,それは長い間謎のままであった.近年,場の理論的手法と超弦理論的手法の双方のさらなる発展に伴い,この謎を解決する形で分類の理解が進んでいる.まず,場の理論的手法においては,クーロン的真空を正しく同定する方法が提唱され,その結果,問題のない理論が新たに存在する可能性があることが指摘された.また,超弦理論的手法では,5ブレーンウェブに関する理解の発展などに伴い,様々な5次元超対称ゲージ理論が,実際に超弦理論を用いて新たに実現できるようになってきた.その結果,当時の食い違いが解消されるとともに,初期の分類では問題があるとされていた多くの5次元超対称ゲージ理論が実は問題のない理論であることが明らかになってきた.また,それと深く関連する形で,6次元場の理論の分類の研究も進んでいる.5次元超対称ゲージ理論の研究においては,その分類だけでなく,様々な量子的性質が研究されている.例えば,5ブレーンウェブを用いた構成を応用することにより,超対称性の一部を保つ状態の数え上げや,空間の一方向が周期的になっている場合の有効結合定数の計算,ゲージ結合定数が発散するときのヒッグス的真空の解析などが行われている.その結果,摂動論では捉えきれなかった効果が定量的な形で明らかにされつつある.高次元場の理論は,古くからの研究テーマでありながら今なお新しい進展が続いており,今後のさらなる発展が期待される.
13 0 0 0 OA 「総中流」と不平等をめぐる言説 : 戦後日本における階層帰属意識に関するノート(3)
- 著者
- 神林 博史 Kanbayashi Hiroshi
- 出版者
- 東北学院大学学術研究会
- 雑誌
- 東北学院大学教養学部論集 (ISSN:18803423)
- 巻号頁・発行日
- no.161, pp.67-90, 2012-03
11 0 0 0 日本軍「慰安婦」研究の現状と課題 (特集 日本の敗戦から70年)
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 校倉書房
- 雑誌
- 歴史評論 (ISSN:03868907)
- 巻号頁・発行日
- no.784, pp.29-40, 2015-08
10 0 0 0 OA 能登半島輪島地域の中新統の層序・堆積環境・テクトニクス
- 著者
- 小林 博文 山路 敦 増田 富士雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.5, pp.286-299, 2005 (Released:2005-09-01)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 16 15
能登半島輪島地域の下部中新統は,扇状地成ないしファンデルタ成の砕屑岩層からなり,浅海成ないし広大な湖の浅部で堆積した薄層を数層準に挟む.積算層厚が1800 mを越えるこの地層中には傾斜不整合が複数認められ,それらによって層序が区分される.複数の鍵層を追跡することにより,地質図規模の正断層が推定された.また,頻繁にみられる小断層は,様々なトレンドの斜めずれ正断層を主とする.規模の異なるこれらの断層は,ともに東-西ないし北東-南西方向の伸長変形を示す.しかしこの地域の中部中新統以上の海成層には同様の変形がみられない.したがってこれは,前期中新統の堆積時の変形であったと考えられる.この伸長方向は能登半島北東部から報告されたグラーベン群の示唆する伸長方向と直交するが,半島西側の海域で発見された下部中新統のグラーベン群のそれとは調和的である.このことから日本海拡大時,西南日本は複雑なブロック化をしつつ移動したらしい.
8 0 0 0 日本軍慰安婦問題の現在 (特集 いま学ぶ日本軍「慰安婦」問題)
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 歴史教育者協議会
- 雑誌
- 歴史地理教育 (ISSN:02881535)
- 巻号頁・発行日
- no.798, pp.10-17, 2012-12
8 0 0 0 F理論を用いた超弦理論の現象論的応用
本研究の目的は、超弦理論の真空を用いて現象論における問題を解明することである。その中でも特に、F理論のコンパクト化は四次元の超対称性大統一理論に出現する物質場と湯川結合を全て生成することができるため、現象論を議論する超弦理論の真空として非常に魅力的である。本年度はF理論を用いた超対称性大統一理論における陽子崩壊問題について議論した。超対称性を持った大統一理論は、繰りこみ可能な陽子崩壊を引き起こす演算子の存在が一般には許されてしまう。そこで、F理論を用いて大統一理論を構築した際にも、この項をなんらかの方法で禁止する必要がある。我々の研究以前まででよく用いられてきた方法は、あるゲージ群を大統一理論のゲージ群へ破る際に導入する随伴表現スカラー場の期待値を特殊に調節することによって、余分なU(1)対称性を低エネルギー理論に残すというものである。このU(1)対称性によって次元四の陽子崩壊演算子は禁止されると思われてきた。しかし、内部空間の構造をよく調べるとこの期待値が発散し、ゲージ理論の近似が悪くなる場所があり、そこを考えてもU(1)対称性が残るかは自明ではない。そこで、我々は期待値が発散する場所も含めたF理論の内部空間全体を詳細に解析することで、生成されると思われてきたU(1)対称性が実際には破れていることを示した。さらにその元で、次元四の陽子崩壊演算子が生成されることをも明らかにした。我々の研究によって初めて、ゲージ理論の枠内を越えた寄与が物理的帰結を与えることが示され、F理論の内部空間全体の構造も重要であることが認識された。
7 0 0 0 OA 政治的態度におけるDK回答と政治的行動
- 著者
- 神林 博史
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.452-467, 2005-09-30 (Released:2010-01-29)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 2
調査票調査では, 広い意味での政治的態度に関する質問において「わからない」 (don't know=DK) という回答が発生しやすいことが知られている.DK回答は通常の場合, 欠損値として処理され, 分析の対象とはならない.一方で, 政冶意識におけるDK回答は回答者の政治に対する消極性を示す重要な情報であるとの可能性が指摘されてきた.この見解が正しければ, DK回答と実際の政治的行動との間に関連が予想される.全国規模のパネル調査データを用いた分析の結果, DK回答の多い回答者は政冶行動に参加しない傾向があることが明らかになった.
5 0 0 0 OA 電気刺激を利用した痛み定量計測法の開発と実験的痛みによる評価
- 著者
- 嶋津 秀昭 瀬野 晋一郎 加藤 幸子 小林 博子 秋元 恵実
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.117-123, 2005 (Released:2007-01-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4
We have developed a method and a system to quantitatively evaluate human pain without relying on subjective criteria. The concept of pain quantification is to compare the magnitude of the subject's pain to the magnitude of a painless electric stimulus that is comparable to actual pain. We quantified degree of pain as the pain ratio, based on the ratio between pain equivalent current and minimum perceived current. In the system developed as the objective of this study, a gradually increasing pulsed current (frequency was 50 Hz, and the pulse width was 0.3 ms) was applied to the subject's medial forearms, and the subjects compared the magnitude of this sensation to electrical stimulation produced by an electrical current. Using test equipment, we conducted basic evaluations of measurement principles. We induced two types of experimental pain, by applying weight load to the upper arm and the lower leg, and by pinching the skin using clips. We examined whether changes in the degree of sensation with respect to electrical stimulation used in this method could be accurately observed, and whether or not it was possible to accurately and with high reproducibility measure minimum perceived current and pain equivalent current. As a result, we were able to make a clear comparison between pain and the degree of stimulation by electrical current, which was a sensation differing from pain. Although there were individual differences in the measured values, the reproducibility of the pain equivalent current as measured was favorable, and the measured values for pain ratio were also reproducible. We confirmed in the present study that the degree of experimental pain can be expressed as quantitative numerical values using an index defined as pain ratio.
5 0 0 0 産業界におけるデジタルセラピューティクスの実用化と課題
- 著者
- 前川 雄亮 里見 佳典 小林 博幸
- 出版者
- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会
- 雑誌
- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.315-322, 2022 (Released:2022-09-30)
- 参考文献数
- 24
今日においては多くの医療機器がデジタル技術に支えられて開発されている.このような機器の中でも本稿では,特にSoftware as a Medical Device(SaMD)およびDigital Therapeutics(DTx)について述べる.まず,DTxについて簡単に歴史を振り返り,海外において開発された特筆すべきDTx製品の例を紹介する.次に,日本のDTxの開発状況へ話題を移し,特に海外に対する日本の開発状況の遅延について議論する.日本におけるSaMD/DTxの開発は①保険償還制度における収益予測の不確実性,②事例の蓄積不足による規制情報の限定,③臨床試験計画や承認後のソフトウェア修正戦略の困難さ,④ソフトウェア物流・認証システムの構築,⑤競合製品としてのSaMD以外のソフトウェアの増加といった多くの課題を抱えている.以上の議論をふまえ,日本におけるデジタルヘルスケアの発展における望ましい将来像と予想される課題をいくつかあげる.SaMD/DTxだけでなく,non-SaMDも含めたさまざまな製品が開発され,エコシステムが形成・相互に接続され,トータルヘルスケアが実現されるであろう.製品開発を充実させるためには,前述の課題を一歩一歩解決していく必要がある.それらに加えて,Personal Health Record(PHR)の保護と活用のためのルール作りが必要である.最近になって,日本のSaMD開発企業数社が,業界統一組織JaDHAを設立した.企業,規制当局,その他関係者の対話を通じて,この難問が解決されることを期待する.
5 0 0 0 IR 高度経済成長期の階層帰属意識--戦後日本における階層帰属意識に関するノート(1)
- 著者
- 神林 博史 Kanbayashi Hiroshi
- 出版者
- 東北学院大学学術研究会
- 雑誌
- 東北学院大学教養学部論集 = Faculty of Liberal Arts review, Tohoku Gakuin University (ISSN:18803423)
- 巻号頁・発行日
- no.156, pp.25-54, 2010-07
5 0 0 0 OA 「全然」再考 : 迷信、アプレ、前提の否定など
- 著者
- 梅林 博人
- 出版者
- 相模女子大学
- 雑誌
- 相模国文 (ISSN:03029999)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.71-82, 2012-03
- 著者
- 小林 博志
- 出版者
- 東北社会学研究会
- 雑誌
- 社会学研究 (ISSN:05597099)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.61-85, 2021-02-15 (Released:2022-03-10)
- 参考文献数
- 21
本稿では、農協婦人部の機関誌的存在である雑誌『家の光』を通し、第一次ベビーブームの親世代に着目して、高度経済成長期の農村社会における学歴アスピレーションの高まりについて考察する。一九五〇年代からの生活改善運動の展開と、一九六〇年代のテレビ普及を背景に、家族計画を一つの契機として教育への関心が高められ、その関心は子どもの成長と共に学歴取得へと向けられる。兼業化の加速による農外収入の増加と、テレビ普及による近代家族的価値観の浸透によって、工業製品の普及だけでなく、高卒という学歴も都市と同様に取得され、農村の都市化が進展する。これにより、消費財という「モノ」だけでなく、学歴という「経歴」も一般化していく。それは、都市と農村が共有しうる、「人並み」という生活水準意識の一端が形成されていく過程でもある。