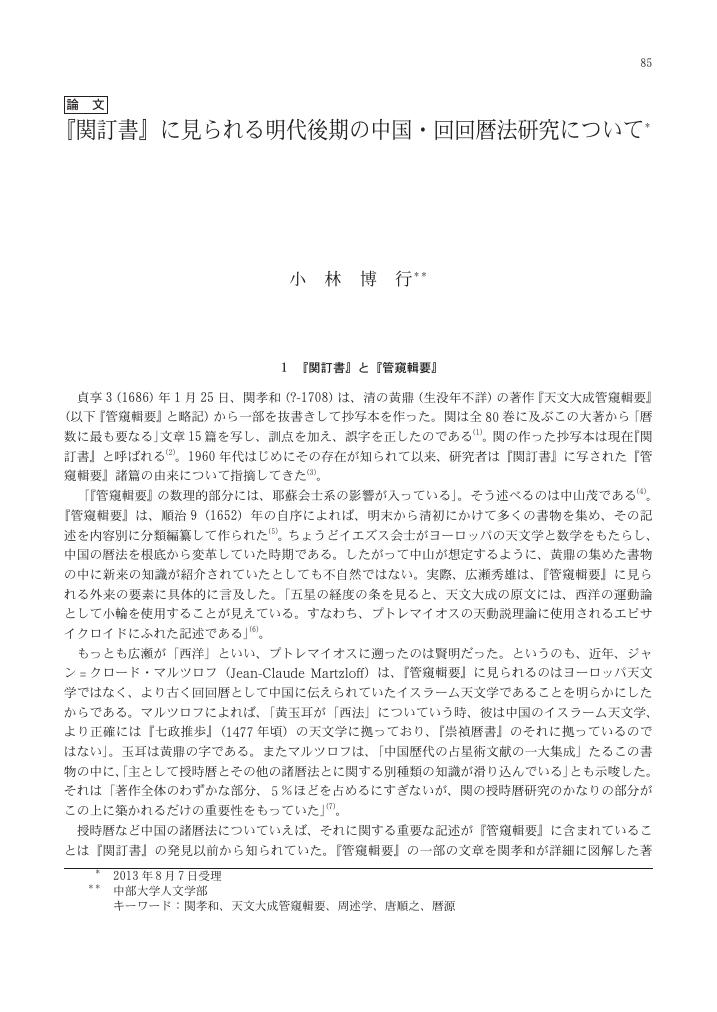1 0 0 0 OA 無侵襲的連続血圧測定装置を用いた洞刺による降圧効果の評価
- 著者
- 秋元 恵実 小林 博子 嶋津 秀昭 伊藤 寛志 木下 晴都
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.409-415, 1988-12-01 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 11
指動脈圧を無侵襲的かつ連続的に計測する容積補償式の血圧計を使用し, 本態性高血圧症16名を対象に, 洞刺による血圧応答について正常血圧群と比較検討した。本態性高血圧群では鍼刺激直後から収縮期・拡張期血圧は有意 (P<0.05) な下降を示した。平均では収縮期血圧で14mmHg, 拡張期血圧では9mmHgの下降であった。洞刺の効果は刺激後30分まで持続し, 洞刺後15~20分で最大の下降が認められた。脈圧および心拍数については有意な変化は認められなかった。本態性高血圧群と正常血圧群の血圧変化を比較すると両群共に類似した下降曲線が得られ, 両群には同様な反射が出現しているものと推察する。しかしながら洞刺による血圧変化には個体差が見られた。
1 0 0 0 OA ロシアの銀行部門と東ロシア資源開発のための資金調達
- 著者
- 小林 博
- 出版者
- 島根県立大学
- 雑誌
- 北東アジア研究 (ISSN:13463810)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.51-61, 2005-03
In eastern part of Russia including Sakhalin, there are many oil and gas projects which are ongoing or at the planning stage. In order for these projects to be developed successfully, huge amount of fund raising is required. Even though the number of banks is very large, second in the world after the United States, the Russian banking system is very underdeveloped. As a result, it is extremely difficult to finance big oil and gas projects domestically. Accordingly, the large scale external financing is necessary so that the oil and gas projects would be developed successfully. To finance huge amount of fund externally for oil and gas projects, the finance technique of project finance is used in many cases. Usually, international development banks and official credit agencies of the advanced countries take part in the project finance. These banks and agencies take the political risks of the projects. In addition to these international development banks and official credit agencies, many parties take part in the project finance. These parties are sponsor companies, constructing companies, management companies, commercial banks, sellers of raw materials, buyers of products and so on. These parties share the risks involved in the projects. In the case of big oil and gas projects in Russia, the project finance is expected to be used to raise the fund. If the commercial banks do not join the financing of those projects because the project finance is not structured successfully, the projects will be greatly scaled down.
1 0 0 0 第16回日本医学教育学会総会および大会〈プログラムと予稿集〉
- 著者
- 西園 昌久 高橋 流里子 対馬 節子 松永 智子 福屋 靖子 土屋 滋 大貫 稔 高橋 美智 浅野 ふみぢ 小松崎 房枝 鈴木 小津江 平山 清武 中田 福市 鈴木 信 壁島 あや子 名嘉 幸一 鵜飼 照喜 福永 康継 浪川 昭子 高田 みつ子 岩渕 勉 森脇 浩一 加藤 謙二 早川 邦弘 森岡 信行 津田 司 平野 寛 渡辺 洋一郎 伴 信太郎 木戸 友幸 木下 清二 山田 寛保 福原 俊一 北井 暁子 小泉 俊三 今中 孝信 柏原 貞夫 渡辺 晃 俣野 一郎 村上 穆 柴崎 信吾 加畑 治 西崎 統 大宮 彬男 岩崎 徹也 奥宮 暁子 鈴木 妙 貝森 則子 大橋 ミツ 川井 浩 石川 友衛 加世田 正和 宮澤 多恵子 古賀 知行 西川 眞八 桜井 勇 三宅 史郎 北野 周作 竹洞 勝 北郷 朝衛 橋本 信也 斉藤 宣彦 石田 清 畑尾 正彦 平川 顕名 山本 浩司 庄村 東洋 島田 恒治 前川 喜平 久保 浩一 鈴木 勝 今中 雄一 木内 貴弘 朝倉 由加利 荻原 典和 若松 弘之 石崎 達郎 後藤 敏 田中 智之 小林 泰一郎 宮下 政子 飯田 年保 奥山 尚 中川 米造 永田 勝太郎 池見 酉次郎 村山 良介 河野 友信 Wagner G. S. 伊藤 幸郎 中村 多恵子 内田 玲子 永留 てる子 石原 敏子 河原 照子 石原 満子 平山 正実 中野 康平 鴨下 重彦 大道 久 中村 晃 倉光 秀麿 織畑 秀夫 鈴木 忠 馬渕 原吾 木村 恒人 大地 哲郎 宮崎 保 松嶋 喬 桜田 恵右 西尾 利一 森 忠三 宮森 正 奥野 正孝 江尻 崇 前沢 政次 大川 藤夫 関口 忠司 吉新 通康 岡田 正資 池田 博 釜野 安昭 高畠 由隆 高山 千史 吉村 望 小田 利通 川崎 孝一 堀 原一 山根 至二 小森 亮 小林 建一 田中 直樹 国府田 守雄 高橋 宣胖 島田 甚五郎 丸地 信弘 松田 正己 永井 友二郎 向平 淳 中嶌 義麿 鎮西 忠信 岡田 究 赤澤 淳平 大西 勝也 後藤 淳郎 下浦 範輔 上田 武 川西 正広 山室 隆夫 岡部 保 鳥居 有人 日向野 晃一 田宮 幸一 菅野 二郎 黒川 一郎 恩村 雄太 青木 高志 宮田 亮 高野 純一 藤井 正三 武内 恵輔 南須原 浩一 佐々木 亨 浜向 賢司 本田 麺康 中川 昌一 小松 作蔵 東 匡伸 小野寺 壮吉 土谷 茂樹 岡 国臣 那須 郁夫 有田 清三郎 斎藤 泰一 清水 強 真島 英信 村岡 亮 梅田 典嗣 下条 ゑみ 松枝 啓 林 茂樹 森 一博 星野 恵津夫 正田 良介 黒沢 進 大和 滋 丸山 稔之 織田 敏次 千先 康二 田中 勧 瓜生田 曜造 尾形 利郎 細田 四郎 上田 智 尾島 昭次 大鐘 稔彦 小倉 脩 林 博史 島 澄夫 小池 晃 笹岡 俊邦 磯村 孝二 岩崎 栄 鈴木 荘一 吉崎 正義 平田 耕造
- 出版者
- Japan Society for Medical Education
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.145-173, 1984
1 0 0 0 OA ゴンズイの成群に関する嗅覚の役割
- 著者
- 林 徳之 中村 聡一 吉川 弘正 安部 恒之 小林 博
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.7-13, 1994-05-20 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
We examined the role of olfaction involved in schooling of Japanese sea catfish Plotosus lineatus, and attempted to elucidate the relationship between the sensitivity to an aggregating pheromone and bodylength in reference to a reduction of the school size with growth in Japanese sea catfish. Behavioral test of preferenCe for sea water which had held their own school were carried out on 97 fish (42 to 235mm in total length), using filtrated sea water or sea water which had held another school as a control. The catfish discriminated and selected the sea water holding their own school. However, anosmic fish no longer discriminated their holding sea water, suggesting that this preference leading to a school was established by olfaction but not other sense organs including taste. No distinct change in the preference with fish growth was recognized. However, larger fish especially maturing females tended to show a lowered preference. This suggests that reduction in the constituent members of the school with growth in Japanese sea catfish was dependent upon breakaway from menace of predators or upon dispersal of maturing females from their school to avoid incest breeding.
1 0 0 0 『関訂書』に見られる明代後期の中国・回回暦法研究について
- 著者
- 小林 博行
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.269, pp.85-98, 2014
The Seki Teisyo (関訂書), a manuscript compiled by Seki Takakazu (関孝和) in 1686, is known to consist of 15 treatises which Seki extracted from an early Qing astronomical and astrological corpus, the Tianwen Dacheng Guankui Jiyao (天文大成管窺輯要). Containing a detailed account of the Shoushi Li (授時暦) as well as a comparative study of Chinese and Islamic calendrical systems, these treatises have drawn the attention not only of Seki but of modern historians. In this paper, I show that 14 of the 15 treatises Seki selected had been composed by a late Ming scholar, Zhou Shuxue (周述学), who discussed issues with Tang Shunzhi (唐順之). Their time predates the era in which the mathematical basis of the Shoushi Li was scrutinized and a new Chinese calendrical system was invented incorporating Western astronomical knowledge. I also mention some earlier works that Tang and Zhou could have consulted. Although Seki never knew the author of the treatises nor their background, his concern centered on themes that seem to have derived from one of those earlier works: the Liyuan (暦源).
1 0 0 0 IR シンガポール華僑粛清
- 著者
- 林 博史
- 雑誌
- 自然人間社会 (ISSN:0918807X)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.1-31,
1942年2月にシンガポールで日本軍がおこなった華僑粛清事件は、アジア太平洋戦争期における日本軍の代表的な残虐行為としてよく知られている。シンガポールでは体験記や資料集が数多く刊行され、日本側の関係者の証言もある程度は出されているが、この事件の全容を解明した信頼できる研究が日本にもシンガポールにもない。そうした中で本稿は、この粛清事件の全体の概要を、日本側の動きと要因を中心に明らかにする。まず粛清の命令・実施要領の作成・実施過程を日本側資料によって明らかにする。また日本軍の構成、華僑政策の特徴など背景について分析し、定説がなく議論となっている犠牲者数の検討、粛清をおこなった理由について検討する。シンガポール華僑粛清が、シンガポール占領前から計画された華僑に対する強硬策の一つであり、長期にわたる中国への侵略戦争のうえになされた残虐行為であると結論づけている。
1 0 0 0 伝播負担関数による文化の伝播路の抽出
- 著者
- 加藤常員 小林 博昭 小沢 一雅 今枝 国之助
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.418-428, 1988-04-15
- 被引用文献数
- 2
考古学へのコンピュータ・サイエンスの応用 とくに文化とその伝播に関するモデル化および計算機シミュレーションについて述べる.ある特定の文化に帰属する遺跡の集まりを取り上げ 遺跡間の文化の伝播のネットワークを求めるモデルを提案する伝播は 遺跡間の係わり合い(交流)が基本であり その大きな要因と考えられる空間的距離に着目する.距離についての伝播負担関数および伝播係数を導入する.伝播係数の特性である中継効果を明らかにする.中継効果を使い遺跡相互の伝播路のネットワークを求める.このネットワークを伝播路網と名付ける具体例として 後期旧石器時代・国府型ナイフ形石器文化の56か所の遺跡を対象にシミュレーションを行った結果を示す.また 弥生時代中期・畿内の拠点集落遺跡理か所について 考古学的手法による結果と比較・検討を行う.
1 0 0 0 OA 油脂類のクラスター水への分散性に関する研究
- 著者
- 柿野 賢一 津崎 慎二 田中 克幸 服部 利光 松下 和弘 岡林 博文 正山 征洋
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.379-385, 1998-12-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 32
水をベースにした化粧品を考える上で, 水のクラスターが小さい水 (クラスター水) の挙動には非常に興味深いものがある。われわれは, 松下が提唱した水の17O核磁気共鳴 (17O-NMR) スペクトルの半値幅を求める方法により, クラスター水のクラスターの大きさを市販の精製水と比較した。クラスター水の半値幅は56.3Hz, 精製水のそれは142.4Hzであり, この事実からクラスター水が精製水に比較して平均的にクラスターのサイズが小さいことがわかった。さらに, クラスター水と精製水への油脂の分散性を1H核磁気共鳴 (1H-NMR) 分光法を用いて, 油脂の有するメチレン基のプロトンをもとに評価したところ, クラスター水への分散性は精製水と比較してよいことが確認された。また, モノオレインを用いたエマルジョン形成においても, クラスター水は精製水と比較して均一なエマルジョンを形成しているのが確認された。以上より, 水のクラスターの大きさ, 動的構造の差異が油脂の分散性に影響を及ぼすことが示された。
1 0 0 0 OA 松浦川におけるイシガイ目二枚貝の沈降特性とその生息制限要因に関する考察
- 著者
- 稲熊 祐介 林 博徳 辻本 陽琢 島谷 幸宏
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.I_1297-I_1302, 2013 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 2
The Matsuura river, study site of present study, has three Unionoida species which are known as good indicator of river environment health. However Anodonta lauta, one of the three species, has been drastically decreasing in past decades. One of those reasons is change of flood water disturbance system against their habitats. Though this phenomenon is strongly related to hydraulic flow of the habitat and hydraulic characteristics of Unionoida mussels, relationship between hydraulic flow and hydraulic characteristics of Unionoida mussels are not known yet. If we can reveal that, conservation and restoration skills for river environment should be improved. In this study, we focus on hydraulic characteristics of three Unionoida species, and conducted a hydraulic experiment. As a result, Anodonta lauta had characteristic which was susceptible to the hydraulic flow. In addition, smaller sized mussels were settled slowly and easily influenced by flowing water.
1 0 0 0 OA 研究討議に関する総括的報告
- 著者
- 小林 博英
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.37, pp.27-31, 1978-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 西ドイツにおける教育哲学の最近の動向 教育学的人間学の試み
- 著者
- 小林 博英
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1967, no.16, pp.81-86, 1967-10-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 新殺菌剤フルアジナムのハクサイ根こぶ病に対する作用特性
- 著者
- 鈴木 一実 杉本 光二 林 博之 光明寺 輝正
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.395-398, 1995-08-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 16 22
フルアジナム(フロンサイド®)のハクサイ根こぶ病に対する作用特性を検討した。1ppm以上のフルアジナム存在下で休眠胞子を培養したとき,遊走子発芽はほとんど観察されなかった。フルアジナムに接触させた休眠胞子を接種した場合には根毛感染の頻度が減少した。フルアジナムを土壌施用したところ,根毛感染および根こぶ形成は著しく阻害された。根毛感染成立後,第二次遊走子放出前にフルアジナム含有非汚染土壌にハクサイ苗を移植した場合,根こぶ形成は阻害されたが,皮層感染成立後では防除効果は認められなかった。以上から,フルアジナムは休眠胞子に殺菌的に作用するとともに根毛感染および皮層感染を阻害し,その結果根こぶ形成阻害をもたらすことが示唆された。
1 0 0 0 OA 『関訂書』に見られる明代後期の中国・回回暦法研究について
- 著者
- 小林 博行
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.269, pp.85-98, 2014 (Released:2020-12-09)
The Seki Teisyo (関訂書), a manuscript compiled by Seki Takakazu (関孝和) in 1686, is known to consist of 15 treatises which Seki extracted from an early Qing astronomical and astrological corpus, the Tianwen Dacheng Guankui Jiyao (天文大成管窺輯要). Containing a detailed account of the Shoushi Li (授時暦) as well as a comparative study of Chinese and Islamic calendrical systems, these treatises have drawn the attention not only of Seki but of modern historians. In this paper, I show that 14 of the 15 treatises Seki selected had been composed by a late Ming scholar, Zhou Shuxue (周述学), who discussed issues with Tang Shunzhi (唐順之). Their time predates the era in which the mathematical basis of the Shoushi Li was scrutinized and a new Chinese calendrical system was invented incorporating Western astronomical knowledge. I also mention some earlier works that Tang and Zhou could have consulted. Although Seki never knew the author of the treatises nor their background, his concern centered on themes that seem to have derived from one of those earlier works: the Liyuan (暦源).
1 0 0 0 OA 近現代の新語・新用法および言語規範意識の研究
近現代の日本語における新語・新用法の事例に関する記述的研究とそれに関する言語規範意識の研究を行った論文の発表、従来学界で注目されてこなかった資料の紹介、さらに中国で開催の国際シンポジウムで計3回の研究発表・招待講演を行った。そして、メンバー全員による共同発表として、「代用字表記語」(「当用漢字表」にない字を使う漢字語の書き換えにより、新たに生じた漢字語)に関する発表を『日本語学会』で行い、それに関連する論文を計3件発表した。また、最終年度末には紙媒体(非売品)の「研究成果報告書」を作成した。
- 著者
- 小林 博
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科学会雑誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.521-530, 1968-05
生体にstressが加わるとcatecholamines〔(以下CAと略), adrenaline (以下Aと略), noradrenaline (以下NAと略), dopamine (以下DAと略) の総称で特にA, NAを指す〕が増量することは基礎的並びに臨床的な実験によって確かめられている. Selyeのstress学説による適応ホルモンの概念の導入によりCannonのemergency reaction と stressとの関連が問題とされて来たが, Selye自身も強調している如く, 適応ホルモンの機転が唯一の非特異的防禦手段ではなく, 自律神経系も又重要な役割を演じていることは疑いがない. 妊娠という試練を母体はどう受け止めるか. 妊娠中毒症はこの様な負荷に対する異常反応に基づく生体のbalanceの破綻 (換言すれば適合不全) によって起ると解されないだろうか. 著者はこの様な観点から自律神経系のneurotransmitterであり昇圧物質でもあるCAの妊娠中毒症における動態について検討を加えた. 尚測定に当っては尿中CAの測定に際し問題となっていたDOPAを除去する為, イオン交換樹脂Duolite C-25を使用した. その概要は以下の如くである. 1) 妊娠後半期になるとNAの平均値は上昇し, 高値を示すものもあり, かつバラツキも著明となり自律神経系の不安定性が示唆された. 2) 妊娠中毒症では毎日連続的に測定すると, NA値は必ずし.も血圧の動きとは関係なく, 周期的な波状の変動を示した. 全平均値は妊娠末期と差がない. この事から血圧上昇には血管のNAに対する感受性の光進も又重要な因子となることが推測される. 3) 分娩子癇の患者では子癇発作後 pheochromocytoma に於てのみみられる様な, 正常人の約30倍にも達するNAがspike状に放出され, 一たん減少後, 再び一見rebound的に上昇している. これは子癇独自の現象で, その意味ずけはいまだ困難である. 4) 尿中CA値と血圧とは相関関係が明らかでなく, CAが一次的に昇圧機序レこ関与するとしても, 二次的には, 他の昇圧機構ないし血圧維持機構が作働することが推測される. すなわちCAが妊娠中毒症の一元的な原因とはいえないが, 交感神経系が妊娠中毒症発症に関与していることは充分考えられる.
1 0 0 0 石山寺に蔵する「古瓦譜」およびその古瓦について
- 著者
- 林 博通
- 出版者
- 日本考古学会
- 雑誌
- 考古学雑誌 (ISSN:00038075)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.p502-516, 1982-03
1 0 0 0 IR 連合国戦争犯罪政策の形成 -連合国戦争犯罪委員会と英米(下)-
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 関東学院大学経済学部教養学会
- 雑誌
- 自然人間社会 (ISSN:0918807X)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.51-77,
本稿では連合国の戦争犯罪政策の形成過程について、連合国戦争犯罪委員会に焦点をあて、同時に連合国の中小国の動向、役割に注意し、かつイギリスとアメリカ政府の動向を合わせて分析する。枢軸国による残虐行為に対してどのように対処するのかという問題を扱うために連合国戦争犯罪委員会が設置された。委員会は従来の戦争犯罪概念を超える事態に対処すべく法的理論的に検討をすすめ、国際法廷によって犯罪者を処罰する方針を示した。だがそれはイギリスの反対で潰された。その一方、委員会の議論は米陸軍内で継承されアメリカのイニシアティブにより主要戦犯を国際法廷で裁く方式が取り入れられていった。委員会における議論はその後に定式化される「人道に対する罪」や「平和に対する罪」に繋がるものであり、理論的にも一定の役割を果たすことになった。だが当初の国際協調的な方向から米主導型に変化し、そのことが戦犯裁判のあり方に大きな問題を残すことになった。
1 0 0 0 IR 市町村の提起する境界に関する訴えと当事者訴訟(2)-市町村間訴訟の研究-
- 著者
- 小林 博志 コバヤシ ヒロシ KOBAYASHI HIROSHI
- 出版者
- 西南学院大学学術研究所
- 雑誌
- 西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.59-114, 2015-10
1 0 0 0 OA 肺結核患者におけるマスク着用行動の変容ステージとその関連要因
- 著者
- 荒井 弘和 所 昭宏 平井 啓 野長 さおり 小林 博美 井上 亜由美 上砂 陽子 田中 孝浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.7, pp.667-673, 2010-07-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 14
本研究では,肺結核患者のマスク着用行動に対する変容ステージを検討し,マスク着用に関する恩恵と負担,阻害要因と促進要因,社会的要因,身体症状,および心理的適応状態が,変容ステージによって異なるか比較を行った.対象者は,入院中の肺結核患者および肺結核疑い患者であった.研究デザインは横断的調査であった.本研究の48名の対象者のうち,ステージの分布は,準備期22名および実行期26名であった.48名の平均年齢は53.09±16.70歳(19〜78歳)であった.分析の結果,マスク着用の負担,マスク着用の阻害要因,身体症状において,2つのステージ間に違いがみられる項目が存在した.入院日数およびマスク着用の促進要因においては,ステージ間で有意に異なる傾向が認められた.特に,マスク着用の阻害要因については,複数の項目において,ステージ間に差が認められた.今後は,看護師を中心とした医療スタッフが,促進要因を増強するだけでなく,阻害要因が存在していてもマスクを着用するよう意識づけるべきである.さらに,着け忘れを防止するような介入を行うことが好ましいと考えられる.
1 0 0 0 OA プロティノスの時間概念とベルクソンに見るその継承について
- 著者
- 小林 博和
- 出版者
- 武蔵野大学教養教育リサーチセンター
- 雑誌
- The Basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 = The Basis : The annual bulletin of Research Center for Liberal Education, Musashino University (ISSN:21888337)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.155-165, 2016-03-01