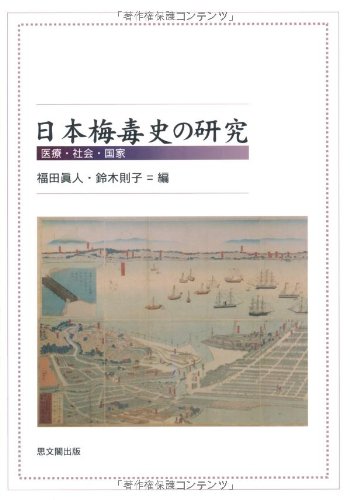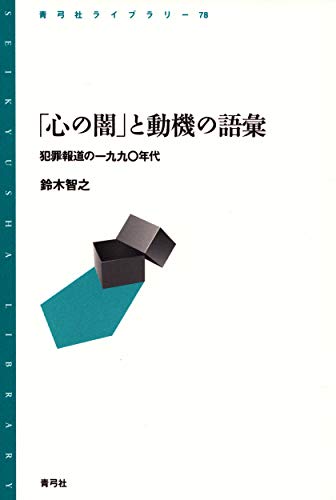- 著者
- 鈴木 智也
- 出版者
- 龍谷大学経済学会
- 雑誌
- 龍谷大学経済学論集 (ISSN:09183418)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.1-15, 2007-10
1 0 0 0 IR 18世紀英国小説に見られるロマンス構造の意味
- 著者
- 鈴木 万里 Mari SUZUKI 東京工芸大学芸術学部基礎教育課程 Division of Liberal Arts and Science Faculty of Arts Tokyo Polytechnic University
- 出版者
- 東京工芸大学芸術学部
- 雑誌
- 芸術世界 (ISSN:13493450)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.87-96, 2007
The relationship of women and literature changed radically by the mid eighteenth century in England. Samuel Richardson's Pamela, which has been often called 'the first novel', focuses the inner experience of a woman. It gave such a great impact upon the society that it determined the heroine type of the following novels throughout the century ; young, beautiful, modest, and vulnerable. It also represented gender positions and politics ; man provided with wealth, being superior, and woman deprived and dependent, inferior. Women had been disadvantaged because of some changes in kinship structures, economic processes, and legal arrangements by the beginning of the century. They first encountered a serious problem of an alienated self. The situation often placed a woman as the main character of the novel. In spite of the realism tradition of the English novels, women writers sometimes adopt a "romance" structure, the traditional pattern from the classic period, in which a prince or a princess is abandoned, adopted and raised by a kind shepherd, eventually recovers his/her original status and wealth. Although this story appears to be a kind of anachronism in the modern bourgeois society, it flourishes in the best-seller novels by women at the end of 18th century. Four novels will be discussed in this article ; Evelina (1778) by Frances Burney, Emmeline (1788) by Charlotte Smith, A Simple Story (1791) by Elizabeth Inchbald and The Romance of the Forest by Ann Radcliffe (1791). These novels bear an implicit resentment of women deprived of the resources to support themselves, trying to convey a challenging message under the disguise of a conservative attitude to the maledominated society.
1 0 0 0 並立制における投票行動研究の統合的分析アプローチ
- 著者
- 鈴木 基史
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.30-41,186, 2000
本稿は制度論的な投票行動仮説を提示する。具体的には,選挙制度が政党のとる政策ポジションに影響を与え,そのポジショニング戦略が投票行動における争点と特性の相対的重要性および投票行動モデルの経験的妥当性を規定するという仮説を提示する。たとえば,相対的多数制(小選挙区制)は,諸政党の政策ポジションに中位収斂化圧力を与え,大きな選挙区規模と低い議席獲得のための最低得票率を設定した比例代表制は,そうした圧力をかけない。そのため,前者による選挙では,争点が希薄化し,投票行動は特性志向にならざるをえないが,後者による選挙では,争点は明瞭化し,争点志向の投票が促進される。本稿では,新選挙制度で行われた1996年衆議院総選挙のサーベイ•データを用いて仮説検証を行う。計量分析では,理想点モデルと特性モデルが掲げる投票決定因を兼ね備えた統合モデルを利用して,比例区と小選挙区の評価関数を同時に推定し,争点と特性の重要性を検討する。
1 0 0 0 日本梅毒史の研究 : 医療・社会・国家
- 著者
- 福田眞人 鈴木則子編
- 出版者
- 思文閣出版
- 巻号頁・発行日
- 2005
- 著者
- 見方 洪三郎 上田 西村 久美子 後藤 昭二 KURTZMAN Cletus P. 鈴木 基文 YARROW David 中瀬 崇
- 出版者
- 日本微生物資源保存学会
- 雑誌
- Microbiology and Culture Collections : official publication of the Japan Society for Culture Collections : 日本微生物資源学会誌 (ISSN:13424041)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.49-57, 1999-12-30
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA ヨツユビハリネズミの食餌操作による体重管理
- 著者
- 大楠 千暁 鈴木 馨
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.135-140, 2017-10-10 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 6
フェレットフードの夜間不断給餌で飼育されてきたヨツユビハリネズミ(1歳9ヶ月齢、雄2個体、雌3個体)について、1日1回夕刻20分間の制限給餌へ食餌時間を4週間かけて変更し、その後の4週間でハリネズミフードへの食餌内容の転換を試みた。フェレットフードの不断給餌を制限給餌に変更したところ、体重は5.2~16.4%減少し、肥満傾向が改善する個体もみられた。ハリネズミフードはフェレットフードより明らかに嗜好性が低かったものの、ほとんどの個体でハリネズミフードに転換できた。ハリネズミフードを1日1回夕刻20分間の制限給餌から夜間不断給餌にして4週間観察しても体重の増加はみられなかった。 肥満がしばしばみられるハリネズミの体重管理には、食餌時間の管理とハリネズミフードの給餌が有効であることが示された。
1 0 0 0 OA スキージャンプのためのビデオ即時共有システム
- 著者
- 佐藤 永欣 梅木 紀之 鈴木 彰真 村田 嘉利
- 雑誌
- 第24回マルチメディア通信と分散処理ワークショップ論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, pp.102-108, 2016-10-12
スキージャンプ競技の練習のうち,練習メニューの仕上げがジャンプ台で行われる.スキージャンプ競技においては踏切が飛距離の要因の 8 割を占めるといわれており,スキージャンプ競技の練習はよい踏切をするための練習である.ジャンプ台における練習では,踏切台付近にいるコーチが踏切前後の模様をビデオ撮影し,ビデオを選手と一緒に再生して踏切が理想に近いかどうかを確認している.しかし,選手は着地後,踏切台付近のコーチのところまで 100 メートルほどジャンプ台を登る必要があるため,確認するまでジャンプ後 5 分以上かかってしまう.本システムは,着地点付近と踏切台をネットワーク接続して双方に端末を置き,ビデオを共有することで着地後直ちに踏切のビデオを確認しコーチの指導を受けることを実現する.
1 0 0 0 「心の闇」と動機の語彙 : 犯罪報道の一九九〇年代
It has been known that molding characteristics were important factors which contributes to compressive properties among various ones forming the compressive properties of a corrugated fiberboard container. In this study, sources of the vibration on the high-low corrugation as well as the relation between the high-low corrugation and physical properties of corrugating medium were investigated.<BR>The results showed that the resonance of the vibration clearly existed at the velocity of 130 m/ min on the single-facer, and that the vibration remarkably influenced a high-low corrugation. It was also found out that the bite of corrugator rolls mainly caused the vibration. The frequency (f) of the vibration is represented as f=n (number of the gear) × (revolution of the corrugator roll), here n is integer. It was clarified that the resonance occured when the frequency became near or agreed with the natural frequency of the corrugator roll.<BR>The evaluation of high-low corrugation aptitude for various corrugating medium becomes possible when evaluation system of high-low corrugation was estabished. It was found that physical properties of corrugating medium greatly influenced high-low corrugation. And further, caliper inversely related to the density of corrugating medium, and related to the thickness of it.
1 0 0 0 19世紀を中心とした軍事的学知をめぐる人と書物の交錯
- 著者
- 谷口 眞子 中島 浩貴 竹本 知行 小松 香織 丸畠 宏太 斉藤 恵太 柳澤 明 長谷部 圭彦 原田 敬一 佐々木 真 吉澤 誠一郎 鈴木 直志 小暮 実徳
- 出版者
- 早稲田大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
本研究は、国民国家が形成される19世紀を中心とし、軍人のグローバルな移動による人的ネットワークと、軍事関連書の翻訳・流通・受容という分析視角から、軍事的学知の交錯を研究するものである。日本・フランス・ドイツを主とし、オランダ・オスマン帝国・清朝を参照系と位置づけ、軍人と軍事関連書(人とモノ)の移動から、軍事的学知(学知)に光を当てることにより、軍事史的観点からみた新たな世界史像を提起したい。
1 0 0 0 児童養護施設における自立支援のための食育システムの開発
- 著者
- 梅本 奈美子 布施 晶子 杉浦 正美 鈴木 正子 岡見 雪子 辻 とみ子
- 出版者
- The Japan Dietetic Association
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.356-365, 2014
児童養護施設に入所している子どもたち(施設入所児童)が、自立して食生活を営む力を習得するために、実用的で効果的な食育システムの開発と食育プログラムの作成に必要な基礎調査を行った。名古屋市内児童養護施設14施設の施設入所児童(3歳~18歳)を調査対象者とし、食育指導状況調査、身体状況調査、調理実習による技術調査、アンケートによる食意識調査を実施した。食意識調査は、名古屋市内S小学校在籍児童を比較対象者(家庭生活児童)とした。幼児では、食事の姿勢についてのクイズ正解率が95.8%と正しい知識が身に付いていた。小学生低学年では、施設入所児童は家庭生活児童と比較し、野菜の判別クイズ正解率が有意(<i>p</i><0.05)に低く、野菜の名前を知らないことが分かった。また、施設入所児童は「食事の前に手洗いを行う」項目では、83.1%と家庭生活児童の52.7%と比べ有意(<i>p</i><0.05)に高く、施設における指導の効果が表れていた。「ごはんの時間が楽しみ」と答える割合が、幼児96.4%、小学生低学年81.7%、小学生高学年64.7%、中高生50.0%と年齢が上がるにつれて有意(<i>p</i><0.001)に低くなり、食に対する肯定感が低くなることが分かった。しかし、調理の経験が多い子どもは、食に対する肯定感が高くなり、自立後の自炊に対する不安感が少なかった。本研究の結果から、児童養護施設の食育指導においては、幼児から小学生低学年までに食育体験を多くさせることが有効な指導であり、子どもたちが豊かな食経験を会得できる大切な期間と考えられた。また、小学生高学年からは、技術的体験が多い計画を立案することが有効であると考えられた。
1 0 0 0 同期会議支援システムICE90における アイデア整理支援について
- 著者
- 榊原 正義 桂林 浩 鈴木 敏克 守屋 康正
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告マルチメディア通信と分散処理(DPS)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.83, pp.75-80, 1991-09-24
多くの情報をボトムアップに整理し、構造化する手法であるKJ法を利用してグループによる情報整理を支援するために、同期会議支援システムICE90の一つのアプリケーションとして、電子KJ法システムを構築した。電子KJ法システムは、各参加者が個人作業空間として使用するワークステションを通してKJカードの作成や移動等の操作を並行して実行できることを特徴としている。紙を使った従来のKJ法と比較すると、試行錯誤を行いながらのグループ編成や、グループ単位でのカードの操作が容易に行えるようになることが確認された。For the purpose of supporting groupwork to organize information, the authors developed ICE90: a face-to-face meeting support system. It has KJ-Method support function as one of its applications. The KJ-Method support function on ICE90 enables participants to create and operate KJ cards at the common workspace in parallel through each workstation for individual use. In comparison with the conventional KJ-Method with paper, it is easier to group KJ cards by trial and error, and to operate multiple cards in a group with ICE90.
1 0 0 0 同期会議支援システムICE90の概要と電子会議室について
- 著者
- 桂林 浩 鈴木 敏克 榊原 正義 守屋 康正
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告マルチメディア通信と分散処理(DPS)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.83, pp.63-38, 1991-09-24
オフィスでの作業は共通の目的を達成するための会議などの共同作業が中心であるが、ワークステーションによる支援は個人作業が中心である。そこで、ワークステーションによる会議の支援を考えた。まず個人作業用ワークステーションの応用可能性を検討し、次に会議支援特有の機能を実現した会議システム(E)を構築した。さらに、オフィスで行われている会議を3つのタイプに分類し、本システムにおける各タイプに対するワークステーションの利用可能性を検討した。その結果、会議タイプにより改良方法は異なるが、ワークステーションを使って支援できることを確認した。Cooperative work to achieve the shared target is the nucleus of office works, however personal work support is the major objective of many computer-supported systems. Therefore, the establishment of computer-supported meeting system is considered. We investigate the potentialities to use workstations at meetings, before making a system which includes special functions for the meetings. We classify meeting types into three, and investigate the applications of this system to support each meeting type. Consequently, the workstations indicate the potentialities to support meetings, though it requires some improvement according to meeting types.
1 0 0 0 高知県中央部の地形, 地質条件と土砂災害との関係 (1)
- 著者
- 岡林 直英 栃木 省二 鈴木 堯士 中村 三郎 井上 公夫
- 出版者
- The Japan Landslide Society
- 雑誌
- 地すべり (ISSN:02852926)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.3-10_1, 1978
1975年・1976年の台風5号ならびに17号時の豪雨に伴い, 高知県中央部では多数の土砂災害が発生した。この土砂災害について, 地形・地質条件, および2つの台風における降雨状況との関係について, 考察した結果を報告する
1 0 0 0 OA 接客労働の3極関係(<特集>労働論の現代的位相)
- 著者
- 鈴木 和雄
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.36-46, 2010-10-20 (Released:2017-04-25)
The purpose of this paper is to examine the structure of triangular relationship of the labor process in interactive service work and the effects which the relationship brings about on workers. In examining how relations of control are shaped among management, workers and customers, this paper elucidates two distinct types of control of interactive service work: control of customers by managers and workers, and that of workers and managers by customers. After showing patterns of alignment and opposition of the interests in interactive service work, this paper indicates two effects that these alignment and opposition bring about on workers. One is supervising effect of workers, as customers behave like 'another bosses' who control workers along with management in the labor process. Another is conforming effect of workers to management interests, as workers seek to control customers to increase their own work performances by aligning with management. This paper then examines transfer processes of conflicting interests among management, workers and customers. Conflicts between managers and customers are transferred to those between workers and customers, as workers appear representatives of firms in interactive service work. Conflicts between management and workers are also transferred to those between workers and customers, as customers see workers representing firms. In these transferring processes one actor represents another, which can be called as substituting effects. It is concluded that in the triangular relationship traditional conflicts between workers and management cannot be apparently manifested. In a situation in which customers become 'another bosses' and conflicting interests among actors are transferred, labor control by capital is blurred. Also in a situation in which workers seek to control customers in favor of management, real opposition between capital and labor become concealed. Therefore the triangular relationship of interactive service work tends to transform workers' class consciousness from explicit to distorted one.
1 0 0 0 IR 法医中毒学から法中毒学へ
- 著者
- 鈴木 修
- 出版者
- 日本法医学会
- 雑誌
- 日本法医学雑誌 (ISSN:00471887)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.330-344, 2000-11-05
The importance of forensic toxicology has been increasing until now, because of the increasing numbers of toxic substances and poisoning incidents. In Japan, a special translational word "houi-chudoku-gaku" has been used for the forensic toxicology especially in the field of legal medicine. The Japanese word, however, does not seem appropriate for translation of forensic toxicology, because it covers medicine, pharmacy and police sciences interdisciplinarily. In 1980, Emeritus Prof. Hidetoshi Yoshimura created an appropriate word "hochudoku-gaku" for translation of forensic toxicology. In 1982, Prof. Yoshimura and his friends established the Japanese Association of Forensic Toxicology, consisting of people from legal medicine, pharmacy and police institutes. This Association enabled lively discussions among different fields and greatly contributed to advances of forensic toxicology in Japan. We started studies of forensic toxicology using gas chromatography (GC)/mass spectrometry (MS) in 1979. Until now, we delt with solid-phase extraction (1987~1994), surface ionization GC (1989~1997), negative ion chemical ionization MS (1981~now), solid-phase microextraction (1994~now), cryogenic oven trapping GC (1997~now), surface ionization organic MS (1998~now) and high-performance liquid chromatography/tandem MS (1998~now). In this review, the author presents some details of solid-phase microextraction, negative ion chemical ionization MS, cryogenic oven trapping GC and surface ionization organic MS. Unprecedented poisoning terrorism by use of sarin took place in Matsumoto and Tokyo in 1994 and 1995, respectively. On July 25,1998, a curry poisoning incident using arsenious acid occurred in Wakayama, resulting in the death of 4 people and injury of 63 people. Since then, more than 30 imitative poisoning cases have been reported by mass communication within 1 year. In spite of the above continuing poisoning cases, almost no effective measures have been taken by the administration of our country and local governments. Many serious problems concerning poisoning and drug abuse are accumulating in Japan. In this review, the problems are also made manifest, and some proposals are presented to solve the problems.
1 0 0 0 OA ヴュルム氷期の世界の気候
- 著者
- 鈴木 秀夫
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.171-180, 1972-12-28 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 1 2
Locations of the main frontal zones in the Würm Glacial Age are reconstructed as in Fig. 1. Abbreviations in the figure are as follows: A; Arctic or Antarctic Front, P; Polar Front, NI; Northern Intertropical Convergence Zone, SI; Southern Intertropical Convergence Zone, s; northern summer location and w; northern winter location. An English version of this article with a slight difference in explanation has already appeared in the Bulletin of the Department of Geography University of Tokyo No. 3, 1971, under the title of “Climatic Zones of the Würm Glacial Age.”
1 0 0 0 OA ピッツバーグ睡眠質問票日本版を用いためまい患者における睡眠障害の検討
- 著者
- 許斐 氏元 鈴木 衞 小川 恭生 大塚 康司 萩原 晃 稲垣 太郎 井谷 茂人 斉藤 雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.502-511, 2014-12-31 (Released:2015-02-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 15
This study was performed to determine the frequency and degree of sleep disturbance in patients with dizziness using the Pittsburgh Sleep Quality Index, Japanese Version (PSQI-J), and investigate the relationship between dizziness and sleep disturbance. Fifty-two patients (20 male, 32 female) with a chief complaint of dizziness visited the dizziness clinic of the Department of Otolaryngology, Tokyo Medical University, for 3 months in 2013. The patients' age (average ± standard deviation) was 54.4±17.0 years (range, 10-88 years). The average PSQI global score was 7.6±4.2 points, which exceeds the 5.5-point cut-off for insomnia. In total, 67.3% of patients scored >6 points, and 35.8% scored >9 points, indicating definite sleep disturbance. With respect to the demography of disease groups, patients with Meniere's disease scored an average of 7.9 points, those with autonomic imbalance scored 8.8 points, and those with psychogenic dizziness scored 9.7 points; all of these diseases were associated with high PSQI scores. Patients with benign paroxysmal positional vertigo and patients with no abnormal findings showed relatively low scores (6.7 and 5.3 points, respectively). Patients with suspected sleep apnea syndrome, restless leg syndrome, and parasomnias tended to show high scores (>10 points). A high rate and high grade of sleep disturbance were confirmed in patients with dizziness, indicating that sleep quality affects several types of dizziness and vertigo. Understanding sleep disorders is helpful for the diagnosis and treatment of dizziness and provides a new perspective on the etiology of dizziness.
1 0 0 0 OA 立教関係者一一名の追放とその後
- 著者
- 鈴木 勇一郎
- 雑誌
- 立教学院史研究 = Journal of the history of Rikkyo University and Schools
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.31-59, 2018
1 0 0 0 OA 体幹筋力と静的バランスおよび立ち直り反応の関連性
- 著者
- 山崎 岳之 鈴木 珠実 上出 直人 石井 麻美子 南部 路治 清水 忍 前田 真治
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0493, 2005 (Released:2005-04-27)
【目的】姿勢保持課題には、体幹を安定させるための体幹筋力と体重心の動揺を最小限にする静的バランス能力、さらに体重心の変位を適切に修正する立ち直り反応が必要である。しかし、姿勢保持課題に対するこれらの因子が、それぞれ独立した因子なのか関連した因子なのかは明確ではない。本研究では、体幹筋力、静的バランス、立ち直り反応の各因子間の関連性を検討することを目的とした。【対象】整形外科的疾患や神経学的疾患、ならびに7日間以上継続した下肢痛と腰痛を有さない健常女性30名(平均年齢21.3歳)を対象とした。【方法】体幹筋力の測定には、ハンドヘルドダイナモメーター(Hoggan Health, MICRO FET2)を用い、徒手筋力テストの肢位で腹直筋と脊柱起立筋の筋力を3回ずつ計測した。静的バランス能力の測定には、重心動揺計(Mアニマ,G5500)を用い、前方1m先の指標を注視させながら、軸足での片脚立位を60秒間を3試行し、総軌跡長と矩形動揺面積を算出した。さらに、立ち直り反応の測定には、下記の外乱刺激発生装置と1軸(前後方向)加速度計(日本光電,TA-513G)を用いた。外乱刺激発生装置は、台車上に椅子を固定したもので、台車の後方にはロープで10kgの重錘を滑車を介して吊した。被験者を固定した椅子の上に座らせ、重錘を高さ170cmより鉛直方向へ不意に落下させることで、被験者は後方から前に瞬時に押されるような外乱を発生させることができる。外乱刺激に対する立ち直り反応を頭部に取りつけた加速度計で3試行計測し、外乱刺激発生から500ms間の各方向への頭部加速度ピーク値とピーク値までの時間を算出した。なお、被験者の体重によって、外乱のエネルギー量は変化するため、台車上に重錘を載せて負荷が一定になるよう調整をした。また、外乱刺激の同定のために台車の軌道上の床面に荷重センサーを設置した。統計処理には、計測した3試行のデータを平均化し、体幹筋力、静的姿勢保持能力、立ち直り反応の関連性を被験者の体重を制御変数とする偏相関を用いて解析した。また、体幹筋力の測定値の再現性は信頼係数アルファを用いて検討した。なお有意水準は5%とした。【結果】体幹筋力の測定値には再現性が認められた(α=0.9436)。有意な相関が認められたものは体幹屈曲筋力と総軌跡長(r=-0.56)、更に体幹伸展筋力と矩形動揺面積(r=-0.38)、外乱刺激後の前方への頭部加速度ピーク値(r=-0.48)および後方への頭部加速度ピーク値(r=0.43)に有意な相関が認められた。【考察・結語】体幹筋力が弱い程、静的バランス能力は低下する傾向にあり、また立ち直り反応も低下する傾向にあると考えられた。一方、静的バランスと立ち直り反応には相関は認められなかった。従って、体幹筋力が姿勢保持課題に大きく寄与している可能性が示唆された。