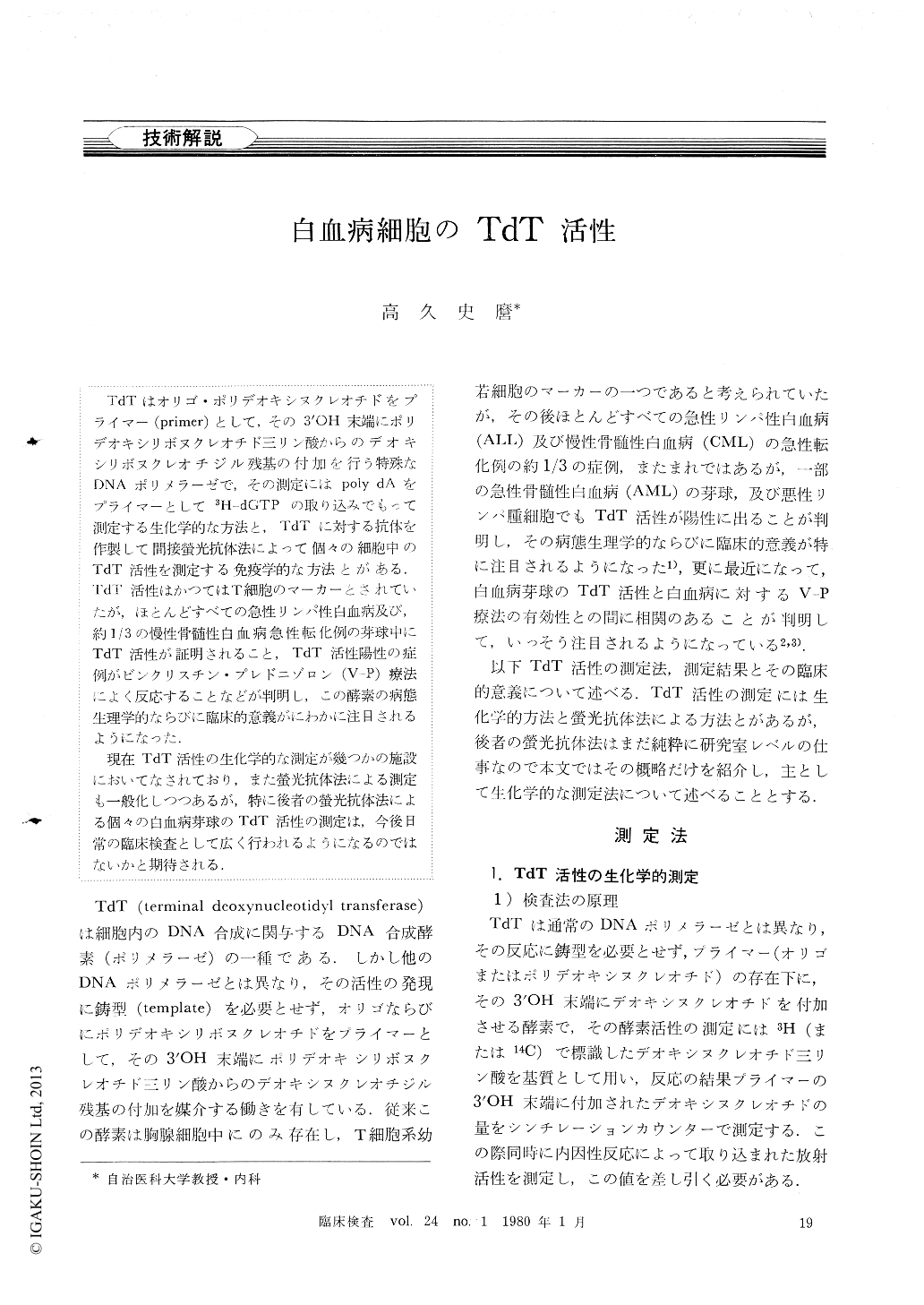3 0 0 0 ゲノムサイエンス:ヒトゲノム解析に基づくバイオサイエンスの新展開
本研究は平成2-12年度に行われた特定領域研究「ゲノムサイエンス」の研究成果をまとめ、公表し、我が国のゲノム解析計画を新段階へと発展させることを目指すものである。そこでは「ヒトゲノムの構造解析」、「ゲノムの機能解析」、「ゲノムの生物知識情報」の3項目を中心に各々に成果を取りまとめ、公開シンポジウムなどを通して社会にゲノム研究の現状、意義と今後の展望を示すことを目標とした。研究成果の報告書は、既に平成12年度の研究成果報告と共に5年間のまとめを合わせて研究成果報告書として世に出したので、今年度は公開シンポジウムに焦点をあてて研究成果を社会に公開することとした。公開シンポジウムは日本科学未来館の協力のもと、関東一円の中高生を中心に若者世代を対象として行われ、約300名が参加した。「ゲノムから見たヒト」、「ゲノム科学の医学への応用」、「ゲノムから見た発生分化」などをテマとした。講演と共にパネル討論会も開催した。また未来館長の毛利衛氏の挨拶も頂いた。この公開シンポジウムの企画は文科省ヒトゲノム計画の中核となる本研究班の班会議で決定されたが、その内容は、我が国のバイオサイエンス全般、特に多くの国民の健康に直接かかわる疾患の医学研究の発展にとっても重要なものであり、その社会的意義、必要性、緊急性はきわめて大きいと言える。
2 0 0 0 OA 重症感染症に対する抗菌薬との併用療法における静注用ヒト免疫グロブリンの効果
- 著者
- 正岡 徹 長谷川 廣文 高久 史麿 溝口 秀昭 浅野 茂隆 池田 康夫 浦部 晶夫 柴田 昭 齊藤 英彦 大熊 稔 堀内 篤 斎藤 洋一 小澤 敬也 宇佐美 眞 大橋 靖雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学療法学会
- 雑誌
- 日本化学療法学会雑誌 (ISSN:13407007)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.199-217, 2000-03-25 (Released:2011-08-04)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2 16
厚生省から再評価指定を受け, 重症感染症に対する静注用ヒト免疫グロブリン (以下MG) 製剤の抗生物質との併用効果を検証するため, 抗生物質単独投与を対照とした多施設共同非盲検ランダム化試験を実施した。広範囲抗生物質の3日間の投与において感染症の主要症状の改善が認められない無効例をmG群または対照群に無作為に割り付けた。割り付け日 (第1日目) より, いずれの群も抗生物質をimipenem/cilastatin (IPM/CS)+amikacin (AMK) に変更し, 7日間投与した。MG群のみにWIGを第1日目より1日59, 3日間連日併用投与した。効果は解熱に要した日数ならびに臨床症状の消失に要した日数を中心に判定した。有効性評価からの除外率は26.1% (178/682) であった。背景因子 (性, 年齢, 病態の区分, コロニー刺激因子 (以下CSF) 製剤投与の有無, 投与前アルブミン濃度, 投与前IgG濃度および好中球数の推移) に関してはすべての項目で両群間に偏りは認められなかった。Kaplan-Meier法にて推定した第7日目までの解熱率はmG群54.8%, 対照群37.2%で, IVIG群が有意に早く解熱した (一般化Wilcoxon検定: P=0.002)。同様に第7日目までの臨床症状の消失率はIVIG群57.3%, 対照群39.4%で, IVIG群が有意に早く消失した (一般化Wilcoxon検定: P=0.002)。客観的な半掟基準にもとつく「有効」以上の有効率はMG群61.5% (163/265), 対照群47.3% (113/239) でIVIG群が有意に優れていた (x2検定: p<0.001)。IVIG製剤は重症感染症に対し, 抗生物質との併用において有効であると考えられた。
1 0 0 0 OA 腎臓と貧血
- 著者
- 田村 峯雄 高久 史麿
- 出版者
- 社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 人工透析研究会会誌 (ISSN:02887045)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.81-89, 1973-06-09 (Released:2010-03-16)
- 著者
- 川村 肇 武田 昭 権田 信之 隅谷 護人 押味 和夫 狩野 庄吾 高久 史麿 酒井 秀明
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.159-165, 1980
- 被引用文献数
- 1
食道狭窄を合併し, 10年の長い経過後に腎症状を呈したWegener肉芽腫症の1例.<br>39才の女性. 10年の経過中,関節痛,紅斑,遊走性肺陰影,鼻汁,口咽頭びらん,鞍鼻,嚥下困難が出現し,第7頸椎の高さに限局性食道狭窄を認めた.入院中尿蛋白・顆粒円柱出現と腎機能低下がみられ, cyclophosphamide大量投与により軽快した.<br>本例の食道狭窄は, Wegener肉芽腫症の活動期に発症しており,他の誘因もないのでWegener肉芽腫症によるものと考えられる. Wegener肉芽腫症の食道狭窄合併例の報告はないが,食道に円周性びらんを呈し,組織学的に血管炎を認めた剖検報告例があり,本症も血管炎によるびらん形成後の瘢痕化による食道狭窄と考えられる.<br>また本例は10年間限局型Wegener肉芽腫症として経過した後でも古典的Wegener肉芽腫症にみられるような糸球体腎炎を呈する可能性があることを示唆している.
1 0 0 0 OA 先端医療と生命倫理
- 著者
- 高久 史麿
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.192-203, 2002-11-10 (Released:2018-02-01)
1 0 0 0 白血病細胞のTdT活性
TdTはオリゴ・ポリデオキシヌクレオチドをプライマー(primer)として,その3'OH末端にポリデオキシリボヌクレオチド三リン酸からのデオキシリボヌクレオチジル残基の付加を行う特殊なDNAポリメラーゼで,その測定にはpoly dAをプライマーとして3H-dGTPの取り込みでもって測定する生化学的な方法と,TdTに対する抗体を作製して間接螢光抗体法によって個々の細胞中のTdT活性を測定する免疫学的な方法とがある.TdT活性はかつてはT細胞のマーカーとされていたが,ほとんどすべての急性リンパ性白血病及び,約1/3の慢性骨髄性白血病急性転化例の芽球中にTdT活性が証明されること,TdT活性陽性の症例がビンクリスチン・プレドニゾロン(V-P)療法によく反応することなどが判明し,この酵素の病態生理学的ならびに臨床的意義がにわかに注目されるようになった. 現在TdT活性の生化学的な測定が幾つかの施設においてなされており,また螢光抗体法による測定も一般化しつつあるが,特に後者の螢光抗体法による個々の白血病芽球のTdT活性の測定は,今後日常の臨床検査として広く行われるようになるのではないかと期待される.
- 著者
- 月本 一郎 塙 嘉之 高久 史麿 浅野 茂隆 上田 一博 土田 昌宏 佐藤 武幸 大平 睦郎 星 順隆 西平 浩一 中畑 龍俊 今宿 晋作 秋山 祐一 櫻井 實 宮崎 澄雄 堺 薫 内海 治郎 黒梅 恭芳 古川 利温 山本 圭子 関根 勇夫 麦島 秀雄 矢田 純一 中沢 真平 小出 亮 加藤 俊一 金子 隆 松山 秀介 堀部 敬三 小西 省三郎 多和 昭雄 筒井 孟 高上 洋一 田坂 英子 植田 浩司
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.10, pp.1647-1655, 1990 (Released:2009-03-12)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rG-CSF), produced by Chinese hamster ovary cells, was administered in 69 chemotherapy-induced neutropenic pediatric patients (pts) with malignant tumors. Each pt received two cycles of the same chemotherapy and had neutropenia with absolute neutrophil counts (ANC) <500/μl in the first cycle. Initiating 72 hours after termination of chemotherapy in the second cycle, rG-CSF (2 μg/kg/day) was given subcutaneously or intravenously to each pt for 10 days. rG-CSF significantly increased ANC at nadir; 72±14 vs. 206±40/μl (data in the first cycle vs. data in the second cycle, respectively), and reduced the period of neutropenia with ANC<500/μl; 9.7±0.6 vs. 5.1±0.6 days, and the period for restoration to ANC≥1,000/μl after initiation of chemotherapy; 25.5±0.6 vs. 17.5±0.9 days. rG-CSF did not affect other components of peripheral blood. The number of days with fever ≥38°C was significantly reduced by rG-CSF treatment. Neck pain and lumbago were observed in one pt, polakysuria in one pt, and elevation of the serum levels of LDH and uric acid in one pt, however these were mild to moderate, transient, and resolved without any specific treatment. We concluded that rG-CSF was effective in neutropenia induced by intensive chemotherapy for malignant tumors without any serious side effects.
1 0 0 0 OA 自治医科大学における入学試験より医師国家試験に至る学業成績の追跡調査
1 0 0 0 OA 項目反応理論を用いた第1回共用試験医学系CBTの統計解析
- 著者
- 仁田 善雄 前川 眞一 柳本 武美 前田 忠彦 吉田 素文 奈良 信雄 石田 達樹 福島 統 齋藤 宣彦 福田 康一郎 高久 史麿 麻生 武志
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.3-9, 2005-02-25 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
共用試験CBTにおける項目反応理論の有用性を評価するために, 2002年の2-7月に実施した医学系第1回トライアルのデータを解析した. このトライアルはモデル・コア・カリキュラムの大項目分類 (6分野) をすべてカバーできるようにデザインされており, 含まれている試験問題数は2, 791題であった.各分野において, 3-40題の問題がランダムに抽出され, コンピューターシステムを用いて5, 693名 (4年生-6年生: 解析対象者5, 676名) の学生に実施された. 各学生には100題出題された. 項目反応パターンについては3母数ロジスティックモデル (項目識別力, 項目困難度, 当て推量) により分析した. 以下の知見が得られた. 1) 項目困難度と正答率には強い負の相関がみられた (r=-0.969--0.982). 2) 項目識別度と点双列相関係数には中程度の相関がみられた (r=0.304-0.511). 3) 推定された能力値と得点とには強い正の相関が見られた (r=0.810-0.945). 4) 平均能力値は学年が上がるにつれて増加した. 5) モデル・コア・カリキュラムの6分野間の能力値の相関係数は0.6未満であった. 1人ひとりが異なる問題を受験する共用試験の場合, 項目反応理論を使用することが望ましいと考える. 第1回トライアルは, 項目反応理論を使用することを想定してデザインされていなかった. 第2回トライアルでは, これらの比較を行うために適切にデザインされたシステムを用いた. 現在, この結果について詳細に解析を行っているところである.
- 著者
- 宮脇 修一 恵美 宣彦 三谷 絹子 大屋敷 一馬 北村 邦朗 森下 剛久 小川 啓恭 小松 則夫 相馬 俊裕 玉置 俊治 小杉 浩史 大西 一功 溝口 秀昭 平岡 諦 小寺 良尚 上田 龍三 森島 泰雄 中川 雅史 飛田 規 杉本 耕一 千葉 滋 井上 信正 濱口 元洋 古賀 大輔 玉置 広哉 直江 知樹 杉山 治夫 高久 史麿
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.12, pp.1279-1287, 2005 (Released:2009-07-28)
- 参考文献数
- 12
急性骨髄性白血病(Acute myeloid leukemia: AML) 191症例の末梢血のWT1 mRNA発現(Wilms tumor gene 1: WT1)量を定期的に測定し臨床経過との関連を検討した。初発未治療のAML症例におけるWT1の陽性率は93.9% (107/114)であった。寛解が得られ寛解を継続した症例66例の全例でWT1量は寛解に伴い低下し50 copies/μgRNA未満(陰性)となり,84.8% (56/66)の症例が1年後の経過観察終了時陰性であった。非寛解症例54例のうち87.0% (47/54)の症例のWT1量は,経過観察期間中50 copies/μgRNA以上(陽性)であった。寛解後再発した29例の全例において,寛解に伴い低下したWT1量は再発に伴って上昇に転じた。寛解後再発症例の79.3% (23/29)の症例のWT1の値は再発の43日(中央値)前に200 copies/μgRNAを超えて上昇していた。再発診断率,寛解継続診断率および診断効率を考慮するとAMLの早期再発診断のための基準値としては200 copies/μgRNAが妥当と考えられた。WT1量は,微小残存病変(Minimal residual disease: MRD)を反映しAMLの臨床状態に対応して変動していた。今回,WT1測定に使用したキットでは末梢血を用いたことからこのキット検査は患者への負担が少なく,定期的検査に適していると考えられた。
1 0 0 0 白血病細胞における癌遺伝子の相互作用
骨髄異型性症候群(Myelodysplastic syndrome,以下MDS)は主に高令者をおかし,血液学的に末梢血の汎血球減少と骨髄の異型を伴う正〜過形成像を主徴とする予後不良な疾患である。我々は既に,本症患者骨髄細胞DNAをNIH3T3細胞に遺伝子導入した後,悪性形質転換をヌードマウスにおける腫瘤形成能により検定し,本症患者骨髄中に,N-rasがん遺伝子コドン13における点突然変異がしばしば観察されることを報告した。このin vivo selection assayは活性化がん遺伝子を非常に高い感度で検出するが,操作が非常に煩雑で時間を要するため,多数の検体を調べることは困難であった。そのため,本年度は、ポリメレース・チェーン・リアクション(PCR)とオリゴヌクレオチド・ハイブリダイゼーションを組みあわせて,MDS症例の骨髄細胞中におけるN-rasの点突然変異の有無を検討した。N-rasがん遺伝子はそのコドン12,13,61における点突然変異により活性化を受けることが知られているので,上記の領域を含むような範囲の両端のプライマーを用意し,患者骨髄DNAに加えて,Taq ポリメレースによりPCR法で,当該領域を選択的にin vitroで遺伝子増幅した。これをフィルターにドット・ブロットし,それぞれのコドンの点突然変異を出しうるようなオリゴヌクレオチド・プローブでハイブリダイゼーションした。本法により,患者骨髄細胞中に1%の点突然変異をもつ細胞が存在すれば,それを同定することができた。19例,のべ21検体のMDSについて検討した所,RA(refractory anemia)の一例,RAEB in T(refractory anemia in transformation)の一例そして,MDSより急性白血病へ進行した一例において,それぞれコドン61,12,61における点突然変異が同定された。以上より,点突然変異のおこる位置とMDS,急性白血病の間には何ら相関がないことが推定され,また,本法はその簡便性と高い検出感度により,前白血病状態の患者の経過観察に有用であると考えられた。
1 0 0 0 白血病細胞における癌遺伝子の相互作用
ヒト白血病細胞における癌遺伝子の機能、相互連関を明らかにする目的で、これまでにPCRを用いてNーRAS、ABLなどの既知の癌遺伝子の活性化の有無を検討した。更に、白血病細胞に特異的に発現している新しいタンパク質チロシンキナーゼ遺伝子であるヒト1+K遺伝子のcDNAをクローニングし、その構造、発現、機能について検討した。1.PCRによる活性化癌遺伝子の検出種々のヒト白血病、前白血病よりDNAもしくはRNAを抽出し、ヒトNーRASをPCRもしくはRTーPCRにより遺伝子増幅した。急性白血病18例中5例、慢性白血病12例中0例、前白血病状態23例中3例にNーRASコドン12、13、61における点突然変異を検出した。この検出感度は全細胞の1%に点突然変異が存在すれば、これを検出できた。更に、RTーPCRによりBCR/ABL再配列mRNAの有無を検討した。慢性骨髄性白血病、Philadelphia染色体陽性急性リンパ性白血病の全例に再配列mRNAが検出された。この検出感度は10^6細胞に1つの突然変異細胞を検出できた。このように、PCRを用いると非常に高感度、簡便に突然変異を検出でき、患者の経過を観察する上で、有意義であった。II.新しいチロシンキナーゼ遺伝子1+Kヒト白血病に関与していると思われる新しい癌(関連)遺伝子を同定する目的で、ヒト白血病細胞株であるK562のcDNAライブラリーをcーfmsプローブで低ストリンジェンシーで、スクリーニングしクローニングを得た。構造解析により、これはマウスで報告された1+Kのヒトホモログであることが分かった。この遺伝子は膜貫通部位とチロシンキナーゼドメインを持ち、ROS遺伝子と強いホモロジーを示すいわゆるレセプタータイプのチロシンキナーゼである。18例の血液悪性腫瘍細胞(株)と17例の非血液悪性腫瘍株についてトザンハイブリダイゼーションにより発現を検討した。10例の血液悪性腫瘍(株)発現が見られたが、他の非血液腫瘍に見られなかった。
白血病においても他の悪性腫瘍の場合と同様に活性化された癌遺伝子、すなわちtransforming geneが存在することが証明されている。transforming geneの証明には、通常、培養NIH3T3細胞を用いるtransfection assayが行われているが、われわれはその方法を用いて32例の白血病症例を対象にして患者白血病細胞DNA中のtransforming geneの有無を検索し、4例でその存在を確認、この中の2例(慢性骨髄性白血病ならびに急性リンパ性白血病各1例)で遺伝子のクローニングを行って、いずれもN-ras oncogeneの34番目のヌクレオチドがguanineからthymineに変わっており、この点突然変異がN-ras oncogeneの活性化すなわちtransforming geneの存在にむすびついていることを明らかにした。また、腫瘍細胞由来のDNAをtransfectしたNIH3T3細胞をヌードマウスに移植して、腫瘍の形成によるtransforming geneの検索をも行い、前白血病状態と呼ばれる病態でも、その半数でtransforming geneを証明した。各種の分化、増殖因子やレセプターと癌遺伝子との密接な関係が注目され、癌遺伝子の質的、量的変化が各種疾患の病態の発現に重要な役割を演じていることが明らかになってきているが、われわれの行った血液細胞における分化・増殖因子とレセプター、癌遺伝子ならびにレトロウイルスなどを中心とする研究は今後、白血病の病態の解明に大きく寄与するものである。
1 0 0 0 AAABC療法による悪性リンパ腫の自家骨髄移植
- 著者
- 高木 省治郎 須田 啓一 小松 則夫 大田 雅嗣 加納 康彦 北川 誠一 坪山 明寛 雨宮 洋一 元吉 和夫 武藤 良知 坂本 忍 高久 史麿 三浦 恭定
- 出版者
- The Japanese Society of Hematology
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.2274-2280, 1986
Five patients with malignant lymphoma in whom primary chemotherapy had failed were treated with high-dose chemotherapy using AAABC regimen, total body irradiation, and transplantation of cryopreserved autologous marrow. Complete remission was achieved in all five patients. In these patients, the recurrence of malignant lymphoma did not occur during the follow up time of 2 to 59 months after autologous bone marrow transplantation. Three of them are alive in continuous remission for 33, 49, and 59 months, respectively. In one of these three patients, acute lymphoblastic leukemia developed 44 months after bone marrow transplantation. However, successful chemotherapy resulted in a complete remission of leukemia, he is alive in remission. The remaining two patients died of pneumonia and respiratory failure 72 days and 82 days after bone marrow transplantation, respectively. Our results show that intensive chemoradiotherapy and autologous-marrow transplantation can produce a prolonged remission in patients with malignant lymphoma in whom conventional chemotherapy has failed.
1 0 0 0 老年痴呆の分子機構-研究の総括-
当研究班では脳老化に伴う神経変性とくにアルツハイマー型老年痴呆を中心課題としてとり挙げ、その発症機序を分子生物学的ならびに分子遺伝学的手法により追求した。まず神経系細胞の生存維持に直接関与する神経栄養因子に関しては神経成長因子(NGF)およびそのファミリー蛋白質であるBDNF,NT-3,4,5を中心に特異抗体の作成とそれによる鋭敏な測定方法の確立、受容体のTrkA,B,Cなどの核酸、蛋白レベルでの検索で成果を挙げた。さらに神経突起進展作用を持つ新しい細胞接着因子ギセリンを発見し、逆に成長を遅らす因子GIFについてそのcDNAのクローニングから発現状態までを明らかにした。アルツハイマー病の2大病変である老人斑と神経原線維変化(PHF)については、主な構成成分であるβ蛋白とタウ蛋白を中心に検討を進めた。β蛋白に関してはびまん性老人斑は1-42(43)ペプチドから成り、アミロイド芯と血管アミロイドは1-40ペプチドから成ることを発見した。タウ蛋白に関しては、そのリン酸化酵素TPKI,IIを抽出し,それがGSK3とCDK5であることをつきとめた。さらには基礎的な業績として神経細胞突起の構成と機能、とくに細胞内モーター分子についての広川らの業績は世界に誇るものである。アルツハイマー病の分子遺伝学上の重要点は第14,19,21染色体にある。第14染色体の異常は若年発症家系で問題となり、わが国の家系で14q24.3領域のS289からS53の間約8センチモルガンに絞り込んでいた。最近シエリントンらによりpresenilin I(S182)遺伝子が発見され、その変異が上記のわが国の家系でも検出された。第19染色体のアポリポ蛋白E4が、遅発性アルツハイマー病のみならず早発性の場合にも危険因子となることを、わが国の多数の症例から明らかにした。第21染色体ではダウン症関連遺伝子とともにAPP遺伝子があり、そのコドン717の点変異をわが国のアルツハイマー家系でも確認した。さらに第21染色体長腕部全域の物理地図を完成した大木らの業績は今後、学界への貢献度が大であろう。これらの研究成果を中心に、単行本として「アルツハイマー病の最先端」を羊土社より平成7年4月10日に発行し、また週刊「医学のあゆみ」の土曜特集号として平成7年8月5日号に「Alzheimer病-up date」を出版した。