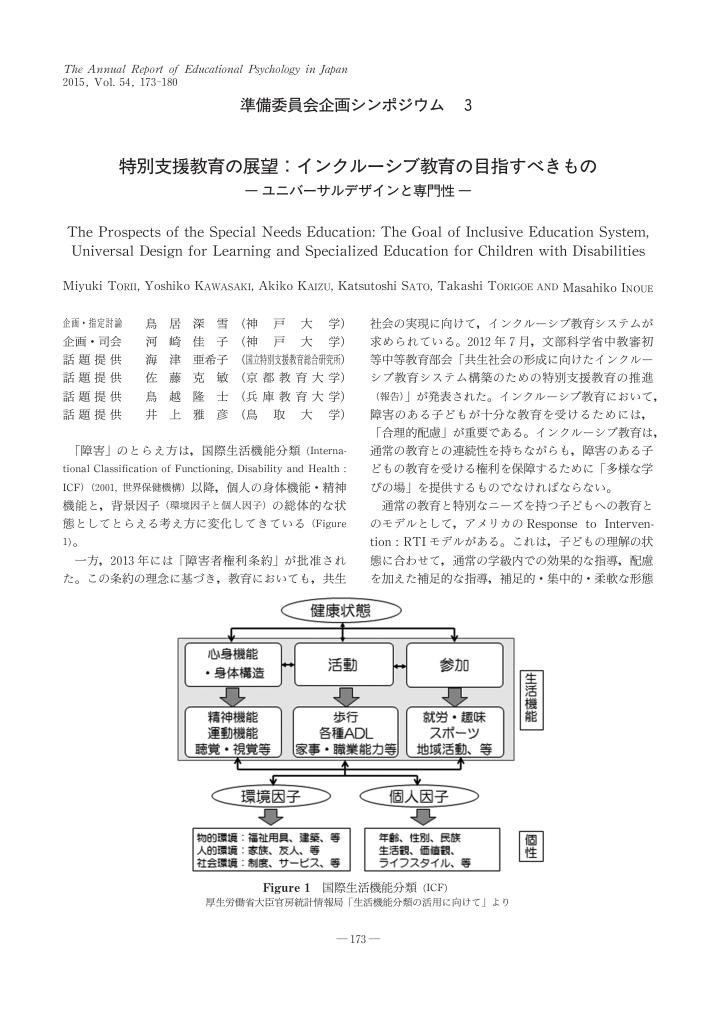1 0 0 0 新しい家庭の建設(座談会)
- 著者
- 山田 恭平 千代 章一郎
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会中国支部研究報告集
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.733-736, 2012-03
1 0 0 0 ANCを用いた広島平和記念式典での騒音対策の基礎検討
- 著者
- 田中 大輔 石光 俊介
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- Dynamics & Design Conference
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
<p>Every year the City of Hiroshima holds the Peace Memorial Ceremony to console the souls of those who were lost due to the atomic bombing as well as pray for the realization of everlasting world peace. Since the ambient noise of this ceremony is very loud, these noise was tried to reduce using a passive method and Active Noise Control (ANC). There are some problems that audiences or TV crews cannot catch the meanings of presenter's messages such as the Prime Minister's, because of ambient noise. To reduce these noises, tents were prepared in the venue. There were also useful for protect people from the strong suns. The difference between the sounds near the loudest place in the park and those in the venue was measured to confirm the effectiveness of each countermeasure. The one of the loudest noise came from an opposite bank of the river. Though the noise was detected at the river side, it was not detected in the venue. As a result, the noise in the venue was reduced by 15 dB owing to each countermeasure. As most of the noise are speech, a 6-second young woman's voice was used as the noise source and reference signal in the ANC test of this study. Noise source includes the high frequency components up to 4000Hz. High-speed signal processing was required to reduce the noise that has high frequency components and changes its amplitudes rapidly. FPGA with a clock of 40MHz was selected for the fast signal processing. Filtered-x LMS algorithm was used in the ANC, and sampling frequency was 15 kHz and adaptive filter coefficients were set to 3000 tap. As the results of control, the noise was reduced by 10dB in 500Hz to 5000Hz.</p>
1 0 0 0 Twitterにおけるニュースツイートの閲覧と動画視聴の関連性
- 著者
- 小川 祐樹 高野 雅典 森下 壮一郎 高 史明
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, pp.1D4OS3c03, 2021
<p>様々なニュースメディアが存在するなか、人々のニュースに対する意識や行動も多様化してきている。ネット上におけるニュース接触に関しても、新聞社・通信社が運営するニュースサイトや、ポータルサイトからニュースを知るといった場面だけでなく、SNS上でニュースを知るといった場面も一般的になりつつある。一方で、TwitterなどのSNSは同質な情報環境になりやすいことから、利用者が接触できるニュースの範囲や内容が限定的になってしまうことで、多様な情報に接触する機会が低下してしまうことが懸念される。本研究では、Twitter上でのニュースツイートに着目し、このツイートの閲覧者がその後どのようなニュース動画の視聴行動を行ったかを分析することで、Twitter上でのニュース閲覧の効果を考察する。具体的には、ニュースのツイートとそこからリンクされるニュース動画の視聴ログを用いて、ニュースの継続視聴や視聴ジャンルの変化などの行動を分析する。</p>
1 0 0 0 OA 銀電極を基準とした電極電位と電池の極性(小・中・高のページ)
- 著者
- 小池 守 森川 鐵朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.878, 1992-12-20 (Released:2017-07-13)
- 著者
- 関本 静一 斎藤 賢弘 五十嵐 哲 大原 守弘 西間木 友衛 粕川 禮司
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.8, 1985
- 出版者
- 飛鳥新社
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA コールド・チェーンにおける青果物の品質保持と温度許容度に関する研究
- 著者
- 緒方 邦安 伊東 卓爾 岩田 隆
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.8, pp.394-399, 1974-08-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
コールド・チェーンにおける果実そ菜の品質保持と温度変動の許容度との関係について,今回はホウレンソウとセロリーについて調査した。(1) ホウレンソウの商品性保持期間は1℃区で約5週間,6℃区で約15日,20℃区では3~4日であった。冷蔵遅延区は20℃の影響が強く,1日の遅れは1℃区に比べて約25日間劣った。6℃ 3日→1℃区も約10日間短縮された。冷蔵中断区は20℃下で急激な鮮度低下を示した。また貯蔵温度の変動は著しい品質低下をまねき,商品性保持期間はかなり短縮された。(2) セロリーでは,20℃区は5~6日後に腐敗を生じ商品性を失なつた。6℃区は25日前後が限界であったが,1℃区は約35日間商品性を保持した。冷蔵中断区では,中断後急速に商品性を失った。1℃〓6℃(1日毎)と1℃〓6℃(5日毎)の変温区を比較すると,5日ごとの区が1ごとの区よりも7日近く劣った。(3) ホウレンソウの還元型アスコルビン酸含量は,貯蔵中に減少したが,とくに冷蔵の遅れや中断によって強く影響を受け減少した。(4) セロリーの揮発性成分のGLCパターンは貯蔵温度により大きな影響を受け,とくに20℃区および6℃区での商品性の限界付近でのピークとの著しい増加を認めた。1℃区では28日後でもピークとの増加はなく,逆にピークaの増加を認めた。(5) セロリーの還元糖含量は,1℃区では漸次増加する傾向にあり,6℃区はほとんど変らず,20℃区は減少の傾向を示した。(6) 以上のように,ホウレンソウおよびセロリーは低温要求度が高く,かつ温度変動に敏感に反応することが判明した。したがって,このような青果物では,収穫後ただちに1℃付近の低温でしかも厳密に調整された条件の下で貯蔵を行なう必要があることを指摘した。
1 0 0 0 自閉症スペクトラム障害の言語行動のアルゴリズム構築
①日本語話者の自閉症スペクトラム障害(以後ASD)児/者及び定型発達児/者の話し言葉のコーパスを基に、選択体系機能言語学(SFL)の理論的枠組みによる語彙-文法資源の選択網を作成し、ASD児/者が選択する語彙-文法資源と定型発達児/者のそれを対照し、ASD児/者の言語資源の選択網を作成する。②①で得られたシステムネットワーク(選択網)を基に、ASD児/者の言語選択のアルゴリズムを作成し、ASDの言語脳解析及び言語セラピーへの適用を目指す。③①のコーパスに対応する英語話者のASD児/者及び定型発達児/者のコーパスを構築し、選択網の対比マッピングを行い、日英語の語彙-文法資源選択の対照研究を行う。
1 0 0 0 OA 復興と文化の創造―被爆都市広島のビジュアル・エスノグラフィ
- 著者
- 松尾 浩一郎 根本 雅也 小倉 康嗣 清水 もも子 後藤 一樹 土屋 大輔 福山 啓子 岩舘 豊 加藤 旭人 鈴木 雅人 長峯 ゆりか
- 出版者
- 帝京大学
- 雑誌
- 挑戦的萌芽研究
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
本研究では、原爆投下日である8月6日の広島平和記念公園という象徴的な時間と空間に着目し、ビジュアル・エスノグラフィの手法を用いてその包括的な記録と分析を行った。本研究から明らかになったことは、8月6日の平和記念公園では、広島における原爆被災とその後の復興の過程が、きわめて多様なやり方で受け止められているということである。原爆という一つの出来事を受け止めるにも、お互いに鋭く対立しあうような複数の立場性がある。それらが一つの時空間のなかで「共存」しているありさまを、映像データを駆使して明らかにした。
1 0 0 0 OA 四季和洋料理法 : 簡易速成
1 0 0 0 21pAB-6 横方向のウオブリング運動モードの安定性について
- 著者
- 田辺 和子 田辺 孝哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.71, 2016
- 著者
- 柄澤 薫冬 窪田 亜矢
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.1114-1121, 2015-10-25 (Released:2015-11-05)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 2
災害により甚大な被害が発生すると元から離れた位置で復興せざるを得ない。津波や土砂災害だけでなく、火災や建物倒壊であっても多くの人が移動を強いられる。しかし、移動は往々にしてコミュニティを寸断し、人間関係の希薄化を招く。本稿では阪神淡路大震災において復興のモデルケースと名高い芦屋市若宮町を取り上げ、復興プロセスの実態と20年経た現在における住民の認識を分析した。若宮町では、良い空間であると内外から評価されているものの、震災前後の物理的空間は全く変質しており、復興事業完了直後は住民は「良い」と感じていなかった。むしろその後の復興プロセスで、新たな人間関係を形成しながら「若宮町」とは何かの概念をお互いに集団の中で醸成していくことが帰属意識につながり、満足感を得る状況が明らかとなった。
1 0 0 0 IR カリフォルニア稲作と移民日本人 : その資料に関する考察
- 著者
- 立岩 寿一 Toshikazu Tateiwa
- 出版者
- 東京農業大学
- 雑誌
- 東京農業大学農学集報 = Journal of agriculture science, Tokyo University of Agriculture (ISSN:03759202)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.1-8, 2020-06
カリフォルニアの商業的稲作には多くの移民日本人達が最初から深く関わっていた。日本人差別と排斥が強まる中で移民日本人たちが現地社会とどのような関係をつくり地域に根付いていったのかは,アメリカ農業史と日本人移民史をクロスさせた研究となる。しかし差別と排斥ゆえに資料的制約が大きい。本稿はこの制約を乗り越えるため,「動産抵当証書」,「入国カード」,現地雑誌・ジャーナル,「日米年鑑」等の意義と分析方法を考察し,英語表記と日本語表記(漢字)の対照,移民日本人の特定方法を明らかにした。それにより20世紀初頭日本人移民の農村での定着過程が明らかになる。
1 0 0 0 IR 虚報被害者救済法の日本法的アプロ-チとコモンロ-的アプロ-チ
- 著者
- ミドルトン ジョン
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 法学研究 (ISSN:04393260)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.241-306, 1996
1 0 0 0 OA 人と法を結ぶもの 弁護士の不在と非専門リソース
- 著者
- 大澤 恒夫
- 出版者
- 日本法社会学会
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.70, pp.206-219, 2009 (Released:2017-01-31)
1 0 0 0 OA 少額事件•本人訴訟と裁判手続
- 著者
- 和田 仁孝
- 出版者
- The Japanese Association of Sociology of Law
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.43, pp.22-30,232, 1991-04-30 (Released:2009-01-15)
This paper examines the conditions on which small Claim litigation process canbe more favorably accepted by lay litigants. The point is that, beyond the role of legal decision-malcer, judges should give emotional support lay litrgauts to help them establish theiv own strnctnred idea of their problems. In order to make this judge's newrole workable, followiny alternative perceptions on litigation, lawyers and small claim cases must be emphasized:1) litigation as a process of transformation of each litigants idea of his problem, 2) judge as dispnte processor or negotiator (not as "legal" profession), 3) small claim case as a complex which consists of emotioual, societal and legal problems.
- 著者
- 寺尾 洋
- 出版者
- 九州法学会
- 雑誌
- 九州法学会会報 九州法学会会報 1989 (ISSN:24241814)
- 巻号頁・発行日
- pp.7-8, 1990-09-29 (Released:2017-08-17)