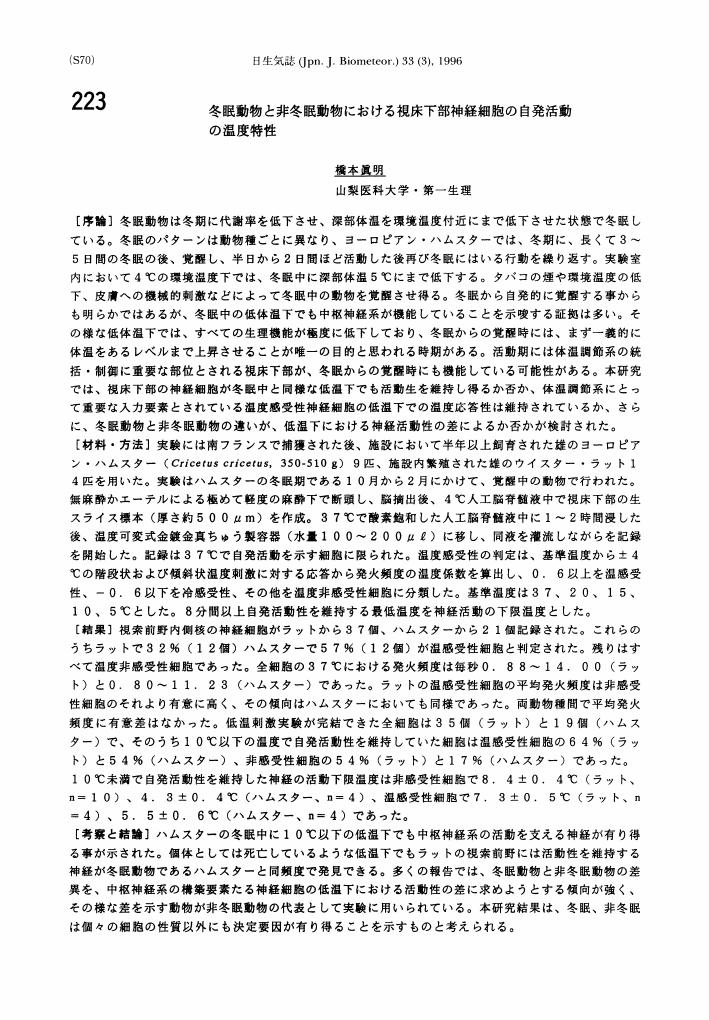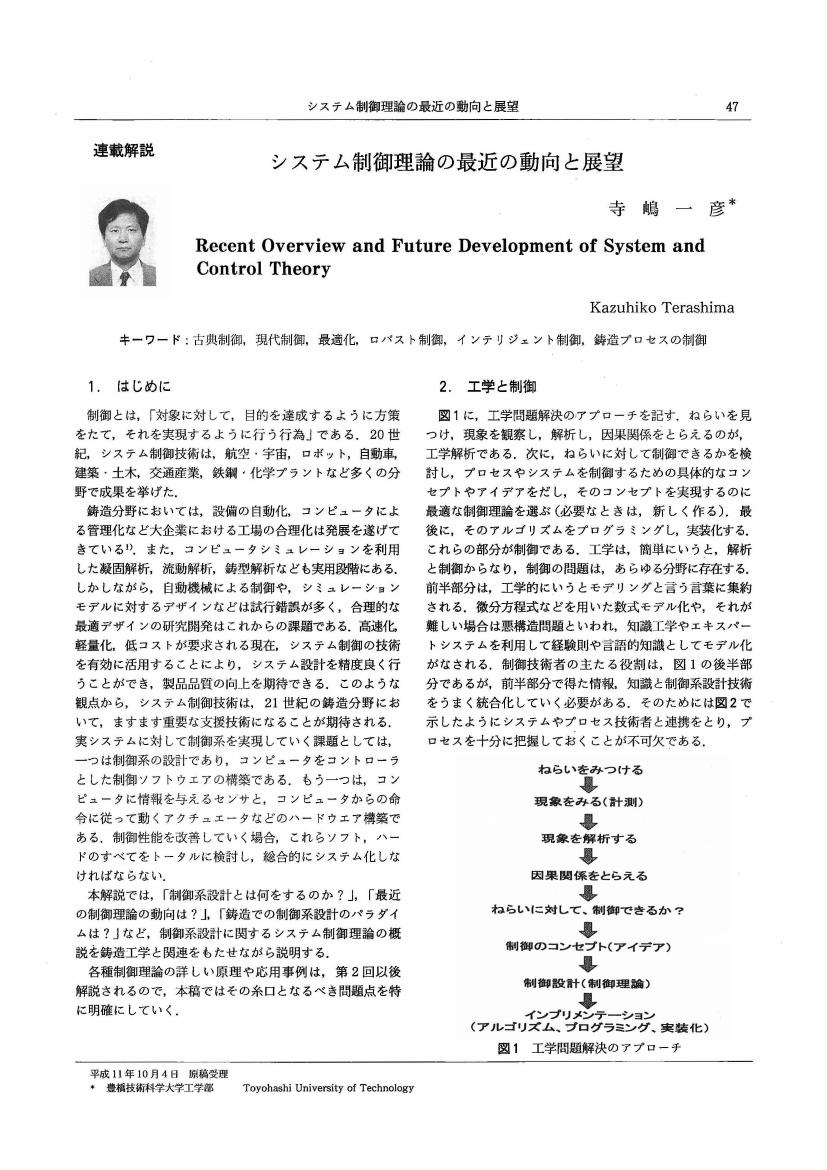1 0 0 0 OA 223 冬眠動物と非冬眠動物における視床下部神経細胞の自発活動の温度特性
- 著者
- 橋本 眞明
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.S70, 1996-10-19 (Released:2010-10-13)
1 0 0 0 OA 絶海中津の仏儒一致の思想と道家思想の受容 : 詩集『蕉堅稿』を中心に
- 著者
- 余 六一 任 萍
- 雑誌
- 神戸女学院大学論集 = KOBE COLLEGE STUDIES
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.41-47, 2008-06-20
絶海中津是日本〓〓宗禅僧,也是日本中世禅林的代表人物,〓同門〓堂周信同被称〓"五山文学双壁"。其詩文造詣高深,作品《蕉堅集》被視〓日本五山文学的瑰宝。他33〓入明留学,在明滞留〓間〓〓10年,其留学〓〓不〓使其詩文造詣大〓提高,而且思想上也深受中国禅林〓〓的影〓。其詩文集《蕉堅稿》就集中体現了其〓儒一致思想及其〓道家思想的受容。前者可从其多次提及宋代倡〓〓儒一致的代表人物契嵩及其《〓教編》,并多次借用〓代僧,儒交好的典故〓抒胸臆等得以看出,后者則在其詩中多〓表〓了隠逸出世思想和逍遥游世的〓度中得以体現。通〓〓《蕉堅集》的考察和研究,我〓不〓窺出絶海中津在思想〓面上有着〓同〓期日本禅林僧侶不同的特点,尤其〓得〓注。
1 0 0 0 OA 基礎歯科医学教育におけるiPad とデジタル教材の利活用について
- 著者
- 山崎 洋介 網干 博文 湯口 眞紀 鳥海 拓 高詰 佳史 磯川 桂太郎
- 出版者
- 日本デジタル教科書学会
- 雑誌
- 日本デジタル教科書学会年次大会発表原稿集 日本デジタル教科書学会2014年度年次大会 (ISSN:2188062X)
- 巻号頁・発行日
- pp.89-90, 2014 (Released:2017-06-14)
- 参考文献数
- 4
日本大学歯学部では、2013年からiPadを導入した講義・実習を開始した。年度ごとに順次導入を進め、2014年度には全学生の約半数にあたる第1~3学年の学生がiPadを保有し、利活用している。iPadは大学から学生に配付または貸与されたものではなく、学生個人が購入したもので、いわばBYOD(Bring Your Own Device)の形式であるから、MDM(Mobile Device Management)の仕組みで機能制限を課すことも行っていない。勉強にもプライベートにも垣根なくiPadを利用することで、より活用度が高まると考えての方略である。今回、iPad利用に合わせて各種のデジタル教材を独自に開発・利用したので報告する。
1 0 0 0 IR 香川県郷土教育史研究序説(1)
- 著者
- 溝渕 利博
- 出版者
- 高松大学・高松短期大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:21851786)
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.117-232, 2016-02
1 0 0 0 OA 現代ロシア正教聖職者の護教論
- 著者
- 渡辺 圭
- 出版者
- 日本ロシア文学会
- 雑誌
- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.121-140, 2015-10-15 (Released:2019-05-22)
- 著者
- 井島 正博
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.58-63, 2012-04-01 (Released:2017-07-28)
1 0 0 0 OA 仁田義雄『語彙論的統語論』の疑問
- 著者
- 島田 昌彦
- 雑誌
- 金沢大学文学部論集. 文学科篇 (ISSN:02856530)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-26, 1982-03-25
金沢大学文学部
1 0 0 0 OA システム制御理論の最近の動向と展望
- 著者
- 寺嶋 一彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本鋳造工学会
- 雑誌
- 鋳造工学 (ISSN:13420429)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.47-56, 2000-01-25 (Released:2014-12-18)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 IR 大学英語授業における英語資格・検定試験の利用と位置付け -自主的学習促進の観点から-
- 著者
- 松岡 弥生子
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A 教育研究 = Educational Studies (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.111-118, 2020-03-31
文科省によるグローバル人材育成推進を目的とした英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試 験の活用促進は,大学の一般英語授業の内容や評価指標に少なからぬ影響を与えている。中でも TOEIC は,企業や就職活動との関連性が強いことから,多くの高等教育機関において正課および課外のカリキュ ラムに取り入れられている。本論では,TOEIC の一般英語授業への適用方法や学習効果を考察するため, 2 年生必須のビジネス英語(授業 A)と 3 年生の選択英語ライティング(授業 B)の 2 つの授業を取り あげ,省察と検証を行う。各授業のとTOEIC との関係性と評価方法,取り入れた問題の具体的な内容 等を報告する。特に授業 A については,TOEIC 対策問題の授業内導入に対する学生の受け止め,モチベー ションなど,学習者アンケートの結果,および事前事後のミニ模試の結果もふまえて,低習熟度クラス への外部検定試験の導入に対する問題点を探る。 Now that the term globalization is sweeping across Japan, Ministry of Education, Culture, Sports and Technology Japan (MEXT) is aggressively promoting the use of foreign language (FL) proficiency tests to foster human resources with high-level FL competence. Many of Japanese universities and colleges are mainly focusing on TOEIC (Test of English for International Communication) because of its strong relation to job market requirement and its pervasiveness in Japan's society. They are offering TOEIC preparation courses in both regular curricula and extracurricular activities. Moreover, as the test spreading more and more widely, the influence of TOEIC on ordinary English courses may become significant, in terms of content, activities, purposes, and assessment. The present research notes report on the application of TOEIC in regular skill-based English courses and discusses the feasibility and effectiveness of implementing language proficiency tests in higher education. Two English classes discussed in this paper are a compulsory business English course for sophomores (Class A) and an academic English writing course for juniors and seniors (Class B). The paper examines their relationship with TOEIC, the inclusion of materials and content of TOEIC, and effects of the application of TOEIC.
- 著者
- Masateru MAEDA Hao LIU
- 出版者
- The Japan Society of Mechanical Engineers
- 雑誌
- Journal of Biomechanical Science and Engineering (ISSN:18809863)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.344-355, 2013 (Released:2013-12-24)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 10 22
In very few studies it is shown that an increase in vertical force can be achieved when a flapping-wing hovers in ground effect (IGE). The body, however, has usually been neglected and its influence on three-dimensional vortex structures and consequent aerodynamic forces is still unclear. In this study we carried out a computational fluid dynamic study of a fruit fly (Drosophila melanogaster) hovering for two cases: “in ground effect” and “out of ground effect” (OGE), where the heights from the ground are less than one and more than five times the wing length, respectively. The wings in the IGE computation generated merely 0.7% larger wingbeat cycle-averaged vertical force than in the OGE condition. The body, in contrast, exhibited a significant increase in the vertical force: when out of ground effect, the average vertical force of the body was almost zero (-0.0025 μN); whereas in ground effect, the force increased to 0.78 μN, which is the major contributor to the 8.5% increase in the total vertical force (from 9.9 μN at OGE to 10.8 μN at IGE). Meanwhile, the aerodynamic power of the wings decreased by 1.6%, resulting in a 10% improvement in the overall vertical force-to-aerodynamic power ratio. The flow-field visualization revealed that the downwashes generated by the wings create a high pressure “air cushion” underneath the body, which should be responsible for the enhancement of the body vertical force production. Our results point to the importance of the presence of body in predicting the vertical forces in flapping flights in ground effect.
1 0 0 0 OA 海浜リゾートの創設と観光資本家:東京ベイ臨海型テーマパークの魁・三田浜楽園を中心に
- 著者
- 小川 功
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.1-14, 2009-03
現在東京ベイ・エリアは東京ディズニー・リゾートに代表される海浜リゾートの一大集積地である.当該地域の臨海遊園地の先駆として京成電鉄直営の谷津遊園とともに三田浜楽園が有名で,ともに湾岸部の塩田等を埋め立てて築造された.本稿では戦前期に文豪川端康成,太宰治なども滞在して小説の舞台となった日本文学ゆかりの三田浜楽園を取り上げる.事業の永続性にリスクが不可避な観光経営の視点からこの種の観光施設の経営が一般には不安視されていた時期に,いち早く東京湾岸の将来性に着目して一大海浜リゾートを創設した資本家は如何なる人物で,広大な敷地と巨額の建設費はいかなる手段により調達されたのかを明らかにしようとしたものである.すなわち同地は明治初期に高級軍人により塩田として開発され,請負業者などに譲渡され地元の船橋商業銀行の資金で拡張された.この間請負業者の没落,船橋商業銀行の破綻,台風による水害等を経て最終的に塩田の権利を継承したのは京和銀行専務の平田章千代であった.平田塩業により経営された塩田もやがて塩田そのものの採算性の低下に加え,金主の京和銀行の破綻という予期せぬ不幸に見舞われる.こうした環境の激変の最中に昭和2年12月遊園地,温泉旅館,土地建物の経営を目的とする資本金10万円の観光企業・三田浜楽園が設立された.本稿では設立時の三田浜楽園の役員構成等を詳細に分析することにより,京和銀行の人脈との関係を解明しようと努めた.また北海道の「板谷財閥」から海運業で蓄積した豊富なリスクマネーが三田浜楽園の土地を担保として豊富に供給された事実も明らかにした.
- 著者
- 柳川 重規
- 出版者
- 日本比較法研究所
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.63-73, 2016-12-30
2016年1月30日に多摩キャンパスにおいて開催された日本比較法研究所と韓国・漢陽大学校法学研究所共催のシンポジウム「日本及び韓国における現在の法状況」における報告
1 0 0 0 OA 純化論の観点から見た近代国語観の多様性に関する歴史的研究
近代日本の国語政策をG.Thomasによる純化論の観点から類型化した上で、明治期の国語調査委員会及び文部省による標準語政策は第一次世界大戦前のヨーロッパの帝国的国家語を志向した改革的純化論に当たるものとして位置づけられること、大正・昭和期以降の柳田国男を中心とする民俗研究における国語観は第二次世界大戦後のヨーロッパ新興国家の国語観を意識した民俗的純化論であったこと、さらに、標準語教育が破綻した学校教育現場で地域方言を郷土を象徴する教材としてとらえるようになったことを明らかにし、これらの民俗的純化論の姿勢が戦後の民主的な共通語政策の前提となっていったことを歴史的に明らかにした。
1 0 0 0 OA [研究ノート] レギュラシオン理論と「制度の経済学」
- 著者
- 若森 章孝 大田 一廣
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.653-670, 1994-10-30
1 0 0 0 宇宙論 並行宇宙は実在する
- 著者
- Tegmark Max
- 出版者
- 日経サイエンス
- 雑誌
- 日経サイエンス (ISSN:0917009X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.26-40, 2003-08
この世には「別の宇宙」がたくさん存在し,あなたとまったく同じ人生を歩んでいる「もう1人のあなた」がどこかにいる。そんなバカな? いやいや,宇宙に関する最新の観測結果は「並行宇宙」の存在を示唆している。
1 0 0 0 OA ウェブ実験の長所と短所,およびプログラム作成に必要となる知識
- 著者
- 黒木 大一朗
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.250-257, 2020-03-31 (Released:2020-06-09)
- 参考文献数
- 26
Recently Web-based/online psychological studies have been reported, in which web browsers familiarized by participants such as Microsoft Edge, Apple Safari, and Google Chrome are used for presenting stimuli and recording responses. The present article summarizes advantages and disadvantages of conducting Web-based experiments, and provide brief explanations of the knowledge required to create the programs. Technically speaking, it is better to know HTML, CSS, JavaScript (frameworks), and web servers. Web-based studies will be conducted more broadly in psychology because researchers can recruit more efficiently large and diverse samples from crowdsourcing marketplaces than from traditional participant pools.
- 著者
- 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ 宮崎大学地下水ヒ素汚染研究グループ
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.105-126, 2000-03-25 (Released:2017-07-14)
- 被引用文献数
- 4
1996年以来,インド西ベンガル州とバングラデシュで重大な健康被害をもたらしている,地下水ヒ素汚染について,アジア砒素ネットワーク(AAN)と応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ(RGAG)は,バングラデシュのシャムタ村をパイロット地区として活動してきた.地下水調査ではAANと宮崎大学は,地下水のヒ素濃度と水質を民家所有井戸について主に調査した.RGAGはヒ素汚染解明のため,1998年からコア分析を含む水文地質調査と地下水モニタリングを行ってきた.AANの調査では,地下水中のヒ素濃度として,村の南部で0.05mg/l以上,北部でそれ以下の値を得た.シャムタ村は,ガンジスデルタに位置するため,標高海抜約5〜7mであり,自然堤防と後背湿地からなる.既存資料や調査結果から深度約200mまでの地質は,下位より下部砂質層,下部泥質層,上部砂質層,上部泥質層,最上部砂質層,および最上部泥質層であり,下部砂質層は,第二帯水層,上部砂質層は,第一帯水層に区分される.第一帯水層は,ヒ素に汚染されているが,公衆衛生工学局(DPHE)で使用している深井戸は,第二帯水層に含まれ,第一帯水層ほどヒ素には汚染されていない.地下水位変動では,第一帯水層は漏水系帯水層の特徴を示し,農業用井戸による第一帯水層の垂直的な漏水が引き起こされている.地層中のヒ素含有量は,上部泥質層で高く,とくにピート層が非常に高い.第一帯水層の地下水ヒ素濃度は,シャム夕村の南部で高く,北東部で低い.民間所有井戸では,1997年10月の雨季が,1997年3月や1998年5月の乾季にくらべ地下水ヒ素濃度が高い.観測井では,深度が浅いほどヒ素濃度が高く,深いほど低い.第一帯水層での平面的な地下水流動とヒ素濃度とはさほど相関しない.季節的な差異もヒ素濃度との良い相関を示さない.水文地質的な観点からの地下水ヒ素汚染に関係する要因としては,次の点があげられる.(1)上部泥質層とピート層中のヒ素含有量(2)上部泥質層の層厚(3)農業用での地下水利用による垂直的な地下水流動
1 0 0 0 OA 冬眠研究が拓く新たな生物医学領域
- 著者
- 近藤 宣昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.2, pp.97-102, 2006 (Released:2006-04-01)
- 参考文献数
- 33
哺乳類の冬眠動物が冬眠時期に数℃という極度の低体温を生き抜くことは良く知られている.さらに,細菌や発ガン物質などにも抵抗性を持ち,脳や心臓では低温や低酸素,低グルコースにも耐性を示すとの興味深い報告もなされている.このことから,冬眠現象には種々の有害要因や因子から生体を保護する機構が関与しているとの指摘がなされ,最近,生物医学分野での関心が高まりつつある.特に,冬眠発現に関わる体内因子には古くから強い関心が寄せられ探索されてきたが成功せず,近年その存在も疑問視されてきた.これには,冬眠が複雑な生体機能の統合による現象であることや,その発現が1年の長い周期性を持つこと,体温低下により生体反応が著しく抑制されることなど,実験の障害となる深刻な問題が関わっていた.その様な状況下で,我々は1980年代初期に始めた心臓研究を切っ掛けに,冬眠にカップルする新たな因子をシマリスの血中から発見した.冬眠特異的タンパク質(HP)と命名した複合体は,冬眠時期を決定する年周リズムにより制御され,血中から脳内へと輸送されて冬眠制御に深く関わることが明らかになってきた.ここでは,冬眠研究の現状や問題点を含めて,我々が見出したHP複合体が初めての冬眠ホルモンとして同定されるまでの経緯を概説し,医薬分野での新たな応用を秘めた冬眠現象について述べる.
- 著者
- Kazutoshi Sakurai Kenichi Tomiyama Yoshihiro Yaguchi Yoshinori Asakawa
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- pp.ess19262, (Released:2020-06-09)
- 被引用文献数
- 5
The volatile components produced by Leptolejeunea elliptica (Lejeuneaceae), which is a liverwort grown on the leaves of tea (Camellia sinensis), were collected and analyzed using headspace solid-phase microextraction–gas chromatography/mass spectrometry (HS-SPME–GC/MS). 1-Ethyl-4-methoxybenzene (1), 1-ethyl-4-hydroxybenzene (2), and 1-acetoxy-4-ethylbenzene (3) were identified as the major components together with several other phenolic compounds, including 1,2-dimethoxy-4-ethylbenzene, and 4-ethylguaiacol in addition to sesquiterpene hydrocarbons, such as α-selinene, β-selinene, β-elemene, and β-caryophyllene. GC/Olfactometry showed the presence of linalool, acetic acid, isovaleric acid, trans-methyl cinnamate, and trans-4,5-epoxy-(2E)-decenal, as the volatile components produced by L. elliptica.
1 0 0 0 OA 牛の脂肪壊死症とハトムギ
- 著者
- N. Y.
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.147, 1980 (Released:2008-11-21)