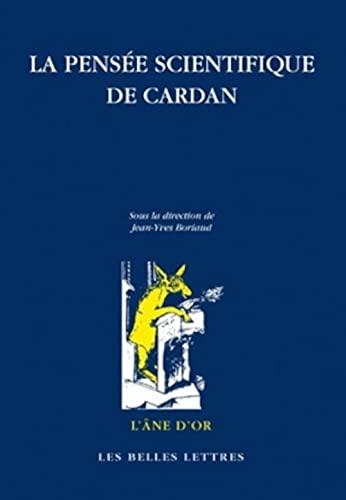2 0 0 0 OA 高校野球・選手宣誓の時代性
- 著者
- 陣内 正敬
- 出版者
- 九州大学大学院人文科学研究院言語学研究室
- 雑誌
- 九州大学言語学論集 (ISSN:13481592)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.267-280, 2011 (Released:2012-08-03)
In this paper, the declarations (player's oaths) by senior high school baseball players at Koshien stadium every year are analyzed from the viewpoint of the modification of the texts. In result, 26 texts from 1968 to 2010 are divided into three groups according to the time. First group (named "traditional type") consists of the oaths from 1968 to 1983, that is traditional and stereotyped version made up of almost the same vocabularies and expressions. Second group ("innovation type Ⅰ") is from 1984 to 2000, that has variety and individualities. Third group("innovation type Ⅱ") is from 2001 ahead, that has the same character as the former but is different in that has entertainer's viewpoint in the texts. In conclusion, the reason why this kind of modification has occurred is that "liberation from restraint" emerged among Japanese young people after 1980s, and furthermore, "players as entertainers" consciousness has also emerged after 2000s.
2 0 0 0 NEC技報 = NEC technical journal
- 著者
- NECマネジメントパートナー株式会社 編
- 出版者
- 日本電気
- 巻号頁・発行日
- vol.37(4), no.175, 1984-04
2 0 0 0 La pensée scientifique de Cardan
- 著者
- sous la direction de Jean-Yves Boriaud
- 出版者
- Les Belles Lettres
- 巻号頁・発行日
- 2012
2 0 0 0 OA ドメイン特化型開発における自動化テストプロセスの提案
- 著者
- 森 奈実子 久住 憲嗣 中西 恒夫 福田 晃
- 雑誌
- 研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス通信(MBL)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010-MBL-53, no.12, pp.1-8, 2010-03-19
ドメイン特化型開発では,特定の市場領域に属するソフトウェアを効率的に開発できる DSL (Domain-Specific Language) を定義し,開発者はその言語を用いてソフトウェアを開発する.しかし,ドメイン特化型開発では特有のテストプロセスは定義されていない.そこで,本稿では DSL の分類に応じたテストケース自動生成手法を援用したテストプロセスを提案する.ケーススタディとして小規模な DSL に提案手法を適用し,その結果を基に従来手法との比較を行った.
2 0 0 0 OA 合名会社玉屋商店商品目録
- 出版者
- 玉屋商店
- 巻号頁・発行日
- 1915
2 0 0 0 連想としての意味
- 著者
- 持橋 大地 松本 裕治
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.95, pp.155-162, 1999-11-25
本論文では,単語の意味を単語間の連想関係を表す確率分布として表現し,その定式化と連想確率の獲得について述べる.単語の意味的な重みを表す指標として単語の共起確率分布の情報量から計算される連想情報量を提案し,共起確率との組み合わせにより連想確率を計算する.連想はMarkov過程の上で行われ,その状態確率分布として意味が定義される.状態遷移として連想を行うことによって,直接共起しない語の意味的な関係が表現できる.また,確率ベクトルとして捉えた意味のスケール変換として文脈を捉え,先行単語集合の数を仮定しない非線型な更新式を提案し,これにより文脈の強化と順序への依存が表現できることを示す.現実のテキストから意味を獲得し,文脈をモデル化することで,意味的類似度や文脈解析だけでなく,情報検索などにおいて様々な実際的な意味処理が可能になる.This paper describes meanings of a word by stochastic association. First, we propose a new indicator of semantic informativeness of a word by its co-occurrence distributions. Second, we define the association probability by a combination of co-occurrence probability and the indicator. Then, regarding context as a vector of scaling factors against semantic vector, we propose a nonlinear formula of context succession to show its validity in modeling reinforcement and order depencency of context. Stochastic treatment of meaning and its aquisition from texts is useful in real semantic processing.
2 0 0 0 OA 行事食の指導要領
- 著者
- 塩田 教子
- 出版者
- 活水女子大学
- 雑誌
- 活水論文集. 生活学科編 (ISSN:0919584X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.17-25, 1998-03
近年,食生活環境が変化して,家庭における行事食が衰微してきた。その原因は経済成長の結果,毎日「ハレ」の日のような食事が食べられるようになり,主婦が行事食に無関心になっため,子供達はその内容も知らずに成長した。しかし,子供達は国際社会の一員として日本民族の文化を理解しておく必要があり,そのため是非ともそれを経験し伝承することが大切と考えて,家庭において行事食の伝承が少なくなった現状では学校でその伝承を行う必要性を感じ,その指導要領を考察した。(1) アンケートによると学生達の行事食の喫食率はお正月料理,クリスマス料理,自分の誕生日の料理などが高く,また行事食を食べた経験はより伝承意識を高めるということがわかった。そして作ってみたい行事食の内容の選択では容易に作ることができる料理,和洋折衷料理,ご飯は混ぜご飯などが好まれ,時代に沿った新しい感覚の内容の献立が選ばれていた。(2) 行事食を指導した結果はある程度の基礎技能を習得した段階で,予め,調理に対する手順のフローチャートと作品のイメージを考えさせ,それをチェックしてやれば「料理法を読みとりながらの調理」の指導でも各自が作り上げる意欲が起こり,それまでの技能の復習と創造性を引き出せることが確認できた。(3) 食環境と行事食の伝承意識の調査では伝承意識は「手作り料理の食事が多いこと」や「ただ家で行事食を作ること」と相関がなく,「家で行事食を作って友達を招待すること」や「家族の慶事ごとにお祝い料理をよく食べる食環境」と相関が高いことを確認した。また,学校で行事食を作ることは行事食の特徴を把握させ,共食の喜びを経験させ,行事食に関心を持たせて伝承意識を高めることに役立つということも確認された。終わりに,行事食の献立資料をご提供いただきました北九州市のヘルスアップ料理研究会の栄養士の皆様に深く感謝いたします。
2 0 0 0 OA 梓川上流・トバタ崩れ (1757) に伴う天然ダムの形成と決壊対策
- 著者
- 森 俊勇 井上 公夫 水山 高久 植野 利康
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.44-49, 2007-09-15 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 21
As many as 19 landslide dams have been formed in the northern region of Nagano prefecture, central Japan, in last 500 years except one case. Of this number, seven were formed when the Zenkoji Earthquake occurred in 1847. This abundance is likely because of the geotectonic background of this area which is located at the western end of the “Fossa Magna, ” or Japan's central graben belt.The Tobata landslide occurred in the early morning of June 24, 1757 due to heavy rain. Blocking the Azusa River, which is upstream of the Shinano River, a landslide dam with a height of 130 m and a storage capacity of 85 million m3 was formed. Around 10 a.m. on the third day (54 hours later), this landslide dam burst and its water flooded the area up to the confluence with the Narai River. According to calculation using the Manning's formula, it is estimated that the flood water ran down the river in a concentrated path with a velocity of 12 m/s and a peak flow of 27, 000 m3/s.When the dam burst, local people were quickly ordered to evacuate and no casualties were caused during this flood.
2 0 0 0 OA 047 E30107 女子レスリング選手の減量方法の実態
- 著者
- 甲田 道子 杉山 三郎 坂本 涼子
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- no.54, 2003-08-26
2 0 0 0 OA 言葉遊びを通して語彙力を育てる : 帯単元の試み
- 著者
- 高谷 秀
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.91-92, 1994-10-19
- 著者
- Hideharu OCHIAI Taiki MORISHITA Ken ONDA Hiroki SUGIYAMA Takuya MARUO
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.7, pp.917-922, 2012 (Released:2012-08-04)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 5 9
A full-length cDNA sequence of canine L-type amino acid transporter 1 (Lat1) was determined from a canine brain. The sequence was 1828 bp long and was predicted to encode 485 amino acid polypeptides. The deduced amino acid sequence of canine Lat1 showed 93.2% and 91.1% similarities to those of humans and rats, respectively. Northern blot analysis detected Lat1 expression in the cerebellum at 4 kb, and Western blot analysis showed a single band at 40 kDa. RT-PCR analysis revealed a distinct expression of Lat1 in the pancreas and testis in addition to the cerebrum and cerebellum. Notably, Lat1 expression was observed in the tissues of thyroid cancer, melanoma and hemangiopericytoma. Although the cancer samples examined were not enough, Lat1 may serve as a useful biomarker of cancer cells in veterinary clinic.
2 0 0 0 OA 大伴家持と<なでしこ>の歌
- 著者
- 島田 裕子
- 出版者
- 梅光学院大学
- 雑誌
- 日本文学研究 (ISSN:02862948)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.25-33, 1993-11-01
2 0 0 0 大会前・中・後における内科系スポーツドクターの果たす役割
- 著者
- 坂本 静男
- 出版者
- 日本臨床スポーツ医学会
- 雑誌
- 日本臨床スポーツ医学会誌 = The journal of Japanese Society of Clinical Sports Medicine (ISSN:13464159)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.154-160, 2001-04-25
- 著者
- 安酸 建二 緒方 勇
- 出版者
- 日本管理会計学会
- 雑誌
- 管理会計学 : 日本管理会計学会誌 : 経営管理のための総合雑誌 (ISSN:09187863)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.3-21, 2012-01-15
本稿の目的は,利益目標の達成圧力にさらされている企業において,自由裁量的支出費用の代表である研究開発費(以下,R&D費用)の削減を通じて「期中に」利益調整が行われているのかどうかを検証することにある.利益目標として注目するのは,経営者による利益予測値である.分析の結果,利益目標を達成できそうもない状況におけるR&D費用の削減を通じた利益調整が,売上高に占めるR&D費用予算の割合が大きい場合(本研究では5%以上)に見られることを発見した.これらの発見は,R&D費用の期中における削減を通じた利益調整の存在を示す証拠となる.
2 0 0 0 IR 学力問題再考 : 秋田と沖縄の比較を通して
- 著者
- 馬居 政幸
- 出版者
- 静岡大学
- 雑誌
- 静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇 (ISSN:0286732X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.13-42, 2010
2 0 0 0 OA 神聖なる瞬間 : リラダンにおける「断頭台」テーマについて
- 著者
- 小西 博子 コニシ ヒロコ Konishi Hiroko
- 出版者
- 大阪大学フランス語フランス文学会
- 雑誌
- Gallia (ISSN:03874486)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.51-60, 2009-03-07
- 著者
- 浦上 博逵
- 出版者
- 城西大学
- 雑誌
- 城西大学経済経営紀要 (ISSN:03866947)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.143-147, 1994-03-20
- 著者
- 高橋 恒雄
- 出版者
- 日本理科教育学会
- 雑誌
- 日本理科教育学会関東支部大会研究発表要旨集 (ISSN:13417762)
- 巻号頁・発行日
- no.42, 2003-10-04
2 0 0 0 OA 中国植物に関する日本の研究
- 著者
- 北村 四郎
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類・地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.119-122, 1989-07-30
中国の医学や薬物に関する書籍は6世紀の中頃に日本に伝来した。中国薬用植物と日本野生植物との同定は19世紀の中頃まで,日本の本草学者の主な仕事であった。私は日本の従来の伝統的な同定を現代の中国の植物分類地理学的著作を参考にして再検討した。それぞれの植物漢名は中国古典にある原記載と原産地によって現代の学名に同定した。私は『本草の植物』1-638頁(1985)を保育社(大阪市鶴見区鶴見4-8-6)から出版した。また,その追補を続本草の植物として『植物文化史』405頁~613頁(1987)に保育社から出版した。これによって久しく誤り同定されていた植物を正しく同定したが,なお原記載や産地が不十分で同定のできないものも多い。中国植物の同定で革期的な研究は小野蘭山の『本草綱目啓蒙』(1803)と松村任三の『改訂植物名彙前編漢名之部』(1915)であろう。これらは原記載や原産地を意識しての同定はやっていない場合が多い。19世紀の後半から日本の植物分類学者が日本の植物に学名を同定し始めた。20世紀から日本の植物分類学者は台湾,中国東北部,朝鮮,南樺太の植物を研究し多くの新種を発表した。20世紀の後半から日本の植物分類学者はヒマラヤ・ヒンズークシ,東南アジアの植物を研究し,多くの新種を発表した。これらの地域には中国と共通している植物が分布しており,中国の研究者と日本の研究者がともに協力することが必要である。その協力に基づき21世紀には革期的な進歩が期待される。この論文は1989年10月4日に中国雲南省昆明で開催された国際植物資源学術討論会で講演した。中国科学院昆明植物研究所創立50周年式が7日にあった。外国からは日本からの講演者や参加者が最も多かった。岩槻邦男,近田文弘,坂田完三さんらは同窓であるが,津村研究所の三橋博所長や同研究所員が多く来ておられた。広島大学の田中治さん,横浜大学の栗原良枝さん,静岡大学の北川淳子さんなどである。フランスからはJ. E. VIDALさんも参加した。昆明の街ではキクの花盛りであった。日本にあるものと同様である。華亭寺でカワイスギCryptomeria japonica var. sinensis SIEB. et ZUCC.の大木があった。日本のスギときわめて似ている。西山では路南鳳仙花Impatiens loulanensis HOOK. f. が多く,よく咲いていた。昆明植物研究所にメキシコ原産のベニチョウジCestrum purpureum STANDL. が赤い花をぶらさげて美しかった。
2 0 0 0 IR 散骨をめぐる諸問題--散骨禁止条例を中心として
- 著者
- 石川 美明
- 出版者
- 大東文化大学
- 雑誌
- 大東ロージャーナル (ISSN:18801242)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.61-77, 2008-03