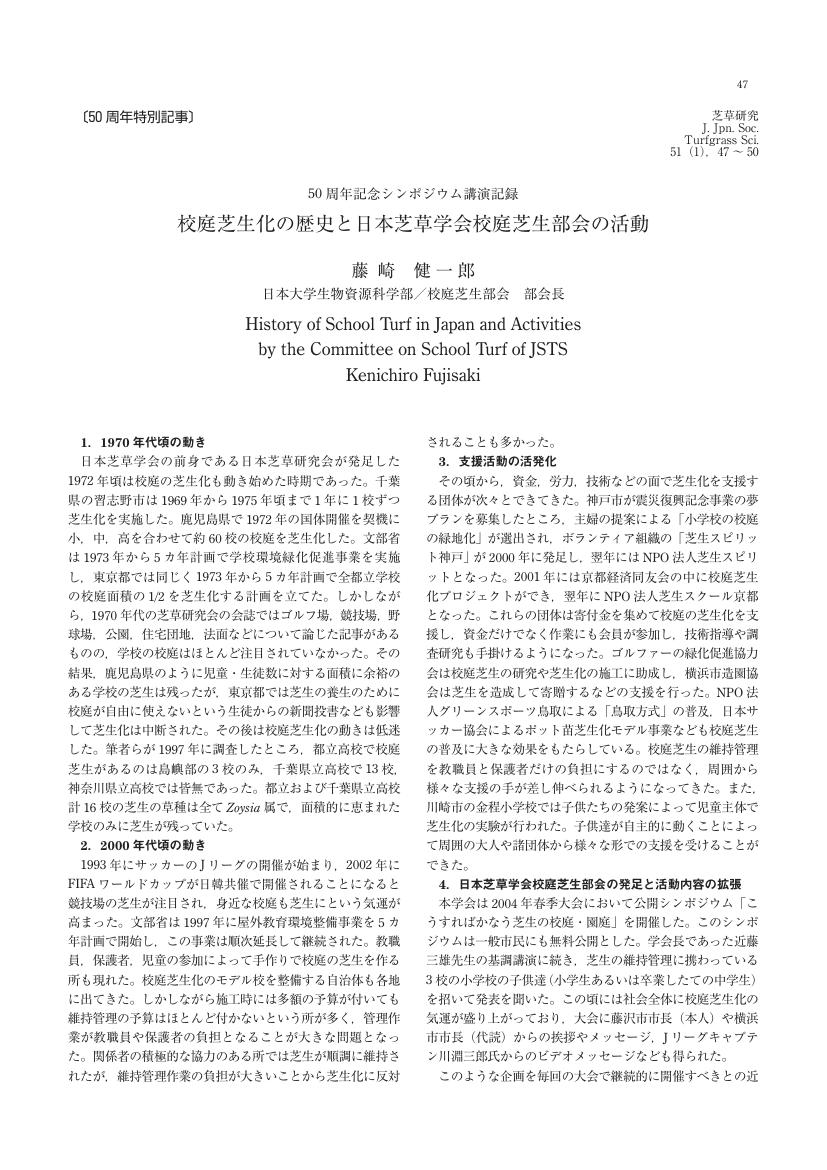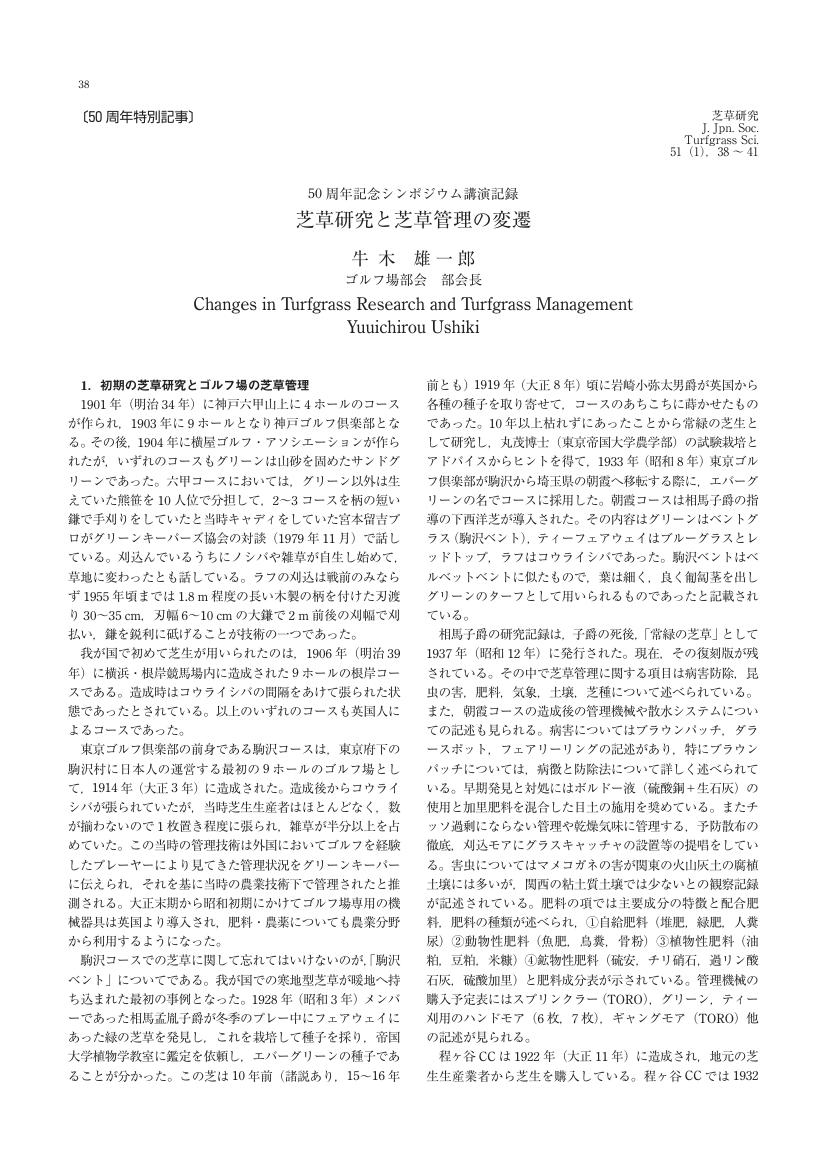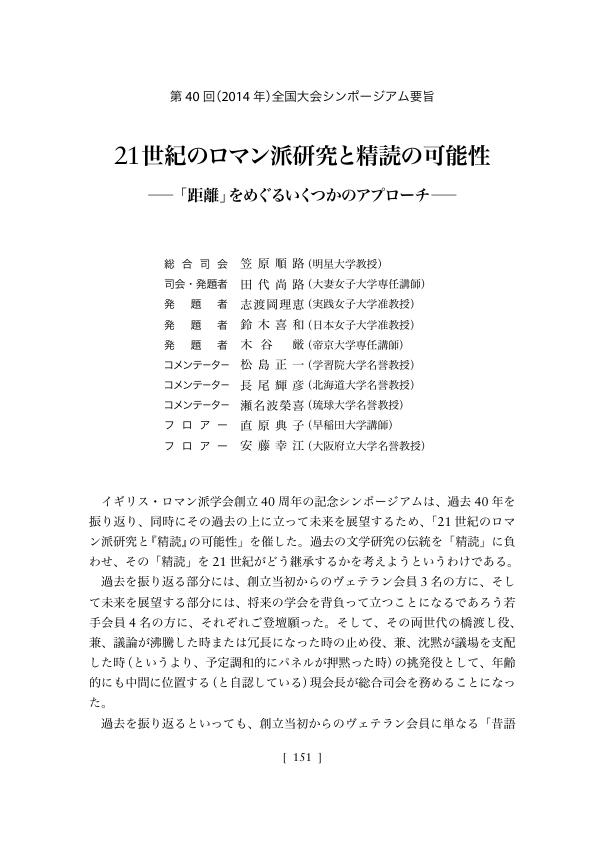1 0 0 0 OA 校庭芝生化の歴史と日本芝草学会校庭芝生部会の活動 50周年記念シンポジウム講演記録
- 著者
- 藤崎 健一郎
- 出版者
- 日本芝草学会
- 雑誌
- 芝草研究 (ISSN:02858800)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.47-50, 2022-10-31 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 芝草研究と芝草管理の変遷 50周年記念シンポジウム講演記録
- 著者
- 牛木 雄一郎
- 出版者
- 日本芝草学会
- 雑誌
- 芝草研究 (ISSN:02858800)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.38-41, 2022-10-31 (Released:2023-10-31)
1 0 0 0 OA 日本芝草学会50年のあゆみ 50周年記念シンポジウム講演記録
- 著者
- 矢口 重治
- 出版者
- 日本芝草学会
- 雑誌
- 芝草研究 (ISSN:02858800)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.32-37, 2022-10-31 (Released:2023-10-31)
1 0 0 0 OA いわゆるあおり運転について考える!
- 著者
- Andros Theo Tracy Masebe Yasuhiro Suzuki Haruhisa Kikuchi Shoko Wada Chikwelu Larry Obi Pascal Obong Bessong Motoki Usuzawa Yoshiteru Oshima Toshio Hattori
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.217, no.2, pp.93-99, 2009 (Released:2009-02-11)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 35 42
The biodiversity of medicinal plants in South Africa makes them rich sources of leading compounds for the development of novel drugs. Peltophorum africanum (Fabaceae) is a deciduous tree widespread in South Africa. The stem bark has been traditionally employed to treat diarrhoea, dysentery, sore throat, wounds, human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS), venereal diseases and infertility. To evaluate these ethnobotanical clues and isolate lead compounds, butanol and ethyl acetate extracts of the stem bark were screened for their inhibitory activities against HIV-1 using MAGI CCR5+ cells, which are derived from HeLa cervical cancer cells and express HIV receptor CD4, a chemokine receptor CCR5 and HIV-LTR-β- galactosidase. Bioassay-guided fractionation using silica gel chromatography was also conducted. The ethyl acetate and butanol extracts of the stem bark of Peltophorum africanum showed inhibitory activity against HIV-1, CXCR4 (X4) and CCR5 (R5) tropic viruses. The ethyl acetate and butanol extracts yielded previously reported anti-HIV compounds, (+)-catechin, a flavonoid, and bergenin, a C-galloylglycoside, respectively. Furthermore, we identified betulinic acid from the ethyl acetate fraction for the first time. The fractions, which contained betulinic acid, showed the highest selective index. We therefore describe the presence of betulinic acid, a not well-known anti-HIV compound, in an African medicinal herb, which has been used for therapy, and claim that betulinic acid is the predominant anti-HIV-1 constituent of Peltophorum africanum. These data suggest that betulinic acid and its analogues could be used as potential therapeutics for HIV-1 infection.
- 著者
- Rachel S. Martins Erika S. J. Péreira Sérgio M. Lima Jr. Maria I. B. Senna Ricardo A. Mesquita Viagner R. Santos
- 出版者
- Nihon University School of Dentistry
- 雑誌
- Journal of Oral Science (ISSN:13434934)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.41-48, 2002 (Released:2011-03-11)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 15 19
The present study assessed the susceptibility of Candida albicans strains, collected from HIV-positive patients with oral candidiasis, to a commercial 20% ethanol propolis extract (EPE) and compare it to the inhibitory action of the standardized antifungal agents nystatin (NYS), clotrimazole (CL), econazole (EC), and fluconazole (FL). Twelve C. albicans strains collected from MV-positive patients with oral candidiasis were tested. The inhibition zones were measured with a pachimeter and the results are reported as means and standard deviation (M ± SD). Data were analyzed statistically by the non-parametric Kruskal-Wallis test. EPE inhibited all the C. albicans strained tested. No significant difference was observed between the results obtained with NYS and EPE, while significant differences were observed between EPE and other antifungals. The C. albicans strains tested showed resistance to the remaining antifungal agents. The propolis extract used in this study inhibited the in vitro growth of C. albicans collected from HIV-seropositive Brazilian patients, creating/forminginhibition zones like those ones formed by NYS. This fact suggests that commercial EPE could be an alternative medicine in the treatment of candidiasis from HIV-positive patients. However, in vivo studies of the effect of EPE are needed to determine its possible effects on the oral mucosa.
1 0 0 0 OA 大学発ベンチャー企業における黒字化のメカニズム
- 著者
- 明石 一暉 大江 秋津
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2020年全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.69-72, 2021-01-28 (Released:2021-01-18)
新しさゆえの不利益を持つベンチャー企業の資金繰りは厳しい。本研究は、黒字化した大学発ベンチャー企業の特性が速やかな黒字化に与えた影響を実証する。2016年から2019年の115社の経済産業省によるデータを用いて重回帰分析をした。大学発ベンチャー企業の代表者属性と大学属性、設立場所、関連研究者が速やかな黒字化に与える影響を実証し、大学は代表者を研究者にすると黒字化しやすいことを示した。さらに代表者の属性と企業特性を組み合わせた交互作用分析により、速やかな黒字化を生むメカニズムを示した。本研究は、新興企業家研究に対する理論的貢献だけでなく、大学発ベンチャー企業設立戦略を提示することにより実務的貢献とした。
1 0 0 0 OA SROI(社会的収益投資)に関する批判的考察
- 著者
- 津富 宏
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本評価学会
- 雑誌
- 日本評価研究 (ISSN:13466151)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.33-41, 2016-11-17 (Released:2023-06-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
本稿では、エビデンスを「つくる・つたえる・つかう」運動であるEBP(Evidence-based practice)の観点から、社会的投資のための評価ツールのひとつであるSROI(Social Return On Investment: 社会的収益投資)について批判的検討を行った。まず、SROIの普及状況について概説した後、SROIがCBA(Cost-Benefit Analysis: 費用便益分析)の一種であることを確認し、Nicholls et al.(2009)に従って、SROIの原則、SROIの手順について概観した。これを踏まえて、Arvidson et al.(2010, 2013)によるSROIに対する、的を得た8つの批判を紹介した。その後、SROIに関する具体例の検討を行い、SROI比率算定における恣意性やSROI比率がインフレートされる可能性を見出した。最後に、福祉国家論における社会的投資の役割についての考察を踏まえ、SROIは、投資対象としての事業や組織を評価するためではなく、EBPが長年にわたり行ってきたように、社会的共通資本としてのセクターの漸進的改善を支援するために用いられるべきであると主張した。
1 0 0 0 熱音響エンジンの最適な熱交換器サイズの予測
- 著者
- 市川 暉 兵頭 弘晃 琵琶 哲志
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- スターリングサイクルシンポジウム講演論文集 2019.22 (ISSN:24242926)
- 巻号頁・発行日
- pp.C03, 2019 (Released:2020-06-25)
A thermoacoustic engine model with heat exchangers is introduced to show how a product of heat transfer coefficient h and heat transfer area of heat exchanger A determines the output power of the engine. Effective hA values are determined from experiments and calculation in a thermoacoustic engine prototype. The experimental and calculation results are compared with the favorable hA values estimated in the model.
1 0 0 0 OA 図書館と文学館の連携(<特集>図書館にできること:周辺との連携を中心に)
- 著者
- 岡野 裕行
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.233-237, 2011-06-01 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 25
文学館と呼ばれる施設は,文学を対象とした専門図書館として機能している。また,文学館は博物館や文書館としての特徴も兼ね備えている。図書館と文学館との連携には,施設の規模による違いが見られる。連携を考える場合には,それぞれの施設の形態のみに注目するのではなく,収集対象としている資料の主題分野のほか,それに関係する個人や団体にも関心を払うことが求められる。
- 著者
- 服部 敦 宮道 喜一 小阪 亘
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.813, pp.2988-2997, 2023-11-01 (Released:2023-11-01)
- 参考文献数
- 23
The purpose of this study is to re-evaluate regional plans in Okinawa designed by Atelier Zo. By analyzing how the distinctive concepts and methods of a series of regional plans were expressed in the design works of Atelier Zo, we re-evaluate a series of regional plans these works as having produced these outcomes, as well as the value of the design works of Atelier Zo as planning heritages of regional plans, thereby contributing to their preservation and utilization.
1 0 0 0 糞尿と生活文化 : 21世紀のスカトロジー
- 著者
- Hitoshi YAMAMOTO Takahisa SUZUKI Yuki OGAWA Ryohei UMETANI
- 出版者
- The Society of Socio-Informatics
- 雑誌
- Journal of Socio-Informatics (ISSN:18829171)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.17-31, 2023 (Released:2023-11-01)
- 参考文献数
- 41
The COVID-19 Pandemic is a global problem, and to prevent the spread of the infections, it is crucial not only to develop vaccines and therapeutic medications but also to encourage people to change their behavior. Behavioral change to prevent the spread of infectious diseases has required people to give up many activities, especially pleasures outside the home. However, it is hoped that if most people behave cooperatively, individuals’ selfish pursuit of pleasure will have little effect on the spread of infection. This conflict between benefits for individuals and those for the community as a whole can be considered a social dilemma. Clarifying the factors that define people’s behavior during epidemics is essential for designing social systems after the COVID-19 Pandemic is declared over. Here, we analyze the determinants of people’s behavior in the framework of a social dilemma by conducting a two-wave panel survey in 2020 and 2021. The results show that in the first wave, psychological attitudes that affect prosocial behavior, such as reciprocity, positively affect prosocial behavior. However, in the second wave, these effects disappear, and other factors define people’s behavior. Continuous analysis of the factors determining people’s behavior under drastically changing circumstances can provide information for planning measures to promote desirable behavioral changes.
1 0 0 0 OA 日本の哲学と社会学
- 著者
- 丸山 徳次
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.26-34, 2005-05-28 (Released:2017-09-22)
日本の大学における社会学のありようについての社会学者による反省は、哲学者による哲学についての反省と極めて類似している。第一に「暗い」とか「かたい」とかいったイメージや世間的評価に悩む点で類似している。第二に、理論や方法論の紹介や研究が、現実社会の問題の究明よりも尊重される、ということに対する学問の現状批判の点で類似している。第三に、学問構造が類似している。社会学は、近代における社会諸科学の成立と連動しながらも「最後の社会科学」と言われるが、それはまた、哲学から自立していった「最後の科学」でもある「越境する知」としての社会学の不安定さは、ハードなパラダイム科学となり得ない学の宿命であると同時に、絶えざる自己反省を必然とする哲学的性格にもよる。こうして、大学教育のあり方への反省は、学およびその対象(近代社会)の生成についての歴史的反省と結びつく必要があるし、それを教育に生かす必要がある。また、当の学問の意義自体を反省すると同時に、新しい制度化を考えることにつながらねばならない。そこで一つのヒントを与えているのは、応用倫理学の新たな胎動である。応用倫理学は、科学技術の高度の発達がもたらす社会問題に応答するものである。こうした時代と社会の「切実な問題」の解決には、多様な専門家が参集する「問題共同体」が形成される必要がある。社会学がそこで期待されるのは、社会調査の能力であって、哲学的自己反省の能力ではない。
1 0 0 0 OA 資本主義の危機としての少子化 生活の空間的組織化の困難化
- 著者
- 中澤 高志
- 出版者
- 日本地域経済学会
- 雑誌
- 地域経済学研究 (ISSN:13462709)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.3-23, 2023-02-28 (Released:2023-04-04)
- 参考文献数
- 94
1 0 0 0 OA 外山礼三氏のこと
- 著者
- 北川 尚史
- 出版者
- 日本蘚苔類学会
- 雑誌
- 日本蘚苔類学会会報 (ISSN:02850869)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.21-22, 1977-08-10 (Released:2018-07-03)
1 0 0 0 OA 21世紀のロマン派研究と精読の可能性―「距離」をめぐるいくつかのアプローチ―
- 著者
- 笠原 順路 田代 尚路 志渡岡 理恵 鈴木 喜和 木谷 厳 松島 正一 長尾 輝彦 瀬名波 榮喜 直原 典子 安藤 幸江
- 出版者
- イギリス・ロマン派学会
- 雑誌
- イギリス・ロマン派研究 (ISSN:13419676)
- 巻号頁・発行日
- vol.39and40, pp.151-185, 2015-11-30 (Released:2016-12-27)
1 0 0 0 OA 両親の輸血拒否に対して児童相談所の支援により治療を行った神経芽腫例
- 著者
- 加藤 正也 佐藤 雄也 中山 幸量 奥谷 真由子 福島 啓太郎 黒澤 秀光 吉原 重美
- 出版者
- 日本小児血液・がん学会
- 雑誌
- 日本小児血液・がん学会雑誌 (ISSN:2187011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.50-52, 2019 (Released:2019-04-12)
- 参考文献数
- 7
高リスク群の神経芽腫の治療において輸血は重要な補助療法である.小児領域で輸血を行うためには親権者から承諾を得る必要があるが,宗教的な理由で拒否した場合は親権停止の申立を考慮する必要がある.しかし,この行為は親権者と医療従事者との関係を悪くさせる可能性があり,神経芽腫の児の治療にとって望ましくない環境である.高リスク群の神経芽腫である18か月男児が入院した.両親は宗教的な理由で児への輸血を拒否した.医療ソーシャルワーカー(SW),児童相談所と連携し患児を一時保護で入院させた.輸血同意書を含めた全ての承諾書は児童相談所長がサインすることで両親から加療をする承諾を得た.親権停止の手続きは行わず,医療者と両親間のトラブルもなく予定通りの加療を行った.