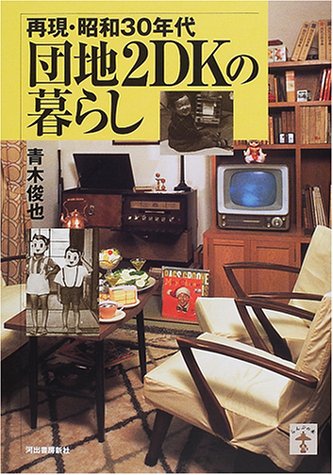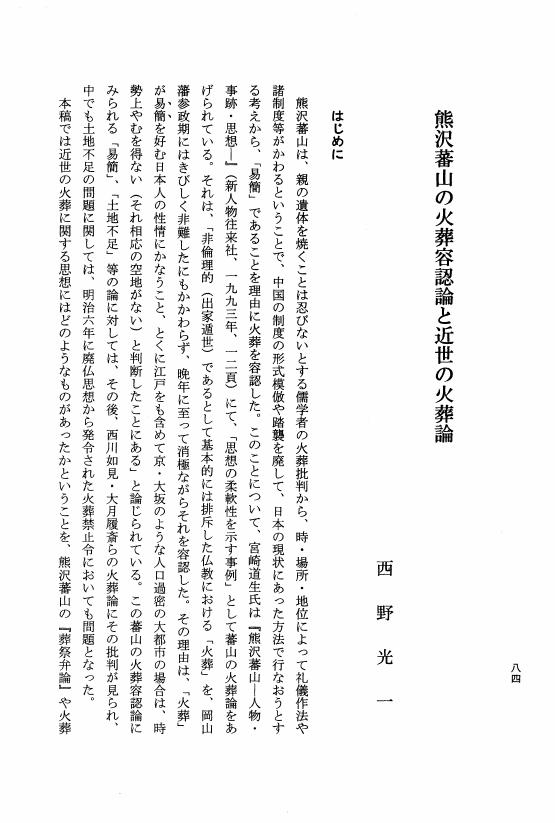1 0 0 0 OA 光学シミュレーションによるアコヤ真珠の構造色の再現
- 著者
- 尾崎 良太郎 丸飯 虎太朗 門脇 一則 小田原 和史
- 出版者
- 宝石学会(日本)
- 雑誌
- 宝石学会(日本)講演会要旨 2022年度 宝石学会(日本)講演論文要旨
- 巻号頁・発行日
- pp.6, 2022 (Released:2022-07-08)
- 参考文献数
- 2
真珠の構造色は、表面の真珠結晶層内のアラゴナイト結晶層とコンキオリン層で発生する光の干渉によって発色することが知られている。一般的な構造色では、反射光の干渉が色彩を決めることが多いが、アコヤ真珠の場合は、特に透過の干渉色が重要であることを小松氏は指摘している。我々は、透過の干渉色と反射の干渉色のメカニズムを光学の視点から考え、そのモデル化に成功した。真珠の光学特性は、透過と反射と散乱の組み合わせである。真珠核および真珠結晶層での多重散乱は Kubelka-Munk 理論で計算し、アラゴナイト結晶層とコンキオリン層での干渉は、 Transfer Matrix 法で計算した。計算で得られたスペクトルを色情報に変換し、その色情報に基づき OpenGL シェーディング言語で作成したプログラムで可視化した。図 1 は、コンキオリン層を 20 nm として、アラゴナイト結晶層が 360 nm のときの結果である。上段が写真であり、下段がコンピュータグラフィックス(CG)であるが、撮影角度に伴う干渉色のグラデーションの変化をよく再現できている。また、アラゴナイト結晶層を300 nm、 360 nm、 400 nm としたときの結果を図 2 に示す。結晶層厚の変化に伴う、干渉色のグラデーションの変化も再現可能である。今後は、 CG の更なる高度化を目指し開発を進める予定である。【謝辞】本研究は農研機構生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち先導プロジェクト)」の支援を受けて行われたものです。
1 0 0 0 OA ドクウツギの果実の味と中毒
- 著者
- 松田孫治
- 出版者
- 植物研究雑誌編集委員会
- 雑誌
- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.9, pp.555-556, 1941-09-15 (Released:2023-04-03)
1 0 0 0 OA 繊維産業廃水の処理の実際 ―染色廃水の脱色を中心に―
- 著者
- 山田 博
- 出版者
- 環境技術学会
- 雑誌
- 環境技術 (ISSN:03889459)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.5, pp.281-292, 1994-05-30 (Released:2010-03-18)
1 0 0 0 炊飯米に強いせん断を付与する押出加工法
- 著者
- 甲斐 彰 斎藤 幸雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- pp.NSKKK-D-23-00055, (Released:2023-10-31)
炊飯米から製造するペーストについて, 一般的な高速せん断加工とは異なる押出加工による製造方法を試みた. 従来は困難であった加工直後の米ゲルの物性評価に, 塗装や油脂の調整などで用いる簡易的な工業計測の適用を試みた. そして, 次の結果が得られた. (1) ポートホールダイスを用いて均質なペーストを短時間に得ることができる. (2) ポートチャンバー部で剪断力を与えることにより, 炊飯米の硬い部分もクリアランスより小さい粒子に破砕することができる. (3) コンテナ径およびダイスの仕様により, 人力によるペースト加工が可能となる. (4) 必要荷重が大きくなるが, 硬めに炊飯した米でもペースト加工が可能である. (5) ペーストに含まれている粒子の大きさの評価にグラインドゲージが利用でき, 加工直後の高温条件であっても迅速に評価ができる. (6) ペーストの柔らかさの評価にちょう度計が利用でき, 加工直後の高温条件であっても迅速に評価ができる. (7) 炊飯米から加工したペーストには肉眼で判別可能な白い塊が見られ, これは触感では粒状には感じない程度に容易に塑性変形する.
1 0 0 0 OA 核磁気共鳴画像を用いた男性における骨盤底筋トレーニングの解析
- 著者
- 平野 正広 秋山 純和 加藤 崇洋 岡庭 栄治 丸山 仁司 天野 裕之 鬼塚 史朗
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.41-46, 2012 (Released:2012-02-21)
- 参考文献数
- 29
〔目的〕前立腺がんに対する根治的前立腺全摘除術の術後合併症に腹圧性尿失禁があり,その治療法にはPFMT(Pelvic Floor Muscle Training:骨盤底筋群トレーニング)がある.MRI(Magnetic Resonance Imaging:核磁気共鳴画像)によってPFMT時の骨盤底部の運動変化を検討した.〔対象〕健常成人男性7名とした.〔方法〕PFMT方法は,「おしっこを止めるように」,「肛門を閉めるように」の2つの指示とし,MRIによる撮影を実施した.骨盤底筋群の収縮による運動変化を捉えるために,安静時と指示を与えた時で恥骨─尾骨先端(P-C)距離,床面-尾骨先端(F-C)距離,恥骨─膀胱頚部(P-B)距離を測定し比較した.〔結果〕P-C距離は減少し,F-C距離,P-B距離の増大する傾向を認めた.指示「おしっこを止めるように」でP-C距離は減少幅が大きく,指示「肛門を閉めるように」でF-C距離の増大幅が大きかった.〔結語〕MRIを用いてPFMT時の骨盤底部の運動変化を明らかにした.PFMT指導によるP-C距離の減少,F-C距離の増大は,男性における尿失禁治療のPFMT 指導方法に役立つことが示唆される.
1 0 0 0 OA Rainfall-runoff characteristics in a tropical forested catchment, Puchong, Selangor, Malaysia
- 著者
- Mariko Saito Maki Tsujimura Siti Nurhidayu Abu Bakar
- 出版者
- Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH)
- 雑誌
- Hydrological Research Letters (ISSN:18823416)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.28-35, 2023 (Released:2023-05-10)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
This study aims to clarify the contributions of pre-event water to storm runoff using environmental tracers (dissolved inorganic ions and stable isotopes) in a tropical forested catchment in Puchong, Selangor, Malaysia. We performed intensive sampling campaigns of stream water and throughfall for two storm events in July and November 2018. The discharge showed a low peak of 0.13 mm/h in event 1, with 18 mm of total rainfall, whereas event 2, with 50 mm of total rainfall, showed a quick discharge peak of 1.17 mm/h and a slow recovery of 0.39 mm/h. The nitrate concentration in the stream water during event 2 was higher than that in event 1. The temporal variations in nitrate ions indicate that subsurface water provided a dominant stormflow in event 2. Hydrograph separations using silicate as a tracer revealed that pre-event water was the dominant component of the storm hydrograph (58–98%). Our results suggest that pre-event water plays an essential role in storm runoff of headwaters in humid tropical regions.
1 0 0 0 OA 死後硬直の解除とCa2+ 熟成するとなぜ食肉は軟らかくなるのか
- 著者
- 高橋 興威
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.261-267, 1981-04-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 牛乳・乳製品の好冷細菌
- 著者
- 矢野 信礼
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.103-111, 1964-04-05 (Released:2010-03-01)
- 参考文献数
- 78
好冷細菌に対する関心は, 近来食品工業および食品衛生の分野において急速に増大しつつある. この綜説ではもっぱら牛乳, 乳製品の好冷細菌について論議を進めたが, 好冷細菌の問題は食品全般について, 食品の加工利用方式の変化とともに重要となってきている.好冷細菌と一言であらわしても, その内容はおびただしい広がりをもっている. 特定の食品のみの好冷細菌の問題に限定しても, そのなかには性質および作用の異なる多数の種類の細菌が含まれている. そして食品自体が非常にバラエティに富んでいる.好冷細菌に関する諸問題を解明してゆくには, 個々の好冷細菌の生理学的生化学的諸特性および発育特性を究明してゆくとともに, 好冷細菌群の生態学的な追究が必要となってくる. 好冷細菌による食品汚染に対する対策, さらには好冷細菌の制御を合理的に推進してゆくためには, 今後これらの研究が大いに発展してゆくことが望まれる.
1 0 0 0 OA サインペン・マーカー
- 著者
- 井上 繁康
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.40-46, 2003-01-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 小田 和正
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.39-57, 2020-02-01 (Released:2022-04-07)
- 参考文献数
- 33
本稿では、U. Beckに代表されるような時代診断的研究の基本構図と諸機能、社会学理論としての諸特徴を理論的 に整理することを通して、時代診断学が社会学的研究のなかに固有の位置価をもつこと、すなわち社会学の一研究ジャ ンルとして独自の地位を占めることを示す。そのために本稿ではまず、社会学的時代診断学というK. Mannheimの 先駆的な構想に着目し、彼の構想を批判的に再検討するという方法を採る。彼の構想に見出される不備を修正することで、時代診断学における「時代」や「社会」の概念を明確化し、「診断」や「処方」の概念もまた理論的に再規定することができるからである。その上で、時代診断学について近年なされている議論の一部を参照しつつ、時代診断学が果たす独自の諸機能、および社会学理論としての諸特徴について考察している。 本稿が提示する時代診断学における時代/社会概念とは、そのときどきに人々が抱く社会像>=包括的な状況の定義であり、時代診断学はその診断において、そのときどきの社会状況に基づいてそうした状況の定義を解釈し、社会状況に非適合的な状況の定義やその定義が依拠する解釈図式を批判する。そしてその処方において、社会状況に適合的な状況の定義や解釈図式を提案する。これが本稿が提示する時代診断学の基本構図である。こうした診断・処方によって時代診断学は、直示的機能、パラダイムの刷新機能、公共的機能という三つの機能を果たしうる。これらは通常の社会記述や社会理論が担う機能とは異なると同時に社会学的研究に不可欠の機能であるがゆえに、社会学的時代診断学は社会学的研究のなかで固有の位置価をもつと言える。
1 0 0 0 OA ロボットマニピュレータのロバストな軌道追従制御
- 著者
- 吉川 恒夫 井村 順一 村井 雅彦
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.7, pp.218-225, 1990-07-15 (Released:2011-10-13)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
In this paper, we propose a robust control scheme which achieves trajectory tracking with prescribed accuracy for robot manipulators with bounded unknown parameters. This scheme is based on Lyapunov stability theorem, and the Lyapunov function is constructed using the intertia matrix. Therefore, the control law takes a very simple form which does not include the inverse of the intertia matrix. Moreover, based on the assumption that the dynamic equation can be expressed as a sum of products of unobservable matrices which contain unknown parameters and observable state vectors, this scheme makes the best use of observable states. Due to this we can expect smaller control gains. Finally, the effectiveness of the proposed control sheme is shown by numerical simulations and experimental results using a 2-degree-of-freedom manipulator.
1 0 0 0 OA 個人情報保護法と業法 ――改正電気通信事業法を検討対象として
- 著者
- 川野 智弘
- 出版者
- 情報法制学会
- 雑誌
- 情報法制研究 (ISSN:24330264)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.004-014, 2022 (Released:2023-05-26)
- 参考文献数
- 15
This paper examines the relationship between Act on the Protection of Personal Information and various business laws, with the Telecommunications Business Act, which was revised in June 2022, as the subject of the study. First, the contents of the revised Telecommunications Business Act as it relates to the provisions of Act on the Protection of Personal Information are explained. Next, the relationship between the new regulations under the revised Telecommunications Business Act and Act on the Protection of Personal Information will be analyzed and summarized. Finally, the relationship between the regulations of Act on the Protection of Personal Information in the private sector and various business laws in general will also be discussed.
1 0 0 0 OA 「ネット中立性」が目指す価値――電気通信事業法のフレームワークを踏まえた考察――
- 著者
- 実積 寿也
- 出版者
- 情報法制学会
- 雑誌
- 情報法制研究 (ISSN:24330264)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.29-40, 2020 (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 20
Net neutrality has been one of the most debated issues in the telecommunications policy arena since the 2000s. Japan is no exception, with the Japanese telecommunications authority working very hard to draft rules for net neutrality. In order to design optimal rules, we need to establish a clear and unambiguous definition of net neutrality in the Japanese context as well as policy measures to evaluate the optimality of the proposed policy package. To date, however, there is still no definition of net neutrality in the official document. There are only naïve applications of this concept that appear inconsistent with the articles of the Telecommunications Business Act of Japan, which aims to “ensure sound development of telecommunications and convenience for citizens and to promote the public welfare” (Article 1). In addition, because net neutrality rules have to provide solutions to the problems of the domestic market, there is no one-size-fits-all definition, i.e., the Japanese telecommunications authority must come up with its own unique version. In this article, the author proposes a definition of Japanese net neutrality. It discusses who should be responsible for securing net neutrality in the broadband market, how to measure the degree of neutrality, and how we should deal with the issue of fair pricing to help policymakers design an optimal policy package.
1 0 0 0 再現・昭和30年代団地2DKの暮らし
1 0 0 0 OA 〈他者〉の変奏 インヴェンションとシンフォニア
- 著者
- 油井 清光
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.102-106, 2020 (Released:2021-08-25)
- 著者
- 小嶋 崇弘
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局
- 雑誌
- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.279-343, 2008-12
1 0 0 0 『少女』文化の友 : 年報『少女』文化研究
- 著者
- 「少女」文化研究会編
- 出版者
- 「少女」文化研究会
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 OA 石炭-ペルム系秋吉石灰岩の堆積作用とカルスト化作用
- 著者
- 藤川 将之 中澤 努 上野 勝美
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.8, pp.609-631, 2019-08-15 (Released:2019-12-27)
- 参考文献数
- 99
- 被引用文献数
- 2 1
山口県中西部に位置する美祢市には,日本最大級のカルスト台地として知られる秋吉台が分布する.秋吉台は前期石炭紀~中期ペルム紀にパンサラッサ海大洋域の海洋島頂部で形成された生物礁起源の秋吉石灰岩からなり,そこには約8000万年間の気候・海水準変動が記録されている.本巡検では,海洋島の基盤となった玄武岩,後期石炭紀の現地性礁石灰岩,前-中期ペルム紀のフズリナ化石層序に基づく地層の逆転構造,前期ペルム紀オンコイド石灰岩,前期ペルム紀干潟相堆積物を観察し,現地討論を行う.また,秋吉石灰岩の代表的な堆積相を理解するため,秋吉台科学博物館所蔵の大型研磨石板標本の観察を行う.あわせて秋吉台上および秋芳洞を自然地理学的な視点から観察し,カルスト化作用とその特徴について理解する.
1 0 0 0 OA 熊沢蕃山の火葬容認論と近世の火葬論
- 著者
- 西野 光一
- 出版者
- Research Society of Buddhism and Cultural Heritage
- 雑誌
- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.9, pp.84-107, 2000-10-10 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 30