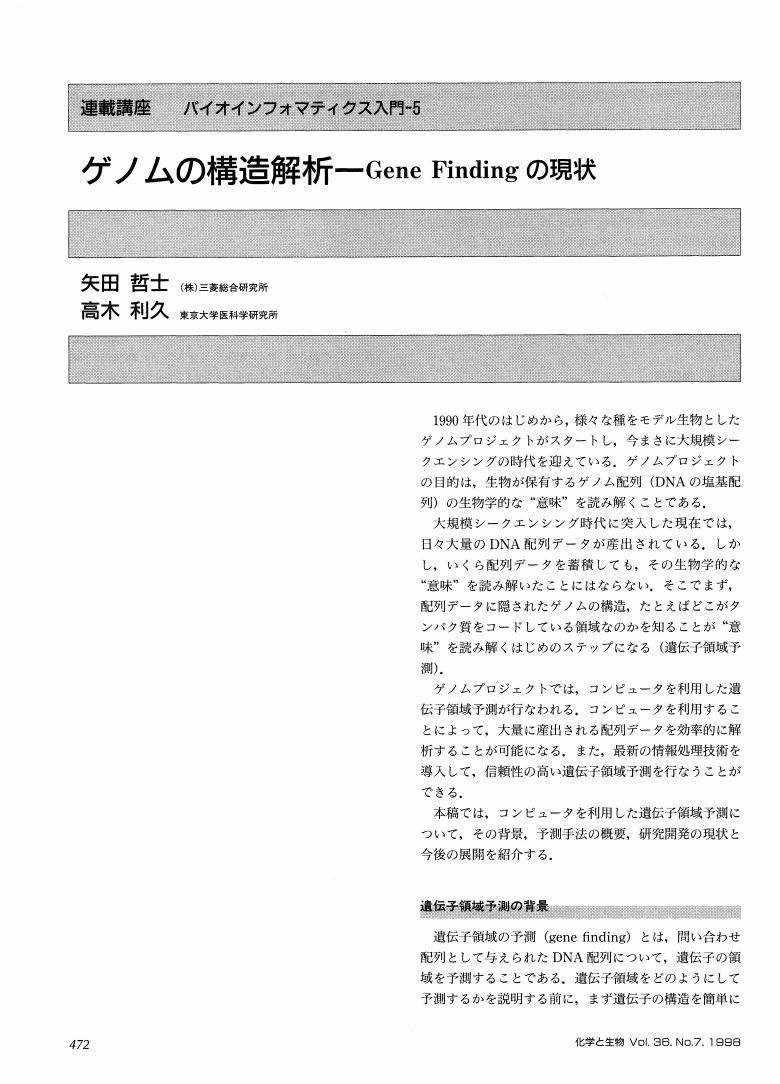1 0 0 0 OA 画像診断による植物の汚染ガス吸収機能に関する研究
- 著者
- 大政 謙次
- 出版者
- The Society of Agricultural Meteorology of Japan
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.181-186, 1992-09-10 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 化学合成独立栄養細菌における炭酸固定
- 著者
- 高橋 令二 徳山 龍明
- 出版者
- Japanese Society of Microbial Ecology / The Japanese Society of Soil Microbiology
- 雑誌
- Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology(日本微生物生態学会報) (ISSN:09117830)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.135-147, 1994-12-31 (Released:2009-10-05)
- 参考文献数
- 62
CO2 accumulation as a factor of global warming is requiring attention. Obligate chemoautotrophic bacteria grow independently of organic conditions with energy from the oxidation of reduced inorganic compounds and CO2 from the atmosphere as sole carbon sources. Chemoautotrophic bacteria consume (fix) CO2, and assimilate CO2 via the reductive pentose phosphate cycle (Calvin cycle). CO2 assimilation via the reductive tricarboxylic acid cycle (TCA cycle) occurs particularly in thermophilic hydrogen-oxidizing bacteria. This paper reviews studies on the tricarboxylic acid cycle in relation to CO2 fixation reactions of chemoautotrophic bacteria, especially nitrifying bacteria.Nitrifying bacteria promote nitrification, a stage in the nitrogen cycle. Ammonia-oxidizing bacteria (Nitrosomonas) oxidize ammonia as the sole nitrogen source of nitrite, and nitrite-oxidizing bacteria (Nitrobacter) oxidize nitrite as the sole nitrogen source of nitrate. Both bacteria fix CO2 mainly via the Calvin cycle in which ribulose 1, 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO) is a key enzyme. Less CO2 is assimilated by the phosphoenolpyruvate carboxylase pathway. The TCA cycle of nitrifying bacteria was studied and CO2 assimilation was clarified in greater detail.
1 0 0 0 OA 末梢神経再生に最適な超音波刺激方法の開発
- 著者
- 河合 秀紀 伊藤 明良 王 天舒 黒木 裕士
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.Annual59, no.Abstract, pp.236, 2021 (Released:2021-10-17)
末梢神経損傷は運動機能障害を引き起こし生活の質を低下させる。損傷した末梢神経は自己再生能をもつが、再生速度は1日に1-2mmと遅く、神経再支配が遅延すると筋や神経筋接合部の変性が原因となって運動機能回復は妨げられる。そのため、損傷後の末梢神経再生を促進させる治療方法の開発が必要である。末梢神経損傷に対する治療として、運動介入や物理的刺激を用いた介入は不動による筋萎縮や関節拘縮を予防するだけでなく、末梢神経再生や運動機能回復を促進することが報告されている。物理的刺激の中でも、超音波刺激は非侵襲的で痛みを生じない介入方法として注目されており、骨折治療をはじめとして臨床においても用いられている。損傷した末梢神経に対しても超音波刺激が再生を促進すると動物実験において認められているが、その刺激条件や介入時期といった末梢神経再生に最適な介入方法は明らかになっていない。更なる末梢神経再生促進のためにも最適な超音波刺激介入方法を解明する必要がある。我々は坐骨神経挫滅損傷モデルラットを用いて超音波刺激の強度や介入開始時期の検証研究を行ってきた。本演題では、末梢神経再生に最適な超音波刺激方法の開発に向けた研究結果を紹介する。
1 0 0 0 OA 北海道官設鉄道と札幌農学校出身の鉄道技術者
- 著者
- 原口 征人 日野 智 今 尚之 佐藤 馨一
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.213-218, 2001-05-01 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 14
本研究では土木教育機関とその所在地にある土木事業の結びつきについて、教育機関の果たしてきた役割を考察する。特にこれまでの札幌農学校は、広井勇の築港事業に焦点が当てられてきたが、組織運営的な観点から多くの技術者が関わったといえる鉄道事業との関係を取り上げた。考察の結果、北海道庁の鉄道建設部署と札幌農学校で相互に人事上の結びつきがあり、一貫した教育の形成に作用していたことが分かった。
1 0 0 0 OA 原子・分子論の成立が導いた物理学と化学の変貌(化学が変えた 20 世紀)
- 著者
- 細矢 治夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.782-785, 2000-12-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 4
電子が発見されたのが百年前だから, 科学者が原子や分子の存在を実証的につかんだのも百年前である。更にその後誕生した量子力学とエレクトロニクスの助けを借りて, 20世紀の化学は大きく発展した。自然科学や社会の中での化学の重要性と役割は, 原子や分子の実体を知らなかった化学の祖ラヴォアジェーが考えていたものよりはるかに大きい。世間の人の化学に対する認識もここまで上げる必要がある。こういう見方で, 化学だけでなく, 20世紀の諸科学や技術の発展を評価することができる。
1 0 0 0 OA 学術雑誌と査読
- 著者
- 岡本 悦司
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療経営学会
- 雑誌
- 日本医療経営学会誌 (ISSN:18837905)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.3, 2023 (Released:2023-10-04)
1 0 0 0 重みつき組合せ最適化と多項式行列理論のインタラクション
- 著者
- 大城 泰平
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 ACT-I
- 巻号頁・発行日
- 2018
一部の組合せ最適化問題は行列理論を経由して効率的に解くことができ、また逆にある種の行列の問題は、組合せ最適化の道具を用いて解けることが知られています。本研究では、この相互に確立された活用手法を拡張し、「重みつき組合せ最適化問題」と「多項式行列の問題」の対応に迫ります。特に、組合せ的問題において多項式行列が果たす役割の解明、および多項式行列理論における組合せ最適化手法の活用法の創出を目指します。
1 0 0 0 OA ゲノムの構造解析-Gene Finding の現状
- 著者
- 矢田 哲士 高木 利久
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.7, pp.472-476, 1998-07-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 開口部の日射熱取得率測定法に関する研究 : 開口部の断熱・遮熱性能 その1
- 著者
- 倉山 千春
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.604, pp.15-22, 2006-06-30 (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 11 10
Evaluation of thermal performance of fenestration system under cooling season is based on heat gains by temperature difference and solar radiation, characterized by thermal transmittance (U-value) and solar heat gain coefficient (SHGC), respectively. However, current test methods are only concerned with nighttime performance, and may not accurately reflect the performance improvements of specific window designs. With nighttime test methods, the thermal performance of a fenestration system is characterized only by the U-value. In this paper, a new test method has been developed to measure the thermal performance of fenestration systems. This method enables the determination of SHGC and U-value for various fenestration systems under cooling season, including integral shading devices and complex frame designs.
1 0 0 0 OA 腹部外傷による出血性ショックに対する緊急O型未交差赤血球輸血の経験
- 著者
- 森脇 義弘 鈴木 範行 杉山 貢
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.147-153, 2009-02-01 (Released:2011-12-23)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 3
はじめに:肝,脾,腸間膜損傷で出血性ショック合併の腹部外傷では,蘇生的緊急開腹術など外科手技の適応と緊急輸血の適応判断を迫られる.異型輸血を含む危険を内在する未交差赤血球製剤(uncrossmatched-red cell concentrate;以下,UCM RCC)緊急輸血の安全性と問題点を考案する.方法:過去5年間で,O型Rh+UCM RCCを含むUCM RCC緊急輸血を実施した腹部外傷を対象にUCM RCC輸血の実態と輸血関連インシデント・アクシデント回避の成否を検討した.結果:UCM RCC輸血は33例に54回,388単位実施され,準備UCM RCCは426単位で使用率は91.1%であった.出血源は肝臓13例,脾臓8例,腸間膜17例で,輸血前平均収縮期血圧は62.5 mmHg,脈拍数117回/分,ショック指数(脈拍数/収縮期血圧)1.97,base excessは−12.7 mEq/l,7日生存例は48.5%であった.血液型判定(blood typing test;以下,BTT)未判定でのO型UCM RCC輸血は17例(21回,168単位),うち非O型への輸血は11例(14回,120単位)であった.1回のBTT後のO型UCM RCC輸血は8例(12回,96単位),うち非O型への輸血は4例(7回,54単位)で,1回のBTTでの非O型症例への未確認同型UCM RCC輸血は15例(20回,120単位)であった.O型UCM RCC輸血全体に年度別増減はなかったが,1回のBTTでの非O型への未確認同型UCM RCC輸血は減少した.ABO型不適合輸血,輸血に関わるインシデントはなかった.考察:UCM RCC輸血では,院内マニュアルを整備したうえでのO型UCM RCCの使用は安全と考えられた.
1 0 0 0 OA J-13 熱収支の面から見た寒冷地の窓における望ましい性能
- 著者
- 鈴木 憲三
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成24年 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.1037-1040, 2012-08-20 (Released:2017-08-31)
- 著者
- 加藤 正宏 山中 俊夫 小林 知広 渡部 朱生
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.285, pp.17-27, 2020-12-05 (Released:2021-12-05)
- 参考文献数
- 14
大面積の窓を有するエントランス・吹抜空間や,窓性能が低く暖房時に窓近傍の温熱環境悪化が懸念される場合にはペリメータファンおよび自然対流型ペリメータヒータなどの窓対策設備の使用が検討される。本報告では冷却された窓面下部に機器を設置した場合の詳細な現象の把握とシミュレーション検証データ取得を目的とした温度分布およびPIV による風速分布測定を行った。また,特に上下温度分布予測モデルの検証やモデル化に反映するため,窓面近傍の上昇流・下降流風量の推定と,室温・窓面熱流の測定値より,対流・放射熱伝達率を算出した結果について報告する。
1 0 0 0 OA 社会選択理論―一つのノート―
- 著者
- 山口 利夫
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱経済研究所 経済研究書 (ISSN:27587711)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.51, pp.1-108, 2000-06-15 (Released:2023-08-01)
1 0 0 0 OA メニエール病発作時の血中コルチゾール値の変動
1 0 0 0 IR 政党助成をめぐる政党間カルテルの形成と維持に関する研究
1 0 0 0 OA 学術系 VTuber のススメ
- 著者
- 北川 俊作
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.10, pp.633-635, 2023-10-01 (Released:2023-10-01)
1 0 0 0 OA ICTやAIの時代にバイオフィードバックはどう活用できるか : 産・学・官の連携
- 著者
- 中尾 睦宏
- 出版者
- 日本バイオフィードバック学会
- 雑誌
- バイオフィードバック研究 (ISSN:03861856)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.87-92, 2018 (Released:2018-12-22)
- 参考文献数
- 13
バイオフィードバック・ツールを 「社会」 で活用してもらうためには, ①どこで, どのように使われるのが望ましいのか仮説設定をし, ②導入・継続運営するのに要するリソースを計算し, ③社会実装する段取りを決める, という3つのプロセスが必要となる. その上で, 仮説設定と強化のために関係する見込みのある企業等と意見交換し, ステークホルダー (利害関係者) を同定できたら, 行政にも働きかけることが肝要となる. 本シンポジウムでは, バイオフィードバック・ツールの社会実装の例として, ゲーミフィケーションを紹介した. まず演者らは, 「認知行動療法的アプローチによるココロの元気が出るアプリ」 を, 大手ゲーム会社の協力を得て開発をした (中尾ら.第42回日本バイオフィードバック学会学術総会発表). 完成したアプリは, 1年間の限定配信で, 1万ダウンロードを超える反響を得た. 同時並行して, 次世代アプリに実装するための認知行動療法プログラムの開発を行い, その臨床効果を示した (Shirotsuki K, et al. BioPsychoSoc Med 2017 Sep 19 ; 11 : 2). これらの活動は, 神奈川県の 「未病プロジェクト」 研究の1つとして採択され, 2015年度から3年間の助成を受けた. その経験から, ICT・AI社会でバイオフィードバックを今後さらに発展させるため, 4つの方向性を提言した. ウェアラブル端末への実装 (健康状態の把握), 生活補助ツールとしての活用 (生活機能の介助), 生活空間への活用 (個人-環境インターフェイス), バイオフィード従事者の新たな役割 (健康マネジメントのリーダーシップをとる人材育成) の4つである.