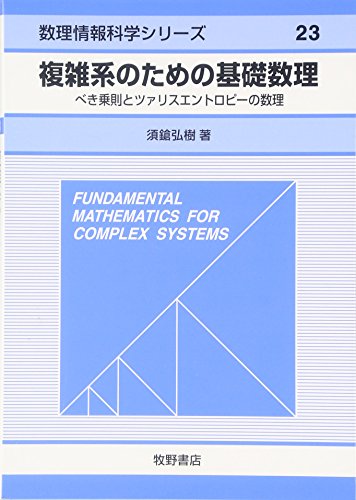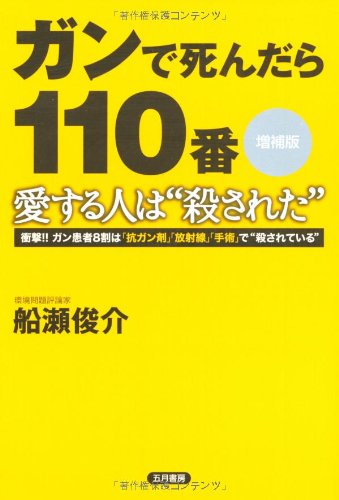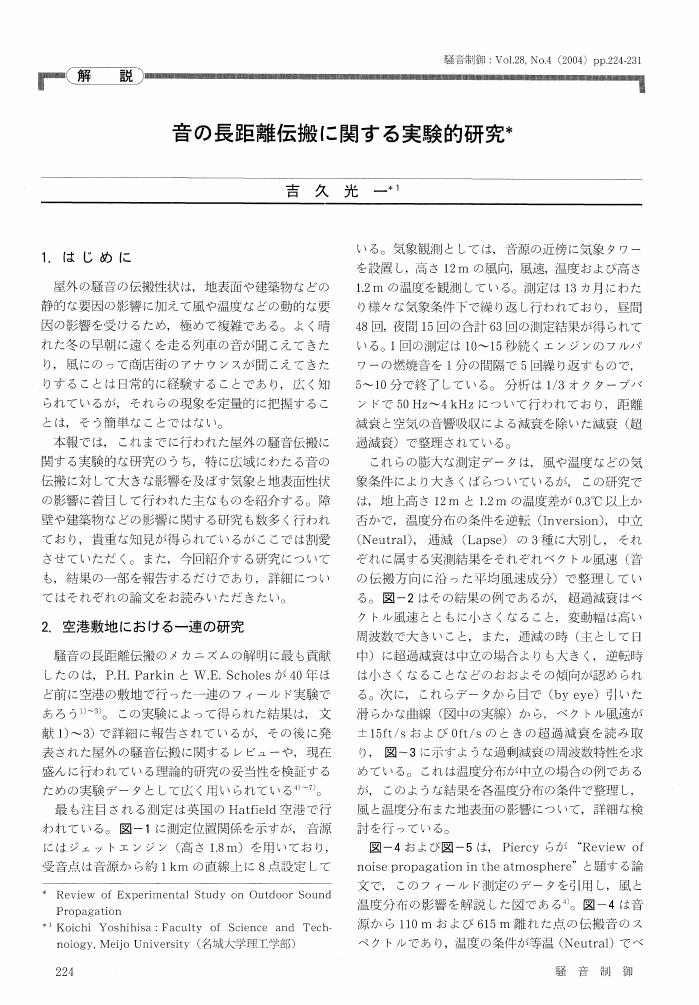1 0 0 0 OA 自治体相談支援業務と非正規公務員 その実態
- 著者
- 上林 陽治
- 出版者
- 公益財団法人 地方自治総合研究所
- 雑誌
- 自治総研 (ISSN:09102744)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.498, pp.25-52, 2020 (Released:2020-12-02)
1 0 0 0 OA 古地図の幾何補正に関する研究
- 著者
- 清水 英範 布施 孝志 森地 茂
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.625, pp.89-98, 1999-07-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 10 5
江戸時代の絵図に代表される古地図は, その図が作成された当時の土地利用や交通路の状況を空間的に把握するための数少ない貴重な資料である. 都市史や土木史の研究で古地図を分析対象とする際には, 現代図と比較対照する必要が生じるが, 古地図の幾何的精度は一般に著しく低く, その作業は容易なことではない. 本研究は, 地理情報システムの利用環境を想定し, 古地図の幾何的歪みを可能な限り自動的に補正し現代図と重ね合わせる手法を開発することを目的としている. 論文では, まず古地図の幾何補正に必要な要件を整理し, その要件を満たす手法としてTINモデルとアフィン変換を組み合わせた幾何補正手法を提案する. また, いくつかの実際の応用を通して古地図の幾何補正ならびに提案する手法の意義を例示する.
1 0 0 0 複雑系のための基礎数理 : べき乗則とツァリスエントロピーの数理
- 著者
- 上小牧 駿 倉本 宣
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.215-218, 2021-08-31 (Released:2021-12-29)
- 参考文献数
- 15
国外移入種アレチケツメイの発芽特性を明らかにするため,発芽実験を行った。また,アレチケツメイの侵入地である安倍川において,同所的に生育が確認された同属の在来種カワラケツメイについても同様の実験を行った。その結果,アレチケツメイはカワラケツメイと比べて,物理的休眠の打破が起こりにくいこと,乾熱への感受性が低いこと,発芽最適温度が高いことが示唆された。アレチケツメイは永続的な埋土種子集団を形成し,相対的に発芽時期が遅い可能性がある。これらのことから,アレチケツメイは一度侵入すると根絶は困難であり,侵入初期やまだ侵入していない河川においては十分な対応が求められる。
1 0 0 0 OA 学びの場が生まれるとは
- 著者
- 佐伯 胖
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.153-160, 2015 (Released:2015-08-25)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 軌道緑化に対する住民意識構造とその整備効果に関する研究
- 著者
- 伊藤 雅
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.I_621-I_628, 2013 (Released:2014-12-15)
- 参考文献数
- 7
路面電車の軌道緑化は,都市景観の創出,ヒートアイランドの緩和,騒音の抑制など様々な効果をもたらしている.本研究では,2007年度から本格的に軌道緑化がなされ,2012年度末には道路延長にして8.9kmの併用軌道区間全ての緑化が完成するという,日本で最も整備が進んでいる鹿児島市の路面電車沿線住民を対象として,軌道緑化に対する住民意識に関するアンケート調査を実施した(有効回答数327世帯).その結果,軌道緑化の整備が進むにつれ市民の評価意識は高まり,公的事業としての軌道緑化事業の実施推進や税金利用に対する意識の向上を促していることがわかった.また,アンケートによる支払意思額にもとづいて軌道緑化の環境価値を推計したところ,年間数億円程度の便益がもたらされている可能性を示した.
- 著者
- 山本 喜久
- 出版者
- 国立研究開発法人科学技術振興機構
- 雑誌
- 源流 (ISSN:13453610)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.2, pp.1-5, 2000 (Released:2000-11-30)
- 参考文献数
- 14
極低温に冷やした半導体(GaAs)に作成した二次元電子ガスがフェルミ縮退していることを利用して、電子衝突過程の量子干渉効果とアンチバンチング性の直接観測に成功した。量子干渉効果は電流雑音(ゆらぎ)から観測し、アンチバンチング性については量子ポイントコンタクトから放出される電子の負の強度相関により観測した。
1 0 0 0 OA ホログラフィックスキャナとホログラフィックプロジェクション技術
- 著者
- 下馬場 朋禄
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.137-141, 2015-02-10 (Released:2019-09-27)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
ディジタルホログラフィや計算機合成ホログラムなど,コンピュータ上でホログラムを扱う技術を総称してコンピュータホログラフィと呼ぶ.コンピュータホログラフィの応用は多岐にわたるが,本稿では,特に大面積のホログラムを撮影するためのスキャンニング技術とレンズを使用しないホログラフィックプロジェクション技術について紹介する.
- 著者
- Hirokazu NAGASAKI Michihisa NARIKIYO So OHASHI Hidenori MATSUOKA Yoshifumi TSUBOI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-0042, (Released:2023-08-23)
- 参考文献数
- 12
In revascularization of internal carotid stenosis with carotid vertebrobasilar anastomoses, attention should be paid not only to the anterior circulation but also to the posterior circulation cerebral infarction. A 74-year-old man was referred for treatment of carotid artery stenosis; NASCET 75% stenosis in the right internal carotid artery and acute cerebral infarction were confirmed. Occlusion of the left subclavian artery and vascular anastomosis between the right external carotid artery and the vertebral artery were indicated, such that the right external carotid artery may maintain blood flow to the vertebrobasilar artery. Therefore, dual shunts were used for the common and internal carotid arteries and the common and external carotid arteries to maintain blood flow during carotid endarterectomy. Management of the dual shunts is difficult due to the instable parallel placement of the common carotid artery shunt balloons. To solve this problem, the "dual internal shunts technique" was performed. The first shunt was inserted into the external and common carotid arteries, and the second into the internal and common carotid arteries. The shunt balloon on the common carotid artery side was placed distal to the first shunt balloon so that the dual balloons were placed in a tandem position. The proximal balloon was subsequently deflated gradually to improve flow in both shunts. The procedure is technically easy and safe.
1 0 0 0 OA 植物の化学防御戦略からみた毒と昆虫における毒検出戦略
- 著者
- 尾﨑 まみこ
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第47回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.S11-3, 2020 (Released:2020-09-09)
植物は常に食植生昆虫の脅威にさらされているため、昆虫による食害に対抗して植物体内に毒を生産するものが多い。特に解毒機構を進化させてこなかった昆虫種は、植物体を食べ尽くすころには絶命することになる。しかし、昆虫の方でも毒を素早く検出して避けることができれば、生き延びる可能性が高くなることから、ヒトと同様に、毒物を苦味として知覚する味覚受容・認識機構を発達させて毒を検知している。昆虫の苦味受容については2000年ごろまではほとんどわかっておらず、私達とイタリアの研究グループがほぼ同時にハエの味覚器で苦味受容細胞を機能的に特定することに成功したが、その細胞が、経口毒の検出に関わって緊急な嘔吐反応を引き起こすきっかけとなっていることは、味覚器における匂い物質結合蛋白質(gustatory OBP)の関与に気づいた私達の研究によって初めて明らかとなった。また、同一物質の匂いを認知するための嗅覚器も毒の検出に一役買っており、嗅覚器である触角で嗅ぎ分けられた毒物の匂い情報が、昆虫の食欲を有意に低下させること、その匂いの記憶が食欲低下を一生涯維持させることなども分かってきた。この食欲不振はハエにとって、一見不健康にみえるかもしれないが、毒物を摂取して絶命することを思えば有益な反応であるとも考えられる。そうであれば、植物は、もはや自らを食べ尽くさせてまで致死毒を以て昆虫を殺す必要はなく、昆虫の味覚器や嗅覚器の毒検出機構にターゲットを絞って、ほんの少しの食害で、苦い味、食欲を減退させる匂いをもつ嫌悪物質を生産する方が賢明であろう。このような、防除戦略に移行した植物がいる。後半では、双方が死に至る毒に頼った防御放棄して、双方の生き残りが望める新たな防御戦略を獲得したアブラナ科植物の話をつけ加えたい。
1 0 0 0 OA 植物の化学防御 異種間のせめぎ合い
- 著者
- 石原 亨 野下 浩二 謝 肖男
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.46-53, 2020-01-01 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 ことわざ故事金言小事典 : 付・いろはがるた略解
- 著者
- 江藤寛子 加古三郎共編
- 出版者
- 福音館書店
- 巻号頁・発行日
- 1968
1 0 0 0 OA 音の長距離伝搬に関する実験的研究
- 著者
- 吉久 光一
- 出版者
- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.224-231, 2004-08-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 22
- 著者
- Yoichi Ikeda Yoshihiko Umemoto Daiju Matsumura Takuya Tsuji Yuki Hashimoto Takafumi Kitazawa Masaki Fujita
- 出版者
- The Japan Institute of Metals and Materials
- 雑誌
- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.9, pp.2254-2260, 2023-09-01 (Released:2023-08-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
Extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) and neutron diffraction experiments were carried out to clarify the typical features of the local structure of a family of medium-entropy alloys (CrCoNi, MnCoNi, and FeCoNi). A simple random cluster model was constructed for analyzing EXAFS spectra, and static and dynamic components of the mean-square relative displacement (MSRD) were separately extracted. In our analysis, the static MSRD of the MnCoNi sample was slightly larger than those of the CrCoNi and FeCoNi samples, whereas the dynamic MSRDs of these samples were almost identical. Based on the complementary neutron diffraction data, we argued that the origin of the large static displacement in the MnCoNi alloy can be associated with a short-range structural transformation through long-term structural relaxation.
1 0 0 0 OA 自然気胸の心電図
- 著者
- 堤 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.210-214, 2017-11-02 (Released:2018-04-16)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA ブール代数を用いた制約充足問題の定式化と解法についての検討
- 著者
- 永井 保夫 長谷川 隆三
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.808-821, 1995-04-15
制約充足は人工知能や画像理解の分野をはじめ、グラフの問題やパズルなどの探索間題、いわゆる組み合わせ問題を対象として研究がおこなわれている。制約充足問題の代表的な解法として、探索法や整合化手法を用いる方法が知られている。われわれは、このような探索主体のアプローチとは対照的な位置付けにある代数的アプローチについて諭じる。本アプローチでは、制約論理型言語の探索機構を利用した制約充足問題に対する研究とは異なり、制約論理型言語におけるブール制約評価系を用いて代数的に制約充足をおこなう。本論文では、ブール代数により制約充足問題を定式化し、得られたブール方程式の求解を制約論理型言語CALにおけるブール制約の評価とみなすことにより、解であるブーリアン・グレブナ基底を求める方法について述べる。さらに、ブール制約評価系を用いた制約充足問題の効率化手法として、1)ブーノレ制約の簡単化方式、2)制約ネットワークの構造情報に基づいた制約の評価順序の決定方式、について提案する。そして、本効率化手法の有効性を確認するために、ブール制約を用いて記述された問題に対して適用実験をおこなう。その結果、制約充足問題の解法として探索法がよく知られているが、それとは異なるあらたなブール代数評価系を用いた代数的な方法ならびに効率化手法が有効であることを示す。
1 0 0 0 アトピー性皮膚炎患者のYG性格検査
- 著者
- 遠藤 薫
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.6, pp.945-959, 2003-05-20 (Released:2014-12-13)
- 被引用文献数
- 1
アトピー性皮膚炎入院患者504名(男202名,女302名)に施行した矢田部―ギルフォード(YG)性格検査の結果を健常人164名(男45名,女119名)と比較すると,男性患者は健常人男より性格因子D(抑うつ的),I(劣等感),N(神経質)が高く,G(活動的)が有意に低くなっていた.女性患者は健常人女よりAg(攻撃的)とR(のんき)が低くなっていた.健常人女は健常人男よりD,C(回帰性傾向),Iが高く,情緒的に不安定であった.逆に男性患者は女性患者よりNが高く,S(社会的外向)が低く,女性患者は男性患者よりAgとRが低くなっていた.アトピー性皮膚炎の症状で比較すると,男では,入院時重症になるほど,DとCが高く,Sが低くなっていたが,女では性格因子に差がなかった.治療などを考慮した疾患重症度をみると,男では,D,Cの有意差が消失していた.顔面重症度を見ると,女性患者では中等症に比べて軽症及び重症患者で,GとSに低下が見られた.発疹型を6群(紅斑型,丘疹型,紅斑+丘疹型,貨幣状型,肥厚・苔癬化型,痒疹型)に分類すると,男において,紅斑型と肥厚・苔癬化型は,紅斑+丘疹型,貨幣状型に比べて,D,I,N,Co(非協調的)が高く,Ag,G,R,A(支配的),Sが低くなっていた.アトピー性皮膚炎を臨床経過から,現在の発疹が悪化してからの年数が5年未満の群と5年以上の群に分けると,5年以上の群は男性患者でCoが高くなっていた.入院直前1カ月のステロイド外用量から,5群(0g/月,5g/月未満,5~50g/月,50g/月以上,ステロイド内服・注射)に分類した.男性患者では,5g/月未満と5~50g/月の群は0g/月とステロイド内服・注射の群に比べてAgが高く,女性患者では50g/月以上の群でAgが高くなっていた.さらに,入院中のステロイド外用量から同様に分けると,男性患者ではステロイド内服した群において,性格因子D,Iが高く,G,R,A,Sが低下していた.女性患者では,ステロイドの外用が多くなると,AgとSが低くなっていた.検査値との関係を見ると,血清LDH値では,高値であるほど女性患者でRが低下していた.血清IgE値が高いほど,男性患者ではDが高く,女性患者ではRが低下していた.また,血清cortisol値が低いほど,男性患者では,O(主観的)が高く,女性患者では,DとIが高くなっていた.アトピー性皮膚炎の男は,健常人より情緒が不安定で人間嫌いで閉じこもる傾向があり,女は優柔不断で他人の意見に左右されやすく,特に顔面が悪化すると人間嫌いで閉じこもる傾向があると言える.また,皮膚症状が性格因子に影響する以上に,性格因子の問題点が臨床経過に重大な影響を及ぼしている可能性がある.
1 0 0 0 OA 植物DNA修復選択システムを利用した低モザイクゲノム編集育種技術の構築
本研究は、正確なNHEJがどのような経路によって制御されているのか?、またどのような因子が関わっているのか? などの疑問点を解明し植物ゲノム編集技術に応用することで、正確なモザイク性が低い変異導入システムを構築することを目的とする。さらに、安定な変異系統の固定技術として、一世代で固定する技術の基盤となるセントロメアヒストンの制御機構を利用した簡便で汎用性のある半数体作出法および誘導型ウィルスベクターを用いたゲノムに外来遺伝子を組み込まないゲノム編集法を開発・確立し、3つの技術を組み合わせることにより、従来のゲノム編集技術を用いた育種法の問題を克服した作物分子育種基盤を構築する。