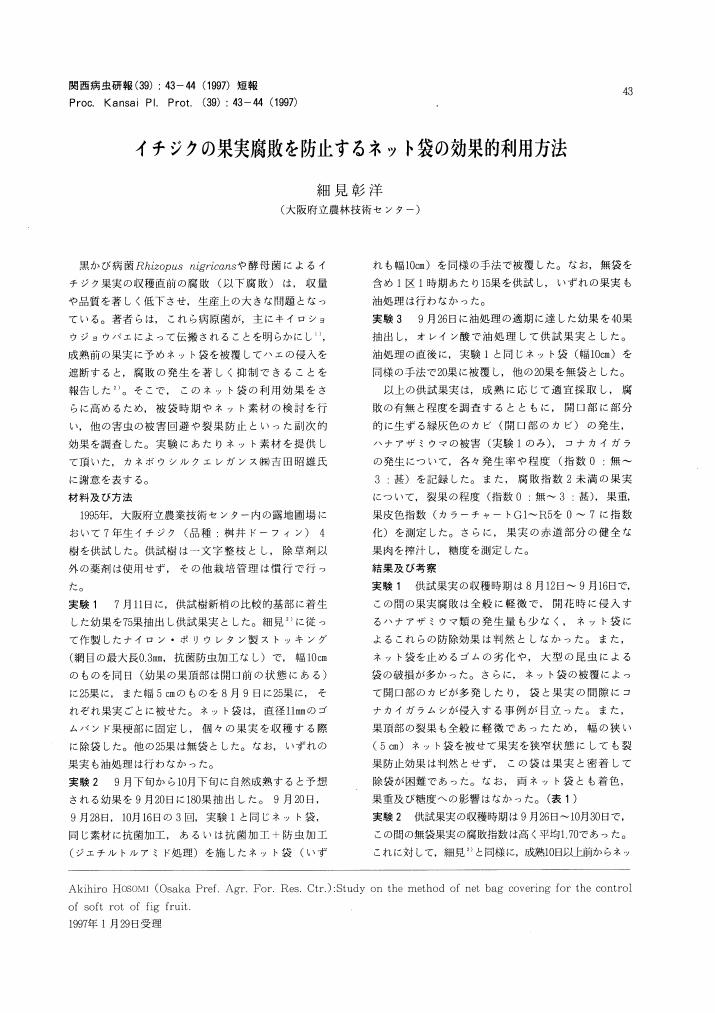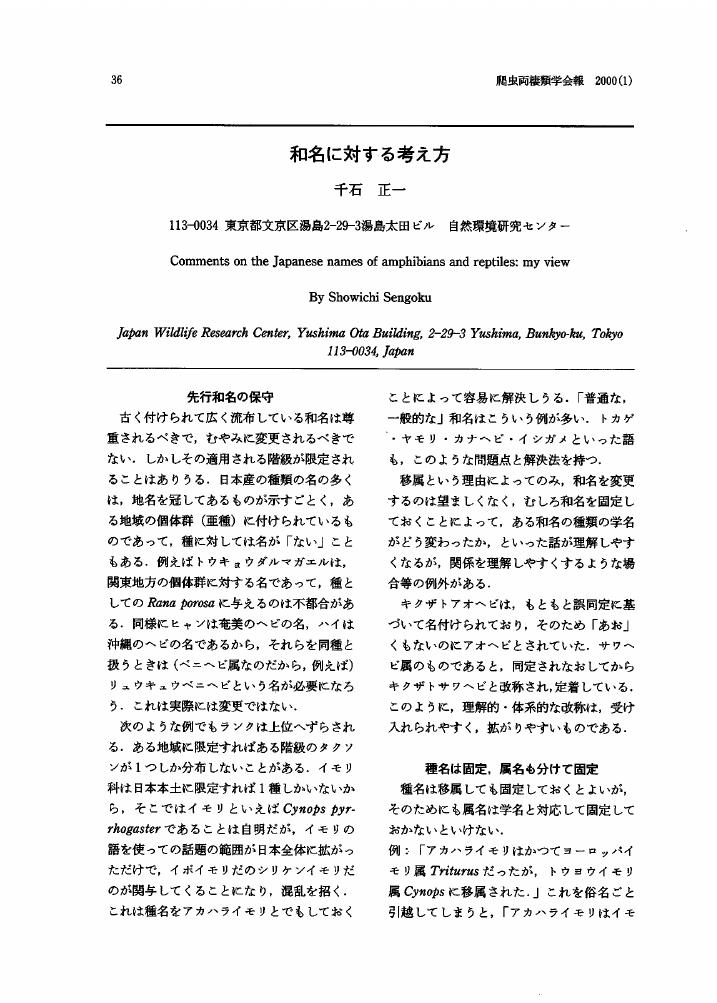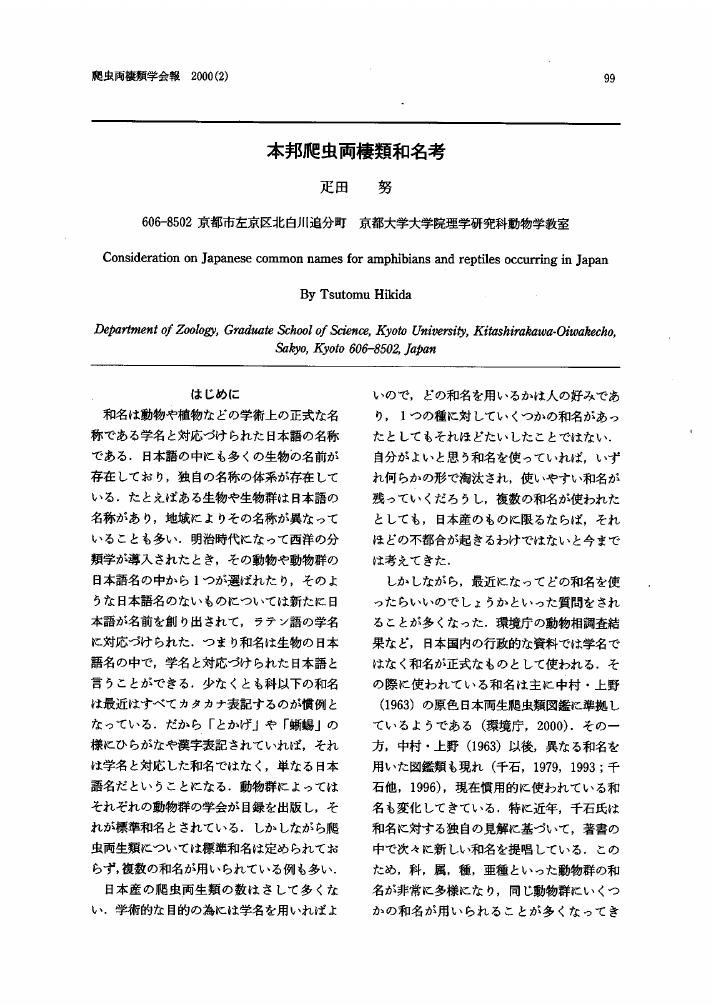1 0 0 0 OA イチジクの果実腐敗を防止するネット袋の効果的利用方法
- 著者
- 細見 彰洋
- 出版者
- 関西病虫害研究会
- 雑誌
- 関西病虫害研究会報 (ISSN:03871002)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.43-44, 1997-05-01 (Released:2012-10-29)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 食品パッケージに見られるレアな昆虫の事例Ⅱ イトメン株式会社の「チャンポンめん」
- 著者
- 高田 兼太
- 出版者
- 伊丹市昆虫館
- 雑誌
- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-3, 2018-03-31 (Released:2019-11-11)
1 0 0 0 OA GENECUBE®モデルCの異なる核酸抽出法によるSARS-CoV-2核酸検出能の比較
- 著者
- 亀井 直樹 田口 愛海 石橋 万亀朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.638-643, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 8
目的:SARS-CoV-2の新しい検査法は開発・普及が急速に進んでいる。当院では鼻咽頭ぬぐい液を検体とする検査は自動遺伝子解析装置のGeneXpertシステムを用いて実施していた。2020年7月以降より唾液検体が新型コロナウイルス核酸検出における正式な検体として認められたことから検体採取時における医療従事者への2次感染の防止などを考慮し,唾液検体での検査を要望された。これを受け新たにGENECUBEモデルC(東洋紡)を導入し,ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2(東洋紡)にて唾液検体での検査を実施することとなった。導入にあたり,唾液検体からの核酸抽出についても検討を進めることとなり,自動核酸抽出法であるmagLEAD(PSS,magLEAD法)とヒートブロックを使用する加熱抽出法について3つの検討を行った。方法:①擬似ウイルス管理試料で希釈系列を作成し,両核酸抽出法の検出能を検証した。②陰性確認済みの唾液検体に擬似ウイルス管理試料を加えた疑似検体を用いて両核酸抽出法への阻害物質の影響を検証した。③magLEAD法にて陽性であった臨床検体を加熱抽出法でも確認した。結果:magLEAD法の検出能は0.25コピー/μL,加熱抽出法で1コピー/μLであった。一方で加熱抽出法では検出ができなかった。結論:唾液検体を用いる場合は阻害物質の影響を考慮して検査をする必要があると思われた。
1 0 0 0 OA ワークライフバランス:7.4歳の子どもを連れて学会に参加してみた
1 0 0 0 OA 戦前の日本における外国人犯罪の歴史的変容
- 著者
- 中條 晋一郎
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.110-129, 2003-10-18 (Released:2017-03-30)
本稿は,明治期より太平洋戦争終結までの日本の外国人犯罪を分析するものである.戦前の外国人犯罪に関する公式統計は,『検察統計年報』の前身である『刑事統計年報』にのみ現存するため,このデータを分析に用いた.しかしこのデータは,外国人に係る刑事裁判の受理件数,及び人員数を集計したものであったため,警察統計や検察統計に比べ,当時の外国人犯罪の実体に迫るには限界が生じることとなった.そのような条件の下で,全ての第一審終局処理人員における罪種の傾向と,外国人の第一審終局処理人員における罪種の傾向とを比較して,外国人犯罪の特徴を探った.加えて,当時の犯罪傾向や外国人労働者問題等に関する先行研究を参考として,データを分析し,解釈を試みた.その結果,「外国人被告」における主要罪種は,時代によって変遷していることが分かった.また,戦前を通した外国人犯罪の特徴としては,(1)中国人による犯罪が中心であったこと,(2)窃盗や賭博など,比較的軽微な犯罪が中心であったことなどが示された.なお,戦前の日本には,朝鮮半島出身者も多数在留していたが,「外国人」ではなかったため,犯罪の状況を分析することはできなかった.
1 0 0 0 特殊環境を用いた動的多感覚統合脳機能の解明
1 0 0 0 OA 熱水活動が海洋環境と深海生態系にもたらす影響
- 著者
- 砂村 倫成 野口 拓郎 山本 啓之 岡村 慶
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.6, pp.1160-1173, 2009-12-25 (Released:2010-03-23)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 3 2
Hydrothermal circulations supply a huge amount of chemical species into the deep sea. More than 99% of chemical species emitted from high-temperature hydrothermal fluids flow into the deep sea and construct deep-sea hydrothermal plumes. Observations of hydrothermal plumes have led studies of deep-sea hydrothermal vents, such as locating deep-sea hydrothermal vents, locating deep-sea volcanic eruptions, and calculating geochemical fluxes from sub-seafloor to deep ocean. Hydrothermal plumes affect the microbial community in deep seas by supplying many reduced chemicals, which are possible energy sources of chemolithotrophic microbes. This paper (1) reviews physical, chemical, biological studies of hydrothermal plumes and (2) discusses novel field survey technology and ecological infection of sub-seafloor to the deep-sea environment.
1 0 0 0 OA 木下尚江『小説 墓場』私論
- 著者
- 青木 信雄
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.9, pp.20-28, 1977-09-10 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 OA 河川連続体仮説と洪水パルス仮説を統合した河川水系一貫物質循環解析
- 著者
- 戸田 祐嗣 溝口 裕太 野尻 晃平 山下 貴正 辻本 哲郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.I_1687-I_1692, 2013 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 20
A numerical simulation model was presented to describe the material cycling along a river with floodplain, in which river continuum concept and flood pulse concept were modelled to be taken into account for considering the energy flow in river ecosystem. Using the discharge and the river channel conditions observed in Yahagi River, the dynamics of organic matter was illustrated. The organic matter entering into the river from terrestrial area is transported under the effects of physical and biochemical processes in each longitudinal segment of the channel. The results of the simulation show that the amount of organic matter transported during floods is about 28% in Segment.2.
- 著者
- 中川 和明
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.7, pp.44-63, 2023-07-01 (Released:2023-07-20)
NHK放送文化研究所は、2020年から新型コロナウイルスに関する世論調査を毎年行っており、3回目となる2022年の調査については、感染拡大の不安やストレスなどに関する結果を『放送研究と調査』(2023年5月号)に掲載した。本稿は、それに続くもので、コロナ対策やデジタル化、コロナ禍がもたらしたものなどについて報告する。主な内容は以下のとおりである。なお、ここで紹介する調査結果は、2022年の調査時点のものである。 政府のコロナ対策について『評価する』が55%で『評価しない』の44%より多いものの、『評価しない』と答えた人が前回よりも増えている。感染対策のために個人の自由が制限されることについて『許されない』と答えた人が20%で前回より増加した。いま力を入れるべきこととして、『経済活動の回復』と答えた人が60%で、『感染対策』と答えた人の39%を大きく上回った。 コロナ禍を経て様々な手続きや活動がオンラインでできるようになったが、オンラインで仕事をしたことがあると答えた人は22%にとどまり、7割の人はしたことがないと答えた。さらに、オンラインで仕事をしたことがあるのは、事務職や管理職などのいわゆるホワイトカラーで多く、年収の高い、大都市に住む人たちでよく利用されていた。一方、オンライン化の進展に関して、個人情報を把握される懸念を感じている人が7割から8割ほど、また個人情報の流出も該当者の8割ほどを占めた。 3年にわたったコロナ禍について、マイナスの影響が大きいと答えた人が74%で多くを占めたが、若い人たちを中心に、「家族と過ごせる時間が増えた」「在宅勤務など柔軟な働き方ができる」「今までと違う楽しみを見つけた」など、前向きに捉える人たちも一定数にのぼった。
- 著者
- 宇治橋 祐之 渡辺 誓司
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.30-63, 2023-06-01 (Released:2023-06-20)
NHK放送文化研究所では,全国の学校現場におけるメディア環境の現状を把握するとともに,放送,インターネット,イベントなどNHKの教育サービス利用の全体像を調べるために,1950年から定期的に学校を単位として,あるいは教師個人を対象として全国調査を行ってきた。全国の小・中学校で「児童生徒向けの1人1台端末」と「高速大容量の通信ネットワーク」を一体的に整備するGIGAスクール構想の本格的な運用が始まり2年目となる2022年度は、1人1台端末の授業での利用だけでなく、家庭への端末持ち帰りとその利用状況を把握するために、中学校の教師個人を対象とした。対象教科は初めて5教科(理科、社会、国語、外国語、数学)としている。 GIGAスクール構想前の2019年度の結果と比べると、タブレット端末を利用できる環境にある教師が大幅に増加(63%→91%)、インターネットを利用できる環境にある教師(77%→93%)も増えていた。 また、生徒に1人1台ずつ配付されたパソコンやタブレット端末(「GIGAスクール端末」)を授業で生徒に利用させている教師は、5教科全体で87%であった。さらに授業で「GIGAスクール端末」を生徒に利用させている教師でみると、6割を超える教師が「家庭への持ち帰り学習」を行っていた。 授業でのメディア教材の利用についてみると、「指導者用のデジタル教科書」(33%→49%)の利用と、NHKの学校放送番組あるいはNHKデジタル教材のいずれかを利用していた「NHK for School教師利用率」(38%→49%)が増加していた。また、教科別にみると理科と社会で「NHK for School教師利用率」、外国語で「指導者用のデジタル教科書」と「学習者用のデジタル教科書」の利用が多く、教科による違いがみられた。 教師が生徒の家庭学習に行っている支援については、「紙の市販ドリルやプリント教材」「教科書」を利用した紙教材での支援が7割で多かった。ただし「アプリなどデジタルのドリル教材」など、生徒が家庭でパソコンやタブレット端末を利用して行う「デジタル教材」での支援も6割で、家庭学習の支援が多様化している様子もみられた。 またビデオ会議や資料共有、コミュニケーション機能などがある、授業と家庭学習で利用できる「学習支援ツール」は、84%の教師が利用していた。 GIGAスクール構想の実現で、教室のメディア環境は大きく変わった。家庭のメディア環境の差などの課題はあるが、授業と家庭学習を繋げられる「NHK for School」や「学習者用のデジタル教科書」などのメディア教材と「学習支援ツール」などを利用することで、生徒の学びをどう広げていけるのか、学校と家庭の両方を見渡した学習支援のトータルデザインを考える必要があると考えられる。
- 著者
- 中山 準之助
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.26-61, 2023-05-01 (Released:2023-05-19)
令和の中学生と高校生の生活実態、意識や価値観を捉えるため、2022年夏、NHK放送文化研究所は、全国の中高生などとその親を対象にした世論調査、第6回「中学生・高校生の生活と意識調査」を実施した。前回10年前の調査のあと、SNSの浸透、新型コロナウイルス感染症など、中高生を取り巻く環境は大きく変化してきた。2回にわたり掲載する調査報告の初回となる本稿では、「コロナ禍のストレスと、ネット社会を生きる中高生の人間関係など」について報告する。 「コロナ禍の悩みやストレス」 ▶コロナ禍のストレスは「自由に遊べない」「外出できない」など。女子が男子を上回る。 ▶今の悩みは「成績、受験」が中高ともに6割。女子で「外見」が3割と、男子より多い。 「中高生のネットの利用」 ▶中高ともに「SNS利用」9割超。 ▶投稿することがある人のうち、投稿の反応が少なくても『不安にはならない』が7割超。「不特定多数の人」に向けて投稿するは4人に1人。SNSへの抵抗感は薄く、ネットリテラシーは向上も。 「SNSでの人間関係の変化」 ▶「SNSだけのつきあいで、会ったことがない友だち」がいる人は高校生で4割。 ▶「深刻な悩みごとを相談できる友だち」が「いない」は中高とも2割ほど。 「不安や将来への期待」 ▶「自分の将来」に「自分の将来」に『期待あり』は中高ともに6割超。一方で、『不安あり』は中学生で7割台、高校生で8割台。 ▶「18歳から大人」として扱われることに高校生では「早い」が5割超で多い。
- 著者
- 小林 利行
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.2-25, 2023-05-01 (Released:2023-05-19)
NHK放送文化研究所が行った新型コロナに関する3回目の世論調査の結果について報告する。本稿では、感染が長期化する中で人々の意識や生活にどのような変化があったかを考察し、特に去年からの行動制限の緩和などの「ウィズコロナ」に向けた政策が、これまでコロナ禍のしわ寄せを受けていた女性や自営業者などにどのような影響を及ぼしたかに注目する。主な結果は以下の通りである。 感染拡大が『不安だ』という人は84%と多いが、時系列では年々減少している。外出回数は過去に比べて増え、特に「散歩や運動」「買い物」の回復が目立つ。一方で、ストレスを感じる人は少しずつ増加している。過去と同じように女性のほうがストレスを感じる人が多く、「ウィズコロナ」に向けた制限緩和による減少はほとんどみられない。ストレスの原因として「収入が減っていること」を挙げた人は、全体では19%だが自営業者では50%となっている。これは過去と同様の数字で、現時点では回復の兆しはうかがえない。 感染収束後でも、マスクを「前よりは多く着ける」と「できるだけ着ける」が合わせて約75%に上った。その理由の90%は「衛生上の理由」だが、「素顔をさらしたくないから」という人も7%いて、18~39歳では男女とも16%いた。コロナの法律上の扱いを引き下げることに『賛成』は約6割で、『反対』を上回った。賛成の理由は「重症化しづらくなっている」などで、反対の理由は「感染しやすくなるから」などだった。
- 著者
- 平田 明裕
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.12-23, 2023-03-01 (Released:2023-03-30)
本稿では、2021年に実施した「メディア利用の生活時間調査」のテレビ画面で動画を視聴する人(全体の6%)に焦点をあて、テレビ画面の利用実態や動画の視聴状況を分析し、今後、コネクテッドテレビが普及しテレビ画面の動画を視聴する人が広がると、テレビ画面の利用が変わるのかどうかについて考察する。テレビ画面での動画視聴者がテレビ画面で「動画」を視聴する時間量は1時間47分で、「リアルタイム」(1時間39分)と同じくらいであった。1日の推移をみてみると、朝の時間帯は「リアルタイム」が圧倒的に多い一方で、夜間の遅い時間にかけて「動画」が増えていくなど、テレビ画面での動画視聴者は時間帯によってテレビ画面で何を見るかを変えている様子がみられた。また、テレビ画面での動画視聴は、「ながら」視聴も「専念」視聴も同じくらいであった。動画を見ながらしている行動は「食事」「SNS(スマホ)」「身のまわりの用事」などで、リアルタイムと同じような「ながら」視聴が行われていて、これまでのリアルタイムテレビに近い見方で動画を視聴するようになっている様子もうかがえた。こうしたテレビ画面での動画視聴者の特徴であるテレビ画面の使い方は、今後、コネクテッドテレビが普及しテレビ画面での動画視聴者が増えていくと、広がっていくのではないかと考えられる。
- 著者
- 熊谷 百合子
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.34-61, 2023-02-01 (Released:2023-03-20)
ソーシャルメディアの台頭により情報発信・獲得の手段が多様化し、若い世代を中心にテレビ離れ、ニュース離れは深刻さを増しているが、背景には、必要な情報を必要とする人に届ける役割を果たせていないマスメディア自身の課題もあるのではないか。こうした問題意識から、コロナ禍に運用が開始された、仕事と育児を両立する親を対象とする支援制度の問題を伝えた報道が、どこまで当事者に伝わり、制度の利用につながったのかを検証するとともに、主に未就学児を育てる働く親のメディア接触の実態を可視化するインターネット調査を実施した。調査の結果からは、デイリーニュースを確認する手段としてテレビのニーズが確認された一方で、家事育児の多忙や、子にチャンネル権が優先されることなどを理由に、親自身がテレビニュースを見る機会が減少するケースが多いことが認められた。また、支援制度を知った経路として、テレビは一定程度貢献をしているものの、制度を利用する行動変容を促すまでの役割は果たせていない。必要な情報を必要とする人に届けるためには、報道手法そのものを見直す必要があると考えられる。
1 0 0 0 OA 和名に対する考え方
- 著者
- 千石 正一
- 出版者
- 日本爬虫両棲類学会
- 雑誌
- 爬虫両棲類学会報 (ISSN:13455826)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.1, pp.36-39, 2000-03-31 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 本邦爬虫両棲類和名考
- 著者
- 疋田 努
- 出版者
- 日本爬虫両棲類学会
- 雑誌
- 爬虫両棲類学会報 (ISSN:13455826)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.2, pp.99-111, 2000-10-10 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 日本産爬虫両生類の和名の変遷と現状
1 0 0 0 OA 神奈川県庁本庁舎のデザインに関する一考察 -フランク・ロイド・ライトへのオマージュ-
- 著者
- 佐藤 嘉明
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.718, pp.2915-2922, 2015 (Released:2015-12-25)
The Kanagawa Prefectural Office Building was designed by the local government official engineers and completed in 1928. And this design was based on the plan which Karo Obi got the first prize of design competition held in 1926. 1 So far, this building has been often mentioned as the first Imperial Crown Style (TEIKAN-YOSHIKI) which expresses Japanese nationalism. 2 By the comparative study between Obi's application plan to the competition and the great architect Frank Lloyd Wright's works, there exist several undeniable commons. 3 Karo Obi graduated architecture course of the Nagoya Technical College in 1921, and his graduate qualifying design obviously imitated one of Wright's masterpieces, the Midway Gardens in Chicago. 4 Owing to my study about design of the Kanagawa Prefectural Office Building, composition, shape of tower roof, statue of Buddha on the tower, decorative cantilevers, and other decorations, they show a strong influence of Frank Lloyd Wright's works, especially the Midway Gardens and the Imperial Hotel. 5 As a result, the Kanagawa Prefectural Office Building never stands for any ideologies such as nationalism, but simple homage architecture for Frank Lloyd Wright.