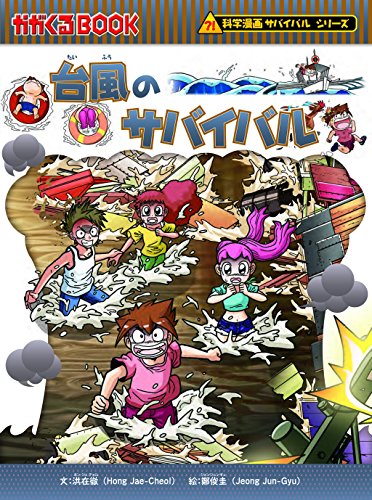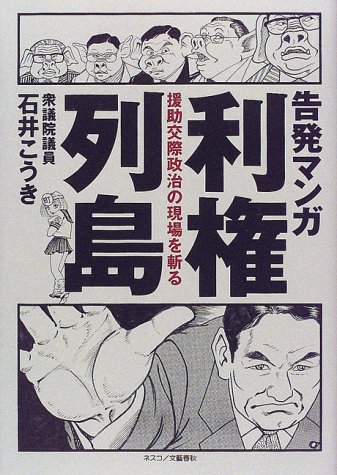1 0 0 0 OA Martin Schwind 先生の逝去を悼む
- 著者
- 矢澤 大二
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.295-296, 1992-04-01 (Released:2008-12-25)
1 0 0 0 OA 覚醒剤使用妊婦の管理について:国内文献のレビューによる検討
- 著者
- 赤澤 宗俊 橋本 和法
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.451-456, 2020 (Released:2020-12-10)
- 参考文献数
- 20
覚醒剤の乱用は一般の人々にも広がっており,本邦でも妊娠中に覚醒剤を使用した症例が複数報告されている.その周産期管理については,医学的のみならず社会的,法的にも対応に苦慮したとの報告が多い.今回われわれは医学中央雑誌を用いて文献レビューを行い,覚醒剤使用妊婦について国内13症例を集約し,管理上の問題点について検討した.患者背景では全症例が未受診妊婦であり,児は多くの症例で乳児院入所となっていた.母体の重篤な合併症として頭蓋内出血(脳幹)と,産後に甲状腺クリーゼ,心不全を来した症例を認めた.新生児経過としては,4症例で易刺激性,振戦,呼吸障害といった薬物離脱症候群の発症を認めた.法的な問題としては,①薬物の尿検査の施行に本人の了承が必要か,②警察への通報は医師の守秘義務違反になるのか,の2点が議論されていた.覚醒剤使用妊婦の管理は稀であるが,法的な問題も含有するため,治療指針の作成が望まれる.
- 著者
- Satoshi TSUZUKI
- 出版者
- Biomedical Research Press
- 雑誌
- Biomedical Research (ISSN:03886107)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.127-146, 2023-08-03 (Released:2023-08-05)
- 参考文献数
- 198
Fat (triglycerides) consumption is critical for the survival of animals, including humans. Being able to smell fat can be advantageous in judging food value. However, fat has poor volatility; thus, olfaction of fat seems impossible. What about fatty acids that comprise fat? Humans smell and discriminate medium-chain fatty acids. However, no conclusive evidence has been provided for the olfactory sense of long-chain fatty acids, including essential acids such as linoleic acid (LA). Instead, humans likely perceive the presence of essential fatty acids through the olfaction of volatile compounds generated by their oxidative breakdown (e.g., hexanal and γ-decalactone). For some people, such scents are pleasing, especially when they come from fruit. Nonetheless, it remains unclear whether the olfaction of these volatiles leads to the recognition of fat per se. Nowadays, people often smell LA-borne aldehydes such as E,E-2,4-decadienal that occur appreciably, for example, from edible oils during deep frying, and are pronely captivated by their characteristic “fatty” note, which can be considered a “pseudo-perception” of fat. However, our preference for such LA-borne aldehyde odors may be a potential cause behind the modern overdose of n-6 fatty acids. This review aims to provide a view of whether and, if any, how we olfactorily perceive dietary fats and raises future purposes related to human fat olfaction, such as investigating sub-olfactory systems for detecting long-chain fatty acids.
1 0 0 0 OA 私のブックマーク:第一言語獲得から考える人工知能
- 著者
- 折田 奈甫
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.282-286, 2023-03-01 (Released:2023-03-02)
1 0 0 0 台風のサバイバル : 生き残り作戦
1 0 0 0 OA ショウジョウバエの配偶行動にみられる意思決定制御の神経回路機構
- 著者
- 上川内 あづさ 石元 広志
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.10, pp.672-677, 2021-10-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 現代「棄民」研究 : (1)江戸三大飢饉と新自由主義的「選択と集中」
- 著者
- 景井 充
- 出版者
- 立命館大学産業社会学会
- 雑誌
- 立命館産業社会論集 (ISSN:02882205)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.1-20, 2022-03
1 0 0 0 OA 細胞製造性を鑑みたヒト細胞加工の特徴と工程による品質変動
- 著者
- 紀ノ岡 正博
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.369-376, 2021-11-25 (Released:2022-02-25)
- 参考文献数
- 6
ヒト細胞加工製品の製造は、製造所内外でのさまざまな工程(上工程、下工程、外工程)からなる。その際、種々の固有の特徴を有し、工程の変動つまりは品質の不安定性を導くため、細胞製造性を加味した設計を行うことが必要である。本稿では、ヒト細胞加工製品の製造工程および製品品質の特徴について述べる。さらに、細胞分注凍結工程における品質変動性について理解を深め、システムの変動要因を区別し解析することや、細胞製造固有の工程構築法を体系化することが重要であることを示す。
1 0 0 0 OA 誰が移民を送り出したのか : 環太平洋における日本人の国際移動・概観
- 著者
- 坂口 満宏
- 出版者
- 立命館大学国際言語文化研究所
- 雑誌
- 立命館言語文化研究 = 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.53-66, 2010-03
1 0 0 0 告発マンガ利権列島 : 援助交際政治の現場を斬る
- 著者
- 石井こうき原作・監修
- 出版者
- ネスコ
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 OA 100 kV級雷インパルス電圧による分圧器の国内持ち回り比較試験
- 著者
- 石井 勝 小山 博
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.1, pp.91-97, 1994-01-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 2
Intercomparison tests of dividers for lightning impulse measurement were carried out Japan participated by 12 laboratories. Two resistive dividers, one with 300 kV rating and the other with 1 MV rating, were circulated among the laboratories. The comparison test is one of the methods for checking the uncertainty of a high voltage measuring system, and is proposed in the course of the revision of an IEC standard to incorporate a new idea, that is, the traceability of the uncertainty in high voltage measuring systems. This paper reports on the determination of the scale factor, evaluation of the unit step response parameters and the comparison tests with lightning impulse voltages at about 100 kV. It is demonstrated that the participating 12 laboratories are all capable of realizing the idea in the revision of the IEC standard, that is, to establish traceability. On the other hand, a few problems to be solved in the testing procedures are found, to reduce the scatter in the measured parameters in these tests.
- 著者
- Laiba Salman Takayuki Ogata
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2023年大会
- 巻号頁・発行日
- 2023-03-24
1 0 0 0 Chunambei : revista mensual
1 0 0 0 OA 大腿直筋の筋活動パターン特性 ―遂行運動の違いが二関節筋の部位別筋活動に与える影響―
- 著者
- 園部 俊晴 勝木 秀治 堤 文生
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.7, pp.245-249, 2002-12-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 10
今回の研究の目的は,二関節筋の多関節運動におけるメカニズムを理解することである。特に,同一筋内の部位別の筋活動比の違いに着目した。二関節筋のうち大腿直筋を用いて,健常成人10名(男性6名,女性4名)を対象とし,4つの遂行運動(大腿直筋が協同的に働く①膝関節伸展,②股関節屈曲,また協同的作用と拮抗的作用を同時に果たす複合運動として③膝関節股関節同時屈曲,(④膝関節股関節同時伸展)での大腿直筋の筋活動を調べた。大腿直筋の近位部から最遠位部までの4部位の表面筋電図を筋電計を用いて測定し,遂行運動間及び,各部位における筋活動の割合を比較した。その結果,筋断面積が最大となる中間電極位置では,遂行運動間に筋活動比の差が認められなかった。また,遂行運動①②のように大腿直筋が協同的な役割のみを果たすとき,その筋活動は同一筋内の部位による変化をほとんど認めなかった。しかし,④膝関節股関節同時伸展では股関節に近い近位電極部では筋活動は小さくなり,膝関節に近い最遠位電極部では筋活動は大きくなった。同様に,③膝関節股関節同時屈曲でもそれとは逆の現象が起こっていた。筋が,隣接する関節の協同作用と拮抗作用を同時に果たすという二関節筋の場合,その同一筋内において相反神経支配に似たメカニズムが存在することが示唆された。
1 0 0 0 Dai Nippon : revista mensual
1 0 0 0 OA 画素型プリンタ
- 著者
- 渡辺 昭則
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.478, pp.969-975, 1974-11-05 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 超高齢者の薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)に対して外科的療法を行った4例
- 著者
- 田中 克弥 吉本 仁 閔 理泓 窪田 亮介 窪 寛仁 大西 祐一
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.21-29, 2023-03-25 (Released:2023-06-25)
- 参考文献数
- 20
高齢者社会が急速に進んでいる昨今,90歳以上の超高齢者への外科手術はまれでなくなってきた.今回われわれは超高齢者MRONJ患者に対し,全身麻酔下で外科的療法を施行した4例について検討を行った.4例の年齢は平均94.3歳で,骨粗鬆症の治療に対して3例はビスフォスフォネート製剤の内服,1例はデノスマブ製剤の皮下注射を行っていた.すべての症例で重大な術後合併症なども認められず術後の経過も良好であった.しかし,超高齢者の手術では全身状態や社会背景から手術の適応をより慎重に判断し,quality of lifeの改善を最優先した治療を選択する必要があり,慎重に検討が必要であると考えられた.
1 0 0 0 『ロランの歌』の電子校訂(C/V7写本)とデータベースの構築
中世の手書き写本は、様々な略号が使用される上、句読点もない。文字自体も現代のものとは異なる。そのため、たとえ活字で中世の言葉を読めたとしても、写本そのものを専門外の人間が読むことは極めて困難である。校訂作業とは、そうした手書き写本を印刷本の体裁に仕立て直す作業である。本研究の目的は、フランス最古の叙事詩、『ロランの歌』の、シャトルー写本、ヴェネツィア写本を校訂し、さらに、そのテキストをコンピュータで容易に扱えるようにするところにある。本研究の主な内容は、校訂作業と、その作業を容易にしたり、校訂テキストを扱うための電子ツールを作成するところに存する。
1 0 0 0 OA 日本のEEZ (排他的経済水域) ・大陸棚の深海底鉱物資源開発の可能性と必要性
- 著者
- 山崎 哲生
- 出版者
- The Mining and Materials Processing Institute of Japan
- 雑誌
- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.12, pp.829-835, 2008-12-25 (Released:2011-02-15)
- 参考文献数
- 31
Japan has a manganese nodule mining claim in the Clarion Clipperton Fracture Zones, the Kuroko-type massive seafloor sulfide deposits (SMS) and cobalt-rich manganese crusts (CMC) in Japan's exclusive economic zone (EEZ) and the continental shelves. Japan needs to use these deep-sea mineral resources as future strategic metal and rare earth element supply sources. Furthermore, the development technologies have wide variations in applying for the other food and energy supply targets in EEZ and continental shelves and the same-type resources of Pacific island nations'.Some current topics in deep-sea mineral resources development and the development technologies are introduced. Possibility and necessity of deep-sea mineral resources development for Japan are discussed.