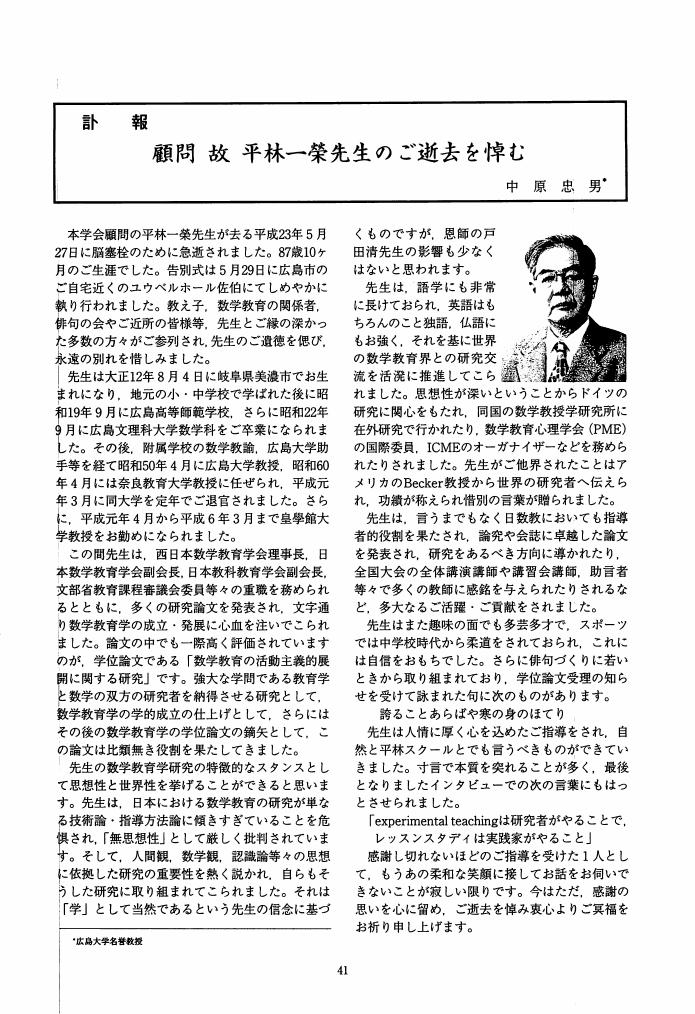1 0 0 0 均衡財政 : 附 占領下三年のおもいで
1 0 0 0 間接税等改正税法解説 : 酒税等ノ増徴等ニ関スル法律解説
1 0 0 0 OA 鉛蓄電池多機能型再生装置
- 著者
- 水本 巌 小熊 博 由井 四海 山本 桂一郎
- 出版者
- 科学・技術研究会
- 雑誌
- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.121-124, 2017 (Released:2018-01-06)
定電流間断充電と短パルス大放電電流を組み合わせて、多機能型劣化鉛蓄電池回復機を開発した。本機は、劣化鉛蓄電池回復機能、定電流・定電圧充電機能、定電流放電機能を備えた多機能型鉛蓄電池回復機である。本機をシリアルケーブルでパソコンに接続することによりインターネットを介して、電流電圧モニタ、遠隔制御、制御プログラムの変更が可能である。そのため蓄電設備に本機を組み込むと、現地に赴かなくても劣化鉛蓄電池の再生・放電試験が可能である。実際に通勤用軽四自動車で4年間使用したエンジン始動用鉛蓄電池について、CCA値および放電時間を同型の新品電池同様に再生した。再生する電池については、エンジン始動用であれば製造時から5年以内、ディープサイクル型の中古電池であれば8年以内の電池が望ましい。
1 0 0 0 OA 大庭みな子「三匹の蟹」 : ミニスカート文化の中の女と男
- 著者
- キムラ-スティーブン チグサ
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 巻号頁・発行日
- pp.1-50, 2005-03-31
会議名: 日文研フォーラム, 開催地: 国際交流基金 京都支部, 会期: 2001年12月11日, 主催者: 国際日本文化研究センター
1 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム障害の発症と新生児黄疸の関連性についての研究
1 0 0 0 OA 光合成を利用した太陽エネルギーの変換技術
- 著者
- 田中 和子
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.25-31, 1990-01-20 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 9
Photosystems of plants or photosynthetic microorganisms have a function to split water molecules to produce electrons. This paper describes a trial to draw photosynthetically generated electrons out from the microorganisms to produce electricity by using a electron transfer mediator. Such devices, which we call microbial fuel-cells, enable us to convert light energy to electricity directly. A microbial fuel-cell containing a marine alga and 2-hydroxy-1, 4-naphthoquinone as a mediator has been discussed and the conversion efficiency from light energy to electricity has been estimated from the comparison between output current and the amount of oxygen evolved.
1 0 0 0 OA 顧問 故 平林一榮先生のご逝去を悼む
- 著者
- 中原 忠男
- 出版者
- 公益社団法人 日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.9, pp.41, 2011 (Released:2021-04-01)
1 0 0 0 OA ロール軸周りに自由度を持つデルタ翼ウイングロックの 数値シミュレーション
- 著者
- 平野 正隆 宮路 幸二
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会論文集 (ISSN:13446460)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.611, pp.535-540, 2004 (Released:2005-02-25)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
A wing rock is known to be a self-excited rolling oscillation of a delta wing that is induced by unsteady aerodynamic forces. In this study, free-to-roll simulations are carried out by incorporating time-accurate computational fluid dynamics with an equation of motion of a wing. A limit cycle oscillation and the histogram of a hysteresis in the rolling moment, which has four peaks within one cycle, are successfully simulated. The strength of the leading-edge vortices at a fixed roll angle is rather different from that during the wing rock especially at large angular velocities and that causes the characteristics behavior of the unsteady moments.
1 0 0 0 OA 実習や演示実験にパワーポイントを加味した授業実践の一例
- 著者
- 和田 幸雄
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.57-63, 2014-03-27 (Released:2018-03-29)
1 0 0 0 OA 身体の構造化 : 身体運動への現象学的アプローチ
- 著者
- 滝沢 文雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.211-219, 1988-03-01 (Released:2017-09-27)
The present paper discusses, from a phenomenological viewpoint. how a movement learner structurizes his own human body, i.e., the body in phenomenological implications through his movement. The points of issue were as follows: 1. What is the structure of the body in the phenomenological context? 2. What does a learner structurize as his own human body? 3. How does a learner structurize it as his own human body? After the discussion, following results were obtained. 1. The human body exists as a function of learner's own body, so that it maintains a specific structure which is distinguished from the mere physical body. 2. A learner maintains bodily space and time according to his own capability of moving. He uses them as a framework of articulating and identifying his own percepts and structurizes these percepts centering on a specific movement. This means structurizing the human body. 3. Movement learning is a process of restructurizing one's own human body that is able to move and moving now, because a movement learner structurizes his movement constantly by revising his percepts that have already been identified. It means that the process of structurizing the human body has certain order. 4. A movement learner should know what he structurizes and how he structurizes his percepts as his own human body. Without knowing these, he can not learn his own human body effectively.
1 0 0 0 OA 難治性三叉神経痛に対する “nerve combing” による治療経験
- 著者
- 森 健太郎 佐々木 裕亮 酒井 淳 赤須 功 山川 功太 北川 亮 吉田 浩貴 沼澤 真一 伊藤 康信 渡邉 貞義
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.464-469, 2022 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 14
微小脳血管減圧術を施行したが再発, あるいは未治癒の突発性三叉神経痛でカルバマゼピン非耐性の5症例に対して, 再手術の際に三叉神経知覚枝のnerve combingを施行した. 全例術直後からカルバマゼピン内服なく疼痛発作が完全消失したが, 5例中4例 (80%) に三叉神経第3枝領域を中心とした顔面知覚障害が残存した. 術後1~5年の時点で再発を認めずQOLも良好である. 再発三叉神経痛で責任血管が明らかでなく, かつカルバマゼピン非耐性例に対してはnerve combing法は有効な治療法と思われる. なお, nerve combing法を予定する場合は術前に顔面知覚障害をきたす可能性が高いことを説明すべきである.
1 0 0 0 OA 「あの人はどんな気持ち?」 : 聾精神遅滞者のサインおよび書字による感情表現語の獲得
- 著者
- 望月 昭 野崎 和子 渡辺 浩志 八色 知津子
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-20, 1989-03-31 (Released:2017-06-28)
4名の精神遅滞を伴う成人聾者を対象として, 4種の「表情画」(「かなしい」「おこる」「うれしい」「ふつう」), 対応する「サイン」, および「文字」の3者間の等価関係の獲得訓練を条件性弁別課題を用いて試みた。対象者のうち, 2名は「サイン」-「表情画」, 「文字」-「表情画」の2種の条件性弁別課題における選択行動を強化した結果, 「サイン」-「文字」課題と表出課題については, 直接訓練することなしに獲得することができた。他の2名については, 「サイン」-「表情画」課題に引き続き行われた「文字」-「表情画」課題の獲得が困難であり, 「サイン」-「文字」課題について直接訓練したところ, 他の課題についても完成することができた。表出への転移は, 4名の対象者ともに書字あるいはサインのいずれかで, 弁別訓練中に使用した表情について行うことができたが, 新たな人物の表情写真あるいは生きた人物の表情に対する表出の般化は, 直後のテストでは4名中2名で認められた。また, 訓練の脈絡を離れた場面で4名中2名について獲得した語彙を表出したことが報告されたが, 場面に適した使用が認められたのは1名のみであった。
1 0 0 0 OA 最近の動向をふまえた飽和不飽和浸透数値計算法の検討
- 著者
- 大野 亮一 鈴木 雅一 太田 猛彦
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.3-10, 1998-11-15 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3
Prediction of ground water movement is very important and critical to forecasting slope failure because many slope failures are triggered by the surcharge of water weight and drop of suction when precipitation infiltrates into soils. It is necessary to consider both saturated and unsaturated flow phases, particularly for sequentially estimating ground water flow to specify the time and location of the failure.Richards' equation has strong nonlinearity of coefficients. As a result, its numerical analysis tends to be much more difficult than that under moderate conditions, especially with very dry soils or a perched water table. Recently, new methods to solve Richards' equation that focused on diminishing water balance errors and less limitation of time step size were presented (Celia 1990, Pan 1995). In this paper, those new methods are first introduced with explanation of their algorithms specified for balance errors or time step size. Second, based on the fact that both steady and unsteady phases are combined in Richards' equation, the consequent oscillation problem is demonstrated and examined. The algorithm of the oscillation is explained with the analytic method presented in this paper.
1 0 0 0 OA 運動による血清リン調節作用の解明とCKD-MBDの予防・治療への応用
慢性腎臓病は、日本人の1300万人が罹患していると推定されており、その対策が喫緊の課題である。慢性腎臓病では、腎機能が低下し、悪化すれば人工透析が必要となる。それに加え、心筋梗塞などの心血管疾患のリスクや骨粗鬆症、筋肉の萎縮による低栄養状態を招き、これらが重なると生命予後が悪化する。我々は、腎機能低下に伴い上昇する高リン血症が、これらの病態に共通した因子であることを見出してきた。これまでは、食事や薬剤で高リン血症の改善を試みてきたが、運動を行うことが、高リン血症の改善や骨粗鬆症、筋肉の萎縮などを改善するために効果的であると考え、その効果の検証と分子機序の解明に取り組む。
1 0 0 0 OA 情報倫理の可能性 : ネット依存における情報倫理の課題
- 著者
- 竹井 潔
- 雑誌
- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)
- 巻号頁・発行日
- vol.第32巻, no.第1号, pp.41-56, 2019-10-25
ネット依存はスマートフォンによるオンラインゲームやSNSにより,中高生を中心に増加している。またゲームのやりすぎによる様々な日常生活への支障をきたしたゲーム依存症はWHOにより疾患として認定された。ネット依存は若い層を中心に急増してきており,ネット依存を情報倫理の重要な課題として取り上げたい。AI社会になってAIへの依存が高くなってくると,ネット依存はさらに深刻になってくるであろう。AIの時代に入り,ネットの利便性だけではなく,ネット依存,さらにAI依存の倫理的側面を考慮していく必要がある。 本稿では,情報倫理の視点から,ネット社会の進展とネット依存について概観し,AI社会に向けてのネット依存における情報倫理の課題を検討することを試みる。