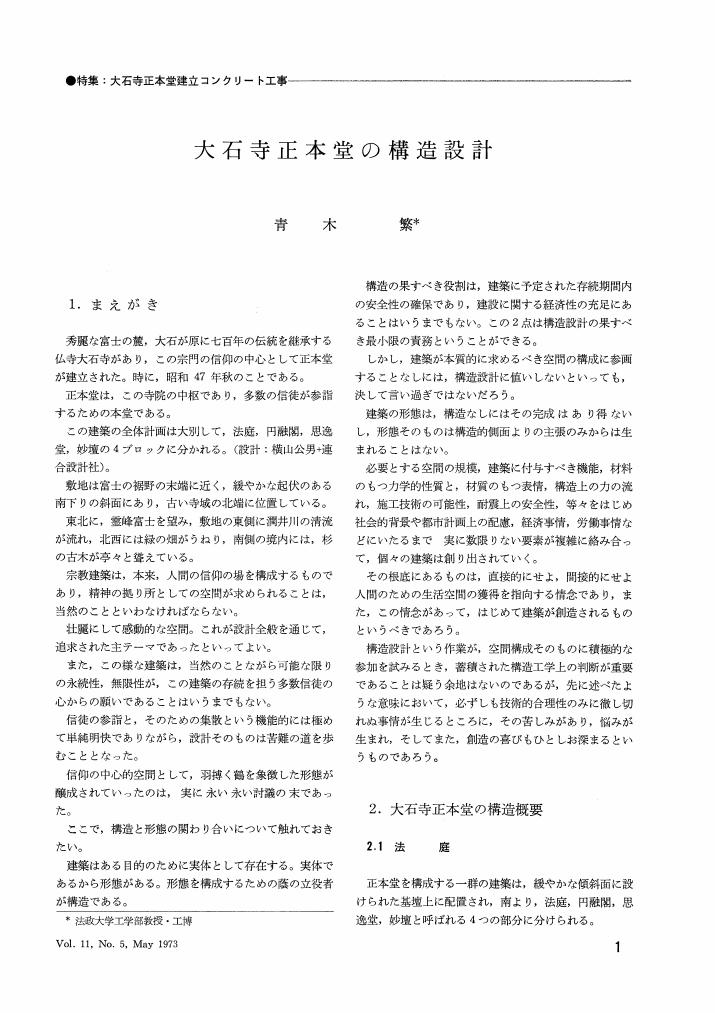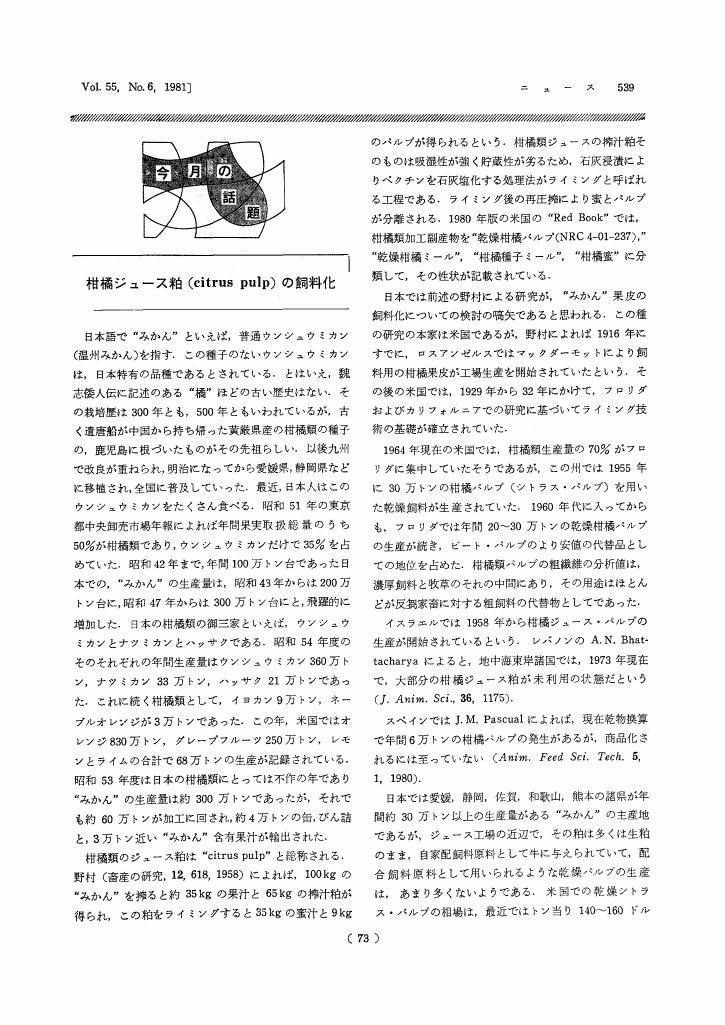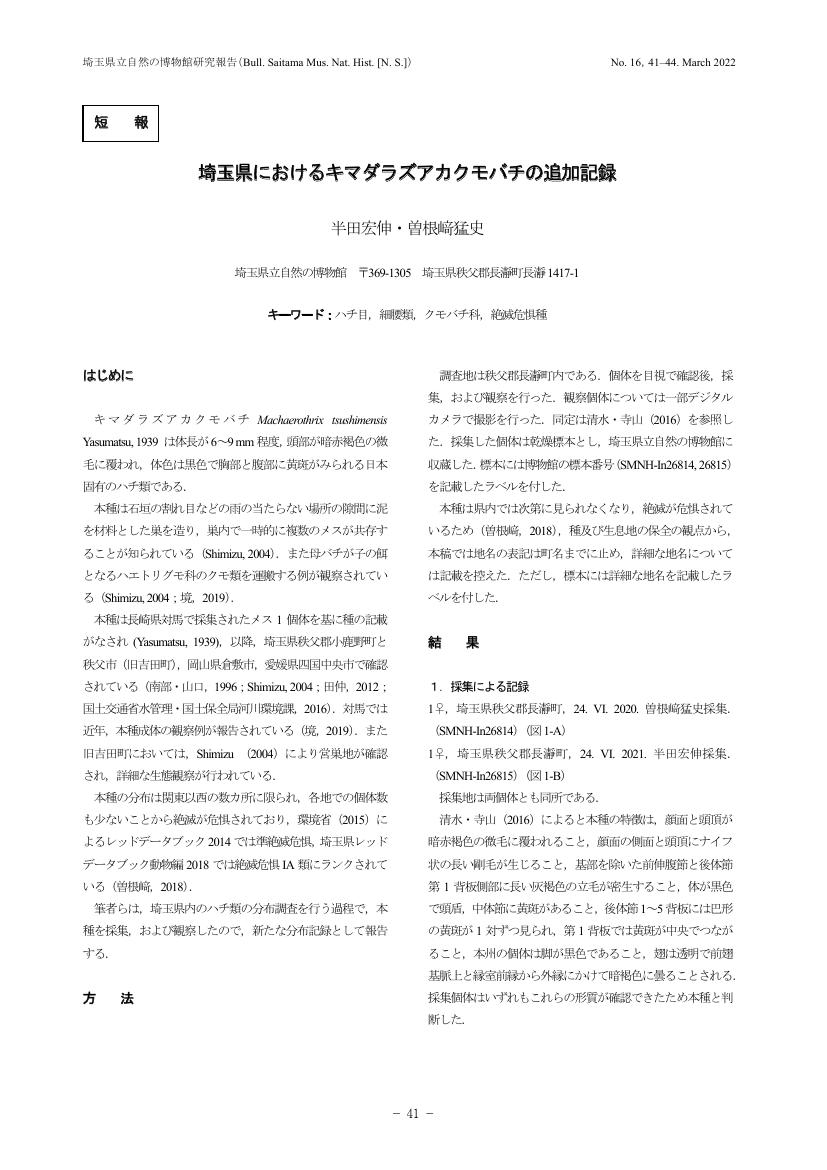- 著者
- 蓑輪 裕子 林 玉子 中 祐一郎 小滝 一正 大原 一興 佐藤 克志 狩野 徹 前川 佳史 堀端 克久
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.493, pp.109-115, 1997-03-30 (Released:2017-02-02)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4 4
The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of the house remodeling support system for the elderly. We administered questionnaires and conducted interviews with recipients of house remodeling grants in Edogawa-ku in Tokyo. The results are summarized as follows; for the elderly there are many difficulties of various types. It was found to be most expensive to remodel bath equipment. Regarding support system, we determined that the elderly need subsidy program, advice concerning methods of remodeling from specialists who have some knowledge about construction and the elderly, and a rental system for technical aid because some items are too expensive and are needed only short term.
1 0 0 0 OA 媒体技術
- 著者
- 川久保 伸
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.2, pp.79-83, 2005 (Released:2007-02-02)
本記事に「抄録」はありません。
- 著者
- 西村 洋平
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.164-167, 2010-03-24 (Released:2017-05-23)
1 0 0 0 OA 大石寺正本堂の構造設計
- 著者
- 青木 繁
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリートジャーナル (ISSN:00233544)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.5, pp.1-8, 1973-05-15 (Released:2013-04-26)
1 0 0 0 OA 解離性脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対して開頭術が有効と考えられた2例の検討
- 著者
- 土屋 亮輔 栗栖 宏多 後藤 秀輔 小林 理奈 小泉 博靖 櫻井 寿郎 小林 徹 竹林 誠治 瀧澤 克己
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.11, pp.796-803, 2021 (Released:2021-11-25)
- 参考文献数
- 19
解離性脳動脈瘤破裂に対し開頭術で治療した2症例を報告した. 症例1は血腫の局在と前大脳動脈 (A1部) のわずかな形態変化から, 同部の解離の破裂と診断した. 血腫除去, および直視下に穿通枝を温存した破裂点を含む母血管のtrappingを施行した. 症例2は右椎骨動脈解離の破裂で, 対側椎骨動脈はposterior inferior cerebellar artery (PICA) endであった. 破裂点を含んだ血管形成的なpartial clippingを行い, 椎骨動脈の血流温存を図った. 穿通枝や母血管の血流温存を図りながら急性期の再破裂予防を達成するという観点からの開頭手術の有効性が示唆された.
1 0 0 0 OA 小石川植物園草木圖説
- 著者
- 伊藤圭介, 賀來飛霞 編
- 出版者
- [書写者不明]
- 巻号頁・発行日
- vol.卷2, 1800
- 著者
- 坪田 博美
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 分類 (ISSN:13466852)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.15-27, 2008-02-20 (Released:2017-03-25)
- 参考文献数
- 81
- 被引用文献数
- 1
この総説は,日本植物分類学会奨励賞の受賞講演「コケ植物の分子系統学的研究の現状」(2007年3月16日,新潟大学)についてまとめたものである.受賞講演では,おもに私自身の研究の歴史と,予報的な内容ではあるが,現在のコケ植物の大きなレベルでの系統関係について触れた.また本稿では,時間の関係で講演の際に取り上げることのできなかったコケ植物の分子系統学的研究について,私がこれまで関わってきた研究を中心に,その概略を述べるとともに,コケ植物の分子系統学的研究の現状を紹介する.とくに,分子系統学的研究によって明らかになったことと,未だ明らかになっていないことを含めて紹介したい.
1 0 0 0 OA COPDにおける外来呼吸リハビリテーションの長期効果
- 著者
- 佐藤 一洋 本間 光信 伊藤 伸朗 高橋 仁美 菅原 慶勇 笠井 千景 土橋 真由美 清川 憲孝 敷中 葉月 澤田石 智子 加賀谷 斉 鹿島 正行 佐野 正明 伊藤 武史 佐竹 將宏 塩谷 隆信
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.242-248, 2000-12-31 (Released:2018-08-07)
- 参考文献数
- 31
COPD患者に外来呼吸リハビリテーションを施行しその長期効果を検討した.呼吸筋ストレッチ,呼吸筋訓練,上下肢の筋力訓練などを外来で指導し自宅で継続させ,2週間ごとに外来で経過観察と指導を行い,12ヵ月後まで経時的に呼吸機能,運動耐容能,健康関連QOLの評価を行った.その結果,COPD患者ではVC, RV, PImax, PEmax, 6MD, CRQが12ヵ月後までに有意に改善した.以上の成績からCOPDにおける外来呼吸リハビリテーションは呼吸機能,運動耐容能および健康関連QOLを長期に改善させる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 崇高論をめぐって : 弁証法から誇張法へ
- 著者
- 梅木 達郎
- 出版者
- 東北大学大学院国際文化研究科
- 雑誌
- 国際文化研究科論集 (ISSN:13410857)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.73-94, 1996-12-20
1 0 0 0 OA ベトナム経済の現段階:発展論と体制移行論からみた特徴
- 著者
- トラン・ヴァン トウ
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済研究 (ISSN:18805647)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1_15-1_30, 2012 (Released:2012-03-06)
- 参考文献数
- 17
本論文は,経済発展段階と制度変化との関係についての作業仮説の下でベトナムの経済発展と市場経済体制への移行過程を分析し,現段階の特徴を明らかにしたものである.漸進主義的移行戦略でベトナムは低位の中所得国へ発展できたが,社会主義経済システムの制度的基盤である一党制支配体制と国家的所有の維持は権力主導型経済体制を作り上げ,今後持続的発展のための高品質の制度の整備を妨げる可能性が高い.ベトナムはそのような「中所得国の罠」を回避し,持続的に発展していくために権力主導型経済体制を脱皮しなければならない.
- 著者
- 金野 健人 Samuel Chibwana 高田 雄一
- 出版者
- 保健医療学学会
- 雑誌
- 保健医療学雑誌 (ISSN:21850399)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.105-111, 2018-10-01 (Released:2018-10-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕マラウイ共和国の僻地に生活する脳性麻痺児に対する集中理学療法とCommunity Based Rehabilitation がもたらす効果について検討することを目的とした. 〔対象と方法〕脳性麻痺両麻痺GMFCS レベルⅢである5歳男児1 名を対象とした.運動機能評価にはGMFM−88 を使用し,減点項目である立位と歩行を中心に訓練プログラムを作成し,母親とコミュニティのボランティアが中心となって訓練を行った. 〔結果〕GMFM−88 の立位項目のみ変化を認めた.集中理学療法開始時と終了時では8%増加,2 ヶ月後には26%,合計34%増加した.また,CBR マトリックスについても改善を認めた. 〔結語〕2 週間の集中理学療法と家族・ボランティア指導を併用することで,運動機能の向上だけでなく,参加した家族・ボランティアが共同し理想的なCBR 介入を促した.
1 0 0 0 OA 甘橘ジュース粕(citrus pulp)の飼料化
- 著者
- N. Y.
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.539-541, 1981 (Released:2008-11-21)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 田所 摂寿
- 出版者
- 作新学院大学
- 雑誌
- 作大論集 = Sakushin Gakuin University Bulletin (ISSN:21857415)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.49-63, 2018-03-15
本論文の目的は「カウンセラー」という専門職のアイデンティティについて、歴史や定義を振り返ることによって再検討し、明確に構築することを試みたものである。本論文では、日米の歴史の変遷を概観し、それぞれの団体や論文が提示するカウンセリングの定義についてまとめた。その上で、日本におけるカウンセリング実践者およびカウンセラー教育者として、最重要であると考える6つの課題をまとめた。①カウンセラーのアイデンティティを明確に確立し、カウンセリングの定義を公に示し、理解を広める努力をしなければならない。②カウンセリングのそれぞれの専門分野を尊重し、カウンセラーとして統一見解に至った発言をしなければならない。③カウンセラー教育プログラムは、実証的データに基づく専門知識と専門技術を提供しなければならない。④カウンセリング専門団体は、最前線の実践家を団体の意思決定に組み入れ、研究と実践が乖離しないように努力しなければならない。⑤カウンセラーは、研究者-実践家モデルに忠実であり、個々人の状況に応じた形で研究に関わるように努めなければならない。⑥カウンセラーは、エビデンスに基づき倫理的な実践を行わなければならない。
- 著者
- Kazunori UTSUNOMIYA
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.Supplement, pp.S64-S66, 2022-11-30 (Released:2022-11-25)
- 参考文献数
- 11
The type 2 diabetes (T2DM) pandemic in Asian countries has become an urgent problem to be solved for each country from a socioeconomic viewpoint, because the expense for management of diabetic complications is rapidly increasing. This is due to Westernization of lifestyle in Asian countries, which results in a greater prevalence of visceral obesity. Thus far, it is believed that impaired insulin secretion from pancreatic islets mainly contributes to the pathogenesis of T2DM in Asians. However, insulin resistance clearly underlies the prevalence of T2DM in Asian countries, as well as Western countries. Lifestyle intervention, including exercise and diet is an essential approach in care for patients with T2DM. In particular, nutrition therapy is a fundamental treatment that aims to correct overweight and improve insulin resistance. The principal requirement of nutrition therapy consists of energy restriction and a well-balanced intake of various nutrients. The lifestyle of people in Asian countries has dramatically changed in recent decades due to economic growth, which has made it difficult to provide guidelines for nutrition therapy. The uniform setting of nutrition goals is difficult to achieve because of diversity in eating patterns. This symposium aims to promote optimal nutrition therapy for T2DM through comparing the guidelines of different countries, including Korea, Japan, and the United States. Interactive talks among speakers are expected to yield a new perspective in nutrition therapy for the management of T2DM.
1 0 0 0 OA STEM統合の立体的な構造に関する試論
- 著者
- 齊藤 智樹
- 出版者
- Japan Society for Science Education
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.15-20, 2022-12-03 (Released:2022-12-01)
- 参考文献数
- 24
This study aimed to depict the structure of integrative STEM education. Referring to literature from the period when discipline-based education was actively discussed, the paper argues the nature of the structure, its three-dimensional view, and the differences depending on the structures of teaching and learning. As a result, it is shown that there is a need to reconsider the boundary between Inter- and Trans-disciplinary STEM education and to redefine the classification.
- 著者
- 斎藤 千草 大坪 茂 治田 宗徳 池田 智慧美 川原 克恵 後藤 康司 成田 晃子 三和 奈穂子 久保田 孝雄
- 出版者
- 東都大学
- 雑誌
- 東都大学紀要 = Tohto University bulletin (ISSN:24358878)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.41-50, 2022-05
当院の透析患者COVID-19感染対策について報告する。従来の感染対策に加え、全職員、患者への疾患の啓発、マスク着用、来院時並びに透析室入室時に手指消毒、毎日検温、透析室入室時にも検温、昼食提供の見直し、感染が疑われる際の電話受けのチェックリスト作成、疑いエリアのリネン等の物品の扱い方の工夫、環境整備、休みやすい勤務体系作り、鼻咽頭ぬぐい検査場所の見直し等を行った。感染疑いの強い患者は導線を分け、裏口より入室し、普段使用していない時間帯のフロアーで隔離透析を行った。その結果、今まで患者150名、スタッフ35名中、血液透析患者1例の感染発生のみで経過している。また、他院より透析室内濃厚接触(疑い含む)13例、家庭内濃厚接触者1例、治療退院直後で維持透析先受け入れ困難3例の合計17例の患者を受け入れた。東京都の血液透析患者のCOVID-19罹患率2.1%に対し、当院の罹患率は0.7%と低値であり、当院の感染対策は効果があったと思われる。(著者抄録)
1 0 0 0 OA 県初記録18種を含む埼玉県におけるアリガタバチ類の記録
- 著者
- 半田 宏伸 辻井 健太郎
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 埼玉県立自然の博物館研究報告 (ISSN:18818528)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.69-76, 2022 (Released:2022-11-17)
本研究は膝前十字靭帯損傷受傷の危険因子を解明し,それを元に予防に有効なトレーニングプログラムを作成し,その効果を評価することを目的としています.本年度の目標は,本プロジェクトの最も基礎となる危険因子の解明のために,フィールドワークを行いスポーツ選手の身体的特徴,運動能力などのデータを採取することでした.昨年度に行った予備調査によって決定した調査項目1)全身関節弛緩性,2)膝関節前方安定性,3)Q角,4)関節位置覚,5)大腿四頭筋・ハムストリング等尺性筋力,6)バランス機能,7)全身反応時間,8)動的下肢アライメントについて高校生スポーツ選手を対象としてデータ採取を行いました.平成17年度男子106名,女子100名,平成18年度男子118名,女子77名,合計男子224名,女子177各につき調査項目のデータを採取しました.男女間による統計学的比較では,全身関節弛緩性,Q角,大腿四頭筋・ハムストリング等尺性筋力,動的膝関節アライメントで有意差を認め,膝前十字靱帯断裂の危険因子として男女間の発生率の相違に関連している可能性が示唆されました.特に動的下肢アライメントの分析では,女子で有意にknee-inとなることが明らかとなり,危険因子となりうる可能性が示唆されました.その後の追跡調査によって,平成19年4月の時点で男子1名,女子5名に前十字靭帯損傷の受傷が確認されました,しかしながら現時点では対象数が少なく,受傷者に特徴的な所見は得るには至っていません,更なる調査対象の拡大,追跡調査の延長が必要と考えられます.また,独自に予防トレーニングプログラムを作成し,膝関節キネマティクスに対する効果を三次元動作解析法を用いて検討しました.大学生バスケットボール選手を対象とした6週間のトレーニングでは,女子選手でジャンプ着地動作における膝外反の減少が認められ,予防につながる可能性が示唆されました.
1 0 0 0 OA 埼玉県におけるキマダラズアカクモバチの追加記録
- 著者
- 半田 宏伸 曽根﨑 猛史
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 埼玉県立自然の博物館研究報告 (ISSN:18818528)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.41-44, 2022 (Released:2022-11-17)
1 0 0 0 OA 埼玉県におけるシロズヒラタハバチの初記録
- 著者
- 半田 宏伸 真野 博 真野 樹子
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 埼玉県立自然の博物館研究報告 (ISSN:18818528)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.37-40, 2022 (Released:2022-11-17)