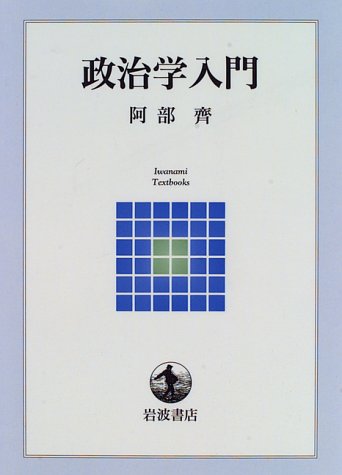1 0 0 0 OA 冷やしながら発電する「フロー熱電発電」の開発
- 著者
- 村上 陽一 池田 寛
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.12, pp.755-758, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)
- 参考文献数
- 27
世の中には冷却により取り除かなければならない熱が多く存在する.エンジンなどの熱機関,データセンターのCPU群,パワー半導体,バッテリなどの運転に伴い生じてしまう排熱がそれである.これらの熱には冷却の義務が伴う.従来の固体ベースの熱電変換は,発生場所から外に出たあとでまだ利用価値が残存している廃熱についてエネルギー回収を行う試みが大半であった.他方,積極除去の義務が伴う「発生場所から発生しつつある熱」については,その冷却と熱電発電を統合した技術は未開拓であった.筆者らは2015年より強制対流冷却と「液体側で行う熱電発電」とを統合する新技術を開発してきた.2019年には発電密度が0.5W/m2以下だったが,改良によって2021年には10W/m2と急増させている.本稿では本技術のコンセプトと成果の概要を紹介する.
1 0 0 0 OA 積層制御による2次元強誘電体の設計
- 著者
- 安田 憲司
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.12, pp.750-754, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)
- 参考文献数
- 29
分極の方向を電場によって制御可能な強誘電体は,情報の保持が可能な不揮発性メモリとして機能する.不揮発性メモリの微細化のうえでは,強誘電体の薄膜化が重要であるが,従来の強誘電体では薄膜化が困難であり,物質科学的にこの問題を解決する必要があった.この問題に対し我々は,ファンデルワールス積層構造と呼ばれる構造を作製することで人工的に2次元強誘電体を作り出した.もともと強誘電性を持たない層状ファンデルワールス化合物である窒化ホウ素に対して,積層構造を人工的に変えることで強誘電体へと変化させることに成功した.得られた強誘電体はナノメートル以下の厚さにもかかわらず室温まで安定であり,これを用いて我々は不揮発性強誘電体トランジスタを実現した.さらに我々は半導体遷移金属ダイカルコゲナイドを同様に強誘電体へと変換することで,本設計指針の汎用(はんよう)性を実証した.
- 著者
- Keisuke Kida Miho Nishitani-Yokoyama Yuji Kono Kentaro Kamiya Takuya Kishi Koichi Node Shigeru Makita Yutaka Kimura Shunichi Ishihara for the Japanese Association of Cardiac Rehabilitation (JACR) Public Relations Committee
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.10, pp.469-473, 2022-10-07 (Released:2022-10-07)
- 参考文献数
- 16
Background: We previously reported the results of a questionnaire survey of 37 cardiac rehabilitation (CR) training facilities conducted during April 2020, in Japan.Methods and Results: We conducted a second questionnaire survey in 38 CR training facilities to explore the preventive measures against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) after a nationwide state of emergency was declared and to investigate differences between the 2 surveys. No significant differences were observed, except for the requirement for patients to wear surgical masks during CR (P=0.01) in the second survey. Thirty-four facilities (89%) continued CR with innovations, 61% revised their instruction manuals (vs. 46% in the first survey), and, in 39%, patients requested resumption of ambulatory CR and training videos.Conclusions: In the second survey, 74% of facilities were unable to continue conventional group ambulatory CR; however, patients maintained their physical activity and exercise regimens and managed their illnesses with the aid of telephones and mobile devices.
1 0 0 0 OA 初心者が勘所を育てるにはどうすればよいか—大月(2016)へのリプライ—
- 著者
- 菊田 和代
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.349-351, 2016-09-30 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA キャリアコーチングにおける価値創造パターンの抽出
- 著者
- 浜田 百合 庄司 裕子
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.513-521, 2016 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 2
In recent years, coaching has been utilized in various fields. Much practical research on coaching has employed observable indicators, such as scores in sports, to demonstrate coaching effectiveness. However, career coaching does not have such observable indicators. The authors consider the client's generation of internal values to be an important factor in career coaching. Therefore, the purpose of this study was to analyze unobservable internal value creation in the career coaching process, and to clearly assess coaching effectiveness in this light. The results revealed two types of coaching pattern which elicited client value judgments: one which enhanced existing client values, and one which provided new variables. In addition, we found that the career coaching process had two phases, in which understanding and then consent are enhanced. The study suggested the importance of the coaching process in general, and of the generation of internal values therein.
1 0 0 0 OA 英語の多義語“spirit”の認知意味論的分析
- 著者
- 上原 星奈 清水 裕子
- 出版者
- 国立大学法人 香川大学医学部看護学科
- 雑誌
- 香川大学看護学雑誌 (ISSN:13498673)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.23-32, 2021-03-30 (Released:2021-04-03)
- 参考文献数
- 25
本研究は,認知意味論の理論的枠組みにおいて,記述的に英語の“spirit”という言葉のもつ内容や情報量を検討し,“spirit”の意味体系を明らかにすることを目的とする.研究方法は,3種類の中型英語辞典から英語の“spirit”の意味を抽出し,カテゴリー分類を行い,語義に定義づけを行った.また,皆島が作成した多義語放射状カテゴリーモデルの形態を引用して“spirit”の放射状カテゴリーのモデルを作成した.さらに,“spirit”の認知意味論的分析の結果と日本語の「霊性」との比較を試み,日本人が宗教性と混同しないためのカタカナのスピリチュアルというの語が示す内容や物事を検討した.結果と考察は,“spirit”が身体や物体とは区別される精神の部位を表す語義であることが明らかであった.さらに,言語の概念構造のメタファー(隠喩)による意味の派生には「霊」が分類され,メトニミー(換喩)による意味の派生には「熱」「アルコール」,「姿勢」「団結精神」,「真意」,「特質」,「超自然的存在」「秘密裏」が分類された.さらに「霊性」との意味を比較した結果,本来の性質として,肉眼的に捉えることのできない精神的実態であるという共通点はみられた.しかし,「霊性」は,“spirit”のメトニミー(換喩)による意味の派生にみられた「熱」「姿勢」「団結精神」「真意」などの語義は見いだせなかった.結論として,“spirit”の意味は多様に派生しているため,「霊性」と異なった意味があった.したがって,日本の看護分野で用いられているカタカナのスピリチュアリティ,あるいはスピリチュアルは,英語の“spirit”の意味を理解することにより,英語圏諸国の人々が理解するスピリチュアルケアを共通理解できるものと考えられた.
1 0 0 0 OA 「ブロードウッド社製ピアノ」修復報告
- 著者
- 平山照秋
- 出版者
- 大阪音楽大学
- 雑誌
- 音楽研究 : 大阪音楽大学音楽博物館年報 (ISSN:21867690)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, 2010-05
- 著者
- Hiroshi OTA
- 出版者
- Japanese Educational Research Association
- 雑誌
- Educational Studies in Japan (ISSN:18814832)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.91-105, 2018 (Released:2018-10-17)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 18 46
This paper discusses the meaning of the internationalization of higher education in Japan, based on a review of global trends in this area. Globalization has brought major changes to higher education, and in order to deal with them, the Japanese government has promoted internationalization as an important policy for higher education reform with a series of competitive funding programs. Universities in Japan, too, have made efforts to internationalize themselves. Despite the government's policy initiatives, the internationalization of Japanese higher education has not been understood as a high-priority issue at the institutional level, with many examples of superficial or partial add-ons of the international aspect, and has even been criticized as unable to contribute to transformative change at universities. Internationalization tends to be used as a means to prevail in the domestic competition between universities (inward-facing internationalization) and does not necessarily result in initiatives which lead to the improvement of learning in a globalized environment.All in all, the government's competitive funding projects for internationalization have indeed intensified domestic competition among universities. However, it is not certain that the funds have increased the international competitiveness and compatibility of Japanese higher education as a whole.
1 0 0 0 OA プレイヤー適応型健康促進のMotion Gaming AI
- 著者
- 草野 貴宏 中川 裕登 プージャナー パリヤワン 原田 智広 ラック ターウォンマット
- 雑誌
- 第79回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.1, pp.475-476, 2017-03-16
本論文では,Motion Gamingにおいて,プレイヤーの行動傾向に適応して健康促進するAIを提案する.身体全体の動作によってゲームの操作を行うMotion Gamingにおいて,プレイヤーはゲームを楽しみながら運動することができる.しかし,プレイヤーによっては,身体のある部位を使いすぎることで痛みを引き起こすなど,逆効果をもたらす可能性がある.そこで本論文では,AIの行動に対するプレイヤーの行動の傾向の分析を行う.AIの行動に対するプレイヤーの運動量を予測し,プレイヤーが身体の各部位を満遍なく用いるように行動するAIを提案する.対戦型格闘ゲームを用いた被験者実験により,提案手法の評価を行う.
1 0 0 0 OA 道成寺創建縁起と『道成寺縁起』
- 著者
- 大橋 直義
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.42-51, 2021 (Released:2022-06-22)
1 0 0 0 小原与一郎雑記抄 : 文久2年3~12月
- 著者
- 賀川 真理
- 雑誌
- 阪南論集.社会科学編
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.303-321, 2021-03
1 0 0 0 OA 下肢周径囲測定における個人内再現性と個人間再現性
- 著者
- 宮田 伸吾 寺田 茂 松井 伸公
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第24回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.O006, 2008 (Released:2008-12-09)
【目的】 下肢周径囲測定の目的には筋肥大や筋萎縮の評価、浮腫の評価などがある。特に、筋肥大による周径囲の変動幅は短期間では小さく、周径囲測定の高い再現性が必要不可欠である。しかし、予備的研究では同一部位の測定を指示した際にも検者によって3cm程度の誤差が発生してしまう場合があることが判明した。誤差を生む要因としては、測定部位の決定能力の違い、測定値を読み取るときの巻尺の締める強度の違い、下肢の長軸に対する巻尺を巻きつける角度の違い、被検者と検者の測定肢位の違いなどが考えられ、この中で特に大きく影響を及ぼすと考えられたのが、測定部位の決定能力である。本研究の目的は検者にあらかじめ測定部位の決定方法に関して個別指導し、方法を統一した条件下での下肢周径囲測定の個人内再現性と個人間再現性を検討することである。 【方法】 被験者は7名(男性3名、女性4名)で、平均年齢26.0±5.0歳、平均身長167.0±9.1cm、平均体重58.5±10.1kgであった。被験者には本研究の目的と方法について説明し、参加の同意を得た。検者は当院リハビリテーション科の理学療法士10名で、平均経験年数は7.8±6.5年(0年から22年)であった。測定部位の決定方法や、測定値を読み取る際の巻尺の締める強度、下肢の長軸に対する巻尺の角度、被検者と検者の測定肢位を事前に指導し、統一した。特に、大きく影響を及ぼすと考えた測定部位の決定方法については個別に実技指導した。検者全員が同一の巻尺を使用し、測定順序はランダムとした。測定肢は左下肢とし、測定肢位は仰臥位で左下腿を検者の左大腿に載せ、左膝関節伸展0度とした。測定部位は膝蓋骨上縁から近位に10cmと腓骨頭下縁から遠位に7cmの2箇所とした。1回目の測定から6日間の間隔をあけて2回目の測定を実施した。測定値より、級内相関係数(ICC)を算出し、個人内再現性と個人間再現性を検討した。 【結果】 個人内再現性において大腿周径囲でICCは0.83から0.99であり、標準誤差は0.54cmから0.64cmであった。下腿周径囲でICCは0.91から0.99であり、標準誤差は0.37cmから0.46cmであった。 個人間再現性において大腿周径囲で1回目ICCは0.92、2回目0.92で、標準誤差は1回目0.25cm、2回目0.27cmであった。下腿周径囲で1回目ICCは0.93、2回目0.93で、標準誤差は1回目0.18cm、2回目0.16cmであった。 【考察】 個人内再現性においては大腿周径囲測定時と下腿周径囲測定時ともにICCは0.8以上で、桑原らの基準では良好、個人間再現性において大腿周径囲測定時と下腿周径囲測定時ともにICCは0.9以上で、優秀という結果であった。今回のように測定部位の決定方法、特に膝蓋骨上縁や腓骨頭下縁の触診法を統一することで、高い再現性が得られ、臨床において信頼に足るデータを得られることが解かった。
1 0 0 0 OA 明治後期村役場文書の引き継ぎ 東京府北多摩郡砂川村と愛媛県東宇和郡魚成村との比較から
- 著者
- 冨善 一敏
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.52-69, 2014-05-31 (Released:2020-02-01)
本論文では、市制町村制下における村役場文書の引き継ぎについて検討し、東京府北多摩郡砂川村と、愛媛県東宇和郡魚成村の明治36年(1903)の引継目録の比較を行った。両者の共通点として、1)村長引継文書と収入役引継文書との区別が存在したこと、2)残存率は比較的高いが近世文書は少ないこと、相違点として、3)文書の保存年限制は砂川村では適用されなかったが、魚成村では適用されたこと、4)砂川村では引継目録の記載形式に村長交代が反映し、郡役所が強力な指導を行ったが、魚成村では郡役所の関与が少ないこと、5)砂川村では戸籍関係文書及び町村制施行以前の文書が引継目録に多数記載されているが、魚成村では少ないこと、の5点を指摘した。
1 0 0 0 OA 砂川村役場の組織分析と文書群構造 町村制下を中心に
- 著者
- 大石 三紗子
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.6-27, 2014-05-31 (Released:2020-02-01)
砂川村役場文書を作成した行政機関は、明治6年(1873)4月~番組(小区)会所、明治11年~戸長役場、明治22年~村役場、昭和29~38年(1954~63)に町役場と変化している。砂川町は、昭和38年5月1日に立川市と合併し、現在の東京都立川市が誕生した。本稿では、この砂川村役場文書の構造を、作成した組織の分析に基づいて考察し、町村制下の役場文書の特徴に言及する。現存する砂川村役場文書は、大半が町村制下の村役場で作成された文書である。町村制下の村役場は、村長などを含めて5~10人程の吏員が勤める程度であり、機構も分化されていない小規模な組織であった。このような組織で作成された文書を、事務内容によって分類すると、大半が郡役所とのやり取りによって発生した収受・発送文書であったことが判明した。この特徴は、町村制下の町村役場が、中央集権体制下における末端の機関として上意下達の文書を重視した結果である。
1 0 0 0 OA グローバルタレントマネジメントの国際比較による類型化とその新理論の構築
2016年度には、研究代表者と研究分担者によって、当該研究テーマ関連の研究論文・文献・資料を網羅的に収集すると同時に、それ以降の調査研究設計をおこなった。そして2016年度中に、研究協力者を募り、共同研究会を組織した。2017年度中に、調査・分析をおこない、二回にわたり共同研究会を開催し、報告・討議をおこなうことができた。そして2018年度には、本共同研究の最終研究報告を研究書の一つとして編集し、ミネルヴァ書房より守屋貴司・中村艶子・橋場俊展編著『価値創発(EVP)時代の人的資源管理 Indstry4.0の「働き方」「働かせ方」』と題して、2018年 10月に刊行することができた。
- 著者
- 林 玉子 中 祐一郎 小滝 一正 大原 一興 佐藤 克志 狩野 徹 蓑輪 裕子 安部 博雄
- 出版者
- 一般財団法人 住総研
- 雑誌
- 住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.229-240, 1994 (Released:2018-05-01)
我が国の住宅は高齢者にとっては支障が多く,在宅生活を円滑に過ごすには適切な住宅改善を行なう事が大切である。本研究の最終的な目的は,質の高い改善を行なうための総合的サポートシステムのあり方を示すことにある。具体的には主に,全額助成を実施し,先進的なサポートシステムである「江戸川区すこやか住まい制度」の実態と問題点を明らかにした。研究方法としては,同制度の利用者,役所,協力工務店へのアンケート及び訪問調査を行なったほか,それを補完するために全国の福祉機器ショップ・メーカーヘのアンケート調査,高齢者向け住宅改善の経験のある建築士へのヒアリングを行なった。調査結果の概要は以下の通りである。①改善のプロセス:本人・家族が直接関与した場合に改善後のイメージが捉えやすくなり,ひいては問題点の少ない改善に結びつく。支援制度が改善の促進に非常に役立っている。②改善に要する費用:改善費用は手すりの設置など小規模な場合でも平均約17万円と高額で,特に設備工事,木工事にかかる費用が大きい。助成する際には見積書の統一が課題となる。③改善の効果:1.住宅性能の変化,2.本人の日常生活動作・介護負担の変化,3.意欲・生活態度の変化,を軸として捉え,改善の有効性を明らかにしたが,さらに効果を測る軸についての検討が必要である。④改善の経年的変化:再改善を行なう率は高くその原因は,身体機能や意欲の変化,当初の改善の不備等であり,今後は不必要な再改善は少なくしていくことが必要である。さらに補足調査により重要なテーマである「福祉機器」に関する実態と問題点を把握した他,改善に関する専門的知識・情報のデータベース化に向けて具体的に構成要素と内容を整理した。住宅改善サポートシステムの構築は専門職種の適切な関与,改善に関する知識の一般化,費用の助成,福祉機器の給付等,多面的な対応が必要とされていることが明らかとなった。