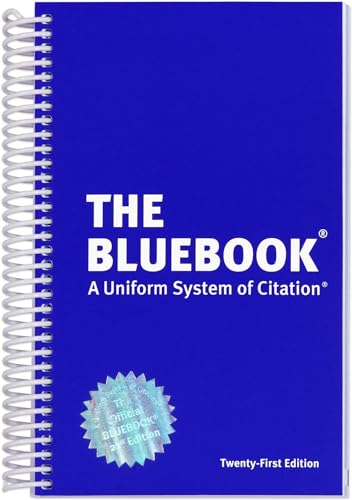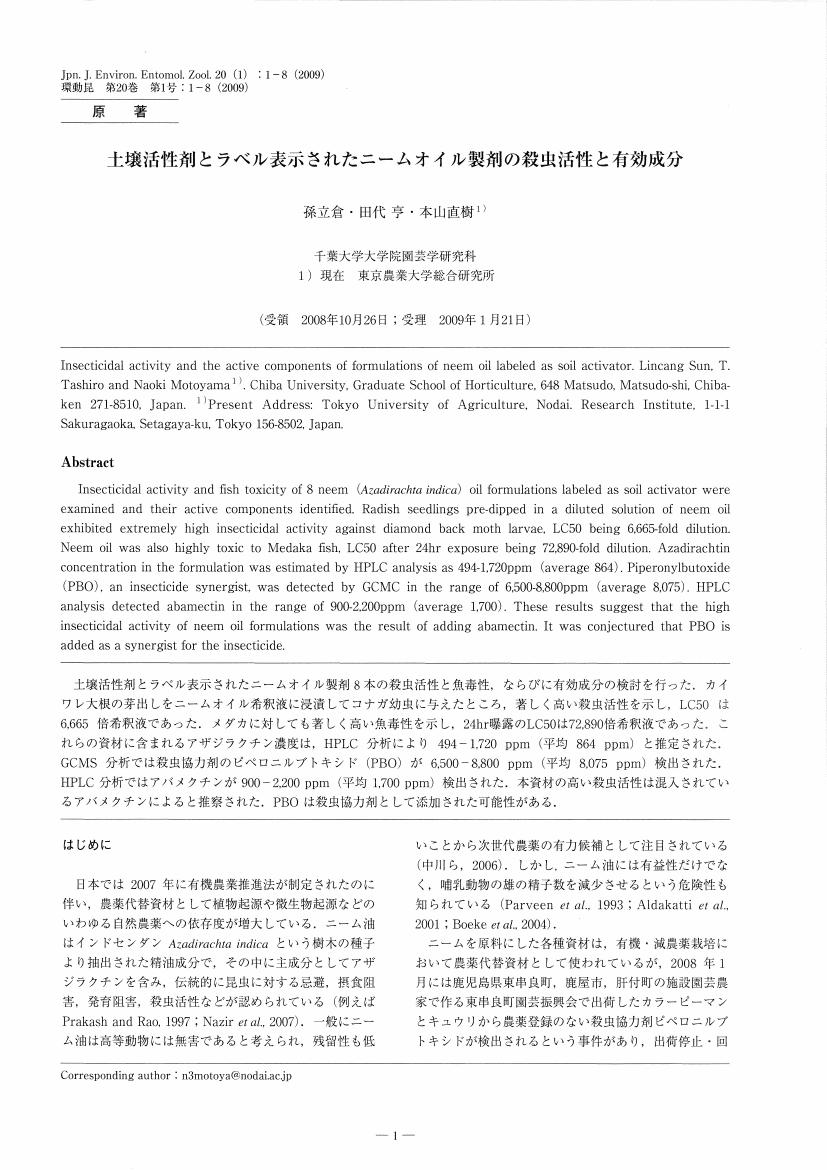- 著者
- Kazuko MATSUMOTO
- 出版者
- Faculty of Mathematics, Kyushu University
- 雑誌
- Kyushu Journal of Mathematics (ISSN:13406116)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.107-121, 2018 (Released:2018-06-27)
- 参考文献数
- 22
A. Takeuchi showed that the negative logarithm of the Fubini-Study boundary distance function of pseudoconvex domains in the complex projective space CPn, n ∈ N, is strictly plurisubharmonic and solved the Levi problem for CPn. His estimate from below of the Levi form is nowadays called the ‘Takeuchi's inequality.' In this paper, we give the ‘Takeuchi's equality,' i.e. an explicit representation of the Levi form of the negative logarithm of the Fubini-Study distance to complex submanifolds in CPn.
1 0 0 0 OA 甲斐国志
1 0 0 0 OA 職業作家・松本清張の出発 : 全集未収録小説「女に憑かれた男」、「渓流」を読む
- 著者
- 石川 巧
- 雑誌
- 大衆文化 = Popular culture
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.2-19, 2015-03-25
1 0 0 0 OA 産業看護職による地域保健との連携の実態と連携経験に関連する要因の検討
- 著者
- 三橋 祐子 荒木田 美香子 錦戸 典子
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-016-B, (Released:2022-11-03)
目的:地域・職域連携は,生涯を通じた効果的な健康づくりを推進するため,国としても推進している事業であるが,健康支援活動を展開する専門職を始めとした実践者レベルでの連携には至っていない現状がある.そこで,本研究は,産業看護職における地域保健との連携の実態と連携経験に関連する要因を明らかにし,産業看護職が地域・職域連携を推進していくための示唆を得ることを目的として実施した.対象と方法:(社)日本産業衛生学会の会員である産業看護職2,574名を対象とし,自記式質問紙調査を2017年に実施した.調査項目は,基本属性,連携の必要性の認識とその理由,連携経験の有無,および自己研鑽や学習経験等である.結果:分析対象者756名中,地域保健との連携経験者は34.0%,連携の必要性を感じている者は80.8%であった.また,連携経験の有無には,産業看護職としての通算経験年数,ガイドラインの閲読経験や地域保健主催の研修会や勉強会などへの参加経験,連携の必要性に関する認識が関連していた.考察と結論:地域保健との連携経験者は少なく必要性を認識していない者もいたことから,産業看護職が地域保健との連携事例に触れる機会が乏しく,その必要性を見出しにくい可能性が考えられた.本研究により,ライフイベントによる学びを補強し,産業看護職が地域保健に関する情報を得られる仕組みをつくること,連携経験者が連携未経験者へ具体的な連携事例を通して伝える機会を設けることで,産業看護職が地域保健との連携を推進していける可能性が示唆された.
- 著者
- 亀澤 美由紀 Harris Nigel
- 出版者
- 首都大学東京大学院 人文科学研究科 表象文化論分野 南大沢言語文化研究会
- 雑誌
- FORMES = フォルム
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.62-68, 2019-11-02
1 0 0 0 OA 「納得感」を与える意思決定支援システムについて
- 著者
- 山下 利之
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.44-51, 1995-02-15 (Released:2017-09-22)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 10 7
- 著者
- compiled by the editors of the Columbia Law Review ...
- 出版者
- Harvard Law Review Association
- 巻号頁・発行日
- 2020
- 出版者
- United States Government Printing Office
- 巻号頁・発行日
- 1926
1 0 0 0 OA 松果体胚細胞腫瘍患者の高次機能
1 0 0 0 OA ケースノート
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.401-416, 1985-08-15 (Released:2011-08-10)
1 0 0 0 OA 隨意性眼振の1例 種々の眼振 (その1)
- 著者
- 吉本 裕
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.57-60, 1973 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA Fecal Microbiota Transplantation Alleviated Cerebral Ischemia Reperfusion Injury in Obese Rats
- 著者
- Tao Xie Rui Yang Xianxian Zhang Xiaozhu Shen Liqiang Yu Juan Liao Tianhao Bao Qi Fang
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022.J094, (Released:2022-11-10)
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 大賀 圭子 杉田 誉子 関 顕洋 本多 輝行 川口 源太
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬剤疫学会
- 雑誌
- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)
- 巻号頁・発行日
- pp.26.e6, (Released:2021-07-31)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
医薬品の安全性監視活動は,すべての医薬品に対して実施する通常の医薬品安全性監視活動と,製品特異的な安全性検討事項に対して実施する追加の医薬品安全性監視活動からなる.通常の医薬品安全性監視活動の中においてシグナル管理は重要な部分であり,欧米では当局から規制およびガイダンス文書が発行されている.医薬品リスク管理計画の充実のため 2018年より活動を開始した日本医療研究開発機構(AMED)医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:RMP)研究班は,欧米のガイドラインおよび関連文献をレビューし,その考え方をまとめた.欧米のガイドラインにはシグナル管理の原則と手順に加えて,シグナル検出・評価の方法や実施において考慮すべき点,責任分担,当局内での活動結果の公表手順も記載されており,製薬企業を含めた公共に対する透明性が図られている.研究班では考え方をまとめるにあたって,まずは日本語のシグナル関連用語の定義一覧を作成した.また,これを基にシグナル検出からリスク特定に至る一連の活動を概念レベルで取りまとめるとともに,今後の日本のシグナル管理の在り方について考察した.
1 0 0 0 外務省の百年
- 著者
- 外務省百年史編纂委員会編
- 出版者
- 原書房
- 巻号頁・発行日
- 1969
- 著者
- Yukiko Shiraishi Yohei Kanzawa Naoto Ishimaru Saori Kinami
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.15, pp.2515-2516, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 土壌活性剤とラベル表示されたニームオイル製剤の殺虫活性と有効成分
- 著者
- 本山 直樹
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-8, 2009 (Released:2016-10-15)
1 0 0 0 OA 再生医学を巡る私の温故創新
- 著者
- 沖田 極
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.5, pp.537-543, 2005 (Released:2005-06-14)
- 参考文献数
- 23
臨床医である以上,死亡率の高い難病にチャレンジし有効な治療法を開発し救命率の改善に寄与したいという強い願望を持つのは当然である.私自身は若い劇症肝炎患者を救命できなかったことが,その後25年に及ぶ肝再生療法開発に走らせたといえる.2004年度DDW-Japanの際の第46回日本消化器病学会大会の会長講演で,その一端を“再生医学を巡る私の温故創新”というタイトルでお話する機会を与えられた.今回,日本消化器病学会誌編集委員会から総説としてまとめるようにとの指示であるが,若い消化器病研究者の参考となればと思い執筆することにした.
- 著者
- 井口 壽乃 森脇 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.3_81-3_88, 2022-01-31 (Released:2022-02-05)
- 参考文献数
- 28
本研究の目的は,名古屋市で 1989 年から 1997 年に全5回開催された国際ビエンナーレ「アーテック」(ARTEC)の歴史的意義を明らかにすることにある。アーテックが開催されたおよそ 10 年間は、インターネット社会の到来以前の高度情報社会を背景としたアートとデザインの転換期にあたる。この展覧会の意義は,いわゆる現代芸術の一つのジャンルとしての「メディアアート」の形成にとどまらず,1980 年代から国が主導する地域産業の高度化に寄与する特定事業構想に基づいて名古屋市が推進する「デザイン都市名古屋」の文化政策に貢献したことが指摘できる。 本稿では,第1にアーテックと同時に開催された世界デザイン博覧会および世界デザイン会議 ICSID と名古屋市の地域的課題の関連を考察する。第2に,アーテック企画者の森茂樹と山口勝弘に注目し,ハイテクノロジー・アート国際展からアーテック開催までの過程における彼らの役割を明らかにする。第3に,名古屋市の都市政策,および通産省の政策とハイテクノロジー・アートの関係を考察する。最後に,アーテックは国と地域経済,都市のイメージづくりと文化創造,そして芸術の国際化が複雑に関連した文化事業であったと結論づけた。
- 著者
- 白川 真裕 島田 貴仁 樋口 匡貴
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.93.21044, (Released:2022-11-10)
- 参考文献数
- 32
Based on the protection motivation theory and previous studies that discussed the effects of risk perception, perceived response effectiveness, and self-efficacy on behavioral intentions and changes in behavior, this study conducted an experiment to examine the effects of the Metropolitan Police Department's crime deterrence task force’s official Twitter account on crime prevention behavior. Information on the threat of communications fraud, the effectiveness of preventive behavior, and self-efficacy was presented via Twitter, and changes in behavioral intention, behavior, fear, effectiveness, and self-efficacy were checked over time. Participants in their 20s to 50s were assigned to a Metropolitan Police Department group presented with tweets about scams or to a control group presented with other tweets. The results of the analysis of the 60 participants in the police department group and the 49 participants in the control group showed that the presentation of information increased behavioral intention, but it did not necessarily lead to changes in behavior. Therefore, it was suggested that there may be other factors that increase behavioral intention and changes in behavior.