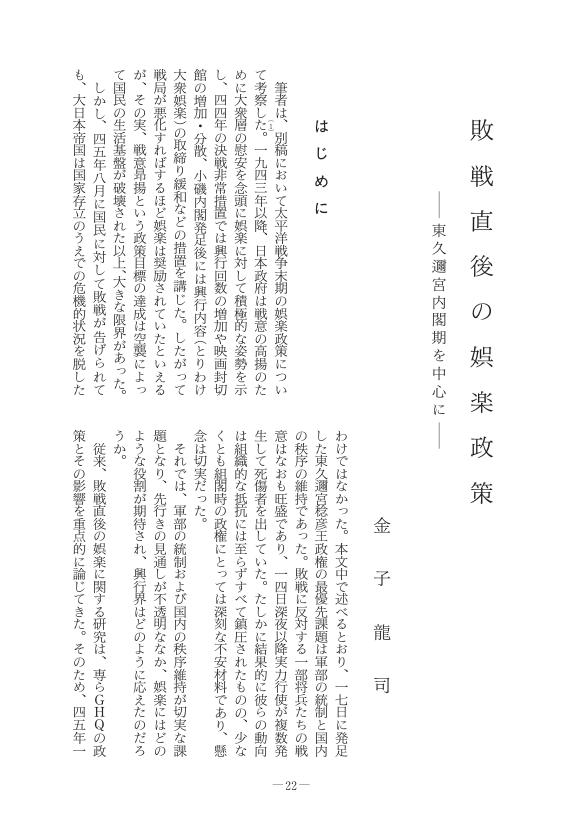1 0 0 0 ルータキャッシュを用いた優先度制御による超低遅延通信基盤
本研究では、コンピュータネットワークで用いられているルータのStore-and-Forward転送において輻輳時に起きるキュー遅延をなくすアーキテクチャ、制御を明らかにする。ルータにキャッシュをすることができる情報指向ネットワーク(ICN)を用い、輻輳時には、ルータのインターフェースからパケットをキャッシュに退避することで、常にキューにはパケットがたまらない状況にして遅延が起きないアーキテクチャを明らかにする。さらに、通信(コンテンツ)に優先度をつけ、キューの待ち時間が全くないコンテンツと、キャッシュにコンテンツ一時退避されるコンテンツの間で優先制御を行う仕組みを明らかにする。
1 0 0 0 OA スロヴェニア文学におけるウィーン像
- 著者
- 三田 順
- 出版者
- 学校法人 北里研究所 北里大学一般教育部
- 雑誌
- 北里大学一般教育紀要 (ISSN:13450166)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.85-102, 2016-03-31 (Released:2017-01-12)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
オーストリア文学史ではこれまでにもスロヴェニア文学におけるウィーン像が扱われてきた。マリーア・ヴェーラ・クラリツィーニは、浩瀚な著書『磁石としてのウィーン Wien als Magnet』(1996)でスロヴェニア作家イヴァン・ツァンカルとウィーンの関係を論じている。またシュテファン・ジモネク(2004)は、特にツァンカル作品におけるウィーンの公園の役割に焦点を当てた、より独創的な考察を行っている。スロヴェニアでこの問題に取り組んだ中心的研究者は当然ながらフランツェ・ベルニク(1998)である。これまでの研究ではツァンカルが主な考察対象となってきたが、本論はウィーンを描いた他の作家たちにも目を向け、スロヴェニア人のウィーン像に認められる幾つかの定数を示したい。
1 0 0 0 OA (書評)市大樹著『日本古代都鄙間交通の研究』
- 著者
- 渡辺 滋
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- vol.673, pp.66-73, 2018 (Released:2022-09-30)
1 0 0 0 OA (書評)市川裕士著『室町幕府の地方支配と地域権力』
- 著者
- 伊藤 大貴
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- vol.673, pp.73-79, 2018 (Released:2022-09-30)
1 0 0 0 OA (研究)敗戦直後の娯楽政策 東久邇宮内閣期を中心に
- 著者
- 金子 龍司
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- vol.673, pp.22-51, 2018 (Released:2022-09-30)
- 著者
- 尾谷 雅比古
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- vol.673, pp.52-65, 2018 (Released:2022-09-30)
1 0 0 0 OA (書評)冨善一敏著『近世村方文書の管理と筆耕―民間文書社会の担い手―』
- 著者
- 東 昇
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- vol.673, pp.80-86, 2018 (Released:2022-09-30)
1 0 0 0 OA 車載LiDAR向けSPAD ToF方式距離センサ
- 著者
- 田代 睦聡 伊東 恭佑
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.4, pp.220-223, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 10
シングルフォトンアバランシェダイオード(SPAD)は,フォトンカウンティングを実現するデバイスとして長年研究されてきた.最近,直接Time-of-Flight方式で自動運転および先進運転支援システムの実現に向けて,物体との距離測定,交差点の認識,路面状況把握などのためLiDAR(Light Detection And Ranging)センサ開発が数多く行われている.本稿では,90nm CMOS互換プロセスを使用し,金属埋め込み型のフルトレンチアイソレーションとCu-Cu接続を備えた,最先端の裏面照射型10µmピッチSPADアレイセンサについて報告する.7µmの厚さのシリコン層,SPAD内で同時に設計されたアバランシェ領域と光電変換領域,および専用プロセスにより905nmの波長で22%を超える高い光子検出率,および超低ダークカウントレートを実現した.本センサを用いた実証実験用SPAD LiDARシステムでは,117kluxの太陽光条件で200m先の95%反射率のターゲットを距離測定誤差0.1%で測距可能なことを実証した.
1 0 0 0 OA 協会だより/編集後記
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.408-410, 2022-10-01 (Released:2022-10-01)
1 0 0 0 OA 「第47回情報科学技術協会賞」を受賞して
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.405-407, 2022-10-01 (Released:2022-10-01)
1 0 0 0 オルタナティブデータを用いた経済活動分析
- 著者
- 水門 善之
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.390-396, 2022-10-01 (Released:2022-10-01)
昨今,経済分析において,従来の経済統計を補完する形で,様々なデータを活用する流れが進んでいる。これらはオルタナティブデータと呼ばれ,高頻度の売上データや物流データ,携帯電話のGPSデータやクレジットカードの決済データ,更にはインターネット上のテキストデータや経済活動を物理的に観測した画像等のような非構造化データまで多岐にわたるオルタナティブデータを使用するメリットは,その情報の豊富さに加え,速報性の高さも挙げられる。本稿では,日本経済を対象として,これまで著者らが行ってきた,製造業の生産活動や家計部門の消費行動に関する各種オルタナティブデータを用いた研究を紹介する。
1 0 0 0 わが国の公的統計調査から見た家計消費の十大費目の実態
- 著者
- 伊藤 伸介
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.383-389, 2022-10-01 (Released:2022-10-01)
本稿は,世帯の社会人口的属性だけでなく,家計の消費,所得,資産といった経済的属性の捕捉を指向した,わが国の代表的な公的統計調査である家計調査と全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)を例に,家計消費の十大費目の実態を明らかにしている。本稿では,第1に,近年における十大費目の変化の動向,さらには貯蓄現在高や年間収入との関連性を明らかにした。第2に,全国消費実態調査のミクロデータの特性を生かしつつ,世帯類型と配偶者の就業選択の違いが世帯の消費の構成に与える影響についての実証分析に関する成果について述べた。
1 0 0 0 特集:「統計データの活用」の編集にあたって
- 著者
- 海老澤 直美
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.369, 2022-10-01 (Released:2022-10-01)
2022年10月号の特集は,「統計データの活用」と題してお届けします。世の中の変化を知り,今後の展開を予測するためにまず参照すべきデータとして公的統計データがあり,国内においては総務省の「国勢調査」や同省と経済産業省がまとめる「経済センサス」がよく知られています。これらのデータは公的統計の「総合窓口e-Stat」等で検索できるようになっており,ビジネス,行政政策,研究等の様々な分野で役立つ情報です。データの偏りが比較的少なく,継続性もある重要な情報源です。その一方で,従来の公的統計データは集計・公表に時間がかかり即時性が必要とされる政策,例えば今起こっている新型コロナウイルス禍への対応等には適さないことが明らかとなっています。この即時性の観点から注目されているのがオルタナティブデータとも言われる民間データです。カード決済履歴やスマートフォン位置情報等のリアルタイムの民間ビッグデータが政策現場等に急速に普及しています。本特集では統計データを用いた調査・研究や,レファレンス事例等に触れ,統計データの種類やアクセス先等をご案内するとともに,公的統計データ,民間データ両者の長所・短所と,統計データのより良い活用方法等をご紹介いたします。まず山澤成康氏(跡見学園女子大学)から総論として,公的統計の概要とそれを活用するための統計学をご説明いただくと共に,新型コロナウイルス感染拡大以降,重要になっているオルタナティブデータ(民間データ)についてもご解説いただきました。つづいて倉家洋介氏(国立国会図書館)からは,公的統計のみではなく民間統計等の検索窓口としても活用できる,国立国会図書館が提供している「リサーチ・ナビ」を利用した統計データの調べ方をご解説いただきました。さらに公的統計データ,オルタナティブデータの活用事例と海外統計データの調べ方について3名の方々にご解説いただきました。伊藤伸介氏(中央大学)からは,公的統計データの利用方法やそれらを活用した調査研究の成果についてご解説いただきました。水門善之氏(野村證券株式会社)からは,オルタナティブデータを用いた経済活動分析についてご解説いただきました。最後に上野佳恵氏(有限会社インフォナビ)からは,海外統計データの効率的な調べ方についてご説明いただきました。本特集が情報やデータを扱うインフォプロの業務の参考になれば幸いです。(会誌編集担当委員:海老澤直美(主査),安達修介,今満亨崇,野村紀匡)
- 著者
- Keita YOKAWA Yuji MATSUMOTO Keina NAGAKITA Yoko SHINNO Kenichiro KUDO Nanami NIGUMA Kosaku SUENOBU Hideyuki YOSHIDA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.323-328, 2022-12-31 (Released:2022-09-23)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
Leptomeningeal metastasis (LM) is a rare but devastating cancer complication. LM occurs when cancer spreads into the leptomeningeal layer or cerebrospinal fluid. Intracranial magnetic resonance (MR) images of LM are characterized by the diffuse enhancement of the leptomeninges along the cerebral sulci, cerebellar folia, and cranial nerves. Here, we report an extremely rare case of LM with an atypical MR image revealing tumor mass confinement to the arachnoid membrane. The case involves an 85-year-old man who was referred to our hospital with a three-day history of dysarthria. Radiological examination revealed a solid lesion with heterogeneous enhancement and a cystic component in the extra-axial region of the right parietal lobe. Upon subsequent general examination, multiple lung cancer metastases were suspected. The patient underwent gross total resection of the brain mass in the right parietal region. Although the tumor slightly adhered to the dura mater, it was sharply demarcated from the surrounding parenchyma and pia mater. Based on pathological examination, the tumor was diagnosed as small cell lung cancer metastasis. This metastatic brain tumor was exclusively confined to the arachnoid membrane and, except for a few blood vessels, the dura mater was not infiltrated by metastatic tumor cells. To our knowledge, this is the first reported case of LM in which the tumor mass is confined only to the arachnoid membrane. Thus, in cases with atypical MR images, a general examination considering the possibility of LM is important for prompt and accurate diagnosis.
- 著者
- 森 雄兒
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育学会年会物理教育研究大会予稿集 22(2005) (ISSN:24330655)
- 巻号頁・発行日
- pp.30-33, 2005-08-06 (Released:2017-07-20)
ガスマントルを使うと手軽に陽電子源を作ることができる。さらにそれを用いて磁界を加えた霧箱で使うとリアルタイムで対生成を観察させることもできる。こうした陽電子の教材は生徒が興味を強く示す魅力的な教材である。また物理教育の立場からみても陽電子は質量とエネルギーや宇宙の創生の内容にに発展させていくことができる教材であるが、現状の物理教育では、残念ながらこうした教材を有効に扱えているとはとてもいえない。ここでは「物質の歴史」を中心にすえ、陽電子、対生成を生かした授業の展開例も紹介してみたい。
- 著者
- Mizuho Itoh Yasunaga Iwasaki Dong-Hyuk Ahn Tadahisa Higashide
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.UTD-381, (Released:2022-09-30)
- 被引用文献数
- 1
The relationship between fruit Brix and the electrical conductivity (EC) of the nutrient solution was investigated under gradually increasing EC conditions to predict and control tomato fruit Brix in commercial greenhouses in Japan. Based on the three experiments, fruit Brix was significantly and highly correlated with the cumulative EC of the drainage during the period from anthesis to harvest (cECd). This relationship followed a linear regression function. We then modelled fruit Brix based on cECd and validated this model to predict and control fruit Brix in four other experiments in different growing seasons using two cultivars, slab substrates, and irrigation systems. Using this model, we calculated the target cECd (cECdt) to achieve a target fruit Brix of 6% or higher and used cECdt as an indicator to manipulate the EC of the nutrient solution. In the validation experiments, cECd was lower than cECdt at the beginning of harvest in all experiments. cECd reached cECdt at 72.3–214.0°C·day after the first harvest. When cECd was higher than cECdt, more than 86.9% of the fruit had a higher than Brix 6%. In addition, the marketable yield was higher than 88.2%. RMSEs between the observed fruit Brix and predicted fruit Brix were 0.60–1.25. These results indicate that our model can predict and control fruit Brix.
- 著者
- Takuya Morimoto Yunosuke Matsuda Ryo Sekiguchi Akihiro Itai
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.UTD-383, (Released:2022-09-30)
- 被引用文献数
- 2
The development of intergeneric hybrids for horticultural crops has been attempted to introduce new quality and resistance traits and to enlarge the gene pool. Interspecific and intergeneric hybridization are often hindered by incompatibility reactions occurring at various stages of hybridization, from early pollination to initial growth, and the reproductive stages of the progeny. In this study, we investigated intergeneric and interspecific cross-compatibility among six species in the tribe Maleae (Rosaceae), namely, Pyrus communis (European pear), P. pyrifolia (Japanese pear), Malus × domestica (apple), Eriobotrya japonica (loquat), Cydonia oblonga (quince), and Pseudocydonia sinensis (Chinese quince). In vivo pollen tube growth tests showed the presence of a postmating, prezygotic barrier in many cross-combinations, in which cross-compatibility was regulated by both genetic distance and crossing direction. Strong hybridization barriers were observed in pollen tube growth and fruit setting when intergeneric hybridization was performed with E. japonica, a species phylogenetically distant from the others studied. Different compatibility reactions in reciprocal crosses were observed in some intergeneric hybridizations; C. oblonga as a pollen donor was incompatible with P. sinensis, whereas the reciprocal cross was compatible, resulting in the development of hybrid seedlings. Furthermore, the pollen tube growth rate differed among Pyrus species when pollinated on the apple pistils, suggesting divergence of cross-compatibility response in a specific linage. Factors affecting intergeneric hybridization are discussed with reference to the genetic distance between species and morphological characteristics such as pistil length. Our comprehensive assessment of intergeneric cross-compatibility will help provide a way to overcome crossing barriers and develop new hybrid crops in the tribe Maleae.
- 著者
- 鈴木 大助
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-CE-164, no.12, pp.1-4, 2022-03-05
コロナ禍下での対応のため,大学では妥当な評価が可能なオンライン試験の実現に向けて,様々な試みが行われている.筆者は,授業内小テストとして減点方式の正誤判定問題を利用したオンライン CBT 試験を行った.受講生数が多くても採点が容易であること,どのような科目にも応用可能であること,受講生個々人の理解度を測定できる試験であることを目指した.本試験は,制限時間 60 分,満点 40 点で,学習管理システムの小テスト機能を利用して実施した.問題は,減点方式の正誤判定問題 40 問からなり,全問解答必須である.受講生は,各設問の文章を読み,その文章が正しい場合は「正しい」,誤っている場合は「誤り」,自信が無いので解答したくない場合は「解答しない」をそれぞれ選択する.また,「誤り」を選択した場合は,対応する解答欄に正しくなるように修正した文章を記述する.修正した文章の記述が無い場合または修正した文章が誤っている場合は,誤答となる.採点は,正答数から誤答数を引いた数を得点とし,得点がマイナスとなる場合は 0 点とする.「解答しない」を選択した設問は正答数にも誤答数にも数えない.30 人が本試験を受験した結果,得点は 10~15 点の得点区間をピークとし,0 点から 33 点の範囲に広く分布する結果となった.また,「解答しない」選択数の分布からは,受講生が確実に得点するために「解答しない」という選択肢を戦略的に利用している様子がうかがえた.以上のことから,本試験は受講生の達成度を識別する能力を有しており,受講生個々人の理解度を測定できていると期待される.また,工夫は加えているものの基本的には正誤判定問題かつ CBT であるため,採点も比較的容易である.減点方式の正誤判定問題を利用したオンライン CBT 試験は,妥当な評価が可能かつ実践が容易な試験になりえると言える.