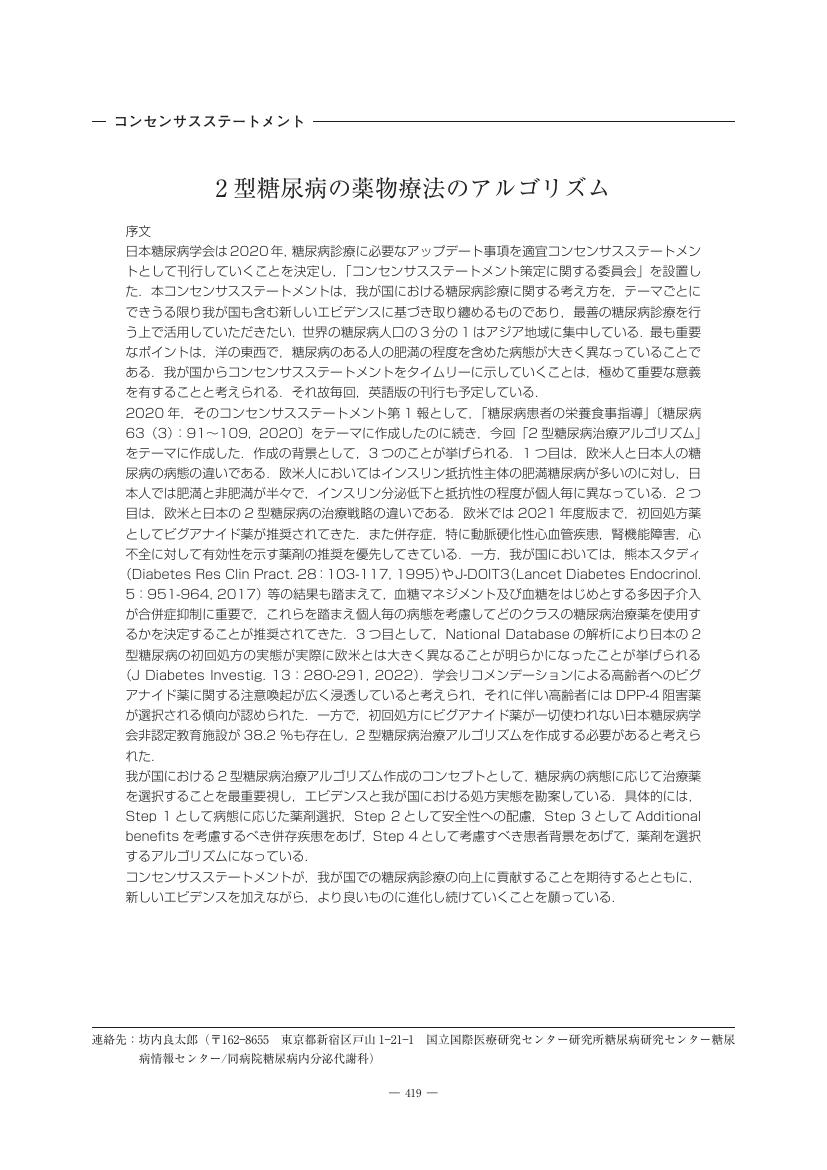1 0 0 0 OA X線CTを用いた内部構造の分析に基づく土偶製作技術の研究
- 著者
- 佐藤 信輔
- 出版者
- Tohoku University Museum
- 雑誌
- Bulletin of the Tohoku University Museum (ISSN:13462040)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.31-63, 2019-03
1 0 0 0 直線の感情 : 歌集
1 0 0 0 OA 初等算数教科書としての「塵劫記」
- 著者
- 川本 亨二
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.105-114, 1968-08-01 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 コトバ
- 著者
- 国語文化学会 [編]
- 出版者
- 国語文化学会
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, 1939-12
1 0 0 0 OA 鉄の道と鉄道 : 滑川鉱山と板谷峠の文化的景観
- 著者
- 粟野宏
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大学紀要(人文科学)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, 2008-02-15
1 0 0 0 OA グアバ果実のケチャップ加工への適性とその抗酸化評価
- 著者
- 広瀬 直人 前田 剛希 和田 浩二 高橋 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本食品保蔵科学会
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.143-148, 2013 (Released:2022-03-19)
- 参考文献数
- 24
To examine the possibility of using guava fruits as an ingredient in daily-use ketchup with food functionality, we prepared purees of eight pink guavas that were obtained from different areas in Okinawa and their chemical and physical compositions by measuring the Brix, pH, and color. The eight kinds of guava purees showed little difference in their compositions, Brix, pH, and color values. In addition, the purees maintained their color values after heating at 80℃ for 5 min. The guava puree was then treated with pectinase to decrease the puree viscosity. The viscosity of the puree treated with pectinase (0.24 Pa・s) was lower than that of the untreated puree (0.6 Pa・s). The guava ketchup was prepared using the untreated guava puree. In the sensory evaluation, the guava ketchup scored low for sourness because the citric acid content was lower than that in the commercial tomato ketchups. To evaluate the antioxidant activity, guava ketchups prepared using guava purees with and without pectinase treatment (GK-P and GK, respectively) were examined for total polyphenol contents and DPPH radical-scavenging activities. The total polyphenol content and DPPH radical-scavenging activities were higher in guava ketchups than in the commercial tomato ketchups. Interestingly, GK-P showed significantly higher radical-scavenging activity than GK. These results suggest that guava fruits have the potential to be used in the manufacturing of ketchup, which could serve as an antioxidant food.
1 0 0 0 OA 複製物に物理的加工を施して販売する行為に著作権は及ぶか(5・完)
- 著者
- 谷川 和幸 Tanikawa Kazuyuki
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学法学論叢 = Fukuoka University Review of Law (ISSN:04298411)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.461-485, 2020-12
1 0 0 0 OA 潮の理 : 通俗解説
- 著者
- 小倉伸吉 著
- 出版者
- 現代之科学社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1914
1 0 0 0 2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム
1 0 0 0 OA 楽曲探索を支援するための類似楽曲提示手法
- 著者
- 小林 恭輔 高久 雅生
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.287-293, 2022-05-28 (Released:2022-07-01)
- 参考文献数
- 11
本研究は効果的なブラウジング探索を通した楽曲の発見を促すことを目的としている. その手法として,楽曲間の関連関係を表現する類似楽曲の提示方法を提案する. これを実現するにあたり, Spotify のAPI が提供する楽曲データの一部を利用してユークリッド距離による類似度計算を行った. 探索の始点となる楽曲と上位の類似楽曲を取り出し, グラフレイアウトの力学モデルによるネットワークの可視化を行った.
1 0 0 0 OA 工場に於ける栄養調査(第2報)
1 0 0 0 OA 経皮経肝的に良性胆道狭窄を拡張しえた1例
- 著者
- 宮田 哲郎 松峯 敬夫 石田 孝雄 福留 厚 袖山 元秀 小山 広人
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.1087-1091, 1983-08-25 (Released:2009-02-10)
- 参考文献数
- 18
総胆管良性狭窄の治療は手術療法が中心となっているが,胆道系の手術と炎症をくり返している症例や,状態の悪い症例では手術的に狭窄を解除することはかなりの危険を伴なうことになる.我々は胆嚢摘出術後,総胆管狭窄をきたし化膿性胆管炎と総胆管結石とをくり返した症例に対し,減黄のためのPTCD瘻孔を拡張し胆道ファイバーで截石後,小児用挿管チューブでブジーを行ない狭窄部を拡張した.この方法は治療期間が長くなるという問題点があるが,手術療法に比較し侵襲が少なく安全であると思われる.
1 0 0 0 OA コミュニケーションの場の動的ゲーム論理
- 著者
- 石川 竜一郎
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.12, pp.429-438, 2019-12-15 (Released:2020-03-15)
- 参考文献数
- 24
This paper provides a game theoretical framework to analyze speech acts in rules-based communication places such as Parliamentary debates and Bibliobattle. The game consists of two stages:(1) the first stage of deliberation, and (2) the second stage of resolution. In the first stage, players discuss a common topic from various viewpoints, and in the second stage all the participants decide which opinion is plausible following a social choice rule as voting. The theory to examine the game involves dynamic epistemic logic (so-called dynamic game logic), and then enables us to focus on players' epistemic states through speech acts. Furthermore, it is connected to a part of mechanism design in the second stage, and secures players' incentives compatibility in social decisions. As a result, it captures how the rules work and what kind of speeches in speech places are derived through players' strategic thinking with rationality.
1 0 0 0 IR イタリア南部の民俗舞踊の構造と身体表現:ポッリーノのパストゥラーレを例に
- 著者
- 金光 真理子
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学教育人間科学部紀要. II, 人文科学 (ISSN:1344462X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.21-35, 2012-02
1 0 0 0 OA 新潟県の最深積雪について
- 著者
- 田村 伸夫
- 出版者
- Japan Society for Snow Engineering
- 雑誌
- 日本雪工学会誌 (ISSN:09133526)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.3-24, 1988-03-01 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 28
The purpose of this paper is to explain the distinctive features of the maximum snow depths in NIIGATA prefecture. The maximum snow depth data for the 'cold half' years from 1891 to 1987 were collected from the NIIGATA Local Meteorogical Observatory. The number of observatories keeping data is 60.Concluding remarks are as follows :(1) The deepest disturibution of maximum snow depth is determined by the difference in the height of the eastside or southside mountain chains. (Figs.1, 2, 3, 4)(2) The shallowest disturibution of maximum snow depth is closely proportional to the height of each observatory. (Figs.1, 5)(3) The heavy snow's patterns in NIIGATA prefecture are classified into two types : 1945 yr. and 1963yr. (Figs.6, 7, 8, 9)(4) The upper limit of maximum snow depth which is estimated relative to an observatoty's height is shown by the following formula. (The upper limit line is designated "N-Line", Fig.10)Hs=200 logH+75Hs : the upper limit of maximum snow depth (cm)H : the height of the observatory (m)However, the maximum snow depths of two observatories, TAKADA and TOCHIOMATA, were over the N-Line.(5) Taking into account the changes in the maximum snow depths after the latter term of the Meiji era, there seems to be two cycles of snowfalls : a cycle where there is a relatively little snowfall followed by a period of heavy snowfall and then repeating. (Fig.11)(6) In the UONUMA area which has a heavy snowfall for NIIGATA prefecture, there are cycles of mild winters from 5-8 years. All mild winters are not the same as in El Nino years, but there is a possibility that a big El Nino brings a mild to average winter (relatively mild snowfall) to the UONUMA area. (Fig. 12)
1 0 0 0 文学の中のアイヌ民族の表象ーその変容と他の先住民文学との比較ー
明治時代に日本の同化政策により民族存亡の危機に瀕したアイヌ民族を取り上げ、これまで文学の中にどのようにアイヌが描かれてきたのかを検証する。その際、アイヌ人の文学だけでなく、日本人が描いたアイヌの文学を含め、近・現代を通して文学におけるアイヌ像の変容を追い、「滅亡の民」から最近の「生のエネルギーに満ち自然と共に生きるたくましい民族」へのイメージ転換の契機と理由を、漫画、映像作品も含めて考察する。また、日本に隣接するロシアの文学の中のアイヌ表象や、米・豪の文学に著された先住民族との対立、反省、和解、共生への道程と日本の場合とを比較し、文学の立場から真の多民族共生への道を模索する。
1 0 0 0 OA 量子生物学の窓
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.9, pp.596-599, 1973-09-25 (Released:2009-05-25)
1 0 0 0 OA 在宅医療推進における訪問看護ステーション連携への取組に関する一考察
- 著者
- 櫟 直美 尾形 由起子 小野 順子 中村 美穂子 大場 美緒 吉田 麻美 猪狩 崇 平塚 淳子 田中 美樹 吉川 未桜 山下 清香
- 出版者
- 福岡県立大学看護学部
- 雑誌
- 福岡県立大学看護学研究紀要 (ISSN:13488104)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.13-23, 2022-03-31
「目的」本研究の目的はA県の3年間にわたる訪問看護ステーション連携強化の取組について意義と課題の整理を行い、今後の訪問看護ステーション連携について検討することを目的とした。「方法」A県の同意の得られたすべての訪問看護ステーション419か所に所属する訪問看護師3,750名を対象として無記名自記式質問紙調査を実施し、統計学的解析を行った。「結果」936名から回答を得た(有効回答率:25.0%)。交流会に参加して他のステーションと連携がしやすくなったのは37.1%だった。今後の必要性について、交流会を必要とする肯定群は936人中641人(68.5%)で、同行訪問研修を必要とする肯定群は936人中562人(60.0%)だった。しかし同行訪問研修の実際の参加率は16.8%にとどまり、参加の困難さがあった。医療介護福祉の連携意識は、年代と職位に有意な差があった。また交流会および同行訪問研修の必要性と連携意識に有意な差があった。在宅医との連携では、最も必要であると感じているが、連携の取りやすさでは困難さを感じていた。「考察」本研究結果では訪問看護ステーション間での連携の深まりを明らかにすることはできなかった。しかし交流会や同行訪問研修の必要性を感じている割合が高かったことから継続する意義はあると考えた。その意義として具体的には、連携上の課題が共有でき、医療的ケアの知識や技術が学べることや運営方法を知る機会となることである。また在宅医療推進のために在宅医との調整の積み重ねの必要性があり、コミュニケーションスキルを磨き、連携力を獲得していくための場への積極的参加の啓発と参加しやすい仕組みづくりが必要である。