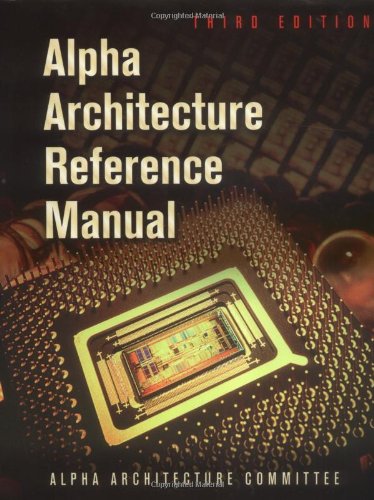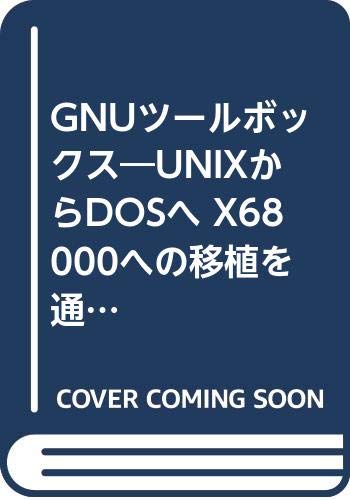- 著者
- 近藤 真里子 鈴江 妃佐子 河合 靖子 鈴木 陽子 大堀 裕子 市川 芳枝 牧野 トモエ 中村 あつ子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.117, 2008
〈緒言〉あつみの郷は老健を中心に、在宅サービスの他、介護予防サービス事業所などからなる福祉複合施設である。看護を中心とした各事業所代表からなる感染防止対策委員会では、感染症対策の基本である手洗いと感染症の基礎知識を中心に毎年勉強会を開催し、その効果として手洗いの意識調査と実態調査をしてきた。認識度と実施率は年々上昇し、勉強会の効果を実感していた。ところが、平成18年秋、あつみの郷の老健内で短期入所利用者から感染性胃腸炎の発症が始まり、関わった職員・利用者へと感染が拡大し、結果として利用者37名、職員10名が感染した。感染拡大の原因として、知識不足から職員が伝播者となり感染が拡大したことが大きな原因と考えられ、感染防止対策委員会の力不足を思い知らされた。終息後、職員にアンケート調査した結果をもとに、19年度の活動計画をたて、その結果感染症の発生をゼロにすることができたので報告する。<BR>〈方法と効果〉活動計画(1)感染症対応時フロー整備。今まで感染対応のフローが統一されていなかったので発症報告から、ケアまでの流れを整備した。これにより、各事業所間の感染情報も共有化されるようになった。(2)勉強会の実施。5月に標準予防策など感染症について、特に手洗い方法の手技についてビデオ学習を取りいれ、11月はノロウイルスの予防と発生時の対応および消毒方法を実技指導した。勉強会の内容と、新聞等の感染症発生情報等を常時掲示板を使って、継続して職員周知した。(3)手洗いの調査。職員が使用するゾーンの手洗い蛇口やドアノブの汚染度を大腸菌群とブドウ球菌群の拭き取り簡易調査を毎月実施し、検査結果を掲示した。検査を始めて3ケ月は、特に大腸菌群が多数検出され、汚染状況に大変驚いたが、2回の勉強会、毎月の検査結果の公表が効果あったか、徐々に菌の検出は減少した。職員が手洗いの必要性と、手洗い実施のタイミングを理解した結果と思われる。(4)外部からのウイルス侵入防止。外部からのウイルス侵入を遮断するため、利用者家族を始め、出入り業者へもノロウイルス感染予防のための協力依頼文書を10月に配布した。施設内においては発生に備え、仮に発生しても混乱したり、拡大しないように消毒マニュアルと消毒セットを各トイレに準備し、利用者および職員から疑いのある症状が発生した場合の対応も掲示した。(5)職員の感染症に関する習熟度調査。年間を通し職員の感染に関する知識変化を把握するため、基礎知識と各感染予防法ごとに理解度を点数化し、5月の勉強会前と一年間の活動後とで習熟度を調査した。介護・看護など職種別に統計学解析に基づきT検定を実施した結果、いずれの職種も習熟度は有意(p<0.05)に上昇し、これは活動による効果と思われる。<BR>以上の様に年間を通し活動を実施した結果、平成19年の利用者発症は0、家族内感染職員は2名あったが、施設内での感染は防止することができた。集団発生しなかった理由として感染疑い利用者への対応が早かったことが57.1%、次に予防と対策の知識が根付いたことが35.7%になった。実際に、突然の熱発者や嘔吐発症者にも迅速に感染症対応するなど職員の危機意識が認められた。<BR>〈結論〉一年間の感染防止活動により、アウトブレイクを防止することができた。これは職員の意識改革による影響が非常に大きい。今後も施設全体で感染に関する情報の共有化を図り、啓蒙活動を継続し職員の意識を高め、引き続き感染防止に努力して行きたい。<BR>
- 著者
- 満田 久義 Mulyanto Harahap H.S. Rizki M. Syahrizal B.M. Yudhanto D.
- 出版者
- 佛教大学社会学部
- 雑誌
- 社会学部論集 (ISSN:09189424)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.1-15, 2010-03
本稿は,2005年にマラリア・アウトブレイクの発生したインドネシア東ロンボク島で実施したマラリア血液検査データとマラリアに関する住民意識と行動の社会疫学調査(CBDESS,2006)のデータを解析し,マラリア・アウトブレイクの因果関係を実証的に明らかにしようとするものである。2005年の東ロンボク島アウトブレイクは,NTB州政府報告によると,1443名の罹患者と14名の死亡が公式確認され,その75.2%は熱帯熱マラリアであった。マラリア蔓延の発生源は,Korleko地区の石灰工場の労働者だと推測されている。同島では,マラリア・アウトブレイクはこれまでも頻発していたが,2005年の場合は,ほとんどコントロールが利かず,いくつかの地区では,医療体制の崩壊に襲われた。さらに,この石灰工場の多くの労働者は,地方からの出稼ぎ労働者であったために,マラリア発生源として帰郷し,このことが従来は全くのマラリアフリーだった山間僻地における新たなマラリア感染拡大の原因となった。本研究では,マラリア感染率(AMI)を被説明変数とし,98の社会学的変数を説明変数として用いて,マラリア感染拡大の地域間比較分析をする。その分析結果によると,マラリア感染は経済貧困と教育問題,とくにマラリア教育の不足が顕著な要因であることが分かった。マラリア対策に関連して,抗マラリア薬の耐性問題や媒介生物のハマダラ蚊駆除の困難性のほかに,マラリア教育に関する社会的解決の重要性についても議論を深めている。マラリア・アウトブレイクインドネシア・ロンボク島社会疫学調査
1 0 0 0 製品スタイルの選択と社会心理的評価
- 著者
- 小松 亜紀子
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.55-64, 2004
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 4
本研究では,携帯電話を題材とし,形態的要素の類型化によって得た異なる6つの製品スタイルについて,大学生を被験者とする選択と評価のアンケート調査を行った。分析の結果,因子分析により独立的要因である「訴求力(時代感覚,美的価値や高級感などの心理的に訴える力と関連)」「自分らしさ(自分の個性,性別や年齢と製品スタイルの適合)」,相互依存的要因である「相互依存性(周囲における製品スタイルの普及状況)」「普遍性(製品スタイルの定着や懐古と関連)」の4つの社会心理的な評価要因を抽出した。さらに,この評価要因を説明変数,製品スタイルの満足度を目的変数とする回帰分析により,「自分らしさ」と「訴求力」で有意な寄与が認められた。この結果から,製品スタイルに関する嗜好変化には,「自分らしさ」という社会的な理由だけでなく,「訴求力」という知覚的な理由が関与していると考えられ,従来の社会的な理由を中心とする流行や消費者の選択行動の説明に一考を迫るデータを得た。
- 著者
- 小倉 英郎 井上 和男 武市 知己 原 昭恵
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.265, 2014
はじめにインフルエンザの感染様式は飛沫感染、接触感染、空気感染が考えられるが、空気感染に関しては、インフルエンザの感染拡大防止対策において重要であるとする意見とそれを疑問視する意見が対立している。今回、われわれは当院重症心身障害病棟において空気感染の可能性を示唆する事例に遭遇したので報告する。事例2014年3月24日〜26日、重症心身障害病棟、1個病棟(41名)において、A型インフルエンザの病棟内流行を認めた。予防接種は40名に行われていた(接種率97.6%)。診断は迅速診断で行ったが、24日9名、25日12名、26日5名が発症し、27日には患者の流行は終息した(罹患率63.4%、うち2名でH1N12009が分離された)。職員では、25日4名、26日5名、27日1名が発症した。3月19日〜21日に個別支援計画の説明が家族になされており、この後の面会がインフルエンザの侵入に関与した可能性が否定できなかった。急激な発症パターンであることとアウトブレイク初日の患者配置図の検討から、空気感染の可能性を強く疑い、現場を検証した。その結果、おむつ交換時に換気スイッチを押すことにより、病棟入り口の天井から急速に吸気され、病室内から外部に排気されることが判明した。このため、病棟廊下から病室への気流が発生し、感染拡大の原因となった可能性が示唆された。この臨時の換気システムは病棟全体の換気システムとは別になっており、応急措置として、おむつ交換時の換気はしないこととした。なお、予防投与を含め、タミフル®が37名、リレンザ®が16名、ラピアクタ®が1名に投与され、流行は終息した。重篤な合併症を呈した例はなかった。考察当院の重症心身障害病棟は3個病棟であるが、他2個病棟では当該病棟のような気流の流れを生じる構造になっていなかった。重症心身障害病棟ではインフルエンザやノロウイルス感染症の流行はしばしば経験される。空気感染対策を考慮した病棟の設計が望まれる。
1 0 0 0 IR <総説> 麻酔薬と体温調節機構について
- 著者
- 松川 隆
- 出版者
- 山梨大学医学会
- 雑誌
- 山梨医科学雑誌 = 山梨医科学雑誌 (ISSN:13485091)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.13-20, 2007
周術期における体温管理の重要性は近年ますます高まっている。体温は中枢温と末梢温の2 つに分けられる。体温調節としては自律性の体温調節機構が重要である。それらにより発汗,末梢血管収縮,シバリング(ふるえ)などが調節されており,その中枢の本幹は視床下部(特に前方)とされている。麻酔中の体温変化は低下(すなわち負)することが多く,それによって,様々な副作用・合併症が生じることが近年明らかとなってきた。大きい副作用(心筋虚血の頻度増加,出血増加,感染増加)などは手術患者のQOL や医療費に多大な影響を与える可能性がある。体温調節,低体温発生のメカニズムを熟知し,適切な体温管理を行うことは臨床上極めて重要である。
1 0 0 0 OA 新型コロナウイルスに対する集団免疫を付与する経口ワクチンイネの開発
- 著者
- 川﨑 努 山口 公志
- 出版者
- 近畿大学
- 雑誌
- 令和2年度"オール近大"新型コロナウイルス感染症対策支援プロジェクト研究報告書
- 巻号頁・発行日
- pp.1-3,
カテゴリー:開発・改良
1 0 0 0 母子同室が新生児メチシリン耐性黄色ブドウ球菌院内感染に及ぼす影響
- 著者
- 井原 基公 三田尾 賢 小滝 照子 重光 昌信 木村 公重
- 出版者
- 日本環境感染学会
- 雑誌
- 環境感染 (ISSN:09183337)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.291-294, 2000-11-09
- 参考文献数
- 6
母子同室を行っていなかった母子異室期間と, 希望者に対し母子同室を行った母子同室期間での退院前新生児鼻腔からのブドウ球菌メチシリン感受性黄色ブドウ球菌 (以下MSSAと略), メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (以下MRSAと略), コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 (以下CNSと略) 検出率を比較し, 母子同室が新生児のMRSA院内感染に及ぼす影響について検討した.<BR>母子異室期間 (1567例) では黄色ブドウ球菌は5.8% (MSSA5.0%, MRSA0.8%) に検出された. これに対し母子同室期間 (927例) では黄色ブドウ球菌は5.8% (MSSA5.7%, MRSA0.1%) に検出され, 母子異室期間と母子同室期間において有意差を認めなかった. 母子同室期間で母子同室実施者 (555例) では黄色ブドウ球菌は7.6% (MSSA7.4%, MRSA0.2%) に検出された. これに対して母子異室実施者 (372例) では, 黄色ブドウ球菌は7.3% (MSSA7.3%, MRSA0.0%) に検出され, 母子同室実施者と母子異室実施者で差を認めなかった.<BR>この結果から, 母子同室がMRSAを含めた黄色ブドウ球菌による新生児院内感染増加の要因とはならないことが判明した.
1 0 0 0 IR 在日外国人の学習ニーズと生活状況に関する予備的考察
- 著者
- 今井 貴代子 Imai Kiyoko イマイ キヨコ
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系
- 雑誌
- 大阪大学教育学年報 (ISSN:13419595)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.77-88, 2007-03
1970年代以降日本に定住するようになった新来外国人の数は増加の一途をたどっている。彼らに対する日本語教育支援は推進されつつあるが、学習の機会が全ての人に十分に提供されているとは言えない。これまでのニーズ調査や生活実態調査では、学習の場に参加していない外国人の多さが指摘されるとともに、学習要糞の高さが明らかにされてきた。しかし、このような調査は量的な調査に限られることが多く、学習状況や学習ニーズが具体的な生活背景から検討されることは少ない。本稿では、公的な学習の場に参加していない中国人女性2人へのインタビューをもとに、具体的な生活状況から学習ニーズを検討する。インタビューから以下のことが示唆された。1)ことばの面で最も不自由しているのは職場でのやりとりである。しかし、職場では相互交流によるインフォーマルな日本語学習が行われている。2)学習状況や学習ニーズは、移住という社会プロセスの中で変化する。新たなコミュニティへ参加する段階において最もニーズが顕在化する。今後は、こうしたインフォーマルな学習に着目すると同時に、移民プロセスという観点から学習ニーズをとらえることが求められる。
1 0 0 0 IR 免疫(6)免疫学的治療法としての生物学的製剤
- 著者
- 田中 栄一
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 = Journal of Tokyo Women's Medical University (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.6, pp.187-201, 2015-12
関節リウマチ(Rheumatoid arthritis:RA)治療は生物学的製剤の出現に伴いこの10年間で大きく進歩した。生物学的製剤は遺伝子組み換え技術を応用して、特定の標的分子を特異的に認識する抗体や受容体を改変した医薬品である。RAの病態を増悪させているtumor necrosis factorやinterleukin-6などの特定のサイトカインや、リンパ球活性化に関連する分子と結合し、その作用を減弱または消失させる働きを有する。本邦では、2003年にインフリキシマブが発売されて以来、RAに対する生物学的製剤としてはバイオシミラーの1製剤を含めると現在8種類の製剤が承認され使用可能である。いずれの生物学的製剤もRA患者の臨床症状の改善、骨関節破壊の進行防止、身体機能の改善などの作用を有し、より"寛解"が現実的な治療目標として認識されるようになった。しかしながら一方で、生物学的製剤には、感染増加などの安全性の問題、使用すべき適応となる患者の選択、高額な薬剤費、必ずしも大多数の患者が十分な効果を得ているわけではないこと、使用しているうちに当初は認められていた効果が減弱してくる二次的な効果減弱、いつまで継続的な投与が必要なのか、生物学的製剤の中止は可能かなどいくつかの問題点も残されており、今後、これらの問題点が明らかにされることが望まれる。
1 0 0 0 IR 本邦における男性同性愛者のHIV感染増加に関する心理的問題と性教育の課題
- 著者
- 山下 菜穂子
- 出版者
- 了德寺大学
- 雑誌
- 了徳寺大学研究紀要 = The bulletin of Ryotokuji University (ISSN:18819796)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.97-115, 2017
本研究は本邦における男性同性愛者のHIV感染増加に関する心理的問題と性教育への課題を明らかとすることを研究目的とした.世界規模では日本のHIV感染者数,HIV新規感染者数ともごく少数である.しかし,その感染者数は男性同性愛者の性行為を中心に2000年~2011年にかけて増加傾向であるという問題を抱えている.同性愛者の精神健康度は異性愛者に比べ低い傾向であり,国内の男性同性愛者を対象とした研究では,同性愛者が精神健康度を良好に保つために教育機関における性教育の中で,同性愛についても肯定的な情報提供が必要だと報告している.しかし,教育機関での性教育は異性愛を前提として行われていることが現状であり,教育機関におけるその計画実施までに年月がかかるのは明白である.よって10代の男女に性教育を行っているNGOと男性同性愛者の地域ボランティア組織が連携し,セクシュアリティの考え方を見直す働きかけを行うこと,その活動内容を教育機関に発信し,同性愛者に対する問題とその対策をともに検討していくことが短期間で実現可能な方法である.
- 著者
- The Alpha Architecture Committee
- 出版者
- Digital Press
- 巻号頁・発行日
- 1998
- 著者
- 吉野智興 村上敬一郎共著
- 出版者
- ソフトバンク
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 X680x0 TEX
- 著者
- 吉野智興[ほか]共著
- 出版者
- ソフトバンク
- 巻号頁・発行日
- 1994
1 0 0 0 IR 再植林:安全かつ効率的な二酸化炭素の貯留の動態
- 著者
- Hosokawa Robert Tuyoshi Yamamoto Hiroyuki Rochadelli Robert KLOCK Umberto REICHER Fany BOCHICCHIO Renato
- 出版者
- 名古屋大学農学部附属演習林
- 雑誌
- 名古屋大学森林科学研究 (ISSN:13442457)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.9-18, 2002-12
The Brazilian Ministry of Science and Technology (MCT) / National Council for Science and Technological Development (CNPq) financed the research project "Identification and Quantification of the Main Chemical Components of Mimosa scabrella Benthan, related to Forest Management Parameters". One of the objectives of the study was to determine the dynamics and structure of carbon fixation in reforestation, quantitatively and qualitatively. It examined permanent carbon storage in living trees using conventional reforestation practices aimed at producing diverse traditional products. The carbon density decreased with the diameter class of the stands : the carbon density in non-dominant trees was 310 kg/㎥, while it was 280 kg/㎥ in dominant trees. The production function for carbon assimilation C (ton/ha) was given by the model : C=I^2/(0.154397-0.011314×I+0.026268×I^2),where I is stand age (years). This permitted calculation of the productive structure. For continuous production, in the optimized regime, the forest in 30 rural farms should be divided into four age classes, each with the same area of production (167.84 ha) ; this would maintain a permanent stock of 13, 131 tons of carbon in the living population of Mimosa scabrella.農林水産研究情報センターで作成したPDFファイルを使用している。
1 0 0 0 農村地域におけるHIV感染の拡大について 第2報:疫学状況
- 著者
- 西島 健 高山 義浩 小林 智子 小澤 幸子 岡田 邦彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.67, 2007
【緒言】第2報では、2002年より2006年までの5年間に佐久総合病院を受診した新規HIV感染者について、AIDS発症者数、国籍、医療保険の有無、初診時受診契機、感染経路、転帰により分析する。そこから対策すべき課題を検討し、とくに佐久総合病院が実施もしくは検討している外国人感染者を対象としたHIV対策を紹介する。<BR>【結果】2002年1月より2006年12月までに39人の新規HIV感染者の受診があり、24人(61.5%)のAIDS発症者の受診があった。その国籍の内訳は、日本人27人(69.2%)、タイ人12人(30.8%)であった。また、タイ人感染者のうち医療保険のない者が6人(15%)を占めていた。これら39人の初診時契機は、AIDS関連疾患の発症 61.5%、その他の疾患による受診 17.9%、パートナー陽性のために検査 12.8%、妊娠時検査 7.7%であり、自主的に検査を受けて陽性が判明したケースは1例もなかった。感染経路は、84.6%が異性間性的接触であり、大多数を占めた。以下、同性間性的接触による感染 7.7%、薬物使用 2.6%、不詳 5.1%と続いた。また、その転帰は当院通院中 71.8%、死亡 10.3%、帰国支援 7.7%、行方不明 5.1%、他院に紹介 5.1%であった。<BR>【考察】農村地域ではHIV感染の拡大が進んでおり、いわゆる「いきなりエイズ」症例が全国と比しても高く、早期発見がすすんでいない状況が継続している。その背景には、自主的に検査を受けて判明するケースが認められないことからも、一般市民への啓発活動の遅れが大きな要因と考えられる。日本人については様々な施策が展開されつつある。しかし、次いで外国人への感染拡大が確認されるものの、無資格滞在外国人であることが少なくないため、自治体行政によるアプローチが困難となっている。よって、医療機関と地域のNGO活動との連携による展開が求められている。無資格滞在外国人の感染が判明した場合に、単に帰国させる対応では単なる感染者のたらい回しにすぎず、国内でもHIV検査を受けるように促すことができない。よって、陽性判明後に彼らが医療面・社会面において安心して受診できるシステムを事前に策定しておく必要がある。<BR>【提言】この地域でエイズ治療拠点病院として活動してきた佐久総合病院は、自治体や保健所などと連携して様々なHIV対策を実施もしくは検討している。しかしながら、外国人向けの対策は途上であり、感染増加の状況からも緊急の課題と考えている。これまでも外国人向けの医療相談会を年に2回程度実施してきたが、本年度より在日タイ国領事館と協力して佐久総合病院内に移動領事館を開設。このとき併せて、佐久総合病院として医療相談会を実施する方針としている。こうして、タイ人らへの社会的・身体的問題へ包括的に対応できる体制を整え、外国人らとの信頼関係を深めてゆきたい。また、無保険の外国人においてHIV感染が判明した場合、何らかの方式による医療費助成制度を策定し、帰国支援まで安定した医療サービスを提供できるようにしたいと考えている。
1 0 0 0 化膿性膝関節炎の検討
- 著者
- 藤村 謙次郎 山下 彰久 白澤 建藏 城戸 秀彦 原田 岳 林 哲生 牛島 貴宏
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.27-31, 2009
【目的】当院で2000年以降に経験した化膿性膝関節炎を検討し,今後の治療方針決定に役立てる.【対象および方法】2000年から2008年2月までに当科で化膿性膝関節炎と診断されたのは21例21膝.うち合併症のために最終的に下肢切断術を余儀なくされた2例とACL術後感染1例,真菌性膝関節炎1例を除外して検討を加えた.平均年齢69.5(32~89)歳,男性8例,女性9例であった.手術方法は関節鏡下滑膜切除+持続灌流を基本とし,症例に応じて適宜変更した.【結果・考察】退院時のBallard評価基準はgood 2,fair 13,poor 1,死亡1であった.起炎菌の同定,早急な外科的治療および抗生剤投与が重要であり,また,MRSAは治療遷延化および変形性膝関節症(OA)の進行を招き機能予後を低下させる原因であった.さらに2006年以降の4例中3例はMRSA感染であり,近年のMRSA感染増加が示唆された.
- 著者
- 新井 賢一郎 仁木 久照 田中 達朗 平野 貴章 岡田 洋和 秋山 唯 別府 諸兄
- 雑誌
- 日本創外固定・骨延長学会雑誌 = The journal of the Japanese Association of External Fixation and Limb Lengthening (ISSN:13423495)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, 2010-01-13
1 0 0 0 IR 道命阿闍梨の伝記的考察
- 著者
- 田中 新一
- 出版者
- 愛知教育大学国語国文学研究室
- 雑誌
- 国語国文学報 (ISSN:03898350)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.p59-69, 1985-03