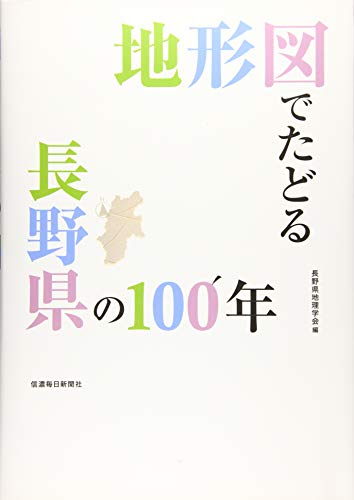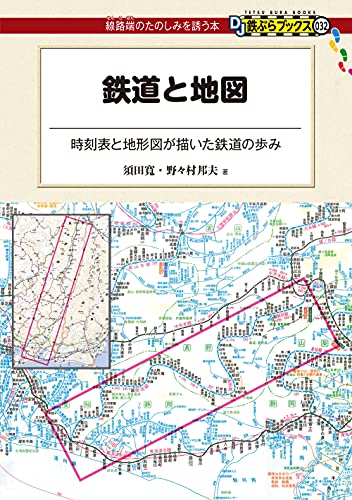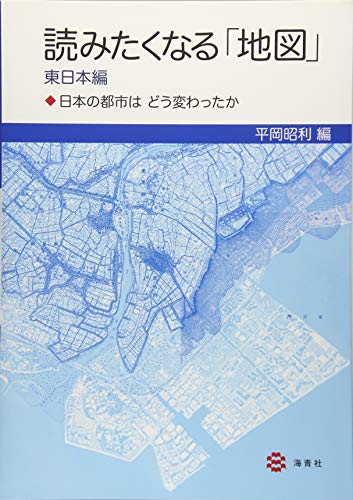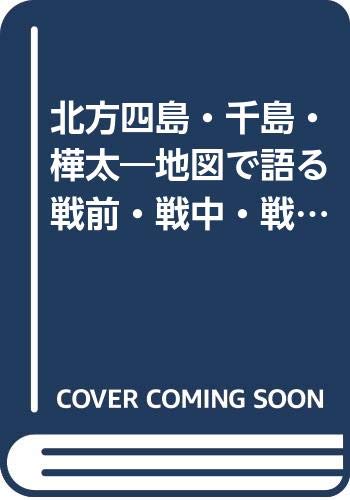1 0 0 0 駒澤大学マップアーカイブズの現状と新規受け入れ資料の概要について
- 著者
- 大槻 涼 村上 優香 小林 護
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, 2019
<p><b>概要</b></p><p></p><p> 駒澤大学マップアーカイブズは、駒澤大学が所蔵する地図資料の周知、保存、活用を目的として、2004年に始まった、学生主体のプロジェクトである。設立から10年以上経過した現在も、新規地図資料の収集と整理作業を継続している。学生が主体であることと、現在も整理作業が続いていることの2点は他に例のないプロジェクトである。これまでに成果として2冊の目録、『駒澤大学所蔵外邦図目録』(2011)と『駒澤大学所蔵外邦図目録 第2版』(2015)を刊行した。刊行以降も駒澤大学の学内から外邦図を含む新たな地図資料の受け入れを行い、整理作業と目録編纂作業を行なっている。次期地図目録編纂にあたり現状を報告する。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>外邦図とは</b></p><p></p><p> 明治期から第二次世界大戦終戦まで、旧日本陸軍参謀本部・陸地測量部が作成した、日本領土以外の地域の地図である。駒澤大学には、多田文男教授(1966〜1977)より寄贈された外邦図を中心としたコレクションが所蔵されている。『駒澤大学所蔵外邦図目録 第2版』時点で、収蔵されている地域は、樺太千島126枚、朝鮮1277枚、台湾97枚、中国3196枚、インド1293枚、東南アジア1641枚、オセアニア地域188枚、アメリカ国内111枚、ヨーロッパ34枚、海図947枚など、地域としては中国が多い傾向にある。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>新規受け入れ資料</b></p><p></p><p> 駒澤大学外邦図目録 第2版の刊行(2016年)以降、新たに図書館と駒澤大学地理学科から新しく地図資料を受け入れた。この中には前述の外邦図ばかりではなく、国内を対象地域とした旧版地形図や、海図、兵要地誌、航空図のほか、関東大震災発生時の消失地域図といった主題図、海外の旅行図も含まれる。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>新規受け入れ資料の概要</b></p><p>駒澤大学図書館から地理学科地図室へ移管:454枚(航空図7枚含む外邦図のほか、日本国内の主題図や中国の地質図などが含まれる。) 地理学科所蔵の旧版地形図:2234枚 駒澤大学外邦図目録に未収録資料:204枚</p><p>外邦図22枚</p><p></p><p>海外の領域の海図10枚</p><p></p><p>旧版地形図23枚</p><p></p><p>米軍作成都市計画図18枚</p><p></p><p>駒澤大学 地理学教室からの受け入れ資料</p><p></p><p>高木正博名誉教授から 79枚</p><p></p><p>橋詰直道教授から 401枚</p><p></p><p>(千葉県内の二万分の一正式図と全国の五万分の一の地形図など)</p><p></p><p></p><p></p><p><b>学生主体の地図整理作業の意義</b></p><p></p><p> 駒澤大学マップアーカイブズの活動の特徴として、学生主体であることが挙げられる。作業方針や資料の収集、日々の整理作業は、課外活動として学生自身の自主的な活動で行われている。確かに目録の完成だけを目指すのであれば業者やアルバイトに依頼する方が短時間で完了することが期待できる。しかし、学生が時間をかけ、一枚一枚地図を読み取ってリスト化する作業の過程では作製年代や目的、作製方法、用途も様々な地図を直接読み取る経験を得ることができると考えられる。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>駒澤大学マップアーカイブズの活動</b></p><p></p><p> 現在、学部生17名(1年生1名、2年生5名、3年生2名、4年生9名)、大学院生1名が週1回(90分)集まり整理作業を行なっている。未整理の地図資料については駒澤大学での整理番号(駒大番号)を付け、図幅名、縮尺、経緯度、製作者などを読み取りリスト化している。すでにリスト化が完了している地図は地域ごとやコレクションごとに分類し整理を続けている。また、受け入れた地図資料のうち、未整理のコレクションは地図ケースに納め管理している。</p><p></p><p> また、駒澤大学学園祭「オータムフェスティバル」や駒澤大学禅文化博物館での企画展示、地理学科の授業への資料提供を実施している。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>今後の展望</b></p><p> これまでの外邦図、海図ばかりではなく、多くの地図資料を盛り込んだ、第3版の目録編纂作業を実施している。また、作製されてから70年以上が経過した地図も多く、退色や劣化、破損が目立つ資料も多い。今後はこうした地図の修復や管理も行う予定である。</p>
1 0 0 0 主題図(土地条件図・湖沼図)の数値化について
- 著者
- 岡庭 直久
- 出版者
- 国土地理院地理調査部
- 雑誌
- 地理調査部技術ノート
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.40-51, 1998-01
- 著者
- 岩本 廣美
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.181-201, 2021
<p>本稿の目的は,第二次世界大戦後の日本の中学校地理教育における地域学習の展開状況を明らかにすることである。研究方法として,次の3点を検討した。①学習指導要領の記述,②単元「身近な地域」の教育実践に関する先行研究,③単元「身近な地域」に関するフィールドワークを取り入れた教育実践事例。その結果は次のとおりである。まず,1958年から2017年までの学習指導要領において,単元「身近な地域」は,名称や位置付けを変えながら,一貫して配置されてきたことがわかった。次に,先行研究から,近年の単元「身近な地域」の教育実践において,地形図は盛んに活用されていることがわかった。高等学校の入学試験でしばしば地形図に関する問題が出題されるからである。しかし,フィールドワークを取り入れた教育実践はきわめて少ない。多くの教師は,その理由に年間の授業時間の不足を挙げる。筆者は,多くの教師が,「身近な地域」で学習すべき問題を発見できないためであると推測する。3つ目に,フィールドワークを取り入れた単元「身近な地域」の教育実践事例には,水準の高いものがあることがわかった。多くの教師が実践しやすいフィールドワークの指導方法として,近年では,内容を精選し,50分以内に実施できるものが提案されている。その実現のためには,教員養成・研修の充実が必要である。</p>
1 0 0 0 反轉戰爭之眼:從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡
1 0 0 0 地形図でたどる長野県の100年
1 0 0 0 鉄道と地図 : 時刻表と地形図が描いた鉄道の歩み
- 著者
- 須田寛 野々村邦夫著
- 出版者
- 交通新聞社
- 巻号頁・発行日
- 2021
1 0 0 0 読みたくなる「地図」 : 日本の都市はどう変わったか
1 0 0 0 火山基本図及び湖沼図のインクジェット出力による刊行
- 著者
- 根本 正美 吉武 勝宏 岡本 勝浩
- 出版者
- 国土交通省国土地理院
- 雑誌
- 国土地理院時報 = Journal of the Geospatial Information Authority of Japan (ISSN:04309081)
- 巻号頁・発行日
- no.132, pp.119-128, 2019
- 著者
- 土屋 利雄
- 出版者
- CQ出版社
- 雑誌
- インターフェース = Interface (ISSN:03879569)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.89-95, 2014-03
1 0 0 0 地震防災のための仙台地区の造成宅地地盤図作成
- 著者
- 栗谷 将晴 佐藤 真吾 小倉 薫 向山 雅史
- 出版者
- 公益社団法人 地盤工学会
- 雑誌
- 地盤工学研究発表会 発表講演集
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.1893-1894, 2004
- 被引用文献数
- 1
1978年宮城県沖地震以降、丘陵地を造成した住宅地において、地震時に切土盛土の境界付近や盛土内で、住宅が被災する可能性が高いことが知られている。そこで、造成宅地の切盛分布を広範に調査することを目的として、国土地理院発行の2万5千分の1地形図と同旧版地形図の等高線を用いて10mメッシュのデジタル標高データを作成し、両者の差を計算することで、造成宅地の切土盛土分布を示す造成宅地地盤図を作成した。また誤差に対する検討を行った。本図は、地震防災計画の立案や住民への防災意識の高揚、住宅の耐震化等に活用することができる。
- 著者
- 久保 純子
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.81, pp.101-113, 1999-03
東京低地における歴史時代の地形や水域の変遷を,平野の微地形を手がかりとした面的アプローチにより復元するとともに,これらの環境変化と人類の活動とのかかわりを考察した。本研究では東京低地の微地形分布図を作成し,これをべースに,旧版地形図,歴史資料などから近世の人工改変(海岸部の干拓・埋立,河川の改変,湿地帯の開発など)がすすむ前の中世頃の地形を復元した。中世の東京低地は,東部に利根川デルタが広がる一方,中部には奥東京湾の名残が残り,おそらく広大な干潟をともなっていたのであろう。さらに,歴史・考古資料を利用して古代の海岸線の位置を推定した結果,古代の海岸線については,東部では「万葉集」に詠われた「真間の浦」ラグーンや市川砂州,西部は浅草砂州付近に推定されるが,中央部では微地形や遺跡の分布が貧弱なため,中世よりさらに内陸まで海が入っていたものと思われた。以上にもとづき,1)古墳~奈良時代,2)中世,3)江戸時代後期,4)明治時代以降各時期の水域・地形変化の復元をおこなった。
- 著者
- 網島 聖
- 出版者
- 大阪市立大学都市研究プラザ
- 雑誌
- 空間・社会・地理思想 = Space, society and geographical thought (ISSN:13423282)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.13-35, 2020
I はじめに : 西日本の大学にある人文系地理学教室の多くが史学科ないし史学地理学科に所属していたという伝統を共有する。その発信源となったのが、第二次世界大戦前における……
1 0 0 0 IR 全学教育科目「自然地理学」におけるアクティブ・ラーニングの実践報告
- 著者
- 植木 岳雪 大野 希一 関谷 融 UEKI Takeyuki OHNO Marekazu SEKIYA Toru
- 出版者
- 長崎県立大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:2432616X)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.87-93, 2016-12-28
長崎県立大学シーボルト校の全学教育科目の自然地理学の授業では、2012年度から2016年度の5年間、地形図、地質図、空中写真を使った室内作業、スケッチの描き方の実習、島原半島世界ジオパークにおける野外実習、野外実習のまとめのポスター発表といったアクティブ・ラーニングを中心に行った。自然地理学の履修者は、これらの地域の素材を生かしたアクティブ・ラーニングを肯定的に評価した。
1 0 0 0 世界各国の地形図整備状況と西欧6カ国における地形図の縮尺体系
- 著者
- 保谷 睦子
- 出版者
- 日本地図学会
- 雑誌
- 地図 (ISSN:00094897)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.31-38, 1983
1 0 0 0 湖沼図の設計に関する二・三の問題
- 著者
- 小谷 昌
- 出版者
- 日本地図学会
- 雑誌
- 地図 (ISSN:00094897)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.7-13_2, 1968
昭和30年夏, 琵琶湖湖南水域において, H. S型精密測深機を使用して湖沼調査を実施し, 湖底地形・底質・水中植生・湖岸構造物など陸水地理的な内容を総合的にあらわした, 1万分1湖沼図琵琶湖湖南水域I・IIの2図葉を作成した。基本測量にもとづく湖沼図の第1号であるが, 同年3月には筆者らの指導のもとに静岡県が浜名湖の深浅測量図を作成した。これも同種の音響測深機を使用し, 音響測深法による完全な公共測量の形式をそなえた最初のものであった。<BR>敗戦のもたらした深刻な食糧工・エネルギー資源不足の対策と, 荒廃した国土の災害保全を推進するため国土総合開発法が制定されたのは昭和25年5月であった。<BR>湖沼図がこのような時代的背景のもとに, 河川・湖沼など, 基本図の空白部を埋める目的以外に, 国土総合開発計画の基本的な資料として十分その効果を発揮できるよう, 設計上の考慮がはらわれていることはすでにのべた。<BR>このようにきわめて明快な目的設定のもとに湖沼図像のアウトラインの素描がおこなわれた。等深線であらわされる湖底地形は単なる湖水の深浅や, 水面下の土地の凹凸の忠実な表現ではなく, 地形営力 (湖水の運動など) の総和であり, 底質や水中植生と密接な関係を有し, 水産生物環境の重要な部分をしめている。漁港や舟溜り, 漁業組合などの図上表示は漁労および流通の拠点を, 揚水ポンプ場と関連水路の分布は湖水の逆水灌漑 (農業用水) 地域をそれぞれあらわすものである。<BR>湖沼図の構成要素のうちもっとも基本的な等深線については如上の目的に適合させるため, 従来の挿入法によらず, 測線のネットワークから音測記録の解析, 等深線の図化にいたる新らしい作業システムを考案し, 机上実験による方法論の確立をこころみた。次いで予備設計, 現地作業の工程を経て琵琶湖湖南水域の湖沼図の試作図を完成印刷した。試作図は直ちに各省, 県, その他関係諸機関および大学などに配布し, アンケートをとり, 一方学識経験者および水資源開発担当官15名による意見聴取会を開催し, ユーザーの立場における試作図の検討をおこなった。<BR>ヒアリングおよびアンケートの結果はユーザーの側から試作図に対する補足的な要望と, 読図理解の難易という二点に関する再検討資料として活用し, 予備設計の部分的な修正をおこなった。とくに湖沼図はその性質上対象ユーザーの想定階層をきわめ広範にとってあるため, 図の構成要素を重点的にしぼり, 図の"読み易さ"に相当の比重をかけ, いたずらに煩瑣になることをさけた。<BR>しかし湖沼図は縮尺の制約をうけ, 多用途という基本図的性格をもつものである以上, ヒアリングやアンケートの結果をそのまま反映させるわけにはいかない。たとえば透明度や水色・水質など流動性に富み周年観測を必要とするもの, あるいは水産生物の自然繁殖地点とその優先種などの表示の希望が出されたが, これは明らかに湖沼図とは別個な調査研究の体系に属するものである。また図式の構成やレイアウトなど少なくともカルトグラフィーの範ちゆうに属する事項についても, もとよりヒアリングやアンケートの対象にはしなかった。
1 0 0 0 北方四島・千島・樺太 : 地図で語る戦前・戦中・戦後
1 0 0 0 地形図に歴史を読む : 続・日本歴史地理ハンドブック
1 0 0 0 阪神大震災地域における埋立地の推移と大正初頭の水田・市街地の分布
- 著者
- 藤田 元夫
- 出版者
- 一般社団法人日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.88-91, 1995-04-10
- 被引用文献数
- 1
本年1月17日に発生した"阪神大震災"は5000人を上回る死者を出す大惨事となったが、この大地震による激震地域が帯状の分布を示していたことが明らかになりつつある。現在のところ、このような震度分布を"活断層"のみによって説明しようとする論調が目立っているが、地震動や震災を"地盤"との関係から検討する視点が重要であることは、関東大震災を初めとする種々の震災で指摘されてきたところである。筆者は、阪神大震災の発生直後から、この震災と"地盤"との関係に着目し、この関係を検討するための資料として、明治以降の古地形図と最新の地形図を読図することにより、神戸市・芦屋市・西宮市一帯における埋立地の推移と、大正初頭の水田・市街地の分布、および地形区分を明らかにする図面(p.90〜91)を作成した。初版図は本年1月末に作成したが、本報で発表するものは2月初旬に作成した改訂版である。
- 著者
- 和田 雅昭 畑中 勝守 雫石 雅美
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 日本航海学会論文集 (ISSN:03887405)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, pp.83-89, 2006
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3 1
The instrumentation for the measurement of seafloor topography with the data of fishing echo sounder and GPS accrued by the sensor network technology has been presented in this study. In our previous paper, details of the present system and the accuracy of it have been discussed and the authors have shown the potential of the present system for practical use. In this paper, the data analysis of experimental results of about 680,000 data obtained by a real fishing operation is discussed. The experiment for practical use by the present system has been carried out for about a year using a fishing vessel. The records of a fishing echo sounder and GPS have been stored in a database and used to draw a bathymetric chart of experimental site. However, many suspicious parts of water depth can be seen in the bathymetric chart because the data of double reflection were included in the chart. In order to increase the reliability of the bathymetric chart obtained by the present system, the authors examined the data analysis for removing suspicious data due to the double reflection from the bathymetric chart. The retouched bathymetric chart after utilizing the data analysis are compared with the "Basic chart of the sea" represented by the Japan Coast Guard and 90% of all difference between the two of them were less than 5m.
1 0 0 0 IR アロハ形予約衛星パケット通信網におけるアクノリッジ方式の解析
- 著者
- 田坂 修二 深谷 和義
- 出版者
- 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B 通信 (ISSN:09135715)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.7, pp.p780-790, 1987-07
- 被引用文献数
- 1
衛星パケット通信網の性能評価に関しては,既に多くの研究が行われている.しかし,そのほとんどが送達確認応答パケット(ACK)の存在を無視している.本論文は,衛星パケット通信用多元接続プロトコルの中でも,比較的実用性が高いと考えられるスロット付アロハ予約チャネルを用いた予約プロトコル(アロハ形予約プロトコル)を採用したシステムにおけるACK問題を解析したものである.本システムでは,ACKと予約パケットは同一のサブフレームで送信される.ACKの衝突が生じうる通常のACK伝送方式の解析に加えて,無衝突ACK伝送を実現する一つの優先ACK方式を新たに提案し,その解析も行っている.解析には,平衡点解析の手法を用いている.非優先および優先の両ACK方式について,スループットと平均応答時間を求め,システムの安定性も評価している.また,ACKトラヒックの存在が最適フレーム長の決定に及ぼす影響について考察し,その影響は低負荷では小さく,高負荷になると大きいことを示している.更に,ACKに優先権を付与することによって,システムの安定性は増大し,性能全搬が改善されることも示している.