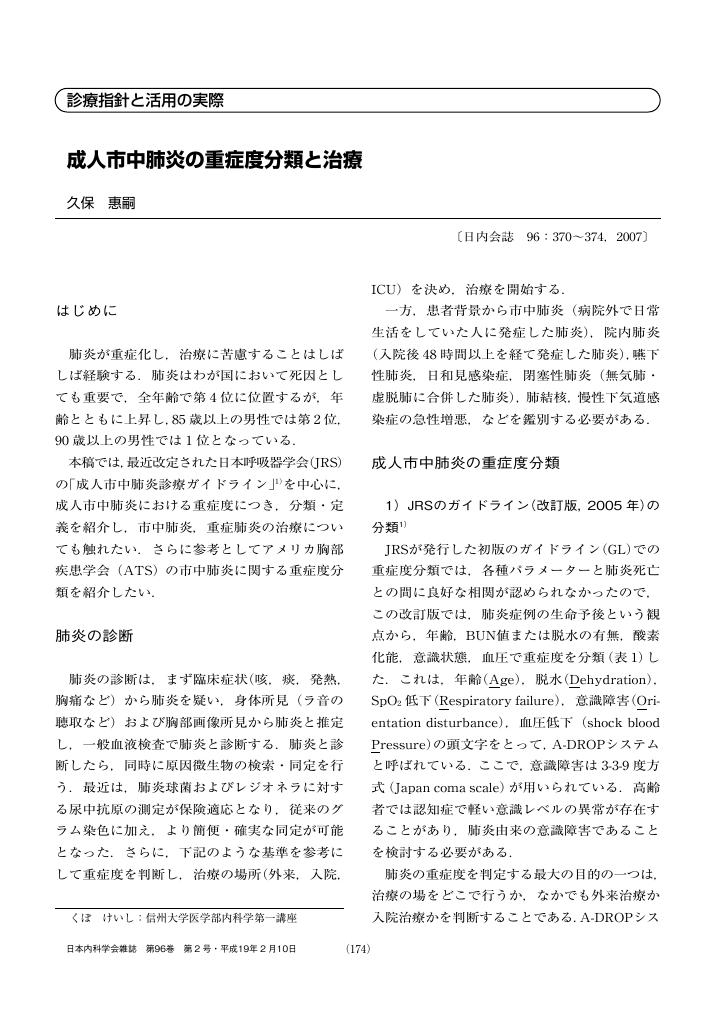1 0 0 0 OA 成人市中肺炎の重症度分類と治療
- 著者
- 久保 惠嗣
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.2, pp.370-374, 2007 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 銃後の護り
- 著者
- 久我 荘多郎
- 出版者
- 社団法人 大阪生活衛生協会
- 雑誌
- 家事と衛生
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.9, pp.36-38, 1937
1 0 0 0 OA 「古事記」に現われた酒(3)
1 0 0 0 OA 刈り取り管理の時期および回数が特定外来生物オオキンケイギクに及ぼす影響と防除効果
- 著者
- 畠瀬 頼子 小栗 ひとみ 松江 正彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.421-426, 2010 (Released:2011-07-22)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 5 1
We aimed to investigate the control effect of season and time of mowing on Coreopsis lanceolata. To this end, we conducted a 2-year mowing experiment on the vegetation of gravely beds of Kiso River. Mowing was conducted either once, twice, or thrice a year, in June, October, and/or February, since 2007. We observed that the number of flowering shoots decreased in the plot mowed in February (once) ; in plots mowed in June and February and in October and February (twice) ; and in plots mowed in June, October, and February (thrice). In addition, overall, mowing had no effect of reducing the number of individuals, but the number decreased in plots selectively-removed only in June. This experiment shows that mowing in February is effective in decreasing the flowering of Coreopsis lanceolata, and mowing more than once (in February and another season) enhances this effectiveness. Moreover, in this 2-year experiment, we found that mowing does not decrease the number of individuals of Coreopsis lanceolata.
1 0 0 0 血管内大細胞型B細胞リンパ腫研究の現状と今後の展望
- 著者
- 島田 和之
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.631-640, 2021 (Released:2021-07-03)
- 参考文献数
- 49
血管内大細胞型B細胞リンパ腫は,全身臓器の細小血管内に腫瘍細胞が選択的に増殖する節外性B細胞リンパ腫の一型である。生検臓器より十分な腫瘍細胞を得られないことが,病態解明を妨げてきたが,異種移植マウスモデルや血漿遊離DNAを利用することにより,本病型が活性化B細胞型びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に類似する分子遺伝子学的特徴を持ち,免疫チェックポイント関連遺伝子に高率に異常を来すことが明らかとなってきた。治療面においては,rituximab併用化学療法による治療成績の向上と高い二次性中枢神経浸潤リスクを勘案した,R-CHOP療法に高用量methotrexate療法と髄腔内抗がん剤注射を組み合わせた治療を試験治療とする臨床第II相試験が行われ,同治療により良好な無増悪生存割合と低い二次性中枢神経浸潤累積発症割合が示された。病態に対する理解の深化と治療成績のさらなる向上が今後の課題である。
1 0 0 0 OA ソーシャル・マーケティング研究における理論的視座の再検討
- 著者
- 水越 康介 日高 優一郎
- 出版者
- 日本商業学会
- 雑誌
- JSMDレビュー (ISSN:24327174)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.33-39, 2017 (Released:2019-10-29)
- 参考文献数
- 70
- 被引用文献数
- 1
本稿では,ソーシャル・マーケティング研究について検討し,今後の具体的な研究指針を提示する。この試みは,近年ますます注目される社会的活動において,マーケティング活動やマーケティング研究が果たす意義を明らかにするとともに,営利企業の活動にとどまらないマーケティングの可能性を示す。具体的に,本稿では,ソーシャル・マーケティングがコマーシャル・マーケティングの応用として発展し,個人の行動変革を目的とするダウンストリームに注目してきたことを確認する。その上で,近年の新たな研究として,社会変革までを見据えたアップストリームに注目するとともに,アップストリームとダウンストリームの相互依存関係に関する実証的な研究が必要とされるようになっていることを示す。
1 0 0 0 OA 『源氏物語』右大臣家の四の君考 : 大臣家の娘、そして北の方として
- 著者
- 河村 知加子
- 出版者
- 愛知淑徳大学国文学会
- 雑誌
- 愛知淑徳大学国語国文 (ISSN:03867307)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.121-140, 1999-03-20
1 0 0 0 愛情ホルモン・オキシトシンによる炎症免疫抑制作用の分子基盤の解明
1 0 0 0 OA 副腎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内分泌学会
- 雑誌
- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.S.Update, pp.73-99, 2019-06-20 (Released:2019-07-17)
1 0 0 0 馬尾症候群を契機に肺生検で診断できた血管内大細胞型B細胞リンパ腫
- 著者
- 井手 史朗 大原 慎 内田 智之 井上 盛浩 華 見 萩原 政夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.326-330, 2019 (Released:2019-05-08)
- 参考文献数
- 11
65歳,男性。膀胱直腸障害と両下肢の感覚障害を自覚し入院となった。入院時,画像検査で胸部すりガラス影を認め,さらに抗サイトメロウイルス(CMV)-IgM陽性を有意と捉え,一連の症状をCMV感染によるものと考え,ステロイドパルス療法および抗ウイルス療法を開始するも,改善を認めなかった。その後,肺野病変が悪化したため気管支鏡検査を行い,生検も追加し,血管内大細胞型B細胞性リンパ腫(IVLBCL)の診断を得た。R-CHOP療法が施行され,自覚症状,採血データは速やかに改善傾向を認め,完全寛解に到った。MTXによる髄注療法を追加し,2年間の寛解を維持している。IVLBCLは9.5%に末梢神経障害を合併することが報告されているが,馬尾神経障害を呈する例は末梢神経障害のうちの14.5%とさらに稀であるとされ,ここに報告する。
1.抗卵白アルブミン抗体で受動感作した後に、アルブミン抗原でイヌの脳内肥満細胞を刺激した。脳内肥満細胞の刺激でACTHを介して副腎皮質ホルモンが、交感神経を介して髄質ホルモン分泌が亢進した。Compound 48/80で脳内肥満細胞を刺激しても副腎髄・皮質ホルモンが上昇し、抗利尿ホルモンやレニン分泌も亢進した。これらの反応は正中隆起部の肥満細胞が脱顆粒しヒスタミンを放出し、CRF分泌をへて下垂体-副腎皮質系と交感神経-副腎髄質および腎傍糸球体細胞系を活性化するとともに、下垂体後葉をも賦活した結果であり、脳内肥満細胞が抗原センサーとなり得ることを示唆している。2.副腎の肥満細胞は内包するヒスタミンやPAFを放出し、副腎皮質ホルモン分泌を高めるので副腎の肥満細胞はI型アレルギー発症時に亢進した皮質ホルモン分泌により炎症を抑制し、生体防衛に働く可能性がある。腹腔内の炎症ではエンテロクロマフィン細胞と肥満細胞に含まれるセロトニンやヒスタミンが内臓求心性神経を介して炎症情報を脳へ伝え発熱し、摂食や行動を抑制し体力の温存と炎症からの回復を計り生体防衛に寄与していることが分かった。3.GlucocorticoidはLPS誘発の発熱、摂食抑制などの炎症を抑制する。脳内でも末梢にでも居住する肥満細胞はアレルゲンに反応して脱顆粒し、Chemical mediatorを放出しストレスホルモンを分泌亢進する。このことは肥満細胞誘発のアレルギー症には皮質ホルモン分泌亢進で、アナフィラキシーショクに対してはカテコールアミン、レニン、ADH分泌亢進で、呼吸不全に対してはEpinephrineと皮質ホルモン分泌亢進で対抗し,ネガティーブフィードバック的に炎症の進行を抑制する可能性が明らかになった。
1 0 0 0 OA 脳生検で診断し得た多発脳出血を伴った血管内大細胞型B細胞リンパ腫の1例
- 著者
- 矢浦 一磨 渡辺 源也 中村 貴彬 突田 健一 鈴木 博義 鈴木 靖士
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- pp.cn-001373, (Released:2020-02-26)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
症例は53歳女性,左上肢の間代性痙攣を認め入院した.頭部MRIで大脳に複数のFLAIR高信号,磁化率強調画像(susceptibility-weighted imaging; SWI)で多発する微小な低信号病変が見られ,抗痙攣薬の内服を開始した.しかし痙攣発作が再発し,頭部MRIで大脳にさらにSWI低信号の病変が新規に出現したため,脳生検し,出血を伴った血管内大細胞型B細胞リンパ腫(intravascular large B-cell lymphoma; IVLBCL)と診断した.IVLBCLは典型的な多発梗塞性病変だけでなく出血性病変でもIVLBCLを鑑別疾患の一つとして列挙する必要がある.
1 0 0 0 OA 経気管支肺生検により診断に至ったびまん性B細胞性血管内リンパ腫の1例
- 著者
- 中田 樹海 鈴木 剛
- 出版者
- 東都大学
- 雑誌
- 東都医療大学紀要 = Tohto University bulletin (ISSN:21861919)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.61-66, 2018-03
1 0 0 0 OA 血管内大細胞型B細胞リンパ腫に伴う過活動型せん妄に対してステロイド投与が有効であった1例
- 著者
- 木原 里香 山添 有美 浅井 泰行 足立 佳也 桒原 恭子 藤野 雅彦 佐部利 了 小田切 拓也 綿本 浩一 渡邊 紘章
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.199-204, 2020 (Released:2020-07-21)
- 参考文献数
- 15
【緒言】血管内大細胞型B細胞リンパ腫が疑われた患者が過活動型せん妄を呈し,ステロイド投与が過活動型せん妄に有効であった1例を経験したので報告する.【症例】67歳男性.発熱と貧血,高LDH血症を認め,精査中に,過活動型せん妄をきたした.抗精神病薬のみでは症状緩和が困難であった.血管内大細胞型B細胞リンパ腫による微小血管閉塞がせん妄の直接因子となっていることが強く疑われたため,骨髄検査と皮膚生検を施行したうえで,プレドニゾロンを増量したところ,速やかに症状が改善した.【考察】血管内大細胞型B細胞リンパ腫の症例においては,微小血管梗塞や中枢神経病変といった原病によるせん妄に対し,ステロイド投与が症状緩和に寄与する可能性がある.
1 0 0 0 当院における血管内大細胞型B細胞リンパ腫の臨床像
- 著者
- 奥野 達矢 岩田 哲 早川 浩史 宮尾 康太郎 梶口 智弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.184-190, 2019 (Released:2019-05-08)
- 参考文献数
- 13
血管内大細胞型B細胞リンパ腫(IVLBCL)は稀な節外性B細胞リンパ腫であり,特異的な所見に乏しいため診断に苦慮することが多いが,急速な経過を辿るため診断の遅れは致命的となる。IVLBCLの診断に有用な所見を検索することを目的に,当院で診断されたIVLBCL患者10例について臨床像を検討した。最多の症状は発熱で8例にみられ,次いで呼吸器症状(咳嗽,喀痰,呼吸困難感)が7例にみられた。血液検査所見では血球減少を10/10例,高LDH血症を9/10例に認め,動脈血液ガス分析ではPaO2低下を6/7例に認めた。画像検査所見上は7例に肝脾腫がみられ,9例に胸部異常陰影がみられた。これらの所見は治療により改善した。IVLBCLにおける肺病変の合併頻度はこれまでに報告されている以上に高い可能性が示唆される結果であり,原因不明の呼吸器症状,低酸素血症でもIVLBCLを鑑別に挙げる必要があると考えられる。
1 0 0 0 OA MRI磁化率強調画像で大脳に多発する低信号域を認めた血管内大細胞型B細胞リンパ腫の1例
- 著者
- 津田 曜 小栗 卓也 櫻井 圭太 梶口 智弘 加藤 秀紀 湯浅 浩之
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.504-508, 2017 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4
71歳男性.異常言動と全身性痙攣にて入院.高次脳機能障害を認めたが初回頭部MRIは異常がなかった.血中LDH・可溶性IL-2受容体高値より悪性リンパ腫を疑ったが,初回骨髄穿刺と皮膚生検では腫瘍細胞を認めなかった.10日後の頭部MRI磁化率強調画像(susceptibility-weighted image; SWI)で大脳皮質・皮質直下に異常低信号域が出現,ステロイドパルス療法を行うも無効であった.後に胸部単純CTで両肺にスリガラス影が出現,経気管支肺生検と骨髄穿刺再検にて血管内大細胞型B細胞リンパ腫(intravascular large B cell lymphoma; IVLBCL)と診断した.本疾患では脳梗塞様変化を呈することが多いが,本例ではむしろ大脳のSWI低信号域が主たる所見であり,中枢神経病変による出血性変化と推測された.
- 著者
- 石川 立則 福見 拓也 守山 喬史 村上 裕之 永喜多 敬奈 吉岡 尚徳 牧田 雅典 神農 陽子 角南 一貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.1455-1461, 2019 (Released:2019-11-06)
- 参考文献数
- 14
64歳,女性。2013年に,びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)と診断され,R-CHOP療法8コース後のFDG-PET/CTで完全奏効を確認後,残存した後腹膜腔の軟部陰影に対し局所放射線照射を追加した。2016年初頭からLDH・可溶性IL-2受容体の高値が持続し,再発を疑いFDG-PET/CT撮影行うもリンパ節腫大や異常集積は認めず。同年7月末より発熱・盗汗出現し,血管内リンパ腫を疑いランダム皮膚生検を行ったところ,皮下脂肪織内の血管周囲および血管内に大型の異型細胞の浸潤を認め,細胞形態および免疫染色,免疫グロブリン重鎖遺伝子PCR結果からDLBCLの再発が示唆された。救援化学療法に加えて自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法を行ったが,約15ヶ月後に肺病変を伴い再発し,再度化学療法を行い現在再奏効が得られている。DLBCLが血管内リンパ腫様に再発を来すこともあり,臨床所見や検査所見から疑わしい際は,IVLBCLに準じた検査を検討する必要があると考える。
- 著者
- 阿江 数通 小池 関也 川村 卓
- 出版者
- 日本バイオメカニクス学会
- 雑誌
- バイオメカニクス研究 : 日本バイオメカニクス学会機関誌 (ISSN:13431706)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.2-14, 2013
1 0 0 0 OA 英語論文における漢方の英語表現の文献計量学的研究
- 著者
- 新井 一郎 津谷 喜一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.161-171, 2011 (Released:2011-07-08)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
漢方の英語論文において文献データベースで付与されているキーワードと論文中の漢方の英語表現との関係を調査し,漢方が英語論文中でどのように表現されるべきかを考察した。まず,The Cochrane Library中のCENTRALからPubMed由来の漢方論文を選出した。“Medicine, Kampo”というMedical Subject Headings(MeSH)が付与されている論文は,本MeSHが設定された2000年以後では53報中13報と少なかった。次に,論文中の“Kampo”という言葉の有無や漢方が“Japanese medicine”と表現されているかどうか,また,それと“Medicine,Kampo”付与との関係を調査した。その結果,論文中に“Kampo”と“Japanese”を含む表現が併記されていると,“Medicine,Kampo”が付与される割合が高いことが判明した。英語論文を書く場合には,漢方の英語表現として“Kampo”および“Japanese”が含まれる“Kampo medicine (traditional Japanese medicine)” のような表現を用いるべきである。
- 著者
- 宮内 義彦 入山 章栄
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1883, pp.82-85, 2017-03-20
宮内 コンセッション事業(空港などの公共施設の運営権取得)はまさに当てはまりますが、40年先まで見通して手掛けるものですね。オリックスにとっては一番長い視点で見るべき事業が入ってきたと捉えています。入山 宮内さんは常々、オリックスはイノベーシ…