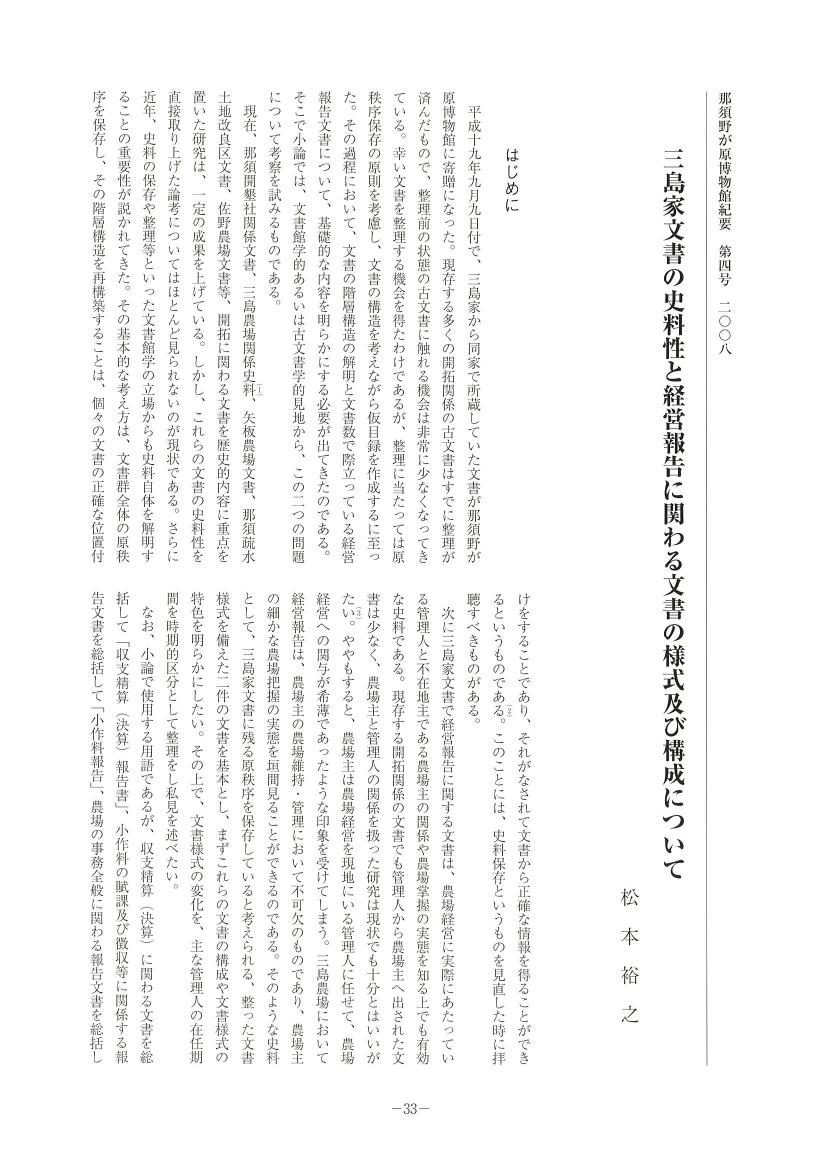- 著者
- 高橋 久一郎
- 出版者
- 千葉大学文学部
- 雑誌
- 千葉大学人文研究 = The journal of humanities (ISSN:03862097)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.114-175, 2018-03-31
1 0 0 0 IR アリストテレスの『詩学(悲劇論)』における「行為」と「悪」の問題
- 著者
- 高橋 久一郎
- 出版者
- 千葉大学文学部
- 雑誌
- 千葉大学人文研究 = The journal of humanities (ISSN:03862097)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.57-113, 2018-03-31
1 0 0 0 OA 三島家文書の史料性と経営報告に関わる文書の様式及び構成について
- 著者
- 松本 裕之
- 出版者
- 那須塩原市那須野が原博物館
- 雑誌
- 那須野が原博物館紀要 (ISSN:13499238)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.33-58, 2008-02-29 (Released:2020-02-13)
1 0 0 0 OA マルチメディアタスキングと広告説得効果
- 著者
- 安藤 和代
- 出版者
- 千葉商科大学国府台学会
- 雑誌
- 千葉商大論叢 (ISSN:03854558)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.35-54, 2018-11-30
- 著者
- 木戸 彩恵 荒川 歩 鈴木 公啓 矢澤 美香子
- 出版者
- 立命館大学人間科学研究所
- 雑誌
- 立命館人間科学研究 = 立命館人間科学研究 (ISSN:1346678X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.85-103, 2015-08
1 0 0 0 OA 文学とオノマトペ
- 著者
- 小松 英輔
- 雑誌
- 研究年報/学習院大学文学部 (ISSN:04331117)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.275-289, 1992-03-20
- 著者
- 村上 健太郎 上久保 文貴
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.820, 2005
大阪府南部から和歌山にかけての沿岸部は,温暖な地域として知られ,暖温帯から亜熱帯地域にかけて生育する植物の分布北限となっている。特に,年平均気温15℃,年最低気温平均値-3.5 ℃の等値線はヒガンバナ科ハマオモトの分布限界であり,ハマオモト線として知られている。しかし,近年,年間を通して気温は上昇傾向にあり,今後植物分布に大きな影響を及ぼす可能性がある。そこで本研究では,近年の気温上昇にともなって,大阪府周辺のハマオモト線付近を分布限界とする植物の分布について調べ,気温変化との関連を考察した。まず,1938年に描かれたハマオモト線に近い19府県の1980年代以降の気象観測所データと1990年代初めまでに作成された各県植物誌による植物分布データを,市民向けに開発された地理情報分析支援システムMANDARAに入力し,ミミズバイ,タイミンタチバナなど30種の分布限界域における気温データをえた。次に,大阪市立自然史博物館および兵庫県立人と自然の博物館のハーバリウムにおいて,大阪府および兵庫県の上記南方系植物30種の採集地および採集年代を調べ,1980年代以前と1990年代以降で,分布に差があるかを調べた。その結果,ヤナギイチゴなど,一部の種では,分布が北上している可能性が示唆された。また,先述した分布限界域の気温データを用いて,これらの植物の大阪府付近での現在の分布限界域について推定すると,多くの植物が現状では京都市付近まで分布拡大可能であると推定された。本研究でとりあげられた種のうち,自生個体が京都市付近にまで分布拡大している例は少ないが,都市域の石垣などの人工物に適応しているイヌケホシダや京都市内の二次林に移入したアオモジなど,人為によって持ち込まれた可能性が高い種については,大阪府_から_京都市において確実に分布を拡大している。今後は,各種の分散力やハビタットの選考性に関する調査を行い,より正確な分布拡大予測を行いたいと考えている
1 0 0 0 IR 鑑画会再考
- 著者
- 佐藤 道信
- 雑誌
- 美術研究 = The bijutsu kenkiu : the journal of art studies
- 巻号頁・発行日
- no.340, pp.1-27, 1987-11-30
Kangakai was an artists' club which aimed at the renovation of painting in traditional Japanese medium, founded at the initiative of Ernest F. FENOLLOSA in 1884. The activity of the club has been traced by art historians based on literary documents and its ideals have been studied on the ground of the analysis of the works by Hōgai KANŌ and other members. However, there was a limit in the past investigation since many of the works exhibited in their shows seem to have been sent out to the United States. The author, who recently had an opportunity to examine the relevant works in American museums such as Museum of Fine Arts, Boston, Freer Gallery of Art and Philadelphia Museum of Art, found there some pieces which might have been contributed to their exhibitions. In the present paper, the author lists up the works of artists related to the Kangakai and reconstructs the personal histories of the members including those who have been almost forgotten. His study of the characteristics of their activity revealed some interesting facts, namely, that Japanese art in the Meiji Era was linked with the Japonisme in the contemporary West and that Ernest FENOLLOSA and the Kangakai, as well, could not be out of the current.
1 0 0 0 IR 「総人のミカタ」活動報告書 2017年度前期~2018年度前期
- 著者
- 人間・環境学研究科院生による総合人間学部生向け模擬講義企画「総人のミカタ」運営委員会
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科 学際教育研究部
- 雑誌
- 「総人のミカタ」活動報告書
- 巻号頁・発行日
- pp.1-120, 2018-10-01
まえがき (真鍋公希) i「総人のミカタ」活動報告書に寄せて (杉山雅人) ii第1部「総人のミカタ」の概要 1活動概要と運営体制 2「総人のミカタ」について--部局の歴史における位置づけと中心的理念をめぐって (真鍋公希) 5「総人のミカタ」活動年表--始動~2018年前期 16会計報告 18メンバー紹介 19第2部 講義 212017年度前期 222017年度後期 482018年度前期 74第3部 特別企画 99【卒業生企画】総人の卒業生の話を聞いてみよう! 100【2017年度末シンポジウム】「研究を他者に語る」の先へ --教養と学際の未来を考える 104【院生向け企画】学振申請書 (DC・PD)検討会 108京都大学吉田南総合図書館 X 総人のミカタ コラボ企画 110「総人のミカタ」に関する研究活動 112第五回 京都大学 学際研究着想コンテスト 112編集後記 120<コラム/資料>学部生からみた「総人のミカタ」の凄さ (飯田昇平) 49ただの模擬講義ではない (橋本悠) 103他大学出身者のミカタ (あるいは「総人のミカタ」について語るときに私の語ること) (三升寛人) 111アンケートの分析 98「総人のミカタ」企画書 114受講者向けアンケート 118講義記録 (院生記入用) 119
1 0 0 0 OA タイピング動作特性の解析
- 著者
- 高岡 詠子 杉浦 学 小宮 仁志
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014-CE-125, no.9, pp.1-14, 2014-05-31
本研究ではタッチタイピングのできるタイピング中級者に焦点を当てて実験を行い,タッチタイピング初心者の打鍵特性と比較や分析を行った.その結果,中級者も初心者も同じような文字を得意とし,同じような文字を苦手としている,中級者は初心者に比べ誤打鍵のミスの割合が減り,入れ替えや挿入のミスの割合が増える,中級者は左右の交互打鍵が速く,初心者は一つの指による連続打鍵のほうが左右の交互打鍵より速い,中級者は左手より右手による打鍵のほうが打鍵間隔が短い,多く打鍵すれば速く打鍵できるようになるが,正解率が高くなるとは限らない,正解率をあげるためにはある程度の速度を保ったまま多く打鍵する必要があるなどの結果が導かれた.これをもとに,有効なタッチタイピング学習方法や問題文を検討することが可能となる.
1 0 0 0 OA Fe-10Cr合金の不働態化特性に及ぼすAl, SiおよびMoの効果
- 著者
- 樋尾 勝也 安達 崇 山田 隆志 土田 豊 中島 浩衛 細井 祐三
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.12, pp.1148-1155, 2000 (Released:2008-04-24)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 1
A study has been made on the effects of Al, Si and Mo on anodic polarization characteristics of Fe-10Cr alloys in 0.05-1.0 kmol·m−3 H2SO4 and NaCl aqueous solutions. Potential decay curves have also been measured in order to evaluate the stability of the passive films formed on Fe-10Cr alloys containing Al, Si and Mo. The analysis of the chemical composition of the passive film has been carried out by AES and XPS.The addition of Mo was very useful to decrease the critical passivation current density of Fe-10Cr alloys which contained Al and Si. The passive current density decreased with addition of 2 mass%Mo to an Fe-10Cr-3Si alloy, while it increased in an Fe-10Cr-3Al alloy. Pitting potential was moved toward the noble direction by the addition of Mo, except for the case of an Fe-10Cr-3Al-3Si-2Mo alloy. It seems that Laves phase (Fe2Mo) was precipitated in this alloy, and Mo-depleted zone was formed locally. The activation time was increased by the addition of Al, Si and Mo to Fe-10Cr alloys. Two step potential decay curves were obtained in Si-containing alloys, and this behavior of the decay curve was shown more clearly in an Fe-10Cr-3Si-2Mo alloy. The results of AES and XPS analysis indicated that Cr and Al concentrated in the passive film of an Fe-10Cr-Al alloy. In the case of an Fe-10Cr-Si alloy, Si concentrated in the surface region of the film and Cr did in the internal region of the film. The confirmation was not possible for the enrichment of Mo in the passive film.
1 0 0 0 三宅島の2000年噴火被害林における埋土種子組成
2000年7月の噴火以降、亜硫酸ガスの噴出が続く三宅島ではスギの枯死が顕著であり、今後、島内の多くのスギ植林地に何らかの植生回復・緑化手段が講じられる可能性がある。そこで本研究では、三宅島におけるスギ人工林の土壌中に含まれる埋土種子集団について、発芽可能な種子数および種組成を明らかにし、その植生回復・緑化利用に対する可能性を検討した。2002年12月、島内のスギ人工林において噴火により堆積した火山灰(以下、火山灰)と噴火前の埋没土壌(以下、表土)を採取した。2003年4月、表土と火山灰、および表土と火山灰の混合物(以下、混合)を用いて、播き出し実験を開始した。定期的に発芽数の測定を行い、さらに出現個体を同定した。表土試料から平均2776±90個体/_m2_(値は現地換算したもの)が発芽し、28種が同定できた。一方、火山灰試料からは85±37個体/_m2_が発芽し、6種が同定できた。また、混合試料からは 1912±638個体/_m2_が発芽し、31種が同定できた。主な出現種は、草本ではダンドボロギク・ハシカグサ・コナスビ・シマナガバヤブマオ・ドクダミ・カヤツリグサ類、木本ではカジイチゴ・ヤナギイチゴなどであり、三宅島の二次遷移初期にみられる種が多く見られた。三宅島での一次遷移初期にみられるハチジョウイタドリやハチジョウススキ、オオバヤシャブシなどの先駆種は全く出現しなかった。また、出現した種のうち、外来種はダンドボロギクの一種のみと少なく、在来種が多かった。以上のことから、三宅島のスギ人工林における埋土種子集団は、種子数・種組成ともに植生回復・緑化利用に対して大きな可能性をもつことが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 塗膜の透過性と塗膜下腐食
- 著者
- 今井 丈夫
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.12, pp.713-723, 1980-12-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- Hoon Han Sumin Kim Mee Youn Jin Chris Pettit
- 出版者
- International Community of Spatial Planning and Sustainable Development
- 雑誌
- International Review for Spatial Planning and Sustainable Development (ISSN:21873666)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.41-61, 2021-04-15 (Released:2021-04-15)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 1 4
This paper examined the impact of providing affordable rental housing through inner-city urban renewal projects in Australia. Providing affordable rental housing for lower-income households remains a challenge for planners, builders, policymakers and residents alike. Government intervention for inclusionary zoning in Australia has enhanced affordable housing supply but has also generated negative impacts such as NIMBY-ism, decreasing house price and urban sprawl. This study conducted in-depth interviews with housing and planning experts in affordable housing projects in Australia and evaluated the barriers and opportunities of providing affordable rental housing as stand-alone projects, or as part of urban renewal projects. This study found several existing challenges such as limited longevity of related policies and limited financing sources for renewal projects. The findings inform policymakers that the existing housing affordability issue can be tackled by adopting more innovative approaches such as negative gearing.
1 0 0 0 OA 15)凍結乾燥された細菌の保存に影響する諸因子について
- 著者
- 大林 容二 太田 淳 新井 四郎
- 出版者
- 低温生物工学会
- 雑誌
- 凍結および乾燥研究会記録 (ISSN:02888289)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.92-104, 1960-07-17 (Released:2017-08-01)
凍結乾燥された細菌の保存性,ことに高い温度における保存の成績から,乾燥条件や保存条件の適否を検討した。使用した菌は乳酸菌,BCGおよびYeast等である。成績の重要な点は以下のようであつた。1)媒質としてのグルタミン酸ソーダの至適濃度は菌の濃度によつて異なり菌濃度を下げれば,媒質の至適濃度も低下する。また以上の至適濃度は被乾燥体の保存期間によつても左右される。すなわち,短期間保存の場合の至適濃度は必ずしも長期間保存の際の至適濃度と同一ではない。2)高温度の保存に堪える媒質として,BCGの場合およびL. bifidusの場合にグルタミン酸ソーダの優秀性が報告されたが,今回L. bifidusについての実験で,グルタミン酸ソーダに可溶性澱粉を加えることにより保存性が著しく高められることを認めた。3)乾燥面を真空中に保存する方が空気中に保存するよりも生菌の低下が少ないことは,従来,凍結乾燥についての定説となつているが,L. bifidusやL. bulgaricus等の嫌気性菌については,常圧の空気中に保存する場合の生残率は真空保存の場合の生残率に劣らぬ成績が得られた。
1 0 0 0 OA 三奇人夜話-エクセルギーに関する対話
- 著者
- 山内 繁
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.144-149, 1979-03-05 (Released:2019-11-14)
1 0 0 0 各種仮封材(剤)の封鎖性に関する基礎実験成績について
- 著者
- 対馬 具海
- 出版者
- 東京歯科大学学会
- 雑誌
- 歯科学報 (ISSN:00373710)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.95-110, 1967-04