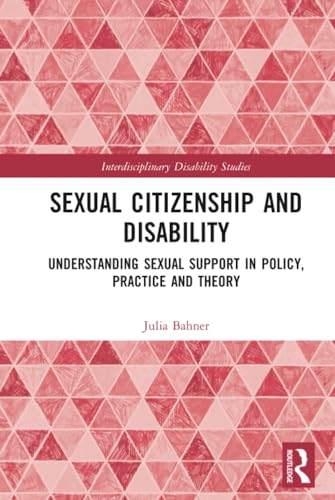- 著者
- 牲川 波都季 Hazuki Segawa
- 雑誌
- 総合政策研究 = Journal of policy studies (ISSN:1341996X)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.71-87, 2021-03-20
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1451, pp.50-54, 2008-07-28
埼玉、千葉県との県境に近い茨城県境町の田園地帯にひっそりと建つ旭化成建材・境工場。住宅用外壁や杭、断熱材などを生産する同社は、化学から電子材料、医療用機器、住宅、繊維まで7つの事業を抱える旭化成が2003年10月に持ち株会社化し、同時に事業を分社した子会社の1つ。典型的な内需型成熟市場に生きる企業である。 2008年3月期の売上高は557億円、営業利益は28億円。
1 0 0 0 IR 高等学校における援助要請の仕方とその受け止め方に関する心理教育プログラムの実践
- 著者
- 小野寺 峻一 山本 奬 川原 恵理子 亘理 大也
- 出版者
- 岩手大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 岩手大学大学院教育学研究科研究年報 = Research Journal of the Iwate University Professional School for Teacher Education (ISSN:2432924X)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.243-253, 2021-03-31
本研究の目的は,自殺予防教育の一環として,「援助要請の仕方・受け止め方」の心理教育プログラムを作成し,高校生を対象に実施し,その成果を検証することであった.作成したプログラムについて,援助要請の仕方・その受け止め方共に,当初の自信による適用の禁忌はないことが確認された.援助要請の仕方・その受け止め方の自信の向上については,自信の程度が,中程度,低い生徒に対して,効果が認められた.援助要請姿勢のへの変化に関しては,「部活や習い事」は有意に多く,「友達と口論」は有意,「成績が上がらない」は有意傾向であることが示された.高校生にとって,心理教育プログラムは,援助要請の仕方とその受け止め方の自信を向上する傾向にあり,心理面,社会面の問題において,援助要請姿勢を変容させる可能性が示唆された.
- 著者
- 藤森 新作 安養寺 久男
- 出版者
- 農林水産省農業土木試験場
- 雑誌
- 農業土木試験場技報 A 土地改良 (ISSN:05495660)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.p35-62, 1982-03
1 0 0 0 OA 電波航法 = Electronic navigation review
- 著者
- 蒲原 聖可
- 出版者
- ファンクショナルフード学会
- 雑誌
- Functional Food Research (ISSN:24323357)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, 2020
<p><b>背景</b>:地方自治体とヘルスケア企業との公民連携による健康寿命延伸産業創生および課題解決型保健事業の取り組みが散見されるようになった.</p><p><b>目的</b>:公民連携による健康づくり事業としての非対面型減量プログラム「さかいまちメタボ脱出プロジェクト」(茨城県境町)の有用性を検証する.</p><p><b>方法</b>:茨城県猿島郡境町在住の成人肥満者を対象に,ICT(Information and Communication Technology;情報通信技術)対応・非対面型減量プログラムを構築し,2017 年11 月から2018 年2 月の間に,機能性食品素材を含むフォーミュラ食(置き換え食)の利用を通じた,肥満改善施策を「さかいまちメタボ脱出プロジェクト」として実施した.本プロジェクトでは,(1)管理栄養士を中心とした医療有資格者による非対面型支援,(2)1 日1 食を目安にフォーミュラ食を利用,(3)減量に関する啓発情報の定期配信,(4)運動の啓発動画を提供,(5)低エネルギー食品や機能性食品成分の利用に関する案内を行った.なお,フォーミュラ食として用いた「DHC プロティンダイエット」の標準的な製品は,1 袋50 g 当たりのエネルギー量が167 kcal であり,タンパク質20.1 g,推奨量の約3 分の1 のビタミン類およびミネラル類,その他の機能性食品素材を含有する.また,希望者に対して,プログラム実施前後において,腹部CT撮影による内臓脂肪面積を測定した.さらに,プロジェクト終了時に,住民参加型イベント「さかいまちダイエットアワード」を開催した<sub>.</sub></p><p><b>結果</b>:87 名(男性42 名,女性45 名,平均年齢47.2 歳)がプロジェクトを完了した.12 週間のプログラム前後の変化(mean ± SE)は,BMI(kg/m <sup>2 </sup>)が29.0 ± 0.3 から27.1 ± 0.4 へ,体重(kg)が77.0 ± 1.3 から71.4 ± 1.3 へ,腹囲(cm)が96.1 ± 0.9 から89.1 ± 0.9 へ,それぞれ有意に減少した(<i>p</i><0.01).なお,参加者全員の減量の総計は,12 週間で337.8kg に達した.さらに,52 名が腹部CT撮影による内臓脂肪面積の評価を受け,介入前の145.62 ± 7.62 cm<sup> 2 </sup>から,介入後に119.65 ± 8.04 cm<sup> 2 </sup>へ有意な減少を認めた(<i>p</i><0.01).</p><p><b>考察</b>:肥満の改善という行政課題に対する取り組みとして,公民連携による健康づくりとして,非対面型減量プログラムを実施し,一定の有効性が認められた.今後,ファンクショナルフード素材を扱うヘルスケア企業の可能性として,公民連携に基づく健康寿命延伸産業創生および課題解決型保健事業の取り組みを継続する.</p>
- 著者
- 坪田 祐基 石井 秀宗 野口 裕之 TSUBOTA Yuki ISHII Hidetoki NOGUCHI Hiroyuki
- 出版者
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発達科学 (ISSN:13461729)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.47-56, 2016
Perfectionism is the striving for flawlessness, and extreme perfectionists are people who want to be perfect in all aspects of their lives. It is known that perfectionism is related to a number of psychological and physiological problems, such as apathy, neurosis, alcoholism and anorexia nervosa. A number of studies have investigated the relationship between perfectionism and maladaptation. Recent studies have suggested that perfectionists have certain cognitive biases, including selective attention to failure, which is particularly problematic. The few previous investigations of this problem based on the social cognitive paradigm had the shortcomings that the used task was limited to the emotional Stroop task, and used stimulus words were only negative perfectionism-related words (failure-related words). In order to overcome these problems, relationships between perfectionism and selective attentions to success- or failure-related words were investigated with the dot-probe task. The result indicated moderate correlations between perfectionism and selective attention to both success- and failure- related words in males, whereas little correlation was found in females. However, success- and failurerelated words used in that study were associated with the task situation (e.g., "correct", "achieving," "mistake," and "error"), which are familiar to male, but not to female perfectionists. Therefore, it is still unclear if the above result was caused by the fact that female perfectionists did not pay attention to successes and failures, or that the words used were not familiar to females. In order to resolve this issue, this study employed the dot-probe task and words related to social situations and investigated relationships between perfectionism and selective attentions. Undergraduates (N = 100, 50 female and 50 male) were asked to perform the dot-probe task and complete self-report questionnaires. In the dotprobe task, participants first focused on a central fixation cross that was shown on a computer screen. It was replaced by two stimuli after 500ms, which were displayed one above the other. For example, the screen displayed a word related to success in social situations and a neutral word. These words disappeared after 500 ms, and a symbol appeared on the screen replacing one or the other word. Participants should respond to the shape of this symbol as fast as possible. If a participant had tendency to pay more attention to such words related to social situations, reaction time to the words would be shorter when the symbol replaced a word related to social situations compared to when it replaced a neutral word. Three kinds of stimuli were used. The first group was words related to successful social situations such as "compromise" and "closeness". The second group was words related to failures in social situations such as "isolation" and "friction". The third group was neutral words such as "pencil" and "weather. Self-reporting questionnaires were also administered: Self-Oriented Perfectionism (SOP) items in the Multidimensional Perfectionism Scale (MPS), the Multidimensional Self-oriented Perfectionism Scale (MSPS), and the Multidimensional Perfectionism Cognition Inventory (MPCI). Ratio of reaction time in neutral condition (neutral words vs. neutral words) to that in conditions including social situations related words (e.g., social situation failure- vs. neutral words) was computed as an index of selective attention. Pearson's product-moment correlation coefficients between this index and perfectionism scale scores showed almost no significant correlations in both males and females. These results suggest that perfectionists do not pay attention to success- or failure words in social situations. Sex differences in relationships between perfectionism and maladaptation in social situations would be caused by other factors such as behavior and consciousness.
1 0 0 0 OA eスポーツの産業化に向けて : 選手へのインタビューに基づく考察
- 著者
- 野田 光太郎 中村 勉
- 出版者
- 花園大学文学部
- 雑誌
- 花園大学文学部研究紀要 = Annual Journal Faculty of Letters Hanazono University (ISSN:1342467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.99-118, 2019-03-10
1 0 0 0 OA 石森延男と第4 期国定国語教科書(サクラ読本)
- 著者
- 宇賀 神一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.57-58, 2018 (Released:2019-12-05)
1 0 0 0 OA SQMで福井の夜空の明るさを測る : 測定方法とその問題点
- 著者
- 山本 博文 小林 暉 藤井 純子
- 雑誌
- 福井大学地域環境研究教育センター研究紀要 「日本海地域の自然と環境」
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.15-26, 2017-11-01
- 著者
- 礒田 正美 野村 剛 柳橋 輝広 岸本 忠之
- 出版者
- 公益社団法人日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.2-12, 1997-01-01
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
本研究は,数学的コミニュケーション力育成という今日的教育目標に対して,一斉指導の場面で二人教師が対立意見を闘わす討論を常設したティームティーチングの新たな方法を導入することで,生徒がいかに二人教師の討論に関係を持ち,授業への参画の仕方を変化させていったかを1年にわたり記録し,分析したものである.,生徒は,教師の討論に耳を傾けることにはじまり,自然に討論に口を挟むようになり,やがて,自由に意見を言うようになった.,そして,生徒が自ら教師の討論を代弁し,さらには生徒どうしが自ら討論を起こすようになっていった.,その分析から,教師が討論の見本を示せば,生徒も漸次討論に加わるようになり,やがて自ら討論できるようになること,自ら討論に加わることにこそ価値を認めた数学の授業観が生徒に育つことが確認された.,そして,適切な見本を示し,生徒の討論への参画の仕方が漸次進化するように年間指導計画を構成し,日々の学習指導を工夫すればすれば,討論は指導可能であることが示唆された.,
- 著者
- 吉野 瑞恵
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.11-20, 2000
『蜻蛉日記』は、「国文」の規範たる仮名文で書かれていたため、近世以来明治に至るまで、評価すべき作品とされていた。だが、その「文学性」が評価されていたわけではなかった。大正に入って「自照性」というキーワードが導入されることによって、『蜻蛉日記』の文学史的地位は上昇したものの、この日記は良くも悪くも「女流」文学の王道を歩むこととなったのである。
- 著者
- 番定 賢治
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.198, pp.198_111-198_126, 2020-01-25 (Released:2020-04-16)
- 参考文献数
- 47
This article focuses on activities of Japanese officials who worked for the Secretariat of the League of Nations (LN), and their influences in the Secretariat as a whole. Not only two Under Secretary-Generals (Inazo Nitobe, and Yotaro Sugimura) were appointed from Japan, but also many young officers (Ken Harada, Tetsuro Furugaki, and others) worked for the LN Secretariat. However, the number of Japanese officers in the LN Secretariat and the variation of the sections in which Japanese officers in the LN Secretariat engaged was evidently smaller than those of officers from any other permanent council member States. As for Japanese officers in the LN Secretariat, expertise in policy making is not so much important as ability to adapt themselves to Eurocentric environment of the LN Secretariat, and the main missions of Japanese officers in the LN Secretariat were liaison work between the LN Secretariat and Japanese government or Japanese press, and propagation of information about the work of the LN towards Japanese public. However, some Japanese officers were engaged in more various works, such as drafting communiques in some committees of the Assembly, and liaison work between the LN and other Asian nations. Moreover, during their temporary visits of Japan, Japanese officers in the LN secretariat went on lecture trips to promote understanding of the activities of the LN, and Nitobe’s lecture trip from 1924 to 1925 led to the creation of Tokyo branch of the LN Secretariat Information Section, which enhanced propagation of specific information about the work of LN. When the Institute of Pacific Relations (IPR) invited the LN Secretariat to its conference, Nitobe insisted that this institute and Pan-Pacific movement would be helpful to support the activities of the LN, and Sugimura and other Japanese officers in the LN Secretariats repeatedly insisted the significance of IPR for the LN. In 1927, two officers of the LN Secretariat (One of them was Setsuichi Aoki, the head of Tokyo branch of the LN Secretariat) was sent to the second biannual conference of IPR. In 1929, when the third biannual conference of IPR was held at Kyoto, Sugimura himself attended the conference. However, at the time of this conference, Sugimura tried to invite the LN representative in the conference to Manchuria and Korea, which indicates Sugimura’s intention to lead the LN Secretariat to support the political interest of his home country.
- 著者
- 左近 幸村
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター内 グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアと世界」
- 雑誌
- 境界研究 (ISSN:21856117)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.155-159, 2012
1 0 0 0 Sexual citizenship and disability : understanding sexual support in policy, practice and theory
- 著者
- Julia Bahner
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2020
- 著者
- 小林 哲
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.113-130, 2000
- 被引用文献数
- 22
日本の本州・四国・九州などを流れる河川に生息するカニ類の生態をまとめ,河川環境におけるカニ類の生態的地位と現状について考察を加えた.カニ各種の分布と回遊のパターンから,6タイプを分けた.タイプAとタイプBは感潮域付近でのみカニ期を過ごし,タイプAは繁殖のための回遊はないがタイプBは繁殖のため河口域から海域へ水中を移動する.タイプCとタイプDはカニ期を感潮域から淡水域に沿った陸域で過ごし,タイプCは河川の淡水域から感潮域にかけてで卵を孵化させ,幼生は広い塩分耐性があり感潮域へと流れくだる.タイプDは繁殖のためカニが海域へと移動し,海域で孵化を行う,タイプEは河川の淡水域でカニ期を過ごし,成熟したカニが川を降り感潮域に達しそこで繁殖する.これらのタイプはいずれも浮遊生活期の幼生が海域を分散する.タイプFは全生活史を淡水域上流部で過ごし,幼生期は短縮される.<BR>河川ではカニの分布は感潮域周辺に集中している.干潟に多くみられるスナガニ類は底質の粒度組成に応じてすみわけており,ヨシ原など後背湿地にはイワガニ類が多く出現する.淡水域の下流~中流域では,モクズガニが水中に,ベンケイガニ類3種(ベンケイガニ,クロベンケイガニ,アカテガニ)が水辺から陸上に出現する.上流域では,サワガニが水中から陸上にかけて分布する.代表的なスナガニ科8種,コブシガニ科1種イワガニ科10種,サワガニ科1種についての生態をまとめ,紹介した.<BR>河川生態系においては,カニ類は感潮域で腐食連鎖の上で重要な位置を占めていると考えられる.特にスナガニ類およびイワガニ類は,感潮域において有機物を消費している.また巣穴を多数掘ることで堆積物に沈積した有機物の分解を助け,環境浄化を助けている.近年,底質の変化によりカニ類の生息場所が損なわれ,堰の建設による流れの遮断により回遊の過程が妨害を受けている.河川改修による後背湿地における植生の喪失も,カニ類の生息場所を奪う危険性がある.以上のような,カニ類の生態を考慮に入れた改修事業が必要と考えられる.
1 0 0 0 馬の頭部局所麻醉と其方法概觀
- 著者
- 宮川
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- 應用獸醫學雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.5, pp.408-411, 1931
1 0 0 0 OA D-OODA ループを取り入れた教育実践に関する研究
- 著者
- 坂井 清隆
- 出版者
- 福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻(教職大学院)
- 雑誌
- 福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻(教職大学院)年報 = Bulletin of University of Teacher Education Fukuoka Graduate School of Education Division of Professional Practice in Education (ISSN:21860351)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.73-84, 2021
本小論は,今次改訂の理念を教育実践レベルで具体化を目指す教育方法について検討を行うことを目的とする。具体的には,教育実践研究において通常使われる PDCA サイクルに対して,近年ビジネス界で注目されている「OODAループ」の教育実践への適用可能性を追求するものである。 本研究では,教育実践にOODAループ取り入れた場合,「ビジョンの設定」と「動機付け・育成」,そして「意思決定」という3つの機能が同時並行的に駆動することによって,教師の単元展開における実践的力量を高めていることがうかがえた。ビジョンの設定には,「どんな成果(outcome)を出すか」という方針を固め,学習者をどのように日々の教育実践に生かすかといった意思決定の具体や,単元展開に対して洞察力や構想力をもち,その教師・その学習者ならでは学習内容を創り出す意識の芽生えを詳細に捉えることの重要性を見出すことができた。