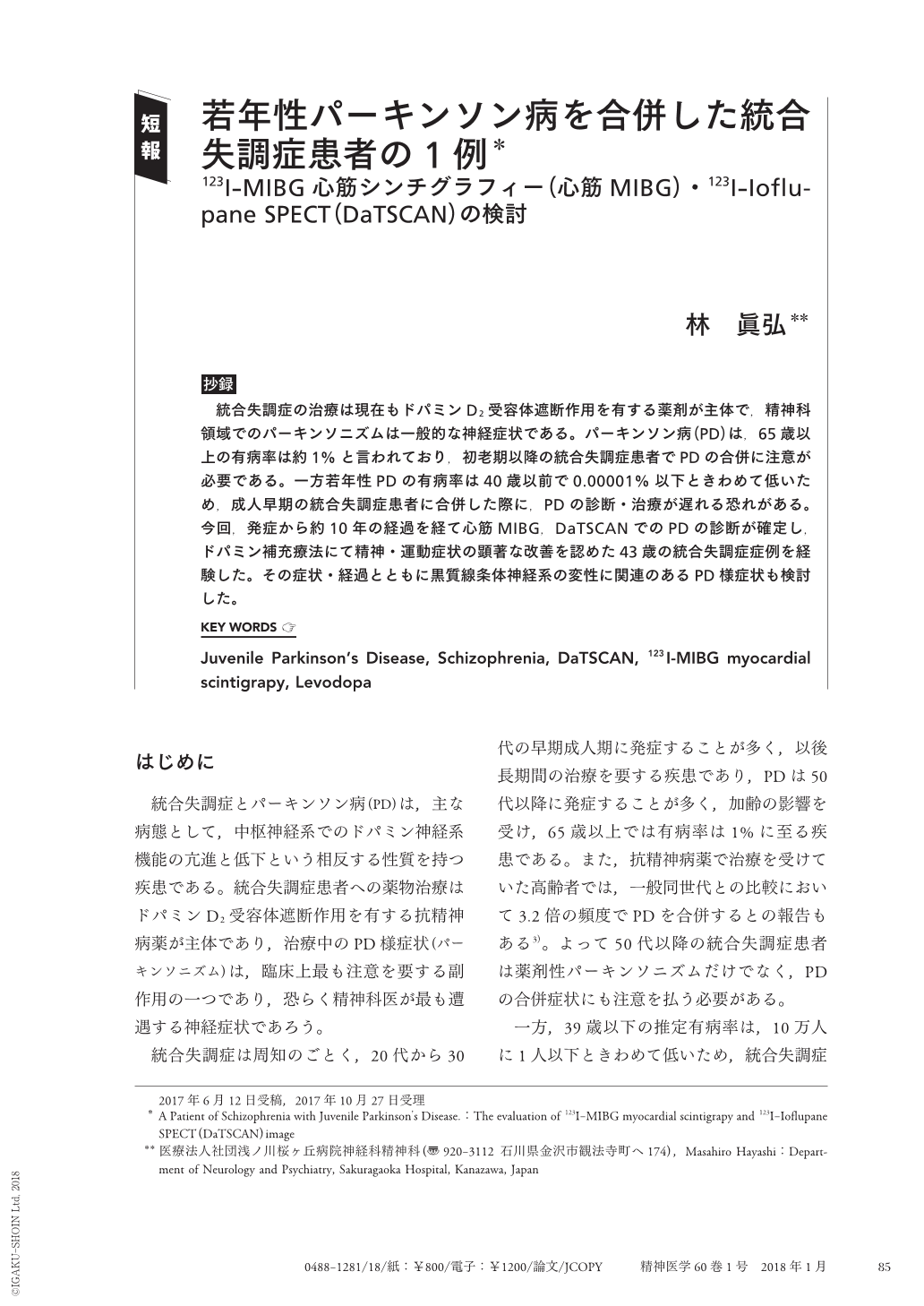1 0 0 0 OA 中国地域の地殻内応力マップの作成
- 著者
- 今西 和俊 内出 崇彦 椎名 高裕 松下 レイケン 中井 未里
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.23-40, 2021-03-30 (Released:2021-04-14)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
中国地域の地殻内応力マップを作成するため,過去12年間にわたるマグニチュード1.5以上の地震の発震機構解を決定した.気象庁一元化カタログもコンパイルし,10 kmメッシュの応力マップとして纏めた.小さな地震まで解析して発震機構解データを増やしたことで,先行研究よりも応力場の空間分解能を格段に高くすることができた.得られた応力マップから,この地域は東西圧縮の横ずれ場に卓越しているが,島根県・鳥取県の日本海側になると応力方位が時計回りに約20°回転して西北西−東南東方向を示すようになる様子が詳しくわかるようになった.応力マップをもとに活断層の活動性について評価を行ったところ,地震調査研究推進本部 地震調査委員会(2016)が評価対象とした中国地域の30の活断層のうち,現在の応力場,一般的な摩擦係数のもとで再活動する条件を満たしているのは28あることがわかった.残りの2つの活断層は現在の応力場では動きにくく,再活動するためには,異常間隙水圧の発生や隣接する活断層の破壊に伴う応力変化でトリガーされるなどの外的要因が必要になると考えられる.
抄録 統合失調症の治療は現在もドパミンD2受容体遮断作用を有する薬剤が主体で,精神科領域でのパーキンソニズムは一般的な神経症状である。パーキンソン病(PD)は,65歳以上の有病率は約1%と言われており,初老期以降の統合失調症患者でPDの合併に注意が必要である。一方若年性PDの有病率は40歳以前で0.00001%以下ときわめて低いため,成人早期の統合失調症患者に合併した際に,PDの診断・治療が遅れる恐れがある。今回,発症から約10年の経過を経て心筋MIBG,DaTSCANでのPDの診断が確定し,ドパミン補充療法にて精神・運動症状の顕著な改善を認めた43歳の統合失調症症例を経験した。その症状・経過とともに黒質線条体神経系の変性に関連のあるPD様症状も検討した。
1 0 0 0 OA 食品の機能性成分としてのパントテン酸誘導体の脂質低下作用に関する研究
食肉中には、パントテン酸(PaA)、パンテテイン(PaSH)、コエンザイムA(CoA)など各種PaA誘導体が含有される。これらには、血中コレステロール(CH)やトリグリセリド(TG)の値を減少させるなど脂質低下作用のあることが知られている。しかし、いずれの化合物も、含有量が少ない、生理作用が弱い、不安定で容易に酸化される、分解されやすい、工業的生産に不向きである等の欠点があるので、機能性食品として応用するためには、それらの欠点を解決する必要がある。本研究では、PaA誘導体の中で、比較的安定で酸化されにくく、工業的生産が容易なパンテテイン-S-スルホン酸(PaSSO_3H)に注目した。 PaSSO_3Hの生理作用に関する研究は、これまでビフィズス菌の成長促進因子としての観点から進められてきた。例えば、Bifidobacterium bifidum N4株を用いたPaSSO_3Hの代謝経路に関する研究では、PaSSO_3Hは、PaA誘導体の中で脂質低下作用を示し、機能性食品として用いられているパンテチン(PaSS)と、PaAから4'-ホスホパンテテイン(P-PaSH)を経てCoAに至る一連の代謝経路の中で、P-PaSH以降CoAまで同様の経路で代謝される。もし動物の生体内においても、PaSSO_3Hが細菌と同様の経路で代謝されるならば、PaSSと同様に脂質代謝に効果を持つ可能性がある。しかし、今までにPaSSO_3Hおよびその塩が脂質代謝に影響を及ぼすという報告はない。 PaSSO_3Hは粘稠性が高く結晶化が困難なので、本研究では、そのカルシウム塩のパンテテイン-S-スルホン酸カルシウム(PaSSO_3Ca)を用い、脂質低下作用およびその作用機序について以下の検討を行った。第1章 マウス、ラット、ハムスターおよびウズラの血中脂質に及ぼすPaSSO_3Caの影響 PaSSO_3Caの各種動物に対する脂質低下作用を調べた結果、脂質低下作用に種差が存在し、血中CH低下作用はマウス、ハムスターおよびウズラにおいて、血中TG低下作用はマウス、ラットおよびハムスターにおいて認められた。このような種差が見られた理由としては、動物種による脂質およびリポタンパク代謝の違い、また、リノレン酸、ビタミンE誘導体あるいはセサミンに見られるような動物種による投与化合物への感受性の違いが考えられる。第2章 高CH飼料給与動物の脂質動態に及ぼすPaSSO_3Caの影響 高CH飼料で飼育した時の血中脂質に及ぼすPaSSO_3Caの影響を、マウス、ラット、ハムスター、ウズラおよびウサギを用いて検討した。 その結果、1%CH(0.5%コール酸ナトリウム(CA)含有)飼料で2週間飼育したマウスではCH低下作用を示さなかった。ハムスターでは、1%CH(0.2%CA含有)飼料での3週間飼育による血中CH上昇に対し、有意ではないが、低下傾向を示した。一方、1%CH(0.5%CA含有)飼料で2週間飼育したラットでは、1週間から2週間で有意(p<0.05)な血中CH低下作用を示した。他方、ウズラを0.5%CH(0.1%CA含有)飼料で飼育すると、4週間で血中CHは正常群の約6倍に上昇し、16週間目まで上昇した。この血中CH上昇に対し、PaSSO_3Caは観察期間中すべての週で有意(p<0.05)な低下作用を示した。さらに、ウサギを0.5%CH飼料で30日間飼育すると、血中CHは10日から30日まで上昇し、この上昇に対しPaSSO_3Caは21日目に有意(p<0.05)な低下作用を示した。第3章 実験的高CH・TG血症ラットに及ぼすPaSSO_3Caの影響 卵黄の2週間反復経口投与(卵黄:卵白=3:1、2mL/日)による高CH・TG血症、甲状腺ホルモン合成阻害剤であるPTU(6n-propyl-2-thiouracil)の2週間反復経口投与(1mmol/kg/日)による甲状腺機能低下時の高CH・TG血症、およびトライトン(界面活性剤、400mg/kg、静脈内単回投与)誘発高脂血症のモデルラットに対するPaSSO_3Caの脂質低下作用を検討した。 その結果、卵黄投与ラットでは無処置群ラットと比較し、血中CHおよびTGが上昇したが、PaSSO_3Caはこの無処置群ラットの両脂質の上昇を有意(p<0.05)に抑制した。PTU投与ラットでも、無処置群ラットより血中CHおよびTGが上昇し、PaSSO_3Caは、この両脂質の上昇を有意(p<0.05)に抑制した。また、トライトン投与によりラット血中CHおよびTGは、他のモデル同様上昇するが、PaSSO_3Caはこれに対しても有意(p<0.05)な上昇抑制効果を示した。第4章 実験的高TG血症および脂肪肝ラットに及ぼすPaSSO_3Caの影響 高TG血症および脂肪肝には、(1)血中TG分解酵素活性の低下による高TG血症モデル(アロキサン(AX)、イントラリポス(IL))、(2)外因性TG投与による高TG血症モデル(IL)、(3)脂肪組織からのFFA動員による高TG血症モデル(AX)、(4)脂肪の合成亢進による高TG血症モデル(フルクトース(FW)、AX)、(5)FFAの酸化障害性高TG血症・脂肪肝モデル(急性エタノール(ET)投与、慢性ET投与)、(6)VLDL合成障害による肝臓からのTGの血中への放出抑制による脂肪肝モデル(テトラサイクリン(TC)、オロチン酸(OA)、エチオニン(EN))、および(7)VLDL合成亢進による脂肪肝モデル(FW)などが知られている。そこで、それぞれのタイプの高TG血症および脂肪肝ラットを作成し、PaSSO_3Caの高TG血症および脂肪肝に対する効果について検討した。 その結果、AX、IL、FW、ETで誘発した高TG血症のラットにおける血中TG、およびET、TC、OA、ENで誘発した脂肪肝のラットにおける肝臓のTGに対して、PaSSO_3Caは有意(p<0.05)な低下作用を示すことを明らかにした。第5章 PaSSO_3Caの脂質低下作用機序の検討 第1節 高CH飼料給与ラットを用いたCH低下作用の機序 PaSSO_3Caの血中CH低下の作用機序について、1%CH(0.5%CA含有)飼料で2週間飼育したラットを用いて、PaSSO_3Caの、(1)CHの吸収、分布および胆汁中への排泄に及ぼす影響、(2)胆汁中への胆汁酸(BA)およびCHの排泄に及ぼす影響、(3)低比重リポタンパク(LDL)-CHの血中からの消失に及ぼす影響、(4)CHのふん中への排泄に及ぼす影響、および(5)肝臓における酢酸およびメバロン酸(MA)からのCH合成に及ぼす影響について、それぞれ検討した。 その結果、PaSSO_3Caは、(1)[^3H]-CH経口投与後の経時的な血中放射能レベル(48時間まで観察)から、CH吸収に影響しなかった。胆汁中への[^14C]-CH(静脈内投与)および[^3H]-CH(経口投与)由来の放射能の排泄量(CHあるいはBAを含む。48~50時間の2時間分)をそれぞれ高CH群の118%および120%に上昇させた。(2)高CH群に比較し、胆汁中へのBA排泄量を0~6時間で高CH群の118%に上昇し、CH排泄量に影響を与えなかった。(3)[^14C]-CHで標識したLDL-CHを多く含む血清を静脈内投与(3.7×10^6dpm/ラット)した後の、血中放射能([^14C]-CH)を経時的に測定したところ、血中からのCHの消失時間を0~30分で高CH群の約1/3に短縮した。(4)ふん中への[^14C]-CHおよび[^14C]-BAの排泄量を、高CH群の108%に上昇させた。(5)肝臓での[^14C]-酢酸および[^14C]-MAからの[^14C]-CH合成を、それぞれ高CH群の70%および68%に低下させた。 これらの結果から、PaSSO_3Caは腸管でのCHの吸収に影響を与えず、吸収されたCHのBAへの変換を促進し、BAの腸肝循環を阻害し、胆汁中およびふん中へのCHの排泄を早め、血中からのCH消失を促進することがわかった。一方、肝臓においても、PaSSO_3CaはMAからCHまでの合成経路を阻害することにより、肝臓中のCHを減少させることが判明した。 第2節 ラットの脂質動態に及ぼすPaSSO_3Caの作用 第1章において、市販ラット飼料で飼育したラット(正常群)に対し、PaSSO_3Caの2週間反復投与が血中CH値に影響を与えないことを明らかにした。この原因について、PaSSO_3Caの、(1)CHの吸収、分布および胆汁中への排泄に及ぼす影響、(2)胸管リンパからのCH吸収に及ぼす影響(摂食および絶食下で8時間まで観察)、(3)肝臓における酢酸からのCH合成に及ぼす影響について、それぞれ検討した。 その結果、PaSSO_3Caは、(1)[^3H]-CH経口投与後の経時的な血中放射能レベル(48時間まで観察)から、CH吸収を上昇させることが示された。胆汁中への[^14C]-CH(静脈内投与)および[^3H]-CH(経口投与)由来の放射能の排泄(CHあるいはBAを含む。48~50時間の2時間分)を、それぞれ正常群の117%および137%に上昇させた。胆汁中のBAおよびCHを測定したところ、BAは正常群の116%に上昇し、CH量に変化はなかった。(2)絶食下で胸管リンパ中へ分泌される累積CH量を、6および8時間で有意(p<0.05)に低下した。(3)肝臓で、[^14C]-酢酸からの[^14C]-CH合成を正常群の82%に低下した。 これらの結果から、ラットにおいてPaSSO_3Ca投与によりCHの消化管からの吸収が上昇し、これにより血中CHは正常値より一時的に上昇することが推察された。一方、肝臓において、CH生合成の抑制および胆汁中へのBAの排泄が増加することを明らかにした。また、血中ではCH消失が亢進して血中CHは減少し、正常値に戻ることを示した。このように、PaSSO_3Caは正常ラットの血中CHを低下させない機序を究明した。 第3節 ラットに対するPaSSO_3CaのTG低下作用の機序 第3章および第4章において、PaSSO_3Caは各種高TG血症または脂肪肝モデル動物の、血中および肝臓中のTG低下作用を示すことを、明らかにした。そこで、PaSSO_3Caの血中および肝臓中のTG低下作用の機序を究明するため、ラットを用いPaSSO_3Caの、(1)オリーブオイル(OO)吸収に及ぼす影響(OO投与後24時間まで観察)、(2)胸管リンパからのTG吸収に及ぼす影響(摂食および絶食下で8時間まで観察)、(3)絶食およびノルエピネフリン(NE)静脈内投与時の脂肪組織から血中への脂肪酸(FFA)遊離に及ぼす影響、(4)酢酸からのTG合成に及ぼす影響、(5)肝臓中のCoA量に及ぼす影響、(6)外因性TGの血中からの消失に及ぼす影響、(7)TG代謝関連酵素活性に及ぼす影響(1%CH飼料で飼育したラットおよびTC誘発脂肪肝ラット)、および(8)in vitroでのTG分解に及ぼす添加効果について、それぞれ検討した。 その結果、PaSSO_3Caは、(1)OO投与後の血中TG量を、12時間~24時間で有意(p<0.05)に低下させた。(2)絶食下で胸管リンパ中へ分泌される累積TG量を、4、6および8時間で有意(p<0.05)に低下させ、摂食下でその効果は消失した。(3)絶食およびNE投与により、上昇した血中FFAを有意(p<0.05)に低下させた。(4)[^14C]-酢酸からの[^14C]-TG合成を有意(p<0.05)に上昇させた。(5)肝臓中のCoA量を変化させなかった。(6)脂肪乳剤静注後の血中TGの消失を、対照群の60%に短縮させた。(7)高CH群に比較し、血中lipoprotein lipase(LPL)と肝性TG lipase(HTGL)の活性を上昇させた。TC処置群に比較し、血中LPLとHTGL活性を上昇させた。また、TC処置による肝臓中のTG上昇、血中TG低下を有意(p<0.05)に抑制した。(8)血中TG分解を亢進させ、LPL活性を上昇させた。 これら(6)、(7)および(8)の結果から、PaSSO_3Caによる血中TGの低下は、TGのFFAへの分解(異化)が原因であることが明らかとなった。さらに(3)の結果より、FFA動員の抑制もTG低下に影響を与えることを究明した。また、TC処置時の肝TG上昇、血中TG低下を有意に抑制したことで、PaSSO_3CaによるTGの肝臓からの放出促進が脂肪肝改善の作用機序として示唆された。 このように、脂質代謝の正常なマウス、ハムスター、ウズラに対しPaSSO_3Caは血中CHおよびTGの値を低下させる作用を有し、高CH飼料で飼育したラット、ウズラ、ウサギに対しても血中CH低下作用を示した。一方、PaSSO_3Caは卵黄、PTUおよびトライトン投与により作成した高脂血症ラットに対しても血中CHおよびTG低下作用を示し、AX、IL、FW、ET、TC、OAおよびENによって誘発される高TG血症と脂肪肝に対しても、TG低下作用を有することを見出した。さらに、PaSSO_3Caの持つ血中CH低下作用機序は、主に肝臓でのCHからBAへの変換の促進と、BAの腸肝循環の阻害によることを示した。また、血中TG低下作用機序は、TG分解系の酵素活性を上昇させることに起因することを究明した。
- 著者
- 篠原 陽子
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.1-7, 2014
これまでの研究で,非イオン界面活性剤水溶液を土壌を充填した層に吸引ろ過すると,非イオン界面活性剤(NPnEO)を捕捉・回収することができ,回収したNPnEOは再利用可能であることが明らかになった。このことは非イオン界面活性剤単独系で成り立つが,他の成分が共存する混合系の場合は成立するのかという課題が見出された。そこで,本報では,多成分系における捕捉率,回収率を調べ,それらの影響の有無を把握することを目的とし,非イオン界面活性剤(NP10,NP15,NP20)に,陰イオン界面活性剤(ドデシル硫酸ナトリウムSDS),無機ビルダー(硫酸ナトリウム),有機ビルダー(カルボキシメチルセルロースナトリウム)を混合した系で実験を行った。その結果,NP10(30 ppm)単独系の捕捉率95.6%に対して,硫酸ナトリウム(1.0%)を混合した系の捕捉率は93.1%,SDSを0.1%混合した系の捕捉率は90.5%,SDS 0.5%を混合した系の捕捉率は6.7%となり,単独系とSDS 0.5%混合系に有意差が認められた(Bonferroni,p<0.05)。捕捉率・回収率は,ビルダー混合よりも,陰イオン界面活性剤混合による影響が大きく,混合する濃度によって差がみられた。特に,NPnEOとSDSの濃度が臨界ミセル濃度(cmc)以上になると捕捉率・回収率が著しく低下し10%程度となり,SDSがNPnEOの捕捉を阻害していることが考えられた。以上のことから,混合系においてNPnEOの捕捉率を高めるためには,捕捉処理の過程で成分ごとに分離除去する必要があることが示唆された。
1 0 0 0 IR 女性雑誌出版史と『ナチ女性展望』NS Frauen Warte
- 著者
- 桑原 ヒサ子
- 出版者
- 敬和学園大学
- 雑誌
- 敬和学園大学研究紀要 = Bulletin of Keiwa College (ISSN:09178511)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.23-43, 2017-02
- 著者
- 桑原 ヒサ子
- 出版者
- 敬和学園大学
- 雑誌
- 人文社会科学研究所年報 (ISSN:24321869)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.37-70, 2011
1 0 0 0 書くこと/書かれたもの : 表現行為と表現
- 著者
- 埼玉大学教養学部日本・アジア文化専修課程編
- 出版者
- 埼玉大学教養学部 : [埼玉大学] 大学院人文社会科学研究科
- 巻号頁・発行日
- 2021
1 0 0 0 IR 「混沌」の闇
- 著者
- 高橋 憲昭
- 出版者
- 佛教大学社会学研究会
- 雑誌
- 佛大社会学 (ISSN:03859592)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-2, 1988-03-31
1 0 0 0 アトピー性皮膚炎を難治化させる黄色ブドウ球菌定着・感染症
- 著者
- 岩月 啓氏 大野 貴司 山崎 修
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.Suppl.7, pp.B29-B32, 2006 (Released:2011-03-11)
- 参考文献数
- 16
アトピー性皮膚炎の増悪因子の一つとして黄色ブドウ球菌は重要である。黄色ブドウ球菌表面のタイコ酸はTh2型免疫応答へシフトさせ,protein Aは表皮角化細胞からIL-18を持続的に産生させる。Enterotoxin A(SEA)とB(SEB)は,正常表皮角化細胞にICAM-1 やHLA-DRを発現させる。また,アトピー性皮膚炎患者の半数以上はSEAまたはSEBの両方あるいはいずれか一方に対するIgE型抗体を有する。SEBの経表皮的感作によって真皮に好酸球や単核球細胞浸潤を誘導でき,Th2型サイトカインであるIL-4 mRNA発現を起こすが,Th1型サイトカインのIFN-γは発現しない。最近,スーパー抗原によって制御T細胞(Treg)の機能である抑制効果が失われることが示された。黄色ブドウ球菌はその菌体成分や外毒素によってアトピー性皮膚炎を増悪させる。しかし,皮膚に定着している黄色ブドウ球菌を完全に除菌し,無菌状態に保つことはできない。角層内でバイオフィルムに包まれて静止期にあるような定着(colonization)した黄色ブドウ球菌に対しては,抗菌療法も消毒も十分な効果発現は期待できない。皮膚を清潔に保ち,適切なアトピー性皮膚炎治療を実施することにより,黄色ブドウ球菌を増えすぎないようにコントロールして,正常細菌叢と仲良くするストラテジーが理想的と思われる。
1 0 0 0 OA 知識と行動の不一致に見られる不安全避難行動の危険認知に関する心理実験的検討
- 著者
- 田中 孝治 梅野 光平 池田 満 堀 雅洋
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.356-367, 2015-09-01 (Released:2016-03-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 8
It is not difficult for residents, for the most cases, to know the knowledge of disasterprevention, while it is quite difficult for them to take appropriate evacuation behavior.For example, it is easy to know why flooded underpasses should not be gone through bycars. It is just because cars would be submerged and got stuck on the way. However,people sometimes fail to apply such knowledge to take an appropriate action, due tothe so-called knowledge-to-action gap. In the present study, a preliminary investiga-tion and two experiments were conducted. The purpose of the investigation is to clarifythe kinds of unsafe evacuation behavior with reference to newspaper articles on flooddisaster over the past 15 years. The two experiments are to examine if the knowledge-to-action gap can be confirmed by means of paper-and-pencil tests consisting of knowledgeand intention tasks. Preliminary investigation revealed ten kinds of unsafe evacuationbehaviors in flood disaster. Experiments 1 and 2 indicated that participants take unsafeevacuation behaviors even though they have appropriate knowledge. In addition, theexperiment 2 indicated that they perceived danger in unsafe evacuation behaviors andflood disaster situation.These results demonstrate an aspect of unsafe evacuation be-havior, and the importance of disaster prevention education, which has to be carefullydesigned to bridge the gap between knowledge and action for disaster prevention.
1 0 0 0 OA 音楽が身体に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 三小田 美稲子
- 出版者
- 国士舘大学体育学部附属体育研究所
- 雑誌
- 国士舘大学体育研究所報 (ISSN:03892247)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, 2014
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.639, 2016-05-09
セグメントの崩落は予見が困難で、刑事上の過失責任を問うことはできない──。 2012年2月に岡山県倉敷市で6人の死傷者を出した海底シールドトンネル事故で、岡山地方検察庁は3月31日、業務上過失致死傷の容疑で書類送検された鹿島の元所長ら4人を不起訴とし…
- 著者
- 佐藤 一郎
- 出版者
- 城西大学現代政策学部
- 雑誌
- 城西現代政策研究 = Josai contemporary policies researches (ISSN:18819001)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.57-72, 2020-12
2020 年4 月から導入された高等教育の修学支援新制度(いわゆる「高等教育無償化制度」)では、この制度を受け入れる高等教育機関(大学等)に機関要件として、一定の条件を満たした実務家教員(実務経験のある教員)による授業を指定時間数組み入れること等が義務付けられた。実務家教員の採用自体は、従来からも各大学で行われている。今回の制度によって求められる実務家教員の役割には、これまでと異なるところがあるのだろうか。本稿では、若手社員の早期離職が雇用する企業側にも、また退職者自身のキャリア・プランにも大きな問題となっていることに着目する。この改善のために、実務家教員が自らの経験を活かして在学生に働きかけを行い、卒業後の早期離職を減少させる動機付けをすべきことを、人的資源管理(HRM)分野の「Realistic Job Preview (R.J.P.)」という概念を軸に提案する。A new system of tertiary education learning support (so-called free tertiary education) was introduced from April 2020, and tertiary institutions that adopt this system must meet certain conditions.One of them is that it is now obligatory for institutions to offer classes taught by teaching practitioners (teachers with practical experience) for a specific number of hours.Until now, the hiring of practitioner faculty members has been left to each individual university. Will there any difference in the expected role of teaching practitioners under the new system?In this paper, the author focuses on the issue of newly employed graduates having a tendency of quitting soon after beginning work, which presents a major problem for companies, as well for the futures of the graduate themselves.In order to improve this situation, it is proposed that teaching practitioners should use their experiences to reach out to current students and motivate them in order to reduce numbers who quit soon after beginning work, according to the model of Realistic Job Preview (RJP), in the field of human resource management (HRM).研究ノート
- 著者
- 水戸 博道
- 出版者
- 明治学院大学心理学部
- 雑誌
- 明治学院大学心理学紀要 = Meiji Gakuin University bulletin of psychology (ISSN:18802494)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.69-80, 2017-03-08
本研究は、移調楽器の学習者がどのように音楽的音高の言語的符号化をおこなっているか、その多様性に注目し、実態を明らかにした。調査は符号化の多様な事例を明確にしていくことを目的とし、10名の移調楽器学習者が、実際の音楽活動の場で、どのように音高の符号化をおこなっているのかを、インタビューと歌唱テストによって調査した。また、異なる符号化の事例が、絶対音感などの音感とどのような関係にあるのかを検討するために、すべての参加者に絶対音感テストを実施し、その成績と符号化の方略の関連に関しても、個別に考察していった。考察の結果、ほとんどの参加者は、なんらかの形で音高の符号化をおこなっているが、音感の違いや演奏する楽器によって、符号化の運用の方略は同一ではないことが浮かび上がった。非常に正確な絶対音感をもっている者は、移調楽器を演奏する時でも、移調譜に基づいて音高を符号化して聴くことが難しいことがわかった。一方で、絶対音感をもっていない者に加え、ある程度の絶対音感をもっている者は、移調譜の音名で符号化ができている参加者もいることがわかった。これらの結果より、音高の符号化は、必ずしも絶対音感などに縛られたものではなく、複数の符号化システムを併用していくことも可能であることが示唆された。
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1945年10月17日, 1945-10-17
In Japan, studies on "community" and the reality of everyday life in the city have been both assumed and largely ignored by geographers. This study, in exploring the role of various social bonds within a local area and the influence of some institutions on its bonds, attempts to clarify some aspects of "community" and its transformation in the city. Though "community" is a highly ambiguous notion, it could be defined as the complete range of relationships an individual is led to establish with other peoples within definite place and that members of it conform to certain unwritten rules or informal norms which can't be applied to outsiders.The research field for this study is Hakata, Fukuoka City, from the 1910's to the 1930's. In Hakata, the "Hakata Yamakasa" has long been held and is one of the most famous festivals in Japan.The main results of this study are summarised as follows:1) There is a mutually supportive role of neighbors materially and emotionally. The inhabitants conform to informal norms, for example, the duty of mutual aids at ceramonial occasions and payment of money used for local community's everyday expenses.In consumption, the inhabitants buy daily necessfties mainly through pedlars and retailers who depend on face-to-face local interaction. It seems that this mode of buying has a potential role in the reinforcement of connection within the neighborhood.Though it is clear that the residents keep close contact with each other, we must pay attention to the difference of these interactions according to gender, age, occupation, socio-economic status and so forth.2) As at "Yamakasa" the various and heterogeneous residents are integrated together in the internal system, they recognize each other as members of the local community and preserve identity and loyaly to their own community through various observances. This identity is necessary for the formation and maintenance of community. The division between the internal system and the external one is kept strictly during the festival. This is, however, not absolute and consistent, but relative and contingent. The nature of each grovp is context-bounded and contingent on two relationships, both intragroup-relation and intergroup-relation. The author emphasizes the contingency of these relationships and the relationship with externalities at various levels.3) In the process of modernization and urbanization, the intervention of administration and capital to the local community is thorugh the labor process, consumption and relief of the poor, etc. Although from the standpoint of inhabitants, local community forms an 'absolute territory' which can be a place of identity, from the standpoint of capital, it is a 'relative territory' and an obstacle to capital interests occasionally. The new systems gradually include or substitute for the existing institutions and social order or norms which depend on mutuality within the local community. In short, these institutions make individuals subject to control and the accumulation of capital. It seems, however, that there are cases where through the struggle around these institutions a different consciousness from the old one is generated.
1 0 0 0 OA go get 構文についての一考察:形態統語論からのアプローチ
- 著者
- 山田 昌史
- 出版者
- 常葉大学外国語学部
- 雑誌
- 常葉大学外国語学部紀要 = Tokoha University Faculty of Foreign Studies research review (ISSN:21884358)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.107-114, 2017-03-01
本稿は、英語の口語表現にみられるgo get 構文について、これまで観察されてきた事実に、Corpus of Contemporary American English (= COCA) からの検索例を加えて、この構文に特異的に見られるbare-stem condition(cf. Carden & Pesetsky(1977))について確認した。そして、この構文の理論的な説明を試みるBjorkman (2010)を批判的に検討して、形態統語論の立場から新たな分析を提示した。具体的には、既に複合している複合語の外側には新たな形態素を複合できないとするMyers(1984)の一般化を援用することで、複合動詞の外側に新たな形態素が付与できないと分析することで、この構文が動詞の原形しか生じることができないことを理論的に説明した。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ものづくり (ISSN:13492772)
- 巻号頁・発行日
- no.789, pp.59-61, 2020-06
受注減によって製品の生産量が減少している。開発・設計の領域でも、リモートワークの影響などで顧客や設計者間でのコミュニケーションを取りづらい状況がある─。日経ものづくりが2020年5月中旬に実施したアンケート調査「新型コロナ流行の製造業に与える影響…
- 著者
- 木村 惠司
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1302, pp.129-132, 2005-08-01
大阪市北区の複合施設「大阪アメニティパーク(OAP)」の土壌汚染問題で、6月29日、前社長の高木茂が引責辞任し、私が三菱地所の社長に就任しました(編集部注:大阪府警は3月29日、宅地建物取引業法違反=重要事項の不告知=容疑で、法人としての三菱地所と高木前社長などを書類送検した。5月27日に引責辞任を発表。6月10日に不起訴処分が下されている)。
1 0 0 0 ファミマ上田会長が激白 3位では生き残れない
- 著者
- 上田 準二 飯田 展久
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1821, pp.46-49, 2015-12-21
ファミリーマートとユニーグループ・ホールディングスが経営統合する。水面下で交渉を主導してきたファミマの上田準二会長が統合に懸ける思いを語る。統合後に描く姿とは。