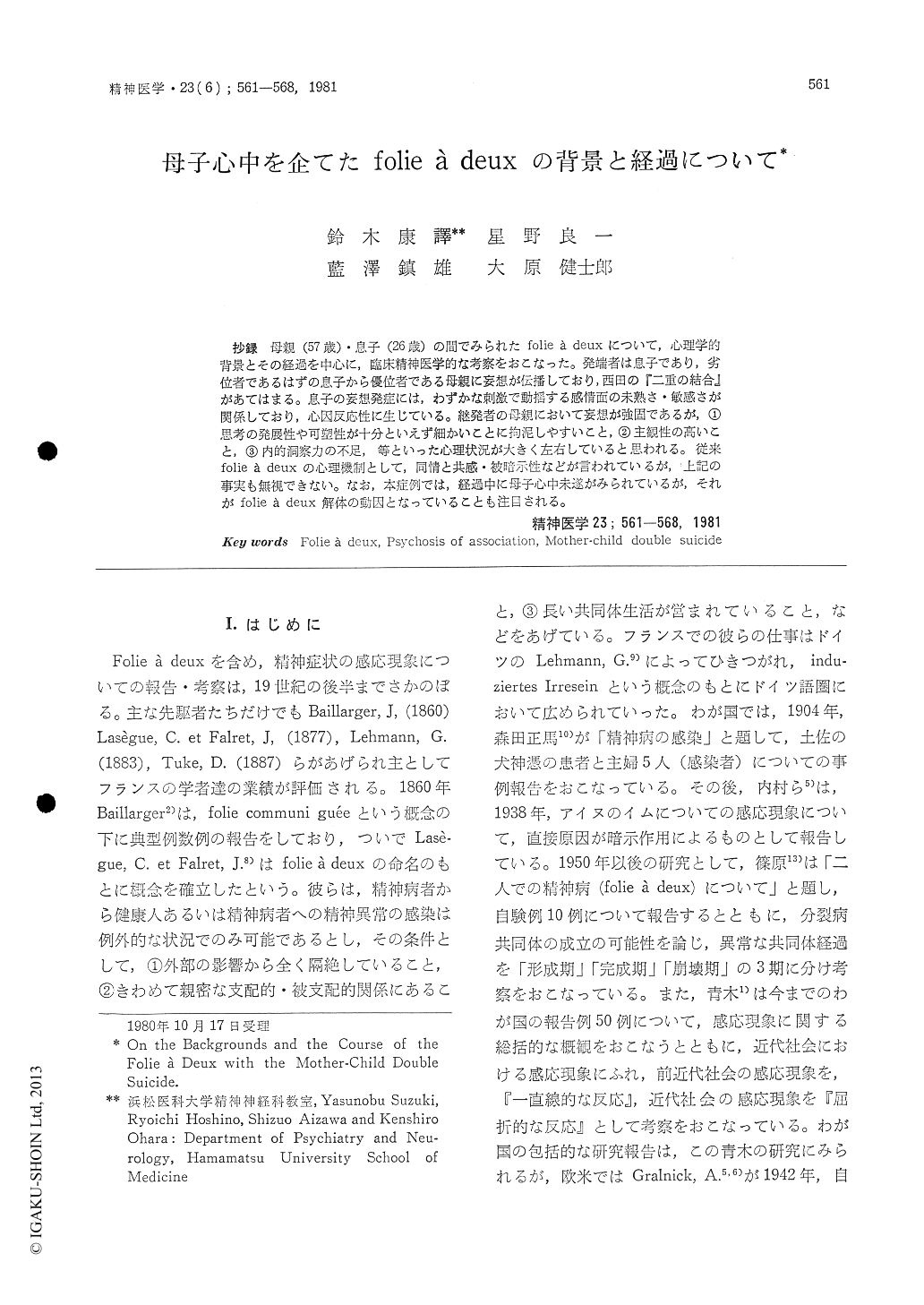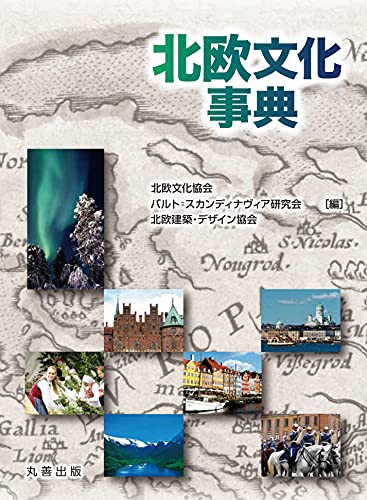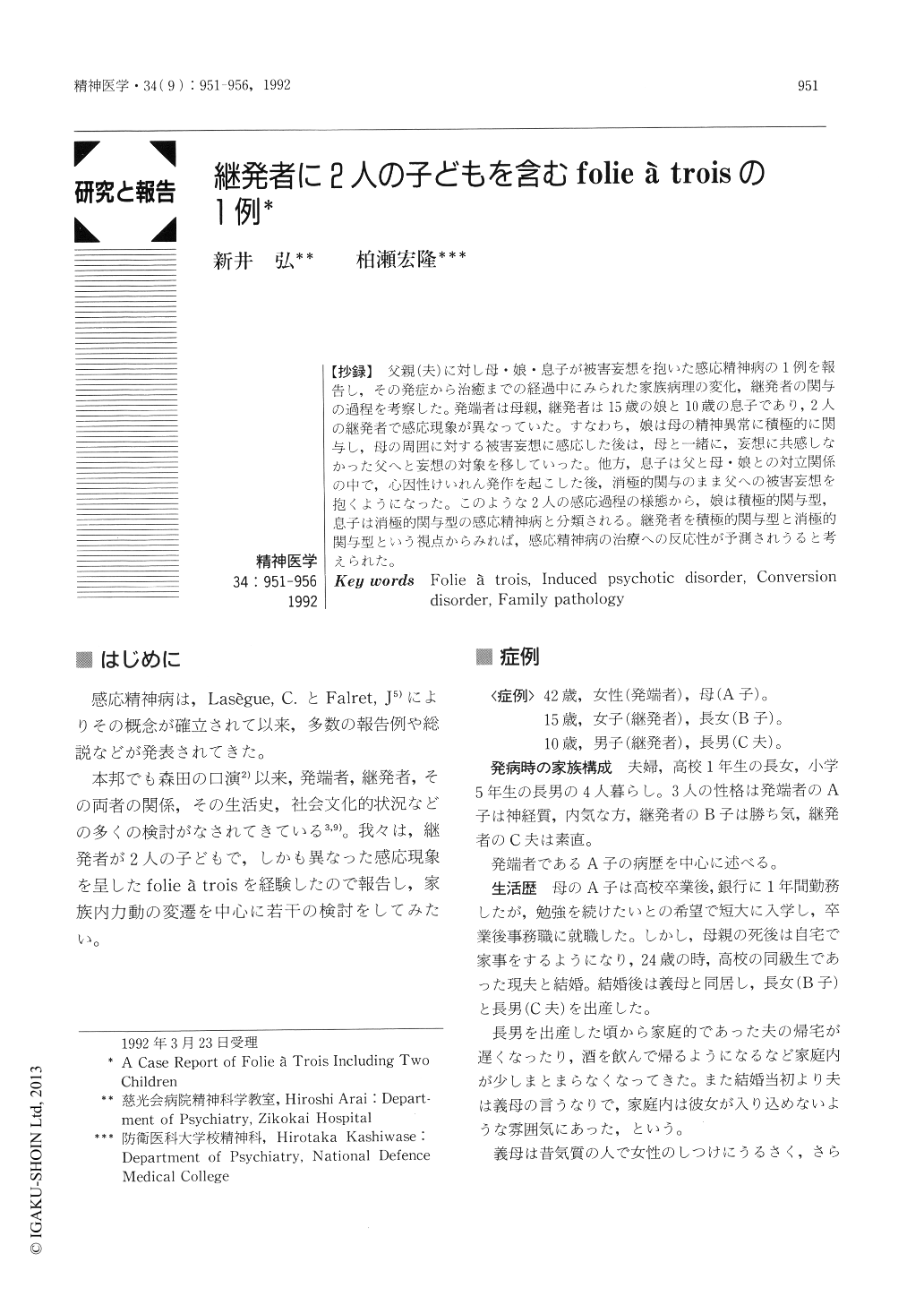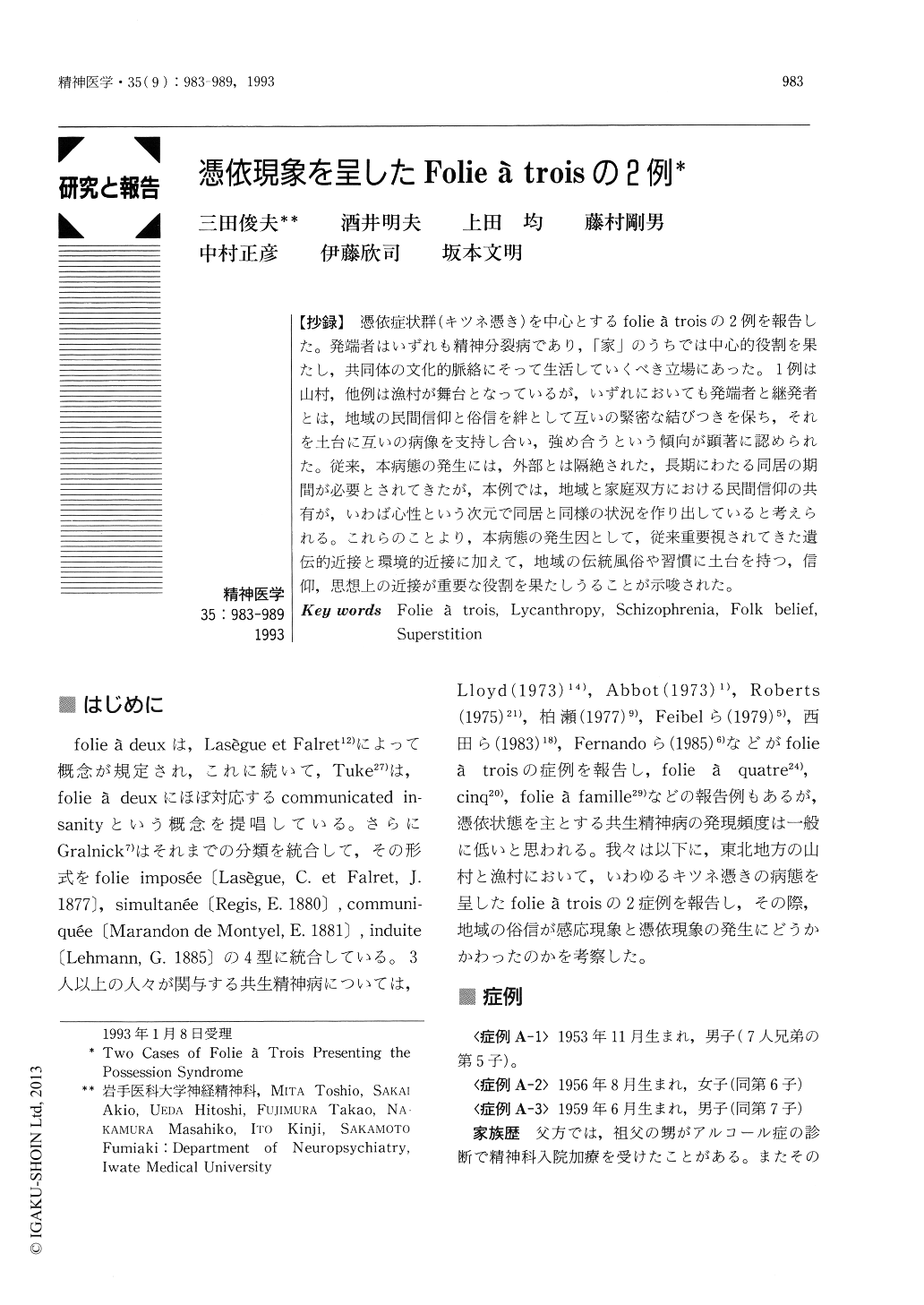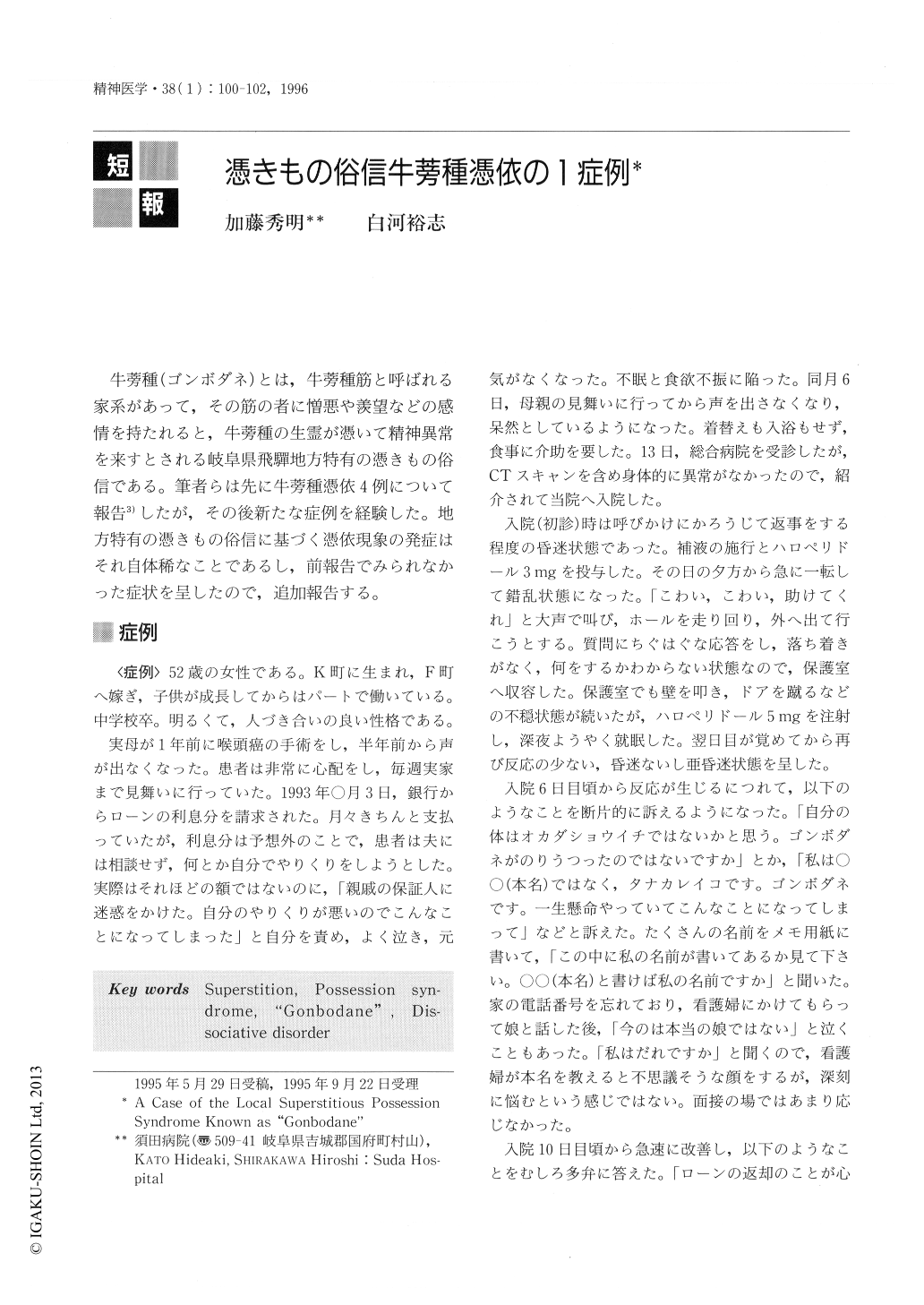1 0 0 0 公文書管理をめぐる近年の動き : 適正な文書管理に向けた取組
- 著者
- 岡田 智明
- 出版者
- 参議院事務局
- 雑誌
- 立法と調査 (ISSN:09151338)
- 巻号頁・発行日
- no.428, pp.66-81, 2020-10
1 0 0 0 OA 虚構の永久機関 : 金井美恵子「兎」と<幻想>の論理
- 著者
- 中村 三春
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.33-42, 1992-02-10 (Released:2017-08-01)
<書くこと>について書くことを一貫して課題としてきた金井美恵子の言説は、文芸の根幹をなす虚構についての原則論的な追求を核心としている。発条を失った私小説的風土にあって、虚構についての究極の洞察を示す金井の文芸様式は、虚構を論ずる際に決して避けて通ることができない。本稿は、初期の短編「兎」(一九七二・六)の<額縁構造>を焦点とし、虚構を<読むこと>へとシフトしつつ、金井文芸を論じたものである。
1 0 0 0 OA 『石蹴り遊び』: メタレベルの非在をめぐって
- 著者
- 井尻 直志
- 出版者
- ASOCIACION JAPONESA DE HISPANISTAS
- 雑誌
- HISPANICA / HISPÁNICA (ISSN:09107789)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.50, pp.95-114, 2006-12-25 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 24
Rayuela (1963), la obra principal de Julio Cortázar (1914-1984), es muchos libros, como el autor mismo indica en “Tablero de dirección”. Está escrita como novela de cada lector, de quien se espera que sea algo más que un espectador pasivo. Entre los muchos libros posibles, como texto para analizar en este trabajo escogemos “el segundo libro” que empieza en el capitulo 73. A nuestro parecer, este texto, además de ser una “obra abierta” o una “obra en movimiento” según la terminologia plasmada por Umberto Eco en Opera aperta aparecida en 1962, un año antes de la publicación de Rayuela, es por excelencia una meta-novela.Aunque, al hablar de la estructura meta-novelística de Rayuela, se suele aludir a la función que desempeña Morelli o a sus comentarios que describen algunas de las coordenadas de la novela, tal estructura la podemos observar ya en el primer capítulo del “segundo libro”. En todo caso Rayuela es una novela que se refleja sobre sí misma.Partiendo de esta premisa, hemos estudiado el tema principal de la obra: la búsqueda de la Maga que Oliveira pretende realizar. Oliveira quiere encontrar a la Maga, que simboliza “el cielo”, “el centro” o “el kibbutz del deseo”, para llegar a un universo que esta fuera del alcance de la dialectica. El universo en el que no existe ningún tipo de dicotomía, para nosotros que seguimos la teoría del universo indicada por SpencerBrown en Laws of Form, es el universo en el que no existe el meta-nivel o el ser trascendental. En el presente trabajo hemos intentado aclarar lo siguiente: el hecho de que Rayuela sea una novela en la que no existe el meta-nivel aparece reflejado en el tema principal de la obra y ello pone aún más de relieve el cáracter auto-referencial de la misma.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1134, pp.36-39, 2002-03-25
2月以降、相場上昇が続く東京株式市場。日経平均株価が年初来高値を更新する株価ボードをにらみながら、松井道夫・松井証券社長は社員にクギを刺した。「いいか、この相場は異常なんだ。今に東証1部売買高が1日3000億円の日がやってくるかもしれんぞ」。 東証1部の売買高はこのところ、1日1兆円を超す日も多い。半日しか取引がない今年1月4日の大発会でさえ4400億円あった。
1 0 0 0 IR 『看聞日記』現代語訳(一六)
- 著者
- 薗部 寿樹
- 出版者
- 米沢史学会
- 雑誌
- 米沢史学 (ISSN:09114262)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.107-125, 2019-10-20
1 0 0 0 OA 森林からの蒸発散(Ⅰ)
- 著者
- 三上 正男
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.45-62, 1997-02-01 (Released:2019-03-28)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 母子心中を企てたfolie à deuxの背景と経過について
抄録 母親(57歳)・息子(26歳)の間でみられたfolie à deuxについて,心理学的背景とその経過を中心に,臨床精神医学的な考察をおこなった。発端者は息子であり,劣位者であるはずの息子から優位者である母親に妄想が伝播しており,西田の『二重の結合』があてはまる。息子の妄想発症には,わずかな刺激で動揺する感情面の未熟さ・敏感さが関係しており,心因反応性に生じている。継発者の母親において妄想が強固であるが,①思考の発展性や可塑性が十分といえず細かいことに拘泥しやすいこと,②主観性の高いこと,③内的洞察力の不足,等といった心理状況が大きく左右していると思われる。従来folie à deuxの心理機制として,同情と共感・被暗示性などが言われているが,上記の事実も無視できない。なお,本症例では,経過中に母子心中未遂がみられているが,それがfolie à deux解体の動因となっていることも注目される。
1 0 0 0 北欧文化事典
- 著者
- 北欧文化協会 バルト=スカンディナヴィア研究会 北欧建築・デザイン協会編
- 出版者
- 丸善出版
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 継発者に2人の子どもを含むfolie à troisの1例
【抄録】 父親(夫)に対し母・娘・息子が被害妄想を抱いた感応精神病の1例を報告し,その発症から治癒までの経過中にみられた家族病理の変化,継発者の関与の過程を考察した。発端者は母親,継発者は15歳の娘と10歳の息子であり,2人の継発者で感応現象が異なっていた。すなわち,娘は母の精神異常に積極的に関与し,母の周囲に対する被害妄想に感応した後は,母と一緒に,妄想に共感しなかった父へと妄想の対象を移していった。他方,息子は父と母・娘との対立関係の中で,心因性けいれん発作を起こした後,消極的関与のまま父への被害妄想を抱くようになった。このような2人の感応過程の様態から,娘は積極的関与型,息子は消極的関与型の感応精神病と分類される。継発者を積極的関与型と消極的関与型という視点からみれば,感応精神病の治療への反応性が予測されうると考えられた。
1 0 0 0 OA 宇宙放射線の観測
- 著者
- 槙野 文命 Makino Fumiyoshi
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構特別資料 = JAXA Special Publication (ISSN:1349113X)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-SP-12-007, pp.1-210, 2013-03-29
資料番号: AA0061888000
1 0 0 0 憑依現象を呈したFolie à troisの2例
【抄録】 憑依症状群(キツネ憑き)を中心とするfolie à troisの2例を報告した。発端者はいずれも精神分裂病であり,「家」のうちでは中心的役割を果たし,共同体の文化的脈絡にそって生活していくべき立場にあった。1例は山村,他例は漁村が舞台となっているが,いずれにおいても発端者と継発者とは,地域の民間信仰と俗信を絆として互いの緊密な結びつきを保ち,それを土台に互いの病像を支持し合い,強め合うという傾向が顕著に認められた。従来,本病態の発生には,外部とは隔絶された,長期にわたる同居の期間が必要とされてきたが,本例では,地域と家庭双方における民間信仰の共有が,いわば心性という次元で同居と同様の状況を作り出していると考えられる。これらのことより,本病態の発生因として,従来重要視されてきた遺伝的近接と環境的近接に加えて,地域の伝統風俗や習慣に土台を持つ,信仰,思想上の近接が重要な役割を果たしうることが示唆された。
1 0 0 0 憑きもの俗信牛蒡種憑依の1症例
- 著者
- 笹田 直人
- 出版者
- 青土社
- 雑誌
- ユリイカ (ISSN:13425641)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.8, pp.52-65, 1997-06
- 著者
- 大内 孝
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.146-164, 2020-09-30
- 著者
- ヴァッカーナーゲル マリアンヌ
- 出版者
- 別府大学文学部芸術文化学会
- 雑誌
- 芸術学論叢 (ISSN:09143149)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.27-34, 2000
- 著者
- 平野 修也 山田 義智 西 祐宜 崎原 康平
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.774, pp.993-1003, 2020
- 被引用文献数
- 4
<p> In order to conduct flow analysis of cement-based material such as cement paste, mortar and concrete, it is important to more accurately obtain the rheological constants representing the flow characteristics of the material. In this study, the rheological constants of mortar were measured by two rheology tests. The first was sphere pull-up test, the second was the measurement by using rotational vane viscometer. According to previous studies, the former was able to measure the rheological constants of high fluidity mortar, and the latter was able to evaluate the shear stress characteristics of cement-based material containing fine aggregate and coarse aggregate. Furthermore, in this study, the flow constitutive equation of mortar was derived and Moving Particle Semi-implicit (MPS) method was proposed. Using this MPS method, flow simulation of mini slump flow test was attempted.</p><p> The results obtained from the experimental study and analytical study in this paper can be summarized as follows.</p><p> Throughout the sphere pull-up test, the rheological constants (yield value and plastic viscosity) of mortar which was the same mix proportion as mini slump tested mortar were measured. In the test results, the larger mini slump flow value was, the lower yield value was, and the relationship between the two values was able to be approximated by an exponential curve. On the other hand, plastic viscosity and arrival time at mini slump flow of 115mm had positive correlation, and the relationship between the two values was able to be approximated by a linear function.</p><p> Using a rotational vane viscometer, the flow curve of mortar was measured for various shear conditions. It was confirmed that the flow curves of all mortar samples were able to be approximated by the Bingham model under all shear conditions. And the obtained flow curve was approximated by the Bingham model, and the rheological constants of all mortar sample was determined. Thixotropy was confirmed in the flow characteristics of the mortar sample from the obtained flow curves. Also, contrary to the general tendency, the larger mini slump flow value was, the higher plastic viscosity was for water cement ratio of 30%. It was suggested that the rheological constants measured by rotating vane blade were affected by amplified apparent viscosity of mortar. As a result, the sphere pull-up test was more appropriate for the evaluation of rheological properties of mini slump flows.</p><p> Applying the polygon model to the wall boundary as boundary condition of MPS method, a phenomenon that mini slump flow was shielded by mini slump cone was expressed on the flow analysis. Adopting the rheological constants obtained by the sphere pull-up test, it was attempted that mini slump flow spread of mortar sample was reproduced by MPS analysis. The results obtained by the analysis agreed well with the experimental results of mini slump flow. Moreover, in terms of mini slump shape, the analysis by MPS method largely reproduced the actual measured shape. Furthermore, following the analysis condition used in mini slump flow analysis, mortar flow spread with slump cone was predicted by MPS analysis. The results obtained by the analysis reproduced the actual measured value of slump flow. Therefore, the analysis by MPS method and the rheological constants obtained by the sphere pull-up test are effective in mortar flow spread.</p>
1 0 0 0 2019年学界展望 歴史地理 近・現代
- 著者
- 花木 宏直
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.291-294, 2020
- 著者
- 保坂 雅子
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集 (ISSN:21898928)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.36-37, 2020
- 著者
- 森近 翔伍 関屋 英彦 田井 政行 高木 真人 丸山 收 三木 千壽
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集A2(応用力学)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.48-57, 2020
<p> 疲労き裂に対する補修・補強を行う際,発見したき裂の大きさ,特に深さを把握することが重要である.き裂先端近傍の応力分布の強さを示す物理量である応力拡大係数(K値)は,き裂深さの情報を含むため,現場にて簡易にK値を推定出来れば,推定したK値からき裂深さの推定が可能である.</p><p> そこで本研究では,き裂先端のひずみ分布に基づく非貫通き裂に対するK値の推定方法と,推定したK値による,き裂深さの推定手法について検討した.初めに,き裂形状および鋼板寸法をパラメーターとした数値解析を実施し,K値に基づくき裂深さの推定手法を提案した.次に,提案手法の実用性を検証するため,引張試験片による疲労試験を実施した.その結果,き裂形状に依らず,誤差28%以内の精度にて,非貫通き裂のき裂深さの推定ができる可能性を示した.</p>
- 著者
- 名嶋 義直
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.5-20, 2020
<p>グローバル化という世界的な変化の流れを考えれば,日本社会の目指す方向は「多様性に寛容な,ゆるやかな結束性を持つ社会」であろう.そこでの「新しい学習・教育」を考えた時,言語研究者には何ができるだろうか.本稿ではドイツや欧州評議会で展開されている「民主的シティズンシップ教育」に「新しい学習・教育」としての可能性を見出す.その上で,それをただ模倣するのではなくローカライズすることが重要であり,それを行えば,民主的シティズンシップ教育はさまざまな場面や手法で実践が可能であることを述べる.そして,多様な他者と「対話」を通して主体的に関わる活動の例を挙げ,「民主的シティズンシップ教育」が有する「新しい学習・教育」としての可能性を論じる.</p>