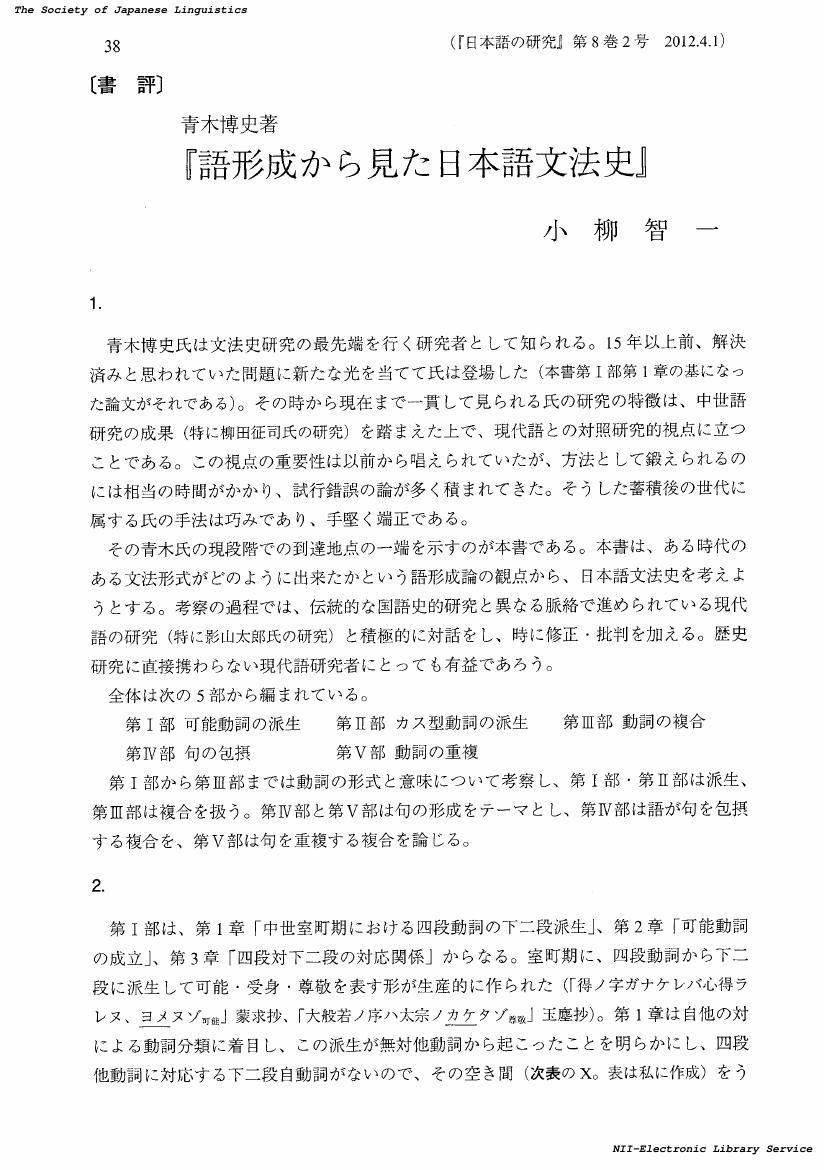1 0 0 0 OA 『プラマーナヴィニシュチャヤ』第3章におけるダルマキールティの帰謬論証
- 著者
- 吉水 千鶴子
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.1246-1254, 2016-03-25 (Released:2017-09-01)
- 被引用文献数
- 1
ダルマキールティはその著書『プラマーナヴィニシュチャヤ』第3章「他者のための推論」の中で,帰謬論証の例をあげる.帰謬(プラサンガ)論証は対論者の主張を論駁するためのものであり,相手の主張から主題とその属性を借用し,それを前提条件として,そこから相手にとって不合理な結論を導き,相手の主張の矛盾を指摘することにより論駁する仮言論証である.ダルマキールティも帰謬論証が対論者によって構想された属性にもとづくことは認めているが,彼が提示する論証式は以下の点で,それまでの帰謬論証とは大きく性格を異にする.(1)論証因を用いること,(2)仮言的表現を用いないこと,(3)遍充関係に相当する論証因と帰結の二つの属性の必然的関係が肯定的否定的遍充の両方で示されること,(4)その必然的関係は実在にもとづくこと.さらに,ダルマキールティが考える「論証因」は,借り物の主題の属性にはなり得ないが,そのような主題を離れれば,正しい認識(プラマーナ)によって成立し,対論者立論者両方によって認められるものである.その「論証因」から必然的に導き出される帰結は論理的帰結であり,誰もが認めざるを得ないものである.このような論証因の導入は革新的なことであったが,これなくして説得力をもった対論者の論駁はなしえないとダルマキールティは考えたのであろう.本論文は,このような彼の意図を明らかにすると同時に,彼が用いる「本性」(svabhava)という語は自らの存在そのものを指すのではないか,また「本来的論証因」(maulahetu)は「自らの理解,認識に根ざした論証因」すなわち他者のための推論にいうところの「自ら認めたもの」(svadrstartha)を指すのではないか,という解釈を提示した.
- 著者
- 小柳 智一
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.38-44, 2012-04-01 (Released:2017-07-28)
1 0 0 0 OA 精神科看護師が行う長期入院患者に対する退院支援の内容―メタ統合による看護実践知の集約―
- 著者
- 川田 陽子 田嶋 長子
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.29-35, 2019-06-30 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 〔追悼〕熊田禎宣先生を悼む
1 0 0 0 ベルト固定を用いたハンドヘルドダイナモメーターによる等尺性膝伸展筋力測定におけるtest-retest再現性,および病棟内杖歩行自立のカットオフ値の検討:大腿骨近位部骨折術後入院患者を対象とした検討
- 著者
- 金子 義弘 加藤 宗規
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48100178, 2013
【はじめに、目的】ハンドヘルドダイナモメーター(以下,HHD)は安価で簡便な筋力測定方法である一方,膝伸展筋力など高い筋力値を測定する場合においては,徒手による固定方法では検者間による測定誤差が生じる可能性がある.この欠点を補うため,徒手に代わり運動を固定する固定用ベルトを使用した計測方法が考案され,先行研究では同一日でのtest-retest再現性について,若年および高齢健常者,脳血管疾患患者において良好な結果であったことが報告されている.しかし,運動器疾患を有する患者における再現性については報告されていない.そこで,本研究では,大腿骨近位部骨折術後の入院患者における本法のtest-retest再現性を検討するとともに,膝伸展筋力値による病棟内杖歩行自立のカットオフ値について検討した.【方法】対象は,大腿骨近位部骨折にて当院入院中で重度な認知症状がなく,免荷指示やその他の影響する疾患を有さない76名(女性60名,男性16名)である.内訳は,平均年齢80歳(55-97歳),平均体重46.7±10.3kg,手術内容は全人工関節置換術1名,人工骨頭置換術41名,骨接合術34名,手術から計測までの平均日数は26.5±8.4日であった.骨折に至った転倒原因は不明だが,計測時の移動能力は病棟内杖歩行自立以上が31名,杖歩行監視以下が45名であった.大腿四頭筋筋力の測定は椅子座位でアニマ社製等尺性筋力測定器 μTas MF-01を使用した.測定にあたり,被検者は体幹をベッドと垂直にして座り,両側上肢は体側両脇に位置して手をベッド面につき体幹を支持した.そして,パッドを含めセンサーを面ファスナーで被検者の下腿遠位部前面で足関節内果上縁の高さに固定し,さらに固定用ベルトでセンサーおよび下腿をベッド脚に固定した.測定肢の膝窩に折りたたんだバスタオルを入れ,測定時に大腿が床面と水平になるようにしたとともに,膝関節が90°屈曲位になるようにベルトの長さを調節した.等尺性膝伸展筋力は,5秒間の最大努力中における最大値として,健側および患側について各3回実施した.そして得られた結果から,3回の測定における再現性について,級内相関係数[The intraclass correlation coefficient;以下,ICC]と対応のある因子の一元配置分散分析により検討した.また,3回の最大値を採用した膝伸展筋力体重比を算出し,Receiver Operatorating Characteristic curveを用いて膝伸展筋力体重比による病棟内杖歩行自立のカットオフ値を検討した.なお,危険率は5%とした.【倫理的配慮、説明と同意】対象者や家族には,研究の目的と方法,およびデータの管理と使用について書面を用いた説明を行い,同意を得た.【結果】膝伸展筋力測定の結果,健側の平均値(±標準偏差)は,1回目12.6±7.6 kgf/kg,2回目13.6±7.8 kgf/kg,3回目13.6±7.4 kgf/kg,患側の平均値は1回目7.6±4.3 kgf/kg,2回目8.2±4.3 kgf/kg,3回目8.5±4.4 kgf/kgであり,一元配置分散分析では両側ともに主効果を認めなかった.3回の測定の再現性について,ICC(1,1)の値は,健側が0.944(95%信頼区間;0.920-0.962),患側がICC=0.953(95%信頼区間;0.932-0.968)であった.また,3回の最大値を採用した体重比の平均値は,健側0.30±0.14 kgf/kg,患側0.19±0.08 kgf/kg,両側の平均値は0.24±0.10 kgf/kgであった.体重比による病棟内杖歩行自立のカットオフ値について,健側0.25 kgf/kg(感度0.65,特異度0.80),患側0.17 kgf/kg(感度0.80,特異度0.73),健患平均0.20 kgf/kg(感度0.70,特異度0.79)であった.【考察】固定用ベルトを用いたHHDによる等尺性膝伸展筋力測定は,大腿骨近位部骨折受傷後の入院患者においても,先行研究に報告された若年および高齢健常者,脳血管疾患患者と同様にtest-retestの再現性が高いことが考えられた.また,病棟内杖歩行自立のカットオフ値として今回示された膝伸展筋力体重比は,臨床における病棟内杖歩行自立の検討に関する一指標となると考えられた.【理学療法学研究としての意義】固定用ベルトを用いたHHDによる筋力測定方法は,大腿骨近位部骨折術後患者においても有効であることが示唆された.
1 0 0 0 OA マレー人社会における離婚とその社会的基盤
- 著者
- 戸谷 修
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5, pp.348-353, 1967-10-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA アブラムシの口針そう入と植物組織
- 著者
- 宗林 正人
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.38-44_2, 1960-03-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 7 7
25属34種のアブラムシについて口針が植物組織にそう入される状態を観察した。その結果の果要は次のとおりである。1) 口針を表皮組織にそう入する際,ほとんどすべての種類では,表皮細胞間または細胞内を貫通するが,あるものは気孔からそう入し,同一種でも一定しない。しかし,カンショワタアブラムシCeratovacuna lanigera ZEHNTNER(ススキ)およびマツノハアブラムシSchizolachnus orientalis TAKAHASHI(アカマツ)の2種は常に気孔からのみそう入する。2) 口針が植物組織内に進入するときには一般に細胞間を通るが,細胞内を貫通することもしばしばあり,結晶体を含む細胞も容易に貫通する。厚膜組織では細胞内を貫通することはまれで,細胞間のみを通るか,あるいはこの組織を避けて柔組織を通る場合が多い。しかしマツノハアブラムシSchizolachnus orientalis TAKAHASHIでは,常にアカマツ針葉組織細胞内のみを貫通する。3) 口針しょうは細胞間を通過する部分よりも細胞内を貫通した部分に顕著で,また表皮と口ふんの先端との間,あるいは葉しょうと茎との間の空気中にも形成される。口針しょうは口針内の気密を保つためにも役だつものと思われる。4) 口針の先端はほとんど常にし部細胞内,特にし管内にそう入される。皮層細胞内にそう入されたものは見られなかったが,まれに木部あるいは管束しょうにそう入されていた個体も見られた。また口針はそう入部から最も近いし部に達するとはかぎらず,皮層を遠回りし,あるいは髄線を経て髄にはいりし部に達するもの,あるいはし部または木部のみを通過することがある。また口針はし部で同一細胞からのみ吸汁するものではなく,たびたび新しい細胞に刺し変えるため口針こん跡の分枝したものが多数みられた。
1 0 0 0 OA 表現の可能性に満ちた魅力ある木版画
- 著者
- 鷲野 佐知子
- 出版者
- 学校法人 山野学苑 山野美容芸術短期大学
- 雑誌
- 山野研究紀要 (ISSN:09196323)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.31-37, 2009 (Released:2019-11-10)
- 参考文献数
- 3
版画には主に木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーンなどの技法があり、それぞれ違った方法論と考え方を持っている。その中でも、木版画は、版木、和紙、顔料、刷毛、バレンなどの素材に於いても、日本の風土に適した表現である。その木版画でインク、和紙、彫り、摺り方に於いて研究を重ね、求める表現とモチーフに最も適した方法と素材について追求した。
1 0 0 0 IR 学生相談機関への援助要請に必要とされる情報
- 著者
- 西 くるみ 高橋 知音
- 出版者
- 信州大学大学院教育学研究科心理教育相談室
- 雑誌
- 信州心理臨床紀要 (ISSN:13480340)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.57-70, 2020-06-01
本研究では,援助要請先の対象を大学の学生相談室と想定し,援助要請をしやすくする際に必要とされる情報は何かを分類すること,相談室へ援助要請するために必要とされる情報は人によって異なるかどうか検言すするととを目的に研究を進めた。必要な情報は「相談室の実績」「相談相手」「相談室のシステム」に分類できることが示された。実際の介入には不気味イメージを払拭できるような情報提供が効果的であること示唆された。スティグマについてはこちらから介入できる効果的な情報は得られなかった。また,「情報があれば行く」という状態になるためには,少なくとも不利益イメージが低くなることが必要であるということが示された。
1 0 0 0 IR 看護師が自ら職場ソーシャルサポートを得るための方策に関する研究
- 著者
- 山本 摩梨子 小澤 三枝子
- 雑誌
- 国立看護大学校研究紀要 = Journal of Nursing Studies, NCNJ (ISSN:13473611)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.1-9, 2020-03
看護師自らが職場ソーシャルサポートを得るための方策を検討することを目的に、3施設の病棟に勤める看護職員を対象に無記名自記式質問紙調査を行った。調査項目は、職場ソーシャルサポート、被援助志向性、援助要請スキル、SOC(sense of coherence;首尾一貫感覚)などである。調査票配布数643、回収数218(回収率33.9%)、有効回答数217であった。単変量解析の結果、看護職経験年数5年未満の群は、5年以上の群より得ている職場ソーシャルサポートが多かった。被援助志向性では性差が見られた。経験5年以上の女性看護師109名を対象とする共分散構造分析の結果、職場ソーシャルサポートへの直接効果は、援助要請スキルからが.50、被援助に対する懸念からが-.22、把握可能感からが-.24であった。SOCが高くなると援助要請スキルが高くなり(.81)、被援助に対する懸念を弱くする(-.63)ことができ、看護師自ら職場ソーシャルサポートを得ることに有用である可能性が示唆された。(著者抄録)
1 0 0 0 IR 評価懸念および気遣いと親しい友人への被援助志向性との関連
- 著者
- 長谷川 彩香 高橋 知音
- 出版者
- 信州大学大学院教育学研究科心理教育相談室
- 雑誌
- 信州心理臨床紀要 (ISSN:13480340)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.95-106, 2020-06-01
本研究では,評価懸念が強く自分の本一音を我慢して相手を気遣う傾向があると,親しい友人への援助要請に消極的な態度や抵抗感が高まるかどうか検討することを目的とした。大学生183名を対象に無記名の質問紙調査を実施した。調査では「親しい友人」を一人想起させ,その友人に対する被援助志向性と気遣いを測定した。その結果,評価懸念が高く自分の気持ちを我慢してまで相手を気遣う傾向にある人は,相手が親しい友人であっても援助要請に抵抗感をもつことが明らかになった。
- 著者
- 小田 宗兵衛
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.131-136, 2009-04-15 (Released:2017-04-15)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 OA 台湾に於ける国語教育の展開
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ものづくり (ISSN:13492772)
- 巻号頁・発行日
- no.785, pp.48-53, 2020-02
トーチのきょう体はアルミニウム合金製。材料は「A6063」で、東日本大震災後の仮設住宅のサッシを再生した材料を30%含む。トーチを上から見ると、桜の花をかたどった形状、すなわち5角形の中心部を5個の楕円(花びら)が取り囲む形になっている。
1 0 0 0 OA 絲状菌によるVitamin C様還元性物質の生成に就て
- 著者
- 福本 壽一郎 下村 弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.7, pp.613-620, 1937 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 11
1. 2, 6-dichlorphenolindophenol solutionを用ひて各種の絲状菌の還元性物質生成量を求め, Asp. cellulosae, Asp. fumigatus, Asp. niger, Asp. nidulans, Asp. melleus, Pen. glaucum及びPen. luteum等の菌種が生成量大なる事を認めたが, Bernhauer氏等に倣ひAsp. nigerを試驗菌種と定めた. 2. 炭素源を異にする培養液にAsp. nigerを接種して炭素源と還元性物質の生成量との關係を試驗し, Fructose, Sucose, Mannit, Starchに於て生成量大なる事を見た. 3. 該還元性物質を濃縮精製してモルモツト飼育試驗を試みた結果, Vitamin Cの如き生理的效果を認め得なかつた. 4. 本還元性物質の化學的性質の若干に就て論じた.
1 0 0 0 OA 物語のための技法と戦略に基づく物語の概念構造生成の基本的フレームワーク
- 著者
- 小方 孝 堀 浩一 大須賀 節雄 Takashi Ogata Koichi Hori Setsuo Ohsuga
- 雑誌
- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.148-159, 1996-01-01
In this paper, we describe a basic framework of the narrative generation system for supporting human creative tasks. The narrative generation process by computer is divided into the conceptual representation level and the surface language generation level, and we deal with only the former level here. The conceptual representation is divided into three aspects; story, plot, and construction. While the story is an events sequence that was arranged according to a temporal order, the plot is an events sequence that was reorganized by an order which each event is introduced into a narrative. These three levels in a narrative are constructed as tree structures. Terminal nodes in the tree structures are events and all nodes other than them are relations that connect subordinate nodes. Narrative generation is performed by expanding or transforming a tree structure. In the story and construction generation, the system enlarges each tree by expanding events or partial trees using appropriate relations, and in the plot generation, a story tree is transformed into a plot tree through the connection relations among nodes in it are rearranged. We call narrative techniques the procedures to expand a tree through applying relations to nodes or to transform a tree using actors" viewpoints or plot patterns. On the other hand, we call narrative strategies the rules to decide a current executable narrative technique and the node to which it is applyed according to narrative parameters that define the features of a narrative to be generated through narrative generation process. The system generates a narrative by executing appropriate narrative techniques under the control of narrative strategies based on a set of events and narrative parameters were given by user. This narrative generation mechanism has some remarkable characteristics. First, the system can flexibly generate a variety of narratives from one input. Next, the system has an ability that integrates a variety of theories or knowledge representations and that extends the system itself. These advantages are relate to clear separation among narrative techniques, narrative strategies, and knowledge base. Lastly, by above reason, the system has potentiality that can use for various purposes. We can change or add each modules in it to apply to specific areas.
1 0 0 0 OA JANE AUSTEN, EMMA VOL.I
- 著者
- 関西大学ジェイン・オースティン研究会 Antony Stephen Gibbs 樋口 欣三 坂本 武 島崎 守 多田 敏男 谷口 義朗
- 出版者
- 関西大学出版部
- 巻号頁・発行日
- 1994-11-04
1 0 0 0 OA 示談と損害賠償
一 紛争解決と契約………………………………………………………… 一二 示談……………………………………………………………………… 一四三 和解と錯誤……………………………………………………………… 二八四 和解の基礎の錯誤……………………………………………………… 三九五 損害賠償と示談の拘束力……………………………………………… 五九六 示談における前提合意と錯誤………………………………………… 九三七 示談契約における免除の効力………………………………………… 一二七八 示談と共同親権………………………………………………………… 一六九九 和解(示談)と解除の遡及効………………………………………… 一八三附録一 和解………………………………………………………………… 一九二附録二 裁判上の和解の成立を前提とする裁判外の和解の効力……… 二〇六附録三 債権の効力………………………………………………………… 二一〇
1 0 0 0 OA 両国夕涼ミの図
- 著者
- 香蝶楼豊国,一陽斎豊国
- 出版者
- 古勝
- 雑誌
- 国芳豊国画帖