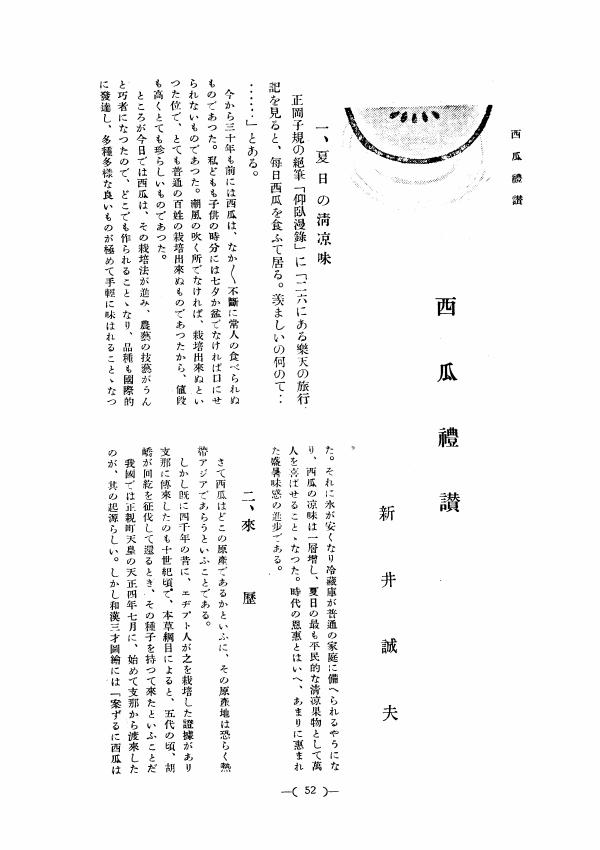1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1918年06月26日, 1918-06-26
1 0 0 0 聴覚に関わる社会医学的諸問題「超高齢社会と聴覚補償」
- 著者
- 岡本 牧人
- 出版者
- 日本聴覚医学会
- 雑誌
- Audiology Japan (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.50-58, 2013-02-28
- 参考文献数
- 23
日本では2007年より超高齢社会となった。2060年には高齢者は人口の40%を占めると予測される。<br>加齢とともに難聴が進行することは良く知られているが, 数十年前の高齢者に比べ, 現代の高齢者の方が加齢変化は遅く出現しているようにみえる。<br>超高齢社会では, 高齢者は生活の質の維持とともに社会人として役割を分担する必要があるが, 会話域純音聴力は60歳代までは若年者と同様に保たれていると考えられる。加齢による難聴に対して補聴器による聴覚補償は有効である。さらに難聴が高度になると人工内耳による聴覚補償も有効である。<br>高齢化社会では生活の質の維持に聴覚的コミュニケーションが欠かせないが, 補聴器や人工内耳の公的補助は, 医療経済的, 医療倫理的観点からも合わせて考えて行く必要がある。
1 0 0 0 難聴児に対する補聴援助システムの有用性
- 著者
- 千田 いづみ
- 出版者
- 日本小児耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.312-317, 2016
 学校の教室には教師と生徒との間の距離や周囲の雑音があるため,難聴児は補聴器や人工内耳だけでは十分な聴取が得られず,補聴援助システムの併用が必要である。以前より普通学校ではFM補聴援助システムが使用されてきたが,チャンネル干渉が生じやすい欠点があった。最近使用されるようになったデジタル無線方式の補聴援助システムは,デジタル変調方式により音質が向上し,受信器と送信器間のペアリングによりチャンネル干渉が防止できる利点がある。<br/> 我々は,「徳島県の難聴児を支える連携」を構築し,地域の教育委員会に働きかけ,難聴児が就学する学校に補聴援助システムを導入してきた。また,一側性難聴児は健聴児と比較して騒音環境での語音聴取能が低下していることを明らかにし,一側性難聴児にも学校の教室に補聴援助システムを導入している。徳島県での補聴援助システム導入の現状と実績について報告した。
1 0 0 0 OA ビザンツ・ヘシュカズムの霊性(<特集>スピリチュアリティ)
- 著者
- 久松 英二
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.455-479, 2010-09-30 (Released:2017-07-14)
ビザンツ末期の一四世紀に正教修道霊性の中心地アトスで始まったヘシュカズムの霊性は、心身技法を伴う「イエスの祈り」の実践と、神の光の観想の意義および正統性弁護のための理論から成り立つ。体位法と呼吸法を伴った「イエスの祈り」は、ビザンツ修道制における静寂追求の伝統上に位置づけられるが、それによって得られる光の観想体験は「タボルの光」という聖書表現をもって解釈しなおされた。次に、ヘシュカズムの理論レベルにおいては、光の観想をめぐる東方キリスト教的な解釈が注目される。その特徴を端的に表現するのが、「働き」(エネルゲイア)という概念で、この概念は光の観想体験の意義および同体験の正統性の説明として機能する。よって、ヘシュカズムの理論は内在や本質の抽象論より、働きや作用のダイナミックな具体論を特徴としている。そのような理論に支えられたヘシュカズムの霊性は、「エネルゲイア・ダイナミズムの霊性」と称してもよかろう。
1 0 0 0 OA 「東海大安楽死判決」の今日的意義
1 0 0 0 OA 近代日本出版業確立期における大倉書店
- 著者
- 鈴木 恵子
- 出版者
- 日本英学史学会
- 雑誌
- 英学史研究 (ISSN:03869490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.18, pp.101-113, 1985-11-01 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 26
Okurashoten was established on September 15th in the 8th year of Meiji era. It developed from Kin'eidb Publishing Company (Ezoshi-ton'ya Kin'eido) which was a branch of Yorozuya Publishing Company. Kin'eido was acknowledged as the Publishing Company of Nishikie in the last days of Edo era.Okurashoten published various dictionaries; English, German, French, Russian dictionaries, Japanese dictionary ‘Gensen’, biographical dictionaries, Buddhist dictionary, etc. Even today its publications are reprinted by many publishing companies, with many influences on our time's thought and ideas.The aim of this treatise is. with the above historical sketch of Okurashoten in mind, to demonstrate the following three themes:(1) what kinds of books Okurashoten published according to its own thought for introducing Anglo-American political and economical ideas to Japan, and for realizing peaceful Japan in the 20's of Meiji era.(2) what parts Okurashoten played for safeguarding Japan's independence and interests against European and American nations.(3) what parts Okurashoten played in modernization of Japan's publishingbusinesses, and in publishing modern school textbooks.
1 0 0 0 道野樟脳工場跡
- 著者
- まくらざき探検隊編纂
- 出版者
- 枕崎市観光協会委嘱枕崎観光ボランティアクラブ「まくらざき探検隊」
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 水泳と健康について
- 著者
- 鈴木 大地
- 出版者
- 順天堂大学
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.308-311, 2003-09-30
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 光リソグラフィの解像度の限界解像度を超えるナノインプリント技術開発
- 著者
- 井上 壮一 櫻井 淳平
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.4, pp.239-242, 2020-04-05 (Released:2020-04-05)
- 著者
- 鈴木 克洋 露口 一成 松本 久子 新実 彰男 田中 栄作 村山 尚子 網谷 良一 久世 文幸
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.187-192, 1997-04-15 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 10
Fifty six clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis were tested for drug susceptibility in Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) containing 0.1μg/ml of INH, 1.0μg/ml of RFP, 3.5μg/ml of EB and 0.8μg/ml of SM. These results were compared with those obtained by testing the same M.tuberculosis isolates by the absolute concentration method using 1% Ogawa egg slant containing 0.1μg/ml of INH, 10μg/ml of REP, 2.5μg/ml of EB and 20μg/ml of SM. Fifty six isolates consisted of 18 pansensitive strains, 27 multidrug resistant strains and 11 single drug resistant strains. The results for individual drugs showed excellent agreement between the MGIT and the Ogawa methods, and overall agreement rate of the two methods were 96.4%. The results were just the same for all drugs in 48 out of 56 strains studied. The drug resistance could be observed much earlier by the MGIT method (mean 5.9 days) than by the Ogawa method (more than 21 days). In conclusion, the MGIT system could be a promising new drug susceptibility test which might become available in Japan replacing the Ogawa method.
1 0 0 0 OA 人工透析と結核症
- 著者
- 藤野 忠彦
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.9, pp.381-388, 1976-09-15 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 18
Risk of developing miliary tuberculosis is increased in a variety of disorders in which host defence mechanisms are impaired. We are presenting four cases of miliary tuberculosis which developed during dialysis therapy for chronic renal failure.The patients' age ranged from 34 to 59 years. None of them received corticosteroids or immunosuppressive therapy during their hospital treatment. These four patients had been treated at different time and different hospitals except cases 2 and 3. A previous histry of tuberculosis was recorded only in case 2. The clinical symptoms of these cases were fever of unknown origin, and cough and sputum during the period of dialysis therapy. Fever was the most frequently observed sign, which raised to 37-39°C after the dialysis or in the evening. The intermittent fever persisted without response to various antibiotics including CER, CEZ, TC, PC, etc. Two of them complained headache and became comatose in the final stage. Miliary lesions were not visible on the chest radiograms, even just before the time of death. The infiltrative shadows in S6 and pleural effusion were found in some cases temporarily on the chest radiograms during the clinical course. The duration of fever ranged from one month to 3 years. In case 2, the smear examination of sputum for acid-fast bacilli was negative, but positive culture was obtained one month after the death of patient. In case 3, one colony of acid-fast bacilli was cultured from the pleural effusion which disappeared without any antituberculous treatment. The serum BUN and creatinine levels were well controlled by the dialysis therapy in these four cases. The diagnosis of miliary tuberculosis were finally obtained by postmortem examination in all cases.The tuberculine skin test was not performed in these patients. It is well established that chronic uremia may influence certain immunological reactions and depress tuberculin skin test. This experience suggests that patients under dialysis therapy have a greater risk of developing miliary tuberculosis, and if fever of unknown origin is observed or tuberculosis is suspected, the prompt institution of antituberculous therapy including prophylactic ones is requested.
1 0 0 0 OA 最近における結核の諸問題
- 著者
- 柳内 登
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.383-385, 1984-04-20 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 4
過去10年間に国立療養所晴嵐荘病院で行つた肺結核, 膿胸の手術例は267例で, 48年を境に減少の傾向にあるが, 外科療法を必要とする症例が存在することも事実である. 手術例のうち興味あるものにつき報告する.1)結核性気管支狭窄例: 6例に手術を行つた. このうち4例は気管支形成術を行い, 下葉の機能を温存することができた. 狭窄部末梢肺に不可逆性変化の生ずる前に気管支形成術を行うことが重要である. 2)膿胸: 肺切除後17年(2例), 22年(1例)目に発生した気管支瘻膿胸に手術を行い治癒せしめた. 結核の手術は長期間の監視が必要である.3)塗沫陽性培養陰性菌(SPCN)を2年間続けた例に切除術を行つた. 病巣の菌を0.5%NaOHで前処理したところ培養陽性であつた.4)化学療法に期待したため病状が悪化, 手術の機会を逸し死亡した症例がある. 再発結核例は積極的に手術を行つた方が良いと考える.
1 0 0 0 OA 西瓜禮讃
- 著者
- 新井 誠夫
- 出版者
- 社団法人 大阪生活衛生協会
- 雑誌
- 家事と衛生 (ISSN:18836615)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.8, pp.52-55, 1936-08-01 (Released:2010-10-13)
1 0 0 0 OA 地面効果翼艇 (WIG) の実用化に向けて
- 著者
- 久保 昇三 松原 武徳 松岡 利雄 河村 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.448, pp.236-242, 1991-05-05 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 IR 継続する第二波フェミニズム理論 : リベラリズムとの対抗へ (部門研究1 『ケアの倫理』からの、合衆国フェミニズムの再構築 : 関係性を中心とした人間像からのリベラルな個人主義批判)
- 著者
- 岡野 八代 オカノ ヤヨ Okano Yayo
- 出版者
- 同志社大学アメリカ研究所
- 雑誌
- 同志社アメリカ研究 = Doshisha American studies (ISSN:04200918)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.103-124, 2017
特集記事(Special Article: Bumon Kenkyu 1)表紙裏のタイトルの表記に誤りあり (誤)Liveralism → (正)Liberalism
1 0 0 0 OA 筋萎縮性側索硬化症における肺気量の変化とFV曲線の関係
- 著者
- 田島 桂子 宮澤 義
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.533-539, 2016-09-25 (Released:2016-11-10)
- 参考文献数
- 8
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は極めて進行が速く,発症後2~5年で半数ほどが呼吸筋麻痺による呼吸不全で死に至る。呼吸管理をするうえでスパイロメトリーは必要不可欠な検査であるが,筋力障害のためスパイロメトリーが困難で,病態に即した値を導きだすことが難しく,努力呼出の誘導や妥当性の基準は不明である。我々は11症例のALSの病期進行に伴う肺気量変化とFV曲線のパターンの変化の関係を解析し,最大努力呼出の誘導や妥当性の確認の目安となる指標を調べた。ALS患者の病期進行に伴うFV曲線のパターンの変化は,呼出の持続ができず呼気終末が止まる腹式呼出障害パターン,スムーズな胸・腹式共同呼出ができず下降脚が乱れる胸・腹式共同呼出障害パターン,速い呼出ができずピークの低い波形となる胸式呼出障害パターンの順に現れた。また,この呼出障害パターンが現れる肺気量(%FVC)は,腹式呼出障害パターンで100%,胸・腹式共同呼出障害パターンは80%,胸式呼出障害パターンは50%程度で出現しはじめた。肺気量とFV曲線の呼出障害パターンを参考にすることで,病態に合致した最大努力呼出の誘導および妥当性の確認が可能となることが示唆された。
1 0 0 0 OA Duplex PCR法を用いた遺伝子組換えパパイヤ改良検知法
- 著者
- 山口 昭弘 清水 香織 三嶋 隆 青木 信太郎 服部 秀樹 佐藤 秀隆 上田 信男 渡邉 敬浩 日野 明寛 穐山 浩 米谷 民雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.146-150, 2006-08-25 (Released:2008-08-04)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 8 11
遺伝子組換え(GM)パパイヤの同定においてわが国の公定法のPCR法を改良し,簡便かつ迅速な検知法を開発した.凍結乾燥処理を省略し,生果肉から直接シリカゲル膜タイプの市販キットを用いてDNAを抽出した.GMパパイヤ特異的遺伝子およびパパイヤ内在性のpapain遺伝子を同時に増幅するduplex PCR法を開発するために,papain遺伝子に対する公定法のPCR増幅産物(211 bp)の内側に,新たなプライマーペア papain 2-5'/3' を設計した.GMパパイヤ検出用のプライマーペアには公定法と同一のものを用いた.これらのプライマーペアを同一チューブ内に共存させて増幅させる duplex PCR 法を行った後,増幅産物をアガロースゲル電気泳動またはマイクロチップ電気泳動により同時検出した.本法により簡便,迅速なGMパパイヤの同定が可能であった.